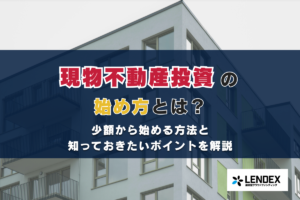株式投資にはさまざまな取引方法がありますが、その中でも「現物取引」は、もっとも基本的な投資手法として広く利用されています。一方で、「現物取引は安全」と思われがちですが、実際にはリスクも存在します。
本記事では、株の現物取引の仕組みやリスク、注意点について解説します。これから株式投資を始める方や、現物取引のリスクを知って安全に運用したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
株の現物取引とは何?

「株式現物取引のリスク」の前に、まずは現物取引の基本的な仕組みと特徴を正しく理解しましょう。
現物取引と信用取引・先物取引の違い
| 取引種類 | 説明 |
|---|---|
| 現物取引 | 自己資金の範囲内で株式を売買するため、借金を背負うリスクが限りなく低いのが特徴です。 |
| 信用取引 | 証券会社に保証金を預け、自己資金の数倍の取引を行う方法です。資金効率を高めることができますが、相場が逆行すると想定以上の損失を被る可能性があり、追証(追加保証金)のリスクも伴います。 |
| 先物取引 |
将来の特定の期日に決めた価格で資産を売買する契約です。価格変動リスクのヘッジや資金効率の向上が主な目的で、レバレッジはその手法の一つに過ぎません。適切に活用すれば効率的な運用が可能ですが、市場次第で損失リスクも伴います。 |
*追証(おいしょう):信用取引などで担保評価額が不足した際、投資家が追加で差し入れる保証金のこと。
「現物取引は安全」というイメージの落とし穴
株の現物取引は、証拠金なしで売買できることから、「最悪の場合でも買った金額以上に損しない」「借金を負うことは少ない」といったイメージが強い投資方法です。
大幅な資産減少のリスクはある
元本以上に損失を被ることはありませんが、資金の大幅な目減りの可能性は十分にあります。過去には、名門企業と呼ばれる企業でも経営破綻し、株価が急落して投資資金が大きく減少した例も少なくありません。
自分で損切りの判断をする必要がある
適切なタイミングで売却できなければ、含み損が拡大するリスクがあります。そのため、市場の状況を冷静に分析し、事前に売却ルールを決めておくことが重要です。
心理的リスク
株式投資では、心理的リスクに陥りやすい点にも注意が必要です。
リスク管理の要は、「感情に流されず、客観的に判断できる仕組みを持つ」ことです。具体的には、テクニカル指標やファンダメンタルズ分析を参考に、買い増しや売りのルールを明文化しておくと良いでしょう。
利益が出ている銘柄を「もっと上がるかもしれない」と期待し、売却のタイミングを逃してしまうケースもあります。結果的に、株価が下落し、せっかくの利益を失う可能性 もあるため、利確(利益確定)のルールを決めておくことが大切です。
ポイント
「現物取引は安全」という安易な認識が、リスク意識を低下させ、十分な調査やリスク管理を怠る原因になることもあります。リスクを過小評価すること自体が、大きなリスクになり得るのです。
現物取引で投資をするメリット

追証(おいしょう)のリスクがない
現物取引では、自己資金の範囲内で株を購入するため、たとえ相場が急変しても証券会社から追加の保証金(追証)を請求されることはありません。借金を背負う心配がないため、精神的な負担を軽減しながら投資を続けることができます。
配当金や株主優待を受け取れる
現物取引で株式を保有していると、企業が配当金を支払う場合、その利益を受け取ることができます。また、企業によっては株主向けに特典として優待を提供しており、長期的に保有することで資産形成とともにさまざまな恩恵を得ることができます。
レバレッジによる過大損失がない
信用取引では自己資金の数倍の金額で取引ができるため、大きな利益を得る可能性がある一方で、相場が予想と反した場合に損失が膨らむリスクもあります。しかし、現物取引は自己資金の範囲内で取引を行うため、株価が下落したとしても損失額が限られており、予想外の負担を抱えるリスクを避けることができます。
投資対象がシンプルでわかりやすい
現物取引は、先物取引やオプション取引、暗号資産などの複雑な金融商品とは異なり、基本的に「株を買って売る」というシンプルな仕組みで成り立っています。そのため、初心者でも理解しやすく、投資の基本を学びながら安定した資産運用を行うことができます。
現物取引で投資をするデメリット

資金効率が低い
レバレッジをかけないため、短期間で大きな利益を得るチャンスが限られることがあります。資金効率を重視する投資家にとっては、やや物足りない選択肢となる可能性があります。
短期トレードに向いていない場合がある
現物取引は、短期間の値動きを狙ったトレード(デイトレードなど)には向いていないことが多いです。売買手数料や税金の影響もあり、短期的な売買を繰り返すとコストがかさむ可能性があります。
精神的な負担が大きくなることも
現物取引では追証の心配はありませんが、「どこまで下がるかわからない」という不安が続きやすいのが特徴です。損切りを決断できないと、長期間含み損を抱え続けてしまうリスクがあります。
現物取引において事前に知っておくべきリスク

「株式取引のリスク」を事前に理解しておくことで、不測の損失を回避する手助けになります。
株価変動リスク(ボラティリティリスク)
レバレッジがないとはいえ、個別銘柄の株価は1日で数%から数十%変動することもあります。特に、マザーズやグロース市場の一部銘柄では、値幅制限いっぱいまで急落するケースもあり注意が必要です。
また、決算発表や市場全体の悪材料によって急激に株価が下落することも珍しくなく、短期間で資産価値が大幅に減少する可能性もあります。現物取引には追証のリスクはありませんが、短期的な値動きによる影響を十分に理解し、長期的な視点で投資することが重要です。
企業固有のリスク
株価は企業の業績や経営状況に大きく左右されるため、以下のような企業固有のリスクにも注意が必要です。
代表的な企業リスク
倒産リスク:業績不振が続くと上場廃止となり、株の価値がほぼゼロになる可能性がある。
不祥事・不正会計:リコール問題や粉飾決算が発覚すると、株価が急落し、信用を大きく失う可能性がある。
増資リスク:企業が新たに株式を発行すると、1株あたりの価値(既存株主の持ち分)が希薄化し、株価が下落することがある。
配当・株主優待の変更リスク
「高配当だから」「株主優待が魅力的だから」といった理由で株を購入する場合は、企業の方針変更によるリスクにも注意が必要です。業績が悪化すると、配当が減額されたり、場合によっては無配となることもあります。
また、企業の経営方針が変わることで、株主優待の内容が縮小されたり、廃止されるケースもあります。そのため、配当や優待の魅力だけでなく、企業の財務状況や長期的な成長性も考慮して投資判断をすることが大切です。
流動性リスク
人気のある大型株や有名企業の株は取引が活発で、売りたいときにすぐに売却できる可能性が高いです。一方、流動性の低い銘柄では買い手が少なく、希望する価格で売却できないことがあります。特に、取引量が少ない銘柄では、売り注文を出してもすぐに約定せず、想定以上に時間がかかる場合があります。
また、大口投資家のように何千万円、何億円といった規模で取引を行う場合、流動性の低い銘柄では売買の影響が大きくなり、思うように取引を進めにくいことがあります。ただし、個人投資家の場合でも、取引量が極端に少ない銘柄では、想定価格よりも不利な価格でしか売買できないリスクがあるため、流動性を考慮した銘柄選びが重要です。
リスク管理の基本:損切りと資金管理の重要性
「現物取引だから損切り不要」 というわけではありません。長期的に資産を守るためには、適切なリスク管理が不可欠です。ここでは、損切りの基準や資金管理のポイントについて解説します。
切り損ラインの設定を行う
株を購入する前に、「株価が○%下がったら売却する」「企業の業績が想定より悪化したら見切りをつける」など、具体的な売却ルールを決めておくことが重要です。あらかじめ基準を明確にしておくことで、感情に左右されずに冷静な判断がしやすくなります。
また、市場が急落した際に自動で売却注文を出す「逆指値注文」を活用すれば、相場の動きに振り回されることなく、あらかじめ決めた損切りラインで確実に売却することが可能です。これにより、予期せぬ損失の拡大を防ぎ、計画的な投資がしやすくなります。
資金管理と分散投資
投資をする際は、必ず余裕資金で行うことが重要です。生活資金や緊急資金を株式投資に回してしまうと、相場が下落した際に冷静な判断ができず、必要な資金を確保するために不利なタイミングで売却してしまうリスクがあります。余裕資金で運用することで、長期的な視点を持ち、落ち着いて投資判断を下すことができます。
また、リスクを抑えるためには分散投資も有効です。1つの銘柄や業種に資金を集中させると、想定外の事態が発生した際に大きな損失を被る可能性があります。そのため、異なる業種やセクターの株を組み合わせたり、国内外の市場に分散させたりすることで、リスクを分散しながら安定した運用を目指すことが大切です。
投資スタイルに応じたリスク許容度を決める
短期売買を行う場合は、頻繁に売買を繰り返すため、損失を最小限に抑えるための明確なルールが必要です。特に、損切りラインをタイトに設定し、資金の回転を早めることで、大きな損失を避けながら効率的に運用することができます。
一方で、中長期投資では、一時的な株価の下落を許容しながら、企業の成長を期待して長期間保有することが前提となります。短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、企業の業績や市場全体の成長性をしっかりと分析し、将来的なリターンを見据えた投資判断を行うことが重要です。
現物取引においてリスク分散が重要

株の現物取引は、自己資金の範囲内で取引を行うため、無謀なレバレッジ取引を回避できるのが特徴です。しかし、その一方で、個別企業のリスクにはさらされやすいというデメリットもあります。
そこで重要になるのが、リスク分散(ポートフォリオの最適化)です。適切な分散投資を行うことで、市場の変動リスクを抑え、安定した運用を目指すことができます。
セクター分散(業種分散)
株式市場では、業種(セクター)ごとに値動きが異なるため、特定の業種に偏った投資はリスクを高める原因になります。異なるセクターに資金を分散させることで、ある業界の不調を別の業界の好調でカバーできる可能性があります。
| セクター | 特徴 | 業種の例 |
|---|---|---|
| 景気敏感セクター | 景気の影響を受けやすい | 自動車、化学、機械 |
| ディフェンシブセクター | 景気に左右されにくい | インフラ、通信、小売 |
時間分散(投資タイミングの分散)
短期的な株価の変動を抑えるために、時間を分散して投資する方法も有効です。
ドルコスト平均法(定期的に定額を投資する手法):高値掴みのリスクを減らし、購入価格を平準化することができる
海外株やETFの利用(地域分散)
国内株だけに投資するのではなく、海外市場やETF(上場投資信託)を活用することで、さらにリスク分散の効果を高めることができます。
例えば、米国株ETFや新興国株ETFなどをポートフォリオに加えることで、日本市場の影響を抑えつつ、成長市場の恩恵を受けることができます。
ETFのメリット
世界の市場に分散投資ができる点です。個別銘柄では特定の企業や業種に依存するリスクがありますが、ETFは複数の銘柄が組み合わされているため、1つの企業の業績が悪化しても全体への影響を抑えやすくなります。
また、個別銘柄と比べてリスクが低減し、安定した運用がしやすいことも魅力です。市場全体の動きを反映するため、急激な株価変動によるリスクを分散できるのが特徴です。
さらに、ETFは少額から投資できるため、初心者でも手軽に分散投資を始めることができます。1つの銘柄を購入するよりもコストを抑えながら、広範囲の資産に投資できるため、長期的な資産形成にも適しています。
現物取引で意外と見落としがちな手数料や税金
「株式取引のリスク」 というと、株価の下落リスクばかりに注目しがちですが、取引にかかるコスト(手数料・税金)も重要です。これらを見落とすと、実際の収益が大きく損なわれる可能性があります。
証券会社の手数料体系を確認する
株式の売買には、証券会社ごとに異なる手数料プランが設定されています。主なプランとして、「約定ごとに手数料がかかるプラン」と「1日定額プラン」の2種類があります。前者は1回の取引ごとに手数料が発生し、後者は1日の取引金額の範囲内で定額となる仕組みです。
また、ネット証券は手数料が安い傾向にありますが、大手証券会社に比べるとサポートが限定的な場合もあります。そのため、コストを抑えたいのか、手厚いサポートを受けたいのかといった自身の投資スタイルに合った証券会社を選ぶことが重要です。
税金(譲渡益税・配当所得税)について
株式投資で得た利益には、約20%(正確には20.315%)の税金がかかります。主な税金としては、譲渡益税(売却益に対する税金)と配当所得税(配当金に対する税金)があります。
また、NISA口座を活用すれば、一定額までの投資収益が非課税となりますが、制度には上限や条件があるため、事前に確認が必要です。さらに、損益通算を活用することで、年間の損失を他の利益と相殺することも可能ですが、場合によっては確定申告が必要になります。
これらの仕組みを理解し、税負担を抑える工夫をすることで、より効率的な資産運用が可能になります。
実質利回りの把握を行う
例えば、「5%のリターン」と聞くと魅力的に感じるかもしれませんが、実際の利益を正しく把握するためには、手数料や税金を差し引いた「実質利回り」を計算することが重要です。
具体的には、リターンの5%から、税金(20.315%)や買付・売却手数料を差し引いた金額が、最終的な手取り利益となります。
そのため、事前に税金や手数料を考慮したうえで投資判断を行うことが、長期的に資産を増やすポイント となります。
おわりに
株の現物取引は、信用取引と比較して 追証リスク(借金リスク)がないという点で魅力的な投資手法です。しかし、企業固有のリスクや相場変動リスクなど、さまざまなリスクが潜んでいることも忘れてはいけません。特に、株価の下落による含み損のリスクや、企業の業績悪化による株価の低迷など、現物取引にもデメリットがあることを理解することが大切です。
投資において最も重要なのは、自分のリスク許容度を明確にし、投資目的や投資期間に応じた最適な戦略を描くことです。株式市場は常に変動するため、状況に応じた柔軟な対応が求められます。リスクを理解し、余裕資金で無理のない投資を心がけましょう。
ぜひ、本記事のポイントを参考にしながら、自分に合った投資スタイルを確立し、長期的な資産形成を視野に入れた投資戦略を考えてみてください。
投資初心者に最適な「LENDEXの融資型クラウドファンディング」
LENDEXは、1万円から投資できる融資型クラウドファンディングで、少額から始められる点が初心者に最適です。運用の手間がかからず、想定利回りは5%~10%と比較的高いため、銀行預金よりも高いリターンを期待できます。
株式投資のように相場の変動を気にする必要がなく、定期的に分配金が支払われる仕組みも魅力です。ただし、元本保証はなく、貸し倒れリスクがあるため、複数案件に分散投資することが重要です。
融資型クラウドファンディングは、長期的な視点で投資しながら安定した運用を目指せる投資手法の一つです。リスクを理解し、余裕資金で無理のない投資を心がけましょう。