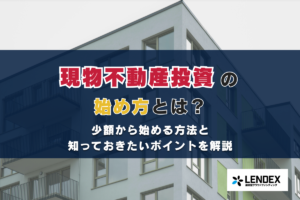競売物件とは?基本的な仕組みを解説

そもそも「競売物件」とはどんな物件?
「競売物件」とは、住宅ローンの滞納などにより債務者(物件所有者)が借金の返済ができなくなった場合に、債権者(金融機関など)が裁判所に申し立てて、担保となっている不動産を差し押さえ、裁判所の管理下で強制的に売却される物件のことです。売却は入札形式で行われ、最も高い価格を提示した人が物件を取得します。落札された代金は、債務の返済に充てられます。
一般的な不動産との違いとは?
競売物件と一般の不動産取引との最大の違いは、「売主」が存在しない点です 。競売では裁判所が物件を売却するため、売主本人による物件の引き渡しや説明がありません。通常の取引では売主から鍵の受け渡しや物件状況の告知がありますが、競売では落札後に所有権が移転しても物件の引き渡し義務がないため、買受人(落札者)が自力で物件を確保する必要があります。
また、不動産会社が仲介しないため宅地建物取引業法に基づく重要事項説明や契約書締結といったプロセスもありません。
競売物件が「やばい」と言われる理由は?
「競売物件」と検索すると予測キーワードに「やばい」と出るほど、ネガティブな印象を持つ人も多いようです。その理由としては、競売には通常の取引にはない様々なリスクやトラブル事例が存在し、それが「やばい(危ない)」というイメージにつながっていると考えられます。専門家によれば、競売物件が「やばい」と言われる主な理由は次の3点に集約できます。
占有者(住人)トラブルのリスクがある
前所有者や賃借人など、物件に住んでいる人が退去せず居座ってしまうケースがあります。不動産会社の仲介がなく引き渡し義務もないため、落札後に自分で立ち退きを交渉・法的手続きをしなければならず、最悪不法占拠状態になる可能性もあります。過去には競売で落札したのに前所有者が強硬に居座り、明け渡しまで長期間かかった例もしばしば取り沙汰されました。こうした占有者とのトラブルは初心者には大きな不安材料です。
契約不適合責任(瑕疵担保責任)が追及できない
競売では売主がいないため、通常の売買で適用される売主の契約不適合責任(※旧瑕疵(かし)担保責任)が免除されています。つまり、購入後に雨漏りやシロアリ被害など重大な欠陥が見つかっても、「話が違うので補償してほしい」とは主張できず 、修繕費は全て自己負担になります。「買ったはいいけど想定外の不具合だらけ…」という金銭的リスクがあるため、「やばい」と感じる人がいます。
購入前に内覧できない
競売物件は原則として落札するまで内部を見学することができません。事前に現地内見ができないため、室内の状態や設備の劣化状況を把握しづらく、どんな物件なのか不透明さが残ります。購入後に「こんな汚部屋だったのか」「設備が故障していた」など発覚しても自己責任となるため、不安を感じる要因です。
実際にはどうなのか?専門家の見解
競売には「怖い人が集まる」「素人が手を出すと危険」などのイメージも一部で語られます。かつては競売に暴力団関係者が関与する例もあったと言われ、そうした噂から敬遠する向きもあります。ただし現在は入札も匿名の封筒入札方式になっており、昔ながらの「怖い競り合い」はありません。
専門家の見解では、競売物件自体が本質的に危険というより「情報不足や手続きの特殊さによるリスク」が「やばい」と感じさせているとされています 。メリット・デメリットを正しく理解し対策すれば、“やばい”先入観は払拭できるでしょう 。
競売物件の特徴とは?知っておきたいポイント
価格が相場より安い
競売物件はリスクや制約が多いため、あらかじめ評価額が低めに調整されています。この「競売市場修正」により、市場価格より概ね3割程度安い基準価格で入札が始まります。実際に不動産相場の6〜7割程度、場合によっては半額以下で落札されるケースも珍しくありません。
優良な物件でも競売にかかれば相場より安く売買される傾向があり、だからこそ投資家にとっては高利回りを狙える手法として語られます。
内覧(室内見学)ができない
競売物件では入札前に物件内部を確認できません。占有者(居住者)がいる場合もちろん立ち入り不可ですし、空き家でも裁判所が内覧会を開いたりはしないため、基本的に「三点セット」と呼ばれる書類(後述)と外観から推測するしかありません。
このため室内の汚損状況や設備の動作状況などは落札して初めて知ることも多く、ある種「中身の見えない福袋」を買うような面があります。
瑕疵担保責任がないという注意点
前述の通り競売には売主がいないため、物件に欠陥があっても売主に責任追及できません。雨漏り・シロアリ被害・給排水の不具合など、どんな瑕疵(欠陥)があってもすべて「現状有姿」で引き受けることになります。通常の売買なら契約不適合責任で修理や損害賠償請求も可能ですが、競売では一切通用しません。
このため安易に入札すると、後から多額の修繕費や欠陥対応に追われるリスクがあります。
引き渡し義務がなく占有者が残っている可能性
競売では物件引き渡しの約束がないため、落札後に前の所有者や賃借人がそのまま居座っている場合があります 。裁判所が差し押さえたとはいえ、強制退去させるところまではしてくれないので、「空き家で引き渡される」とは限らないのが特徴です。占有者がいれば落札者自らが明け渡しの裁判手続きを起こし、最終的には強制執行(強制退去)を申し立てて実現するしかありません。通常の売買なら売主が引越してから引き渡すのが当たり前なので、この点は大きな違いです。
売買契約や仲介手続きが不要
競売では不動産会社を介さず裁判所の手続きで所有権移転まで行うため、通常必要な売買契約書の取り交わしや重要事項説明、仲介手数料の支払いといったプロセスがありません。
入札・落札後は決められた代金を納めれば裁判所が所有権移転登記や抵当権抹消登記まで代行してくれます。その意味では手続き自体は画一的かつシンプルと言えます。ただし後述するように住宅ローンを使う場合などは自力で動く必要があり、手放しで簡単というわけではありません。
競売物件のメリット
競売物件にはリスクばかりでなく、うまく活用できれば大きなメリットもあります。特に投資家目線では、購入価格を抑えられる分だけ利回り向上や資産形成に有利なスタートを切れる可能性があります。
割安で購入できる可能性がある
最大のメリットは何と言っても物件を安く手に入れられることです。前述の通り競売物件は最初から相場より低い価格設定(競売基準価額)となっており、実際の落札価格も一般市場より数割安くなる傾向があります。
価格が安ければ自己資金の負担が減るだけでなく、投資であれば家賃収入に対する投下資本の回収率(ROI)が高まり、売却益も得やすくなります。資産拡大や不動産投資において「安く買う」ことは非常に重要な要素であり、競売はそのチャンスを提供してくれます。
手続きが一律でスピーディー
一般の売買では、売主との価格交渉や契約条件の調整、重要事項説明、ローン手続きなどを経て物件引渡しまで数週間〜数ヶ月かかることもあります。それに比べ競売は、入札〜落札後の段取りが予め定型化されています。売買契約締結は不要で、落札後は決められた期限までに代金を納付すれば所有権取得が完了します。登記の移転や旧抵当権の抹消も裁判所が手配してくれるため、買受人は入札書類の提出と代金支払いという主要ステップだけで済みます。
煩雑な契約実務から解放され、交渉で時間を取られることもないので、手続きをテキパキ進められる点はメリットと言えるでしょう。特に売主都合で取引が流れるリスクもないため、落札できれば確実に契約成立するという安心感もあります。
競売物件のデメリット
メリットの裏には相応のデメリットやリスクがあります。競売物件を検討する際には、以下のような点に十分注意しなければなりません。

立ち退き交渉のリスク
競売物件で最大の懸念は、落札後も前の所有者や借家人が退去しないケースです。競売には鍵の引き渡しや明け渡しの保証がないため、居座られた場合は落札者自身で法的手続きを行う必要があります。
具体的には、裁判所に「引渡命令」を申し立て、従わない場合は執行官による強制執行(退去)を申し立てます。以前はこの手続きが煩雑で、「立ち退き料を払って出て行ってもらう」こともありましたが、現在は制度が改善され、比較的スムーズに強制退去が可能になっています。それでも強制執行完了までには最低2ヶ月ほどかかるため、その間は物件を使えず、手間や損失を覚悟する必要があります。
さらに、賃貸中の物件を落札した場合は注意が必要です。競売開始前からの賃貸借契約があると、借主には最大6ヶ月の明け渡し猶予が法律で認められています。その後も居住継続を希望された場合は、旧契約がそのまま引き継がれ、敷金の返還義務まで新オーナーが負う可能性もあります。仮に旧オーナーが敷金を使い込んでいても、新オーナーが肩代わりするリスクがあるのです。このように、占有者対応は複雑で、特に初心者にとっては大きなリスクとなり得ます。
購入後の修繕リスク
競売物件では内覧ができないため、落札後に初めて室内の状態が分かるというリスクがあります。例えば、「下水道あり」と書類に記載されていたものの、実際には汲み取り式トイレだったという事例もあります。下水管は通っていても未接続で、水洗化には別途工事費がかかることになります。このようなケースでも、「話が違う」と訴えても補償は受けられず、費用はすべて自己負担です。
また、裁判所の調査報告書では綺麗に見えた物件でも、いざ中を確認すると老朽化が激しく、設備も使えない状態だったというケースもあります。結果的に多額のリフォーム費用がかかり、予定していた利回りが出なかったり、赤字になったりすることもあります。
このように、書類上の情報や築年数からある程度の予測は可能ですが、隠れた不具合による出費リスクは完全には避けられません。
手続きが複雑で初心者には難しい?
競売物件は、通常の不動産取引とは流れが異なるため、初心者にとっては手続きが複雑に感じられることが多いです。入札書類を自分で用意して所定の期日・場所に提出しなければなりませんし、保証金の振り込みなども全て指定通り行う必要があります。
また資金面でも、競売では住宅ローンが基本的に使えないというハードルがあります。金融機関は物件の事前確認ができず競売は不確実性が高いため敬遠しがちで、通常は現金一括で支払える人でないと参入しにくいのです。一部に「競売物件ローン」を用意している銀行や、落札後すぐ融資実行してくれるケースもありますが、一般的には競売に参加するには自己資金が潤沢であることが求められます。融資の選択肢が限られる点もデメリットです。
競売物件の購入の流れ
入札から落札までの手順
まずは、入札対象となる物件を探すところから始めます。物件情報は、裁判所の「BIT不動産競売物件情報サイト」で検索可能で、地域や期間を指定して現在受付中または予定の競売物件を確認できます。気になる物件があれば、「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」の三点セットをダウンロードし、内容を精査しましょう。これらには、権利関係や占有状況、建物の評価や写真などが記載されています。あわせて登記簿謄本で抵当権の有無を確認し、現地も外から下見しておくと安心です。
購入を決めたら、入札準備に入ります。物件ごとの入札書を作成し、裁判所へ提出(または郵送)します。保証金の納付も必要で、通常は売却基準価額の20%以上、落札できなければ返金されます。入札は通常1週間の受付期間があり、終了後に裁判所で開札されます。最高価格を提示した人が「最高価買受申出人」として原則そのまま落札者になりますが、場合によっては売却が不許可となることもあります。
必要な資金と期間の目安
落札が決まると、裁判所から「売却許可決定」が出され、確定後に「代金納付期限通知書」が届きます。落札者は、そこに記載された期限(通常1ヶ月以内)までに、保証金を差し引いた残代金を一括で支払う必要があります。支払遅延は落札無効となり、保証金も没収されるため、資金計画は慎重に立てることが大切です。
この支払い期限までは1ヶ月ほど猶予があるため、その間に事前に準備した融資を実行したり、資金を用意することは可能です。ただし、期限の延長は原則不可のため、確実な準備が前提です。残代金の納付後、裁判所によって所有権移転登記が行われ、正式に所有者となります。抵当権もこの時点で抹消されます。空き家であればすぐ利用できますが、占有者がいれば退去交渉や強制執行が必要です。
また、競売物件では住宅ローンが使えないことが多く、現金一括が基本です。融資を希望する場合は、入札前に金融機関と相談し、審査や融資の段取りを事前に整えておくことが重要です。
競売物件は初心者でも買える?向いている人の特徴
ここまで見てきたように、競売物件は通常の不動産投資や購入と比べてハードルが高めです。不動産投資の初心者にいきなり競売は基本的におすすめできません。
実際に専門家も「入札手続きや退去トラブル対応をすべて自分で行う必要があるため、投資初心者にはハードルが高い」「独特のデメリットがあるため初心者には向かない」と指摘しています。リスク管理や専門知識が求められるので、経験の浅い方が安易に手を出すと失敗する可能性が高いでしょう。
競売物件に向いている人の特徴
- 不動産や法律の知識があり、リスクを理解した上で対処できる人
- 十分な自己資金があり、万一想定外の費用や長期間売却できなくなる事態にも耐えうる財務余力がある人
- トラブル対応に粘り強く交渉できる、または専門家に任せる判断ができる人
- 司法書士・弁護士、不動産業者など周囲に競売に詳しい専門家やサポートしてくれる人脈がある人
- 相場観を持ち冷静に入札金額を見極められる人
競売物件を調べるには?情報収集の方法

競売物件に関する情報収集には、いくつかの方法とポイントがあります。信頼性の高い情報源をフル活用して、可能な限り事前に物件の内容を把握しましょう。
BIT(不動産競売物件情報サイト)で検索
競売物件を探す際は、最高裁判所の委託で運営されている公式サイト「BIT」の活用が基本です。全国の地方裁判所で扱う競売物件情報を検索でき、地域や物件種別で絞り込みが可能です。
各物件ページでは「三点セット(物件明細書・現況調査報告書・評価書)」が閲覧でき、占有者の情報や建物の状態、権利関係、写真や図面、評価額の根拠など重要情報が網羅されています。残置物の多さや占有者の連絡状況などから、入札前にリスクをある程度見極めることができます。
また、BITには「売却結果の照会」機能があり、過去に競売で落札された物件の成約価格を検索できます。類似エリア・類似規模の物件がどのくらいの価格で落札されているかを調べ、入札額の目安にしましょう。
裁判所の物件資料閲覧コーナーの活用
各地方裁判所の競売係や書記官室には、管轄内の競売物件の資料が閲覧できるコーナーがあります。基本的にはBITで公開されている情報と同じですが、紙の資料で見た方が見落としが減る場合もあります。
裁判所によっては補足資料や過去の入札状況データなどが用意されていることもあります。また、不明点を競売担当の書記官に質問すれば、教えてもらえる範囲でアドバイスを得られる場合もあります(もちろん中立的な立場なので具体的な入札額の相談等はできませんが)。時間が許せば一度裁判所にも足を運んで情報収集するのがおすすめです。
競売物件を購入する際の注意点
競売物件を安全に購入するためには、いくつかの重要な注意点があります。専門的かつ実践的なチェックポイントを押さえて、リスクを最小限に抑えましょう。「準備8割、入札2割」くらいの意識で臨むことが成功の秘訣です。
物件の権利関係と占有者の確認
まず三点セットや登記簿謄本から物件の権利状況を正確に把握します。抵当権は競落後に消えますが、地上権や先取特権など特定の権利が残るケースはないか確認します。
また占有者について、元所有者なのか賃借人なのか第三者なのかをチェックし、賃貸借契約がある場合は契約内容(例えば競売時の退去条項)も書類から読み取ります。場合によってはその物件への入札を見送る勇気も必要です。
無理のない資金計画
競売では想定外の支出が起きやすいため、資金計画は常に余裕を持たせます。修繕費や当面の諸費用として、物件価格の2〜3割程度は別途確保しておくのが理想です。
また融資利用する場合は、融資が実行されなかったときに保証金没収のリスクを負えるか慎重に判断します。落札できても資金繰りに行き詰まれば本末転倒なので、「安く買うこと」だけに執着せず財務リスクも勘案しましょう。
専門家へ相談・依頼する
不安な点や専門知識が必要な場面では、躊躇なくプロの力を借りましょう。例えば法的な手続き(引渡命令申立てや強制執行申立て)は弁護士に相談するのが確実です。不動産登記や契約書類の確認は司法書士が専門家です。競売物件専門の不動産会社に入札代行やコンサルティングを依頼すれば、物件調査から入札、落札後のサポートまで一貫して手伝ってもらえる場合もあります。
もちろん費用はかかりますが、初めてで不安な場合は利用する価値はあるでしょう。専門家と連携することで見落としが減り、安全性が高まります。
競売物件投資は儲かる?成功事例と失敗事例
競売物件には成功例もあれば失敗例もあります。それらの具体的なケースを知ることで、リスクとリターンの現実的な姿が見えてきます。ここではいくつか事例を紹介し、何が成功を分けたのか分析します。

成功事例:格安取得による高リターン
ある漫画家は、北海道で戸建てを競売により345万円で落札。市場価格の約9割引という破格で、貯金380万円でマイホームを手に入れました。トイレが汲み取り式で改修費はかかったものの、総額でも相場より大幅に安く済んでいます。
また、一棟アパートを競売で取得し、リフォーム後に高利回りで運用した投資成功例もあります。成功パターンの共通点は「購入価格が圧倒的に安い」「想定内の修繕で再生可能」「事前にリスクを織り込んでいる」ことです。相場観を養い、ライバルが敬遠する物件にも果敢に挑む判断力が重要となります。
失敗事例1:立ち退きトラブル
落札した物件に前所有者が居座り、強制執行まで2ヶ月以上かかったうえ、立ち退き料として数十万円の支出も発生。占有者の性格や状況を事前に見極める重要性が浮き彫りになったケースも。
現在は強制執行手続きが簡素化され昔ほどの酷い居座りは減ったとはいえ、人の感情が絡む問題である以上ゼロにはなりません。交渉力と心積もりがなければ、立ち退きトラブルで時間・お金の両面にダメージを受ける可能性があるということです。
失敗事例2:想定外の修繕費で利益の圧迫に
ある投資家は競売の三点セットをもとに入札したが、内部はシロアリ被害やカビだらけで想定以上にボロボロ。修繕費がかさみ、利回りが大幅に下落し、利益が出ない結果になったケースも。
この事例から分かるのは、書類情報の限界とリフォーム費用の読み違えです。築古物件の場合、表面に見えない部分で重大な瑕疵が潜んでいることがあります。競売ではそれを100%見抜くのは難しいですが、物件の築年・構造・管理状況から最悪のケースを想定しておくべきです。
失敗事例3:残置物・遺品の処理に苦労することも
競売で落札した部屋に家具や遺品が大量に残され、処分に数十万円と時間を要したケースもあります。この失敗のポイントは、残置物処理の負担を見込んでいなかったことです。残置物の存在や所有者の所在は入札前に必ず確認しておきましょう。
「やばい」ではなく「賢い選択」になる条件
正しく理解して活用すれば投資の武器に
競売物件は、仕組みやリスクを正しく理解し、徹底した情報収集と準備を行えば、相場より安く優良物件を取得できる現実的な選択肢です。落札後に想定外のトラブルがあっても、冷静に対処できる準備があれば、大きな利益を得ることも可能です。
成功の鍵は、次の6つのポイントにあります。これらを押さえておけば、「競売はやばい」というイメージに左右されず、賢い不動産戦略として活用することができます。
① 正確な知識と徹底調査
② 資金計画の余裕
③ 適正な入札額の設定
④ 物件選びの見極め
⑤ 専門家の活用
⑥ 柔軟な問題解決力
初心者が始めるならどんな物件を選ぶべきか
競売が初めての方は、まずは扱いやすい物件からスタートするのが理想的です。たとえば、占有者の情報が明確で退去のリスクが低く、建物自体も比較的新しく老朽化が少ない物件であれば、手間や追加費用が抑えられます。さらに、三点セットの内容が具体的かつ分かりやすく、不明点が少ない物件であれば、安心して入札判断を進められるでしょう。
競売は通常の不動産取引と比べて情報が限られるため、最初は慎重すぎるくらいでちょうど良いとも言えます。少しでも不安な点があれば、不動産業者や専門家に相談しながら進めることをおすすめします。経験を重ねることで、自然と判断力と自信も身についていくでしょう。
2025年の競売市場見通し
不動産競売流通協会の青山一広代表理事は、2025年度の競売物件数について「やや増加すると予想している」と述べています。その背景には、住宅ローン返済のリスケジュール(返済額の減額)件数が約50万件存在するという分析があり、その一部が債務超過となり競売に出される可能性があるためです。
ただし、「今後、大幅に減少することも増加することもなく、マーケットとしては恐らく1万5千件〜2万件ほどで推移するだろう」との見方も示されています。これは2009年のリーマンショック後の6万件超という状況に比べれば、比較的安定した水準と言えるでしょう。
現在の競売物件の落札者は約8割が法人、2割が個人となっています。不動産競売は買い手を保護する法律がないことから、落札価格の決定、占有者への退去手続き、修繕など、すべてにおいて自己責任で進める必要があります。
資産運用の選択肢は多彩。リスク分散が成功のカギ

競売物件への投資は不動産投資の一形態ですが、資産運用の方法は他にも数多く存在します。例えば、株式や投資信託、預貯金による運用、不動産でもREIT(不動産投資信託)や賃貸経営など、さまざまな選択肢があります。それぞれリターンの可能性やリスクの性質が異なり、投資の難易度や必要資金も幅広いです。
大切なのはリスクを分散することです。ある一つの資産や方法に全てを投じるのではなく、複数の運用手段を組み合わせることで、特定の投資が失敗した場合でも資産全体へのダメージを抑えることができます。競売物件のような高リスク高リターンの投資に挑戦する場合でも、他の安定した運用とバランスを取ることで、安心感が増すでしょう。
資産運用の経験が浅い方やリスクが心配な方は、少額から始められる手段に目を向けるのも一つの手です。近年はテクノロジーの発展により、少額でも参加できる新しい投資手法が充実してきています。その代表例がクラウドファンディングによる資産運用です。
クラウドファンディングによる新しい資産運用の形
クラウドファンディングとは、インターネット上で多数の投資家から少しずつ資金を集め、大きなプロジェクトや事業に投資する仕組みです。従来は大きな資金が必要だった不動産投資も、クラウドファンディングを利用すれば数万円程度から参加できるため、初心者でも取り組みやすい点が魅力です。
クラウドファンディングの中でも、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)と呼ばれる仕組みは堅実な投資手法として知られています。これは、不動産事業者などに対してオンラインで融資を行い、その利息収入を投資家が分配金として受け取るものです。元本が保証されるわけではありませんが、案件ごとに担保や保証が設定されている場合も多く、比較的リスク管理がしやすい特徴があります。少額からコツコツと資産形成したい人にとって、有力な選択肢の一つと言えるでしょう。
こうしたクラウドファンディングによる投資は、伝統的な投資商品と組み合わせて資産ポートフォリオを組むことで、リスクとリターンのバランスを取りやすくなります。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
まとめ
「適切な物件を、十分な準備のもと、適正価格で買う」。この条件を満たせば、競売物件は決して「やばい」ものではなく、むしろ賢い不動産投資の選択肢になり得ます。リスクとメリットを正しく理解し、冷静に対応すれば、市場価格より安く物件を取得し、長期的なリターンを得ることも可能です。実際、誰も手を出さない物件を安く落札し、適切に再生して成功している投資家もいます。もちろん、競売には予想外のトラブルもありますが、それは通常の不動産取引でも同じこと。大切なのは、リスクを恐れすぎず、きちんと管理できるかどうかです。
なお、「いきなり現物不動産はハードルが高い」と感じる方には、少額から始められる融資型クラウドファンディングによる不動産投資もおすすめです。リスクを抑えつつ、不動産投資の仕組みに触れる第一歩として、ぜひ選択肢に加えてみてください。