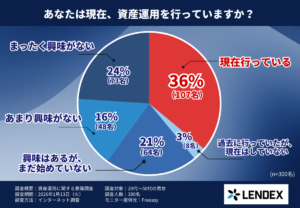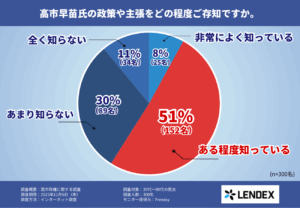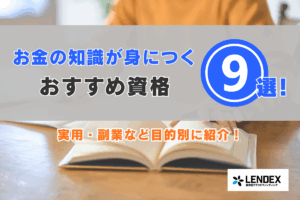近年、投資や資産運用の話題が増え、「貯蓄から投資へ」という流れが強まっています 。しかし、投資は誰にでも向いているわけではありません。たとえブームになっていても、「投資しない方がいい人」は存在します。大切なのは、自分が本当に投資に向いているかを見極めることです。
本記事では、投資で成功する人と失敗する人の違いや、投資しない方がよい人の特徴7選、そして失敗しないための対策やチェックリストについて解説します。ぜひ参考にしてください。
投資は誰にでも向いているわけではない
「投資=やるべきもの」と思われがちですが、実際には投資には向き不向きがあります。投資にはお金を増やすチャンスがある反面、元本割れなど損失のリスクも伴います。そのため、自分の経済状況や性格によっては、無理に投資をしない方がいいケースもあります。
例えば、生活費に余裕がなく貯金もない状態で投資を始めてしまうと、いざというときに投資資金を取り崩す羽目になり、長期的な資産形成ができません。また、投資について十分な知識や準備がないまま流行や人に勧められるままに始めると、思わぬ失敗につながる可能性が高いです。
投資が話題でも「やらない方がいい人」は存在することを理解しましょう。周囲で投資の成功談を聞くと焦るかもしれませんが、自分が当てはまる条件や性格によっては、たとえみんなが始めていても今はやらない方が賢明な場合があります。次章から、投資で成功する人と失敗する人の違いを確認し、自分に投資が向いているか考えてみましょう。
投資で成功する人・失敗する人の違いとは?

同じ商品に投資しても、成功する人と失敗する人に分かれることがあります。その違いには、主に以下のようなポイントが挙げられます。
計画性と目的意識の有無
成功する人は「〇年後に△万円貯める」など明確な投資目的と計画を持っています。
一方、目的がないまま漠然と始める人は運用方針がぶれがちで、必要以上のリスクを取って失敗しやすくなります。目標金額や期限を決めずに始めると、日々の値動きに一喜一憂してしまい、長期的な視点を失いがちです。
リスク管理とメンタル面
成功する投資家は自分のリスク許容度を理解し、どんな損失まで許容できるかを把握しています。一時的な損失が出てもパニックにならず、冷静に対処できます。
逆に失敗しがちな人は、少しでも含み損が出ると不安に駆られて売却してしまったり、感情的な判断で誤った行動を取りがちです。市場の短期的な変動に振り回されて感情で売買してしまうことは、失敗する大きな原因の一つです。
情報収集や学習姿勢
成功する人は投資の勉強を怠りません。新しい投資手法や市場の動向に好奇心を持ち、積極的に知識を身につけようとします。複数の情報源から正しい情報を集め、自分で判断する力を養っています。
一方、失敗する人は「難しいことはよくわからないから」と勉強を避けたり、人任せにしてしまいがちです。基本的な知識がないままでは不利な商品を選んでしまったり、同じ失敗を繰り返すリスクが高まります。
視野の広さと冷静さ
成功する投資家は短期的な利益よりも長期的な資産形成を重視し、忍耐強く運用を続けます。多少価格が上下しても一喜一憂せず、当初の戦略を守り抜く冷静さがあります。
一方、失敗する人は「早く儲けたい」という気持ちが強く、一攫千金を狙った無理な勝負に出てしまう傾向があります。短期間での大きな利益を求めるあまり、基本原則から外れたリスクの高い取引をして失敗するケースが多いのです 。
投資しない方がよい人の特徴【7選】
投資にはメリットもありますが、以下のような特徴に当てはまる人は無理に投資を始めない方がよいでしょう。それぞれの理由を解説します。
貯金がまったくない人
生活に余裕資金がない人は投資に向きません。投資は当面使う予定のない「余裕資金」で行うのが基本です。貯金ゼロで生活費ギリギリの状態では、少しでも運用がうまくいかなかったとき生活が立ちゆかなくなる恐れがあります。
また、運用途中で現金が必要になれば、せっかくの投資を途中で取り崩すことになり、複利効果を十分得られません。まずは最低でも数ヶ月分の生活費を貯蓄し、いつでも引き出せる緊急資金(生活防衛資金)を確保してから検討しましょう。
借金やローンの返済が優先の人
高利息の借金を抱えている人や住宅ローンなど返済を優先すべき人も、借金完済が先決です。借金の利息以上に安定して稼げる投資は簡単ではなく、借金を残したまま投資に手を出すのはリスクが高い行為です。
まずはローンやカードの支払いなど、確実に出ていく支出を整理しましょう。借金を減らせば心の余裕も生まれ、冷静な運用ができるようになります。
リスクを一切許容できない人
元本割れなどのリスクに対して「1円も損したくない」と考える人は、残念ながら投資には向きません。投資である以上、価格変動による損失リスクは避けられません。
リスク許容度が極端に低い人が投資を始めると、少しの含み損にも耐えられずに感情的な判断で資産を失うリスクが高まります 。投資ではある程度のアップダウンを受け入れる心構えが必要です。どうしても損が我慢できない場合、預金や定期積立など元本割れしない方法でコツコツ貯蓄する方が精神的にも良いでしょう。
感情に流されやすい人
日々の株価の上下に一喜一憂したり、周りの意見につい影響されてしまう人も注意です。マーケットのニュースを見ると不安や興奮で衝動的に売買してしまうタイプは、冷静な判断が難しく失敗しがちです。
例えば、株価が上がると「今ならもっと上がるかも」と強気になって高値で買い増ししてしまったり、逆に下落するとパニックになって底値で手放してしまうケースがあります。また、「友人が儲かったらしい」「SNSで話題」など他人の情報に飛びつく人も要注意です。他人に流されてよく調べずに投資すると、詐欺まがいの商品を掴まされる可能性もあります。
感情や噂に振り回されやすい人は、一度立ち止まって自分の判断基準を持てるようになるまで投資を控えた方がいいでしょう。
短期で大きく儲けたいと考える人
「楽してすぐに○○万円稼ぎたい」といった発想で投資を始める人も失敗しやすいタイプです。短期の売買で大儲けしようとすると、必然的にハイリスクな勝負に出ることになり、大損する可能性が高まります。経験の浅い人が短期で利益を狙うと、もはや投資というよりギャンブルのようになってしまう恐れがあります。
実際のところ、リスクを抑えて着実に資産を増やすには長期運用が基本で、短期間で資産が倍増するような魔法の方法はありません。一発逆転を狙う考えの人は、投資ではなく宝くじやギャンブルと混同している可能性があるため要注意です。
投資の勉強や情報収集が面倒な人
投資で成功するにはある程度の勉強と情報収集が欠かせません。基本的な金融知識や経済の動向を学ぶ努力を「面倒だ」と感じる人も、投資には不向きです。何も調べずによく分からない商品に手を出すと失敗しやすく、失敗から学ばずに続ければ損失を拡大しかねません。
逆に「勉強しながら少額で試してみよう」という前向きな姿勢があれば、失敗してもそこから学んで成長できます。勉強自体が苦痛で投資情報を追う気になれない人は、無理に投資を始めず、興味が湧くまで貯蓄に専念するのも一つの手です。
お金の管理ができていない人
自分の月々の収支を把握しておらず、家計管理が雑な人も投資をする前にやるべきことがあります。家計簿をつけるなどお金の流れを管理できないまま投資をすると、どれだけ余裕資金を投じていいか判断できず、余計なリスクを取ってしまう可能性があります。
場合によっては生活費まで投資に回してしまい、生活に支障を来す恐れもあります 。まずは収入と支出のバランスを見直し、毎月安定して確保できる余剰資金を生み出すことが先決です。その上で、その余裕資金の範囲内で投資を検討するのが健全なスタイルと言えます。
投資で失敗しやすい人の共通点とは?
前述の「投資しない方がよい人の特徴」と重なる部分もありますが、投資で失敗しやすい人にはいくつか共通点が指摘されています。
感情に流されて取引してしまう
冷静さを欠き、恐怖や欲望に駆られて売買判断を下す人は失敗を招きやすいです。マーケットの変動に一喜一憂していては長期的な成果は出せません。
損切り(ロスカット)ができない
含み損を抱えていても「そのうち戻るはず」と先延ばしにし、適切なタイミングで損失を確定できない人も要注意です。損切りの判断が遅れると被害が拡大する場合があります。
一攫千金を狙ってしまう
投資をギャンブルのように考え、ハイリスク商品に全力投球する人も失敗しがちです 。高リスク・高リターンの誘惑に飛びつくより、堅実にリスク管理する姿勢が大切です。
余裕資金以上の投資をする
自分の経済力を超える額を投じたり、借金してまで投資するのは非常に危険です。プレッシャーで正常な判断ができなくなり、悪循環に陥る可能性があります。
十分考えずに商品を選ぶ
企業の業績やリスクを調べず、「なんとなく儲かりそう」で商品を選ぶ人も失敗しやすい傾向です。勧められるまま買った商品が自分に合わず損をする例も少なくありません。
他人の意見に頼って判断する
自分で調べずSNSや知人の情報だけを頼りに投資する人も危険です。話題になってから飛びついても遅かったり、根拠の薄い噂に振り回されたりしがちです。
なぜ同じ商品でも「成功する人・失敗する人」に分かれるのか?

同じ投資信託に投資していても、人によって結果が大きく異なるのはなぜでしょうか。その理由は、投資に対する向き合い方の違いにあります。
例えば、ある投資信託を買ったAさんとBさんがいるとします。Aさんはその商品のリスクと目的を理解した上で長期保有し、暴落時も冷静に追加投資するなど計画通り行動しました。一方、Bさんは「みんなが儲かっているから」という理由で何となく買い、価格が下がると怖くなってすぐ売却しました。この場合、Aさんは時間とともに値段が回復し利益を得たのに対し、Bさんは安値で売ったため損失が出てしまいます。
成功する人は、その商品を「どう使いこなすか」にフォーカスします。成功する人は、適切なタイミングで買い増しやリバランス(資産配分の見直し)を行い、多少の下落では方針をぶらさずホールド(継続保有)します。逆に失敗する人は、商品まかせ・運まかせで、自分の運用スタンスが定まっていません。上がれば欲を出し、下がればビクビクして売る、といった調子ではせっかく良い商品でも利益を出すのは難しいでしょう。
また、情報収集と分析にも違いがあります。成功する人は、自分の目標に合うかどうかを考えた上で商品を選びますが、失敗する人は「人気だから」「勧められたから」といった理由で決めてしまいがちです。その結果、商品内容をきちんと理解しないまま購入し、思わぬ損失に戸惑うことになります。
結局のところ、結果の違いは商品ではなく投資家自身の行動と姿勢によるものです。運用力を磨くことが、投資で成果を出すために欠かせない要素なのです。
過去の失敗事例に学ぶ、投資でやってはいけない行動
投資の世界には多くの成功談と同時に失敗談も存在します。過去の失敗事例から、特に初心者がやってはいけない行動を学んでおきましょう。
高リスク商品に全財産を投じる
例えば、ある人は「これさえ当たれば借金も返せる」と高リスクの新興株に貯金のほとんどを注ぎ込みました。しかし予想に反して株価は暴落し、一瞬で資産を失ってしまいました。このように、一つの商品に資産を集中投入するのは非常に危険です。ハイリターンが期待できる商品ほどハイリスクでもあることを忘れてはいけません。
借金やレバレッジを使って投資する
過去には、FX(外国為替証拠金取引)でレバレッジを利かせて大きく張り、相場急変で多額の追証(追加保証金)を抱えて自己破産寸前になった例もあります。借金をしてまで投資すると、失敗したとき取り返しがつかなくなります。自分の身の丈以上のリスクを取ることは絶対に避けましょう。
損切りせず塩漬けにする
含み損を抱えたまま「いつか戻る」と放置し、大損失に繋がった例も多数あります。
ある株式で損失が出た人は、損切りできずに持ち続けた結果、その企業の業績悪化で株価がさらに下落。最終的に最初の損失よりずっと大きな痛手を被りました。損切り(ロスカット)のタイミングを逃すと損失が拡大する典型例です。損失を最小限に抑えるためにも、あらかじめ「〇%下がったら売却」とルールを決めておくことが大事です。
「絶対儲かる話」に乗ってしまう

「元本保証で年利◯%確実」などと謳う怪しい投資話に乗り、大切なお金を失う事件も後を絶ちません。実際、SNSのDMや知人から持ちかけられた話で高利回りをうたうものの多くは詐欺の可能性があります。
過去には高配当を約束する未公開株詐欺やポンジスキーム(自転車操業的な出資金詐欺)で多くの被害者が出ました。「必ず儲かる」「絶対安全」というセールストークは疑ってかかることが重要です。
投資で失敗しないための対策【5選】
投資をこれから始めるにあたって、失敗しやすい人の特徴に心当たりがある場合でも、以下の対策を意識すればリスクを減らせます。
家計を整えて余剰資金を作る
まずは日々の家計を見直し、投資に回せる余剰資金を捻出しましょう。通信費やサブスクの整理、保険の見直しなどで毎月の支出を減らせないか考えてみます。また、生活費数ヶ月分の貯蓄(生活防衛資金)を先に確保しておくことで、投資資金に手をつけずに済み、精神的な安定につながります。家計が整えば、万一投資がマイナスになっても生活に影響が出にくく、冷静に対処できます。
自分に合ったリスク許容度を知る
人それぞれ、経済状況や性格によって許容できるリスクの度合い(リスク許容度)は異なります。投資を始める前に「最悪どれくらいの損失まで耐えられるか」を自問してみましょう。例えば、10万円の投資が一時的に8万円に減っても平気か、それとも動揺して眠れなくなるか、といった具合です。
リスク許容度を理解せずに始めると、予想外の損失に耐えられず感情的な判断で失敗しやすくなります 。証券会社や銀行のサイトにはリスク許容度チェックの簡易診断ツールもあります。それらを活用して自分のリスク許容度を把握し、その範囲内で投資計画を立てることが大切です。
分散投資と長期運用を意識する
投資でリスクを抑える鉄則は「卵を一つのカゴに盛るな」です。資産を複数の商品や分野に分散して投じることで、一つが値下がりしても他で補いやすくなります。
例えば、国内株式だけでなく外国株や債券、投資信託、預金などにバランスよく資産を配分するといった方法です。また、長期投資を前提にすれば、一時的な市場変動の影響は時間とともに平準化され、リターンも安定しやすくなります。実際、長期投資に積立投資や分散投資を組み合わせることで、リスクを抑えて安定したリターンを狙えるとされています。短期で結果を求めすぎず、「長い目でコツコツ増やす」意識を持ちましょう。
定期的な見直し・情報収集を習慣にする
定期的に自分の投資状況をチェックし、目標から大きく逸れていないか見直しましょう。例えば年に一度はポートフォリオ(資産構成)を点検し、特定の資産に偏りすぎていればリバランスする、といった対応が必要です。
また、経済情勢や市場環境は変化しますので、日頃から適度にニュースや投資関連情報に目を通す習慣をつけましょう。「知らないうちに状況が変わって損をしていた」という事態を防ぐため、アンテナを張り続けることが大切です。ただし、情報に振り回されすぎて頻繁に売買を繰り返すのも良くないので、あくまで長期方針に沿って冷静に対処しましょう。
投資詐欺やうまい話に警戒する
常に「おいしい話には裏がある」くらいの警戒心を持ってください。とくに初心者ほど、高利回りをうたう勧誘やSNS上の怪しい投資話に引っかかりやすいものです。
例えば「必ず月利5%出せる」「絶対に損しない」といった謳い文句が出てきたら要注意です。それが本当なら世の中誰も苦労しません。元本保証や100%儲かるといった商品は詐欺の可能性が高いことを肝に銘じましょう。知らない相手からのDM勧誘は無視し、知人からの誘いでも内容が理解できないものには手を出さないことです。金融庁や国民生活センターのサイトでは投資詐欺の手口や事例を公表しています。
投資を始める前にやるべき準備
生活防衛資金の確保とは?
生活防衛資金とは、突然の病気・失業など緊急時でも生活を維持するための蓄え資金のことです。具体的には、日常の生活費の数ヶ月〜1年分程度を目安に現金や預金で確保しておくと安心と言われます。
一般的には単身者なら3ヶ月分、家族がいる場合は6ヶ月〜1年分の生活費が目安とされています 。この生活防衛資金が手元にあれば、投資資金が一時的に目減りしても慌てて引き出す必要がなくなります。
NISAやiDeCoなどの制度理解も重要
日本には個人の資産形成を促すための税制優遇制度が整っています。それがNISA(少額投資非課税制度)とiDeCo(個人型確定拠出年金)です。
NISAは投資で得た利益が一定額まで非課税になる制度、iDeCoは自分で積み立てる年金で掛金が全額所得控除になるなど税優遇がある制度です。それぞれ目的や特徴が異なり、NISAは一般的な資産形成、iDeCoは老後資金作りに適しています。日本政府もこれらの制度を拡充し、「貯蓄から投資へ」の流れを後押ししています。
例えば、NISAを使えば年間一定額までの株式や投資信託の運用益が非課税になります(※2024年からは新NISA制度で生涯投資枠が拡大され、より長期・非課税で運用しやすくなっています)。iDeCoでは掛金拠出時に所得税が軽減され、運用中の利益も非課税、受け取るときにも控除が受けられるといったメリットがあります。ただしiDeCoは60歳まで原則引き出せないなど制約もあります。
これから投資を始めるなら、NISAやiDeCoといった制度をしっかり理解し活用することも重要です。税制優遇を使うことで効率よく資産形成できますが、自分の目的(例えば何年後の資金作りか、老後資金か)によって適した制度が違います。
自分が「投資向き」か簡単に分かる5つのチェックポイント

自分が投資に向いているかどうかをセルフチェックしてみましょう。以下の5つの質問に「はい/いいえ」で答えてみてください。
生活費とは別に、いざという時の蓄え(緊急予備資金)が十分にありますか?
投資に回すお金とは別に、突然の出費や収入減に備えた貯金があるかを確認しましょう。YESなら投資資金に余裕あり。NOならまず貯蓄優先です。
投資金額が一時的に半分に減ったとしても、冷静でいられますか?
最悪のケースを想像してみてください。YESならリスク許容度に余裕あり。NOなら無理なリスクは禁物、投資額を小さく抑えるべきです。
投資の勉強や情報収集を続ける意欲がありますか?
投資本を読んだりニュースをチェックするのが苦にならないか。YESなら知識武装で強みになります。NOなら知識不足で不利にならないよう注意。
「すぐに大金持ちになりたい」より「長期的に資産を増やしたい」という考えですか?
あなたの投資目的が短期のギャンブル的発想ではなく、将来に向けた資産形成になっているか。YESなら堅実志向で◎。NOなら一攫千金狙いは危険信号です。
自分の収支を把握し、計画的にお金を管理できていますか?
毎月の収入・支出や貯蓄計画をきちんと管理できているか。YESなら投資する土台ができています。NOなら家計管理の見直しが先決です。
いかがでしたか?「はい」が多かった人は、比較的投資に向いている素質があります。もちろんYESの数が投資成功を保証するわけではありませんが、少なくとも投資を始めるための基盤は整っていると言えるでしょう。逆に「いいえ」が多かった人は、焦って投資を始める前に準備や改善が必要です。投資は逃げませんので、まずは不足部分を補ってからでも遅くありません。
それでも投資したいなら「少額から」始める
「自分は投資に向かないかも…でもやっぱり興味があるし挑戦してみたい」という場合は、少額からスタートすることを強くおすすめします。

小さく始めてリスク感覚を身につける
投資は実際にやってみないと実感が湧かない部分も多いです。そこで、いきなり大金を投入するのではなく、無理のない範囲の少額で試してみると良いでしょう。例えば毎月5,000円だけ投資信託を積み立ててみる、または株式を1万円分だけ買ってみる、といった具合です。最近では100円から積立投資ができるサービスや、1株単位で少額購入できる証券会社もあります。少額であれば仮に損失が出てもダメージは限定的ですし、値動きによる自分のメンタルの反応も確認できます。
小さく投資を始めてみることで、自分のリスク許容度を肌で感じることができるでしょう。「思ったより価格変動が気にならないな」と感じれば徐々に額を増やせますし、「下がると不安で夜も眠れない」という場合は無理せず一旦やめる判断もできます。このように、経験を通じてリスクへの感覚を身につけることが大事です。
クラウドファンディングの選択肢も
少額から始める方法の一つとして、クラウドファンディングを利用する手もあります。クラウドファンディングとは、インターネット経由で不特定多数の人から少しずつ資金を募り、事業やプロジェクトに投資する仕組みです。投資型クラウドファンディングでは、1万円程度から不動産や企業の案件に出資できるものが多く、まとまった資金がなくても投資体験ができます。
クラウドファンディングのメリットは、小口資金で始められる点と、社会性のあるプロジェクトを応援しながらリターンを得られる点です。ただし元本保証ではなくリスクがある点は通常の投資と同じなので、「絶対安全」というわけではありません。あくまで少額での経験として、興味があれば検討してみると良いでしょう。
少額から始めてみて、うまく運用できたりもっと学びたいと思えたら、本格的に資金を増やしていけば良いのです。最初から完璧を目指さず、トライ&エラーで投資に慣れていくくらいの気持ちで取り組みましょう。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
投資には向き不向きがある。まずは自己理解を深めよう
投資は誰にとっても魔法のようにお金持ちになれる手段ではなく、向いている人もいれば向いていない人もいます。大切なのは、世間の流行や周囲に流されて判断するのではなく、自分自身の状況や性格をしっかり見極めることです。自己分析を深め、「自分は今投資をすべきか?準備はできているか?」と問いかけてみましょう。
もし現時点で「投資しない方がいい人」に該当するなら、無理に始める必要はありません。まずは貯蓄や知識習得など、土台づくりに時間を使ってください。逆に準備万端であれば、少額から経験を積みつつ、長期的な視点で資産形成に踏み出してみましょう。どちらにせよ、闇雲に行動するのではなく正しい情報と計画に基づいて判断することが成功への第一歩です。
最後までお読みいただきありがとうございます。今回の内容が、これから投資を始めるか迷っている方の参考になれば幸いです。