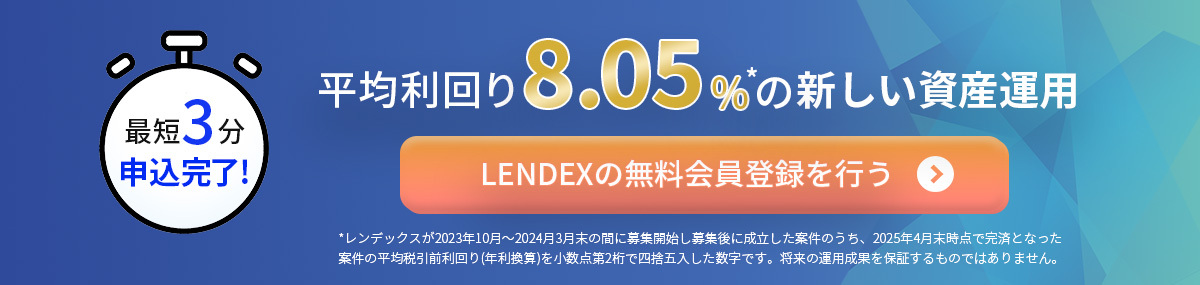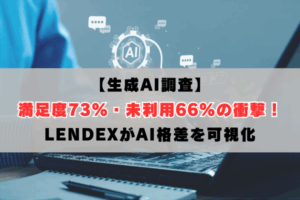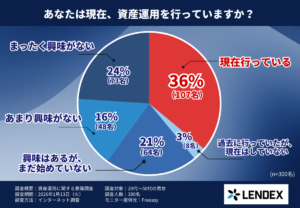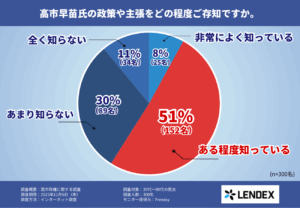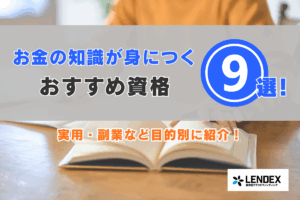初めて不動産投資を検討する方の中には、「オーナーチェンジ物件」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。オーナーチェンジ物件とは、既に入居者がいる状態で売買される賃貸用の不動産のことです。
本記事では、このオーナーチェンジ物件について、網羅的に解説します。不動産投資初心者から中級者の方まで、投資判断の参考になる専門的な内容をわかりやすくまとめました。
オーナーチェンジ物件とは?

すでに入居者がいる物件のこと
オーナーチェンジ物件は別名「入居者付き物件」「賃貸中物件」とも呼ばれ、投資用中古マンションやアパートでよく見られる取引形態です。通常、不動産を購入する際は物件に入居者がいない「空室」の状態で引き渡されますが、オーナーチェンジ物件では入居者が住んだまま物件が引き渡されます。
そのため、新オーナーは購入直後から家賃収入を得られる一方、入居者との契約内容もそのまま継続する点が特徴です。
賃貸契約や家賃収入もそのまま引き継ぐ
具体的には、前オーナーと入居者が結んでいた賃貸借契約をそのまま新オーナーが引き継ぎます。入居者は引き続き同じ条件で居住し、新オーナーに家賃を支払います。敷金・礼金の扱いや物件の管理規約も基本的に変更はできず、契約内容や家賃設定はそのまま据え置かれるのが通常です。
したがって、オーナーチェンジ物件を購入する際は、現在の賃貸借契約書の原本を受け取り隅々まで確認することが重要になります。契約条件や特約事項、更新履歴、敷金の額などを把握し、後から不利な条件が発覚しないよう注意しましょう。
オーナーチェンジ物件が売りに出される理由

オーナー側の事情による売却理由
オーナーの事情による売却は、物件自体に問題がないケースが多く、安心して検討できるパターンです。たとえば、高齢の資産家が老後資金確保のため長年保有してきた物件を売却する場合、建物の管理状態も良く、施工もしっかりしていることが多いです。
また、相続人が納税資金確保や資産分割のために売却するケースもあります。この場合、急いで売却されることもあり、物件に問題がないうえに価格面でも割安な場合があるため、買い手にとって好条件になることがあります。
5年以上保有後に売却される物件も、税制上の理由から自然な売却と考えられます。短期売却と比べて税負担が軽いため、利益確定や資産入替を目的とした合理的な売却である可能性が高く、深刻な瑕疵を抱えているリスクは低いと言えます。
物件・入居者側の事情による売却理由
物件や入居者に問題があって売却されるケースは注意が必要です。 たとえば、入居者との家賃滞納や立ち退きトラブルが原因の物件では、裁判中で家賃が供託されていることもあり、新オーナーが収益を得られないリスクがあります。係争が長引けば空室より厄介です。
また、入居者から家賃の減額交渉を受けている物件も要注意です。たとえ現オーナーが拒否していても、購入後に交渉が再燃し、利回りが下がる可能性があります。
さらに、迷惑行為を繰り返す入居者がいる物件も管理が困難です。深夜の騒音やゴミ問題などにより、他の入居者が退去しやすくなり、空室リスクが高まります。
加えて、特定の部屋が慢性的に埋まらない構造的な問題がある物件も要注意です。日当たりや間取りなど根本的な欠陥があると、空室や退去が続く要因となり、安定した収益が見込みづらくなります。
このような理由で売却されるオーナーチェンジ物件は、購入後に想定外のリスクが顕在化する恐れがあります。不動産会社や売主に対し、「なぜこの物件を売るのか」を必ず確認し、懸念事項があれば納得いくまで説明を受けましょう。売却理由を聞きにくい場合でも、不動産登記簿や賃貸借契約の状況、管理会社へのヒアリングなどから可能な限り情報収集し、リスクの有無を見極めることが大切です。
オーナーチェンジ物件のメリットとは?
オーナーチェンジ物件には、投資家にとって魅力的なメリットがいくつもあります。ここでは代表的なメリットを整理して解説します。
購入後すぐに家賃収入が得られる
既に入居者がいるため、物件購入直後から安定した家賃収入を得られます。空室期間ゼロで投資をスタートでき、入居者募集の手間もかかりません。これは空室リスクを回避できる大きな利点であり、不動産投資でもっとも懸念される空室期間による収入ブレを心配せずに済みます。
収支計画を立てやすい
現在の家賃が確定しているため、購入前にある程度正確な収支シミュレーションが可能です。毎月いくらの家賃収入があるか把握できるので、ローン返済計画や利回り計算も明確です。金融機関からの評価も得やすく、融資審査が通りやすい傾向があります。実際、入居者がいることで収益見込みが立てやすく、「収益還元法」で価格査定されることから融資条件が好転する場合もあります。
購入価格が割安になる可能性
オーナーチェンジ物件は市場相場よりもやや安い価格設定となるケースがあります。収益力に基づいて評価する収益還元法では、同条件の空室物件と比べて1割程度安く査定される傾向があるとのデータもあります 。特に入居中だと実需の自宅希望者には販売できず、買い手が投資家に限られるため競争が減り、その分価格が抑えられる場合があります。
物件の実績データを把握できる
入居者の賃貸履歴や建物の管理状況など、物件の運用実績データを入手しやすいのもメリットです。例えば「何年間家賃滞納なく稼働しているか」「過去にどんな修繕を行ったか」といった情報を前オーナーから引き継げます。新築物件をゼロから賃貸する場合と異なり、実際の運用実績に基づいてリスクを評価できる点は安心材料になります。
オーナーチェンジ物件のデメリット
内部を事前確認できない
入居者が居住中のため、購入前に室内の状態を直接確認しにくいことが最大のデメリットです。内覧できないまま契約せざるを得ず、後になって壁や床の劣化、水回り設備の不具合など想定外の瑕疵が見つかるケースもあります。退去後に初めて室内を確認したら、想像以上に老朽化が進んでいた…というリスクはゼロではありません。
家賃や契約条件を変更しづらい
新オーナーは前オーナーが結んだ賃貸借契約をそのまま引き継ぐため、家賃設定や契約内容を自由に変更できません。仮に現在の家賃が周辺相場より低くても、入居者の同意なしに値上げすることは法律上困難です 。逆に、長年据え置かれ相場より高くなった家賃の場合、次の入居者募集時には家賃を下げざるを得ない可能性もあります。
また契約内容にオーナー不利な特約(例えば過度な設備修繕義務など)があっても、オーナー変更を理由に一方的に改変することはできません。
問題を抱えた物件・入居者リスク
現在進行形のトラブルを抱えた賃貸物件が売りに出されているケースもあり、その場合は購入後に苦労するリスクが高いです。例えば「入居者が家賃を滞納している」「入居者と立ち退き交渉や裁判中である」などのケースです。裁判沙汰になっている物件では、借主が家賃を法務局に供託してオーナーに支払われない状態になっていることもあります。こうしたトラブルメーカーの入居者がいる物件は賃貸経営が困難であり、安易に引き継ぐと収益悪化や精神的負担を招きかねません。
将来的な空室リスクは残る
購入直後は空室リスクがなくても、現在の入居者が退去した後のリスクは常に存在します。例えば物件の立地環境の変化が数年内に予定されている場合、将来的に入居者が付きにくくなる懸念があります。現時点で満室でも、物件固有の弱点(「特定の部屋だけ日当たりが極端に悪くすぐ退去される」等)があれば長期的な空室率に影響します。オーナーチェンジ物件だからといって将来ずっと安泰とは限らない点に注意が必要です。
オーナーチェンジ物件購入時の注意点
前述のデメリットや売却理由とも関連しますが、オーナーチェンジ物件を購入する際には通常の不動産購入以上に綿密なチェックが必要です。以下、購入時の主な注意点を挙げます。
現契約内容の確認

賃貸借契約書の原本を入手し、家賃・敷金・契約期間・更新料・特約事項などを細部まで確認します。更新日が近すぎないか、定期借家ではないかなども重要です。契約書に基づき、敷金の預かりもれや承継すべき費用精算項目がないかチェックしましょう。
家賃の妥当性と支払状況
現在の家賃が周辺相場と比べて適正か確認します。極端に低い場合は利回り向上余地を見込めないことになりますし、逆に高すぎる場合は次回募集時に下げざるを得ない恐れがあります。また入居者の家賃支払い遅延・滞納歴がないか、管理会社経由でヒアリングしましょう。滞納が常態化している入居者だと、引き継いだ後に苦労する可能性があります。
建物・設備の状態
入居中で内見できなくても、建物全体の管理状態はチェックしましょう。管理組合の長期修繕計画書や直近の修繕履歴、外観・共用部の目視点検などから劣化状況を推察します。可能であれば前オーナーに室内写真を提供してもらったり、過去の点検報告書などを見せてもらうと安心です。エレベーターや給排水設備など高額設備の修繕予定も確認し、将来の臨時出費を見積もっておきます。
利回り計算は慎重に
掲載広告の表面利回り(年間家賃収入÷物件価格)だけで飛びつかないよう注意します。固定資産税や管理費、火災保険料、修繕積立金(区分所有の場合)など運営コストを差し引いた実質利回りを算出し、本当の収益性を評価しましょう。特に築古物件では将来の修繕費や家賃下落も織り込んでおく必要があります。
出口戦略の検討も
将来自分がその物件を売却する際のことも考えておきます。購入時と同じようにオーナーチェンジで売るのか、自分の代で投資を終えるのか、戦略によって資金計画やリフォーム投資判断も変わります。短期売却は税負担が重い(5年以内の売却益は約39%課税)ため、長期保有前提であればその期間の融資計画・修繕計画をしっかり立てましょう。
オーナーチェンジ物件の収益性と利回り
投資物件として気になるのが、オーナーチェンジ物件の収益性(利回り)です。一般的に中古の投資用物件は新築より価格が安いため利回りが高めになる傾向がありますが、実際の利回り相場はエリアや物件タイプによって大きく異なります 。
表面利回りの相場傾向
表面利回りの全国平均はおおむね5%弱で、都市部は低く、地方は高くなる傾向があります。 例えば、東京23区内の中古投資マンションでは平均約5.5%とされ、4.0〜5.5%帯の物件が多く分布しています。一方、23区外では平均7.6%超となり、8%前後の高利回り物件も多く見られます。
築年数による違いも大きく、築浅物件は利回りが低く、築古物件は利回りが高い傾向があります。 一般に、築20年以内なら4〜5%、20年以上なら6〜8%以上が目安とされますが、維持費や賃料下落リスクも加味して判断する必要があります。
実質利回りと融資利用の考慮
表面利回りが5%でも、管理費や固定資産税、保険料などを差し引けば実質利回りは3〜4%程度に低下することがあります。投資判断では「家賃収入−経費」で算出した実質利回り(NOI利回り)を基準にすべきです。
さらに、融資を利用する場合は利息分も考慮したキャッシュフローが重要です。低金利下では実質利回りが1〜2%を上回れば投資は成立しますが、今後の金利上昇局面では返済負担が増し、収益を圧迫する可能性があります。 そのため、金利変動リスクも見込んだうえで十分な利回り幅を確保することが重要です。
空室物件との利回り比較
オーナーチェンジ物件は現行家賃が得られている安心感があるため、空室物件より表面利回りがやや低く表示されがちです。一方で、空室物件は将来の家賃上昇を期待して価格が設定されることが多く、埋まらなければ利回りゼロというリスクがあります。つまり、「確実性のある収入を取るか」「将来の伸びしろに賭けるか」という違いがあります。
また、空室物件は満室想定で利回り表示されることが多いため、実際の空室率を考慮して利回りを割り引く必要があります。一方オーナーチェンジ物件でも、現在の家賃が相場より高すぎないか確認し、将来的な賃料下落リスクも見込んで慎重に収益予測を立てることが大切です。
オーナーチェンジ物件と他の投資手法の比較

オーナーチェンジ物件による不動産投資は、他の不動産投資手法や物件種別と比べてどのような特徴があるでしょうか。いくつかの代表的な比較対象とポイントを見てみます。
空室中古物件との比較
空室物件は購入後に自分で賃借人募集を行える自由度があります。自分の裁量でリフォームしたり賃料設定できるメリットがある一方、入居付けできるまで収入がないリスクと手間がかかります。一方オーナーチェンジ物件は手間なく安定収入を得られますが、契約や賃料に自由度がありません。
リスク許容度と手間をかけられる度合いによって向き不向きが分かれるでしょう。初心者で空室リスクを極力避けたい人にはオーナーチェンジ、自由に運用プランを実行したい人には空室物件が向くといった具合です。
新築物件との比較
新築マンション・アパートへの投資は設備や建物が新しく魅力的ですが、価格が高いため利回りが低くなりがちです。購入時は当然空室からスタートするため、最初の入居者募集に時間がかかる可能性もあります。
その点、オーナーチェンジ物件は中古で多少古くてもすでに運用実績があるため、利回りが見えやすくコストパフォーマンスに優れる場合があります。ただし新築は当面大規模修繕も不要で維持費が抑えられるメリットもあります。長期的視野では、減価償却などの税メリットも築年によって異なるため(中古の方が償却短期で節税効果大など)、総合的に検討しましょう。
一棟収益物件との比較
区分マンション(一室)投資と、一棟アパート・マンション投資ではリスク・リターンの性質が異なります。一棟物件のオーナーチェンジでは、複数戸のテナント状況まで引き継ぐため、一部屋の空室でも他から家賃収入があるというリスク分散効果が期待できます。その代わり一棟全体の価格が高額で融資負担も大きくなります。
区分のオーナーチェンジ物件は初期投資が小さい反面、一戸空けば収入ゼロになるリスクがあります。ただし流動性(売却しやすさ)は区分の方が高い傾向があります。一棟物件では管理や維持に専門知識もより必要になるでしょう。オーナーチェンジという点自体のメリット・デメリットは区分でも一棟でも基本同じですが、スケールによるリスク分散と資金計画に違いがあります。
他の資産クラスとの比較
オーナーチェンジ物件投資は不動産という実物資産への投資であり、株式のように日々価格が乱高下することはありません。家賃という安定収入が見込め、インフレにも強い資産とされます。
一方で流動性が低く現金化に時間がかかる、購入にはローン審査等のハードルがある、といった点は不動産投資全般のデメリットです。不動産市況や金利環境によって資産価値が変動するリスクもあります。特にレバレッジ(融資)を利かせるため、返済計画が狂うと自分の信用にも関わる点は金融商品にはないプレッシャーでしょう。ただ総じて、堅実に運用できればミドルリスク・ミドルリターンの資産運用として有力な選択肢となります。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
最新の不動産市場動向とオーナーチェンジ物件

2020年代半ば現在の不動産市場環境がオーナーチェンジ物件の投資判断に与える影響について整理します。近年の市場動向としては、中古マンション価格の高騰と在庫増加、そして金利環境の変化が大きなトピックです。
中古物件価格は高止まりも在庫増加傾向にある
日本の中古マンション市場は長年価格上昇が続いてきましたが、最近では在庫が増加し、成約件数は減少傾向にあります。2023年も価格は前年より+6.9%上昇したものの、東京都23区では価格が下がった物件の割合が増加しており、市場に踊り場の兆しが出てきました。
このような状況では、オーナーチェンジ物件の購入も慎重な見極めが必要です。売り物件が増えたことで選択肢は広がる反面、高値掴みのリスクも。逆に、今後価格が下がれば利回り改善が期待できる局面でもあります。以前は利回り4%台だった人気エリアでも、5〜6%の物件が出始めている可能性があり、買主優位の交渉がしやすくなるタイミングかもしれません。
金利・経済動向と投資環境
日本でも低金利時代の終わりが視野に入りつつあり、長期固定金利はすでに上昇傾向にあります。今後は変動金利も含めて融資環境が厳しくなる可能性があり、不動産投資にとってはローン返済の負担増や物件価格の下落リスクが現実味を帯びてきました。
特に金利上昇は、購入者の減少を招き売却価格の下押し要因にもなります。逆に円安が進めば、海外投資マネーの流入という下支え要因も期待できますが、区分マンションなど小口物件への影響は限定的でしょう。
こうした局面では、収益性を慎重に見極める姿勢が不可欠です。金利上昇や空室リスクを織り込んでもなおキャッシュフローが回るか、ストレステストを行いながら投資判断を下す必要があります。特に賃貸需要の高いエリアや高利回り物件であれば、下落局面でも安定収益が見込めます。
今後は「攻める」よりも備える姿勢が大切で、相場を冷静に見極めつつ、良い物件が出たときに動けるよう知識と資金の準備を怠らないことが成功の鍵となるでしょう。
まとめ
本記事では、オーナーチェンジ物件の仕組みからメリット・デメリット、売却理由の裏側、購入時のチェックポイント、収益性や税金の知識、そして最新の市場トレンドまで幅広く解説しました。不動産投資は情報戦かつ忍耐の要る投資ですが、正しい知識を持って臨めば堅実に資産形成できる手段です。
オーナーチェンジ物件は、その一つの選択肢として非常に有効ですが、メリットに飛びつく前にデメリットやリスクも十分検討しましょう。専門家の力も借りながら、ぜひ安全で有益な不動産投資を実現してください。投資判断の際には本記事の内容がお役に立てば幸いです。今後の市況変化にもアンテナを張りつつ、賢い資産運用にチャレンジしていきましょう。