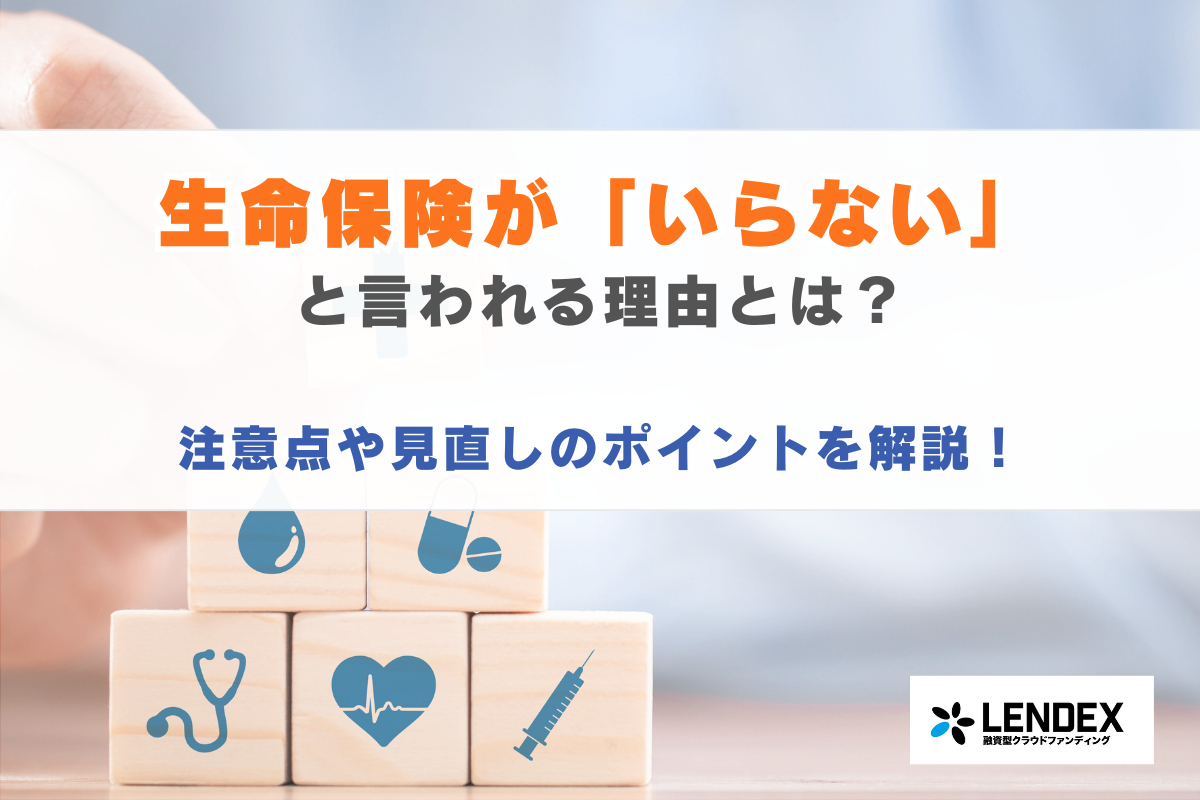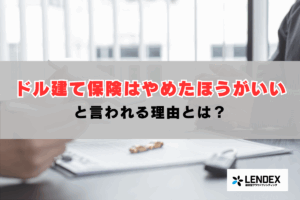最近、「生命保険はいらない」という声を耳にする機会が増えています。実は日本では2人以上世帯の約89%が生命保険に加入しています。しかし、「とりあえず入っておけば安心」というものでもなく、現代では必ずしも全員に生命保険が必要ではない場合もあります。
なぜそのように言われるのでしょうか。本記事では「生命保険がいらない」と言われる理由とその背景、いざという時の注意点や保険の見直しポイントについて、わかりやすく専門的に解説します。
生命保険はいらないって本当?その理由をわかりやすく解説

保険の本質は「万が一の備え」であり、全員に必要ではない
生命保険の本質的な役割は「万が一のときの経済的備え」です。つまり、家計を支える方が亡くなった場合など、残された家族の生活を支えるための保障が本来の目的です。独身で扶養家族がいない人まで含め、すべての人に生命保険が必須というわけではありません。生命保険はあくまで万が一に備える手段の一つであり、状況次第では「いらない」と判断されることもあるのです。
例えば公的保障や十分な貯蓄がある人にとっては、民間の生命保険に頼らなくてもリスクに対応できるケースがあります。日本では2人以上の世帯の約9割が生命保険(個人年金保険を含む)に加入していますが、これは「みんなが入っているから安心」という理由で加入している人も少なくありません。重要なのは自分に本当に必要な保障かどうかを見極めることであり、必要性が低い人にとっては生命保険はいらない場合も十分考えられます。
貯蓄や資産運用でカバーできるケースが増えている
近年では、民間の保険に頼らずとも貯蓄や資産運用でリスクに備える人が増えています。実際、生命保険文化センターの調査によれば、2人以上世帯では万一の場合の備えとして「生命保険」を挙げる人が56.1%と最も多いものの、単身世帯では「あらゆる備えで預貯金(貯蓄)に期待する」傾向が顕著です。このように、特に扶養家族のいない人を中心に自分の貯蓄でカバーしようという考え方が広がっています。
また、保険金額の傾向にも変化が見られます。2人以上世帯の生命保険による死亡保障額は平均約1,936万円で、これは3年前より減少傾向にあります。保障額の平均が下がっているのは、昔に比べて高額の死亡保障を必要とする人が減っていることの表れとも言えます。住宅ローンや教育費なども低金利や公的制度で対応しやすくなり、従来よりも生命保険に頼らなくても良いケースが増えているのです。
実際にどんな人が「生命保険はいらない」のか?

独身・子なし・資産に余裕がある人
まず、独身で子どもがおらず、経済的に余裕がある人は生命保険がいらない代表的なケースです。扶養すべき家族がいないため、自分に万が一のことがあっても金銭的に困る人がいません。現代の日本では全世帯の約3分の1が単身世帯とも言われており、こうした方々の多くは死亡時の保障を必要としていません。十分な貯蓄や資産を持っている場合は、自分自身の貯蓄=「自家保険」で万が一に備えることも可能です。
例えば、ある程度の預金があれば葬儀費用や借金の清算にも充てられますし、遺される家族がいなければ高額な死亡保険金は不要でしょう。もちろん、自営業で親に万一の際の資金を残したいなど特殊な事情があれば別ですが、一般的に独身で経済的基盤がある人に生命保険は必要性が低いと言えます。「自分が亡くなった後の経済的リスク」を冷静に考えた時、心配がほとんどない方は、無理に生命保険に入る必要はないでしょう。
団体信用生命保険などで保障が足りている人
すでに他の保障制度で必要十分な保障を得ている人も、追加で生命保険はいらない場合があります。
代表的なのが住宅ローン利用者が加入する「団体信用生命保険(団信)」です。団信に加入していれば、契約者が死亡または高度障害状態になった場合に残りの住宅ローンが完済されます。つまり、マイホームのローン返済という大きな支出リスクは団信でカバー済みなのです。このように、住宅ローン債務については団信で備えられている場合、改めて死亡保険で住宅費分をカバーする必要は低くなります。
また、会社員の方で企業から手厚い死亡退職金制度や団体保険に加入している場合も同様です。公的保障+勤務先の保障制度で十分に家族を守れる場合、民間の生命保険を追加するのは保険料の無駄になる可能性があります。自分に既に備わっている保障を確認し、過剰な重複があれば見直しを検討しましょう。
いらないどころか損をする?生命保険にありがちな誤解

【2025年最新情報】金利上昇による保険料値下げの動き
2025年は日銀の利上げと長期金利上昇を背景に、約40年ぶりに生命保険の予定利率引き上げが行われています。
大手生保各社が予定利率を0.15%から0.4%程度へ段階的に引き上げることで、新契約の保険料が平均5~12%下がる見通しです。終身保険や学資保険の返戻率も103%から108%程度へ改善するなど、保険商品の魅力が向上しています。
ただし、これは新規契約に限られるため、既存契約の見直しを検討する価値があります。
終身保険=お得と考えるのは危険
生命保険には定期保険(掛け捨て)や終身保険、養老保険など様々な種類がありますが、中でも終身保険がお得だという誤解には注意が必要です。
終身保険は一生涯の死亡保障が続き、解約返戻金(払い戻し金)もある商品です。「払った保険料が無駄にならないからお得」と思われがちですが、実際には保険会社のコストや予定利率が反映されているため、同額の保険料を貯金・運用した場合と比べてリターンは低く抑えられる傾向があります。
例えば、終身保険の解約返戻金の利回りはごく低く設定されており、長期間払い込んでも増えるお金はわずかです。低金利時代では特に、終身保険でお金を増やすことは期待しにくいでしょう。「貯蓄にもなるから得」という宣伝文句をうのみにするのは危険であり、本当に自分に必要な保障か、純粋な貯蓄や投資の方が有利ではないかを冷静に判断することが重要です。
「貯蓄型」の保険は本当に必要?
学資保険や個人年金保険など、貯蓄型の保険も一見すると魅力的に映りますが、本当に必要か再考する価値があります。
貯蓄型の保険商品は、保険でありながら将来に備えてお金を積み立てる仕組みです。しかし、その利回りは預貯金よりやや良い程度か、場合によっては手数料等を考慮すると見劣りすることもあります。加えて途中解約すると元本割れする可能性が高く、資金の流動性も低くなります。
例えば子どもの学費目的で学資保険に入る場合、18年程度の長期にわたり毎月保険料を払い続ける必要があります。その間にライフプランが変わったり、もっと有利な資産運用の方法が出てきたりしても、簡単に乗り換えられません。
「保障が付いた貯蓄」は便利なようで制約も多いのです。本当に必要な保障なのか、あるいは単純に貯蓄や低リスクの投資で備える方が良いのか、メリット・デメリットを比較検討することが大切です。
保険料を払いすぎて家計を圧迫していないか?
生命保険が「いらない」どころか、入りすぎると家計の負担になって損をするケースもあります。
日本の2人以上世帯では、生命保険(個人年金含む)にかける年間保険料は平均で35.3万円にもなります。毎月に直すと約3万円ですから、決して小さくない支出です。必要以上に高額な保険に入っていると、その分貯蓄や投資に回せるお金が減り、将来の資産形成の妨げにもなりかねません。
家計に占める保険料の割合が大きすぎると感じる場合、一度保障内容を見直してみましょう。例えば、大きな死亡保障が必要なのは子どもが独立するまでの期間だけなのに終身保険で一生涯カバーしていたり、医療保険を過剰に重複契約していたりしないでしょうか。
保険は必要最低限で良し、浮いたお金は貯蓄や資産運用に充てる方が、トータルで見て家計にプラスになることも多いのです。「保険料貧乏」になっていないか、この機会に点検してみることをおすすめします。
生命保険が必要なケース|本当に備えておくべき人は?

小さな子どもがいる家庭
ここまで生命保険はいらない場合について述べましたが、やはり必要性が高いケースも存在します。典型的なのは小さな子どもがいる家庭です。子どもは成長するまで長い年月と費用がかかります。もし主要な収入源である親に万が一のことがあれば、残された子どもの生活費や教育費に大きな支障が出るでしょう。
例えば、子ども一人を大学卒業まで育てるには、学費や生活費など数千万円単位の資金が必要になるとも言われます。公的年金には遺族年金という仕組みがありますが、支給額には限りがありますし、子どもの将来まで十分に賄えるものではありません。
子どもが独立するまでの期間に限定して、十分な死亡保障を用意しておくことは重要です。具体的には、定期保険など期間を区切った保障で、子どもが社会人になるまでの生活費・教育費をカバーできる金額を設定すると良いでしょう。
高額な住宅ローンがある場合
次に、高額な住宅ローンを抱えている場合も生命保険(死亡保障)の必要性が高くなります。前述のとおり団体信用生命保険に加入していればローン残債はカバーできますが、ローン以外にも毎月の生活費や子どもの教育費などは遺された家族が払い続けねばなりません。特に住宅ローン返済中の家庭では、ローン以外の支出も多く、万一収入が途絶えたら家計が成り立たなくなる恐れがあります。
たとえ団信で住居費の心配がなくとも、ローン返済期間中は家計全体の保障を手厚くすることが大切です。具体的には、ローン残高や家族の生活費を考慮した死亡保険に加入し、残された家族がローン返済以外の費用も含め困らないだけの保険金を確保します。住宅ローンという大きな債務がある以上、完済までは収入保障保険など収入を補償するタイプの保険で遺族の生活費をカバーする選択肢も有効です。
高額なローンがあるご家庭では、「生命保険はいらない」と安易に考えず、リスク対策を検討しましょう。
自営業・フリーランスで公的保障が薄い人
自営業者やフリーランスの方も、生命保険の重要度が高いケースです。会社員と比べて公的保障が手薄であり、万一の際の支えが少ないためです。会社員であれば厚生年金から遺族厚生年金が支給されたり、勤務先から死亡退職金が出たりすることがあります。しかし、自営業者(国民年金加入のみ)の場合、遺族年金は基礎年金部分だけで支給額が少なく、企業からの保障ももちろんありません。
また、自営業者は収入が不安定なことも多く、十分な貯蓄が難しい場合もあります。そうした中で一家の大黒柱にもしものことが起きれば、残された家族の生活はたちまち苦しくなるでしょう。公的な遺族補償が薄い分、民間の生命保険で手厚くカバーしておく必要性が高いと言えます。
特に小さな子どもがいる自営業の方は、会社員以上に高額の死亡保障を用意しておくことも検討すべきです。生命保険がいらない人もいる一方で、こうした方々にとっては生命保険は家族を守る上で欠かせないセーフティーネットとなります。
保険の代わりに何をすればいい?「自分で備える」時代へ

必要最低限の保障だけ確保する
生命保険にあまり頼らない人が増えている背景には、「自分で備える」意識の高まりがあります。無駄な保険を持たず、本当に必要な部分だけを保険でカバーし、他は自己資金で対応しようという考え方です。
その第一歩は、必要最低限の保障だけ確保するという発想になります。例えば、死亡保障であれば家族に必要な期間・金額を計算し、その範囲を定期保険など割安な商品で備えるにとどめます。過剰な特約や不要な終身保障は付けません。
また、独身であれば思い切って死亡保障をゼロにするのも一つです(なお、単身世帯の生命保険加入率は45.6%と2人以上世帯に比べて大幅に低く、単身者では預貯金による備えを重視する傾向があります)。
保険は「入れば安心」ではなく、「入らなくても困らないなら入らない」で良いのです。こうして節約できた保険料分は貯蓄や投資に回し、自分自身の資産形成に充てましょう。必要最低限の保険+自己資金で備えるスタイルが、これからの新しいリスク管理の形と言えます。
医療・死亡保障は公的制度も活用する
「自分で備える」時代とはいえ、公的な保障制度を上手に使うことも忘れてはいけません。日本には充実した社会保障制度が整っており、医療や死亡時の公的保障もある程度備わっています。例えば医療費については、健康保険により自己負担は原則3割で済み、高額療養費制度によって中程度の収入の方なら1か月の自己負担上限は約8万円程度まで抑えられます。つまり、極端に高額な医療費が発生するリスクは公的医療保険でカバーされているのです。
死亡時についても、会社員であれば厚生年金から遺族厚生年金、自営業でも遺族基礎年金(18歳未満の子がいる場合)などが支給されます。公的年金だけで家族の生活費を全てまかなうのは難しいものの、基本的な生活費の一部は公的制度で支援される仕組みがあります。
民間の保険に入らない場合でも、こうした公的保障+貯蓄でどこまで対応できるかを計算し、不安な不足分だけを民間保険で補うという考え方が重要です。「まず公的制度でどこまで賄えるか」を把握した上で、足りない部分だけ民間保険を検討するのが賢明でしょう。
資産形成の一環として投資を検討する人も増えている
保険より柔軟でリターンが見込める手段とは?
保険に頼りすぎない人々は、その代わりに資産運用(投資)で将来に備える傾向があります。保険は原則として万が一の際にしかリターンを生まない商品ですが、投資であれば将来に向けて資産を成長させることが期待できます。
近年、政府の後押しもあり「貯蓄から投資へ」の流れが強まっています。実際、2024年には少額投資非課税制度(NISA)の拡充が行われ、多くの個人が投資を始めています。金融庁の発表によれば、2024年6月末時点でNISA口座数は約2,428万口座に達し、累計買付額は約45兆円にも上っています。これはより柔軟な資産形成手段として投資が広く受け入れられつつあることを示しています。
投資には価格変動リスクが伴いますが、その分長期的なリターンも期待できます。例えば、投資信託や株式への積立投資は、時間をかけて複利効果を得ることで将来の大きな備えとなり得ます。保険ではインフレに対応した資産成長は見込みづらいですが、投資ならインフレに負けない資産づくりも可能です。「万が一への備え=保険」だけでなく、「将来の安心のための備え=投資」という発想が、徐々に一般の方にも浸透してきています。
分散投資で将来の安心を自分でつくる
資産運用で備えると言っても、闇雲にリスクを取る必要はありません。重要なのは分散投資でリスクを抑えながら資産形成を行うことです。例えば、株式・債券・投資信託・預貯金など複数の資産に分けてお金を配置すれば、一部の投資が不調でも他でカバーできる可能性が高まります。近年はロボアドバイザーやバランス型ファンドなど、初心者でも簡単に分散投資が実践できるサービスも充実しています。
分散投資によって長期的に資産を増やしていけば、将来の万が一の出費にも自分の資産で対応できる余力が生まれます。言い換えれば、自分で将来の安心を作り上げることができるのです。もちろん投資には元本割れのリスクがありますので、無理のない範囲から始め、時間を味方につけてコツコツと資産形成することが大切です。保険に過度に頼らずとも、分散された堅実な投資を継続することで、「いざという時も自分の資産で家族を守れる」という自信と安心感を得られるでしょう。
融資型クラウドファンディングという新しい選択肢も
価格変動のない資産で守りながら増やす
資産運用には興味があるものの、株式の価格変動リスクが心配という方もいるでしょう。そうした方に注目されているのが融資型クラウドファンディングです。融資型クラウドファンディングは、投資家が事業者への貸付に出資し、利息収入を得る仕組みで、「ソーシャルレンディング」とも呼ばれます。特徴は、値動きのない資産であることです。株式のように日々価格が上下することはなく、契約された利率で安定的に運用できます。
この仕組みにより、マーケットの急変動による元本評価額の変化を気にせずに済み、守りながら資産を増やすことが可能です。融資先の事業者が破綻しない限り、元本と利息が約束通りに支払われるため、リスクを抑えつつも銀行預金よりは高い利回りを狙える点が魅力です。生命保険と同様に「元本保証的な安心感」を持ちつつ、資産運用によるリターンも得たいという方にとって、融資型クラウドファンディングは新しい選択肢となり得ます。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
生命保険の見直しポイント|損しないためにやるべきこと

保障内容・保険期間・保険料のバランスを確認
現在生命保険に加入している方も、「いらない保険に入りすぎていないか」定期的に見直すことが大切です。見直しの際にチェックしたいポイントは、保障内容・保険期間・保険料のバランスです。具体的には次のような点を確認しましょう。
保障内容
自分や家族に本当に必要な保障かどうか。例えば死亡保障額が過大ではないか、不要な特約が付いていないかを点検します。家族構成やライフステージの変化に伴い、適切な保障額は変化します。
保険期間
保険の保障期間が長すぎたり短すぎたりしないか。子どもの独立までで良い保障を終身まで契約していないか、逆に必要な期間をカバーできていない穴はないかを確認します。
保険料
保険料負担が家計を圧迫していないか。収入に対して保険料の割合が高すぎる場合は、保障を縮小するかより安い商品への切り替えを検討します。
これらのバランスが崩れていると、無駄な保険料を払い続けることになり損をする可能性があります。逆に言えば、保障・期間・保険料のバランスを最適化することで、必要十分な備えをしつつ家計の無駄を省けます。定期的に証券を見直し、「この保障は今の自分にふさわしいか?」と問い直す習慣を持ちましょう。
保険ショップやFP相談を上手に活用しよう
生命保険の見直しは自分だけで判断しにくい部分もあります。その際は、保険ショップやファイナンシャルプランナー(FP)への相談を上手に活用するのも一つの方法です。保険ショップでは複数社の保険商品を比較検討できますし、FPなら家計全体を踏まえた中立的なアドバイスをもらえます。
例えば、保険のプロに現在の加入内容を見せて「保障が重複していないか」「他に適切な商品はないか」などをチェックしてもらえば、自分では気付かなかった改善点が見つかるかもしれません。無料相談を提供する保険ショップも多く、気軽に意見を聞けるのはメリットです。ただし、ショップによっては特定の保険会社の商品を勧める傾向もあるため、複数の窓口でセカンドオピニオンを得ることも大切です。
FPへの相談では、有料相談であっても家計全体の見直しと絡めて生命保険を考えることで、本当に必要な保障が明確になるでしょう。第三者の視点を取り入れることで、独りよがりな判断ミスを防ぎ、損しない見直しが実現できます。「保険はいらないかも」と思ったら、専門家の知見も取り入れつつ、賢く見直しを進めましょう。
よくある質問(FAQ)|生命保険の不安や疑問に答えます
Q. 医療保険は入っておいたほうがいい?
医療保険に関しては、公的医療保険制度が手厚いため必ずしも必要とは限りません。日本では全国民が何らかの健康保険に加入しており、治療費の自己負担は3割、さらに高額療養費制度で月額負担に上限があります。そのため、がん治療などで長期入院・高額治療となっても、自己負担額は意外と抑えられます。十分な貯蓄があれば、入院費程度はまかなえるケースも多いでしょう。
ただし、公的保険が効かない先進医療や、長期休職中の生活費などカバーされないリスクもあります。そうした不安がある場合は、低額でも民間の医療保険に入っておくと安心材料にはなります。ポイントは、自分の貯蓄額や家族構成に照らして「公的保障+貯蓄で足りるか?」を判断することです。足りない部分だけを補う最低限の医療保険に留めれば、保険料の負担を抑えつつ安心も得られるでしょう。
Q. 途中解約すると損をする?
多くの貯蓄型保険は途中解約すると元本割れ(払込保険料総額より解約返戻金が少ない)になるため、「損をする」と言われます。特に契約から数年~十数年以内の早期解約では解約返戻金がごくわずかしか戻らない商品も多く、支払った保険料の方が大きく上回ります。
ただ、一方で不要な保険をそのまま継続すること自体が損失につながるケースもあります。払込期間が長期に及ぶほど、不要な保険に払い続ける保険料総額は膨らんでいくからです。
したがって、「この保険はいらないかも」と感じたら、損得勘定も大切ですが将来の家計全体への影響で判断しましょう。解約による損失が小さく、浮いた保険料をより有効に活用できるなら早めに見直す価値があります。
逆にもうすぐ満期で返戻金を満額受け取れるなどの場合は継続した方が良いでしょう。保険会社に問い合わせれば現在の解約返戻金額を教えてくれますので、一度試算してもらい、総合的に判断することをおすすめします。
Q. 保険をやめたあと何で備えたらいい?
生命保険を解約・減額して保障を減らした場合、その分の備えは自分で用意する必要があります。具体的には、まずは十分な緊急予備資金を貯蓄しておきましょう。目安として生活費の6か月~2年分程度の貯金があれば、大抵の突発的な出費には対応できます。死亡保障をやめた場合は、葬儀費用や債務清算費用などを見積もってその分の預金を用意しておくと安心です。
加えて、資産運用で長期的な備えを作ることも有効です。投資信託の積立や個人年金代わりの投資商品などにコツコツお金を回せば、将来まとまった資金を作る助けになります。公的年金や退職金なども老後の備えになりますので、そちらの計算も忘れずに。
要するに、保険をやめた分は「自分が保険会社になる」イメージで蓄えや運用を行うのです。そうすることで、保険料を払わなくても万一に備えられる強固な家計を築くことができます。
まとめ|保険は「いらない」のではなく「見直す時代」へ

「生命保険はいらない」という言葉だけ聞くと極端に思えるかもしれません。しかし本質的には、「闇雲に保険に入る時代から、自分で取捨選択して見直す時代へ移行している」ということです。保険が必要かどうかは人それぞれの状況によります。家族構成や資産状況によっては、本当に生命保険がいらない人もいれば、一方で不可欠な人もいます。
大切なのは、「なんとなく不安だから入っておく」という発想を改め、自分に合った保障だけを持つことです。公的保障や貯蓄・運用を駆使すれば、民間の保険に頼り切らなくても生活の安心は確保できます。つまり、保険そのものを否定するのではなく、過不足のない適切な保険に見直すことが求められているのです。ぜひこの機会にご自身の生命保険について見直しを行い、必要な備えと無駄のない家計のバランスを見つけてみてください。
参考元
・公益財団法人生命保険文化センター:「2024年度 生命保険に関する全国実態調査(速報版)」(2025年)
・厚生労働省:「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
・金融庁:「NISAの利用状況の推移」