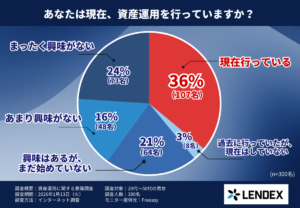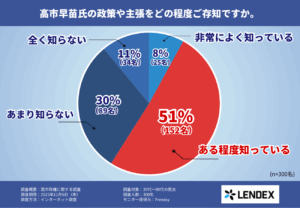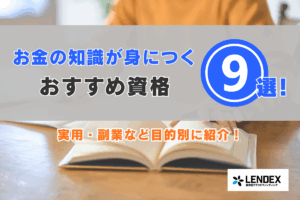「孫にお金を贈りたいけれど、贈与税が心配…」「生前贈与で節税しながら、賢く資産承継したい」そんなお悩みをお持ちの方にぜひ知っていただきたいのが、孫への生前贈与で活用できる「非課税制度」です。一定の条件を満たせば、贈与税ゼロで教育資金や結婚・子育て資金を贈与できる特例が存在し、相続税対策としても大きな効果が期待できます。
しかし、非課税制度には適用条件や期限、使い方の注意点が多く、制度改正も頻繁に行われているため、最新情報を正しく理解することが重要です。特に2024年以降は「相続時精算課税制度」の見直しなど、贈与をめぐるルールが大きく変わり始めています。
この記事では、孫への生前贈与に関する基本知識から非課税制度の具体的な使い方、2024年以降の改正点、よくある誤解や失敗例まで丁寧に解説します。さらに、贈与とあわせて考えたい資産管理や分散投資の視点についても詳しく紹介。将来の不安を減らし、家族に安心を届ける一歩として、今からできる贈与と資産設計のヒントをお届けします。
孫への生前贈与で税金ゼロにできるって本当?

まず結論から言えば、孫への生前贈与によって贈与税をゼロに抑えることは可能です。ただし、それには税制上の特例を活用する必要があります。
通常、個人間でまとまった金銭や資産を贈与すると、その受贈者(もらった側)に贈与税がかかります。親や祖父母など近親者間でも例外ではなく、年間の贈与額が一定額を超えると贈与税が課税される仕組みです。
しかし、日本には贈与税対策としていくつかの非課税制度(特例制度)が設けられており、これらを上手に使えば贈与税をゼロにできるケースがあります。以下では、孫への生前贈与に関わる基本と、税金がかからない特例制度について詳しく解説していきます。
そもそも生前贈与とは?贈与税の基本をおさらい
生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を子や孫などに贈ることを指します。法律上は「あげる人(贈与者)」ともらう人(受贈者)との契約であり、口頭のやり取りでも成立しますが、後日の証明のため書面に残すことが望ましいでしょう。
生前贈与で気を付けたいのが贈与税です。贈与税は贈与を受け取った人に課される税金で、毎年1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額の合計から基礎控除額110万円を差し引いた残りに対してかかります。つまり年間110万円までは非課税で、それを超える部分に税金が発生します。
贈与税率は累進課税で、金額が大きいほど最大55%まで高くなります。なお、複数の人から贈与を受けた場合でも合算して110万円を超えれば課税対象になる点に注意が必要です。
また、親や祖父母が通常必要と認められる範囲で負担する教育費や生活費は、「扶養義務者からの必要な支出」として最初から贈与税の課税対象外と解釈されます。例えば学費をその都度支払う場合などは非課税ですが、将来の分までまとめて渡すと余剰分は課税対象になってしまいます。
税金ゼロにできる“非課税制度”がある
生前贈与による贈与税対策として、「贈与税がかからない非課税制度」がいくつか用意されています。代表的なものは以下の3つで、いずれも一定額までは贈与税がゼロになります。
- 暦年贈与の基礎控除(110万円枠) – 毎年110万円まで非課税で贈与できる制度。
- 教育資金の一括贈与の特例 – 孫の教育目的資金を最大1,500万円まで非課税でまとめて贈与できる制度。
- 結婚・子育て資金の一括贈与の特例 – 孫の結婚や育児目的の資金を最大1,000万円まで非課税で贈与できる制度。
これらの特例を利用すれば、適用範囲内の贈与額については贈与税が一切かかりません。ただし、制度ごとに細かな条件や手続きが定められているため、「非課税だから安心」と安易に考えず、ルールを正しく理解することが重要です。
次の章では、これら3つの非課税制度の内容をそれぞれ具体的に見ていきましょう。
贈与税がかからない制度とは?3つの非課税制度を解説

孫への生前贈与で活用できる主な非課税制度は、先ほど挙げた3種類です。それぞれ適用条件や上限額が異なりますので、順番に解説します。
暦年贈与(基礎控除)|年間110万円まで非課税
最も基本的な非課税枠が暦年贈与による基礎控除110万円です。これは毎年の贈与に適用される枠で、受贈者1人あたり年間110万円までの贈与なら贈与税がかかりません。
例えば祖父母から孫へ毎年110万円ずつ贈与すれば、その都度贈与税ゼロで資産移転が可能です。110万円を超えた部分については金額に応じて贈与税率(10%~55%の累進税率)が適用され、受贈者が翌年に申告・納税する必要があります。
暦年贈与の非課税枠は毎年リセットされるため、計画的に活用すれば長期間かけて多額の財産を税負担なく移転できるメリットがあります。「孫への生前贈与」というとまずこの110万円枠を思い浮かべる方も多いでしょう。
ただし、110万円以内でも贈与の事実を示す証拠(贈与契約書や預金通帳の記録など)を残しておくことが望ましく、後日のトラブル防止につながります。
教育資金の一括贈与|1,500万円まで非課税
祖父母が孫(30歳未満)の教育費をまとめて援助できる教育資金一括贈与の特例があります。この制度では孫1人につき最大1,500万円までの教育資金を非課税で贈与可能です(※学校以外への支払い分は500万円が上限)。
利用時は信託銀行など金融機関で教育資金管理契約を結び、孫名義の専用口座に贈与額を一括入金します。孫は授業料や入学金はもちろん、塾代や留学費用など幅広い教育関連費用にそのお金を充てることができ、支払いの際に領収書等を提出すれば非課税で引き出せます。
孫が30歳に達した時点で契約は終了し、口座残高は贈与税の課税対象となります(※在学中の場合は最長40歳まで延長可)。また、契約期間中に祖父母が死亡した場合、その時点の残額について相続税の課税対象となることにも注意が必要です。当初期限付きの措置でしたが、令和5年度の税制改正で適用期間が2026年3月31日まで延長されています。
教育資金ニーズが高まる中、早めに孫の教育資金を確保しつつ相続税対策にも役立てられる仕組みとして注目されています。ただし、一度に大きな金額を移転できる分、使い切れずに残った資金に課税が生じるリスクもあるため、必要額を見極めて利用しましょう。
結婚・子育て資金の一括贈与|1,000万円まで非課税
孫の結婚や出産・育児を支援できる結婚・子育て資金贈与の特例もあります。祖父母から18歳以上50歳未満の孫に対し、結婚・子育て関連の資金を最大1,000万円まで非課税で贈与可能です。
利用時は金融機関で結婚・子育て資金管理契約を結んで専用口座を開設し、教育資金のケースと同様に領収書提出などの手続きを経て資金を引き出します。対象となる費用は結婚式や新居費用、出産費、子の医療費や保育料など多岐にわたり、用途が指定されたお金だけ非課税で使える仕組みです。
孫が50歳に達すると契約終了となり、口座残高に贈与税が課税されます。また期間中に祖父母が亡くなった場合も残額が相続税の対象です。結婚・子育て資金の非課税措置も期限付きで実施されており、現在は適用期限が2027年3月31日まで延長されています。
制度変更により延長されたとはいえ恒久的なものではないため、利用を検討している場合は期限に留意しつつ計画を立てると良いでしょう。
非課税制度を使うための条件・注意点とは?

上述した非課税制度を正しく活用するには、いくつか押さえておきたい条件や注意点があります。ただ単に孫にお金を渡しただけでは特例は受けられず、所定の手続きを踏む必要があります。ここでは代表的な注意事項を確認しましょう。
金融機関を経由した贈与でなければ対象外に
教育資金贈与や結婚・子育て資金贈与の特例を利用するには、金融機関を通じた贈与が必須条件です。具体的には、信託銀行や銀行等で専用の口座や信託契約を設定し、その口座に資金を入れる形で贈与する必要があります。
単に孫の銀行口座に振り込んだだけでは特例の対象にならないので注意してください。金融機関を経由することで、贈与資金の管理や使途の確認が制度上担保される仕組みになっています。
なお、専用口座を扱う金融機関は限られるため、事前に取扱いの有無や必要書類を確認しておくとよいでしょう。こうした手続きを怠ると非課税措置が受けられなくなるので注意が必要です。非課税枠を確実に適用するため、こうした金融機関での手続きを上手に活用しましょう。
使途の証明や領収書の提出が求められる場合も
特例制度で非課税にするためには、「贈与したお金が本当に規定の目的に使われたか」を証明する必要があります。教育資金贈与では教育費の領収書や請求書、結婚・子育て資金贈与では結婚式の費用明細や医療費の領収書などを金融機関に提出し、確認を受けることが求められます。もし用途外の支出に資金を流用すれば、その部分は非課税枠の対象外となり贈与税が課されてしまいます。
例えば教育資金の口座から教育と無関係な買い物に使えば、その金額は贈与税の課税対象です。このように制度を利用する以上、資金の使い道には厳格な制限がある点に注意しましょう。
また、各費用項目ごとに細かなルールもあります。たとえば結婚資金では招待客にかかる費用は対象外、教育資金では留学渡航費は対象だが旅行費用は不可、といった具合です。制度利用時にはガイドラインをよく読み、不明点は金融機関や専門家に確認することが大切です。
非課税制度の改正ポイント|2024年以降の変更に注意

生前贈与を取り巻く税制は近年見直しが進んでおり、2024年以降に適用される重要な改正点があります。制度を活用する際は、最新のルール変更を踏まえて計画を立てる必要があります。
「相続時精算課税制度」との併用ルール
2024年から、生前贈与の特例である相続時精算課税制度と、暦年贈与の基礎控除110万円との併用が可能となりました。
相続時精算課税とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ生前贈与を行う際、累計2,500万円までの贈与を非課税にし、それを超えた分に対しては一律20%の贈与税が課される制度です。贈与財産は将来の相続時にすべて相続財産として加算され、相続税の課税対象になります。
従来、この制度を選択すると毎年の110万円の基礎控除(暦年課税制度)は利用できませんでしたが、令和6年(2024年)から新たに「年間110万円の基礎控除」が設けられました。
この基礎控除には以下の3つのポイントがあります
-
110万円以下の贈与については申告不要であり、煩雑な手続きなしに非課税で贈与が可能になります。
-
この110万円は相続時に持ち戻しの対象とならず、相続税の課税対象にもなりません。
-
また、相続時精算課税の2,500万円の特別控除枠にもカウントされません。
これにより、相続時精算課税制度を選択した場合でも、毎年110万円までの非課税贈与を「別枠」で併用することが可能となり、より柔軟で計画的な資産移転ができるようになりました。たとえば、祖父母が孫へ教育資金などを支援しつつ、毎年110万円以下の範囲で贈与を行うと、申告不要かつ相続税の対象にもならず、長期的な非課税贈与が実現できます。
孫への生前贈与計画を立てる際には、相続時精算課税と暦年課税のハイブリッド型活用を検討してみるとよいでしょう。贈与者・受贈者の年齢要件や贈与財産の種類などを確認したうえで、最適な組み合わせを選ぶことが重要です。税理士など専門家への相談もあわせてご検討ください。
税制優遇が縮小・見直しされる可能性も?
相続税対策として有効な非課税贈与制度ですが、今後の制度変更や縮小の可能性にも注意が必要です。実際、生前贈与加算(いわゆる“持ち戻し”)期間が「3年」から最長「7年」へと延長されることがすでに決まっており、2024年以降、段階的に適用される点は見落とせません。
具体的な適用スケジュールは以下の通りです
-
2026年12月31日まで:これまで通り、死亡前3年以内の贈与が加算対象
-
2027年1月1日~2030年12月31日:2024年1月1日以降の贈与が加算対象(最長7年・最短4年)
-
2031年1月1日以降:死亡前7年以内の贈与がすべて加算対象
なお、死亡前4〜7年部分の暦年贈与については、加算総額から一律100万円が控除される経過措置も設けられています。これにより、一定の少額贈与については加算対象から実質的に除外される仕組みです。
また、各種特例制度も恒久化されていない点に注意が必要です。たとえば、「教育資金の一括贈与にかかる非課税措置は、2026年3月末まで」「結婚・子育て資金の一括贈与にかかる非課税措置は、2027年3月末まで」と、それぞれに適用期限が設定されています。過去には何度も延長されてきましたが、将来的に廃止される可能性も否定できません。実際、「もう延長はないのでは」との見方も一部にありましたが、直近の税制改正ではいずれも適用期限の延長が決定されました。
さらに、2023年度税制改正では、総資産5億円を超える富裕層を対象に、教育資金贈与の使い残しに相続税を課す新たな措置も導入されています。これは高額な贈与が課税回避に使われることを防ぐ狙いがあり、今後も同様の制限が拡大される可能性があります。
このように、非課税贈与制度や相続税のルールは年々見直しが進んでおり、制度優遇が徐々に縮小していく傾向にあります。相続対策や生前贈与の計画を立てる際は、常に最新の税制動向を確認し、制度改正に応じて柔軟に見直しを行うことが不可欠です。タイミングを誤ると、せっかくの節税効果が十分に得られない可能性もあるため、税理士など専門家と連携して対策を進めると安心です。
孫への贈与が相続税対策として注目される理由

高齢世代から孫世代へ資産を早めに移転することは、単に生前贈与で喜ばれるだけでなく、相続税対策としても大きなメリットがあります。ここでは、孫への贈与が注目される主な理由を2つ説明します。
世代をまたいだ資産移転で相続税の圧縮に
祖父母から子ではなく孫へ直接財産を渡すことは、「資産承継」の観点で相続税を圧縮する効果が期待できます。通常、祖父母の財産は子へ相続され、さらに子から孫へと二段階で受け継がれますが、それぞれの段階で相続税が課税されます。
生前に孫へ贈与しておけば、子の世代で一度財産が膨らむのを避けられるため、将来的な課税総額を抑えることができるのです。具体的な効果を示す例として、5,000万円の財産を持つ人が生前に孫へ500万円を贈与しておいた場合、相続時の課税対象額は5,000万円から4,500万円に減少し、その結果本来かかるはずだった相続税約20万円がゼロになったケースがあります。
もちろん各家庭の相続人構成や資産額によりますが、早めに資産を移転することで相続税の節税につながるのは確かです。また、祖父母から孫への贈与は、子から孫への二次相続を待たずに資産を若い世代に移せるため、資金を子育てや教育などに有効活用できる点でも意義があります。こうした理由から、「孫への贈与=相続税対策」という図式が近年注目されているのです。
「相続開始前3年以内ルール」からの除外も検討材料
生前贈与には、贈与者の死亡前一定期間内の贈与を相続財産に持ち戻して課税する「生前贈与加算」というルールがあります。通常は死亡前3年以内に行った贈与がこの対象で、相続税の計算に含められます。
この加算規定は「相続または遺贈により財産を取得しなかった者」への贈与については適用されません。つまり法定相続人ではない孫への贈与であれば、死亡直前に行ったものでも相続財産に含めずに済むのです。例えば祖父母が亡くなる直前に孫へ110万円を贈与していた場合でも、その110万円は相続財産に含まれません。孫が受け取った額が年間110万円以下であれば贈与税もかからないため、生前贈与加算の対象外となる孫への贈与は「孫への贈与は有利」と言われています。
例外として、祖父母が孫と養子縁組した場合や孫の親(祖父母の子)が先に亡くなって孫が代襲相続人となる場合など、孫が法定相続人に該当するときにはこの加算規定が適用されます。孫への生前贈与を検討する際は、自分の相続時に孫が相続人になる可能性も念頭に置いて計画を立てましょう。
贈与と併せて考えたい資産の「分散管理」
生前贈与で孫や子に資産を渡すことばかりに目を向けず、ご自身の手元に残す資産の管理・運用方法についても考えておく必要があります。せっかく節税して次世代に渡す資産も、自身の資産が目減りしては元も子もありません。リスク分散の観点から、資産の分散管理を検討しましょう。
子や孫への贈与以外に、資産そのものの“守り方”を考える
高齢世代にとって大切なのは、贈与した後に残る自分の資産をどう安全に管理するかです。贈与によってある程度資産を移転したとしても、まだ自分の生活資金や緊急予備資金としての資産が残ります。それらの資産を一箇所に集中させず、複数の金融商品や方法で管理することがリスクヘッジになります。
例えば預貯金だけに頼っているとインフレで実質価値が目減りしたり、万一預金先の金融機関が破綻した場合に元本保証は預金保険制度の範囲(1金融機関あたり元本1,000万円とその利息まで)に限られたりします。また、不動産など現物資産も市場変動や災害リスクがあります。
そこで、現金・預金、不動産、保険、証券投資など複数の資産クラスに適度に分散させ、“守り”を固めることが重要です。特に高齢の方の場合、「元本割れしにくい」「安定収入が見込める」商品を選ぶことで安心感が得られるでしょう。孫や子への贈与額と自分の老後資金とのバランスも踏まえ、家族に資産を残しつつ自分も困らない配分を考えることが肝心です。
「現金で持つ」だけが正解ではない
資産を安全に管理しようとすると、つい「タンス預金」や銀行預金で現金のまま持っておくのが一番確実と思いがちです。しかし、現金で保有するだけが必ずしもベストとは限りません。近年は物価上昇によりお金の実質価値が目減りするリスクも顕在化しており、預金金利よりインフレ率の方が高ければ資産の購買力は低下してしまいます。
せっかく節約や節税で築いた資産も、寝かせておくだけで目減りするのは避けたいところです。そのため、一部資産については値動きの小さい安全性の高い金融商品で運用し、わずかでもインカム(利息・配当)を得る工夫が有効です。元本保証の預貯金や個人向け国債はその典型ですが、超低金利が続く中でもう少し利回りを確保したいと考える方もいるでしょう。
そうした場合に検討されるのが、次に述べる「クラウドファンディング投資」のような比較的価格変動リスクの小さい商品です。
資産の一部は値動きの少ない投資で管理するという考え方も
資産運用というと株式や投資信託などを思い浮かべ、「リスクが高いのでは?」と敬遠する方もいるかもしれません。しかし、商品選びによっては価格変動が小さく、安定した利回りを期待できる投資も存在します。まとまった資金をただ現金で置いておくより、低リスクの商品で堅実に運用するのも一つの考え方です。
価格変動の少ない「融資型クラウドファンディング」とは?
近年注目されている融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)は、値動きの小さい投資手法として知られています。インターネット上のプラットフォームで多数の投資家から資金を集め、企業や事業に融資する仕組みで、投資家には融資先からの利息収入が定期的に分配されます。
株式のように市場価格が日々変動しないのが特徴で、あらかじめ決まった利率に基づいてリターンを得られるため難しい相場分析も必要ありません。比較的低リスクで運用できる反面、元本保証ではないため融資先が返済不能に陥ると元本割れ(貸し倒れ)が発生するリスクはあります。このように価格変動リスクが小さい点は大きな魅力ですが、リスクがゼロではないことを踏まえ、無理のない範囲で活用することが肝要です。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
将来に向けて準備したいこと|贈与と資産運用のバランス
孫への生前贈与と自身の資産運用、この両面をバランスよく考えることが将来の安心につながります。最後に、今から準備しておきたいポイントを整理します。
「贈って終わり」ではなく、家族全体の資産設計が重要
生前贈与は「お金を贈って終わり」ではありません。むしろ贈与した後からが本番です。贈与によって減った自分の資産で今後の生活に支障がないか、逆に贈与を受けた孫や子がその資金を有効に活用できるか、といった家族全体の資産設計を考えておく必要があります。
例えば、まとまった資金を孫に渡す場合、そのお金の管理や使い道について信頼できる親(受贈者の親である自分の子)とも情報共有し、必要なら教育費や住宅資金など具体的な目的のために計画的に使ってもらうよう話し合っておくと安心です。せっかく相続税を節約しても、贈られたお金が無計画に浪費されては本末転倒です。
場合によっては、贈与と合わせて信託や遺言など他の承継手段も組み合わせ、長期的視野で資産が有効活用・保全される仕組みを整えておくと良いでしょう。家族全体でお金の話をするのは気が引けるかもしれませんが、将来のためにオープンに話し合うことが大切です。
FPや税理士との相談も検討しよう
生前贈与や相続対策、資産運用については専門家のアドバイスを得ることも強くおすすめします。ファイナンシャルプランナー(FP)や税理士は、家計診断や税務に精通したプロフェッショナルです。孫への生前贈与を計画する際も、「どの制度を使うのが最適か」「贈与する額とタイミングはどうすべきか」「自分の老後資金は十分か」といった点で専門家の視点から適切なアドバイスをもらえます。
特に税理士は最新の税制や手続きに詳しく、贈与税の申告方法や非課税枠利用時の留意点など実務面でも頼りになります。複雑な制度変更にも迅速に対応できるため、「うっかり制度が変わっていて余計な税金を払った」という事態も防げるでしょう。
相談料はかかりますが、将来得られる節税メリットや安心を考えれば有益な投資と言えます。無料相談会を実施する自治体や金融機関もありますので、積極的に活用してみてください。プロの知見を取り入れつつ、家族とも十分話し合い、贈与と資産運用のバランスが取れた最適なプランを立てていきましょう。
よくある質問(FAQ)|孫への生前贈与Q&A

最後に、孫への生前贈与に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. 孫に贈与したお金の使い道は限定される?
特別な非課税制度を使う場合は使い道が限定されますが、一般的な贈与では基本的に限定されません。
例えば、教育資金贈与や結婚・子育て資金贈与の特例を利用した場合、渡したお金は教育費や結婚・子育て費用にしか使えません。領収書の提出など用途管理が義務付けられ、目的外に使えば課税されます。一方、暦年贈与の110万円枠内で渡したお金や特例を使わない通常の贈与であれば、受け取った孫がそのお金を何に使うかは自由です。
贈与者が用途を指定することも可能ですが、それはあくまで家族間の約束であり、税制上は口座に振り込んだ時点で孫の財産となります。従って、一般贈与では「孫への贈与金の使途」は法律上限定されないことになります。
Q2. 教育資金贈与は何歳まで有効?
教育資金非課税の特例は、基本的に孫(受贈者)が30歳になるまで有効です。
贈与を受けた孫が30歳に達すると契約が終了し、その時点で口座に残っている資金に贈与税がかかります。つまり30歳の誕生日を迎えた時点で残高があれば課税対象となるため、それまでに資金を使い切る必要があります。
ただし、孫が30歳時点で在学中の場合は例外で、在学期間中(最長40歳まで)は口座を継続利用できる猶予措置があります(医療系など長期課程に在学しているケースなど)。なお、この特例制度自体の適用期限にも注意が必要で、現状では2026年3月31日までに開設した契約が対象となっています。なお、在学中であっても40歳に達した時点で契約は終了となり、残高は贈与税の課税対象となる点に注意してください。
Q3. 住宅取得資金は孫にも非課税で渡せる?
はい、一定の条件を満たせば祖父母から孫への住宅取得資金贈与も非課税にできます。
直系尊属(親や祖父母)から住宅購入等の資金を贈与された場合の非課税特例があり、孫も対象に含まれます。非課税となる金額は住宅の種類によって異なりますが、例えば省エネ等住宅の場合1,000万円まで、それ以外の住宅なら500万円までが非課税枠です。
この制度を利用するには、孫の年齢や所得(贈与を受ける前年の合計所得2,000万円以下など)、住宅の床面積や性能要件、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の使用を完了すること等、細かな条件があります。適用期間も法律で定められており、現時点では2026年12月31日までに行われる贈与が対象です。
以上の条件を満たせば、孫に対しても住宅取得資金を非課税で渡すことが可能です。ただし、制度の詳細は変更になる場合もあるため、利用検討時には国税庁の最新資料や税理士に確認すると安心でしょう。
まとめ|制度を正しく使えば、孫への贈与も「節税+資産承継」に
「孫への生前贈与で税金ゼロにできる?」という問いに対する答えは、各種制度を正しく活用すればYESです。暦年贈与の110万円枠や教育資金・結婚子育て資金の特例を駆使することで、大切な資産を非課税で孫に渡し、将来の相続税対策にもつなげることができます。
ただし、制度には適用期限や条件があり、税制改正で変更も起こり得ます。最新の情報にアンテナを張りつつ、今回解説したポイントや注意点を踏まえて計画を立てることが重要です。
また、単に税金をゼロにすることだけが目的化しないよう、贈与後の資産の使われ方や自分の生活設計まで含めた総合的な視野で取り組みましょう。正しく制度を使いこなせば、孫への生前贈与は「節税」と「円滑な資産承継」を両立させる有効な手段となります。家族の笑顔と将来の安心のために、できる準備を少しずつ進めてみてはいかがでしょうか。
参考元
・国税庁:「繰上返済等をした場合の償還期間」
・全国銀行協会 :【住宅ローン減税と繰上返済、どちらを優先させた方がいいですか?】
・住宅金融支援機構:「住宅ローン利用者実態調査(2024年)」