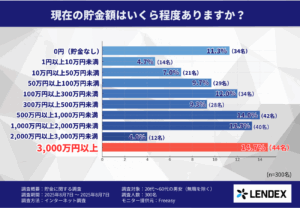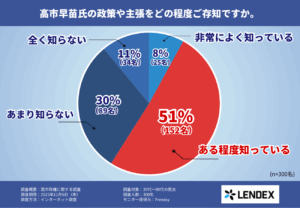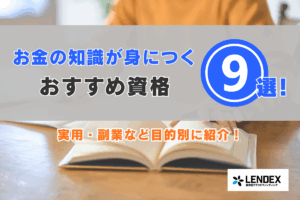「子育てにはいくらかかるのか不安…」「教育費ってどのくらい準備すればいいの?」そう感じている方は多いのではないでしょうか。
実際に、子ども1人を大学卒業まで育てるには2,000万円以上かかるともいわれており、進学先や家庭の教育方針によっては4,000万円超にのぼるケースもあります。人生の中でも最大級の支出となる「子育て費用」は、早めの把握と計画的な準備が欠かせません。
本記事では、子育て費用のシミュレーションをテーマに、年齢別・進路別にどれくらいのお金がかかるのかを具体的に解説。さらに、見落としがちな支出や、公的支援制度の活用法、効率的な教育資金の準備方法まで、投資視点を交えて詳しく紹介します。「今のうちに備えておきたい」「将来の教育費が心配」という方は、ぜひ最後までご覧ください。
子育てにはいくらかかる?全体の目安とシミュレーションの前提

子育て費用は、大きく教育費(学校・塾など)と養育費(生活全般)に分けられ、その合計額が家計の大きな負担となります。まず、一人の子どもが成人するまでに必要となる総額と、本記事で用いるシミュレーション条件を押さえましょう。
0歳〜22歳までにかかる総額とは?
ある調査によれば、子ども1人を22歳(大学卒業相当)まで育てる費用総額は約2,400万~3,800万円程度とされています。幼稚園から大学まですべて公立の場合で約2,400万円前後、すべて私立(大学は理系)を選んだ場合には約3,800万円以上に達する計算です。
特に大学の進学先によって大きな費用差が生まれます。最新のデータによると、大学4年間にかかる学費(入学金含む)は、国公立大学で約243万円、私立大学文系で約443万円、私立大学理系では約573万円にのぼります。これに通学費や教材費、生活費などを加えると、さらに費用は膨らみます。
なお、こうした「子育て費用」の総額には、教育費(学費や習い事代)に加えて、養育費(食費や衣服代、住居費など)も含まれています。内訳としては、22年間の養育費だけでも平均約1,640万円とされており、それに加えて進路に応じた教育費がかかるという構造です。
私立・公立・地域差も踏まえたモデルケース
子育て費用は進路によって大きく異なります。全て公立ルートでは教育費約1,080万円+養育費1,640万円で総額約2,720万円ですが、全て私立(大学理系)の場合は教育費約2,693万円+養育費1,640万円で約4,333万円と、約1.6倍もの差となります。
また地域差もあり、都市部は私立進学率や塾利用率が高いため平均費用が割高になる傾向があります。各家庭の教育方針・居住地によって必要金額は大きく変わる点に注意しましょう。
年齢別・子育て費用シミュレーション|0歳〜高校卒業まで

子どもの成長段階ごとに、かかるお金の内訳や負担も変化します。年齢が上がるにつれて費用負担は増大し、中学生では未就学児期の約1.5倍に達することがデータからもわかっています。以下では年齢別(0歳~高校)の費用シミュレーションを見ていきましょう。
0〜2歳|保育料・おむつ代・ベビー用品など
乳児期(0~2歳)は、年間約90~95万円程度の費用がかかります。ミルクやおむつ、ベビー用品などの消耗品に毎月数万円が必要です。特に両親共働きの場合は保育料の負担が大きく、未就学児では年間約38万円(子育て費用の3割)を保育園に支出したという統計があります。
ただし2019年10月に幼児教育・保育の無償化制度が始まり、住民税非課税世帯なら0歳から、それ以外の世帯も3歳から保育所・幼稚園利用料が無料になりました。とはいえ給食代や行事費は自己負担のため、0~2歳でも毎月一定の出費は避けられません。
3〜6歳|幼稚園・保育園+習いごと費用
幼児(3~6歳)になると、年間支出は平均100万円超に増えます。幼稚園・保育園の利用料自体は無償化で基本無料ですが、制服代や園のイベント費、送迎バス代などの実費負担があります。
また、この頃からピアノや水泳など習い事を始める家庭も多く、その月謝も加わります。公立幼稚園と私立幼稚園では支出総額に大きな差があり、私立園のほうが倍近い費用がかかる傾向です。地域や園によって費用項目が様々なので、入園前に情報収集しておくと安心でしょう。
小学生|学用品・塾・学校関連費用
小学校6年間では、公立の場合で年間110~130万円前後の子育て費用がかかります。小学校は授業料が無料でも、給食費や学用品費、遠足代など学校生活に毎年数万円が必要です。
また、多くの子どもが放課後に学習塾や習い事に通い始め、特に高学年では中学受験に向けた進学塾代が家計を圧迫しがちです。私立小学校に通う場合、学費(授業料・施設費等)だけで年間100万円以上かかるため、別途かなりの教育費を見込む必要があります。学年が上がるにつれ出費も増えるため、計画的に貯蓄・運用しながら備えていきましょう。
中学生〜高校生|部活・スマホ・制服・受験費
思春期の中学・高校では、更に費用負担が増します。中学生の場合、年間支出は平均150万円超と未就学児期の約1.5倍に跳ね上がります。塾代に加え、部活動も本格化し、部活のユニフォーム・用具代、合宿や遠征の交通費などがかかります。
また、中学進学頃から子どもにスマートフォンを持たせる家庭も多く、中高生のスマホ所持率は、中学生で約65-87%、高校生で90%以上に達します。スマホの通信費(月数千円)やネット関連費用も地味な負担です。
さらに、高校受験・大学受験に向けた模試代・受験料も必要で、大学受験では受験校数校分で合計30万円前後の出費になるケースもあります。高校入学時には制服・教材購入等で数十万円単位の初期費用も発生するため、事前に準備しておきましょう。
大学進学で一気に増える費用|学費+仕送りの実態

高校までの教育費と比べ、大学進学時には一気に多額の費用が必要になります。大学の種類や進学先による費用差と、仕送りなど家計負担の実態を確認しましょう。
国公立・私立・理系文系でこんなに違う!
大学の学費は、在学する大学の種類(国公立か私立)や学部系統によって大きく異なります。例えば4年間の学費(授業料+入学金)は、国公立大学で約537万円、私立大学文系で約703万円、私立大学理系では約863万円ほどかかります。
私立理系は実験設備などの費用がかさむため文系より学費が高く、大学によっては年間100万円を超える授業料も珍しくありません(医歯系はさらに別格の高額です)。国公立は授業料が標準額(年約54万円)で横ばいですが、それでも30年前と比べると大学平均の学費は約1.5倍にも値上がりしています。こうした学費上昇も踏まえて、大学進学資金は早めに準備しておく必要があります。
一人暮らしなら年間100万円以上も想定必要
自宅外の大学に進学する場合、仕送りや生活費の負担が追加で発生します。文科省等の調査では、地方から都市部の大学に進学する学生への仕送り額は平均年間約90.3万円(月額7.5万円)にのぼります。家賃や光熱費、食費を含めれば年間100万円を超える生活費が必要となるケースも多いでしょう。
一方、自宅通学の場合はこれら生活費の家計負担を大幅に抑えられます。自宅外進学を予定しているご家庭は、在学中4年間で少なくとも400万円前後の生活費を見込んで教育資金計画を立てることをおすすめします。なお、仕送り負担を軽減するために、学生本人がアルバイト収入で一定額を賄うケースや、奨学金で生活費を補填するケースもあります。
子育て費用でよくある見落としポイント
学費や習い事代など目につきやすい費用以外にも、子育て期には支出の増える項目が多々あります。見落としがちなポイントを確認しましょう。
保険・医療・交通・食費の増加を忘れがち
子育て費用の試算では学費などに目が行きがちですが、実際には保険料・医療費・交通費・食費なども年々増加します。
未就学児期は「子どものための預貯金・保険」費用の割合が大きいですが、子どもの成長に伴いその割合は減り、代わりに食費やレジャー費が増えていく傾向があります。例えば食費は、子どもの成長とともに自宅の食料費や外食費がかさみ、スポーツをしている子では遠征先での外食が月1~2万円増えた例もあります。
行動範囲が広がれば交通費の負担も増し、中高生になるとスマホの通信費(月数千円)も家計に加わります。こうした日常的な支出増を軽視せず、家計予算に織り込んでおきましょう。
中学以降の“想定外出費”に備えられている?
中学・高校生以降になると、想定外の出費も発生しがちです。例えば部活動では入部時に予想以上の費用がかかることがあります。強豪校の運動部では、ジャージや合宿費などで入部時に一括40万円前後を納入するケースもありました。また、子どもが部活を途中で変更し、その都度道具を買い揃えた結果、トータルで十数万円の出費になった例もあります。
この他にも、高校でタブレット端末の購入が必要になる、大学受験直前に志望変更で急遽塾の特別講座を追加受講する、といった予測しづらい出費も起こり得ます。こうした事態にも対応できるよう、教育資金とは別に予備費を確保しておくことが望ましいでしょう。
子育て費用の補助制度|活用したい支援まとめ

公的な支援制度を最大限活用することで、家計の負担を減らすことができます。国が用意する主な子育て支援策と、自治体独自のサポートを押さえておきましょう。
児童手当・高校無償化・大学の奨学金制度
まず、児童手当は0歳から中学卒業まで一人当たり月1万~1万5,000円が支給される制度で、第3子以降は増額されます(所得制限あり※)。中学卒業まで受給すれば総額約200万円になり、高校入学や大学進学の費用に充てられる貴重な財源です。
次に高等学校等就学支援金(いわゆる高校授業料無償化)では、年収目安910万円未満の世帯に公立高校の授業料年11万8,800円を支給、私立高校に通う場合も年収590万円未満なら年間最大39万6,000円を補助してくれます。
さらに、大学などの高等教育修学支援制度では、住民税非課税世帯などの学生を対象に、大学授業料の減免と給付型奨学金の支給が実施されています(減免額や給付額は学校種別や自宅・自宅外かで異なる)。
この他、希望者は日本学生支援機構(JASSO)の無利子・有利子の奨学金を借りることもでき、大学生の約半数が奨学金を利用しています。
● 2024年10月から児童手当制度が大幅に拡充されました。
主な変更点
- 所得制限の完全撤廃:全ての家庭に支給
- 支給対象年齢の延長:中学卒業まで → 高校卒業まで(18歳年度末まで)
- 第3子以降の支給額大幅増:月額1万円 → 月額3万円
- 多子加算の延長:第1子が22歳年度末まで第3子以降の加算継続
● 2025年4月から、3人以上の子どもを扶養する多子世帯を対象とした大学等の授業料無償化制度が開始されました
制度の概要
- 対象:子ども3人以上の多子世帯(所得制限なし)
- 支援内容:
- 国公立大学:授業料・入学金全額免除
- 私立大学:年間最大96万円の支援(授業料上限70万円+入学金26万円)
- 対象機関:大学・短期大学・高等専門学校・専門学校
自治体による独自サポートも要チェック
国の制度以外にも、各自治体が独自の子育て支援策を設けています。例えば、多子世帯向けに第3子以降の保育料を無料化したり、児童手当を上乗せ支給する自治体があります。
また、高校授業料のさらなる補助(独自の支援金上乗せや所得制限緩和)、子どもの医療費助成の対象年齢拡大(高校生まで医療費無料など)、保育所や幼稚園の給食費補助、私立高校・私立大学進学者への奨学金・貸付制度など、多岐にわたります。
ぜひお住まいの自治体の制度も調べて、利用できるものは積極的に活用しましょう。
教育資金はいつ・どう準備する?時期別のおすすめ方法

お子さんの成長に合わせて、教育資金の準備方法も変えていくと効率的です。年代別に適した貯蓄・運用の方法を紹介します。
0〜6歳:児童手当や保険活用で積立開始
幼児期はまだ教育費が本格的にかかる前ですが、早いうちから積立を始めることが肝心です。児童手当はなるべく手を付けず全額貯蓄すれば、中学卒業までに約200万円を貯められます。
また、学資保険(教育保険)への加入も検討しましょう。低金利でリターンは小さいものの、契約者である親に万一のことがあっても満期金が受け取れるため、保障と貯蓄を兼ねた手段として有効です。そのほか給与天引きの財形貯蓄や銀行の自動積立定期預金などを活用し、確実に教育資金を積み立てていきましょう。
小学校以降:学資保険・ジュニアNISAなども検討を
小学生以降は進学先や教育方針が少しずつ見えてくる時期です。引き続き計画的な貯蓄を続けつつ、資産運用も選択肢に入ります。大学入学まで10年以上あるうちに、つみたてNISAなど長期の積立投資にチャレンジしておけば、効率的に資金を作れるでしょう。
実際、教育費の準備はインフレリスクを考慮し、預貯金や学資保険だけでなく投資を組み合わせるべきとの指摘もあります。ただし価格変動リスクもあるため、学資保険や預金と併用してリスク分散することが大切です。中学進学以降は児童手当の支給が終わるため、その分を自動積立の増額や投資の拡充でカバーするなど、ライフステージに応じて準備方法を見直しましょう。
子育てしながら「家計の防衛力」も高めるには?
教育費を準備するために家計のリソースを集中しすぎると、将来的な生活基盤が脆弱になる恐れもあります。子育てと並行して家計全体の防衛力(財政健全性)を高めるポイントを押さえましょう。
「貯金だけ」では教育費の伸びに対応できない
長期的には、預貯金だけの貯蓄では子どもの教育費の伸び(インフレ)に追いつけない可能性があります。
実際、大学の学費は値上がりし続けている費目の一つで、大学志願者数がピークだった1992年度と2021年度を比較すると年間授業料は約1.5倍に上昇しています。国立大学の授業料は過去40年間で約15倍にもなり、物価上昇率を上回るペースで高騰しました。
一方、日本の金利は長年低水準にとどまり、預金をいくら積み立ててもお金は増えません。したがって、将来のインフレや学費上昇に備えるには、預貯金や学資保険だけでなく資産運用を組み合わせて資金を用意する工夫が重要となります。
物価上昇や将来の不確実性に備える考え方
子育て期間中は、予期せぬ物価高騰や収入減などのリスクにも備えておく必要があります。教育資金とは別に緊急予備資金を確保し、家計の防衛力を高めておきましょう。
また、親の死亡・病気に備えた生命保険・就業不能保険などにも加入し、万が一の場合でも子どもの教育資金を捻出できる体制を整えておくことが大切です。
さらに、教育費の準備ばかりに気を取られて老後資金の蓄えが不足することがないよう、複数のライフイベントを見据えた資金計画を立てましょう。教育資金と老後資金は両立可能です。例えば学費のピークが過ぎたら、その分を老後資金の積立に振り向けるなど、家計内でメリハリをつけて資産形成を続けることが重要です。
シミュレーション結果に差が出る3つの要因とは?

冒頭で紹介した子育て費用の試算値は、あくまで一例(モデルケース)です。実際の費用は各家庭の状況によって大きく異なります。特に次の3つの要因によってシミュレーション結果に差が生じます。
教育方針・地域性・世帯収入の違い
まず、親の教育方針によって費用は大きく変わります。私立校や海外留学を積極的に選べば費用は高額になり、全て公立・塾なしでと考えれば低めに抑えられるでしょう。
次に地域性の違いも見逃せません。都市部では中学から私立に進学する割合が高く塾代も高額になる傾向があり、地方と比べ教育費が嵩みがちです。これら3つの要因により、教育費のシミュレーション結果は家庭ごとに大きく異なります。
「平均」をそのまま信じず、自分の家庭に落とし込もう
子育て費用の平均データは目安として有用ですが、「平均だから自分もこれくらい」と鵜呑みにするのは危険です。大切なのは平均値を参考にしつつ、自分の家庭ではどうかを具体的に計算し直してみることです。お子さんの人数・年齢構成、希望する進路、世帯収入や住宅ローン等の状況によって、貯蓄すべき金額やペースは異なります。
例えば子どもが2人いれば単純計算で教育費総額は倍近く必要ですし、年の近い兄弟なら大学進学時期が重なり一時的な負担が倍増します。逆に進路次第では平均より安く済む可能性もあります。
平均データに振り回されず、自分の家庭用のライフプラン表を作成して必要資金を試算することが、計画的な資金準備の第一歩です。
分散投資で教育資金+老後資金をバランスよく準備
子育て世帯に共通する悩みが、教育資金を優先するあまり老後資金が不足してしまう懸念です。ここでは、教育資金と老後資金をバランスよく準備するための考え方を解説します。
NISA・iDeCoに加えて選ばれる“守りの投資”とは?
教育資金と老後資金、両方を計画的に貯めていくには、長期投資と短期~中期の低リスク運用を使い分けることがポイントです。
まず、将来に備えた資産形成には、非課税制度を活用したNISAやiDeCoが強力な手段となります。NISAは必要時に引き出しが可能なため教育費にも流用しやすく、iDeCoは老後資金を効率良く準備できます。
一方、株式投資のような値動きの大きい商品ばかりでは、いざという時に元本割れのリスクがあります。そこで近年注目されているのが、価格変動リスクを抑えつつ定期的な利息収入を得られる“守りの投資”です。具体的には、債券や預金、貸付型(融資型)クラウドファンディング等がこれに該当し、安定した利回りを狙える商品として利用されています。
価格変動リスクを抑えた資産運用の選択肢
例えば貸付型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)は、個人がネット経由で企業などにお金を貸し付けて利息を受け取る仕組みです。投資家は借り手から毎月利息を受け取り、期間終了時に元本が返済されます(貸し倒れが起きない限り)。
一般的な案件期間は数ヶ月~1年程度と短期で、大学入学までの数年といった中期の運用に適しています。また、ほとんどの案件で利息は毎月分配されるため、運用しながら継続的に資金を積み増しできます。株式などと違い価格が日々変動しないため、市場暴落に一喜一憂する必要もありません。
実際、「忙しくて相場を見る時間がない人でも投資しやすい」との声もあります。一方で元本保証はなく、借り手の返済不能リスクや運営事業者の倒産リスクもゼロではありません。したがって、高利回りに偏らず複数案件に小口分散投資する、信頼性の高い業者を選ぶ、といったリスク管理が重要です。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
よくある質問(FAQ)|子育て費用に関する不安と疑問
Q1. 学資保険とNISA、どちらがよい?
学資保険(教育保険)とNISAにはそれぞれメリット・デメリットがあります。
学資保険は元本確保を重視し、満期学資金が確定しているためリスクを抑えたい方に向いています。一方、NISA(積立NISA)は市場運用でリスクはありますが、長期的に資産を増やしたい方、ある程度リターンを狙いたい方に向いています。
学資保険は契約者(親)の死亡時に保険料免除となり学資金が保証される利点がある反面、低金利下では返戻率が低く「貯蓄性」は高くありません。一方NISAは元本保証がない代わりに運用益非課税で高リターンも期待できます。
結論として、併用も検討すべきでしょう。例えば毎月の児童手当分を学資保険で積み立てつつ、それ以外の余裕資金はNISAで投資運用するといった組み合わせによって、保証と運用のバランスを取る方法が考えられます。
Q2. 兄弟が多い場合はどう見積もればいい?
お子さんが複数いる場合、一人当たりの平均×人数分を目安にしつつ、重なり期間に注意して見積もりましょう。基本的には子どもが増えるほど教育費総額も倍増します(2人で約2倍、3人で約3倍…)が、年の近い兄弟では大学進学の時期が重なるといったピークの重複によって一時的負担が非常に大きくなります。
また、家計の収支も兄弟の人数で変わる点に留意が必要です。例えば子どもが3人以上いる世帯では2025年度から大学授業料が所得制限なく無償化される方針が発表されており、今後負担が軽減される可能性もあります。このように、公的支援策も活用しつつ、兄弟が多い家庭ほど早め早めの資金計画と余裕ある貯蓄が求められます。
Q3. 途中で教育方針が変わったらどうする?
当初の想定より教育費が増える進路に変更になった場合、早急に資金計画を見直しましょう。具体的には、必要額を再試算した上で、月々の積立額を増やす・ボーナスを充当するなど、残り期間で捻出できる対策を講じます。
それでも不足する場合、奨学金(大学)や教育ローン(民間・日本政策金融公庫)など外部資金の活用も選択肢に入ります。
まとめ|子育て費用は“計画的準備”と“分散”が安心のカギ

以上、子育て費用のシミュレーション結果と備え方について見てきました。教育費は家庭にとって非常に大きな負担ですが、早めに計画を立てて準備を始めること、そして貯蓄・保険・投資を分散活用することで、無理なく必要資金を確保できる可能性が高まります。
ぜひ本記事のデータや制度情報を参考に、ご家庭独自のライフプランを作成してみてください。計画的な準備と分散投資こそが、将来への安心につながるカギと言えるでしょう。
参考元:
- 内閣府:「平成21年度インターネットによる子育て費用に関する調査 概要(PDF)(2009年度調査、公表2010年) 」
- 文部科学省:「令和3年度子供の学習費調査(結果の概要)(2021年度調査、公表2022年) 」
- 日本学生支援機構:「令和2年度学生生活調査・高等専門学校生生活調査・専修学校生生活調査(2020年度調査)」