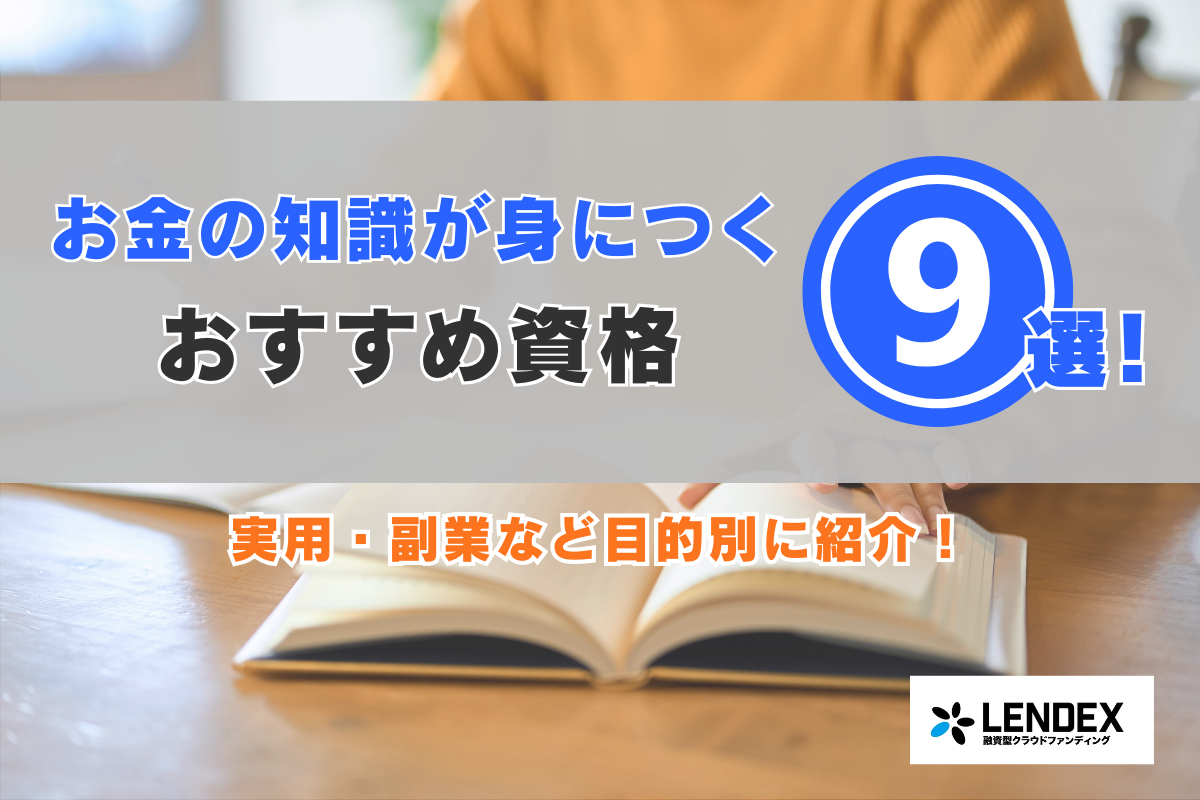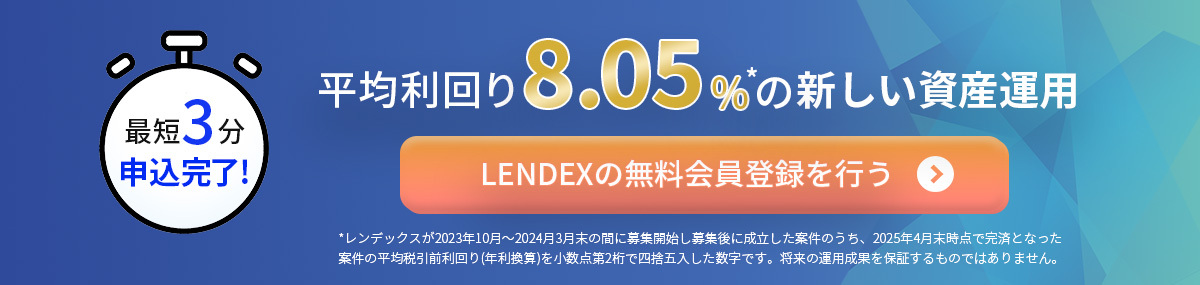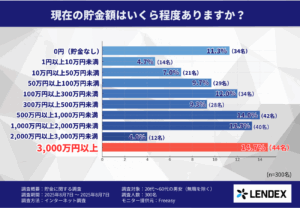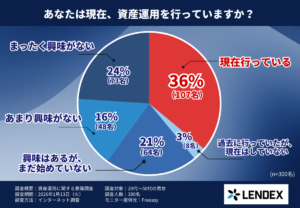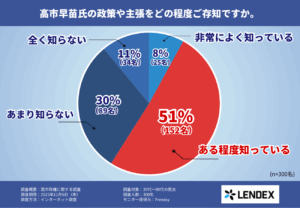「お金の知識」は一生モノの武器。将来への不安が高まる今、資産形成や節約、副業などに役立つ“お金に強くなる資格”が注目されています。中でも、「お金 資格 副業」といったキーワードで検索する人が増えているように、金融リテラシーを高めたいというニーズは年々高まっています。
本記事では、お金の知識を体系的に学べるおすすめ資格9選を目的別に紹介。実生活で使える実用資格から、副業・転職に強い専門資格、投資に役立つ金融系資格まで、幅広く解説します。「貯める・増やす・守る」力を鍛え、自分の資産を守るために、今こそ“学び直し”を始めてみませんか?
お金の知識があると何が変わる?今なぜ注目されているのか

人生100年時代に求められる「自衛力」
平均寿命が延び「人生100年時代」が現実味を帯びる中、自分自身の生活を守るための“経済的自衛力”が一段と重要になっています。公的年金や会社に頼るだけでなく、長い老後に備えて自分で資産を形成し、管理する力が求められています。
実際、金融広報中央委員会の武井会長は「人生100年時代」を前に、「稼いだお金を『貯める』『増やす』『守る』(そして『長持ちさせる』)努力がこれまで以上に重要になる」と述べ、様々なお金の知恵を身に付け磨く必要性を強調しています。金融知識(金融リテラシー)を高めることで、詐欺に遭わない判断力や資産形成への意識も身に付き、長寿時代を安心して過ごす土台となります。
「貯める・増やす・守る」力を鍛える第一歩
お金に強くなる第一歩は、自分のお金を「貯める・増やす・守る」基本スキルを鍛えることです。例えば家計管理を徹底し無駄遣いを減らす「貯める力」、貯蓄だけでは増えない資産を投資で「増やす力」、そして資産を減らさないようリスクを管理する「守る力」を身につけることが大切です。
金融庁の報告書でも、人生100年時代では働くだけでなくお金にも長く働いてもらう必要があると指摘され、これら『貯める・増やす・守る』努力と知識習得の重要性が強調されています。こうした基礎力を鍛えることで、自分の資産を自衛しながら着実に増やす土台が築かれるのです。
お金に強くなる資格を選ぶ前に|目的別の選び方のコツ

実生活で役立てたい?副業につなげたい?
資格を選ぶ際は「その知識をどう活かしたいか」という目的を明確にすることが大切です。
例えば、日々の家計管理や資産運用に役立てたいのであれば、ファイナンシャル・プランナー(FP)や金融リテラシー検定など実生活向きの資格が適しています。FPや簿記などは家計や税金の基礎知識を体系的に学べるため、取得後すぐに家計改善や資産形成に応用できます。
一方、「資格を副業につなげて収入アップしたい」「キャリアアップに役立てたい」という場合は、宅建や証券外務員、税理士など業務に直結する資格が候補になります。これらは取得難易度は上がりますが、専門性が評価され副業・転職で収入増につながる可能性が高い資格です。
資格の種類と難易度・コスパを比較して検討
資格ごとに国家資格か民間資格か、難易度や学習コスト(時間・費用)も様々です。
例えばFPや簿記3級は比較的易しく、独学でも合格率70%前後と高いため初心者に向いています。一方、税理士や中小企業診断士のような国家資格は合格まで数年単位の学習を要し、難易度も非常に高くなります(例:診断士は一次・二次試験合格率合計で約3~8%)。
「コストパフォーマンス」の観点では、短期間で基礎知識を得られる資格から始め、必要に応じて難関資格にステップアップする方法も有効です。また資格取得には受験料や講座費用もかかるため、投資額に見合うリターン(得られる知識や収入増)を見極めて選ぶことが大切です。
【実用性重視】お金の基礎が身につくおすすめ資格3選

① ファイナンシャル・プランナー(FP)
ファイナンシャル・プランナー(FP)は、税金・保険・年金・資産運用など暮らしに関わるお金の幅広い知識を学べる国家資格です。
3級は高校生でも受験可能な入門編で、合格率は約70%と高く初心者に最適です。2級になると実践的な内容が増え合格率は25~30%程度まで下がりますが、FP資格を持つことで人生の三大資金(教育・住宅・老後)に備える知識が体系的に身に付きます。
また金融庁も「語学やPCスキルを学ぶ、資格を取得するなど自己投資を行い、稼ぐ力を高めることも大切」と提言しています。FP資格はまさに自己投資としてお金の基礎教養を高め、将来の資産形成に備えるうえで有用な資格と言えるでしょう。
② 簿記(2級〜3級)
簿記検定(日商簿記)は、企業の財務諸表を読み書きするスキルを証明する資格で、個人の家計管理から企業経営まで幅広く役立ちます。
3級は商業簿記の基本を学び、合格率は30〜50%程度と比較的取りやすいため初心者にもおすすめです。2級では工業簿記や決算書作成まで扱い難易度が上がりますが、合格率は平均20%前後と挑みがいがあります。
簿記2級を取得すれば副業で記帳代行や確定申告の手伝いなど収入につながるチャンスも生まれます。企業の経理・財務に転職したい人にも評価される資格であり、投資家にとっても企業分析力が向上するメリットがあります。受験料は数千円程度で独学教材も豊富なため、コスパ良くお金の基礎知識を身につけられる資格です。
③ 金融リテラシー検定・生活設計アドバイザー
金融リテラシー検定はその名の通り、お金に関する実用的な知識を総合的に問う民間資格です。
高校の金融教育拡充に伴い新設された検定で、生活に活かせる金融知識の習得を目的としており、一般社団法人金融財政事情研究会(きんざい)が運営しています。内容は家計管理、金融商品の基礎、資産運用やトラブル対策まで幅広く、学生から社会人まで誰でも受験可能です。合格することで自分のお金の知識レベルを客観的に把握でき、家計改善にもすぐ役立つでしょう。
一方、生活設計アドバイザーはライフプラン(人生の収支計画)の立て方や相談スキルを養う資格です。人生の三大支出である教育・住宅・老後資金について無理のない計画を立てる知識が学べ、FPの実務的な応用編として位置付けられます。
いずれも難易度は高くなく、実生活のマネーリテラシー向上に直結する資格として注目できます。
【副業・キャリアアップ向け】収入アップにもつながる資格3選

④ 証券外務員
証券外務員は、銀行や証券会社で金融商品を販売するために必須となる国家資格(登録制度)です。証券会社勤務でなくても一般受験が可能で、金融業界を目指す人や独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)志望者にも有用です。
二種と一種があり、二種外務員は株や投資信託の販売が、一種外務員ではデリバティブ取引等も含め幅広い商品を扱えます。試験は選択式で比較的取り組みやすく、合格率はおおむね65〜70%程度と高水準です。副業として証券仲介業に携わるにはこの資格が必須であり、IFAになるには証券外務員資格取得が前提条件となっています。
金融商品の専門知識を習得できるため、自身の資産運用にも役立ち、金融業界へのキャリアアップを狙う方にもまず取得が推奨される資格です。
⑤ 宅地建物取引士(宅建)
宅地建物取引士(宅建士)は、不動産取引の専門知識を持つ国家資格者です。不動産業界だけでなく、個人投資家が不動産を扱う際にも契約や法規の知識が不可欠なため非常に人気の資格となっています。
試験の難易度は中程度ですが、毎年20万人以上が受験し合格率は例年15~17%前後と狭き門です(2024年度は合格率18.6%とやや上振れ)。学習範囲は民法、不動産関連法規、税金など多岐にわたり、合格には約300~400時間の勉強が目安とも言われます。
しかし取得すれば不動産売買や賃貸の仲介業務に従事でき、副業で不動産オーナーや不動産取引のコンサルを行う際にも信用力が増します。自身の物件購入時にも知識が大いに活きるため、“攻めと守り”両面で資産形成に貢献してくれる資格です。
⑥ 日商簿記1級・税理士・中小企業診断士
上級資格として位置付けられるこれら3つは、取得できれば高い専門性による収入増やキャリアアップが期待できます。
まず日商簿記1級は会計分野の最高峰の検定で、合格率は約10%前後と難関です。独学では1000時間超の勉強が必要とも言われますが、得られる知識は財務諸表の高度な分析や経営管理に及び、財務コンサルなど副業にも応用可能です。
税理士は国家資格の一つで、税務のスペシャリストとして独立開業も可能になります。科目合格制で5科目合格に通常数年かかり、毎年数万人が受験しても一度に全科目合格する人は数百人程度(令和6年度は受験者約34,757人中官報合格者578人)という超難関です。それだけに資格保有者の希少価値は高く、企業顧問や確定申告代行など高収入の副業につなげることもできます。
中小企業診断士は経営コンサルタントの国家資格で、企業の財務・労務・経営戦略まで幅広い知識が求められます。一次試験(筆記)と二次試験(論述・口述)に分かれ、最終的な合格率は3〜8%程度とこちらも難関資格です。取得すれば企業支援の専門家として副業コンサルやセミナー講師など活躍の場が広がり、信用力も飛躍的に高まります。
これら上級資格は学習コストは大きいものの、その後得られる収入アップや専門家としてのポジションは非常に魅力的です。
【投資や資産形成に役立つ】専門知識が学べる資格3選

⑦ DCプランナー(企業年金総合プランナー)
DCプランナーは企業年金(確定拠出年金など)や公的年金制度、退職後の生活設計に特化した知識を学べる資格です。金融財政事情研究会と日本FP協会が共同認定する民間資格で、年金や老後資金計画の専門家育成を目的としています。
2級と1級があり、2級DCプランナーはFP2級程度の知識があれば比較的取り組みやすく、企業の人事・総務担当者やFPがスキルアップに取得するケースも多いです。内容はiDeCo(個人型確定拠出年金)や企業年金の制度設計、資産運用の知識まで多岐にわたり、超高齢社会において老後資金のプロとして活躍できる知見が得られます。
副業では年金相談やセミナー講師などが考えられ、特に企業福利厚生やFP実務に携わる人にとって実践的な資格でしょう。人生100年時代に備える「老後マネーの指南役」として役立つ一資格です。
⑧ 行動経済学検定/金融知識普及系の検定
行動経済学検定は、人間の心理や行動パターンが経済活動にどう影響するかを学ぶユニークな資格です。一般社団法人日本営業科学協会が主催しており、2級・1級と段階があります。特にマーケティングや金融商品の設計に興味がある人におすすめで、自分自身の投資行動の改善にも役立つ視点が得られます。例えば「人はなぜ非合理な投資判断をしてしまうのか」といったテーマを体系立てて学べ、投資判断のブレを減らすヒントになるでしょう。
また、この他にも金融知識の普及を目的とした各種検定が存在します。前述の金融リテラシー検定の他、例えば日本証券業協会主催の「証券知識普及プロジェクト」関連テストなど、金融商品や経済の基本をクイズ形式で学べるものもあります。これらは合格そのものよりも学習過程で知識が身に付くことに価値があり、投資初心者がゲーム感覚で金融知識を底上げするのに最適です。
資格取得という形でモチベーションを維持しながら、楽しみつつ専門知識を学べる点が魅力の検定と言えるでしょう。
⑨ 投資診断士・IFA関連資格
投資診断士は一般社団法人投資診断協会が認定する民間資格で、近年注目を集めています。投資診断士は幅広い金融商品知識と投資助言スキルを持ち、個人の資産形成に対して的確なアドバイスができる人材を育成する資格です。
内容はFPよりも投資実務に特化しており、NISA・iDeCoから仮想通貨まで新しい投資手法も含め横断的に学べるのが特徴です。合格後は協会認定の「投資診断士®」の肩書きを名乗れ、金融機関への就職や独立FP業務で強みになります。
また、IFA(Independent Financial Advisor)関連の資格も投資・資産運用に携わりたい人には重要です。IFA自体は特定の資格名ではなく独立系の資産アドバイザーを指しますが、活動するには証券外務員資格が必須(金融商品仲介業者の外務員登録が必要)であり、さらにFP資格や保険募集人資格など実務上求められる知識があります。
つまりIFAを目指す場合、「証券外務員+FP(AFP/CFP)+必要に応じ保険資格」の組み合わせが事実上の資格セットとなります。これらを取得し実務経験を積めば、独立系アドバイザーとして顧客の資産相談に応じるキャリアパスも開けます。投資診断士やIFA関連資格はハードルは高いものの、投資助言のプロとして活躍したい人にとって大きな武器となるでしょう。
勉強時間・費用・リターン比較表|9資格をまとめてチェック
難易度・学習期間・費用・副業収益性などを一覧で可視化
資格ごとの難易度(合格率)や平均的な学習期間、受験費用、そして副業で稼げる可能性を一覧で比較してみましょう。資格選びの参考になるよう、主要9資格の特徴を表にまとめます。
| 資格(略称) | 難易度(合格率) | 学習期間の目安 | 受験費用(公式) | 副業収益性・活かしやすさ |
| FP(3級/2級) | 易~中(3級: 約70%2級: 約30%) | 3級: 1〜3か月程度 2級: 3〜6か月程度 |
3級: ¥6,000前後 2級: ¥8,000前後 |
★★☆☆☆ 日常の家計管理に直結し、副業より実生活向き。上級取得で相談業務も可。 |
| 簿記(3級/2級) | 易~中(3級: 約40%2級: 約20%) | 3級: 1〜2か月 2級: 4〜6か月程度 |
3級: ¥2,850 2級: ¥4,720 |
★★☆☆☆ 副業記帳や経理補助に活かせる。3級でも家計簿・企業分析に有用。 |
| 金融リテラシー検定 | 易(制限なし) | 1〜2か月程度 | ¥4,000前後 | ★☆☆☆☆ お金の基礎力アップが主目的。直接収益化より自分の資産形成に貢献。 |
| 生活設計アドバイザー | 易~中(講習修了試験) | 2〜3か月程度 | ¥10,000前後 | ★★☆☆☆ ライフプラン相談に活用。副業で家計相談や保険見直しアドバイス等の付加価値に。 |
| 証券外務員(二種・一種) | 中(合格率 約65〜70%) | 1〜2か月程度 | 各¥3,000弱 | ★★☆☆☆ IFAや金融業で必須。副業で証券仲介(紹介手数料収入)も可能に。 |
| 宅建士(宅建) | 中(合格率 約15〜17%) | 6〜9か月程度 | ¥7,000前後 | ★★★☆☆ 不動産取引で報酬可。賃貸管理や売買仲介の副業で収入源に。 |
| 日商簿記1級 | 高(合格率 約10%) | 1年以上(500〜1000時間) | ¥7,850 | ★★☆☆☆ 高度会計スキル習得。副業で記帳代行や決算コンサルも可能だが実務経験要。 |
| 税理士 | 非常に高(科目合格制:総合率数%) | 3〜5年(数千時間) | 1科目¥4,000弱×5科目 | ★★★★★ 開業可能な国家資格。税務顧問など高収入副業の道が開ける。 |
| 中小企業診断士 | 非常に高(合格率 ~5%) | 2〜3年(一次・二次対策) | 約¥30,000 | ★★★★☆ 独立コンサルで収入可。専門家として企業支援業務を副業展開できる。 |
| DCプランナー | 中(合格率非公表、FP2級程度) | 3〜6か月程度 | ¥7,000前後 | ★★☆☆☆ 年金・老後資金の専門知識。社内昇進や副業セミナー講師で活かせる。 |
| 行動経済学検定 | 中(2級: 合格率非公表) | 2〜4か月程度 | ¥5,000前後 | ★☆☆☆☆ 知識習得が主目的。マーケ領域で副業する際の付加価値には。 |
| 投資診断士 | 中(合格率非公表) | 6か月〜1年(講座受講) | 講座込¥100,000超 | ★★★☆☆ 投資助言に特化。社内の投資部署やFP業で差別化に有効。 |
| IFA関連(外務員+FP等) | 高(複数資格必要) | 1年以上 | 資格複数分 | ★★★★☆ 独立IFAとして成功すれば高収入(手数料収入)。資格に加え実務経験重要。 |
※受験費用は概算の公式受験料(2025年現在)です。副業収益性は筆者評価(★は目安、★★★★★が最高)で、資格単独で収入化できる度合いや活用しやすさを示しています。
どれを取るか迷ったときの決め手に
一覧を見ると、自身の目的やライフスタイルに合った資格がおおよそ絞れてくるでしょう。迷った場合はまず「実用性」と「興味関心」で比較検討するのがおすすめです。たとえば、「とにかくお金の基本を固めたい」という初心者の方ならFPや簿記3級から、「不動産投資に興味がある」なら宅建から、といった具合です。
また難易度とリターンも重要な判断軸です。仕事や育児で忙しい方がいきなり難関資格に挑戦すると挫折しかねませんし、逆に将来独立を見据えているなら時間をかけてでも難関資格に挑む価値があります。
最後は「この資格の勉強が楽しめそうか」「取得後に自分がその知識を活かしている姿が想像できるか」という直感も大事です。資格はあくまで手段なので、学びの過程も含め前向きに取り組めるものを選ぶのが、長続きの秘訣と言えるでしょう。
資格だけでは不十分?実生活で「使える知識」にする方法
資格取得後に見直したい自分のお金の使い方
資格を取得して知識を身につけても、それを実生活で活かさなければ意味がありません。まずは自分自身の家計や資産状況を振り返り、資格学習を通じて得た視点でお金の使い方を見直すことから始めましょう。
具体的には、収入と支出のバランス(収支計算)を改めて確認し、無駄な固定費がないかチェックします。FPの知識を得た方なら保険料や通信費など人生における六大固定費の見直しができるでしょうし、簿記を学んだ方なら家計簿や個人の貸借対照表を作って資産・負債の把握ができます。金融リテラシー検定で学んだ方であれば、衝動的な消費を避け計画的に貯蓄・投資へお金を回す習慣づくりを意識するでしょう。
このように、資格取得をゴールではなくスタートと捉え、自身のお金の管理方法に反映させることが大切です。一度身につけた知識は日々の意思決定で使ってこそ生きてきます。月1回は家計を棚卸しし、資格テキストを思い出しながら改善策を実践していきましょう。
家計・資産運用・保険・税制などとのつながり
資格勉強を通じて、お金の世界が家計・資産運用・保険・税制など多方面で密接につながっていることに気付いた方も多いでしょう。例えばFP資格では、家計管理から資産運用、保険設計、税金対策まで総合的に学びます。資格取得後はぜひこれらを有機的に組み合わせ、自分のファイナンシャルプランを最適化してみてください。
具体的には、まず生活防衛資金(急な出費に備える預貯金)を適切に確保しつつ、余裕資金は投資に回して増やすバランス感覚が重要です。保険についてもFPで得た知識を活かし、自分に本当に必要な保障額を計算して過不足を是正します。税制面では、年末調整や確定申告で見落としていた控除を活用したり、ふるさと納税など税優遇制度も賢く使いましょう。
資格勉強で培った知識をフル動員し、家計→保険→資産運用→税金のサイクルを一体で捉えると、無駄なお金が減り手元に残る資産が最大化します。お金の知識を横断的に活用してこそ、本当に「使える知識」となります。資格を取った後も学び続けながら、自分や家族のライフプランに知識を反映させアップデートし続けましょう。
資格を取ったあとにやっておくべき5つの行動

資産チェック/ポートフォリオの見直し
資格取得後には、まず自分の持つ資産の棚卸し(チェック)を行いましょう。銀行預金や株式、保険商品、不動産など、自分が保有するすべての資産と負債を一覧化します。FPや簿記の知識を活かせば、自分自身のバランスシート(資産負債表)を作成することもできます。そして、その現状を踏まえて資産配分(ポートフォリオ)が適切かを検討します。特定の資産に偏りすぎてリスクが高くなっていないか、あるいは逆に余剰資金を遊ばせていないかを見極めます。
次に運用方針の見直しです。資格取得で学んだ知識を活かし、各資産の期待リターンやリスクを再評価します。例えば「自分の年齢やライフイベントに照らして、攻めと守りのバランスは適切か?」と問い、必要に応じて目標配分にリバランス(再調整)します。FP資格で学ぶように一般に若いうちはリスク資産比率を高め、年齢とともに安定資産を増やすのがセオリーです。また簿記や投資診断士の視点から、自分の投資先企業の業績や財務指標をチェックし直すことも有効でしょう。
資格取得で得た分析力と思考法を使って、自分自身の資産運用計画をアップデートする、これがまず取り組むべき重要な行動です。
NISA・iDeCo・保険などとの組み合わせを再設計
次に、公的制度や金融商品の組み合わせを最適化しましょう。日本には少額投資非課税制度(NISA)や個人型年金制度(iDeCo)、各種保険商品など、資産形成やリスクヘッジに有効な制度が揃っています。資格勉強でそれらの仕組みを理解した今こそ、自分にとってのベストミックスを考える好機です。例えば投資初心者であれば、まず新NISAを活用した長期・積立・分散投資を検討すると良いでしょう。金融庁も資産形成の鍵として「長期・積立・分散投資」の重要性と、NISA・iDeCoなど非課税制度の活用を挙げています。毎月の積立投資でコツコツ増やしつつ、運用益非課税の恩恵を最大限受けられるよう設計します。
同時に保険の見直しも重要です。FP知識を踏まえ、生命保険や医療保険について保障内容と保険料を再チェックし、不要な特約を外したり不足分を補ったりします。独身で扶養家族がいなければ高額な死亡保障は減らせますし、逆に家族ができたら必要保障額を増やすなどライフステージに合わせ調整します。また住宅購入を考えている場合は住宅ローン減税など税制優遇も勉強の成果を活かしてシミュレーションしてみましょう。
NISAでの資産運用×iDeCoでの老後資金準備×保険での保障、これらを組み合わせた総合プランを、自身の新しい知見で再設計することが、資格取得後にぜひ実践しておきたいステップです。
お金の知識をどう活かす?「分散投資」的思考がカギ
資格で得た知識を「守りの投資」に活かす方法
お金の知識を活かすうえで重要なのが、リスクを分散し資産を守る「守りの投資」の視点です。資格取得により株式や債券、投資信託、不動産など様々な資産の特徴を学んだと思いますが、それらを組み合わせることで一極集中のリスクを避け、安定的な資産運用を目指すことができます。
具体的には、値動きの異なる複数の資産クラスに分散投資することで、一部の資産が不調でも他で補える耐久力のあるポートフォリオを構築します。FPや投資診断士で学んだ人はご存知のように、債券や預金など元本確保型の資産を適度に織り交ぜることで全体のリスクを下げる効果があります。
また、「守りの投資」では確実に利益を積み重ねる仕組みを選ぶこともポイントです。例えば定期預金や個人向け国債はリターンこそ小さいものの元本が守られますし、不動産投資でも家賃収入という安定収益があります。
そして最近注目されている融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)も、守りの投資の一つと言えます。これはネット上で多数の投資家から資金を募り事業者に貸し付ける仕組みで、融資期間が終われば元本が戻り、期間中は利息収入を毎月受け取れるため、株式投資型よりも安定的なリターンが期待できます。実際、「満期に元本が戻り途中で定期的な分配金が得られる」という点で、短期的な値上がり益を狙うより堅実な資産運用として評価されています。
このように資格で得た知識を総動員して「減らさない工夫」「確実に増やす工夫」を凝らすことが、資産形成を長く続ける秘訣です。
「長期・積立・分散」の基本がすべての土台になる
お金の知識を活かす上級編とも言えるのが、「長期・積立・分散」投資という思考法を貫くことです。この原則は金融庁も繰り返し提唱しており、資産形成の基本中の基本とされています。資格学習の中でも耳にタコができるほど出てきたかもしれませんが、それだけ重要かつ有効な考え方なのです。
長期投資は時間の力で複利効果を得て資産を増やし、積立投資はドルコスト平均法で購入単価を平準化し、分散投資はリスク低減を図ります。この3つを組み合わせれば、安定的な資産形成が期待できることは理論のみならず過去のデータが証明しています。
資格取得後は、ぜひこの「長期・積立・分散」のメガネをかけて自分の投資計画を見直してみましょう。例えば短期売買で利益を狙おうとしていた部分を見直し、長期保有前提の優良な投資信託やETFに切り替える。毎月の積立額を設定し、自動積立で機械的に投資を続ける仕組みを導入する。そして投資先を国内外の株式・債券・不動産などに広げ、一つの国や資産に集中しないようにする。こうした調整は地味に感じるかもしれませんが、20年30年というスパンでは大きな差を生みます。
実際、金融庁の試算でも「長期・積立・分散投資を20年間続ければほぼ損をしない」というデータが示されています。資格で得た知識をこの普遍的な投資原則の下で組み立て直すことで、荒波の市場を乗り越える強固な資産形成プランが出来上がるのです。
融資型クラウドファンディングという“知る人ぞ知る”選択肢

リスクを抑えた運用に最適な仕組みとは?
ここまで「守りの投資」の一例として触れた融資型クラウドファンディング(貸付型クラファン)は、まだ一般には馴染みが薄いものの、知る人ぞ知る安定運用向きの選択肢です。これは個人投資家から少額ずつ資金を集め、大口の資金として企業などに融資するサービスで、インターネット上のプラットフォームを通じて行われます。いわば銀行の融資業務をネットで小口化・民主化したような仕組みであり、「ソーシャルレンディング」と呼ばれることもあります。
融資型クラファンのメリットは、比較的安定した利息収入が得られる可能性が高い点です。株式投資のように価格変動リスクで一喜一憂する必要がなく、融資先からの返済が滞りなく行われれば決まった利率の利息が定期的に支払われ、満期時には元本が戻ってきます。つまり、元本割れ(貸し倒れ)さえ起こらなければ、計画通りのリターンが見込みやすいのです。
さらに多くのサービスで1万円程度から投資でき、案件も複数に分散しやすいため、少額・分散でリスクを抑えた運用が実現できます。近年では不動産担保付きの融資案件など安全性に配慮した商品も増えており、初心者でも取り組みやすくなっています。
ただし注意点として、途中解約ができないことや運営事業者の信用リスクなどもあるため、サービス提供会社の実績や案件内容をしっかり見極めることが重要です。総じて融資型クラウドファンディングは、「銀行預金より利回りが欲しい、でも株式ほどの変動リスクは負いたくない」という投資ニーズにマッチした、新時代の運用オプションと言えるでしょう。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
よくある質問(FAQ)|資格取得とお金の知識に関する疑問
Q1. どれが初心者におすすめ?
完全な初心者であれば、まずはファイナンシャル・プランナー(FP)3級や日商簿記3級がおすすめです。これらは合格率も高め(FP3級約70%、簿記3級約40〜50%)で独学しやすく、お金の基礎知識を網羅的に学べます。
FP3級では家計管理から保険・年金・資産運用の基本まで幅広く学べるため、生活全般に直結する知識が得られます。簿記3級はお金の「計算方法」を身につけるのに最適で、家計簿の延長で企業のお金の流れも理解できるようになります。もし勉強時間をあまり取れない場合は、金融リテラシー検定も良いでしょう。高校生から受験できる検定で内容も平易なので、短期間でお金の常識度をチェックできます。
いずれにせよ、まずは「学んでいて興味が持てるか」が大切です。FPと簿記は内容が異なるので、たとえばFPのテキストと簿記のテキストを書店で立ち読みしてみて、ピンときた方から始めても良いでしょう。最初の一歩は、楽しみながらお金の勉強ができる資格を選んでみてください。
Q2. 副業・転職に役立つのは?
副業や転職で直接武器になりやすいのは、宅建や証券外務員、そして難易度は高いですが税理士・中小企業診断士などの国家資格です。例えば副業で不動産投資や不動産仲介をしたいなら宅建士資格があると信頼性が段違いですし、実際に宅建業に従事しなくとも不動産取引の知識が投資で大いに役立ちます。
金融業界に転職したいなら証券外務員資格は必須級です。未経験であっても証券外務員一種を持っていれば証券会社や銀行の採用でアピール材料になりますし、独立系FPとして投資助言の副業をする際にも欠かせません。
より専門性の高い税理士や中小企業診断士は、取得までに年数はかかりますが、得られるリターン(収入アップ)は極めて大きい資格です。税理士なら副業で確定申告代行や税務相談業務が可能となり、企業からのニーズも高いです。中小企業診断士は企業コンサルが本業・副業問わず可能になり、行政の専門家派遣事業などに登録して報酬を得る道もあります。
現実的には難関資格は簡単には取れませんので、まずは日商簿記2級やFP2級程度から初めて徐々にステップアップするのも手です。簿記2級があれば経理の求人に有利になりますし、FP2級を持っていれば金融業界や保険業界で一定の知識を持っていると評価されます。
最終的に何を副業・転職の軸にするかで選択は異なりますが、「不動産で稼ぎたい→宅建」「金融商品で稼ぎたい→外務員+FP」「税務で独立したい→税理士」など、自身の目標に直結する資格を選ぶと良いでしょう。
Q. 資格より実務経験の方が大事では?
確かにお金の世界に限らず、実務経験から学べることは非常に多いです。資格は知識の習得と一定の能力証明にはなりますが、実際にお金を運用したり相談業務に当たったりすると、机上では分からなかった難しさに直面するでしょう。しかし資格と実務経験は二者択一ではなく、車の両輪のように考えるのが賢明です。資格取得で得た知識があるからこそ、実務に入ったときの理解が速くなり、ミスも減らせます。
例えばFP資格を持っていれば金融商品や税制の大枠を把握しているため、銀行や保険会社に勤めてから先輩の言っている専門用語がスッと頭に入ってくるでしょう。逆に実務で感じた疑問を後で資格テキストに立ち返って調べ直すことで、理解が深まるという好循環もあります。
また資格を持っていると周囲から信頼を得やすくなるメリットも無視できません。お金に関するアドバイスをする場面では「○○の有資格者です」と名乗るだけで相手の安心感が違います。特に独立系の仕事(FP相談や投資助言など)では肩書きが信用力に直結します。
理想を言えば、資格を取って→その知識を実務で活かし→さらに経験で感じた課題を勉強で補い→上級資格にチャレンジというサイクルを回していくと良いでしょう。資格取得はゴールではなくスタートです。実務経験と資格勉強を補完し合いながら、お金の知識とスキルを高めていくのがベストな姿と言えます。
まとめ|資格で得た知識を「行動」に変えて資産を守ろう

お金に関する資格は、知識武装して自分の資産を守るための強力なツールです。しかし、その真価を発揮するには資格で得た知識を実際の行動に移し、自分の資産形成に活かしてこそ意味があります。人生100年時代、自ら学び行動する「自衛力」が何より重要であることは繰り返し述べてきました。資格取得をきっかけに家計の見直しやポートフォリオ調整、NISA・保険の活用などさっそく手を動かした方もいるでしょう。その一つひとつのアクションが、将来の安心につながっています。
最後に、本記事のテーマでもある「おすすめ資格9選」で挙げた資格は、それぞれ方向性やレベルは違えど「お金の知識を行動に移す」ための助けになってくれるはずです。例えばFPや簿記で学んだ知識を活かして家計管理を改善したり、副業で宅建や証券外務員のスキルを活かして収入アップを図ったり、融資型クラウドファンディングを利用して守りの投資を実践したりと、できることは数多くあります。大切なのは、得た知識を眠らせないことです。知識は使ってこそ定着し、新たな経験と結びついてさらなる知恵へと昇華します。
資産形成は長いマラソンです。資格という地図と知識というコンパスを手に入れた今、ぜひ一歩ずつでも行動を起こし、自分や家族の資産を守り育ててください。「長期・積立・分散」の地道な積み重ねと、必要に応じた知識のアップデートを続けることで、きっと将来の安心というゴールに近づけるはずです。資格で得た知識を武器に、今日からできることを始めてみましょう。それが将来の自分への何よりの贈り物になるのです。
参照元
- 政府広報オンライン:『「金融リテラシー」って何? 最低限身に付けておきたいお金の知識と判断力』
- 厚生労働省:『iDeCoの概要』