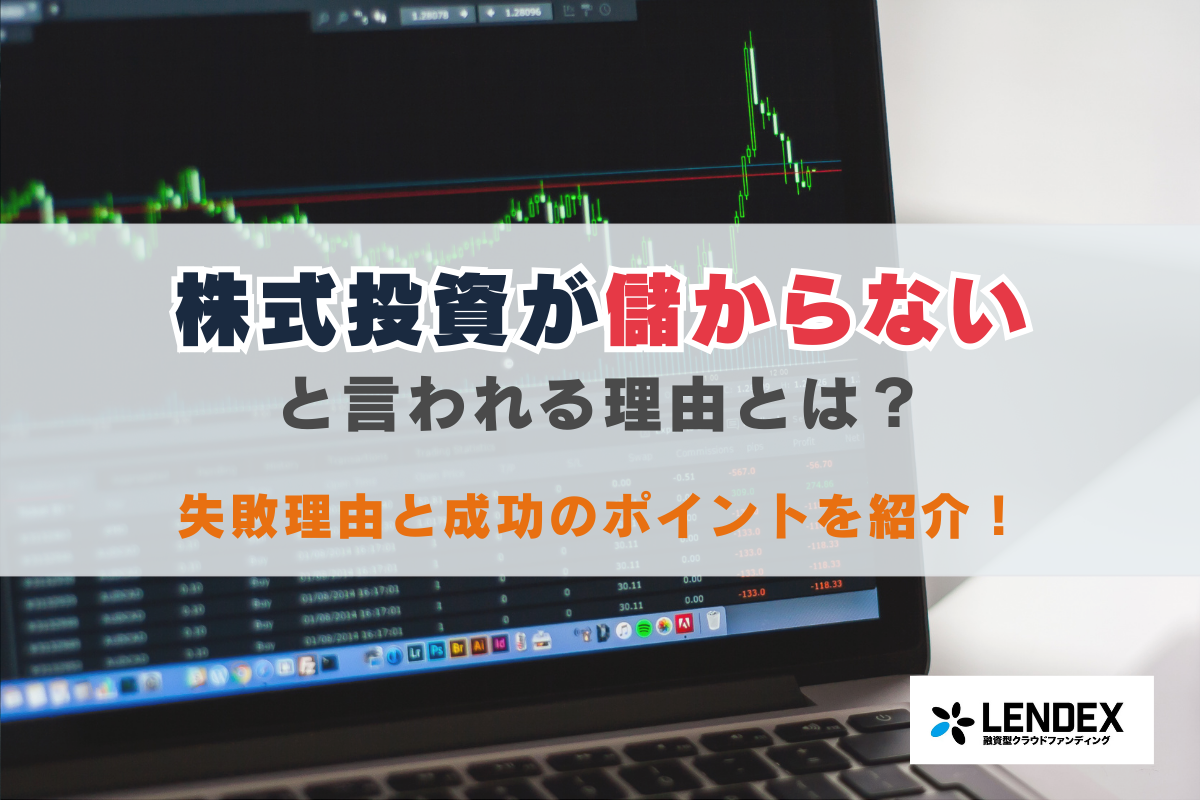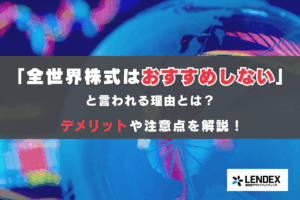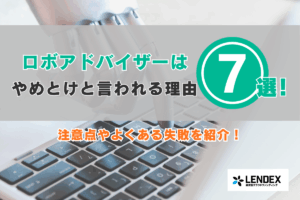株式投資に挑戦したものの「思ったほど儲からない」と感じた経験を持つ人は少なくありません。
実際、多くの投資家が市場の値動きに悩まされ、期待した成果を得られずに途中で諦めてしまうことがあります。しかし、株式投資そのものが必ずしも儲からないわけではなく、背景には誤解や典型的な失敗パターンが隠れています。
本記事では「株式投資が儲からない」と言われる理由を整理し、なぜ失敗してしまうのかを具体的に解説します。そのうえで、安定して成果を得るための考え方や実践的なポイントも紹介します。
初心者の方はもちろん、これまで成果を実感できていない方にとっても、次の投資判断に役立つ内容となるでしょう。
株式投資は本当に儲からないのか?結論から解説

株式投資は短期では損をすることもあるが長期では資産形成につながりやすい
株式投資は短期的に見ると損失が出ることもあります。しかし、長期的に継続すれば資産形成につながりやすいのが大きな特徴です。
株価は日々変動するため短期ではマイナスになる年もありますが、過去の平均ではプラスのリターンが得られる傾向にあります。実際、投資は短期では利益が上下にぶれるものの、長期で平均すると資産を増やす効果が大きいとされています。また、配当金を再投資することで複利効果が働き、長期間保有するほど資産の増加ペースが加速しやすくなります。
こうした理由から、政府もNISA制度などを通じて長期・積立投資による資産形成を推進しています。長い目でコツコツと運用することで、株式投資は将来の財産づくりに有効な手段となるのです。
儲からないと言われるのはリスクとリターンの差を正しく理解していないから
株式投資が「儲からない」と言われる背景には、リスクとリターンの関係を正しく理解していないことが挙げられます。
高いリターンを得るためには相応のリスクを取る必要があり、リスクを避けていては大きな利益は望めません。実際、リスクとリターンは表裏一体の関係であり、「安心で絶対儲かる」投資商品は存在しないのです。例えば、元本保証の預金はリスクが低い反面リターンもごくわずかです。
一方、株式のように価格変動が大きい資産は損失リスクもありますが、高い利益が得られる可能性も秘めています。
このように、リスクとリターンのバランスを理解することが株式投資では不可欠です。リスクを取らずに低いリターンしか得られず、「株は儲からない」と感じてしまう人も少なくありません。
株式投資が儲からない理由とは?

株価の変動が大きく予測が難しい
株式市場は値動きの変動幅が大きく、短期的な株価の上下を正確に予測するのは極めて困難で、ほぼ不可能と言っても過言ではありません。予期せぬ天災や経済ショックなどで株価が急落することもあり、プロの投資家でさえ短期の値動きを的中させるのは難しいとされています。
実際、国内株式は一年で50%以上値上がりする年もあれば30%以上値下がりする年もあり、短期的な変動幅は非常に大きくなり得ます。そもそも株式投資には常に不確実性が伴うため、経験豊富なプロでも短期予測で安定して勝ち続けることは困難です。
こうした予測の難しさから、思惑どおりに利益を得られないケースも多く、「株式投資は儲からない」と感じる原因の一つになっています。
タイミングに左右されやすい
株式投資の利益は売買のタイミング次第で大きく変わります。しかし、常に「安く買って高く売る」ことは現実にはほとんど不可能です。
むしろ人間の心理として、株価が上がると強気になって買い、下がると不安になって売ってしまい、結果的に「高値で買って安値で売る」取引になりがちです。特に経験の浅い人ほど、相場の天井近くで買い、その後の下落で含み損を抱える失敗をしがちです。また、一度逃した利益を取り戻そうと無理に売買タイミングを計ろうとすると、さらに損失を拡大させてしまうケースも頻繁に見られます。
タイミングを誤ると大きな損失を招きやすく、この難しさが株式投資は儲からないと言われる大きな一因となっているのです。
手数料や税金が利益を圧迫することがある
株式投資で利益を出しても、そこから各種コストが差し引かれるため手取り額は目減りします。株式の売買では購入時と売却時に証券会社への手数料が発生し、さらに売却益や配当には約20%の税金がかかります。
例えば、100万円の利益が出ても約20万円は税金で差し引かれ、手数料も考慮すると手元に残るのは80万円を下回るでしょう。頻繁に売買を繰り返せばその都度コストがかさみ、最終的な利益はさらに目減りします。
なお、NISAなどの非課税制度を活用すれば税負担を軽減できますが、それでもコストの存在は無視できません。手数料や税金は確実に発生するため、利益を圧迫し「思ったほど儲からない」と感じる大きな原因となり得ます。
株式投資の失敗理由を具体的に解説

短期で利益を狙いすぎて失敗してしまった
短期間で大きな利益を得ようと狙いすぎると、かえって失敗しやすくなります。相場の変動に乗じて短期売買を繰り返しても、毎回うまく利益確定するのは困難です。
典型的には、短期間で利益を上げようとするあまり相場の細かな上下に振り回され、気づけば損失が膨らむといったケースです。多くの個人投資家が株式投資で損失を経験しているという調査結果もあり、決して珍しいことではありません。例えば、流行のテーマ株に飛び乗って頻繁に売買を重ねた結果、資金を大きく減らして退場してしまう例もあります。
短期売買に専念する個人投資家の多くが利益を出せていないとも言われており、目先の儲けを急ぐ戦略は失敗に陥りやすいのです。
感情的に売買して判断を誤ってしまった
株価の変動に一喜一憂して感情的に売買すると、冷静な判断ができず失敗につながりやすいです。
人は含み損が出ると焦って損切りを躊躇したり、逆に上昇局面では過信して高値掴みするなど、感情に振り回された行動を取りがちです。人間には損失を過剰に恐れる「損失回避」の心理傾向があり、含み損を目にすると冷静さを失いやすいことが知られています。
反対に利益が出ていると判断が甘くなり、大きく儲けようと欲張って売り時を逃すこともあります。実際、株式投資で失敗した投資家からは「感情に左右されず、市場や企業の分析に基づいて判断することが重要」との教訓が多く挙げられています。
冷静さを欠いた取引は誤った判断につながり、大きな損失を招く原因となります。
情報不足で誤った銘柄を選んでしまった
銘柄選びの際に十分な情報収集や分析を怠ると、誤った投資判断につながってしまいます。企業の財務状況や将来性を調べずに、高配当や話題性だけで飛びついた結果、大きく値下がりして損失を被るケースも少なくありません。
例えば「配当利回りが高い」という理由だけで銘柄を選んだ結果、その企業の業績悪化で減配となり株価も急落して大損した、といった例も見られます。ある調査でも、株式投資で失敗した最大の理由として「投資先の分析や知識が不足していた」ことを挙げた人が約46%にのぼりました。
情報武装せずに株式投資に臨むのは極めて危険だと言えるでしょう。十分な情報に基づかない雰囲気任せの投資判断は、失敗のリスクを高めるのです。
株式投資で成功するためのポイント
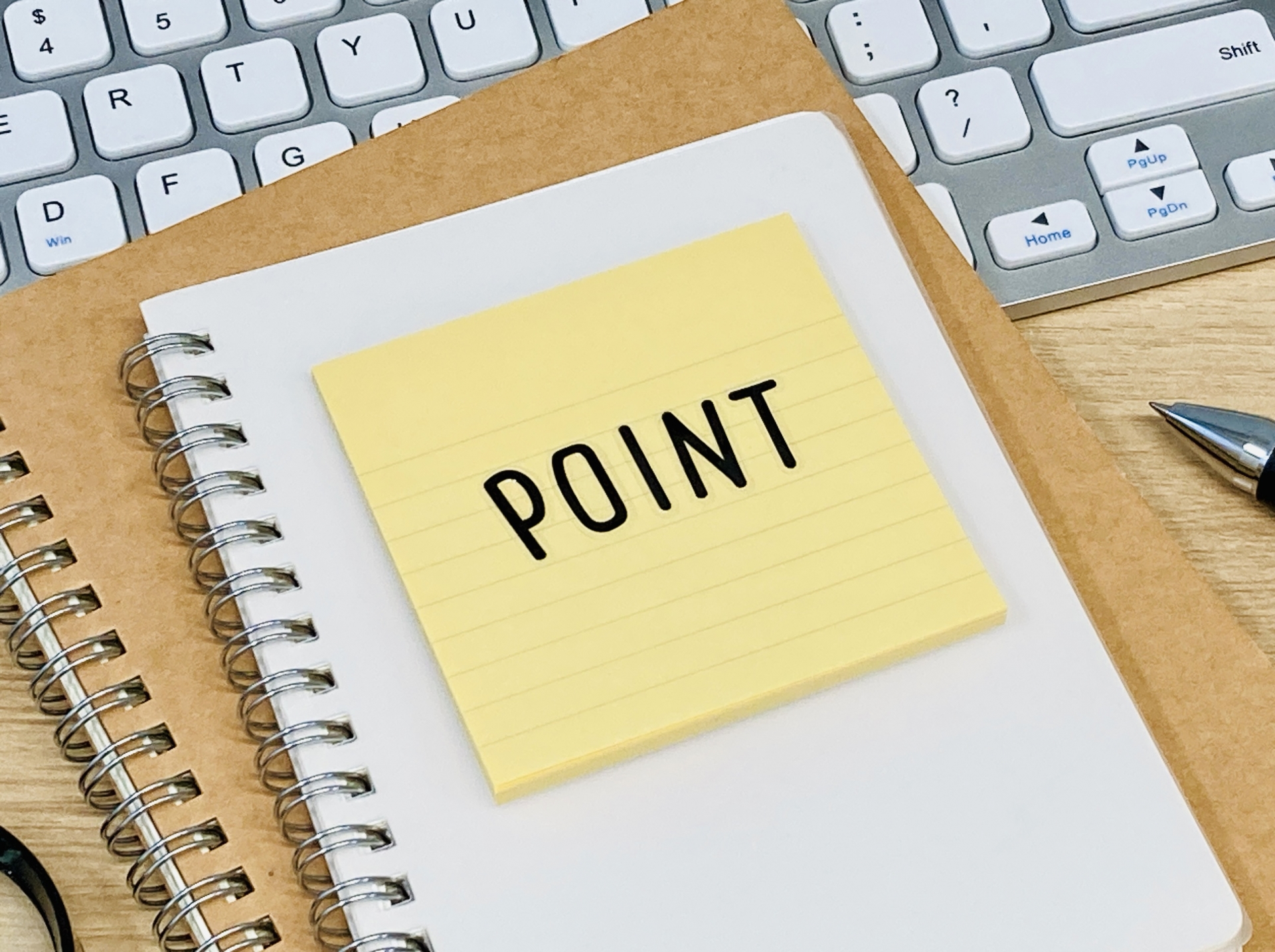
自分に合った投資スタイルを持つことが大切
株式投資で成功するには、自分に適した投資スタイルを確立することが欠かせません。
他人の真似をするのではなく、自身のリスク許容度や資金状況、投資目的に合った手法を選ぶ必要があります。例えば、短期売買がストレスになる人は長期投資を選択した方が良いでしょうし、時間が取れない人はインデックス投資などシンプルな方法が向いているかもしれません。金融庁も「自分の目的やライフプランに合った商品を選びましょう」と投資前の十分な検討を呼び掛けています。
また、リスクをあまり取れない人は安定配当株やインデックスファンド中心の運用にするなど、自分に合った範囲で投資対象を選ぶことも重要でしょう。自分に合うスタイルで取り組むことで、無理なく継続でき成功率も高まります。
長期的な視点でコツコツ続けることが成功につながる
株式投資では「時間を味方に付ける」ことが成功への近道です。
短期の値動きに振り回されず、長期的な視点でコツコツと投資を続けることで、着実に資産を増やせる可能性が高まります。米国では「早く始めて長く続けるほど複利のメリットを享受できる」と言われており、実際に積立投資を長期間続けるほど好結果が得られやすいことが過去の実績から示されています。
また、長期にわたり複利運用を続ければ、小さな元本でも将来大きな資産に育つ可能性があります。例えば、年5%の利回りで20年間運用すれば元本は約2.6倍に増える計算となり、長期投資の威力がわかります。
長期に定期的な投資を続ければ、一時的な相場下落も時間とともにカバーし、平均的な成長軌道に乗せることができるでしょう。
投資ルールを決めて守ることで失敗を減らせる
自分なりの投資ルールを定め、それを厳守することは失敗を減らす上で極めて重要です。明確なルールがないと、その場の感情や勘に頼った取引になりがちで、大きな損失につながる恐れがあります。
例えば「〇%下落したら損切りする」「1銘柄に資金を集中させすぎない」などの基準をあらかじめ決めておくと、暴落時にも冷静に対処できます。実際、株式投資で失敗した投資家の中には「損切りルールを決めておらず損失を拡大させてしまった」と反省する声も多く、タイミングを逃したことを後悔する割合は33.7%に上りました。
定めたルールを遵守することで感情に流されるのを防ぎ、致命的な失敗を避けることが可能になります。
株式投資を安定させるための分散投資という考え方
複数の銘柄に投資してリスクを分ける
一つの銘柄だけに集中投資するのではなく、複数の銘柄に資金を分散させることでリスクを軽減できます。仮に1社の業績悪化で株価が大きく下落しても、他の銘柄の値上がりで損失を補える可能性があるため、ポートフォリオ全体のブレ(変動幅)が小さくなるのです。
極端な例ですが、1社の株式だけを持つよりも10社の株式に分散して持っていた方が、1社の悪材料による資産全体へのダメージは軽減されます。分散により収益機会も広がり、結果として安定したリターンを得やすくなるのです。実際、値動きの異なる複数の資産に分散投資を行うことで価格変動が小さくなり、リスクを抑えられることが確認されています。
このように銘柄数を増やして投資することで、一つの失敗が致命傷とならず、安定した運用につながります。
株式以外の資産にも資金を分ける
株式だけでなく債券や不動産など値動きの異なる資産にも資金を振り分けることで、全体のリスクをさらに抑えられます。
異なる値動きの資産を組み合わせれば、ある資産が下落しても別の資産の値上がりで損失を補いやすく、ポートフォリオ全体の変動幅が小さくなるのです。例えば、株式・債券・不動産に分散投資すれば、一般的にリスクを抑えた効率的な運用が可能になります。実際、年金基金など大口の機関投資家も国内外の株式と債券を組み合わせた大規模な分散投資で安定運用を図っています。
株式以外の資産を組み入れることで、景気変動や金利変動に対する耐性を高めることができます。複数の資産に分散することで、一つの市場の低迷が資産全体に与える影響を小さくできるでしょう。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】株式投資に関するよくある質問

株式投資はなぜ儲からないと言われるのですか?
株式投資が儲からないと言われるのは、短期的な損失が目立ち利益が出にくい場合があるからです。
実際、多くの投資家が損失を経験しているとの調査結果もあり、特に知識不足のまま短期売買を繰り返すと失敗しやすい傾向があります。例えば、十分な分析を行わずに流行の銘柄へ飛びつくと損失が積み重なり、「儲からない」と感じてしまうことがあります。
株式投資はどんな人が失敗しやすいのですか?
短期で一攫千金を狙う人や、十分な知識がないまま感情任せで売買する人は失敗しやすい傾向があります。
実際、失敗理由では「分析や知識不足」が約46%と最も多いとのデータがあります。例えば、勉強不足の初心者が値動きに焦って売買を繰り返すと、判断ミスで損をしやすいでしょう。
株式投資はやめたほうがいいのでしょうか?
いいえ、正しく運用すれば株式投資は資産形成に役立つため、やめる必要はありません。
短期的には損益がぶれるものの、長期平均では資産を増やす効果が大きいとされています。例えば、長期・分散投資を続ければ、一時的な下落に左右されずに利益を得られる可能性が高まります。
まとめ|株式投資が儲からない理由と成功の近道
株式投資が儲からないと言われるのは、短期的な損失の発生やリスクに対する誤解が背景にあります。
しかし、長期・積立・分散を徹底した堅実な運用を行えば、資産を増やす有効な手段となります。時間をかけて幅広い資産に投資を続けることで、値動きのぶれを抑えつつ安定的な成果を得やすくなります。
リスクと向き合いながら計画的に投資を継続すれば、株式投資でも着実に資産を築くことができるでしょう。
参考元
・金融庁「長期・積立・分散投資とNISA制度」
・金融庁「貯める・増やす」
・日本銀行「市場リスク管理体制の整備」
・国税庁「株式・配当・利子と税」
・金融庁「株式投資 投資信託 債券投資」
・日本銀行「金融システムレポート (2025年4月)」
・国税庁「株式等の譲渡所得等の申告のしかた」