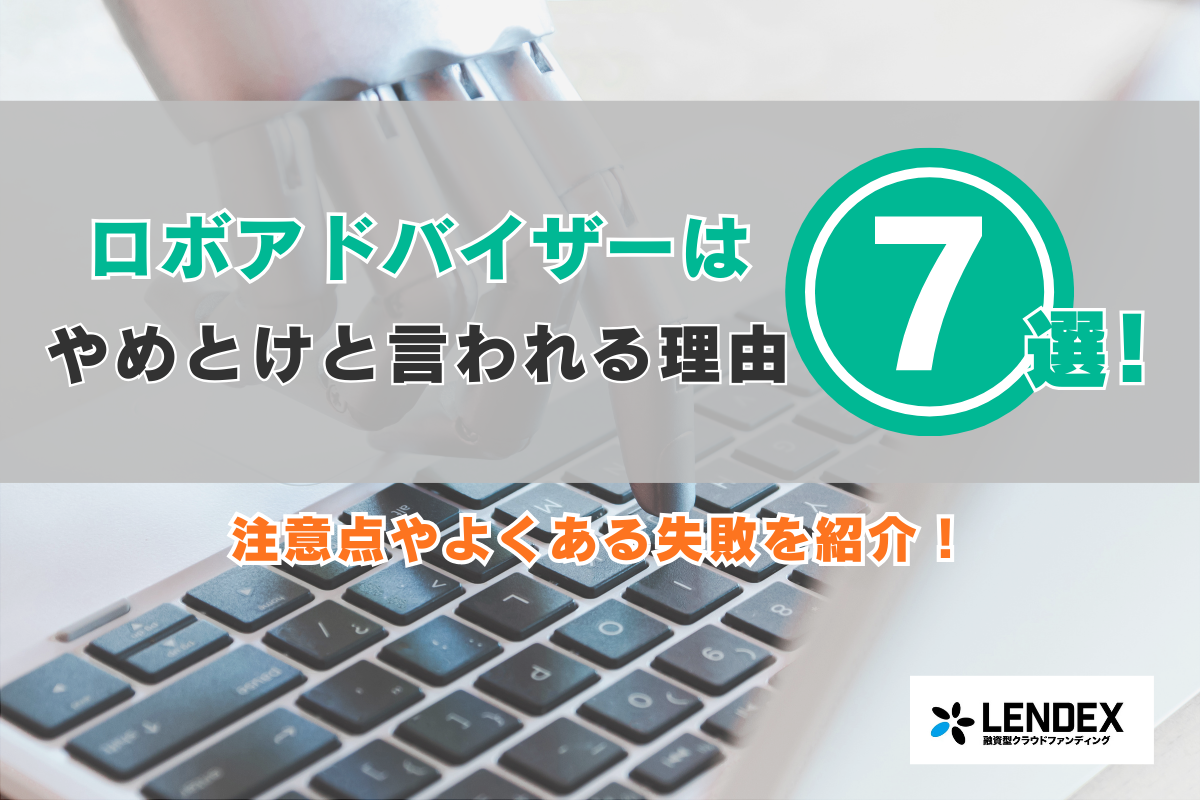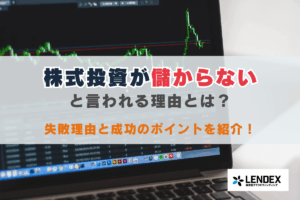投資の世界では便利なサービスとして「ロボアドバイザー」が注目を集めています。
AIに資産運用を任せられる手軽さから利用者は増えていますが、その一方で「ロボアドバイザーはやめとけ」という声も少なくありません。確かに自動運用の仕組みは魅力的ですが、手数料やリターンの面で思ったほど成果が出ないことや、投資家自身の学びが得られにくいといった課題もあります。
では、なぜロボアドバイザーに否定的な意見があるのでしょうか。本記事では「ロボアドバイザーはやめとけ」と言われる具体的な理由や、実際に起こりやすい失敗例、さらに利用する際の注意点について詳しく解説します。
投資初心者でも理解しやすいように整理し、堅実に資産形成を進めるための選択肢も紹介します。
ロボアドバイザーはやめとけ?結論を先に解説

投資初心者が安易に選ぶとリスクが高い
ロボアドバイザーはAI任せで「楽に増やせそう」と初心者が安易に選びがちですが、それは大きなリスクを伴います。「自分のお金をAIに任せても大丈夫なのか」と不安視する声があるように、ロボアドは元本保証がなく、市場次第で資産が目減りする可能性があります。たとえ安定運用のポートフォリオでも、一時的な損失は避けられません。
また、欲張ってリスク許容度以上の設定をしてしまうと、許容範囲を超える損失が出て途中解約に追い込まれる恐れもあります。短期で利益が出ないからと途中で投資をやめてしまえば、せっかくの資産形成も失敗に終わります。
少しの損失にも耐えられない人には不向きな投資法であり、リスクを十分理解しないまま飛びつくと痛手を被りかねません。
思ったほど資産形成につながらない場合がある
ロボアドバイザーは分散投資による安定志向の運用が中心のため、短期間で資産を大きく増やすことはできません。
実際、ロボアドは10年以上の長期投資を前提としており、数ヶ月程度でまとまったリターンを得るような設計にはなっていないのです。そのため「期待していたほど利益が出ない」「自分で運用しても同じリターンだったのでは」と感じるケースも多々あります。
さらに、運用中に年率1%前後の手数料が差し引かれることで実質リターンが目減りし、思ったほど資産が増えない要因となっています。
要するに、ロボアドは大きな儲けを狙うというより、コツコツと資産形成をするための仕組みだと言えるでしょう。
ロボアドバイザーはやめとけと言われる理由7選

手数料が割高で運用効率が下がる
ロボアドバイザーの利用には運用手数料が年間約1%かかります。さらに投資先ファンドの信託報酬なども別途発生し、コストは二重にかかる仕組みです。
インデックス投資信託なら0.1%未満の低コスト商品も多く、単純比較でもロボアドは割高です。わずか1%の差でも、長期で複利運用すれば数十万〜数百万円単位で資産額に影響を与える可能性があります。つまり、手数料が高いぶんリターンが圧迫され、利益が出ても「手数料負け」で資産が思うように増えないリスクが高まります。
利回りが想定より低く感じて期待外れになることが多い
ロボアドバイザーは分散投資による安定運用が前提のため、リターンが平準化されやすくなります。想定利回り自体も年数%程度と決して高くはなく、アルゴリズム任せの運用ゆえリターンの上限が比較的低くなりがちだとの指摘もあります。
その結果、運用成果が「思ったほど伸びない」「期待外れだった」と感じるケースが少なくありません。実際、市場状況によっては期待した利益が出ず、「普通に運用しても同じリターンだったのでは?」と感じることもあります。さらに手数料を差し引くと実質利回りが下がるため、なおさら利回りが物足りなく感じられるのです。
運用方針が一律で柔軟性に欠ける
ロボアドバイザーはあらかじめ設定されたアルゴリズムに従って資産運用を行うため、運用方針が画一的で柔軟性に欠けます。市場環境や個々の投資家の細かなニーズに応じて機動的に戦略変更することは難しく、突発的な相場変動や特殊な状況では対応しきれないケースもあります。
例えば経済危機やパンデミック時に、過去データに基づく機械的な運用ではリスク回避が遅れる可能性が指摘されています。経験豊富な投資家やプロであれば柔軟に方針転換できますが、ロボアドは基本的に一律の運用方針から逸脱できないため、状況に応じた最適な判断ができない場合があるのです。
解約や出金に時間がかかるケースがある
ロボアドバイザーは解約や出金の手続きに時間がかかる場合があります。証券会社やサービスによって異なりますが、運用中の資産を現金化して口座に戻すまでに数日〜数週間を要するケースも少なくありません。
例えば大手ロボアドのウェルスナビでは、解約申込書の郵送手続きが必要で、自動積立の解除も決まった期日までに行う必要があります。そのため「思い立ったらすぐ解約」というわけにはいかず、完了まで1〜2週間程度かかることがあります。
また、出金を申請してから実際に資金が振り込まれるまで約3営業日かかるため、出金にもタイムラグが生じます。急に資金が必要になった際にすぐ引き出せない点はデメリットと言えるでしょう。
自分で判断する力を養う機会が少ない
ロボアドバイザーは投資のすべてを自動で行ってくれる反面、利用者が自分で判断する機会がほとんどありません。資産配分の検討や銘柄選択、市場の分析などを任せきりにしてしまうため、投資の知識や経験を積む場が少なくなります。
特に投資初心者にとっては、市場の仕組みや運用プロセスを理解することが非常に重要ですが、ロボアドを使うことでそれらを学ぶ機会が減ってしまい、将来的に自分で投資判断を行う力が育ちにくくなります。
「任せっきり」の状態が続くことで、いつまでも受け身の投資から抜け出せなくなるリスクも指摘されています。
元本保証がなく損失リスクがある
ロボアドバイザーを利用しても元本が保証されるわけではなく、預けたお金が目減りするリスクは常に伴います。
投資先は株式や債券など市場連動の商品であり、市場動向によっては運用資産が元本を下回る(元本割れ)ことも十分あり得ます。分散投資によってリスクを抑えているとはいえ、損失リスクをゼロにはできません。
実際、市況によっては「現在は損をしている」という状況が発生し得るとされています。焦って低迷時に解約してしまえば、大きな損失が確定する可能性もあり、ロボアドバイザーも例外ではなく他の投資と同様に損失リスクがあることを理解しておかなければなりません。
節税効果や税務面での最適化が弱い
ロボアドバイザーは税制面でのメリットが限定的で、節税最適化が十分ではない場合があります。NISA(少額投資非課税制度)口座に対応していないサービスもあり、その場合運用利益に約20%の税金が課されてしまいます。非課税枠を使えないことで、長期運用では最終的な資産額に大きな差が生じかねません。
節税メリットを活かすにはNISA対応のロボアドバイザーを選ぶ必要がありますが、対応状況はサービスによってまちまちです。また、運用益と損失を相殺する「損出し」などの高度な税務最適化は、人手で行う場合ほど柔軟ではなく、税負担を最小限に抑えきれないケースもあります。
実際に起こりやすいロボアドバイザーのよくある失敗事例

高い手数料が積み重なって資産が増えなかった
長期運用したものの、ロボアドバイザーの高い手数料が重荷となり資産が思うように増えなかったケースです。例えば年率1%の運用手数料が10年積み重なれば、100万円投資していた場合でもトータルで10万円以上が手数料として差し引かれます。
運用益がわずかしか出なければ、その利益は手数料で相殺されてほとんど資産が増えない、あるいは減ってしまう可能性もあります。実際「少々利益が出ても手数料負けで資産が増えなかった」という声は、ロボアドバイザー利用者の失敗談としてよく聞かれます。
このように手数料コストがかさみ、リターンを帳消しにしてしまうのは典型的な失敗パターンの一つです。
相場下落で大きな損失を抱えてしまった
相場の急落局面で大きな損失を抱えてしまったケースです。
ロボアドバイザーのポートフォリオは分散されているとはいえ株式も含むため、市場全体が下落した局面では資産価値も大きく目減りする可能性があります。自動運用だからといって暴落時に勝手に損失を回避してくれるわけではなく、市場下落の影響はそのまま被ることになるのです。
実際、SNS上では「損失が出て不安だ」といった声も見られます。例えば景気後退で株式市場が20%下落した際には、運用資産も二桁%以上の評価損が出ることがあり、タイミング悪く始めた人ほど大きな損失を抱えがちです。
さらに、慌てて底値で解約してしまえば損失が確定し、投資が失敗に終わってしまいます。
他の投資と比べてリターンが物足りなかった
他の投資方法に比べてリターンが物足りなかったケースです。ロボアドバイザーで数年間運用したものの、思ったほど資産が増えず、他の投資を選んでいたほうが良かったと感じてしまった例と言えます。
例えばインデックスファンドに自分で投資していた場合や、より高利回りの投資商品を選んでいた場合と比べて、ロボアドバイザーの利回りが見劣りしたために期待外れに終わってしまいました。「普通に運用しても同じリターンが得られたのでは?」と感じるケースも実際にあります。
身近な知人が個別株や仮想通貨などで大きな利益を上げているのを目にし、自分の成果が物足りなく思えて後悔するといった失敗パターンもよく見られます。
ロボアドバイザーを利用することで得られるメリットとは?

少額から気軽に始められる
ロボアドバイザーの最大のメリットは、少額から手軽に始められる点です。まとまった資金がなくても、最低投資金額が数万円〜数百円程度に設定されているサービスもあり、ハードルが低くなっています。
また、口座開設から運用開始までもオンラインで完結し、数分の簡単な質問に答えてリスク許容度を診断するだけでポートフォリオが提案されます。自分で銘柄選びや資産配分を考える必要がないため、専門知識がなくてもスムーズにスタートでき、投資初心者にとって大きな利点と言えるでしょう。
自動で運用できるため手間がかからない
ロボアドバイザーは運用をすべて自動化してくれるため、投資開始後の手間がほとんどかからない点も大きなメリットです。市場の値動きに応じた資産配分の見直し(リバランス)もロボアドが自動で行ってくれるため、利用者自身が売買のタイミングを判断したりポートフォリオを調整したりする必要がありません。
感情に左右されず機械的に運用してくれるので、相場変動に一喜一憂しがちな人でも安心して長期運用を続けやすいでしょう。忙しい人や資産運用に時間を割けない人にとって、ほったらかしで資産運用できる仕組みは大きな魅力と言えます。
このように自動運用によって投資家の手間と精神的負担を軽減してくれる点は、大きな利点の一つです。
投資初心者でも分散投資の仕組みを体験できる
ロボアドバイザーの大きな魅力の一つは、初心者でも分散投資の仕組みを体験できる点です。
通常、株式や債券、不動産などに幅広く投資するには知識やまとまった資金が必要ですが、ロボアドバイザーなら少額からでも自動で国内外の資産に分散投資できます。投資先は複数のETFを組み合わせたポートフォリオで構成されており、結果的に数百銘柄規模へ資金が分散される仕組みです。
自分で一から銘柄を選んで組み合わせる手間を省き、効率的に投資効果を得られるため、経験の少ない人でも安心して運用を始めやすいでしょう。こうした仕組みを通じて、投資の基本である「卵を一つのカゴに盛るな」というリスク分散の考え方を実践できる点は、大きな学びとなります。
ロボアドバイザーを選ぶときの注意点
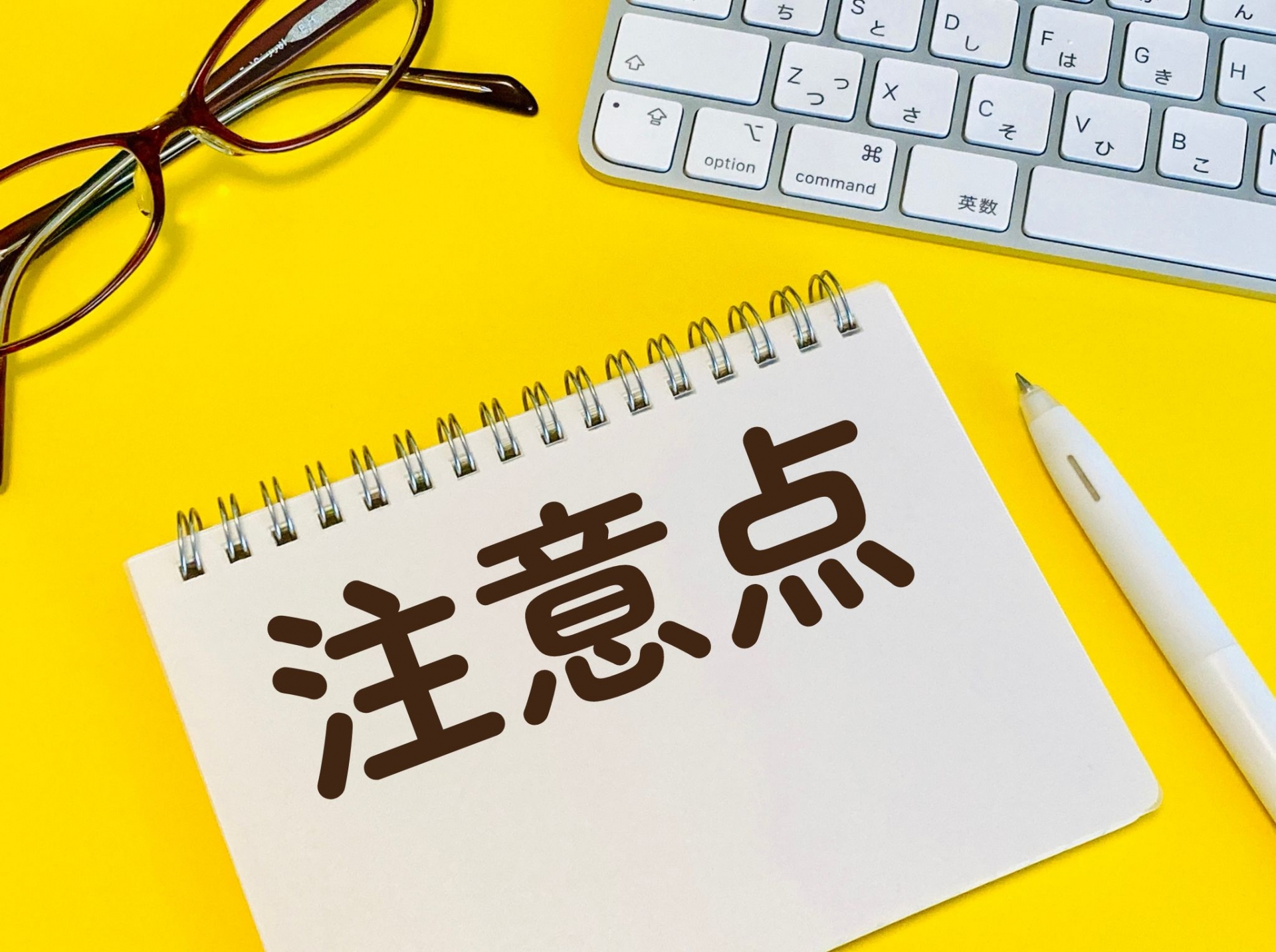
手数料やサービス内容を必ず比較する
ロボアドバイザーを選ぶ際は、各サービスの手数料や提供する機能を必ず比較しましょう。他社と比べて手数料が低いかどうか、運用成績や対応している機能(自動積立やNISA対応の有無など)をチェックすることが重要です。
年間手数料は0.5〜1%前後と差があり、1%を切る低コストのサービスも存在します。わずかな手数料の差でも長期では大きな差となるため、なるべくコストの安いロボアドを選ぶことで手数料負けのリスクを減らせます。
また、NISAなど非課税制度に対応しているかも確認し、自分の運用目的を満たすサービスを選定しましょう。
事前の比較検討を怠らないことが、ロボアドバイザー選びで失敗しないための第一歩です。
利用する目的を明確にしてから選ぶ
ロボアドバイザーを選ぶ前に、自分が何のために投資するのか目的を明確にしましょう。長期的にコツコツ資産形成したいのか、それとも短期間で大きな利益を狙いたいのかによって、適切な選択肢は異なります。
ロボアドバイザーは基本的に10年以上の長期・積立・分散投資でゆるやかに資産を増やすことを前提としたサービスです。したがって、「短期間で大きく儲けたい」という目的には向いていません。
もし数ヶ月〜数年で高リターンを求めるなら、ロボアド以外の高リスク商品(株式個別銘柄やFXなど)を検討すべきでしょう。ただしその場合、損失リスクも格段に高くなる点に留意が必要です。
自分の投資目的とロボアドの特性が合致しているかを確認してから利用することが、失敗を避けるコツです。
期待値を持ちすぎずリスクも理解しておく
ロボアドバイザー利用にあたっては、過度な期待を持たずリスクも十分理解しておくことが大切です。「自動運用だから安全に儲かる」と思い込みすぎるのは禁物で、元本割れの可能性も常にあることを認識しましょう。
実際、ロボアドバイザーでも市場環境次第では一時的にマイナスになることがあり、保証された利益はありません。期待値を高く持ちすぎると、思ったほど増えなかったときに失望してしまいがちです。長期的に見れば緩やかに資産が増える可能性はありますが、短期で大儲けできるものではなく、損失も含めて想定内にしておく必要があります。
最初から適度に現実的な見通しを持ち、損失リスクも許容範囲内か確認したうえで利用することで、失敗や後悔を防げるでしょう。
リスクと失敗を避けるための分散投資という考え方
株式や債券など複数の資産に分けてリスクを抑える
投資でリスクと失敗を避ける基本の一つに、「分散投資」という考え方があります。株式や債券、不動産、現金など複数の資産に資金を分散して配分することで、一部の資産が値下がりしても他の資産でカバーでき、ポートフォリオ全体のリスクを抑える効果が期待できます。
例えば株式100%で運用するよりも、株式と債券に資金を分けておけば、株式市場が暴落しても債券が価値を保ち損失を緩和するといった具合です。どの資産も一度に同じように値下がりする可能性は低いため、資産を分散させておくことで大きな失敗を防ぎ、安定した運用につながります。
「卵を一つのカゴに盛るな」という格言の通り、一点集中ではなく複数のカゴ(資産)に卵(資金)を分けるのが鉄則です。
ロボアドバイザー以外の投資も組み合わせて安定を目指す
分散投資は同じサービス内だけでなく、異なる投資手段を組み合わせることでも効果を発揮します。ロボアドバイザー以外の投資商品も併用することで、さらなる安定を目指せるでしょう。
例えば、株式中心のロボアドバイザー運用に加えて、値動きの連動性が低い不動産系の投資(不動産クラウドファンディングなど)や預金・債券をポートフォリオに取り入れると、株式市場が低迷した際にも別の収益源でポートフォリオ全体の安定性を保つことができます。
国際分散投資だけでなく、異なるリスク特性を持つ資産クラスを組み合わせることで、より堅実な資産運用が可能となるでしょう。要するに、ロボアド一択ではなく複数の投資を分散活用することが、リスク低減と安定運用の鍵と言えます。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】ロボアドバイザーに関するよくある質問

ロボアドバイザーは本当に儲かるの?
短期間で大きな利益を出すのは難しく、利回りは年2〜5%程度にとどまるケースが一般的です。
ロボアドは長期でコツコツ資産形成する設計のため、株式市場の成長を背景にプラスの成果を期待できますが、相場環境次第では一時的に含み損を抱えることもあります。過度に「大きく儲かる」と過信せず、長期的な運用で安定したリターンを目指すのが基本です。
ロボアドバイザーは安全な投資先なの?
完全に安全な投資とは言えず、元本保証もありません。
国際分散投資で極端な損失リスクは抑えられますが、市場が大きく下落すれば資産価値も目減りします。相場急落局面では二桁以上の評価損が出る場合もあります。ただしFXや信用取引のように元本を超える負債を抱える心配はなく、損失は投資元本の範囲内に収まります。
ロボアドバイザーと他の投資はどちらがいい?
目的やスタイルによって異なり、一概にどちらが良いとは言えません。
手間をかけず自動で分散投資したい人にはロボアドが便利です。一方、コストを抑えて自分で商品を選びたい人には、低コストのインデックス投資や個別株投資のほうがリターンを狙える場合があります。経験や許容リスクに合わせて適した方法を選びましょう。
まとめ|ロボアドバイザーはやめとけ?投資で失敗しないために
ロボアドバイザーは便利で始めやすい一方、手数料の高さや利回りの物足りなさ、柔軟性の欠如などから「やめとけ」と言われる理由も明確です。
実際に期待外れの成果や損失を経験する人も少なくありません。失敗を避けるには、手数料やサービス内容を比較し、リスクを理解したうえで長期分散投資を意識することが重要です。
ロボアドバイザーに頼るだけでなく、自分に合った投資手段を組み合わせて運用することで、堅実な資産形成につなげましょう。
参考元
・金融広報中央委員会「資産形成ハンドブック」
・全国銀行協会「その取引、いくら手数料がかかるか、知っていますか?」
・金融庁「NISAを利用する皆さまへ」
・国税庁「No.5433 中小企業投資促進税制」
・金融庁「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」