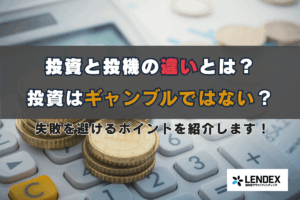老後資金の準備方法として注目を集める「iDeCo(個人型確定拠出年金)」ですが、一方で「おすすめしない」という声も少なくありません。
制度として税制優遇が大きいのは確かですが、誰にとってもメリットばかりとは限らないのです。掛金の負担や長期拘束、運用リスクなどを理解せずに始めてしまうと、期待していた効果を得られない可能性もあります。
では、なぜiDeCoが「おすすめしない」と言われるのでしょうか。
本記事ではその理由や注意点を整理し、逆にどのような人には向いているのか、そして他の投資制度との比較も交えて解説します。読み進めることで、自分にとってiDeCoが本当に適した選択肢なのかを判断できるようになるはずです。
idecoはおすすめしない?結論からわかりやすく解説

長期で縛られる投資は柔軟性に欠ける
iDeCoは加入すると資金を原則60歳まで引き出せず、長期間にわたり運用を継続する必要があります。これはiDeCoの大きなデメリットの一つです。
このため、ライフステージの変化や急な出費に対応しづらく、資金の流動性という面で柔軟性に欠けると言えます。例えば途中で掛金の増減をしたくても、年1回しか変更できず手続きも必要になるなど、他の投資制度に比べて自由度が低く感じられます。
また、一度始めると途中解約ができないため、将来の収入変動や優先順位の変化にも対応しづらい精神的な負担もあります。実際、貯蓄や個人年金保険などと比べてもiDeCoの資産流動性は低いと指摘されています。
他の制度や商品と比べてデメリットが目立つ
一般に、iDeCoは同じ税制優遇制度のNISAと比べて制約が多いと言われます。NISAは運用益が非課税でいつでも換金できる一方、iDeCoは原則60歳まで引き出せません。
つまり、制度設計上iDeCoは老後資産形成を目的とし、NISAはより幅広いライフプランに対応できる仕組みと言えます。また、iDeCoは自分で商品を選んで運用する必要があり、元本保証がない商品も多いため、初心者にとっては難しく感じられるケースもあります。
このように制度の性質上、他の制度や貯蓄商品と比較するとデメリットが際立つことがあります。
idecoをおすすめしないと言われる理由は?
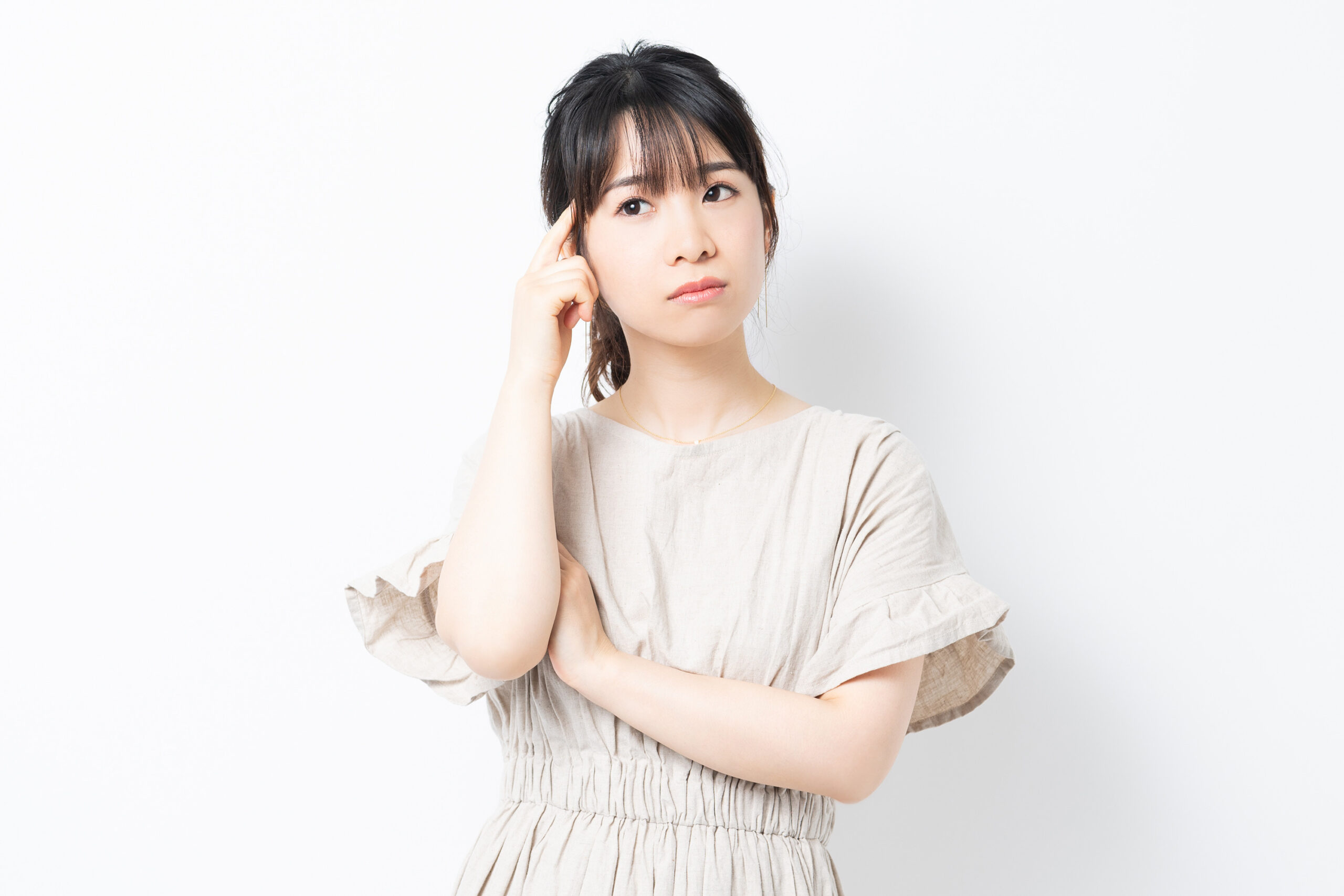
原則60歳まで引き出せない制約がある
iDeCo最大の制約は、原則60歳まで積み立てた資産を受け取れない点です。法律で定められており、脱退(解約)して途中で資金を引き出すことは基本的にできません。
制度上、わずかな例外として脱退一時金の制度もありますが、対象となるケース(掛金拠出期間が短い等)はごく限られており、基本的には60歳まで資金は動かせないと考えるべきです。
たとえ急な出費やライフイベントがあっても、iDeCo口座の資金は60歳になるまでロックされた状態となります。極端な例では、30歳で加入を始めれば最低でも30年間は引き出せない計算です。
このため「自由に使えないお金」になってしまい、流動性の低さがおすすめしない理由として真っ先に挙げられます。
掛金が収入やライフプランに合わないと負担になる
毎月拠出する掛金が自分の収入や家計に見合っていない場合、iDeCoはかえって負担になり得ます。
iDeCoでは原則として毎月掛金を払い続ける必要がありますが、収入が減少したり支出が増えたりして掛金の捻出が厳しくなると、家計を圧迫しかねません。例えば毎月1万円の拠出でも、想定外の出費が重なったり収入が減ったりすれば重荷に感じるでしょう。
掛金の変更は年1回までと制限されているため、柔軟に減額して調整することも簡単ではありません。実際、失業や転職、病気などで掛金拠出が困難になってしまった場合は、掛金の一時停止という選択も可能です。しかしその間も口座管理手数料や運用商品の信託報酬が積立資産から差し引かれていきます。
そのため、掛金設定が自身の収支バランスに合わないと、節税メリット以上に生活面での負担を感じてしまうでしょう。
手数料が積み重なり利益を圧迫する
iDeCoでは口座管理に関わる各種手数料が発生し、長期間では運用益を目減りさせる要因となります。
加入時には国民年金基金連合会への登録手数料2,829円がかかり、さらに毎月の掛金拠出ごとに105円、事務委託先金融機関の管理手数料(概ね66円程度)が差し引かれます。つまり、合計で毎月約171円、年間にすると約2,052円が固定的に必要です。
30年間積み立てを続けた場合、手数料だけで 2,829円+(171円×12か月×30年=61,560円)=約64,389円 となり、数万円規模の負担になります。拠出額が少ない場合は特に手数料比率が高くなり、実質利回りを押し下げる要因となります。
職業別の掛金に上限がある
iDeCoの掛金には職業・加入状況に応じた上限が設定されており、人によって拠出できる額が異なります。
例えば自営業者等の第1号被保険者は月額68,000円まで拠出できますが、会社員の場合は企業年金の有無によって月20,000~23,000円が上限となり、専業主婦(第3号被保険者)も23,000円が上限です。公務員を含む企業年金加入者は上限が20,000円と比較的低く抑えられており、老後資産をもっと積み立てたいと考えても制約があります。
また、転職等で職業区分が変われば上限額も変動するため、その都度掛金の見直し手続きが必要になります。つまり、職業によっては十分な金額を拠出できず、他の制度に比べて物足りなさを感じる場合があるのです。
変更の手続きが煩雑
iDeCoに関する各種手続きの煩雑さも、利用者にとってハードルとなります。掛金額の変更ひとつとっても、拠出限度額の範囲内で年1回しか変更できず、所定の届出用紙を取り寄せて提出する必要があります。
また、転職や退職で加入者の種別(第1号・第2号など)が変わった際にも、掛金上限の変更に応じて届出を行わないと掛金の口座振替が一時停止となる場合があります。金融機関の変更や運用商品配分の見直しなども含め、iDeCoの制度上は様々な手続きが多く、インターネット上で簡単に完結しないケースも少なくありません。
これらの手続きをこなすのに手間と時間を要するため、忙しい人にとっては大きな負担となりがちです。こうした手間の多さが「煩雑」でおすすめできない理由と言われています。
idecoが向いている人

安定した収入があり毎月の掛金を継続できる人
毎月安定した収入があり、掛金を長期間継続できる人はiDeCoに向いています。
掛金が全額所得控除になる節税メリットは、所得税や住民税を支払っている人ほど大きく、安定収入がある人はiDeCoの恩恵を最大限に享受できるからです。例えば所得税率20%、住民税率10%の人が毎月1万円を拠出すると、年間約3.6万円もの税負担軽減効果があります。
また、無理なく掛金を拠出し続けられる人なら運用期間を長く確保でき、非課税運用による複利効果も十分に生かせるでしょう。一方、課税所得のない人は掛金の所得控除を受けられないため、一定以上の収入がある人こそiDeCoの活用に適していると言えます。
老後資金を長期でコツコツ積み立てたい人
老後のために長期でコツコツ資産形成したい人にもiDeCoは適しています。iDeCoは老後資産形成に適した制度と位置づけられており、運用期間が長いほど複利の効果で資産が増えやすくなります。
毎月少額ずつでも着実に積み立てていけば、数十年後の老後にまとまった資金を用意できるでしょう。途中で引き出せないことは裏を返せば老後まで貯蓄を取り崩さない強制力にもなり、計画的な資産形成に役立ちます。
実際、日本は「人生100年時代」と言われ平均寿命が伸びていますが、iDeCoなら若いうちから長期運用で老後資金を準備するのに適した手段と言えます。まさに長期的視野で資産を準備したい人にぴったりの制度です。
節税メリットを最大限に活かしたい人
節税メリットを最大限に活かしたい人にもiDeCoはおすすめです。
iDeCoは掛金拠出時に全額所得控除が受けられ、運用益も非課税、さらに受取時も退職所得控除や公的年金等控除が適用されるため、他の制度と比べても圧倒的に税優遇が手厚いです。言い換えれば、毎年の所得税・住民税負担を減らしつつ老後資産を形成できる点で、節税を重視する人には理想的な仕組みと言えるでしょう。
例えば所得税・住民税の合計税率が30%の人が月2万円を拠出すれば、年間で約7.2万円の税負担軽減となり、30年継続すれば単純計算で216万円もの節税効果が得られます。
このように、税金を抑えて効率良く資産形成したい人にはiDeCoほど適した制度はないでしょう。
idecoが向いていない人

収入や生活費が不安定で急な出費が多い人
収入が不安定だったり、急な出費の可能性が高かったりする人はiDeCoに向いていないと言えます。
原則60歳まで資産を引き出せないため、いざというときにiDeCoの積立金を生活費に充てることができません。例えば、収入が月々大きく変動するフリーランスや、子どもの学費など老後前にまとまった出費を控えている人は注意が必要です。
生活に余裕がなく途中で積立を止める可能性がある人や、老後前に資金を使う必要がありそうな人は、iDeCo以外の柔軟な資産運用法を検討すべきでしょう。投資の自由度や流動性を重視する人も、制約の多いiDeCoではストレスを感じる可能性があります。
こうした条件に当てはまる人にとって、iDeCoはメリットよりデメリットが上回ると言えます。
途中で資金を引き出す可能性がある人
将来的に60歳前に積立資金を使う可能性がある人にはiDeCoは不向きです。
iDeCoは基本的に途中で解約できず60歳になる前に資産を引き出せないため、教育資金や住宅購入資金などで一定額を取り崩す必要が生じても対応できません。例えば子どもの大学費用やマイホーム購入の頭金など、老後前にまとまった支出を予定している場合、その資金をiDeCoで積み立てるのは適切ではありません。
貯蓄や他の投資商品であれば必要なタイミングで換金できますが、iDeCoでは資産の流動性が極めて低く、途中で資金を引き出す可能性がある人は避けた方が良いでしょう。事前に予想できる大きな資金需要がある人は、iDeCo以外の方法で資金準備をするほうが安心です。
投資の自由度や柔軟性を重視する人
投資の自由度や柔軟性を重視する人もiDeCoには不向きです。iDeCoでは運営管理機関が選定した限られた商品(預金・保険・投信等)の中から運用商品を選ぶ必要があり、自分で投資対象を自由に選択することはできません。
また、掛金の拠出も原則として毎月一定額を積み立てる仕組みで、NISAのように好きなタイミングで資金を投じたり引き出したりする自由はありません。運用面でも、銘柄選択や投資タイミングの裁量が限定されるため、自分の裁量で柔軟に資産運用したい人にとってiDeCoは物足りなく感じるでしょう。
資金拘束期間が長く手続き面も含め制約の多いiDeCoは、投資の自由度を最優先する人にはおすすめできない制度です。
idecoで注意すべきデメリット

途中解約ができず資金が固定されてしまう
iDeCoは一度加入すると、原則60歳になるまで積み立て資産を引き出せない制度です。
途中解約は制度上認められておらず、脱退一時金の支給も要件が厳しく限定的で、一般的には利用できないと考えるべきでしょう。そのため、教育費や住宅購入資金など老後以前に必要となる出費には充てられません。
資金を動かせないことは、計画的に老後資産を形成する上でメリットとも言えますが、同時に柔軟性を欠くリスクにもつながります。特に若い世代では、ライフイベントに備えた流動性のある資金と切り分けて考える必要があります。
つまり、iDeCoの資金は「60歳まで使えない長期専用の貯蓄」と割り切って取り組むことが重要です。
運用次第で元本割れのリスクがある
iDeCoでは、運用商品として投資信託や保険商品などを自分で選択する必要があります。元本保証型商品もありますが、期待できる利回りは低いため、資産形成効果を狙う場合は値動きのある商品を組み込むのが一般的です。
その場合、市場環境によっては評価額が下がり、元本割れを起こす可能性があります。例えば、株式市場の急落や債券金利の急変などにより、一時的に運用資産が目減りすることは珍しくありません。長期運用で回復するケースも多いですが、60歳以降の受取時点で市場環境が悪ければ、当初想定したリターンを得られない場合もあります。
つまり、税制優遇があっても「元本保証ではない」ことを理解した上で、リスク許容度に応じた商品選びが求められます。
投資判断を誤ると期待したリターンを得られない可能性がある
iDeCoは自ら運用商品を選び、配分を決める「自己責任型」の制度です。商品ラインアップは金融機関ごとに異なり、国内外の株式・債券型投信、REIT、保険商品などが用意されています。
しかし、金融知識が十分でないまま高リスク商品に偏らせたり、逆に低リスクに偏りすぎたりすると、効率的な運用ができず期待した成果を得られません。また、長期投資では途中の市場変動に不安を感じ、値下がり局面で解約やスイッチングを行ってしまうと、結果的に損失を固定化するリスクもあります。
制度上の節税メリットを活かしつつ成果を得るためには、分散投資や定期的な配分見直しなどの基本を守ることが重要です。投資判断を誤れば、節税効果以上に運用成果が乏しくなる点には注意が必要です。
おすすめしないと言われる中でも知っておきたいidecoのメリット

掛金が全額所得控除となり節税効果がある
iDeCoの最大の特徴は、掛金が全額所得控除の対象になる点です。
これは、毎月拠出した金額がそのまま課税所得から差し引かれる仕組みで、所得税と住民税の両方を軽減できます。例えば課税所得400万円、税率20%の人が月2万円を拠出した場合、年間で約4.8万円の税負担が減少する計算です。
30年間続ければ単純計算で約144万円の節税効果となり、これだけでも大きな資産形成効果があります。給与所得者にとっては「実質的に掛金の一部を税金から取り戻している」感覚で取り組めるため、長期で続けるほど恩恵が大きくなります。
安定した収入がある人にとって、この節税メリットは無視できない強みです。
運用益が非課税で複利効果を得やすい
通常、投資信託や株式投資で得られる運用益には20.315%の税金がかかります。しかしiDeCoでは、運用で得られた利益がすべて非課税です。
このため、運用で得た利益をそのまま再投資でき、長期にわたり複利効果を最大限に享受できます。例えば年利3%で運用し、20年間積み立てを続けた場合、課税口座と比べて非課税口座では数十万円単位で資産額に差が出ます。
特にiDeCoは老後資金を目的に長期で積み立てる制度のため、この非課税メリットが複利成長を後押しします。長期で資産を増やすという点では、NISA以上に恩恵を受けやすいケースもあるでしょう。
税負担を気にせず効率的に運用できる点は、大きな利点です。
受け取り時にも税制優遇を受けられる
iDeCoは掛金拠出時と運用中だけでなく、受け取り時にも税制優遇が用意されています。
具体的には、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」、年金形式で受け取る場合は「公的年金等控除」が適用されます。たとえば20年以上勤務して退職金と合わせて受け取る場合、退職所得控除額が大きくなるため、非課税枠を広く活用できます。
年金形式で受け取る場合も、公的年金と合算した金額の一部が控除対象となり、課税所得を抑えることが可能です。
このように「拠出・運用・受取」のすべてで税制優遇がある点は、他の制度にない強みです。長期的に見れば、節税総額は数百万円規模に達するケースもあり、老後資金形成の大きな後押しになります。
将来のために知っておきたい分散投資という考え方
ひとつの商品に頼ると将来のリスクが大きくなる
将来の資産形成を考える上で、一つの商品だけに頼るのはリスクが高くなります。
俗に「卵を一つのカゴに盛るな」という格言があるように、資金を一つの資産や商品に集中させてしまうと、それが損失を出した際に一度に大きなダメージを受けてしまいます。例えば全資産を株式一種類に投資していた場合、市場暴落で一度に資産が半減する恐れがあります。
しかし、債券や預金、不動産など値動きの異なる資産と組み合わせておけば、一つの資産が下落しても他の資産で損失を補うことができ、リターンの安定度も増します。iDeCoに限らず、将来のための資産は特定の制度や商品だけに偏らず、複数の手段に分散する方が安全と言えます。
資産を分けて持つことで安心につながる
資産を分散して持つことは将来の安心につながります。複数の資産や運用手段にお金を振り分けておけば、一つが不調でも他が補えるため、資産全体として大きな目減りを防ぎやすくなります。
例えば株式だけでなく債券や現金も一定割合保有していれば、株式市場が低迷しても債券からの利息や現金部分でカバーでき、生活への影響を和らげられます。金融環境の変化にも柔軟に対応でき、精神的な負担も軽減されるでしょう。
このように、iDeCoで老後資金を用意しつつ、他の制度(NISAや預貯金、保険など)も組み合わせることで、より堅実で安心感のある資産形成が可能になります。資産を分けて持つことでリスクを減らし、予測不能な将来に備える安心材料となるのです。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】idecoを検討する人のよくある質問

idecoは本当にやらない方がいいの?
人によります。収入が安定していて長期運用できる人には税制メリットも大きく、iDeCoは有益です。
一方、収入が不安定で途中で資金が必要になりそうな人には、無理に利用しない方がいいでしょう(自分に合う場合のみ検討)。例えば、税率30%の人はiDeCoで毎年約3~6万円の節税も期待できます。
ideco以外に初心者が選びやすい投資方法はある?
はい、あります。初心者には積立NISAなど少額から始めやすく、途中換金も自由な制度が選びやすいでしょう。
例えば、毎月1万円ずつ投資信託を買う積立NISAなら非課税で運用でき、必要なときに出金も可能です。また、ポイント投資など預貯金感覚で始められるサービスも増えており、まずは無理のない範囲で経験を積むのがおすすめです。
idecoはデメリットしかないって本当?
いいえ、誤解です。iDeCoには途中引き出せないなどデメリットもありますが、同時に掛金全額所得控除や運用益非課税など大きなメリットも備えています。
例えば、税負担軽減により毎年数万円が戻ってくる効果もあり、上手に活用すれば将来の資産形成に大きく寄与します。要はデメリットとメリットを理解した上で、自分に合うか判断することが大切です。
まとめ|idecoをおすすめしない理由と投資判断のポイント
iDeCoをおすすめしないと言われる主な理由は、60歳まで引き出せない流動性の低さや手数料負担、元本割れリスクなどです。しかし、掛金全額所得控除による年間数万円規模の税負担軽減や、非課税運用による複利効果など資産形成効果は非常に大きく、自身の収入状況や資金ニーズに合致すれば有力な選択肢となります。
メリット・デメリットを正しく理解し、他の制度とも比較しながら賢く活用できるかどうかを判断することが重要です。
参考元
・厚生労働省「iDeCo(個人型確定拠出年金)の概要」
・国税庁「No.1135 小規模企業共済等掛金控除」
・厚生労働省「iDeCoを始めとした私的年金の現状と課題」
・国民年金基金連合会「iDeCo公式ポータルサイト」