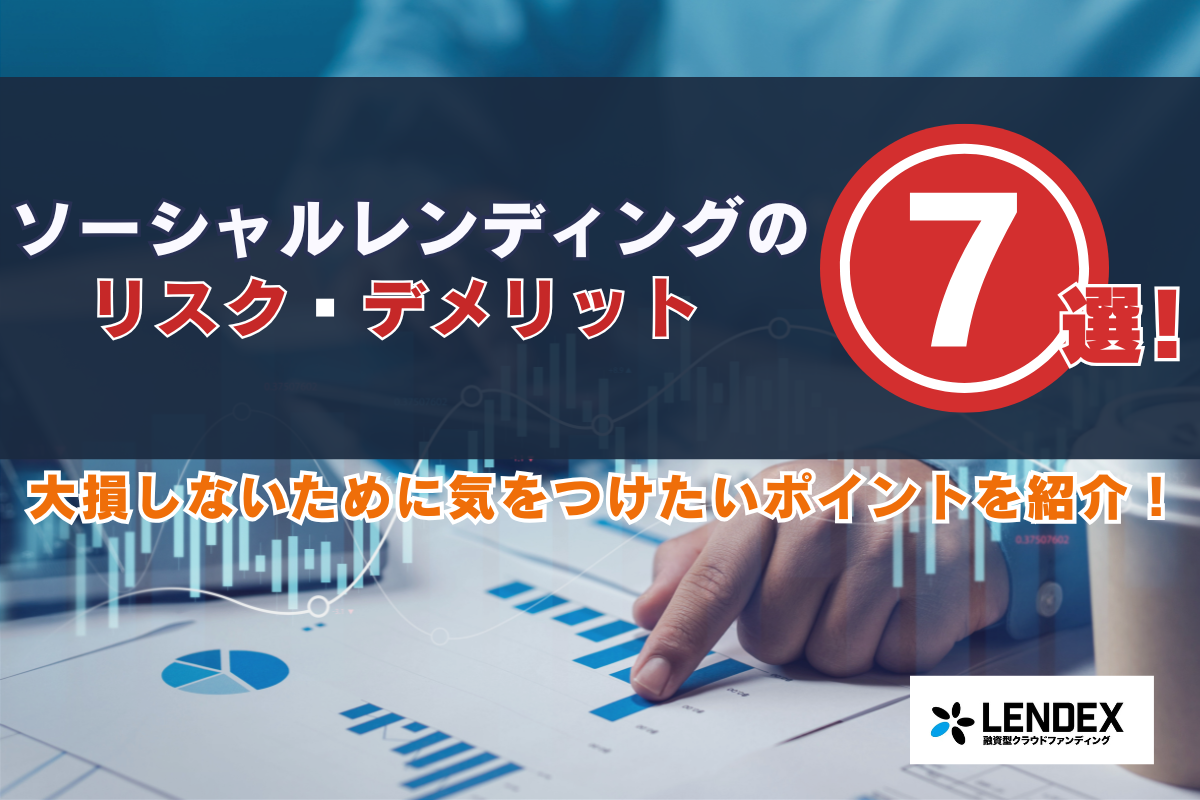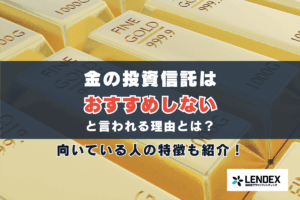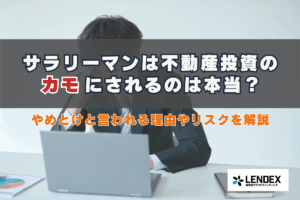ソーシャルレンディングは高い利回りが魅力の反面、「危ない」「大損した」という声も聞かれる投資手法です。実際に過去には投資資金が回収できなくなるケースも発生しており、安全に運用するためにはリスクへの十分な理解と対策が欠かせません。
本記事では、ソーシャルレンディングの仕組みや7つのリスク・デメリットを解説し、大損しないためのポイントを紹介します。
ソーシャルレンディングとは? 仕組みを簡単解説

お金を貸したい人と借りたい人をつなぐ仕組み
ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)は、インターネットを通じて「お金を借りたい企業や個人(借り手)」と「お金を貸して資産運用したい個人投資家(貸し手)」をマッチングする新しい金融サービスです。
複数の投資家から集めた資金を用いて事業者が借り手に融資を行い、借り手からの返済・利息を投資家に分配する仕組みになっています。銀行などの金融機関を介さず直接資金ニーズを満たせる点が特徴で、借り手にとっては銀行融資より柔軟な資金調達手段として利用が広がっています。
近年は国内でも多数のサービスが登場し、個人の新たな資産運用手段として注目されています。
事業者が間に入り「融資型クラウドファンディング」を運営
ソーシャルレンディングでは、運営会社(事業者)が投資家と借り手の間に入ってファンドの組成・運営を行います。
運営会社は融資先企業の審査やファンドの募集、貸付実行、返済金の回収・分配といった重要な役割を担います。このため、運営会社の信頼性と審査能力が投資の安全性に直結することになります。実際に日本国内では、運営会社が投資家から集めた資金を不適切に流用したり虚偽の説明で勧誘するといった不正が発覚し、金融庁から行政処分を受けた事例もあります。
ソーシャルレンディングを利用する際は、事業者が金融商品取引業の登録を受けているか確認するとともに、提供情報を精査して信頼できる会社かどうかを見極めることが重要です。
投資家は少額から参加でき、利息収入を得られる
ソーシャルレンディングの魅力の一つは、投資家が少額から手軽に参加できることです。株式投資や不動産投資と比べても最低投資金額が低く設定されているため、初心者でも始めやすい傾向にあります。
出資したファンドに応じて利息収入(分配金)を定期的に受け取ることができ、満期時には元本の償還が行われます。また、一度出資すれば満期までは配当を受け取るだけで基本的に手間がかからない「ほったらかし投資」が可能な点も魅力です。
特に銀行預金の超低金利と比べると年利5~10%前後の利回りを期待できるため、効率的に資産を増やせる手段として注目されています。ただし、その裏にあるリスクについてもしっかり理解しておきましょう。
ソーシャルレンディングのリスクとは

元本保証がないため損失が出る可能性がある
ソーシャルレンディングの投資には元本保証がありません。銀行預金とは異なり、貸付先からの返済が滞った場合などには投資元本が減額されたり、最悪の場合は全額戻らないリスクがあります。
実際に2017~2018年頃には複数の業者で貸し倒れが発生し、投資家が数十億円規模の元本を回収できなくなる事態も起きました。銀行預金なら預金保険制度による元本保護がありますが、ソーシャルレンディングにはそうしたセーフティネットがない点にも注意が必要です。
損失リスクが現実にある以上、預金のように安全な商品ではないことを十分に理解しておく必要があります。投資経験が浅い方ほど、このリスクを軽視しないことが大切です。
返済遅延や貸倒れが起きるケースもある
借り手の経営悪化やプロジェクトの失敗により、返済が期日通りになされず延滞が発生したり、最終的に貸倒れ(デフォルト)となってしまうケースもゼロではありません。
返済の遅延が生じた場合、予定されていた利息や元本の支払いが滞り、配当金を受け取れないまま長期間資金が拘束される恐れがあります。実際に2018年には複数のソーシャルレンディング会社で大規模な返済遅延が発生し、投資家への元本償還や配当が止まる事態となりました。
貸倒れに至れば出資金の一部または全額が戻らない可能性もあるため、利回りばかりに注目せず最悪のシナリオも想定しておく必要があります。
運営会社の信頼性が投資の成否を左右する
前述のように、運営会社(プラットフォーム)の信用力はソーシャルレンディング投資の成否を左右する重要なポイントです。
運営会社が健全に事業を行っていれば多くの案件で安定した運用が期待できますが、もし運営会社自体が経営破綻したり不正行為を行った場合、投資家の資金は大きな危険にさらされます。たとえ金融庁に登録済みの業者であっても、行政がその業者の経営健全性を保証するものではないため、投資家自身が事業者の実績や財務状況を確認し、信頼性を見極める必要があります。
過去には高利回りを謳って投資資金を集めながら、実際には融資先を自社グループ企業に回すなど杜撰な運用で巨額の延滞を出し、最終的に事業停止に至った業者も存在します。運営会社リスクを軽視せず、信頼できるサービス選びを心掛けましょう。
ソーシャルレンディングの7つのデメリット
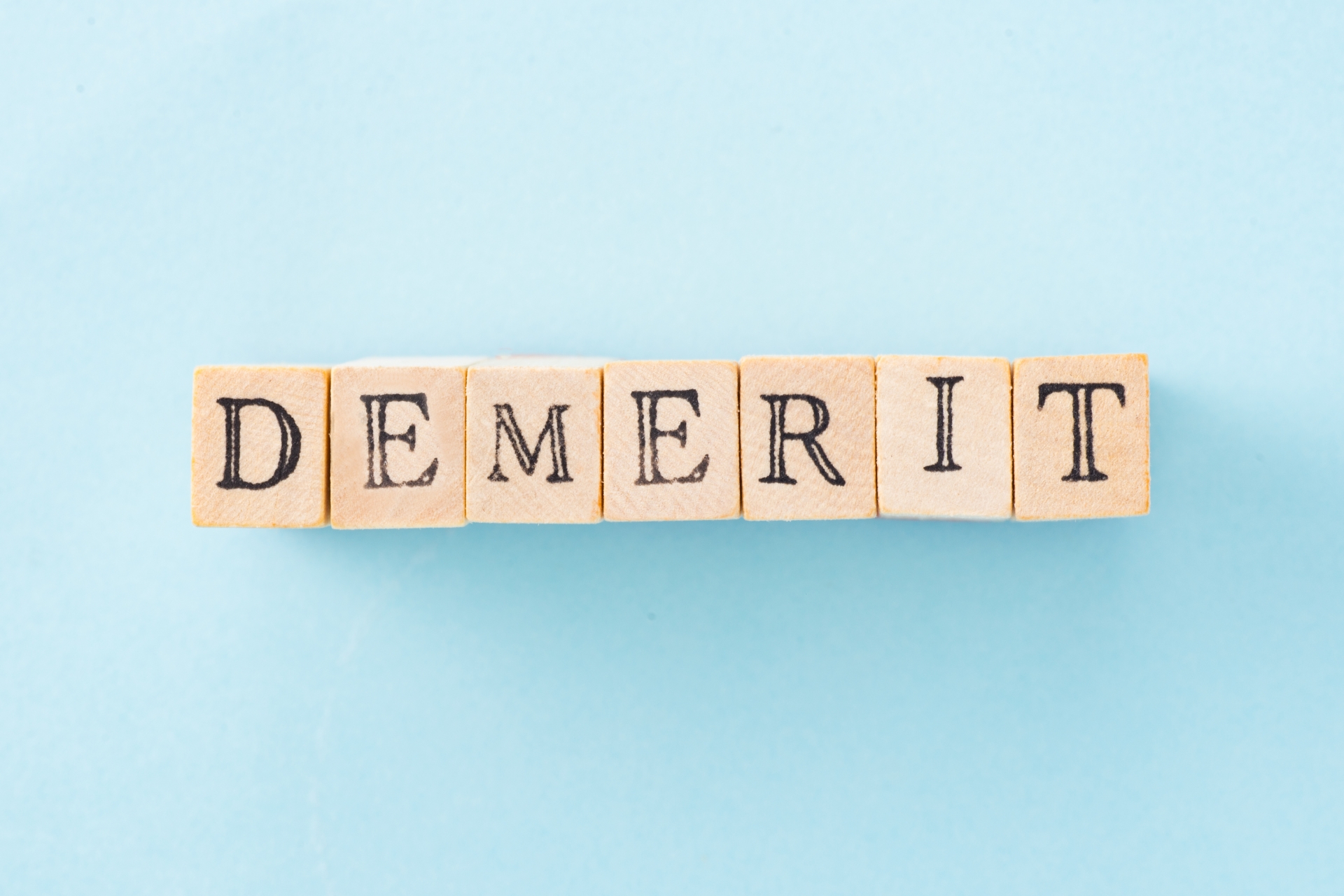
元本割れの可能性がある
上述の通り、ソーシャルレンディングには元本保証がなく、融資先の返済不能などによって元本割れ(受け取る金額が投資額を下回る)となる可能性があります。
たとえば融資先企業が倒産すれば、貸し付けた元本の一部または全額を回収できず損失が確定します。特に不動産開発案件などでは、予定していた売上が得られないと返済原資が枯渇してしまい、投資家が損失を被るリスクが高まります。
預けたお金が目減りする可能性がある点を十分認識しておきましょう。投資経験が浅い方ほど、このリスクを軽視しないことが大切です。
貸倒れ・延滞が起こる場合がある
貸付先企業の業績不振やトラブルにより、返済遅延や貸倒れが起こるケースもあります。
貸倒れが発生すれば、利息はおろか元本も戻らなくなる危険があります。また、返済そのものは実行されたものの当初の予定より遅れて行われる場合(延滞)もあり、その間の利息が支払われなかったり運用期間が延長されることがあります。
過去に行政処分を受けた業者の例を見ても、高い利回りを提示していた案件で大規模な返済遅延が発生するケースが多く報告されています。利回りの高さにつられて投資した案件で延滞・貸倒れが起き、結局大きな損失を被る可能性がある点に注意が必要です。
原則として途中解約ができない
ソーシャルレンディングは一度出資すると、原則として満期まで途中解約(出金)ができません。
株式や投資信託のように市場で売却して現金化することができず、運用期間中は資金が拘束される「流動性リスク」があります。急に現金が必要になっても投資資金を引き出せないため、流動性が低い点は大きなデメリットと言えるでしょう。
運用期間はファンドによって数ヶ月から数年と様々ですが、その間は基本的に資金を動かせません。そのため、生活費や近い将来に必要になるお金を投じることは避け、余裕資金で運用することが重要です。
一度投資した資金は運用終了まで動かせないものと割り切る必要があります。
事業者の不正や倒産リスクがある
ソーシャルレンディング業者(事業者)自体の不正行為や経営破綻リスクも考慮しなければなりません。運営会社が倒産した場合、投資中のファンドの償還業務が滞り、最悪の場合投資資金が戻らなくなる恐れがあります。
日本の規制では顧客資金の分別管理が義務付けられていますが、万一の際に投資家資金を保全する信託保全までは義務ではないため、事業者破綻時に資金の一部しか返還されないリスクも残ります。
また過去には、運営会社による資金の不正流用や虚偽の募集内容が発覚して行政処分に至ったケースも複数あります。たとえばある企業では集めた約40億円の資金の大半を自社関連会社への融資に充て、返済不能に陥る不祥事が起きました。
事業者リスクは表面から見えにくいですが、万が一不正や経営破綻が起これば投資家が被害を被る可能性が高いため、事業者選びは非常に重要です。
情報開示が少なく透明性に欠ける場合も
ファンドの情報開示が不十分で、投資判断に必要な情報が得られないケースがある点もデメリットです。特にソーシャルレンディング黎明期には、貸金業法との兼ね合いから借り手企業の名前や詳細が匿名化される慣行があり、投資家から見て融資先の状況が把握しづらい状況が続いていました。
近年は金融庁の方針変更により条件付きで融資先情報の開示が進みつつありますが、依然として案件によっては必要十分な情報が開示されないこともあります。情報の透明性が低いとリスク評価が難しく、投資家は運営会社の提示する断片的な情報に頼らざるを得ません。リスクに関する説明が曖昧な場合には特に注意が必要です。
利益には税金がかかる可能性がある
ソーシャルレンディングで得た利益(分配金)には税金がかかります。
多くの事業者では分配金から所得税20.42%(復興特別所得税含む)が源泉徴収されます。分配金は「雑所得」に区分されるため給与所得等と合算して総合課税され、所得次第では税率が最大55%にもなります。その結果、所得が多い人ほど高い税率が適用され、手取り利益が目減りする点はデメリットと言えるでしょう。年間20万円を超える利益が出た場合は確定申告も必要になるなど、税務上の手間も発生します。
投資前に税負担も考慮し、手取りベースでリターンを見積もることが大切です。利回りを比較する際には税引き後の実質利回りで評価する姿勢を持ちましょう。
期待利回り通りにならないことがある
ファンド募集時に表示される予定利回り(想定利回り)は確約されたものではありません。
順調に運用が進めば予定通りの利回りが得られますが、何らかの理由で予定通りにいかないケースもあります。たとえば、借り手が予定より早く資金を全額返済してしまう早期償還が発生すると、当初見込んでいた運用期間分の利息収入が得られなくなります。
年利8%で2年間運用予定の案件が1年で繰上返済された場合、残り1年分の利息は支払われないため実現利回りは低下します。延滞や貸倒れが生じれば言うまでもなく利回りは大きく低下し、元本割れに至る可能性もあります。
こうした理由から、提示された期待利回りを鵜呑みにせず、あくまで「達成できるか不確実な目標値」であると認識することが重要です。
大損しないために気をつけたい5つのポイント

リスクを理解して冷静に投資判断をする
高い利回りの宣伝文句に飛びつく前に、ソーシャルレンディング特有のリスクを正しく理解しましょう。元本保証がなく貸倒れリスクがある以上、常に最悪の事態も念頭に置いて冷静に判断する姿勢が大切です。金融庁も「利回りだけに惑わされず、提供される様々な情報を確認したうえで適切な投資判断を行うように」と注意喚起しています。
また、「元本保証」「高利回り保証」など甘い謳い文句を鵜呑みにせず、リスクに関する情報にも必ず目を通しましょう。メリットだけでなくデメリットに目を向け、余裕資金の範囲内で無理のない計画を立てて投資することが、大損を防ぐ第一歩となります。
運営会社の実績や貸付実績を必ず確認する
投資先ファンドを選ぶ際は、まず運営会社の信頼性を見極めることが欠かせません。金融商品取引業者として登録済みであることは最低条件ですが、それだけで安心せずに過去の運用実績や貸付先の開示状況、不祥事の有無などを調べましょう。
具体的には、その事業者でこれまで貸倒れや延滞が発生していないか、行政処分を受けたことがないか、投資家への情報提供が丁寧かといった点を確認します。運営会社の健全性を見極め、信頼できるサービスだけを利用することがリスク軽減につながります。
高利回り案件だけに絞らない
利回りが高い案件ほど人気を集めがちですが、異常に高い利回りをうたう案件にはそれ相応のリスクが潜んでいる可能性が高いです。
実際、2018年に大規模延滞を引き起こした業者の多くは年利10%前後の高利回り案件を多数扱っていました。リスクとリターンは表裏一体である点を忘れずに、リターンにばかり目を奪われないよう注意しましょう。
投資資金を守るためには、案件の内容や担保・保証の有無、借り手の信用度などを総合的に判断する必要があります。高利回り案件のみならず中程度の利回り案件もバランスよく選ぶことで、ポートフォリオ全体のリスクを下げることができます。
無理のない金額から始めて経験を積む
ソーシャルレンディングは少額から投資可能とはいえ、いきなり大金を投入するのは避けましょう。まずは無理のない範囲の金額(数万円程度)からスタートし、経験を積むことをおすすめします。投資に充てられる余裕資金が100万円ある場合でも、初回はその一部(5~10万円ほど)に留めて様子を見るくらい慎重でも良いでしょう。小さな額であれば、仮に損失が出ても生活に与える影響を抑えられるため心理的負担も軽減されます。
実際の運用を通じてファンドの選び方や分配金の受け取りなど投資の流れを把握し、自分のリスク許容度を見極めてから徐々に投資額を増やすと良いでしょう。余裕資金の中で少額から始めることで、大きな失敗を防ぎつつ知識と感覚を身につけることができます。
分散投資でリスクを抑えながら堅実に資産を増やす
大きな損失を防ぐには、複数のファンドに分散投資してリスクを抑えることが重要です。
異なる業種や借り手の案件に出資すれば、仮に延滞や貸倒れが生じてもポートフォリオ全体へのダメージを緩和できます。分散投資は資産運用の基本であり、分散することで大損を防ぎ、着実に利益を積み上げられます。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】ソーシャルレンディングのよくある質問

ソーシャルレンディングは安全?仕組み上のリスクはどこにある?
ソーシャルレンディングは魅力的な投資ですが、仕組み上「完全に安全」とは言えません。
銀行預金と違って元本保証がなく、借り手の返済遅延や貸倒れが起これば出資金を回収できないリスクがあります。過去に返済遅延で元本も利息も受け取れない事例もあり、こうしたリスクを理解した上で運用することが大切です。
元本割れは実際に起こる?投資で損するケースを知りたい
残念ながら元本割れは起こり得ます。
融資先企業の経営破綻などで貸し倒れが発生すると、投資額の一部ないし全額が返ってこないケースがあります。実際、過去には約30億円の投資資金が回収不能となった事件も起きています。リスクを十分認識しておきましょう。
どのくらいの金額から始めればリスクを抑えられる?
1万円程度から投資できるため、まずはリスクを抑えるためにも、数万円程度の余裕資金で始めるのがおすすめです。
少額なら万一損失が出ても痛手は小さいでしょう。慣れてきたら徐々に投資額を増やせば、大きな失敗を避けられます。
まとめ|リスクを知って安全に投資を始めよう
ソーシャルレンディングは年5~10%前後の高い利回りが魅力な一方、貸倒れや事業者リスクなど知っておくべきリスクが多数存在する投資商品です。実際に数十億円規模の元本が回収不能となった事件もあり、リスクを軽視すると大損に繋がりかねません。
だからこそ、事前に仕組みとリスクを正しく理解し、分散投資や信頼できる事業者の選定といった対策を講じることが重要です。
リスクを知って備えた上で運用すれば、ソーシャルレンディングは少額からでも安全に始められる新たな資産運用の選択肢となり得るでしょう。
参考元
・金融庁「ソーシャルレンディングへの投資にあたってご注意ください」
・金融庁「行政処分例(ニュースリリース)」
・国税庁「雑所得の課税方法」
・全国銀行協会「クラウドレンディングの潜在力」