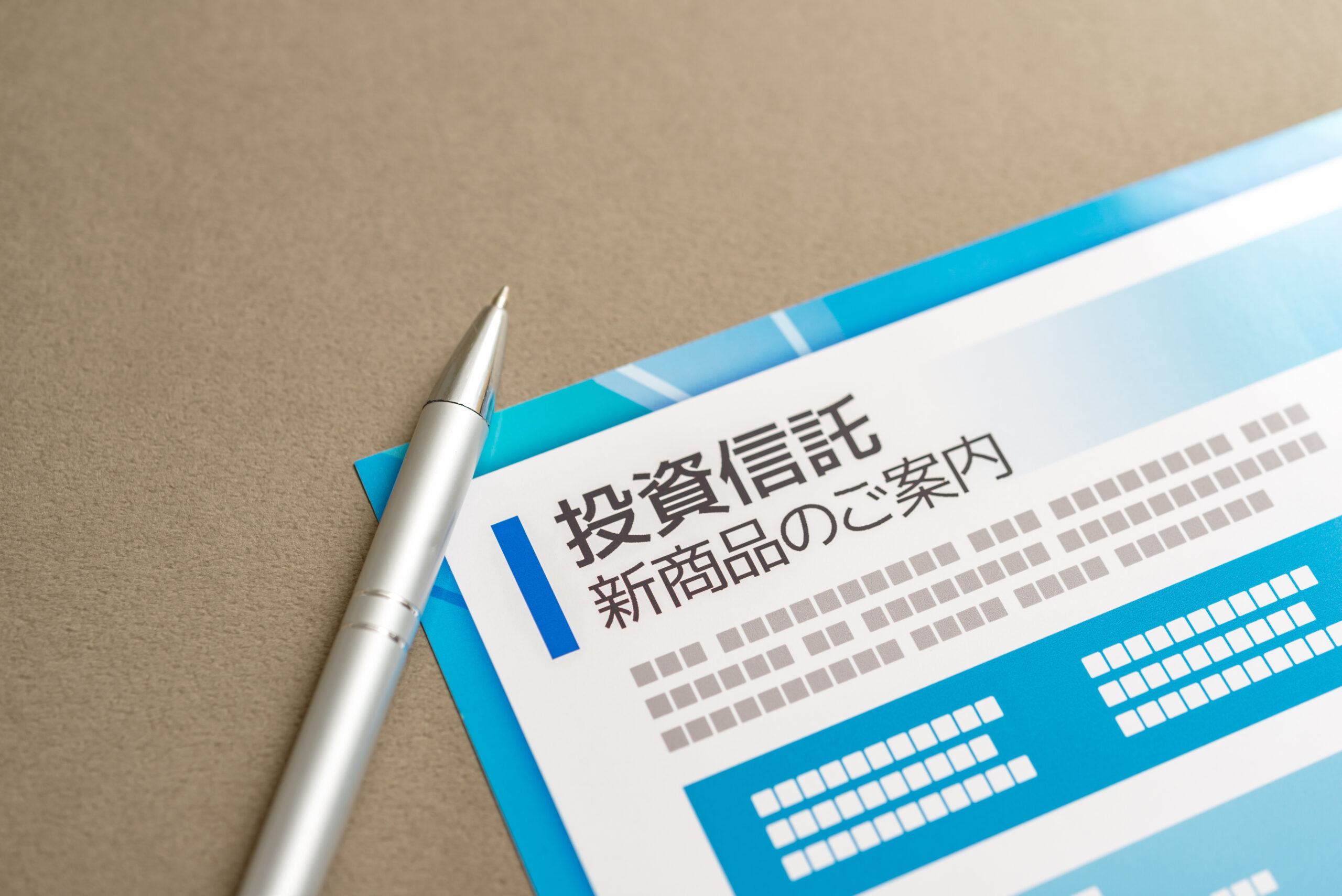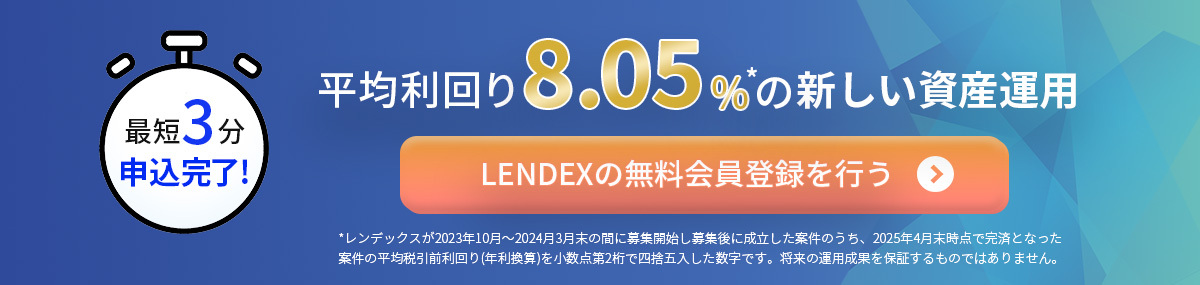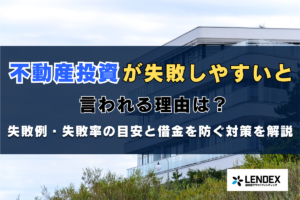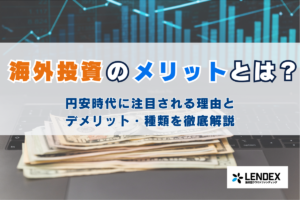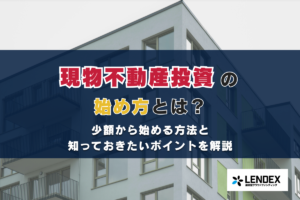投資信託は少額から分散投資ができ、長期的な資産形成に適した金融商品です。しかし、「いつ売ればいいのか分からない」と売り時に悩む方も多いのではないでしょうか。
本記事では、投資信託の「売り時」について初心者〜中級者の方にも分かりやすく解説し、失敗しないためのポイントをまとめます。ぜひ参考にしてください。
投資信託の「売り時」が重要な理由とは?

「いつ買うか」以上に「いつ売るか」は投資成果を左右します。投資信託は購入後も価格が変動し続けるため、売却のタイミング次第で利益にも損失にもなり得るからです。例えば、思い描いた利益が出る前に慌てて売ってしまえば、その後の上昇分の利益を逃すかもしれませんし、逆に下落局面で我慢できず損失確定(損切り)してしまえば、後で価格が回復して後悔するケースもあります。
投資信託の売り時が難しい理由の一つに、人間の心理があります。一般に含み益(評価上の利益)が出ているとき、人は「今のうちに確実に利益を得よう」と早めに売りたくなりがちです。一方、含み損(評価上の損失)があるときには「いつか元に戻るかも」と損失確定を先延ばしにしてしまう傾向があります。この心理的クセによって、多くの人が利益を伸ばし損ねたり、損失を拡大させたりしてしまうのです。
だからこそ、「売るタイミング」を戦略的に考えることが大切です。適切な売却判断ができれば、利益を最大化し損失を最小限に抑えることができます。逆に売り時を誤ると長期保有していれば得られたはずの利益を逃すことにもなりかねません。
よくある誤解:投資信託はずっと保有すべき?
「投資信託は長期投資が大事だから、基本は買ったらずっと持ち続けるべき」という話を聞いたことがあるかもしれません。確かに、投資信託は長期的に保有して時間を味方につけることで、複利効果による資産の成長が期待できます。しかし、「ずっと保有=絶対に売ってはいけない」というわけではありません。
そもそも投資信託は、最終的に売却して現金化することで利益を実現できる商品です。いくら評価額が増えても、売却しないままではそれはただの数字上の利益に過ぎません。極端な話、一生涯売らずに終えてしまっては資産形成の意味がありません。長期投資が大切とはいえ、将来の目標資金が必要な時期にはきちんと売却して利益を確定させる必要があります。
また「長期保有していれば損しない」という誤解も禁物です。市場環境やファンドの状況次第では、長期間持ち続けても期待した成績にならないケースもあります。例えば運用方針や市場動向が大きく変わり、当初見込んでいた成長が望めなくなることもあり得ます。その場合は、無理に持ち続けるメリットはありません。長期投資とは「何があっても永久に売らない」ことではなく、「短期的な変動に一喜一憂せず計画に沿って運用する」ことだと押さえておきましょう。
投資信託の売却を考えるべきタイミング【3選】

ここでは、「売り時」として代表的な3つのタイミングを紹介します。これらに該当する状況では、投資信託の売却を前向きに検討しましょう。
投資目的を達成したとき
最初に設定した投資目的や目標額を達成したら、売却を考える良いタイミングです。例えば、「5年後に○万円貯める」「子どもの進学資金を準備する」といった目標を掲げていた場合、予定の時期になったら売却して資金を目的に充てます。
事前に決めた目標金額に到達した時点で売却すれば、基準価額がその後どう動こうとも確実に目標を達成できます。目標を明確にしておくことで、「いつまでも売れずに迷う」事態を避けられるでしょう。
相場が過熱しすぎていると感じたとき
保有中の投資信託の関連市場が明らかに加熱気味である場合、一度売却を検討するのも一策です。具体的には、株価指数の急騰やPERなどの指標が過去平均より大幅に高い、水準から見てバブル的な熱狂を感じる局面です。市場が楽観一色のときは一見好調に見えますが、その後反動で急落するリスクも高まります。
過去にもITバブル崩壊や○○ショックのように、過熱後に大きな調整が起きた例があります。短期的な天井を予測するのは難しいものの、「すでに十分利益が出ている」「明らかに割高感が強い」と思える場合は、利益を確保するため売却しておくのも賢明でしょう。
ライフイベントや資金需要が発生したとき
結婚・出産、住宅購入、子どもの入学や留学、転職・退職など、大きなライフイベントでお金が必要になった場合も売却のタイミングです。投資信託はいつでも解約できる流動性の高さがメリットなので、必要なときに現金化して使うのは本来の目的に適っています。マイホームの頭金や教育資金、老後の生活資金など、まとまったお金が要る場面では、計画通りに売却して資金に充てましょう。
このようにライフイベントに合わせて売却時期を決めておくと、「必要なときにお金がない」という事態を防げます。なお、急な病気や災害など予期せぬ出費にも備え、投資信託以外に緊急予備資金を用意しておくことも大切です。
損切りのタイミングはいつ?判断基準を解説
投資信託が思惑と反して値下がりしてしまった場合、いわゆる「損切り」(損失覚悟で売却)するかどうかの判断は難しいところです。含み損を抱えていると誰しも躊躇しますが、場合によっては早めに損切りして損失を確定させた方が良いこともあります。
長期的に見て回復が見込めない場合
基準価額が大幅に下落した背景に、ファンドの投資対象や市場環境の構造的な変化があると判断されるときは、損切りを検討すべきです。
例えば、投資対象の業界における技術革新で事業モデルが崩壊した、投資先の国の地政学リスクが高まり長期低迷が避けられない等です。そのように今後長期的な値上がりが期待できないと判断したなら、持ち続けるメリットはありませんから早めの売却が得策と言えます。
当初のリスク許容度を超えて下落した場合
投資の際に「○%下落したら損切りする」といったルールを決めている方もいるでしょう。例えば購入時から20%下落して、自分の許容範囲を超えた損失になった場合などです。こうしたラインを設けておくことで、感情に流されず機械的に損切り判断ができます。
大切なのは、「ここまで下がったら撤退する」という損失許容ライン(ストップロスライン)を事前に決めておき、守ることです。損失が大きくなるほど冷静な判断が難しくなるため、早めに区切りをつけるほうが傷は浅くて済みます。
他に魅力的な投資先が見つかった場合
下落している投資信託に固執するよりも、資金を有望な投資先に振り替える決断もときには必要です。「塩漬け状態」のファンドを抱えて機会損失するより、その資金でより高いリターンが期待できる商品に乗り換えた方が効率が良いケースもあります。
ただし、この判断をするには冷静な市場分析が求められます。安易に飛び移ると「損切り→乗り換え先も下落」という悪循環に陥りかねません。新たな投資先の確信度が高く、かつ現在のファンドの先行きに悲観的な場合に限り検討しましょう。
損切り判断の注意点
一時的な値下がりで焦って売却しないことも重要です。価格下落の原因が一時的要因でいずれ回復が見込めるなら、無理に損切りする必要はありません。実際、保有ファンドが値下がりしてもすぐに売らずに様子を見た結果、その後大きく値上がりして損失どころか利益が出たというケースもあります。
したがって、値下がり局面ではまず冷静に原因分析をしましょう。その下落が一過性なのか、構造的なものかを見極めたうえで判断することが大切です。
「含み益がある=売り時」ではない理由
評価額が購入時より増えて含み益が出ていると、「利益があるうちに売ってしまおう」と考えがちです。しかし、「含み益=今すぐ売却すべき」という単純なものではありません。ここでは、含み益がある状態での売却判断について、誤りがちな点と考慮すべきポイントを確認します。
心理的側面
まず、人間の心理として利益は確実に手にしたいため、含み益が出ると早期に利益確定したくなる傾向があります。確かに、基準価額が上昇して含み益が出ている状態で売却すれば、その利益は自分のものとして確定します。売却しない限り、前述のとおり相場変動でせっかくの含み益が消えてしまうリスクは常につきまといます。「利益を失いたくない」という気持ちで売却する判断自体は間違いではありません。
利益を伸ばす機会を逃すリスク
優良なファンドであれば、含み益が出ているということは運用が順調である証でもあります。本来の投資目的・期間から見てまだ成長余地があるなら、すぐに全部売ってしまうのは早計かもしれません。「もっと持ち続けていればよかったかな」という後悔が大きくなる可能性もあります 。
実際、「もう少し価格が上がるだろうと思って持っていたら下がってしまった…」という後悔の声もありますが、「早く売りすぎて大きな上昇を取り逃した…」という後悔もまた存在します。
利益確定の方法を工夫する
含み益=全部売却ではなく、例えば一部だけ売却して利益を確定させ、残りは引き続き運用するといった戦略が有効です。一部売却なら、仮にその後さらに値上がりしても残りの保有分で利益を享受できますし、もし値下がりしても確保済みの利益のおかげでダメージを抑えられます。いわば「利益の分散確定」です。また、売却によって得た現金を他の有望な投資に回すことで、ポートフォリオ全体の効率を上げる選択肢も出てきます。
税金の観点も考慮する
含み益を確定すると課税対象となり、手取り利益が減ります。特にNISA口座で運用している場合は非課税メリットがあるため、むやみに利益確定すると非課税枠を無駄に使ってしまう可能性もあります。税負担を抑えるために、NISAなど非課税制度を活用している分は極力売らずに運用を続ける、課税口座の分から優先して利益確定する、といった工夫も検討できます。
含み益が出ているからといって即売却が正解とは限らない
重要なのは「その含み益があなたの目標や計画に照らして十分か」「今後さらに増える可能性とリスクをどう見るか」という点です。利益確定のタイミングは、自身の投資計画とリスク許容度次第で柔軟に決めましょう。焦って“売り急ぎ”するのではなく、一部売却なども活用しながら賢く利益を手にしてください。
投資信託の長期保有とのバランス

投資信託は長期保有で資産を育てるのが基本ですが、だからといって「売ってはいけない」というわけではありません。大切なのは、「いつ・どのように売るか」を最初から計画に組み込んでおくことです。
たとえば老後の生活費や住宅購入など、目的に合わせて売却タイミングを決めておけば、迷いなく行動できます。また、相場や自分の状況に応じて資産配分を見直すリバランスも、長期運用における重要な売却判断の一つです。
そして「長期保有=放置」ではなく、定期的に運用状況を確認する姿勢も大切です。予定通りの成果が出ているか、方針にズレがないかをチェックしながら、必要なら見直しや一部売却を検討しましょう。つまり、長期運用と売却は矛盾しません。目的に沿った売却なら、むしろ資産形成の成功に近づく一歩になります。
初心者がやりがちな“売り急ぎ”の落とし穴
少し値下がりしただけですぐ売ってしまう
買った直後に基準価額が下がると、「損したくない」とすぐ売却してしまう初心者がいます。ですが、市場では値下がりと値上がりを繰り返すのが当たり前です。一時的な価格変動に耐えられずに売却すると、その後の反発で得られたはずの利益を逃してしまうことがあります。
特に株式市場は日々上下しますが、長期では成長基調という場合も多いです。短期的なマイナスに慌てて反応しないことが大切です。むしろ下がったときに追加購入するくらいの方針(ドルコスト平均法による積立など)で臨むほうが、長期では成果につながりやすくなります。
少し利益が出たらすぐ売却してしまう
反対に、評価益がわずかに出た段階で「利益があるうちに確定しよう」とすぐ売ってしまうケースもあります。確かに損失になる前に売る安心感はありますが、利益を伸ばす前に手放してしまう行動でもあります。初心者の中には、「利益が出たらすぐ売るもの」と早合点している人もいるかもしれません。
しかし前章で述べたように、含み益が出た時こそ慎重に判断すべきです。利益確定を急ぎすぎると、資産形成の効率が下がってしまいます。特に長期の資産形成が目的である場合、ある程度の利益が出てもすぐ全部を売らず、長期運用に乗せ続けることが重要です。
情報に振り回されて売買してしまう
新聞やネットニュースで「○○ショック到来か」「△△株急落」などの見出しを見ると、不安になって資産を引き上げたくなるかもしれません。ですが、短期的なマーケットニュースに一喜一憂して売買を繰り返すのは典型的な失敗パターンです。売買の度に手数料や税金もかかり、長期的には大きなコストとなります。
頻繁に乗り換えることで常に高値掴み・安値売りのリスクも高まります。むしろ投資信託はいつでも売却可能だが、だからといって常に売買すべきではないと心得ましょう。基本はスタンスを決めたらブレずに保有し、よほどの理由が無い限り方針を変えないことです。
周囲に流されて売ってしまう
友人やSNS上で「今は売り抜けた方がいいらしい」といった話を聞いて焦り、深く考えずに売却してしまうこともありがちです。しかし、他人の事情と自分の事情は違います。その人にはその人のポートフォリオやリスク許容度、目標があるはずです。真似して売った結果、自分だけ置いて行かれたり、売った後に値上がりして後悔する例は枚挙にいとまがありません。他人の発言に惑わされず、自分の投資計画に沿って判断することが肝心です。
売却タイミングでかかる税金の注意点
投資信託を売却して利益が出ると、税金の問題も発生します。日本では、上場株式や投資信託の譲渡益には約20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税金が課されます 。これは譲渡益税と呼ばれ、利益が出た場合に利益額に対して課税されます。特定口座(源泉徴収あり)で運用していれば、売却益に自動で税金がかかり手取り額が計算されるので意識しにくいですが、確定申告をする場合や一般口座の場合は自分で申告・納税が必要です。
目標額設定時に税引後を意識する
たとえば「100万円の利益を得たい」と目標を立てているなら、税金分を加味して税引前で約125万円ほどの利益が出るように売却しないと、手取りで100万円になりません。特定口座の場合、売却代金が口座に入金される時点で税金が差し引かれているため、思ったより手取りが少ないと感じることもあります。目標金額は税引後ベースで考えておくと良いでしょう。
損益通算と繰越控除
複数の投資信託や株式を運用している場合、ある銘柄の利益と他の銘柄の損失を相殺(損益通算)することで課税額を減らすことができます。同じ年の他の売却益と損失はまとめて計算されるため、片方で損失が出ているなら他方の利益とぶつけると節税になります。
また、それでも控除しきれない損失は確定申告で最長3年間繰り越しが可能です。したがって、年末が近づいて売却を検討する際は、自分の年間損益の状況も把握しておきましょう。含み益が出ているファンドでも、他に大きな含み損があるなら同じ年に利益確定すれば税をだいぶ抑えられる、という判断も出てきます。
NISA口座なら非課税
NISA(少額投資非課税制度)口座で保有している投資信託を売却した場合、その譲渡益には税金がかかりません。したがって、税金面だけを見ればNISA枠内の投資信託はいつ売却しても非課税でメリットがあります。
ただし旧制度のNISAでは一度売却するとその非課税投資枠は消失し、新規投資には使えなくなりました。2024年開始の新NISAでは生涯投資枠が設定され、売却すれば翌年にその分の枠が復活する仕組みになっています。それでも、非課税の恩恵を最大化するにはできるだけ長く非課税運用するのが有利です。
解約手数料や信託財産留保額
税金とは別に、投資信託を売却するときにコストがかかる場合があります。一部の投資信託には、解約時にかかる信託財産留保額(売却代金から差し引かれる費用)や解約手数料が設定されています。これは長期運用を促すため、早期解約者に負担を求める仕組みです。
最近の一般的な公募投信(特にインデックスファンドなど)では信託財産留保額がないものも多いですが、購入前に目論見書で確認しておきましょう。仮に留保額0.3%と設定されているファンドを1,000万円分解約すると、3万円が費用として徴収されます。売却益がほとんど出ていない場合でも差し引かれるため、短期で解約すると実質的な損になりかねません。これらコストも踏まえて、「税金+手数料差引後で自分の得たい金額が残るか」を考えることが大切です。
クローズド期間に注意
投資信託によっては、設定から一定期間は解約できないクローズド期間を設けている場合があります。たとえば不動産投信などで運用開始後○ヶ月は解約不可、といったケースです。この期間中は市場価格が上がっていても換金できませんので、流動性リスクとして認識しておく必要があります。
売り時の判断に迷ったときに役立つ3つの視点
実際のところ、売却の判断に迷う場面は少なくありません。相場の先行きは誰にも正確には分からず、「今売るべきか、このまま持つべきか…」と悩むのは当然です。そんなときは、以下の3つの視点から状況を整理してみると判断材料が得られます。
視点① 自分の投資目的・計画の視点
まずは「なぜその投資信託を買ったのか」という原点に立ち返りましょう。目的や目標金額・運用期間が明確であれば、達成した時点で売却を検討するのが自然です。たとえば「子どもが18歳になるまで積み立てる」と決めていたなら、その時期までは保有継続が基本です。
また、収入や家族構成など自分の状況が変わっていないかも確認しましょう。以前は気にならなかったリスクが、今は重荷になっていることもあります。そんな時は一部売却でリスクを抑える判断も有効です。つまり、売るかどうかの判断は、自分のライフプランと資産計画に沿って決めるのが正解です。
視点② 市場環境・ファンドの状況の視点
次に、市場環境やファンドの状況を客観的に見て判断しましょう。経済情勢や金利、為替の動きが自分の投資信託にどう影響するかを確認します。株式型なら景気や企業業績、債券型なら金利動向、不動産型なら不動産市況など、ファンドの種類ごとに注目すべき指標は異なります。
同時に、そのファンドの基準価額や純資産総額の推移、運用成績がどうかもチェックします。ベンチマークや他の類似ファンドと比べてパフォーマンスが劣っていたり、運用方針が大きく変わっていたりするなら、売却を検討する判断材料になります。
逆に、市場が不安定でもファンドの中身に問題がなく、長期的に期待できるなら、保有を続ける理由になります。データと情報に基づく判断が、感情に流されない冷静な選択につながります。
視点③ リスクとリターンのバランスの視点
最後に、自分のポートフォリオ全体のリスクとリターンのバランスから判断しましょう。投資信託は資産の一部であり、売却によってポートフォリオ全体がどう変化するかを考えることが大切です。売って現金比率が高まりすぎれば将来のリターンが期待しにくくなりますし、逆に安定性が増して安心できるという見方もあります。
自分のリスク許容度との兼ね合いも重要です。市場の変動に不安を感じているなら売却によるリスク調整は合理的ですし、長期目線で多少の波を受け入れられるなら保有継続の選択もあります。つまり、「今売ることで得られる安定」と「持ち続けることで得られる期待リターン」のどちらを選ぶかという判断です。
また、売却後の資金の使い道もセットで考えてみましょう。乗り換えたい投資先がある、または明確な支出予定があるなら売却は前向きな判断です。一方で、資金をただ預金に置いておくだけなら、せっかくの投資機会を失うかもしれません。売却の判断は「いま売る理由」と「その後の使い方」まで見据えることで、より納得のいく選択になります。
投資信託以外の選択肢はあるの?

ここまで投資信託の売り時について述べてきましたが、そもそも「売るタイミングに悩むのが嫌だ」という方もいるかもしれません。投資には投資信託以外にも様々な選択肢があり、それぞれ特徴が異なります。売却タイミングの悩みを軽減できるような他の金融商品も検討してみましょう。
個別株式やETFへの投資
投資信託に対して、個別株やETFは自分で銘柄を選び、売買タイミングを判断できるのが特徴です。「この企業の業績が悪化したから売る」など、明確な根拠で判断しやすい反面、分散効果が薄くリスクは高めです。ただし、配当目的で長期保有する戦略も可能で、売却せずに収入を得続ける選択肢もあります。
個別株は自由度が高い分、出口戦略の設計や情報収集が必須で、投資信託以上に知識と判断力が求められます。ですが、自分の意思で運用する醍醐味もあり、やりがいのある投資スタイルと言えるでしょう。
債券・預金など安定資産へのシフト
投資信託から債券や預金などの安定資産へ切り替えるのも一つの選択肢です。特に、教育資金など使う時期が決まっているお金は、必要な数年前から元本保証の資産に移しておくと安心です。リターンは小さくなりますが、「減らさずに確実に使える」ことが最優先の場合に有効な手段です。
不動産やREITへの投資
定期収入を得たい人には、不動産投資信託(J-REIT)や不動産クラウドファンディングが有効です。少額で始められ、家賃収入にあたる分配金を受け取れるため、売却を急がずとも収益が期待できるのが魅力です。基準価額の変動リスクはありますが、長期保有でインカム重視の人に向いた選択肢です。
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)は、事業者向けのローンに出資し、毎月利息を受け取るタイプの投資です。多くの場合、運用期間は半年〜1年程度とあらかじめ決まっており、満期になれば元本が償還される仕組みです。
途中解約はできませんが、価格変動に左右されず、出口のタイミングが明確なのが特長です。利回りが比較的高く設定されているものもありますが、元本保証はなく貸し倒れリスクがある点には注意が必要です。
ロボアドバイザーや投資一任サービス
ロボアドバイザーや投資一任サービスは、資産運用をプロに任せるスタイルで、売却タイミングやリバランスも自動で行ってくれるのが特長です。利用者は自身のリスク許容度や目標を伝えるだけでOKで、あとはおまかせで運用が進みます。手数料は発生しますが、自分でタイミングを悩まなくて済むのは大きなメリットです。特に忙しい方や感情的な売買を避けたい方にとって、有力な選択肢と言えるでしょう。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
まとめ:失敗しない投資信託の売り時の見極め方
長期投資を基本としつつも、適切なタイミングで売却を判断できれば、投資信託は強力な資産形成ツールになります。「買ったら終わり」ではなく「出口戦略まで含めて投資」であることを忘れず、計画的に資産運用を行いましょう。
今回紹介したポイントを踏まえつつ、ぜひご自身の投資信託のベストな売り時を見極めてみてください。健全な判断で売却を行えば、将来必要なときにしっかりと資金を手にし、後悔のない投資成果を得られるはずです。長期的な視野と冷静な判断力を持って、賢い資産形成を続けていきましょう。