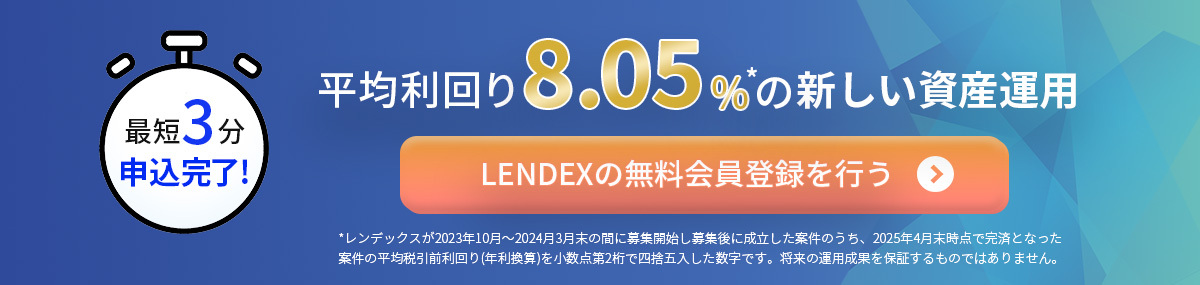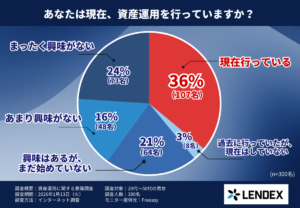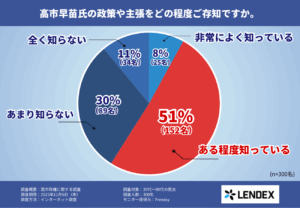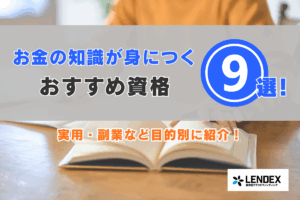日本の株式市場には、配当利回りが高い「高配当株」と呼ばれる銘柄群があります。近年、ネット上では「高配当株はやめとけ」「高配当株はおすすめしない」といった意見を目にすることもあります。しかし本当に高配当株への投資は避けるべきなのでしょうか?
本記事では、高配当株の基本的な仕組みから、「おすすめしない」と言われる理由、メリット・デメリット、さらに投資戦略や代替投資まで網羅的に解説します。高配当株投資が自分に合っているか判断するための参考にしてください。
高配当株の基本的な仕組み、配当の意味や利回り基準
高配当株とは、株価に対する配当金の割合(配当利回り)が相対的に高い銘柄のことです。まず配当と利回りについての基本を押さえておきましょう。
配当金とは
企業が稼いだ利益の一部を株主に還元するお金のことです。通常、年に1〜2回(中間配当・期末配当)支払われ、1株あたり〇円という形で受け取ります。企業の業績や方針によって金額は変動し、配当は出さない(無配)場合もあります。
配当利回りとは
配当金額を現在の株価で割った割合のことです(年額配当金÷株価×100%で計算)。例えば株価1,000円で年間配当50円なら配当利回り5%となります。利回りが高いほど投資金額に対するリターン(インカムゲイン)が大きいことを意味します。
利回りの基準
どの程度の利回りから「高配当」と呼ぶか明確な基準はありませんが、一般的に配当利回りが4〜5%以上あれば高配当株と見なされることが多い印象です。市場平均(東証上場企業全体の平均利回りはおおむね2%前後と言われます)と比べて明らかに高ければ高配当株と認識されます。
企業は稼いだ利益の使い道として、大きく「事業への再投資」か「配当による株主還元」のどちらかを選択できます。高配当株の多くは成熟企業であり、新規事業や設備投資などへの成長投資機会が相対的に少ないため、利益のかなりの部分を配当として株主に還元する傾向があります。その結果、配当利回りが高くなるわけです。反対に、成長途上の企業は利益を配当に回さず事業拡大に投入することが多く、無配か配当利回りは低めです。
高配当株投資の魅力は、銀行預金や債券より高い利回りで定期的な現金収入(インカムゲイン)を得られる可能性がある点です。不労所得への期待から、高配当株は特に初心者や年配の投資家にも人気があります。
高配当株が「おすすめしない」と言われる5つの理由

高配当株が敬遠される背景には、以下のような5つの理由があります。高配当株ならではの弱点やリスクを理解することが重要です。
株価の成長性が乏しく、大きな値上がり益(キャピタルゲイン)を狙いにくい
高配当株は成熟企業が多いため、事業拡大による株価上昇(値上がり益)が得られにくい傾向があります。利益の多くを配当に回す分、再投資による成長余地が小さく、急成長するグロース株のような値上がりは期待しにくいのです。長期的に資産を大きく増やしたい場合、高配当株だけでは非効率になりがちです。
減配や無配のリスクが常にある
配当は企業の義務ではなく、業績や方針次第で減額・停止される可能性があります。高配当につられて購入した株が業績悪化で減配・無配となれば、期待していた配当収入が得られなくなるだけでなく、失望売りによる株価下落で二重の損失を被るリスクもあります。実際、2020年にJT(日本たばこ産業)や日本郵政が減配・配当停止を発表し、大きなニュースになりました。このように高配当株でも配当が将来にわたって保証されているわけではない点に注意が必要です。
配当金に税金がかかり、資産形成の効率が悪い
配当金には約20.315%の税金(所得税15.315%、住民税5%)が課されます 。そのため、受け取った配当を再投資しても約2割は税金で目減りしてしまい、複利で資産成長させる効率は株価値上がり益に比べて劣ります。例えば、企業が利益を配当ではなく内部留保していれば税金はかからずその全額が事業拡大に使われ株価上昇につながるかもしれませんが、配当として受け取ると税引後のお金しか再投資できません。特に課税口座で運用する場合、高配当株は税制面で不利になりやすいのです。
まとまった資産がないと十分な配当収入にならない
高配当株といえども、配当収入だけで生活費を賄うには相当の元本が必要です 。例えば配当利回り3%の銘柄で年間300万円の配当を得るには約1億円もの投資資金が必要になります。仮に利回り5%の高配当株でも、年間120万円(月10万円)の配当を得るには2,400万円程度の投資が必要です。
資産規模が小さいうちは配当金額も僅かで、「雀の涙」のような収入にしかならないため、高配当株だけでは効率的に資産を増やせません。少額資金から大きく増やしたい初心者には不向きと言えるでしょう。
高い配当利回りには落とし穴がある(業績悪化や分散投資の難しさ)
異常に配当利回りが高い株には要注意です。他銘柄と比べ極端に利回りが高い場合、株価下落(業績不安)によって見かけ上利回りが跳ね上がっているだけのケースがあります。実態として業績が悪化し利益が減っていれば、いずれ減配に追い込まれる可能性が高いです。
また、高配当株は特定業種(金融、エネルギー、不動産など)に集中しがちで、分散投資が難しくなる点も見逃せません。不景気に弱い景気敏感株ばかりを高配当だからと集めると、景気後退局面でポートフォリオ全体が大打撃を受ける危険があります。高配当株だけに偏ったポートフォリオはセクター偏重によるリスクが高まるため注意が必要です。
高配当株のメリット

定期的な収入(インカムゲイン)が期待できる
高配当株を保有する最大のメリットは、持っているだけで定期的に現金収入が得られることです。成熟企業は安定した利益を計上している場合が多く、その利益の一部が配当として還元されます。銀行預金の利息が微々たるものに過ぎない中、年数%もの配当利回りが得られるのは魅力です。年金や給料とは別の収入源を確保できるのは心強く、老後資金や生活の足しとしてインカムゲインを重視する人には大きなメリットです。
株価が比較的安定しやすい
高配当株の多くは業界で確固たる地位を持つ大型安定企業です。急成長はしないまでも成熟したビジネスモデルを持ち、収益や株価の変動が比較的小さい傾向があります。配当利回りが高いこと自体、株価が大きく下がりにくいクッションになる場合もあります。株価が下落すると利回りがさらに上がり魅力が増すため、一定の買い支えが入りやすいからです。ポートフォリオ全体のボラティリティ(変動幅)を抑える効果が期待できる点はメリットと言えるでしょう。
長期保有向きで手間がかからない
高配当株投資は、一度買ったら基本的に「ほったらかし」で保有し続ける戦略に適しています。値上がり益で頻繁に売買益を狙う必要がないため、日々の株価変動に一喜一憂せず済みます。むしろ長期保有で配当を安定的にもらい続ける方が得策なので、短期的な株価下落があっても「配当分は入るから」と落ち着いて構えやすい利点があります。心理的にも、定期収入があることで投資を継続しやすくなるというポジティブな効果があります。
不況期にもゼロにはならないリターン
高配当株であれば株価が下がっている間も配当収入が入るため、たとえ一時的に含み損を抱えても全くの無収入にはなりません。配当を再投資し続ければ株数を増やせるので、将来の回復局面で一層大きなリターンを得ることもできます。このように市場環境が悪いときでも現金収入が得られる点は、高配当株の頼もしいメリットです。ただし減配にならないことが前提であり、減配リスクには注意が必要です。
高配当株の主なデメリット
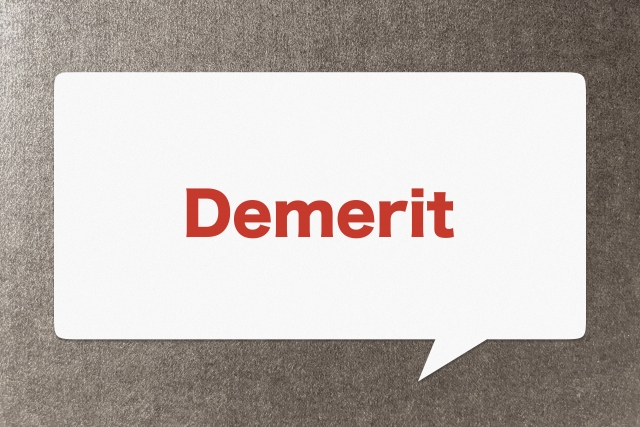
減配・無配リスクによるダメージ
高配当株最大のデメリットは減配や無配による収入減少と株価下落リスクです。特に高配当株に集中投資している場合、一社でも減配になればポートフォリオ全体の収入が大きく落ち込みかねません。
また、減配発表時には株価も急落することが多く、配当狙いの投資家ほど大きな痛手を被ります。これは避けて通れないリスクではありますが、分散投資や銘柄選別である程度コントロールすることが可能です。
資産成長スピードが遅い
高配当株は安定する代わりに、資産を雪だるま式に増やす成長ドライバーにはなりにくいです。例えば、成長株であれば業績拡大とともに株価が何倍にもなる可能性がありますが、高配当株はせいぜい緩やかな値上がり+配当程度に留まりがちです。10年で資産を何倍にも増やしたいといった野心的な目標にはミスマッチでしょう。
また、インフレ局面にも弱いと言われます。物価上昇によって貨幣価値が下がると、同じ配当金額でも実質的な購買力は低下します。増配がなければインフレに取り残されるリスクもあり、将来の経済環境次第では高配当株の実質リターンが目減りする点にも留意が必要です。
分散投資が難しく偏ったポートフォリオになりやすい
高配当株は特定業種に偏りがちなため、ポートフォリオ全体で見るとセクター分散が効きにくい傾向があります。例えば高配当だからといって金融株と不動産株ばかり保有していると、景気悪化時には配当減だけでなく株価も軒並み下落してしまいます。
一方、ハイテクやグロース株には無配も多くポートフォリオに入れづらいため、結果として市場全体に対する分散効果が低い構成になってしまうのです。このように、高配当株投資は上手にやらないと「卵を同じ籠に盛る」状態になりリスクコントロールが難しくなる点がデメリットです。
税金面で不利(ただしNISAで軽減可能)
配当金には約20%の税金が源泉徴収されます。長期投資においてこの税負担は無視できません。配当再投資であっても税引後資金しか投資できず、非課税運用に比べて複利効果が損なわれます。
ただし、日本にはNISA(少額投資非課税制度)があります。NISA口座で保有する株式の配当金は非課税で受け取れるため、税金のデメリットを緩和できます。特に2024年から始まった新NISA制度では非課税保有期間の無期限化・拠出枠の拡大が図られており、高配当株の配当を非課税で長期運用するといった使い方もしやすくなっています。税制を工夫すればデメリットを小さくできるものの、課税口座で高配当戦略を行うと複利効果で見劣りしやすい点は押さえておきましょう。
向いている投資家・向いていない投資家の特徴
高配当株投資が万人に適しているわけではありません。ここでは高配当株が向いている人と向いていない人の典型的な特徴を整理します。
高配当株投資が向いていない投資家
まずは「高配当株はやめておいた方がいい」タイプの投資家像です。
株価の成長(キャピタルゲイン)を重視する人
もしあなたが株価の値上がり益によって資産を倍増させることに主眼を置いているなら、高配当株はミスマッチです。高配当株は株価成長力が低い傾向があるため、大化け狙いの投資には不向きと言えます。成長企業に投資してこそ得られるリターンを求める人は、グロース株や中小型成長株に目を向けるべきでしょう。
短期的に大きな利益を狙う人(アクティブトレーダー)
高配当株投資は基本的に長期保有によるインカムゲイン狙いの受け身の戦略です。短期間で売買を繰り返しキャピタルゲインを稼ぎたい人にとって、高配当株の値動きは退屈に映るでしょう。デイトレードや数ヶ月内の値幅取りを志向するなら、ボラティリティの高い成長株やFXなど他の手段の方が適しています。短期売買派にとって高配当株は機会損失になりかねません。
運用資金がごく少額の人
元本が少ない初心者が高配当株だけで資産形成しようとすると、効率が悪くなります。例えば数十万円程度の元手では、年数%の配当を得てもわずかな金額にしかなりません。むしろ成長性のある投資信託や成長株に投資して元本そのものを増やす方が現実的でしょう。
高配当株はある程度まとまった資金を運用する場合に初めてメリットが活きてくる側面があります。資産規模が小さいうちは高配当株はあまり向いていないと言えます。
企業分析や情報収集をあまりしない人
減配リスクを避けるには、業績や財務、配当方針など企業分析が欠かせません。適切な銘柄選別ができない人がなんとなく高利回り銘柄を買ってしまうと、裏で業績悪化が進行していて配当維持が危ういケースもあります。「ほったらかし」とはいえ最初の銘柄選びは慎重に行う必要があります。企業研究が苦手・面倒という人も高配当株には向いていないかもしれません。
高配当株投資が向いている投資家
次に、高配当株との相性が良い投資家タイプを見てみましょう。以下のような特徴に当てはまる人は、高配当株をポートフォリオに組み込むメリットが大きいかもしれません。
安定した長期収入を確保したい人
株の値上がりよりも定期的なキャッシュフローを重視する人には高配当株は打ってつけです。例えば退職後の年金生活者で預貯金を運用しつつ生活費の足しにしたい場合や、本業とは別に副収入源が欲しいサラリーマンなど、安定収入のニーズがある投資家に適しています。配当金は基本的に企業業績が大きく落ち込まない限り継続的に支払われるため、債券利息のような感覚で長期のインカムゲインを得られます。
まとまった元本があり守りの運用をしたい人
既にそれなりの資産を保有しており、リスクを抑えつつ運用したいケースでは高配当株は有力な選択肢です。資産規模が大きい人ほど、高配当株から得られる配当金額も大きくなります。例えば1億円を高配当株で運用すれば利回り4%でも年間400万円程度の収入です。資産が大きい人ほど高配当株投資に向いているという見方もできます。株価自体も安定しやすいため、大事な元本を大きく減らしたくない人にとって心理的安心感もあります。
コツコツ型の長期投資を志向する人
高配当株は「配当をもらって再投資」を繰り返すようなコツコツ型の長期投資と相性が良いです。地味ではありますが、時間をかけて配当再投資を続ければ複利効果で資産が増えていきます。また「株価が下がったら買い増し、配当も増えてラッキー」というスタンスで動じずにいられる人は高配当株との相性が良いでしょう。市場に左右されずマイペースに投資を継続できる人こそ高配当株の恩恵を受けやすいと言えます。
税制優遇を活用できる人
NISA枠などを活用して配当非課税のメリットを最大化できる人にも向いています。例えば新NISAでは成長投資枠と別に積立投資枠がありますが、高配当ETFや高配当株を非課税枠で長期保有すれば税引き後リターンを高めることができます。制度を理解して賢く使える人は、高配当株の弱点を補いつつメリットを享受できるでしょう。
失敗事例と投資家のリアルな声

高配当株投資にも当然リスクがあり、実際に失敗した例や後悔の声も聞かれます。ここではいくつか典型的な失敗事例と、投資家のリアルな声を紹介します。
減配による株価急落の例(住友商事のケース)
商社大手の住友商事(8053)は高配当株の代表格として個人投資家に人気の銘柄です。しかし、2022年5月に業績見通しの悪化から翌期の減配予想を発表した際、株価が急落しました。実際、この発表で年間配当計画を前期比▲20円(110円→90円)とすると、直後に失望売りが出て株価が大きく下がりました。
高配当株に集中していた投資家の中には、このような減配ニュースで含み損を抱えてしまった人も少なくありません。「配当狙いで買っていたのに、配当も減らされ株価も下がり踏んだり蹴ったりだ」という声が聞かれました。このケースは「高配当=安全」ではないことを示す典型例と言えます。
景気敏感株に偏りすぎた例
ある個人投資家の失敗談として、「高利回りに惹かれて銀行株と不動産株ばかりポートフォリオに入れていたら、景気後退局面で配当も株価もダブルで下がって痛い目にあった」というものがあります。
高配当株には先述のように金融・不動産など景気循環の影響を受けやすい業種が多く含まれます。一つのセクターに集中投資してしまうと、その業界の不調時にポートフォリオ全体が打撃を受けるリスクがあります。特に金融危機や不動産不況の際には、高配当だったはずの銘柄が減配・無配に転落することもあり得ます。分散の重要性を怠った失敗例として戒めたいところです。
方針が定まらず中途半端になった例
高配当株投資にありがちなミスとして、「配当狙いと言いつつ株価下落に耐えられず狼狽売りしてしまう」パターンがあります。例えば配当をもらうつもりで買ったのに、いざ株価が下がったら不安になって売却してしまい、結局安値で手放してしまったという声です。
「売却益も欲しい、でも配当も欲しい」と軸がブレていると、下落局面で正しい判断が難しくなります。高配当株は基本ホールド戦略が前提なので、腹を括れない人はかえって損をするという教訓です。
銘柄の見極め方
高配当株投資で成功するには、投資する銘柄選びが極めて重要です。闇雲に利回りランキング上位の株を買うのではなく、配当の持続可能性や企業の健全性を見極める必要があります。
配当性向に注目する
配当性向とは当期利益に対する配当金総額の割合です。これが100%を超えているような企業は危険信号と考えましょう。利益以上の配当を出すには蓄えの取り崩しや借入に頼るしかなく、長続きしません。一般に配当性向が高すぎる企業は将来減配するリスクが高いです。目安として配当性向は50〜70%以下が健全とされ、80〜90%を超えると黄信号、100%超は赤信号です。持続可能な配当か判断するため、必ず配当性向を確認しましょう。
業績トレンド(収益の安定性)
過去数年の売上高や利益の推移をチェックし、業績が右肩下がりでないか確認します。もし業績悪化が続いているようであれば、いくら現在配当利回りが高くても将来の減配リスクが高いです。逆に安定的または緩やかでも増収増益を続けている企業は配当維持の余力があります。また景気変動による業績の振れ幅も見ておきましょう。安定した収益基盤(インフラ事業や生活必需品など)を持つ企業の方が不況期でも配当を出し続けられる可能性が高まります。
財務健全性(負債やキャッシュフロー)
配当を継続するには財務の健全さも重要です。借入金過多で利払い負担が大きかったり、フリーキャッシュフローがマイナス続きだったりする企業は無理をして配当を出している恐れがあります。自己資本比率や利益剰余金、営業キャッシュフローなどを確認し、配当原資に不安がないかチェックしましょう。
特にインフラ・通信など配当目的の投資家が多い企業は、社債発行で資金を賄ってでも配当を維持するケースもありますが、長期的には望ましくありません。配当余力(会社に蓄積された利益)が厚い企業だと安心感があります。
配当方針と実績を確認する

企業が公式に示している配当方針(例えば「配当性向○%を目安」や「安定配当を継続」など)を確認しましょう。また過去の配当実績も重要です。減配歴がないか、配当額が上下激しくないかを調べます。10年連続増配などの実績がある会社は株主還元に積極的と判断できます。逆に業績は良いのに配当をポンと減らした履歴がある会社は注意です。
近年では累進配当を宣言する企業も増えています。企業IR資料や決算短信で配当方針を読み解き、株主重視の姿勢かどうか判断しましょう。
異常に高い利回りや急な配当増に警戒する
配当利回りが突出して高い銘柄は、その原因を必ず調べることが大切です。「株価暴落で利回りだけ高くなっている」「特別配当を出しているだけで来期以降利回りは平常に戻る」といったケースがあります 。配当額が急増している場合は、その背景(記念配当や一時的要因かどうか)を確認しましょう。また利回りが極端に高い場合、市場が「いずれ減配する」と織り込んで株価を下げている可能性もあります。利回り数字の裏側に何があるかを洞察することが重要です。
分散投資を心掛ける
高配当株投資では一社や一業種に集中しすぎないことも鉄則です。仮に魅力的な高配当株があっても、そこに資金の大半を投じると万一の減配で大きな打撃を受けます。できれば複数の銘柄に分散させ、1社あたりの比率を抑えることで特定銘柄の減配リスクを分散しましょう。
また、国内株だけでなく、米国など海外の高配当株やETF、不動産投資信託(J-REIT)などにも目を向けると地域・資産の分散にもなります。分散の効いた銘柄選びが安定した配当収入を得るコツです。
高配当株を活用した投資戦略
ポートフォリオ構成の一例
例えばポートフォリオ全体を「攻め」と「守り」に分けるとします。攻めの部分には成長株や株式インデックス投信を配置し、資産拡大を狙います。守りの部分に高配当株や債券などを配置し、安定収入とリスク低減を図ります。割合は年齢や資産状況によりますが、若年層なら攻め70%・守り30%、中高年なら攻め30%・守り70%といったイメージです。
高配当株は守りの核として、債券よりはリスクがあるがリターンも期待できる存在として組み入れます。複数の高配当銘柄を組み合わせればある程度分散も効き、配当収入で攻め部分の含み損をカバーするといった効果も期待できます。
配当再投資戦略
受け取った配当金をそのまま預金に置いておくのではなく、再び投資に回すことで複利効果を狙う戦略です。高配当株の配当で追加の株式を買い増すか、他の有望銘柄に振り向けます。これにより保有株数が増え、次回以降の配当がさらに増加するという好循環が生まれます。
ただし前述の通り課税口座だと税金分目減りしますので、再投資の効果を高めるには非課税口座の活用が望ましいです。時間はかかりますが「配当再投資で○○年後に配当年○百万円」といった計画を立ててコツコツ続けるのも一つの戦略です。
NISA枠の活用
高配当株との相性が良いのがNISAです。NISA口座で購入した株式の配当金は原則非課税で受け取れます(証券会社経由の受け取りが条件)。したがって、高配当株はNISA枠を使うことで本来20%取られる税金がゼロになり、実質利回りが向上します。
特に2024年以降の新NISAでは年間360万円の投資枠(成長投資枠と積立枠の合計)があり、期間無制限で非課税運用できます。例えば新NISAで高配当ETFを毎年積み立て、得られた分配金でさらに買い増すといった運用をすれば、税金を気にせず理想的な配当再投資が可能になります。NISAは長期投資推奨の制度でもあるため、高配当株をじっくり運用するのにうってつけです。「高配当株+NISA」で税制面のデメリットを解消することをぜひ検討しましょう。
リスク分散に有効な代替投資

高配当株投資のデメリットを補完したり、リスク分散を図ったりするために、株式以外の高利回り投資にも目を向けてみましょう。近年は少額から参加できる新しい投資手段も登場しています。その中でも注目されるのが融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)や不動産投資型クラウドファンディングなどのサービスです。
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)
インターネット上のプラットフォームを通じて、不特定多数の投資家がお金を出し合い、事業者や不動産開発などに融資を行う仕組みです。投資家は出資額に応じて定期的に利息収入(配当)を受け取れる点で、高配当株に似たインカムゲイン型の投資と言えます。利回りが比較的高く設定されているものもありますが、元本保証はなく貸し倒れリスクがある点には注意が必要です。
不動産投資型クラウドファンディング
不動産物件への投資を小口化したものです。運営事業者が物件を購入・運用し、家賃収入や売却益を出資者に分配します。年利ベースで5〜8%程度の利回り案件が多く、株式投資よりも平均利回りはやや高めとされています。不動産という比較的安定した現物資産が裏付けにあるため、安全性が高い案件も多いです(ただし元本保証ではない点に注意)。株式との相関が低く、株価が低迷しても家賃収入が入るといったように分散効果も期待できます。
その他の代替投資
上記以外にも、J-REIT(上場不動産投資信託)やインフラファンド、社債・公社債、外国債券、高金利通貨の預金など、高利回りを期待できる金融商品はいろいろあります。それぞれ特性は異なりますが、共通するのは株式とは異なるリスク要因でリターンを得られる点です。例えばJ-REITは不動産賃料収入を原資に年4〜5%前後の分配を出しますし、海外債券は為替リスク込みですが利回りが高いものもあります。
これらの代替投資を活用することで、高配当株だけに頼らず収入源を複線化できます。たとえばポートフォリオの一部を融資型クラウドファンディングに振り向けておけば、株式市場が低迷して配当金が減っても、クラウドファンディングからの分配で補填できるかもしれません。実際、融資型クラウドファンディングの大手では過去数年間元本割れ無しで運用が継続している例もあり、安定運用の選択肢として存在感を増しています。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
まとめ:高配当株は万人向けではないが戦略次第で武器になる
高配当株は「楽して儲かる」といった魔法の投資先ではなく、明確なメリットとデメリットが存在する金融商品です。配当利回りの高さゆえに初心者でも魅力を感じやすい一方で、成長性の低さや減配リスク、税負担などから「おすすめしない」「やめとけ」といった意見が出るのも事実です。万人に勧められる投資先ではありませんが、裏を返せば合う人には合うのが高配当株と言えるでしょう。
重要なのは、高配当株の特徴を正しく理解し、自分の投資目的やリスク許容度と照らし合わせて戦略的に活用することです。高配当株は万人向けではありません。しかし、自分の戦略次第でそれは確かな武器にもなるのです。リスクとリターンのバランスを見極め、賢明な投資判断で資産形成を進めていきましょう。