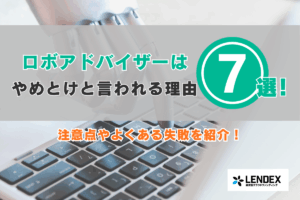仮想通貨は短期間で値上がりする一方、思ったほど「儲からない」と感じる人も多い投資対象です。値動きの大きさや税金・手数料、規制や詐欺リスクなど、利益を削る要因が重なると成果は不安定になりがちです。
本記事では、仮想通貨が危険と言われる理由と典型的な失敗パターンを整理し、損をしないための注意点と実践のコツを具体的に解説します。さらに、分散投資の考え方や少額からの始め方まで網羅し、仮想通貨と賢く向き合うための判断基準を明確にします。
仮想通貨は本当に儲からないのか?知っておきたい結論

長期的に安定して儲けるのは難しい
仮想通貨は価格変動が極めて大きく、長期にわたり安定して利益を出し続けることは困難です。実際、市場が盛り上がった高値圏で参入した投資家の大半は、その後の価格急落によって損失を抱えており、BISの分析でも2015〜2022年にかけてビットコイン購入者の73〜81%が最終的に損をした可能性が高いと推定されています。
株式や債券のように配当や利息といったインカムゲインがない仮想通貨では、値上がり益に頼るしかありません。しかしその値上がりも永続的ではなく、利益が出てもそれを守り続けることの難しさが多くの投資家の事例から明らかになっています。
つまり、長期的・安定的に儲けるハードルは非常に高いと言えます。
一時的に大きな利益を得ても継続しにくい
仮想通貨は短期間で価格が数倍になることもあり、一時的に大きな利益を得ること自体は可能です。しかし、その利益を継続的に維持するのは容易ではありません。
例えば、SNSで話題になっているタイミングで100万円分のビットコインを思い切って購入し、直後に急騰で資産が倍増したとしても、次の急落局面で冷静さを欠いて利確や損切りが遅れると、結局は利益が吹き飛んでしまうケースが多々あります。
実際に、仮想通貨の初期の成功体験に頼りすぎて失敗する人も少なくありません。「もっと儲けられる」と欲張ってポジションを増やし過ぎたり、市場動向の変化に対応できず利益を守りきれなかったりするためです。
このように、一度大勝ちしても油断は禁物であり、利益を継続的に確保する難しさが仮想通貨投資には伴います。
仮想通貨が危険すぎると言われる理由とは

値動きが激しく予測が難しい
仮想通貨の価格は非常に値動きが激しく、短期間で急騰・急落する傾向にあります。法定通貨のように中央銀行による価値の裏付けがないため、需給や市場心理など様々な要因で価格が大きく変動し得ます。
例えばビットコインは数ヶ月で価値が倍増することもあれば、その後わずか数日のうちに半値以下に暴落することも珍しくありません。実際、2021年11月にビットコインが過去最高値を付けた後、わずか数ヶ月で価格が75%以上も下落する暴落が起き、多くの投資家が大きな損失を被りました。
このように値動きの予測が非常に難しい点が、仮想通貨投資の最大のリスクの一つです。
税金が最大55%かかる可能性がある
仮想通貨で利益を得ても、その税金面で大きなハンデがあります。
日本では個人の仮想通貨売買益は「雑所得」として総合課税されるため、利益額によっては所得税・住民税を合わせて最大55%もの税率が適用されます。例えば年間で大きな利益を出した場合、半分以上が税金で持っていかれる計算です。株式や投資信託の譲渡益が一律20.315%の分離課税で済むのに比べると、仮想通貨の税制は非常に厳しく設定されています。
その上、仮想通貨取引では損失を翌年以降に繰り越すことも認められていないため、ある年に大きく儲けて翌年に損失を出しても相殺できず、税負担だけが重く残る可能性があります。こうした税制上の不利さが、仮想通貨は「儲からない」と言われる一因にもなっています。
規制やルールの変更リスクがある
仮想通貨を取り巻く法規制やルールはまだ発展途上であり、変更のリスクが常につきまといます。
実際に日本でも、2017年に改正資金決済法で「仮想通貨」が法律上認められた後、2019年には名称が「暗号資産」に変更され金融商品取引法の規制枠内に組み込まれるなど、大きな制度変更が行われてきました。将来的にも、政府や金融当局の方針次第で取引環境が大きく変化する可能性があります。
例えば海外では、中国が暗号資産の取引やマイニングを禁止したり、米国で証券規制の適用が議論されたりと、各国の対応によってマーケットが急変する事例も見られました。
仮想通貨は新興の金融商品であるがゆえに、規制の強化・変更によって突然これまでのやり方が通用しなくなるリスクを常に意識しておく必要があります。
詐欺の可能性がある
仮想通貨の世界では詐欺的な投資話やスキャンダルも少なくありません。実態のない新興コインへの出資を募って持ち逃げする「ラグプル」や、「必ず儲かる」と謳った高配当を餌に出資金を集めるポンジ・スキームなど、手口は多岐にわたります。
日本の消費者庁も暗号資産に関するトラブルが増加しているとして注意喚起を行っており、実際にマッチングアプリやSNSを通じた投資勧誘から連絡が取れなくなるケースが多発しています。信頼できる業者を装い、最初は少額の利益を出金させて信用させたうえで追加投資を促し、いざ引き出そうとすると「税金」や「手数料」の名目で更なる入金を要求して逃げる――そのような典型的な詐欺も報告されています。
仮想通貨だから特別危険というよりは、新しい技術ゆえに制度や知識の隙を突いた詐欺の温床になりやすい面があり、十分な警戒が必要です。
仮想通貨の取引所がハッキングの被害に遭うリスクがゼロではない
仮想通貨の保管・取引を行う暗号資産交換業者(いわゆる取引所)がハッキング被害に遭うリスクも完全には排除できません。過去には世界最大級だったMt.Gox社が2014年にハッキングされ約490億円相当のビットコインが流出、また2018年には国内のCoincheck社で約580億円相当の暗号資産が盗まれる事件が発生しています。
こうした大規模流出事件では、取引所の補償能力を超える被害額となるケースもあり、最悪の場合ユーザー資産が戻ってこない可能性もあります。銀行預金であればペイオフによる保護がありますが、暗号資産にはそうした公的保護制度はありません。
信頼性の高い取引所ほどセキュリティ対策を強化していますが、それでもハッキングリスクがゼロになるわけではなく、取引所選びや資産の管理には常に注意を払う必要があります。
失敗しやすい人の特徴|こんなタイプは注意

短期間で大きく儲けたいと考えてしまう人
「短期間で一気に大金を儲けたい」という欲が先行してしまうタイプは要注意です。仮想通貨は確かに短期急騰の夢がありますが、短期売買に頼るほど失敗のリスクも高まります。
例えば、SNS上で盛り上がっているからといって数日前にビットコインをまとめ買いし、「すぐに倍にしてやろう」と考える人がいます。しかしそのようなケースでは、ちょっとした悪材料で暴落が起きて数日で数十万円の損失を出してしまうことも現実に起きています。
実際、「みんなが儲かっているから自分も」と焦って飛び乗った結果、数日で給料数ヶ月分を失ったという失敗談も報告されています。短期で大儲けしようとする焦りは冷静な判断を曇らせ、結果として大損につながりかねません。
情報に振り回されて冷静に判断できない人
仮想通貨は日々膨大な情報が飛び交うため、情報に振り回されがちな人も失敗しやすい傾向にあります。
例えばSNSや知人から「このコインが熱い」「今が買い時」といった話を聞くと、十分な裏付けを取らずに飛びついてしまう人です。実際、「周りでみんなビットコインを買っているから大丈夫」と根拠なく信じ込み、相場が高騰している局面で購入してしまった人もいます。
しかし、こうした同調圧力に流された判断は往々にして裏目に出ます。自分で調べず他人の意見に乗っかると、市場急変時にどう対処すべきか分からずパニックに陥りがちです。
仮想通貨投資では、情報収集は大切ですが最後は自分の頭で考える冷静さが求められます。情報過多の状況でも落ち着いて判断できない人は、大きな損失を招くリスクが高いと言えます。
損失が出るとすぐに焦って行動してしまう人
価格が下がって一時的な損失が出ると、慌てて不要な行動を取ってしまう人も注意が必要です。いわゆる「損切り貧乏」やパニック売りに陥りやすいタイプで、含み損が出た途端に冷静さを欠いてしまいます。
例えば、相場急落時に「もうこれ以上耐えられない」と焦って安値で全て売却してしまい、その後の反発で損失を確定させてしまうケースがあります。また逆に、損を早く取り返そうとして無計画にナンピン買い(買い増し)をして傷口を広げることもあります。
仮想通貨の値動きは大きいため、一時的な下落局面で狼狽すると判断を誤りやすいのです。実際に、初心者向けのアドバイスとして「冷静になれないときは取引しない」という言葉があるほどで、感情に駆られて動いてしまう人は長期的に見て不利な結果を招きやすいでしょう。
損失が出ても慌てずに戦略を練り直せる冷静さが、仮想通貨投資では欠かせません。
よくある失敗事例から学ぶ仮想通貨の落とし穴
高値掴みで損をしてしまったケース
「高値掴み」とは、価格がピーク近くまで上がった状態で買ってしまうことです。このケースでは、その後に相場が反転下落し、買値より大幅に下がった価格で売る羽目になり損失を出します。
例えば、2021年末にビットコインが最高値圏にあるときに「まだまだ上がる」と思って購入した投資家の多くは、翌年の暴落で大きな含み損を抱えました。その結果、値上がりの期待から参入した新規投資家の約7割が損失を出す事態になったと分析されています。この事例が示す教訓は、「熱狂期に飛び乗る危険性」です。
マーケットが盛り上がり、多くの人が利益を得ているように見える局面ほど、実は天井が近い可能性があります。人々が楽観しきっている高値局面で無計画に買わないことが、落とし穴を避けるポイントです。
レバレッジ取引で大きな負債を抱えたケース
仮想通貨には、証拠金を担保に資金の数倍もの取引ができるレバレッジ取引(信用取引)の仕組みがあります。このケースでは、レバレッジ取引での失敗により元本以上の損失や大きな負債を抱えてしまった例です。
例えば、手元資金20万円で10倍のレバレッジをかけ、200万円分のビットコインを購入したとします。その後価格が予想に反して下落すると、損失はたちまち手元資金の20万円を超え、追加の証拠金(追証)を入れなければならない事態に陥ります。適切にロスカット(強制決済)されず下落が進めば、借金を背負う形で決済を迎える危険性すらあります。
実際、過去には相場急変時にサーバーダウン等でロスカットが遅れ、多額の追証が発生した例も報告されています。テコの原理で利益を狙うレバレッジ取引は損失も膨らみやすいため、初心者には非常にリスクが高い落とし穴と言えるでしょう。
怪しい投資案件に騙されてしまったケース
仮想通貨の世界では、「誰でも簡単に○倍儲かる」といったうまい話の投資案件に騙されてしまうケースも後を絶ちません。典型的なのは、SNSやマッチングアプリで知り合った人物から儲け話を持ちかけられ、海外の取引プラットフォームへの投資を勧誘される事例です。
例えば、「一緒に暗号資産を運用しないか」と誘われ入金すると、最初は少額でも利益が出て順調に見えるため安心して追加投資してしまいます。しかし、いざ大きな額を投入した後で出金しようとすると、「税金や手数料を支払わないと出金できない」などともっともらしい理由をつけて更なる送金を要求されます。
最終的に連絡が取れなくなり、入金した資金は回収不能になる――これは典型的な暗号資産投資詐欺の手口です。実際に「知り合った外国人女性に勧められ投資し、儲かったので引き出そうとしたら税金名目で追加送金を要求された」という相談事例も報告されています。
このケースから学べるのは、「うまい話」こそ疑う姿勢です。高配当や必勝を謳う投資話には裏があると心得て、安易に乗らないことが肝心です。
仮想通貨投資で必ず押さえておきたい注意点
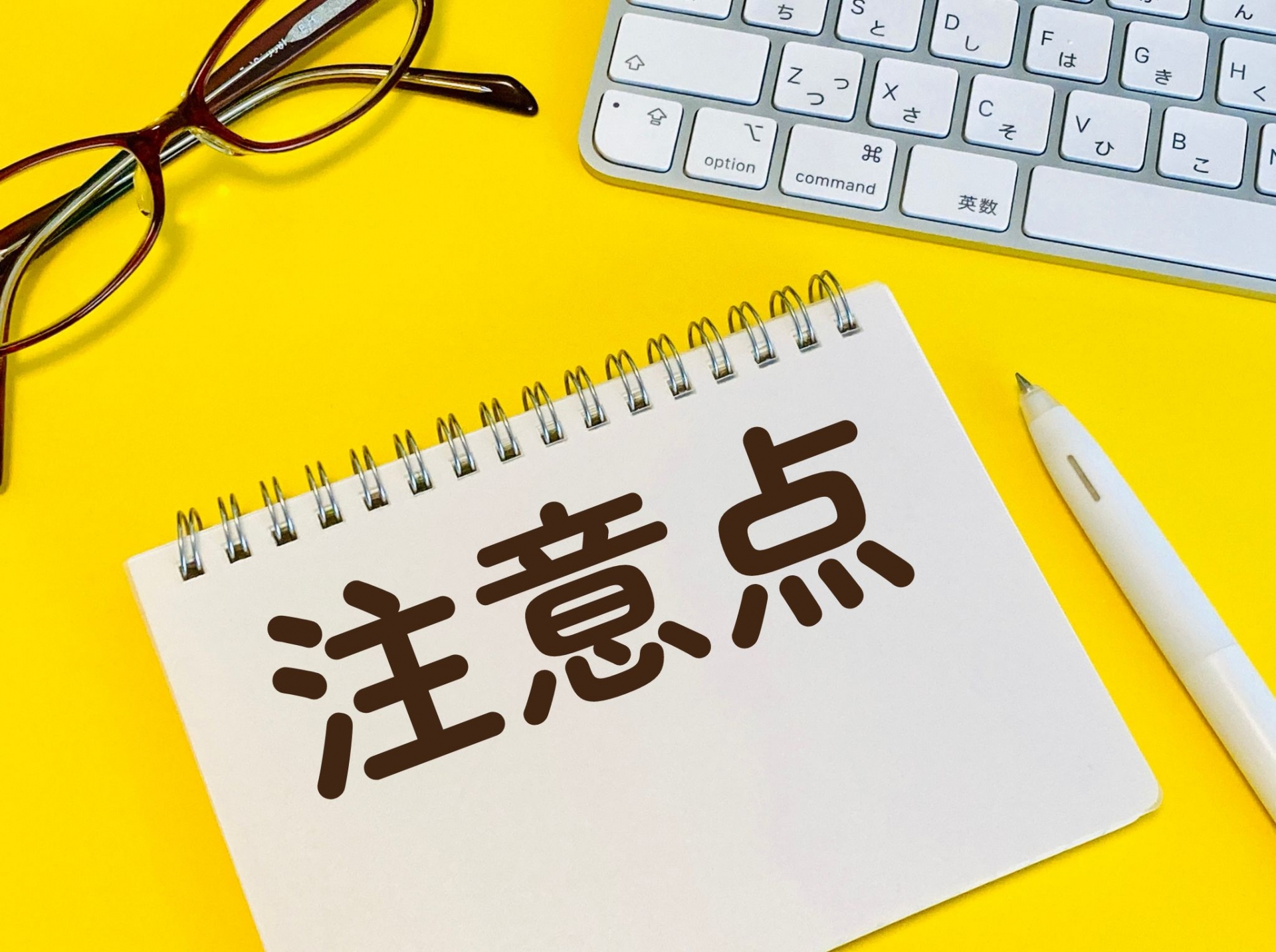
投資額は生活資金に手を出さない範囲にする
仮想通貨に限らず投資全般の鉄則ですが、投資には余裕資金を充てるのが大前提です。日々の生活費や緊急予備資金に手を出してまで投資をすると、想定外の損失発生時に生活が立ち行かなくなるリスクがあります。
暗号資産はハイリスク・ハイリターンな商品であるため、値下がりすれば投資額が一時的にゼロ近くになる可能性も念頭に置かなければなりません。金融庁も「暗号資産取引は価格変動が大きくハイリスクになり得るので、基本は余剰資金で行うべき」と注意喚起しています。
万が一最悪の事態になっても生活に支障が出ない範囲の金額で始めることが、仮想通貨投資の第一の注意点です。
信頼できる取引所を利用することが重要
仮想通貨を購入・保管する際は、信頼性の高い暗号資産交換業者(取引所)を選ぶことが何より重要です。
日本では暗号資産交換業者は金融庁または財務局への登録が義務付けられており、登録業者であるかどうかを必ず確認しましょう。登録業者であれば資本金やセキュリティ体制など一定の基準を満たしていますが、ただ登録しているだけで絶対に安全という保証にはならない点にも注意が必要です。
各社のセキュリティ対策(コールドウォレット保管の有無や二段階認証の提供など)やユーザー評価も確認しましょう。過去にハッキング被害歴のある取引所や、無登録で営業している海外業者は避けるべきです。
自分の資産を預ける場所として信頼できる取引所を選ぶことが、リスク管理の基本となります。
税金や手数料の負担を忘れない
仮想通貨で利益が出ても、税金や各種手数料を差し引いた実質的な利益を意識する必要があります。前述の通り、仮想通貨の利益には累進課税で最大55%もの税金がかかり得るため、思ったほど手元に残らないケースもあります。
また、取引所の売買手数料やスプレッド、入出金や送金時の手数料なども利益を削る要因です。例えば販売所形式でアルトコインを売買すると、買値と売値の差(スプレッド)が実質的なコストとなり、知らないうちに数%分の利益が目減りすることもあります。
こうした見えにくいコスト込みで収支を考えることが大切です。特に大きな利益が出た年は早めに税金分を確保し、翌年の確定申告に備えましょう。
「儲かった」と浮かれて全額を再投資してしまうと、後から税金分が払えず困るといった事態にもなりかねません。必ず税負担と手数料分を見込んだうえで資金計画を立てるようにしましょう。
損をしないために知っておきたい仮想通貨のコツ

少額から試しながら経験を積む
まず重要なのは、少額から投資を始めて徐々に経験を積むことです。仮想通貨は値動きが激しいため、初めから大金を投入すると精神的な負担も大きく、冷静な判断が難しくなります。
最初は数千円〜数万円程度の小さな額で買ってみて、価格変動に慣れるところからスタートしましょう。少額であれば仮に値下がりしても致命傷にはなりませんし、逆に値上がりした場合でも適度な利益確定の練習ができます。
大手取引所も「初心者は少額から始めるべき」とアドバイスしており、実際に経験豊富な投資家ほど初期は無理のない範囲で試行錯誤したと言います。
小さく始めて相場の雰囲気を掴み、勝手が分かってきたら投資額を増やすという段階的なアプローチが、仮想通貨で大損しないための基本的なコツです。
価格変動に一喜一憂せず冷静に対応する
仮想通貨投資では、感情に流されない冷静さが何より大切です。価格が上がったからといって有頂天になってさらに買い増したり、下がったからといってパニックになって投げ売りしたりすると、結果的に高値掴みや安値売りになりがちです。
大事なのは、価格変動に一喜一憂せず自分の投資方針に沿って行動することです。例えば、事前に「○%下落したら損切り」「○%上昇したら一部利確」とルールを決めておき、それを機械的に実行すれば感情に左右されにくくなります。
実際、暗号資産取引で失敗を減らすには「冷静になれない時は取引しない」ことが重要だと指摘されています。急騰局面でも浮かれず、急落局面でも慌てず平常心を保つメンタルコントロールが、仮想通貨とうまく付き合うための秘訣です。
長期目線で資産運用を考える
仮想通貨は短期的な値動きに注目が集まりやすいですが、長期目線での資産運用を心がけることも大切です。
日々の乱高下に振り回されるのではなく、数年スパンで将来性を見据えて投資するというスタンスです。例えば、ビットコインやイーサリアムなど主要な暗号資産は長期的には技術の普及や需給に伴い価値が向上すると見込んで、コツコツ積立投資を続ける方法があります。
金融庁も推奨する「長期・積立・分散」の考え方は暗号資産にも当てはまり、時間を分散した積立によって平均購入単価を平準化し、リスクを軽減する効果が期待できます。実際、短期売買で頻繁に利ザヤを狙うよりも、腹を据えてじっくり保有した方が成果を上げた投資家も存在します。
焦らず長い目で構えて保有・運用することで、仮想通貨市場の成長の恩恵を受けやすくなるでしょう。
リスクを知った上で検討すべき「分散投資」という考え方
仮想通貨だけに資金を集中させないことが大切
仮想通貨だけに全財産を注ぎ込まないことは鉄則です。資金を一つの資産に集中させると、その資産が値下がりした時に大打撃を受けます。
特に仮想通貨は先述の通り値動きが極端に大きいため、もし暴落局面に直面すれば資産全体が大幅に目減りしてしまう危険があります。財務局の投資啓発資料でも「資金を一つの資産や銘柄に集中せず、複数の種類に分散投資すればリスクが分散されリターンの安定度が増す効果がある」と説明されています。
たとえ仮想通貨に将来性を感じていても、資産の一部に留めて他の安定資産にも振り分けておくことで、万一の下落局面でもダメージを軽減できます。「卵を一つのカゴに盛るな」という格言を肝に銘じ、仮想通貨一点張りの投資は避けましょう。
株式や債券など他の資産と組み合わせるメリット
分散投資の具体策として、仮想通貨以外の伝統的な資産クラスとも組み合わせて保有することが挙げられます。例えば、値動きの異なる株式や債券、不動産ファンドなどと仮想通貨をバランスよく持つことで、一方の損失を他方の利益で補える可能性があります。
地域面でも、日本国内資産だけでなく米国株や新興国債券などに広げれば、特定の国の経済状況に左右されにくくなります。実際、「国際的な分散投資を進めることで、より安定的に世界経済成長の果実を得ることが期待できる」とも指摘されています。
仮想通貨はリスクもリターンも大きい資産ですが、値動きの方向性が異なる資産と組み合わせることでポートフォリオ全体の安定性を高める効果が期待できます。異なる資産同士を組み合わせた複数のカゴに資産を分散して持つイメージで、全体のリスクをコントロールしましょう。
リスクを分散することで安定した資産形成を目指せる
分散投資の最終的なメリットは、リスクを抑えつつ安定した資産形成を目指せる点にあります。仮に仮想通貨だけに集中投資していた場合、価格暴落時には資産価値が大きく棄損するかもしれません。
しかし、株式・債券・仮想通貨・現金など複数に分散していれば、一部の下落を他の部分でカバーできる可能性が高まります。分散投資を実践することで価格の変動をある程度抑えて、安定的な運用を目指すことができるとされています。
リスクとリターンのバランスを考慮し、自分の許容範囲内で複数資産に資金を配分することが、長期的に資産を増やしていく上で重要です。適切にリスクを分散しながら、自身のリスク許容度に見合ったポートフォリオを構築することで、仮想通貨も含めた安定的な資産形成への道が開けるでしょう。
少額から始められる堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】仮想通貨に関するよくある質問

仮想通貨はこれからも儲かるの?
仮想通貨がこれから必ず儲かるとは限りません。
ボラティリティが非常に高く、実際に小口投資家の約75%がビットコイン取引で損失を出したとの調査結果もあります。例えばビットコインは最高値から数ヶ月で価格が75%以上暴落したこともあり、短期的な利益が長続きしないケースが多いです。
仮想通貨は危険と言われるけど実際どうなの?
はい、仮想通貨には大きなリスクが伴うため「危険」と言われるのは事実です。
価格変動が激しく、一夜で資産が半減する可能性があるうえ、詐欺やハッキング被害などトラブルも増加しています。例えば2018年には国内取引所から約580億円相当の暗号資産が流出するハッキング事件も起きており、適切な対策なしに手を出すと大きな損失を被る危険があります。
仮想通貨は今から始めても大丈夫?
仮想通貨は今からでも始められますが、慎重な準備と姿勢が必要です。
日本では取引環境の整備が進み安全性は向上していますが、余裕資金で少額から始める・基礎知識を身に付けておくといった自己防衛策が欠かせません。例えば金融庁に登録済みの信頼性の高い取引所を利用し、分散投資や長期運用を組み合わせることで、リスクを抑えつつ仮想通貨を運用することが可能です。
まとめ|仮想通貨は儲からない?危険性を理解して賢く向き合おう
仮想通貨は「楽に儲からない」どころか、高いボラティリティや最大55%にも及ぶ税負担など、利益を得続けるハードルが非常に高い投資対象です。しかし、リスク要因を正しく理解し、少額・長期・分散の運用を徹底すれば、仮想通貨とも賢く付き合いながら資産形成を図ることは可能です。
つまり、儲け話に踊らされるのではなく、リスクと向き合い戦略的に活用できるかが鍵と言えるでしょう。
【脚注】本記事で使用している「仮想通貨」と「暗号資産」は同義です。これは一般的な理解に合わせた表記であり、法律上の用語「暗号資産」として扱っています。
参考元
・国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」
・国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱い及び計算書について」
・国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)」
・金融庁「仮想通貨交換業者に対するシステムリスク管理態勢の自己点検について」
・金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」
・金融庁「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」
・金融庁「事務局説明資料(暗号資産に係る規制の見直しについて)」
・金融庁「暗号資産に関するトラブルにご注意ください!」
・国民生活センター「友人・知人からの誘いをきっかけとした暗号資産のトラブル」
・消費者庁「『消費者被害の実態』~被害救済の現場・その課題~」
・国民生活センター「暗号資産に関する消費者トラブル」