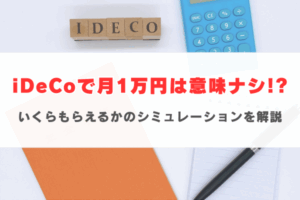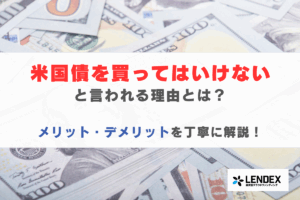「つみたてNISAでは銘柄をいくつ買うべきか?」と初心者の方は一度は疑問に思うのではないでしょうか。つみたてNISAは少額から長期・分散投資ができる魅力的な制度ですが、実際に何銘柄に投資すればよいか迷う人も多いようです。
そこで本記事では、つみたてNISAの基本と2024年からの制度変更をおさらいしつつ、銘柄数の考え方や分散投資のコツを解説します。初心者におすすめの銘柄数や選び方、分散投資の基本戦略、そしてリスクを抑えながらリターンを狙う方法まで、わかりやすく紹介します。迷ったときの参考にしていただき、安心して資産形成を進めていきましょう。
つみたてNISAの基本をおさらい|制度の概要と対象銘柄

つみたてNISAは2018年にスタートした、長期の積立投資に適した少額投資非課税制度(NISA)の一種です。投資で得た利益が一定期間非課税になる仕組みで、初心者でも少額からコツコツ資産形成を始めやすいのが特徴です。まずは制度の概要と対象となる商品について整理してみましょう。
つみたてNISAとは?2024年からの制度変更も解説
つみたてNISAは、少額からの長期・積立・分散投資を支援するために設けられた日本の非課税制度です。年間の投資上限額内で購入した投資信託の売却益や配当金が非課税となるため、資産形成を後押ししてくれます。
2024年からNISA制度が刷新され、一般NISAとつみたてNISAは新しいNISA制度の下で「成長投資枠」と「つみたて投資枠」に一本化されました。これに伴い、非課税保有期間が無期限化され、長期にわたって非課税メリットを享受できるようになった点が大きな変更ポイントです。
従来のつみたてNISAでは年間40万円、最長20年間までの積立が非課税対象でしたが、新NISA制度ではつみたて投資枠が年間120万円へと拡充されました(一般NISAに相当する成長投資枠は年間240万円)。その結果、年間最大360万円まで新NISA口座で非課税投資が可能になっています。
また、生涯で非課税運用できる非課税保有限度額も大幅に引き上げられ、従来の合計800万円(つみたてNISAは累計800万円、一般NISAは累計600万円)から1,800万円へと拡大されています。
※新NISA制度のポイント補足:年間最大360万円という非課税投資枠は、「つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円」を併用した合計額であり、成長投資枠単独で360万円を投資することはできません。また、生涯非課税保有限度額1,800万円のうち、成長投資枠で運用できるのは最大1,200万円までという制限が設けられている点にも注意が必要です。
投資できる商品は?インデックスファンド・アクティブファンドの違い
つみたてNISAで投資できる商品は、金融庁により一定の要件を満たすものに限定されています。具体的には、長期の積立・分散投資に適した投資信託やETFのみが対象です。手数料(信託報酬)が低水準であることや、毎月分配型でないこと、元本保証商品でないことなどの条件をクリアした商品が選定されています。基本的には国内外の株式や債券に幅広く分散投資するインデックスファンドが中心ですが、一部にはアクティブファンドやバランスファンドも含まれています。
インデックスファンドは日経平均株価やS&P500などの株価指数と連動する運用を行うファンドで、銘柄選びや売買の判断を人が行わないため信託報酬(運用管理費用)が低めです。市場全体の平均リターンを狙うため大きな失敗が少なく、安定した運用が期待できます。
一方、アクティブファンドはファンドマネージャーが独自の運用戦略で銘柄選択を行い、市場平均を上回るリターンを狙うファンドです。運用コストは高めですが、運用が成功すれば指数を上回る利益を得られる可能性もあります。ただし、上手くいかなければインデックスに劣る結果となる場合もあります。
内訳を見ると、国内株式や先進国株式、全世界株式といった株式型のインデックスファンドが多数を占めていますが、一部にはバランス型(株式と債券を組み合わせたファンド)や優良なアクティブファンドも含まれます。
初めての方は、信託報酬の低いインデックスファンドを中心に検討するのがおすすめです。インデックス型なら一つのファンドで国内外の多数の銘柄に分散投資されているものも多く、少ない銘柄数でもしっかり分散効果が得られます。
なお、対象商品のラインナップは年々拡充されており、2025年6月5日時点では、つみたてNISAの対象商品数は合計325本にも上ります。その内訳は、インデックス型投資信託が260本、アクティブ型投資信託が57本、ETF(上場投資信託)が8本となっており、投資初心者でも選びやすい低コスト商品が数多く含まれています。これらのファンドは長期の積立投資に適した商品ばかりなので、自分のリスク許容度や投資目的に合ったものを選ぶと良いでしょう。
つみたてNISAで「銘柄はいくつ買うべきか?」という疑問に答えます

つみたてNISAを始めるにあたり、「結局いくつの銘柄に分けて積み立てるのが良いのだろう?」という疑問はよく聞かれます。結論から言えば、特に投資初心者の場合、選ぶ銘柄数は少数に絞るのがおすすめです。もちろん適切な分散は大切ですが、だからといって闇雲に数を増やせば良いわけではありません。
この章では、1本にまとめる場合と複数に分散する場合のメリット・デメリットを比較し、初心者に適した銘柄数の目安と選び方について考えてみましょう。
1本に絞る vs 複数に分ける|メリット・デメリットを比較
つみたてNISAの積立先を1本に絞る場合と、複数のファンドに分散する場合では、それぞれ利点と注意点があります。以下に両者のメリット・デメリットを整理してみましょう。
1本にまとめて積み立てる場合
-
- メリット:管理が簡単で迷いが少なくて済みます。積立先を一つに絞ることで運用状況を把握しやすく、リバランス(資産配分の調整)などの手間もかかりません。また、資金を一つのファンドに集中できるため、分散しすぎてリターンが埋もれにくいという利点もあります。
- デメリット:投資先が一つだけだと、そのファンド特有の運用リスクに偏ってしまう可能性があります。例えば選んだファンドが特定の地域に集中投資している場合、その地域の景気低迷の影響をまともに受けてしまいます。また、ファンド自体の運用方針変更や成績不振など「そのファンド固有のリスク」に全額がさらされる点には注意が必要です。
複数の銘柄に分散して積み立てる場合
-
-
- メリット:ファンドを複数組み合わせることで、より広い分野への分散効果が期待できます。例えば「日本株式+米国株式」のように性質の異なるファンドを組み合わせれば、一方が不調でも他方でカバーし、ポートフォリオ全体のリスクを抑えやすくなります。
- デメリット:銘柄数が増えると管理の手間が増します。また、あまりに分散しすぎると、投資額が薄まりリターンも分散してしまいます。中身が重複する似たようなファンドを複数持っても効率が悪いだけなので注意しましょう。
-
投資初心者におすすめの銘柄数は?目安と選び方
以上を踏まえると、投資初心者には「少数精鋭」のポートフォリオがおすすめです。具体的には、つみたてNISAで積み立てるファンドは1本、多くても2本程度で十分と言えます。実際、多くのファイナンシャルプランナーも「初心者ならまずインデックス投資信託を1〜2本に絞るだけで問題ない」と助言しています。銘柄数を絞った方が管理がしやすく長期運用を続けやすいためです。
もし1本だけ選ぶなら、全世界株式インデックスファンドのようにこれ一本で世界中の株式に幅広く投資できる商品が良いでしょう。信託報酬が低く、組入銘柄も国際分散されているファンドであれば、初心者でも安心して長期間ホールドできます。例えば全世界株式インデックスファンドや先進国株式インデックスファンドなどが該当します。
2本組み合わせる場合は、投資対象が重ならないように工夫しましょう。例えば「全世界株式+国内株式」のように投資対象が重ならない組み合わせにすると良いです。銘柄数は2〜3本に留め、自分が管理できる範囲に抑えましょう。分散は大事ですが、どれをどれだけ保有しているか把握できなくなると本末転倒です。迷ったら、まずは人気の高いインデックスファンド1本から始め、慣れてきたら必要に応じてもう1本追加する程度で十分でしょう。
大切なのは、シンプルで分かりやすいポートフォリオで長期運用を続けることです。
※2025年の投資環境トレンド:ここ数年の投資信託の動向を見ると、米国株式(S&P500)連動型インデックスファンドの根強い人気が続いています。一方で、全世界株式インデックスファンドの持つ分散効果が再評価されており、長期分散投資の選択肢として注目が集まっています。さらに、近年はESG(環境・社会・ガバナンス)重視のファンドや特定テーマ型の投資信託の設定も増加傾向にあり、サステナビリティやテーマ性に着目した商品も初心者から上級者まで関心を集めるようになっています。こうしたトレンドも踏まえつつ、自分に合った銘柄選びを心がけましょう。
分散投資の基本戦略|初心者が押さえるべき3つの分散

投資でリスクを減らし安定したリターンを得るためには「分散投資」が鍵になります。分散投資とは、資金を一箇所ではなく複数の異なる対象に振り分けて投資することです。一つの対象に全額投資すると、もしそれが不調だった場合に資産全体が大きく目減りしてしまいますが、分散しておけば一部の不調を他の好調で補える可能性が高まります。
初心者が押さえておきたい分散投資の基本戦略として、「資産クラスの分散」「地域の分散」「時間の分散」の3つがよく挙げられます。それぞれ順に見ていきましょう。
資産クラスの分散(株式・債券など)
資産クラスの分散とは、異なる種類の資産に投資することです。代表的な資産クラスには、株式(株式市場への投資)、債券(国債や社債への投資)、不動産(REITなど不動産関連資産への投資)、現金・預金などがあります。値動きの性質が異なる資産を組み合わせることで、特定の資産が不調なときに他の資産がポートフォリオを下支えしてくれる効果が期待できます。
例えば、株式はリスクが高いものの長期的な成長が見込める資産です。一方、債券は株式ほど大きく値上がりしませんが価格変動が小さく安定した利息収入が得られます。株式と債券を組み合わせれば、高いリターンを狙いつつ急落時の下落幅を和らげることができます。実際、伝統的な運用では「株式:債券」を組み合わせたポートフォリオがリスク分散の基本とされています。
初心者の場合、つみたてNISAでは株式型の投資信託が中心になりますが、バランス型ファンドを活用したり、NISA以外の口座で債券ETFや預金を保有するなどして、トータルでは資産クラスの分散を図ると安心です。
地域の分散(国内・先進国・新興国)
地域の分散とは、投資対象の国や地域を分けることです。国ごとに経済成長率や市場の動きは異なるため、投資地域を広げることで一国の不調リスクを軽減できます。具体的には、国内(日本)、先進国(米国や欧州など)、新興国(アジアや南米など新興市場)といった具合に分散させるのが一般的です。
例えば日本株だけに投資していると、日本経済が長期停滞した場合に資産も伸び悩むリスクがあります。実際、バブル崩壊後の日本株は長く低迷しましたが、その間に米国株式や新興国株式は大きく成長しました。一国だけに頼るのは危険であり、世界全体に目を向けた分散が重要です。幸い、インデックスファンドを活用すれば簡単に地域分散ができます。先述の全世界株式インデックスファンドは一つで日本・先進国・新興国の株式市場を網羅していますし、「先進国株式インデックス+新興国株式インデックス」のように2本で広範囲をカバーする方法もあります。
自分の投資方針に合わせて、ホームカントリーバイアス(自国贔屓)に陥らないよう意識しましょう。世界経済の成長をまんべんなく取り込むことが、長期投資で効率よく資産を増やすコツです。
時間の分散(ドルコスト平均法)
時間の分散とは、投資するタイミングを分散させることです。将来の相場が上がるか下がるかを正確に当てるのはプロでも難しいため、一度にまとめて投資する(一括投資)よりも時間を分散して投資した方がリスクを抑えられます。典型的なのがドルコスト平均法と呼ばれる手法で、価格に関係なく定期的に一定額を買い続ける積立投資のことです。
ドルコスト平均法では、価格が高いときは少ない口数しか買えず、価格が安いときには多くの口数を買うことになります。その結果、購入価格が平均化され、高値掴みのリスクを軽減できるのです。つみたてNISAはまさにこのドルコスト平均法による長期積立を促す仕組みになっており、毎月一定額をコツコツ投資することで時間分散の効果を自動的に享受できます。相場の上下に一喜一憂せず、時間を味方につけて着実に資産形成を進めましょう。
分散投資の考え方とコツ

基本的な分散投資の方法を押さえたところで、もう少し実践的な考え方やコツにも触れておきます。分散と一口に言っても様々な切り口がありますが、ここでは「資産クラス」「地域」「業種」の分散について整理し、さらに投資において重要な心構えについて確認しましょう。
「資産クラス」「地域」「業種」の分散とは
先ほど資産クラスと地域の分散について説明しましたが、株式投資の範囲内でも業種(セクター)の分散を意識することが重要です。業種とは企業の事業分野のことで、IT・金融・ヘルスケア・エネルギーなど様々なセクターがあります。例えば市場全体が好調でも、特定の業種だけ業績不振で株価が低迷することもあります。もしポートフォリオがその業種の株式に偏っていれば、市場全体は上昇しているのに自分の資産は思うように増えない、という事態も起こりえます。
しかし、広く分散されたインデックスファンドを利用すれば個別に業種の比率を調整しなくても市場全体に投資できます。例えばS&P500指数に連動するインデックスファンドであれば、情報技術から生活必需品まで米国経済の主要業種を網羅しています。ただ、もしテーマ特化型のファンドや個別株に投資する場合は、なるべく複数の業種が混ざるように組み合わせると偏りが和らぎます。
分散投資の基本は「異なる特徴を持つものを組み合わせる」ことです。資産クラスしかり、地域しかり、業種しかり、性質の異なる対象をバランスよく取り入れることを心がけましょう。
タイミングよりも長期・積立・分散がカギ
投資で成功するためのコツは、「タイミングを計ることよりも、長期でコツコツ続けること」です。短期的な相場の上下に振り回され、「今が買い時か?」「売るべきか?」と頻繁に売買タイミングを図るのは初心者には難しく、かえって失敗しやすい行動です。プロでさえ市場の短期変動を完璧に予測するのは困難と言われています。そのため、長期・積立・分散の3原則こそが資産形成の王道なのです。
具体的には、つみたてNISAの非課税枠を活用して長期にわたり積立投資を続けることで、時間の分散によるリスク軽減と複利効果を最大限に享受できます。相場が暴落してもすぐにやめず、むしろ安値で買い増しのチャンスと捉えて継続することが大切です。また、一つの資産クラスや地域に偏らず、常に分散を意識することで大きな失敗を防ぎやすくなります。派手な売買テクニックよりも、地道に続ける長期・積立・分散こそが資産形成の近道だと心得ましょう。
よくある失敗例から学ぶ!銘柄の分けすぎ・偏りのリスク

ここまで分散投資の重要性について述べてきましたが、実際には「分散しているつもりが逆効果」になってしまうケースもあります。銘柄数を増やしすぎて管理しきれなくなったり、分散しているつもりでも実は中身が偏っていたりといった失敗例です。そこで、よくあるケースを取り上げ、そのリスクと対処法について考えてみましょう。
保有しすぎて管理できないケース
「つい手を広げすぎて管理できなくなる」これは初心者によくある失敗です。つみたてNISAで5~6本もファンドを積み立てると、各ファンドの状況を把握しきれず、自分が何にどれだけ投資しているのか分からなくなりがちです。
ファンド数が増えるほど運用状況の確認や配分調整など管理作業も増えていきます。多忙な中で数多くの投資商品を把握するのは難しく、結果的に運用が雑になってしまいかねません。適切に管理できなければ分散投資の意味もないので、管理しきれないほど持つのは本末転倒です。
対策としては、やはり銘柄数を絞るのが一番です。自分がしっかりフォローできる範囲内の数(初心者なら1〜3本程度)に留め、定期的に資産状況をチェックしましょう。また、複数ファンドを持つ場合も、それぞれの役割を明確にしておくことが大切です。「Aファンドはコア(中心)として長期保有、Bファンドは補完的に少額」といったように、自分の中で位置付けをはっきりさせておけば混乱しにくくなります。
同じ市場ばかりに偏るとどうなるか?
一見分散しているようでも、投資対象の中身を見ると偏っているというケースも注意が必要です。例えば名称が違っても投資先が全部日本株ファンドばかりでは、市場が下落すれば保有ファンドがすべて下落する可能性が高く、分散の意味がありません。同様に、投資対象の業種が偏っていてもリスク低減にはつながらない点に注意しましょう。
偏りすぎのリスクに対処するには、まず自分のポートフォリオの中身を定期的に点検することが大切です。それぞれのファンドが主にどの地域・業種に投資しているのか確認しましょう。もし特定の市場やセクターに集中しているようであれば、別の地域のファンドを追加したり、そのセクター以外に投資する商品に乗り換えるなどの対応を検討します。
つみたてNISAの対象ファンドは基本的に分散された商品が多いとはいえ、組み合わせ方によっては思わぬ偏りが生じるので油断は禁物です。「自分は何に投資しているのか?」を意識し、バランスよく配置する習慣をつけましょう。
リスクを抑えながらリターンを狙うなら?分散+別資産の活用

ここまで、つみたてNISA内での分散について述べてきましたが、資産運用全体の視点では「NISAだけに頼らず、他の資産クラスも組み合わせる」ことも重要です。つみたてNISAは株式中心の投資となるため、市場変動リスクはどうしても伴います。そこで、株式以外の値動きが異なる資産もポートフォリオに取り入れることで、リスクを抑えつつリターンを追求することが可能になります。
つみたてNISAだけに依存しない理由
つみたてNISAは非課税の恩恵が大きく、資産形成に非常に有用な制度ですが、「つみたてNISA=万能」というわけではありません。まず、NISAには年間投資額の上限があるため、より大きな額を運用したい場合にはNISA以外の枠も必要になります。また、投資できる商品が投資信託に限定されるため、扱える資産クラスは主に株式や一部債券が中心です。現金・預金や不動産など、株式以外の資産に関してはNISA口座の外で運用する必要があります。
さらに、マーケットリスク(市場変動リスク)への備えも考慮すべきです。長期的には株式市場の成長が期待できますが、短期的には暴落もありえます。NISA口座内がすべて株式ファンドだと、暴落時には評価額が大きく目減りし精神的にも厳しくなるでしょう。そうした局面でも資産運用を継続するには、値動きの異なる別の資産を持っておくことが有効です。株式市場が低迷している間でも他の資産から安定的な収益が得られれば、ポートフォリオ全体のバランスが保てます。
要するに、つみたてNISAの株式投資+他の資産という組み合わせで、より堅牢な資産形成プランを構築できるのです。次の項目では、その「他の資産」の一例として注目されている融資型クラウドファンディングを紹介します。
分散投資の選択肢に「融資型クラファン」という方法もある
融資型クラウドファンディング(融資型クラファン)とは、インターネット上で資金を集めて企業などに貸し付け、利息収入を得る仕組みです。投資家は貸し手側として利息を受け取れる点が特徴で、ソーシャルレンディングとも呼ばれます。
融資型クラファンの利点は、価格の値動きがない資産であることです。株式や投資信託のように日々価格が上下しないため、一度投資すれば満期まで基本的に元本額が保たれ(※途中解約不可、貸し倒れリスクあり)、定期的に利息(分配金)が支払われます。言い換えれば、株式市場の暴落に影響されず、契約上決まった利息収入を得られる可能性が高い資産です。そのため、株式偏重のポートフォリオに組み入れることでリスク分散効果が期待できます。株価が低迷しているときでも、融資型クラファンからの利息収入が見込めれば、精神的にも安定して運用を続けやすくなるでしょう。
また、融資型クラファンは比較的高い利回りも魅力です。案件にもよりますが、年利換算で5〜10%前後の利回りが設定されたファンドが多く、銀行預金や国債と比べても格段に高い収益性を期待できます。ただし、表面上の利回りが高い案件はそれだけ貸し倒れリスクも高い可能性があるため、利回りの数字だけで飛びつくのは禁物です。事業者の信頼性や案件内容、担保や保証の有無などをよく確認した上で、まずは少額から試してみるとよいでしょう。
こうした株式以外の選択肢も活用しながら、ポートフォリオ全体でリスクとリターンのバランスを取ることが重要です。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
つみたてNISAの銘柄選びまとめ|迷ったら「少数精鋭&分散」
最後に、本記事のポイントをまとめます。つみたてNISAでどの銘柄を選ぶか迷ったら、基本は「少数精鋭」で分散を効かせることを意識しましょう。具体的には、低コストで分散効果の高い優良ファンドを1〜2本選び、長期にわたってコツコツ積み立てるのがおすすめです。十分に分散されたインデックスファンドであれば1本でも世界中の資産に投資できますし、必要に応じて性質の異なるファンドをもう1本加える程度でじゅうぶんリスク分散が図れます。
分散投資の基本である「資産クラス・地域・時間の分散」を踏まえつつ、難しいタイミングを考えるよりも長期目線で継続することが何より重要です。そして、株式偏重になりすぎないようNISA以外の資産も取り入れておけば、さらに安心感のある運用ができるでしょう。今回紹介したLENDEXのような融資型クラウドファンディングも活用しながら、自分なりの分散ポートフォリオを構築してみてください。
少数精鋭の銘柄選びと賢い分散投資で、つみたてNISAを上手に活用し、初心者から着実に資産形成を進めていきましょう。
参考元
- 金融庁(Financial Services Agency)NISAを知る:NISA特設ウェブサイト
- 金融広報中央委員会:知るぽると
- 一般社団法人全国銀行協会:投資のリスクを減らすポイントは「分散投資」と「長期投資」