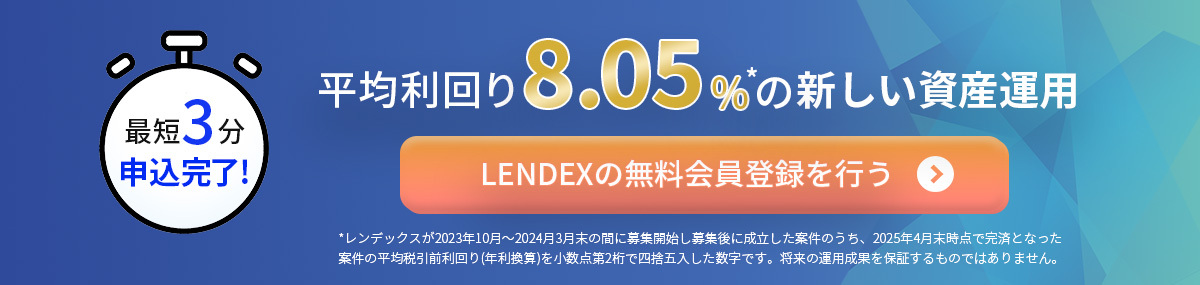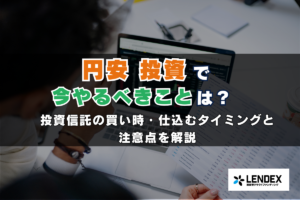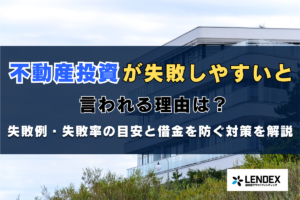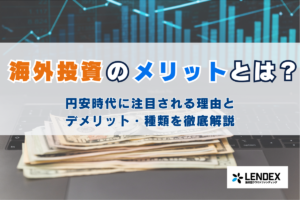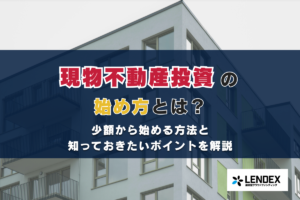近年、副収入や資産形成の手段として「ワンルームマンション投資」が注目を集めています。少額から始められることや安定した家賃収入が期待できることから、会社員や初心者投資家にも広がりを見せています。
しかし一方で、「ワンルームマンション投資は失敗しやすい」という声も少なくありません。実際に国民生活センターには、物件購入後に思うような収益が得られず、ローン返済や維持費に苦しむといった相談が多数寄せられています。
では、なぜワンルームマンション投資は失敗しやすいのでしょうか。
本記事では、その背景やよくある失敗事例を整理し、投資を検討する際に押さえておくべきポイントやリスク対策について、初心者にもわかりやすく専門的に解説していきます。
ワンルームマンション投資は失敗しやすい?結論から解説

ワンルームマンション投資は失敗リスクが高い
ワンルームマンション投資は、思った以上にさまざまなリスクを抱えており、慎重さが求められる投資です。
国民生活センターも「マンションへの投資にはリスクがあり、必ず収益が得られるわけではない」と注意を促しており、物件価格の妥当性や将来の家賃収入、維持費、ローン返済額など多角的に検討する必要があるとしています。こうした点を十分に確認せずに契約してしまうと、期待した収益が得られず失敗につながる可能性が高まります。
実際、家賃保証や高利回りといった宣伝文句があっても、空室や修繕費、返済負担によって想定より利益が残らない事例も報告されています。このように、安易な判断は失敗リスクを大きくする要因になり得ます。
初心者にとっては成功よりも失敗する可能性が大きい
不動産投資を始めたばかりの人にとって、ワンルームマンション投資は収益を思うように上げられないケースが多く見られます。
高利回りをうたう広告は多く存在しますが、実際に安定した成果を得られるのは一部の投資家に限られると指摘されています。知識や判断材料が不足していると、営業担当者の説明をそのまま信じてしまい、誤った判断につながりやすい点もリスクです。
国民生活センターの報告でも、若年層の経験不足を狙った勧誘事例が確認されており、十分な準備なしに始めた場合には失敗を招きやすいとされています。収支計画の甘さやリスク軽視が絡むと後悔につながる可能性が高まるため、始めたばかりの人こそ特に慎重に判断することが重要です。
ワンルームマンション投資のメリット・デメリット

ワンルームマンション投資のメリット
比較的少額の自己資金から始めやすいのがワンルームマンション投資の大きなメリットです。
物件価格が一棟マンションや戸建てに比べて低いためローンを活用しやすく、家賃収入による安定したインカムゲインを毎月得られる可能性があります。特に都心の駅近物件など需要が見込める立地を選べば、空室リスクを抑えて長期的な収益源としやすい点は魅力です。さらに、高所得者の場合は減価償却による節税効果が見込めるケースもあります。
また、ローンには団体信用生命保険が付帯されるため、自身に万一のことがあっても残債が免除され、家族に資産としてマンションを残せるという「生命保険代わり」の側面もあります。
こうした点から、ワンルームマンション投資は初心者が最初に取り組みやすい不動産投資とも言われています。
ワンルームマンション投資のデメリット
一方で、ワンルームマンション投資には無視できないデメリットも存在します。代表的なのは、入居者がつかず家賃収入が途絶える可能性がある点です。物件はローン返済や管理費・修繕積立金といった固定的な支出を伴うため、収入が途切れると赤字に直結します。
また、築年数の経過とともに資産価値が下がりやすく、売却を検討した際に購入時よりも大幅に値下がりするケースもあります。さらに建物や設備の老朽化による修繕費負担も重くなり、収益を圧迫する要因となります。加えて、金利上昇や家賃相場の下落といった外部環境の変化も、投資収支を不安定にするリスクです。
このように、ワンルームマンション投資は「安定収入が得られる」と言われる一方で、多方面から収益を損なう要因を抱えており、事前に十分な理解と対策が必要です。
ワンルームマンション投資が失敗しやすい5つの理由
空室が長期化して家賃収入が途絶えるリスクがある
ワンルームマンション投資では入居者がいなければ収入がゼロになるため、空室が長引けば家賃収入が途絶えて大きな打撃となります。特に需要の乏しい地域や周辺に競合物件が増えた場合、新たな入居者がなかなか見つからず、収入ゼロの期間が続くリスクが高まります。
実際、目黒区のワンルーム3室を所有していた投資家の事例では、近隣に大型マンションが新築された影響で3室中2室が半年以上も空室となり、家賃を1万円以上下げてようやく入居者が見つかったケースがあります。
このように空室が長期化すると家賃収入が途絶え、その間もローン返済や管理費はかかるため、収支計画が大きく狂ってしまいます。一棟アパートと違い、一戸が空けば収入がゼロになる区分投資では、この空室リスクは特に深刻です。
修繕費や管理費など想定外の支出が発生する可能性がある
ワンルームマンション投資では、修繕費や管理費、税金などオーナーが負担すべき費用がかかります。築年数の経過とともに設備の故障や建物の劣化で大規模修繕が必要になる場合があり、予想外の出費が発生して収益を圧迫する恐れがあります。
さらに固定資産税の負担も毎年発生するため、予想外に出費が増えれば利益が一層圧迫されることになります。
例えば、購入当初は毎月数千円だった修繕積立金が数年後に値上げされ、それによって当初の収支計画が大きく狂ってしまったという事例もあります。また、エアコンや給湯器の交換など各部屋内の設備更新費用もオーナー負担となるため、常に一定の修繕積立を行って備えておく必要があります。
築年数の経過とともに資産価値が下がりやすいリスクがある
ワンルームマンションは建物の老朽化に伴い資産価値が年々下がっていく傾向があります。新築時が価格のピークで、その後は築年数の経過とともに売却価格が下落しやすく、特に築古物件では購入価格を大きく下回る値しか付かない場合もあります。
実際、建物や設備の老朽化による価値下落リスクは常に存在し、築年数が進むほど物件の資産価値は目減りしていくため、想定していた利益が得られなくなる可能性が高まります。なお、築古になるほど賃料水準も下がりやすく、年月とともに家賃収入と資産価値の双方が目減りしていく点にも留意が必要です。
このため長期間保有した場合、売却してもローン残債を完済できない、いわゆるオーバーローン状態に陥るリスクにも注意が必要です。
売却時に購入価格より大幅に値下がりする可能性がある
投資用ワンルームは売却時に購入時より価格が大きく下落している恐れもあり、売却損が出るリスクが高いです。
新築時に高値で購入した場合、数年後の売却価格は購入額を大きく下回るケースが多く、結果として手元に残るお金がほとんどないどころか損失が出る可能性もあります。実際の事例では、フルローンで購入した物件を売却する際に市場価格が残債を大きく下回り、1室あたり約1,800万円の相場価格に対して残債が2,100万円弱という状態で、3室合計で約900万円もの赤字が見込まれたケースが報告されています。
このように売却時に大幅な値下がりが生じると、投資期間全体で見れば利益どころか大きなマイナスに転じてしまうこともあるのです。
金利上昇や借入条件の変化で返済が厳しくなるリスクがある
不動産投資ローンの多くは変動金利で組まれるため、市場金利が上昇すればそれに伴い毎月の返済額が増え、キャッシュフローを大きく圧迫する重大なリスクがあります。
実際に日本銀行が2024年にゼロ金利政策を解除し政策金利を引き上げ始めたことで、今後はローン金利の上昇局面も予想されます。金利が上がれば借入コストが増えて家賃収入だけでは返済を賄えなくなる可能性があり、最悪の場合は手元資金から赤字補填を強いられたり、物件を手放さざるを得なくなるリスクもあります。
また、金融機関の融資条件が厳格化され金利優遇が受けられなくなったり、想定より短い返済期間を求められると、月々の返済負担が重くなり計画が破綻する恐れもあります。
実際によくあるワンルームマンション投資の失敗事例

不動産会社の言うことを鵜呑みにして判断を誤った
投資初心者に多い失敗が、不動産会社の甘いセールストークを信じ込んでしまい、冷静な判断ができなくなるケースです。
営業担当者から「家賃保証があるから安心」「自己負担ゼロで資産形成できる」などと勧められると、リスクを十分に検討せず契約してしまうことがあります。しかし実際にはその保証には期限や条件があり、切れた途端に家賃収入が減少してローン返済が困難になる例も見られます。
不動産会社の言うことを鵜呑みにしてしまうと、リスクを直視せずに誤った投資判断を下してしまい、結果的に失敗を招きやすいのです。勧誘トークに惑わされず、自分で利回りやリスクを確認する姿勢がなければ、失敗につながりやすくなります。
収支や利回りを計算せずに投資を始めてしまった
数値シミュレーションを怠ったことによる失敗もよくあります。毎月の家賃収入とローン返済額、管理費・固定資産税などの支出をきちんと計算せず、「なんとかなるだろう」と楽観的に投資を始めてしまうケースです。
収支計画や利回りを事前にシミュレーションしないと、空室が出た途端に赤字になる、想定より低い利回りしか得られないなど、後から「こんなはずではなかった」と後悔する結果になりがちです。
金融庁も、賃貸経営の事業計画やリスクをオーナー自ら十分理解する必要があると注意喚起しており、事前の綿密な収支計算を怠ることは結果的に失敗を招きやすくなります。
メンテナンスを怠って空室や家賃下落につながった
物件の管理を怠ったために入居者が集まらなくなり、結果として失敗するパターンもあります。
例えば、室内設備の故障や老朽化を放置したり、定期的なクリーニングを怠った物件は、入居者から敬遠されやすくなります。エレベーターなし・エアコン無し・古い和室のみといった快適性を欠く物件は需要が低く、賃料を下げても空室になりやすい傾向があります。
このようにメンテナンスを怠ると資産価値や競争力が落ち、入居率が悪化して家賃収入が減少する悪循環に陥ってしまいます。オーナー自身が物件価値向上に努めないと、入居者に選ばれない物件になってしまいます。
結局、設備投資やリフォームを怠れば資産価値が下がり、賃料引き下げや空室の増加を招いて投資計画が破綻してしまいます。
資金計画を立てずに借入をしたことで返済に追われてしまった
無理な融資を受けてしまい、返済負担が重くなって失敗するケースも見られます。自己資金が乏しいのにフルローンを組んだ結果、毎月の返済額が家賃収入を上回ってしまい、差額を自腹で補填し続ける状態に陥るパターンです。
実際、会社員がワンルームを複数戸フルローンで購入した事例では、運用8年で毎年40万円以上の赤字を出し、ついには物件売却を検討せざるを得なくなったケースがあります。このように資金計画なしに過剰な借入をすると、返済に追われ投資どころではなくなり、最終的に行き詰まってしまいます。
その結果、手元資金は常に逼迫し、資産形成どころか借金だけが残ってしまう事態にもなりかねません。資金繰りに行き詰まる典型例と言えます。
失敗を防ぐために必ず押さえるべきポイント

将来の需要を見越して立地や築年数を慎重に選ぶ
ワンルームマンション投資で成功するには、将来的にも需要が見込める物件を選ぶことが重要です。
具体的には、単身者ニーズが高い都市部や駅近の立地、大学・オフィス街へのアクセスが良いエリアなど、長期的に入居需要が安定しそうな地域を選ぶようにします。今後も人口流入が見込まれる東京や大阪などの都市圏に絞れば、空室リスクを軽減できる可能性が高まります。
また、築年数にも注意が必要で、築浅物件なら当面は大規模修繕の心配が少なく、築古物件の場合は安価で利回りが高い反面、早期に修繕費がかさむリスクがあるため、その点も織り込んで選択する必要があります。なお、候補物件はネットの情報だけで判断せず、自分で現地を訪れて周辺環境や競合物件の状況まで確認する姿勢も大切です。
購入前に利回りや支出をしっかりシミュレーションする
事前の収支シミュレーションは投資の成否を左右する極めて重要なプロセスです。物件購入前に、想定家賃収入とローン返済額、管理費・修繕費・固定資産税など全ての支出を洗い出し、利回り(表面利回り・実質利回り)を算出して収支が成り立つか綿密に検証しましょう。
特に空室率◯%の場合や金利が◯%上昇した場合など複数のシナリオでシミュレーションを行い、多少の不測事態でも自己資金の持ち出しが不要な計画になっているかを確認することが大切です。
金融庁も、不動産投資ではオーナー自らがローン返済も含めた事業計画やリスクを十分理解する必要があると注意喚起しています。また、購入時だけでなく将来売却する際の諸費用や税金まで織り込んで収支を見積もっておくとより確実でしょう。
出口戦略(売却や資産入れ替え)をあらかじめ考えておく
ワンルームマンション投資では、物件購入前に最終的な出口(売却や資産の入れ替え)を念頭に置いて戦略を立てておくことも重要です。「いつ・いくらで売却するか」「売れない場合にどうするか」など、投資の出口戦略をあらかじめ考えておくことで、最後に利益を確定させる道筋を描くことができます。
毎月の収支がマイナスにならないようにするだけでなく、購入から売却まで投資期間全体を見据えた計画を立てることが、最終的に成功するためには欠かせません。市場動向や将来の価格変動予測は初心者には難しいため、不動産会社など専門家のアドバイスを仰ぎながら出口まで見据えた戦略を練ることをおすすめします。
出口を決めておけば市場変動にも冷静に対応でき、損失を最小限に抑える判断がしやすくなります。
リスクを減らすなら分散投資という考え方が有効
複数の物件や資産に分けて投資リスクを小さくできる
投資では、一つの対象に全ての資金を集中させるのは大きなリスクを伴いますが、株式・債券・不動産など値動きの異なる資産に分散投資すればリスクを抑えて安定した成長を目指せるとされています。ワンルームマンション投資においても、複数の物件を地域を分けて所有することで、空室や災害など特定物件のトラブルによる損失を限定できます。
このように卵を複数のカゴに分けて持つイメージで投資リスクを分散させれば、一件の失敗が致命傷とならず安定した運用につながりやすくなります。例えば都心のワンルーム1戸に全財産を投じるより、地方も含め複数物件に分散しておけば、一戸の失敗で全資産を失うリスクを避けられるでしょう。分散効果は非常に大きいでしょう。
不動産以外の投資と組み合わせて安定運用を目指せる
ワンルームマンション投資は長期的な家賃収入を狙える一方で、空室や修繕費など不動産特有のリスクに左右されます。こうした影響を和らげる方法として有効なのが「不動産以外の投資」と組み合わせる分散投資です。
例えば株式や債券など値動きの異なる資産に一部を振り分ければ、不動産市況が低迷しても他の収益で補うことができます。特に債券は価格変動が比較的安定しており、家賃収入が減ったときの緩衝材になり得ます。
特に近年は、少額から始められる不動産関連の投資商品として、REIT(不動産投資信託)や融資型クラウドファンディングが注目を集めています。これらは直接物件を購入するよりリスクを抑えながら不動産収益を得られる仕組みで、初心者にも取り組みやすいのが特長です。
こうした新しい選択肢を活用すれば、不動産投資のリスクを補いつつ、安定的な資産形成を目指しやすくなります。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】ワンルームマンション投資に関するよくある質問

ワンルームマンション投資は本当に儲かるの?
正直なところ、ワンルームマンション投資は誰にでも簡単に大きな利益が出るわけではありません。
家賃収入があっても、ローン返済や管理費・修繕積立金などの経費を差し引くと手元に残る金額は限られるケースが多いのです。特にフルローンで購入した場合は、家賃収入の多くが返済や諸費用に充てられるため、実際の収益は想定より小さくなることも少なくありません。
ワンルームマンション投資で失敗する人の共通点は?
十分な準備をせずに楽観的に考えてしまうことが、失敗する人に共通する傾向です。
物件選びや資金計画を怠り、「家賃保証があるから安心」といった営業トークを鵜呑みにして投資を始めてしまうケースが目立ちます。例えば、空室リスクや修繕費を考慮せずにフルローンで購入し、保証期間終了後に家賃収入が減ってローン返済に行き詰まる、といった失敗例が実際に見られます。
ワンルームマンション投資よりリスクが少ない投資には何がある?
ワンルームマンション投資よりリスクの低い運用方法として、分散性の高い投資商品を選ぶ手段があります。
例えば、不動産投資信託(REIT)は少額で多くの不動産に投資でき、空室リスクを減らせます。また、不動産担保付きの融資型クラウドファンディング(LENDEXなど)は2万円から始められ、担保がある分リスクを抑えつつ年6~10%の利回りを狙えます。
まとめ|ワンルームマンション投資の失敗を防ぐために知っておくこと
国民生活センターによれば、20代による投資用マンションの相談件数は2013年度の160件から2018年度には405件へ約2.5倍に増加しました。安易にワンルームマンション投資を始めた結果、収支悪化などで悩むケースが増えていることがうかがえます。
しかしリスクを十分に理解し、立地選びや資金計画・出口戦略を徹底すれば、ワンルームマンション投資の失敗を防ぎ堅実な資産運用につなげることも可能です。
参考元
・国民生活センター「20歳代に増える投資用マンションの強引な勧誘に注意!」
・金融庁「アパート等のサブリースに関連する注意喚起について」
・国税庁「耐用年数による減価償却制度」
・住宅金融支援機構「住宅ローン利用者の実態調査」
・国民生活センター「消費生活相談窓口」
・金融庁「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください」
・総務省「住宅・土地統計調査」