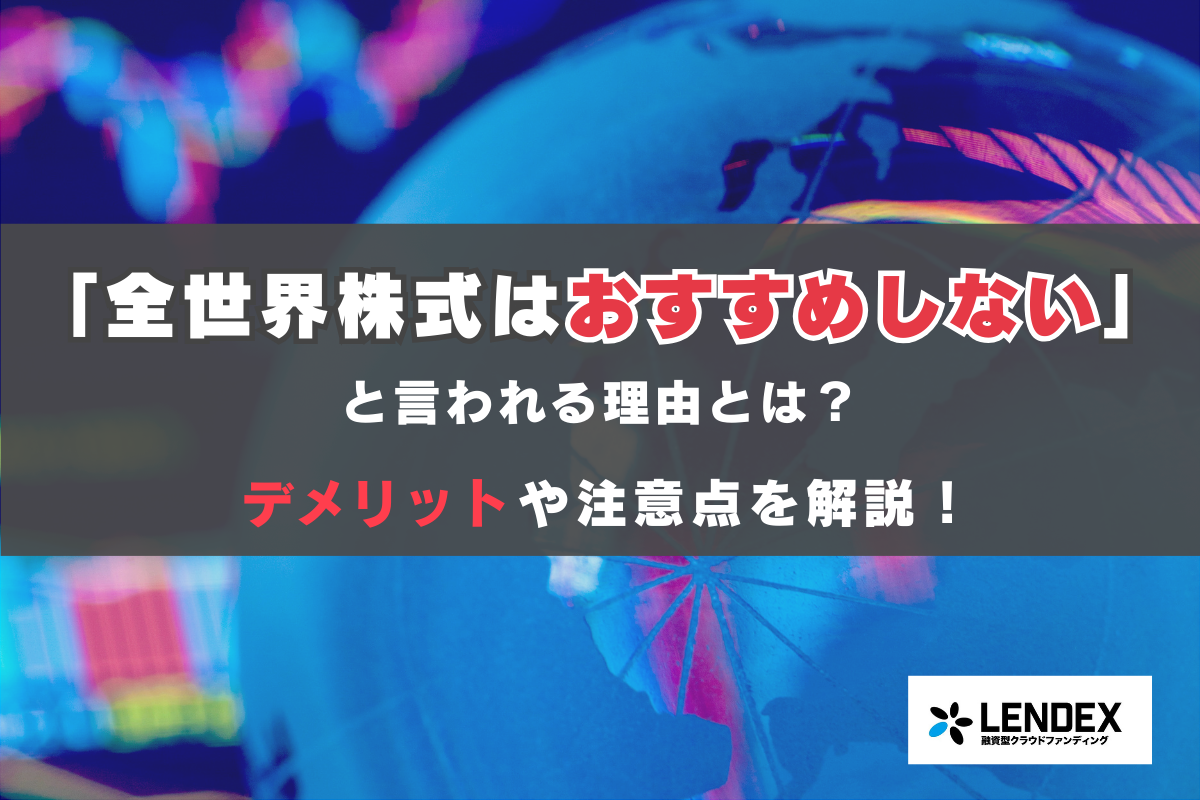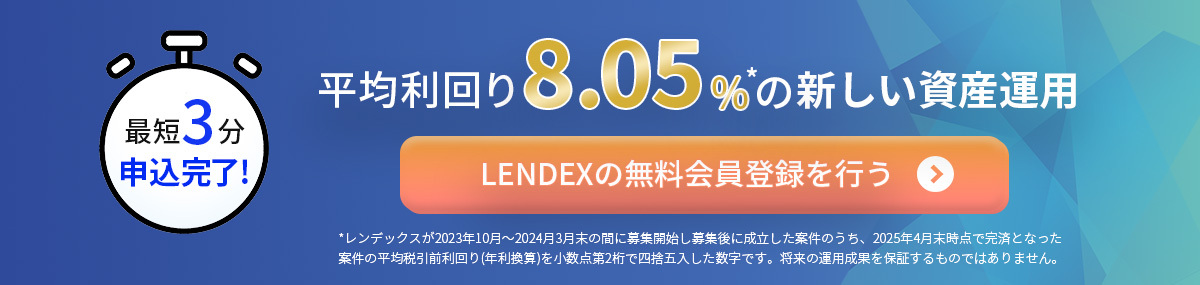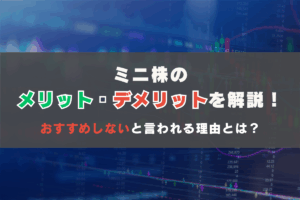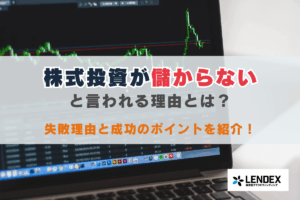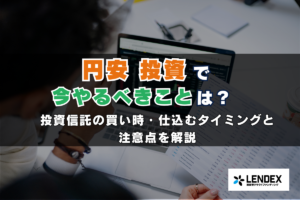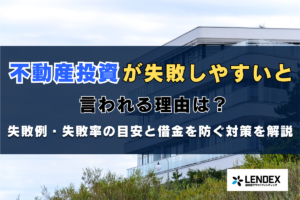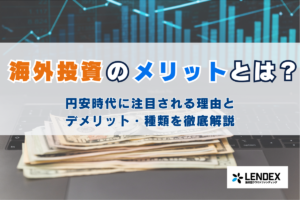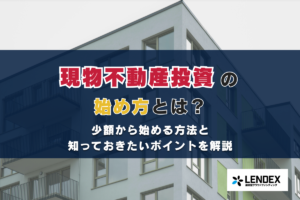株式投資の代表的な手法のひとつとして「全世界株式」が注目を集めています。世界中の企業に分散して投資できる安心感から、初心者にも人気のある商品ですが、必ずしも万能とは限りません。
「全世界株式はおすすめしない」との声もあり、実際にデメリットや注意点を理解せずに購入すると後悔する可能性があります。なぜそのように言われるのでしょうか。
本記事では、全世界株式が敬遠される理由と背景を整理し、具体的なリスクや投資判断に役立つポイントをわかりやすく解説します。
全世界株式は本当におすすめしないのか?結論から解説

全世界株式は必ずしも投資家に有利ではない
全世界株式は、世界全体の平均的な成長に連動するため、投資家にとって必ずしも最高のリターンをもたらす商品ではありません。
過去の実績を見ても、全世界株式の利回りはS&P500を下回るケースがあり、成長性の高い地域へ集中投資した場合よりリターンが低く抑えられる傾向があります。また、全世界株式は新興国や経済成長率の低い国の株式も含むため、それらが全体の利回りを押し下げる要因にもなっています。例えば、2018年末から2022年末までの約4年間では、全世界株式より米国株式(S&P500)の方が高い成績を示しています。
したがって「これさえ買えば安心」というわけではなく、投資家の目的によっては他の選択肢の方が有利になることもあります。
おすすめしないと言われるのはリスクが大きいため
全世界株式は株式100%の商品であるため、世界同時不況のような局面では基準価額が大幅に下落する可能性があります。例えば2020年のコロナショック時には、代表的な全世界株式インデックスファンドでも一時的に20〜30%程度の急落が起こり、短期的に大きな損失を抱えた投資家もいました。
このように急激な価格変動があり得るため、一時的な元本割れを許容できない人には不向きと言えます。
全世界株式がおすすめされない主な理由

信託報酬や手数料がコスト負担になる
全世界株式型ファンドは信託報酬(運用管理費用)などの手数料が毎日差し引かれるため、長期保有するとコスト負担が蓄積します。一見すると年0.1%程度と低い費用ですが、隠れコスト(売買時の手数料や監査費用など)も含めると実質コストはもう少し高くなり、利回りがその分目減りする点に注意が必要です。
例えば、運用利回りが低い年には手数料負担が利益を上回り、実質的な儲けが出ない可能性もあります。なお、為替変動リスクを抑えるために為替ヘッジを行うタイプのファンドでは、ヘッジ費用がかかる分だけ長期リターンがさらに低下します。
特に資産規模が大きくなるほど支払う手数料総額も増えるため、運用期間が長いほどコストの影響は無視できません。
市場平均にしか連動せず大きな成長を狙えない
全世界株式はインデックスファンド(パッシブ運用)であり、市場平均と同程度の成長しか見込めません。つまり、銘柄選択や集中投資によって市場を上回る大きなリターン(アルファ)を狙うことはできず、成果は世界経済の平均的な伸びにとどまります。
実際、新興国株などリスクの高い市場も含まれますが、それが高いリターンに直結していないのが現状です。過去のパフォーマンス比較でも、多くの期間で全世界株式のトータルリターンは米国株指数(S&P500)に劣っていました。また、IMFの予測によれば今後2年間の世界経済成長率は年3%強に留まる見通しで、全世界株式の今後のリターンも急激な成長は期待しにくいでしょう。
このように突出した成長を見込みにくい点も「おすすめしない」と言われる理由の一つです。
為替リスクがリターンを削る可能性がある
全世界株式ファンドの多くは為替ヘッジなしで運用されており、為替相場の変動がリターンに影響します。
代表的なeMAXIS Slim全世界株式もヘッジを行っていないため、円安・円高の動向によって基準価額が変動します。例えば、1ドル=110円から100円に円高が進めば、海外資産の円換算価値は約9%減少します。
一方で、円安が進めば円換算リターンは増加するため、為替は投資成果にプラスにもマイナスにも作用します。
つまり、投資対象そのものの成績だけでなく、為替の動向も結果に影響する点を理解しておくことが大切です。
全世界株式のデメリットをわかりやすく解説
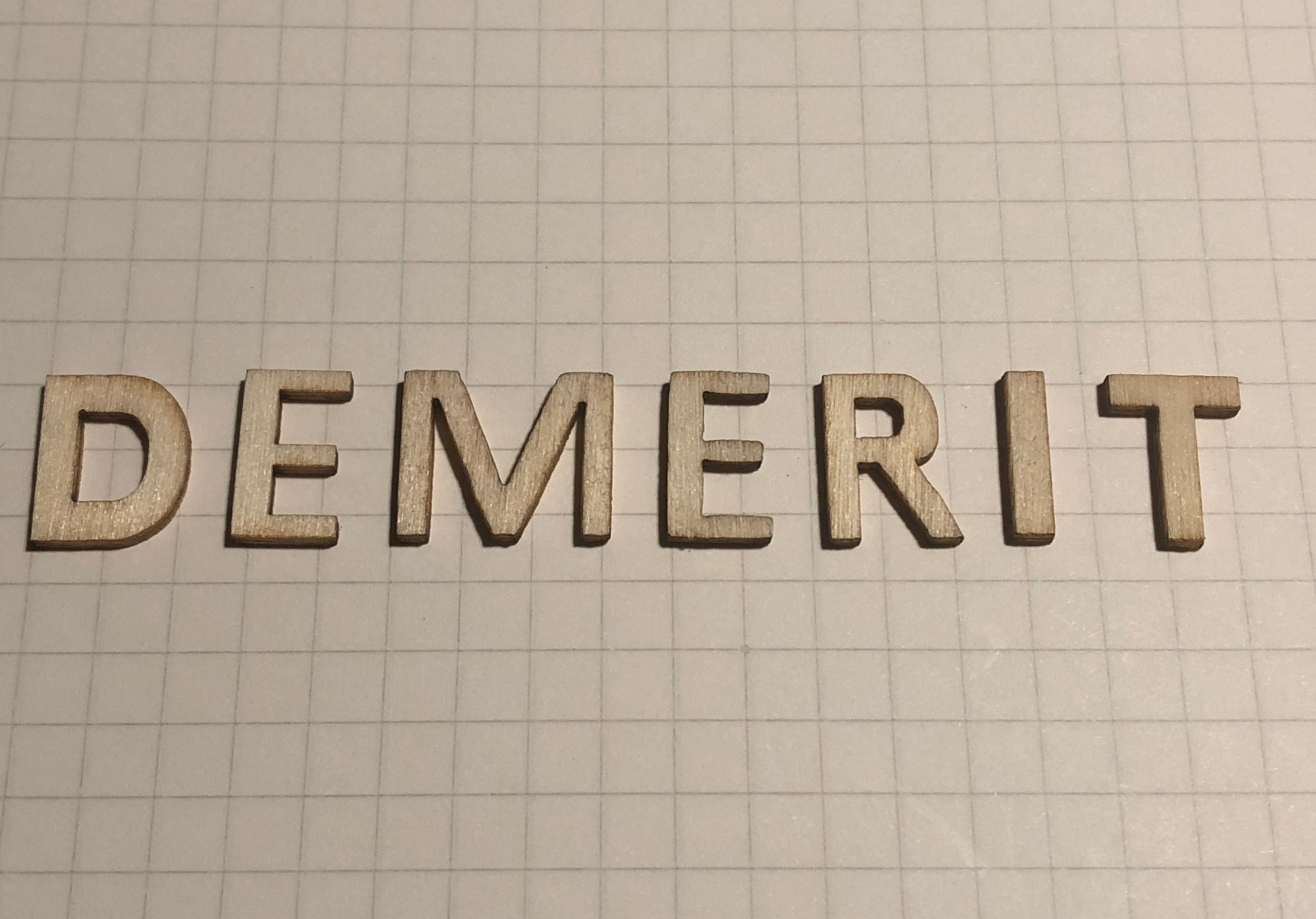
相場次第で元本割れするリスクがある
全世界株式の最大のデメリットは、元本保証がないことです。相場環境によっては、投資した元本割れ(評価額が投資額を下回る状態)になるリスクがあります。
実際、リーマンショックやコロナショックのような世界的経済危機では、全世界株式の基準価額が数十%規模で急落しました。なお、過去の暴落局面では元の価格水準に戻るまで数年を要した例もあり、回復を待つ忍耐が必要です。
長期的に見ればいずれ持ち直す可能性はあるものの、一時的な大幅下落は避けられないため、タイミングによっては大きな損失を被るおそれがある点に注意が必要です。
長期保有すると手数料負担が積み重なる
全世界株式は長期保有前提の投資先ですが、その間の信託報酬などの手数料がずっと差し引かれ続けるため、実質リターンが徐々に目減りします。
仮に年5%で運用できたとしても、年0.1%程度の信託報酬を払うだけで、数十年後には最終的な資産額が数%も減ってしまう試算になります。運用期間が長くなればなるほど手数料負担の累積効果は大きくなり、複利の利益を目減りさせる点は無視できません。
また、信託報酬以外にも監査費用や売買コストなどの「隠れコスト」が加わるため、実質コストは若干上昇します。低コストとはいえ長期では馬鹿にならないコストとなるため、この点を理解しておく必要があります。
精神的に価格変動へ耐えるのが難しい場合がある
株価の乱高下に精神的に耐える難しさもデメリットとして挙げられます。全世界株式は市場全体の動きに連動するため、大きな暴落局面では資産評価額が大幅に減少し、不安やストレスを感じる投資家も少なくありません。
例えば、2020年のコロナショックでは1ヶ月で約3割急落した後、基準価額が元の水準に戻るまでに半年以上を要しました。含み損を抱えた状態で長期間耐えるのは容易ではなく、初心者ほどパニックになって安値で売却してしまうリスクがあります。
こうした心理的負担に耐えられない場合、全世界株式への投資は難しいでしょう。逆に言えば、暴落時にも冷静に継続投資できる強い意志が求められます。
投資を検討する際に押さえておきたい注意点
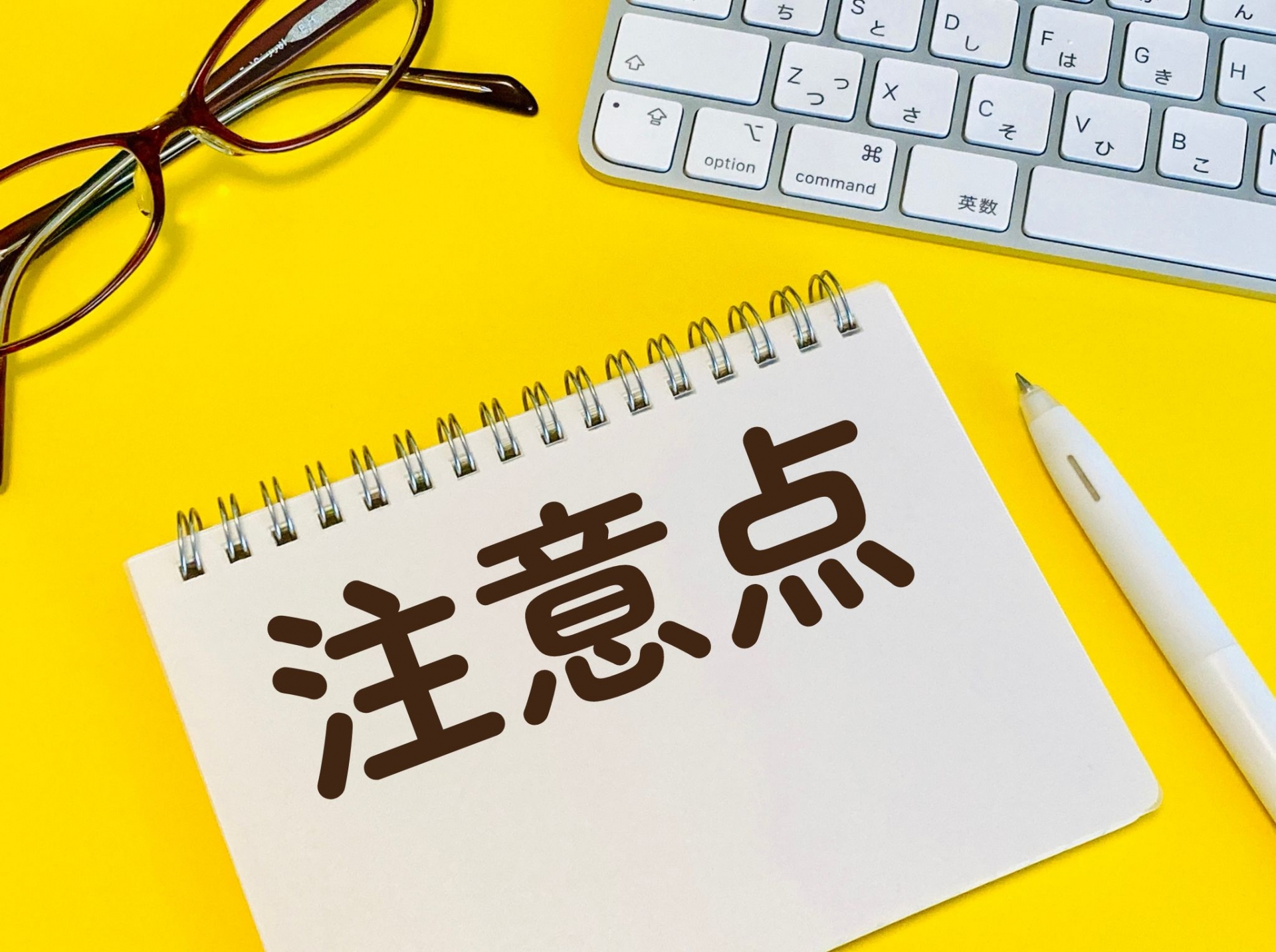
全世界株式に資金を集中させないことが重要
全世界株式1本に資金を集中させないことは重要な注意点です。
たしかに全世界株式だけで複数国に分散投資できますが、投資先の約6割が米国株式であるなど偏りもあります(比率は時期によって変動)。そのため、全世界株式だけに頼ると米国市場の動向次第でポートフォリオ全体が大きく左右される危険があり、本来の意味での分散効果が十分得られない可能性があります。
リスクを抑えるには、他の投資信託や資産にも資金を振り分け、全世界株式1本に絞らない分散投資を心掛けることが大切です。例えば、債券や現金、他の株式ファンドなどと組み合わせておけば、一つの市場急落時のダメージを和らげることができます。
投資期間や目的を明確にしておく必要がある
全世界株式に投資する前に、自分の投資期間や目的を明確にしておく必要があります。一般に、この商品は長期的な資産形成向けであり、最低でも10年以上の運用期間を確保することが望ましいでしょう。
短期で大きな利益を狙う目的には向いておらず、数年以内に使う予定の資金で運用するのはリスクが高すぎます。例えば、5年後に住宅購入資金が必要な場合など、全世界株式のようなボラティリティの高い商品では目標額を割り込む可能性があるため適しません。
一方で、20年以上の長期運用で老後資金を準備したいといった目的であれば、時間を味方につけてリスクを抑えつつ運用できる候補となります。自分の投資目的に全世界株式が合致するかを、事前によく検討しましょう。
仕組みを理解した上で購入判断をすることが大切
全世界株式の仕組みや特徴を十分理解した上で購入判断をすることが大切です。名前のイメージだけで飛びつくのではなく、実際には米国株偏重であることや、信託報酬・為替リスクなどの商品仕様を把握しておきましょう。
例えば、全世界株式と言っても先進国が約90%、新興国は10%程度の比率であり、米国だけで60%前後を占めます(比率は時期によって変動)。こうした組み入れ比率や運用方針を理解せずに購入すると、「思っていたのと違う」と感じる可能性があります。
納得した上で投資を始めるためにも、目論見書や商品資料に目を通し、仕組みを理解した上で判断するよう心掛けましょう。
全世界株式だけに頼るリスクとは?

特定の市場の急変で大きく影響を受ける可能性がある
全世界株式に一本足で投資していると、特定市場の急変により資産全体が大きく影響を受けるリスクがあります。
特に投資割合の高い米国市場で暴落が起きた場合、全世界株式も大きく値下がりするでしょう。実質的に全世界株式のパフォーマンスは米国株の動向に強く左右される構造です。
例えば、米国発の金融危機が起これば、他の国が好調でも全体として大幅な下落は避けられません。同様に、全世界には新興国も含まれるため、ある新興国で政情不安や経済ショックが起きれば、割合は小さくともファンド全体の足を引っ張る可能性があります。
一国の急変でも無視できない影響を受ける点はリスクと言えるでしょう。
配当や利息がなく資産形成に不利になることもある
全世界株式は利息や配当といった定期的なインカム収入が基本的に得られない点も、人によっては資産形成上のデメリットとなり得ます。投資信託内で配当金が自動再投資される運用形態のため、投資家の手元に現金収入が入ることはありません。
例えば、不動産投資や債券のように定期的な利息・分配金が出る商品と比べると、インカムゲインがないぶんリターン実感が湧きにくく、資産が増えている実感を得づらいという側面があります。また、配当を受け取れないことで、複利運用の恩恵を自分で実感しにくい点も指摘できます。
全世界株式だけに頼っていると、マーケットの値上がり以外で資産を増やす手段がなく、その意味で資産形成に不利と感じる場合もあるでしょう。
リスクを踏まえた上で検討したい分散投資という考え方
異なる資産を組み合わせることで損失を抑えられる
全世界株式のような株式資産だけでなく、異なる値動きをする資産を組み合わせることで、トータルの損失を抑えられる可能性があります。いわゆる分散投資の考え方で、株式と債券を組み合わせたり、不動産やコモディティを加えたりすることで、ある資産クラスの下落を他が補いやすくなります。
実際、株式100%よりも株式+債券とした方が、暴落時の下落幅が小さくなる傾向があり、リスク軽減につながります。具体的には、株式:債券を7:3程度に配分しておくと、リーマンショック級の急落時にも株式100%単独より損失を小さく抑えられたというデータもあります。
自分のリスク許容度に応じて複数資産の割合を決めることが、安定した資産形成のコツです。
不動産やクラウドファンディングを加えると安定性が高まる
株式以外の資産として、不動産や融資型クラウドファンディングをポートフォリオに加えると、全世界株式だけの場合に比べて安定性が高まります。
例えば、不動産投資は実物資産に裏付けされた収益が期待でき、株式市場と連動しにくいため、株価暴落時でも価格変動が比較的緩やかです。
また、融資型クラウドファンディング(不動産担保ローンへの投資など)は、想定利回り6~10%前後の定期的な利息収入が得られる商品もあり、株式相場の影響を受けにくい堅実な運用が可能とされています。実際、担保や保証を設定した案件が多く、貸し倒れリスクを抑えつつ毎月分配金を受け取れるケースもあります。
こうした代替投資を少額でも組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスク分散と安定性向上が期待できます。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】全世界株式に関するよくある質問

全世界株式は初心者でも買っていい商品ですか?
はい、初心者でも購入可能です。
ただし元本割れのリスクを理解し、長期運用を前提にできることが条件です。例えば、2020年の急落時には基準価額が約30%下落しましたが、その後回復するまで保有を続けられるかがポイントになります。
全世界株式とS&P500はどちらを選ぶべきですか?
投資目的によって異なります。
安定重視で幅広く分散したいなら全世界株式、高いリターンを狙いたいならS&P500が選択肢となるでしょう。例えば、全世界株式は47カ国に投資しますが、S&P500は米国の主要500社に集中しており、過去の利回りではS&P500が上回る場面もありました。
全世界株式は長期的に儲かる投資先ですか?
基本的には世界経済の成長に伴って長期では資産が増える可能性が高いです。
ただし保証された利益ではなく、経済状況によってリターンは変動します。例えば、過去20年では米国株中心のS&P500の方が高い利回りを記録した時期もあり、全世界株式が必ず大きく儲かるわけではありません。
まとめ|全世界株式の今後の投資判断に
結論として、全世界株式は万人に絶対おすすめできる商品ではありません。米国株偏重(約6割)ゆえのリスクや、市場平均並みのリターンに留まる点などデータが示す通り、メリットとデメリットが混在しています。
過去には1ヶ月で30%超の下落も経験しており、こうしたリスクを踏まえて分散投資を検討することが重要です。
自分の投資目的や許容リスクを見極め、全世界株式に偏り過ぎないポートフォリオで長期的な資産形成を図りましょう。
参考元
・GPIF「分散投資の意義② 投資のリスクとは」
・投資信託協会「全世界株式インデックスファンド(目論見書)」
・金融庁「投資を行っている方へ」