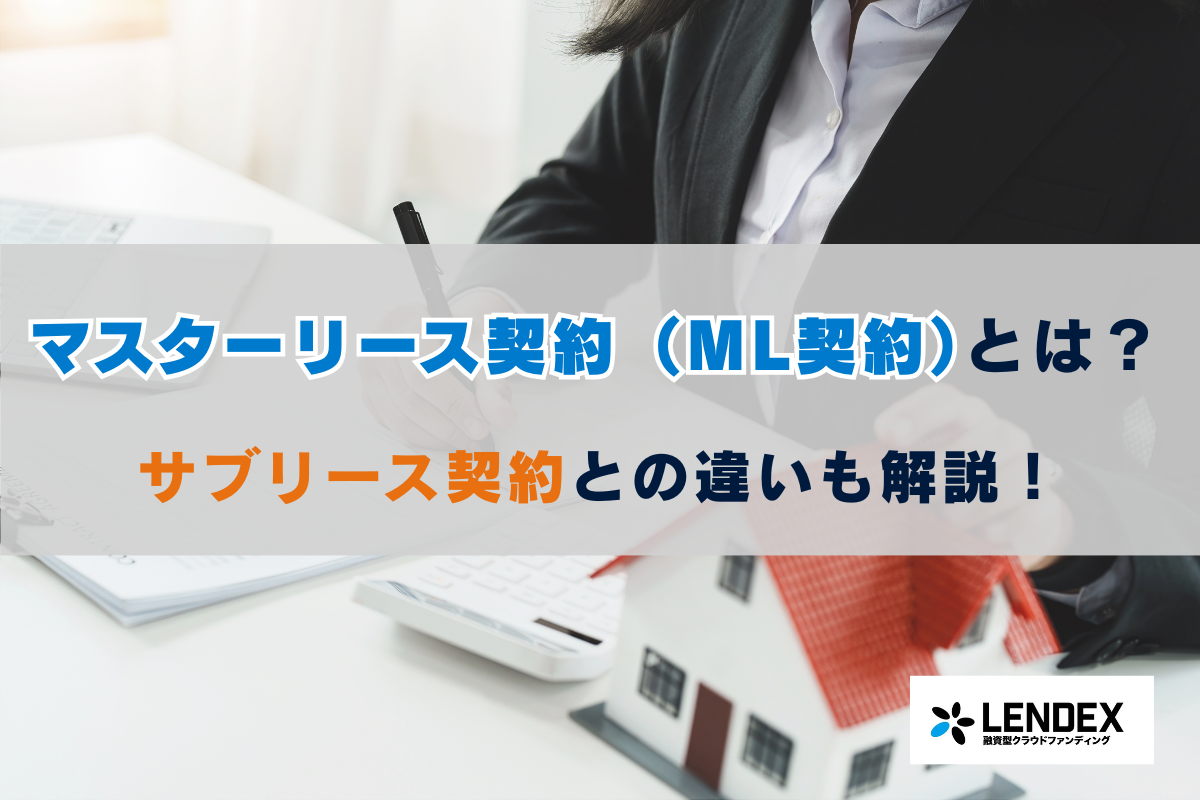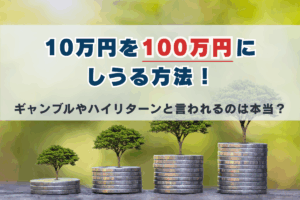最近、不動産投資で「マスターリース契約(ML契約)」という言葉を聞く機会が増えています。これはサブリース業者が物件オーナーから建物を一括で借り上げ、入居者に転貸する賃貸借契約方式のことです。
なぜ今、ML契約が注目されているのでしょうか。本記事では、ML契約の仕組みやサブリース契約との違い、メリット・デメリット、契約形態の種類や活用事例について、わかりやすく専門的に解説します。
マスターリース契約(ML契約)とは?仕組みをわかりやすく解説

業者が物件を一括で借り上げて運用する仕組み
マスターリース契約(ML契約)は、物件オーナーとサブリース会社(不動産業者)の間で結ばれる一括借上げ方式の賃貸借契約です。
オーナーから物件一棟全体を借り上げたサブリース会社が、各部屋の入居者に転貸(又貸し)して運用します。例えば10戸のアパートを所有するオーナーがML契約を結ぶと、サブリース会社がそのアパート全体をまとめて借り受け、入居者募集や賃貸運営を一任される形です。
オーナーは建物を丸ごと業者に貸し出し、一括借上げによる安定運用が見込めます。
家賃は「入居者→業者→オーナー」の流れで支払われる
ML契約では、家賃の受け取り方法が通常の賃貸管理とは異なります。
入居者はサブリース会社と賃貸契約を結び、毎月の家賃をサブリース会社に支払います。サブリース会社はそれを原資に、あらかじめオーナーと取り決めた賃料(マスターリース料)をオーナーに支払います。このように入居者→サブリース会社→オーナーという経路で家賃が流れるため、オーナーは空室があっても契約上定められた賃料収入を得られるのが特徴です。
オーナーは運営を任せ、業者が空室や管理を担当する
ML契約では、物件の賃貸運営に関する実務をサブリース会社が広範囲に担います。
具体的には入居者募集、契約手続き、クレーム対応、退去時の原状回復など、賃貸経営に伴う煩雑な管理業務をサブリース会社が代行します。オーナー自身は入居者と直接やり取りをする必要がなく、契約上もオーナーは貸主(マスターレッサー)、サブリース会社は借主(マスターレッシー)として位置付けられます。そのため、オーナーは物件の管理負担から解放され、日常的な運営はサブリース会社に任せることができます。
空室が出た場合もサブリース会社が新たな入居者募集から契約締結まで対応するため、オーナーは空室対応の手間や不安を大きく減らせます。
このようにML契約では、オーナーは物件運営の主導権をサブリース会社に委ね、空室リスクや入居者対応をプロに任せる形となります。
契約期間や賃料見直しは事前に取り決める
ML契約を結ぶ際には、契約期間や賃料の見直し条件について事前にしっかり取り決めておく必要があります。一般的に契約期間は 数年から長期(10~30年) に及ぶことが多く、その間はサブリース会社がオーナーに対し毎月一定額の賃料を支払う約束になっています。
ただし、契約書には◯年ごとに賃料を改定できるといった条項が設けられるケースが一般的です。これは将来的な家賃相場の変動に対応するためで、例えば家賃相場が下落した場合にはサブリース会社からオーナーへの支払い賃料の減額が請求される可能性があります。
一方で、契約期間中のオーナー側からの一方的な解約や更新拒絶には、借地借家法上の正当事由が必要となる点にも注意が必要です。契約締結時には賃料改定のタイミングや条件、契約更新・解約のルールを十分に確認し、双方が合意した上で契約内容を定めておくことが重要です。
なぜ今、ML契約が注目されているのか

空室率の上昇で自主管理のリスクが高まっている
近年、賃貸住宅の空室率の上昇がオーナーにとって大きな課題となっています。
総務省の調査によれば、日本全体の空き家率は2023年時点で13.8%に達しており、少子高齢化による空き家増加が続いています。都市部を除けば入居者確保が年々難しくなり、自主管理物件では空室が埋まらない期間が長期化するケースも増えています。空室が増えれば賃料収入が直接減少し、ローン返済や維持費負担が重くのしかかるため、自力での賃貸経営リスクは高まる一方です。
こうした背景から、空室リスクを業者に肩代わりしてもらえるML契約への関心が高まっています。ML契約であれば空室が出ても毎月一定の家賃収入が保証されるため、空室率上昇局面でも安定した経営がしやすく、オーナーに安心感をもたらします。
副業としての不動産投資でML契約のニーズが増加
会社員などが本業のかたわら行う副業としての不動産投資でも、ML契約のニーズが高まっています。ある調査では、20~60代のうち「不動産投資を副業として運用している」人の割合は約2.6%に上り、フルタイムでなく副収入目的で賃貸経営に取り組む個人が一定数存在します。
こうした副業大家にとって、手間をかけず安定収入を得られるML契約は魅力的な選択肢です。日中は本業が忙しいサラリーマン投資家でも、ML契約なら入居者対応や物件管理を業者に任せられるため、時間や専門知識の不足を補えます。
また、借上賃料が固定されていることで収支計画が立てやすく、本業の収入と合わせて長期的な資産形成プランを描きやすい利点もあります。政府も副業解禁の方針を打ち出し、副業を始める人の割合は増加傾向にあり、今後ますます副業不動産オーナーが増える中でML契約の需要拡大が見込まれます。
相続物件の管理でML契約が選ばれるケースが多い
親などから受け継いだ相続物件の賃貸管理においても、ML契約が選択されるケースが増えています。
遠方にあるアパートや高齢の親から譲り受けた築古物件など、相続によって大家業を引き継いだものの、自主管理に自信がないオーナーも少なくありません。こうした場合、プロのサブリース会社に運営を任せてしまえるML契約は安心材料となります。特に地方圏や築年数の古い物件では、自主管理のままだと客付け競争に埋もれて空室が埋まりにくいケースが増えており、オーナー自身も「結果に結びつくなら任せたい」という意識にシフトしつつあります。
また、相続対策として一括借上げを利用するメリットもあります。ML契約で常に賃貸中(貸家)とみなされる物件は、相続税評価額が下がる傾向があり、税負担を軽減できる可能性があるためです。以上のような理由から、相続で取得した賃貸物件の管理をML契約で任せるケースが多く見られます。
慣れない賃貸経営もプロに任せてしまえば、相続人は安定収入を得つつ本業やプライベートに専念できるためです。
サブリース契約とML契約の違いをわかりやすく整理
サブリースは一室単位、ML契約は一括借上げ
「サブリース契約」と「マスターリース契約(ML契約)」は、賃貸経営における類似のスキームですが指す契約主体が異なります。
サブリースとは本来、借り上げた物件を第三者に転貸する行為(転貸借契約)のことで、サブリース会社と入居者との間の契約を指します。一方、ML契約とはオーナーとサブリース会社との間で結ぶ一括借上げ(原賃貸借契約)のことです。簡単に言えば、オーナーと業者の契約をML契約、業者と入居者の契約をサブリース契約と呼ぶのが本来の使い分けになります。
実務上は両者をまとめて「サブリース」と呼ぶことも多いのですが、厳密には契約の当事者が異なる別契約です。一般的な文脈では、サブリース方式というと部屋単位で借上げ・転貸する管理方式全般を指し、ML契約というと一棟まるごと借上げる形態を強調する場合に使われます。
つまり、小規模なワンルーム投資でも業者に借り上げてもらえばそれはマスターリース契約ですが、特に一棟丸ごとの借上げであることを明示したい際に「ML契約」と称されるケースが多いと言えます。
家賃の受け取り方法が異なる
サブリース方式とML契約では、オーナーへの家賃の受け取り方に違いがあります。
ML契約では前述の通りオーナーはサブリース会社から家賃を受領します。入居者が支払う家賃は一旦サブリース会社が受け取り、契約で定めた一定額(または一定割合)がオーナーに支払われる形です。
一方、サブリース方式であっても契約内容によっては形態が異なる場合があります。例えば「空室保証」のように、空室発生時のみ一定期間家賃を補填するサービスを指す場合もサブリースと呼ばれることがあります。ただ一般には、サブリース=家賃保証付き一括借上げと認識されており、その場合はML契約と同様に入居者→業者→オーナーという家賃の流れになります。
このように文脈によって指す内容が混同されやすい点に注意が必要ですが、要はML契約ではオーナーが自分で入居者から家賃を集金することはなく、家賃はサブリース会社経由で支払われるという点が大きな特徴と言えます。
空室リスクの負担範囲が違う
空室リスクの負担にも、サブリース方式とML契約で違いがあります。
サブリース(家賃保証)方式では、空室が発生してもサブリース会社が契約で定めた家賃をオーナーに支払うため、オーナーは直接的な空室リスクを負いません。一方、通常の管理委託やオーナー自身で賃貸する場合、空室になった部屋の家賃収入はゼロとなり、その分の損失をオーナーが被ります。つまり空室リスクはオーナーが100%負担する形です。
ML契約(家賃保証型)の場合、空室リスクは基本的にサブリース会社が負うため、オーナーの収入は空室の有無に左右されにくくなります。ただし注意したいのは、契約内容によっては空室が増えすぎた場合に賃料減額の要請が来たり、一定の免責期間(借上げ賃料支払いが免除される期間)が設けられているケースがあることです。
そのため、空室リスクを完全にゼロにできるわけではありませんが、通常よりもオーナーの収入が空室影響を受けにくいのがML契約の利点です。
向いている物件規模が違う
サブリース契約(家賃保証)は小規模物件から一棟物件まで幅広く利用されていますが、特に物件規模によって向き不向きが語られることがあります。一般に、戸数が多いマンションやアパート一棟を経営するケースでは、空室リスク管理や一括運営の効率化の面からML契約(一括借上げ)が適していると言われます。
逆に、区分マンション1室だけを賃貸するようなケースでは、そもそも一室ごとの借上げになるため形式上はML契約でも実質的には単なる家賃保証付き賃貸と変わらず、管理委託と比較した手数料負担の大きさがデメリットになる場合もあります。
実際、家賃保証付きサブリースでは家賃の15~20%程度が業者の手数料となるのに対し、通常の管理委託手数料は5%前後が相場です。満室経営できる自信がある物件なら管理委託の方が収益率は高く、一方で空室リスクの高い物件ほどML契約でリスク移転する価値が高まります。
総じて、大規模な物件ほどML契約で任せるメリットが大きく、小規模物件では手数料負担とのバランスを考える必要があると言えるでしょう。
管理委託との違い|契約形態の比較ポイント

管理委託は所有者が入居者と直接契約する
賃貸経営には、サブリース方式以外に管理委託方式という選択肢もあります。
管理委託ではオーナー(物件所有者)は管理会社と「管理委託契約」を結び、入居者とはオーナー自身が直接賃貸借契約を締結します。管理会社はあくまでオーナーから委託を受け、物件管理業務を代行する立場です。つまり契約関係で見ると、オーナーと入居者の間に直接の賃貸借契約が存在し、その上でオーナーと管理会社の間に管理委託契約があるという構図になります。
一方、先述の通りML契約(サブリース方式)ではオーナーとサブリース会社の間に賃貸借契約(原賃貸借契約)があり、入居者とはサブリース会社が賃貸契約を結びます。契約主体が異なるため、管理委託では入居者に対する法的な貸主はオーナー本人、ML契約ではサブリース会社という違いになります。
ML契約では業者が入居者と契約し転貸する
ML契約(サブリース方式)では、サブリース会社がオーナーから建物を借り上げた上で入居者に転貸し、入居者と賃貸借契約を結びます。つまりサブリース会社が間に入って二重の契約構造をとるのが特徴です。
一方、管理委託方式では契約関係が一重(オーナーと入居者のみ)で、管理会社は契約の当事者にはなりません。これにより、管理委託の場合は入居者から見た貸主はオーナー自身となります。ML契約では入居者から見た貸主はサブリース会社であり、オーナーは入居者と直接の契約関係を持ちません。
この違いから生じるのが、責任範囲と業務範囲の差です。管理委託では入居者対応やトラブル対応は管理会社が代行しても最終責任はオーナーにありますが、ML契約ではサブリース会社が貸主として責任を負い、入居者対応も直接行います。
言い換えれば、管理委託=オーナー主体の経営をサポート、ML契約=業者主体の経営にオーナーが乗るというスタンスの違いです。
空室時の賃料負担の違いを理解する
空室が出た場合の賃料負担も管理委託とML契約で大きく異なる点です。
管理委託方式では、空室が発生した部屋の賃料収入はそのままオーナーの収入減となります。管理会社は入居者募集や広告などでサポートはしますが、空室期間中オーナーへの収入補填はありません。
一方、ML契約(家賃保証型)では空室があってもサブリース会社が契約賃料をオーナーに支払うため、オーナーは空室の間も一定の収入を得られます。これは経営安定上大きなメリットですが、その分サブリース会社への支払賃料(手数料)として、満室時に得られるはずの家賃の一部を差し出しているとも言えます。具体的には、家賃保証型では満室想定家賃の80~90%程度がオーナーに支払われ、残りがサブリース会社の取り分となるケースが一般的です。
したがって、空室リスクと収益性はトレードオフの関係にあり、どちらを重視するかで管理委託かML契約かの選択が変わってきます。空室リスクを自分で負ってでも収益最大化を図りたい場合は管理委託、有事に備えて安定収入を確保したい場合はML契約という考え方もできるでしょう。
どちらが自分の投資スタイルに合うかを見極める
管理委託とML契約のどちらを選ぶべきかは、オーナーの投資スタイルや物件の状況によります。
例えば、本業が多忙で賃貸業に手間をかけられない人や、初めての不動産投資でリスクを極力抑えたい人には、空室リスクを肩代わりしてくれるML契約が向いています。一方で、物件の稼働状況に自信があり、収益性を優先したい人や、物件運営に主体的に関わりたい人は管理委託の方が適している場合があります。
管理委託は手取り収入が最大化しやすい反面、空室発生や家賃滞納のリスクはオーナーに直撃します。また物件規模によっても違い、戸数の少ない物件ではML契約だと手数料負けしてしまい、逆に大規模物件では自主管理リスクが大きいのでML契約が安心、というケースもあります。
自身のリスク許容度・時間的余裕・物件特性を総合的に考慮し、どちらの契約形態が自分に合っているか見極めることが大切です。不明な点があれば複数の不動産会社に相談し、提案内容を比較検討してから決めると良いでしょう。
マスターリースの2つの契約形態|賃料固定型と実績賃料連動型
賃料固定型(空室保証型)の特徴とメリット・デメリット
賃料固定型(家賃保証型)は、サブリース会社が物件を一括借上げし、空室の有無に関わらずオーナーに一定の賃料を支払う契約形態です。
契約時に取り決めた借上げ賃料が毎月保証されるため、空室が続いても収入が途絶えず、長期にわたり安定した運用が可能となります。この型の最大のメリットは収入の安定性で、賃貸経営の長期計画を立てやすい点です。
一方、デメリットとしては保証される家賃額が相場より低めに設定される傾向があることが挙げられます。通常、保証賃料は市場家賃の80~90%程度で、その差額がサブリース会社の収益(いわば保険料)となります。また契約には免責期間が設けられる場合もあり、例えば新築引渡し後最初の1~3ヶ月間や、入居者入れ替え時の一定期間は保証賃料の支払い対象外となるケースがあります。
さらに契約途中や更新時にサブリース会社から賃料減額の打診が来る可能性もゼロではなく、契約内容によってはオーナーから途中解約が難しい点にも注意が必要です。
総合すると、賃料固定型は「安定を取る代わりに収益の一部を差し出す」契約と言え、安定重視型のオーナーに適した形態です。
実績賃料連動型(パススルー型)の特徴とメリット・デメリット
実績賃料連動型(パススルー型マスターリース)は、サブリース会社が入居者から実際に回収した家賃収入に応じて、オーナーに賃料を支払う契約形態です。
満室に近い運用ができれば、サブリース会社の取り分は手数料のみとなるため、オーナーは賃料固定型よりも多くの収入を得られる可能性があります。また、市場家賃が上昇した場合もその分が収入に反映しやすい点が特徴です。
一方、空室分の保証はなく、空室が増えればオーナーの収入も減少します。つまりリスクとリターンがオーナーに直結し、物件の競争力が高い場合には適している反面、空室の埋まりにくい物件には不向きです。
この契約型を採用するサブリース会社は少なく、一般には固定型が中心で一部のみ導入されています。安定よりも高収益を狙いたい、ハイリスク・ハイリターン志向のオーナー向けといえるでしょう。
2つの型の違いが収益性に与える影響
賃料固定型と実績賃料連動型では、オーナーの収益性に与える影響が異なります。固定型は常に一定の収入がある代わりに、満室時でも収入上限が決まっています。連動型は満室なら高い収益を得られますが、空室が出ればその分ダイレクトに収入減となります。
例えば家賃合計100万円の物件で固定型(90万円保証)と連動型(手数料5%)を比較すると、満室時は固定90万円<連動95万円となり連動型が有利です。しかし空室率10%では固定型は依然90万円ですが、連動型は85.5万円に減少し固定型を下回ります。つまり両者の収益逆転ラインは物件の稼働率に左右されます。
都心の人気物件など高い入居率を維持できる場合は連動型で収益最大化を狙え、稼働率低下が懸念される地方物件では固定型が安定します。
契約形態の選び方と判断基準
賃料固定型と実績連動型のどちらを選ぶかは、オーナーのリスク許容度と物件特性によります。
安定収入を重視しローン返済計画を堅実に遂行したいなら、多少利回りが下がっても固定型を選ぶ方が安心でしょう。一方、「多少収入が変動しても高利回りを追求したい」「物件の需要に自信がある」という場合は連動型に挑戦する価値があります。
判断基準の一つとして、物件の立地・需要を客観的に見極めることが挙げられます。都市部の駅近など高い稼働が見込める物件は連動型でも収益を最大化しやすいですし、競合が多く空室リスクが読みづらい物件は固定型でリスクヘッジする方が賢明です。
また、自身の資金繰りの余裕度も考慮しましょう。仮に空室が増えて収入減となっても耐えられる財務体力があれば連動型でも乗り切れますが、月々のローン返済に余裕がない場合は固定型で確実にキャッシュフローを確保する方が安全です。
総合的には、物件の稼働期待値とオーナーの安定志向度を天秤にかけて契約形態を選ぶのが良いでしょう。契約前にサブリース会社と十分に相談し、将来の賃料見通しやシミュレーションを提示してもらった上で判断することをおすすめします。
ML契約のメリット|空室リスクを減らせる安心の仕組み

一定の賃料収入が保証されるため、安定した運用ができる
ML契約最大のメリットは、やはり賃料収入が保証される安心感にあります。
サブリース会社との契約により毎月一定の借上げ賃料が支払われるため、仮に物件に空室や家賃滞納が発生してもオーナー収入は契約通り確保されます。この仕組みにより、賃貸経営における最大の不安要素である空室リスクと滞納リスクが大幅に軽減され、長期的に安定した運用が可能となります。収入が安定すればローン返済計画や将来の資金計画も立てやすく、精神的な安心感も得られるでしょう。
例えば通常の賃貸経営では、繁忙期に満室でも閑散期に空室が出ればその分収入が減ってしまい、年度ごとの収支ブレが大きくなりがちです。しかしML契約なら年間を通じてほぼ一定額の収入が見込めるため、収支計画の予測精度が上がり経営計画を安定化できます。
このような安定収入の確保は、不動産投資初心者やローン利用の投資家にとって大きなメリットと言えるでしょう。
管理や入居者対応の手間を減らせる
ML契約では煩雑な管理業務の大部分をサブリース会社が引き受けるため、オーナーの負担が大幅に軽減されます。
入居者募集広告の手配、内見対応、賃貸契約手続き、苦情や設備不良のクレーム対応、退去時の立会い・原状回復工事の段取りなど、賃貸管理には多岐にわたる実務があります。これらを通常はオーナー自身(または管理会社)が対応しますが、ML契約下ではサブリース会社がオーナーに代わって一切を代行します。
オーナーは入居者と直接接する必要がなく、契約窓口もサブリース会社となるため、夜間の急な設備トラブル連絡や家賃滞納の督促といったストレスから解放されます。その結果、仕事が忙しいサラリーマンや遠方在住のオーナーでも無理なく物件を運用可能です。
実際、「管理の手間がかからないから不動産投資を始められた」という副業大家の声も多く、不動産経営の省力化が図れる点はML契約の重要なメリットです。オーナーは定期的に送られてくるレポートで入居状況を確認し、あとは毎月の家賃が口座に振り込まれるのを待つだけという、半不労所得的な運用が実現します。
長期的な資産運用の見通しを立てやすい
ML契約による安定収入は、オーナーが長期的な資産運用計画を立てやすくする効果もあります。
毎月のキャッシュフローが読みやすいため、将来に向けた資金計画や投資戦略を組み立てやすいのです。例えば、借上げ賃料が契約上10年間一定と決まっていれば、その間のローン返済額や税金・維持費を差し引いた正味収益を正確に見積もることができます。これにより、追加の物件購入や繰上返済のタイミング、リフォーム予算の積み立てなど、長期的視点での経営判断が可能になります。
加えて、ML契約を結ぶことで金融機関からの評価が高まり、融資が受けやすくなるケースもあります。安定した家賃収入が見込める物件は返済能力が高いとみなされ、新たな融資の審査で有利に働くことがあるのです。
以上のように、経営の先行きが見通しやすくなる点は、資産運用全体を考える上でも大きなメリットと言えます。長期安定収入を基盤に、他の投資や資産形成と組み合わせた計画的な運用が可能となるでしょう。
ML契約のデメリット|オーナーが注意すべきポイント
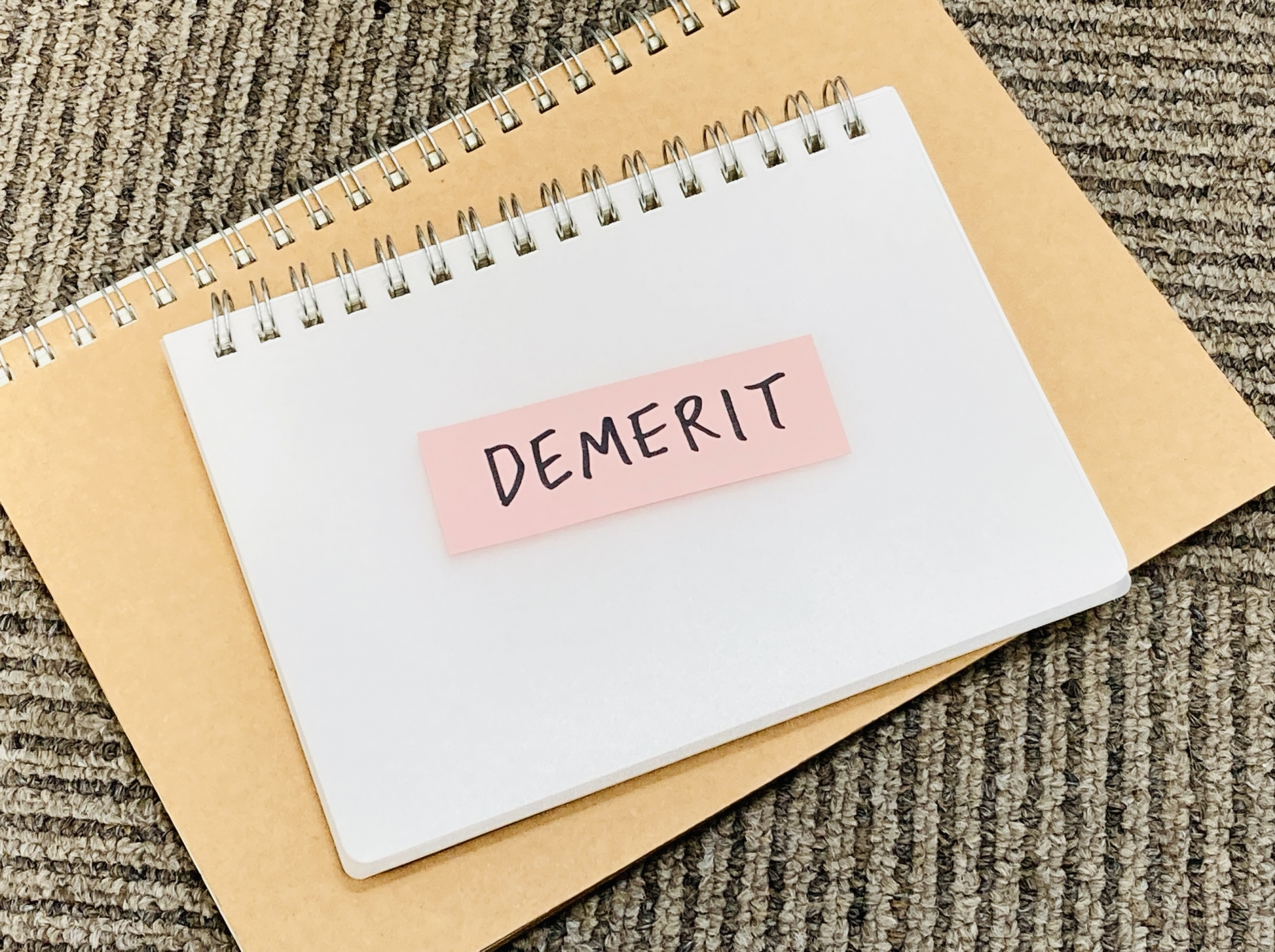
家賃保証額が相場より低く設定される場合がある
ML契約の家賃保証額(借上げ賃料)は、一般に市場家賃より低めに設定されます。サブリース会社は空室リスクを負う代わりに、家賃の一部を手数料として差し引くためです。
実務的には、満室想定の家賃収入の80~95%程度がオーナーに支払われる水準となるケースが多く、その差額5~20%ほどがサブリース会社の取り分(リスクプレミアム)となります。例えば満室時の月額家賃合計が100万円なら、保証賃料は80~90万円程度に設定されるといった具合です。
したがって、ML契約を利用するとオーナーの取り分(利回り)は自主管理より低下します。特に物件が常に満室稼働するような人気物件であれば、保証賃料との差額分だけ機会損失となってしまう点には注意が必要です。
加えて、保証賃料は長期間固定ではなく一定期間ごとに見直される契約が一般的であり、将来的な家賃下落リスクも考慮されます。つまり初年度は高めに設定されていても数年後の更新で減額される可能性があるため、長期で見た収益性はさらに変動し得ます。
以上のように、ML契約では安定を得る代わりに収益性が犠牲になる部分があることを理解しておきましょう。
契約内容によっては途中解約が難しいケースもある
ML契約を一度締結すると、オーナー側から途中解約しづらい場合が多い点もデメリットです。
契約上、サブリース会社は借地借家法における「借主」として保護されるため、オーナーからの一方的な契約解除は原則認められません。正当事由があって初めて解約通知が可能ですが、その場合でも解約申入れから6ヶ月後に契約終了となるなど時間がかかります。また、契約に違約金や解除料の定めがある場合、オーナー都合で途中解約すると高額な違約金負担を求められるケースもあります。
一方で、契約書によってはサブリース会社側から一定条件下で中途解約できる条項が盛り込まれている場合があります。例えば「◯ヶ月以上空室が継続した場合には業者側から契約解除できる」といった内容です。
このように、契約途中での柔軟性が制限される点は注意が必要です。契約前に中途解約の条件やペナルティをよく確認し、無理のない契約期間設定とすることが重要です。
契約更新時の条件変更リスクにも注意が必要
ML契約は長期に及ぶことが多く、契約更新時に条件変更リスクが生じます。
特にサブリース会社から家賃減額の要請を受けるケースがあり、初年度は高めに設定されていた保証賃料でも、周辺相場の下落や物件価値低下で減額されることがあります。収入がシミュレーション通りにならなくなるリスクや、契約期間の短縮・条項変更を求められる可能性も否定できません。
こうした変更に納得できない場合はトラブル発展の恐れもあり、契約期間満了時でもオーナーが自由にやめられない場合があります。長期契約ゆえの条件変更リスクは排除できませんが、契約締結時に見直し条件を明文化する、複数社の条件を比較して有利な契約とする、契約期間中も市場動向と物件状態を注視し交渉の余地あるタイミングを逃さないなどの対策が有効です。
ML契約の活用事例|実際に使われる主なケース
賃貸マンションやアパートの一棟運営に活用される
ML契約は、マンションやアパート一棟丸ごとの賃貸運営で広く活用されています。戸数が多い物件ほど空室リスクの影響も大きくなるため、全戸一括借上げによるリスク軽減効果が高まるからです。地方在住のオーナーが都市部の一棟物件をML契約で運用すれば、現地に行かずとも満室時も空室時も安定収入を得られます。
特に大東建託やレオパレス21などのアパート建築大手は、建設時に一括借上げ(30年保証など)をセットで提案し、一棟オーナーに長期安定収入を約束するビジネスモデルで成長してきました。現在も郊外型のファミリーアパートから都心型の投資マンションまで、一棟所有物件の運営手法としてML契約は一般的です。空室率変動に関係なくオーナー収入は固定されるため、金融機関からの融資も受けやすく売買市場でも人気があります。
不動産会社が開発した新築物件で導入されることが多い
ML契約は、新築の賃貸物件で導入されることが多いです。不動産会社がオーナー向けに企画・建設した物件では、完成と同時に空室保証付き契約が締結され、家賃収入の安定が見込めるようになります。これにより投資ハードルが下がり、オーナーは最初から安心して運用を始められるのが特徴です。
例えば、大東建託や積水ハウスでは「賃貸経営受託システム」や「シャーメゾン一括借上システム」など長期家賃保証サービスが用意されており、多くの新築オーナーが活用しています。新築時は建物価値が高く空室が少ないため、サブリース会社も契約を取り込みやすいタイミングで営業します。パンフレット上で「◯年間家賃保証」などと大きくPRされることが一般的で、建築請負とサブリース契約セットの提案が定着しています。
ホテル・民泊など短期賃貸事業にも応用されている
ML契約のスキームは、住居用物件だけでなくホテルや民泊施設などの短期賃貸事業にも応用されています。土地や建物を所有するオーナーがホテル運営会社に施設を一括賃貸し、ホテル経営を任せる形態で、運営会社は自社ブランドで宿泊運営を行いオーナーに毎月決まった賃料を支払います。
全国展開するホテルチェーンの多くが土地オーナーとのML契約でネットワークを広げており、広島県発祥の「ベッセルホテル」では運営するそのほとんどが、オーナー所有の土地建物を同社がマスターリース契約で借り上げて経営しています。都市部の民泊(Airbnb型簡易宿所)でも、住宅所有者から物件をマスターリースし転貸で運営代行する業者が増加中です。
観光需要や季節変動が大きい分野ですが、ML契約によりオーナーは安定収入を得て、運営側は裁量をもって宿泊事業を展開できます。
ML契約を選ぶときのチェックポイント

契約内容や家賃保証の条件を細かく確認する
ML契約を検討・締結する際には、契約内容の詳細を細かく確認することが重要です。特に家賃保証の条件について、保証賃料の金額だけでなく見直しタイミングや条件(何年ごとに改定可能か、下限保証の有無など)を確認しましょう。
また、契約期間中および更新時の解約規定も見逃せません。業者側からの途中解約条項や、オーナーから解約する場合の制限・違約金を事前に把握する必要があります。
原状回復費や修繕費用の負担区分も要チェックです。基本的に建物の大規模修繕や退去時の原状回復費用はオーナー負担が原則なので、どこまでが借主負担でどこからがオーナー負担かを契約書で明確に確認しましょう。
加えて、免責期間の有無(新築引渡し後何日間か無収入期間があるか)、滞納時の扱い(サブリース会社が立替保証するか)も確認ポイントです。契約前の重要事項説明に加えて、自分自身でも契約書条項を読み込み、不明点はすべて質問してクリアにしておくことが何より大切です。
信頼できる事業者かどうかを見極める
ML契約を成功させるには、サブリース事業者の選定が極めて重要です。
信頼できる業者と組めば長期安定経営が期待できますが、経営ノウハウや実績に乏しい業者だと想定通りの結果を得られない可能性があります。そこで、契約先の会社について以下のポイントをチェックしましょう。
- 実績・ノウハウ: 過去にどれほどの物件でサブリース運営を行ってきたか。空室率やトラブル対応の実績は十分か。
- 市場リサーチ力: 賃貸ニーズを適切に分析し、それに基づいた提案ができるか。家賃設定やリフォーム提案に専門性が感じられるか。
- 経営状況の健全性: 財務基盤が安定しているか。上場企業や大手系列であれば一定の信頼感がありますが、中小でも長年の黒字経営実績など確認できると安心です。
- 担当者との相性: 営業担当者の説明が誠実で分かりやすいか。信頼関係を築けそうか。
通常、ML契約は10年以上の長期に及ぶパートナーシップとなるため、大切な資産を預ける相手として慎重に選ぶ必要があります。
契約前に必ず複数社の話を聞き、条件や対応の比較をしましょう。一社だけの提案で即決せず、評判や口コミ、第三者機関の情報(行政処分歴がないか等)も調べると良いでしょう。万一、サブリース会社が倒産してしまうと家賃保証が途絶えオーナー自ら賃貸経営を引き継がねばならない事態も起こり得ます。
そうした最悪のリスクを避けるためにも、財務的に信用力があり長期運営の実績がある企業を選ぶことが、ML契約成功のカギとなります。
将来の修繕や維持費用の負担を想定しておく
ML契約だからといって、オーナーに全く出費がなくなるわけではありません。
建物の維持管理費や将来の修繕費は基本的にオーナー負担である点に注意しましょう。サブリース会社は日常の清掃や定期点検を行う場合がありますが、エレベーターや外壁塗装、屋上防水といった大規模修繕費用は契約に含まれないことが一般的です。
ML契約で毎月安定収入があっても、その中から将来の修繕積立や不測の出費に備えた予備費を確保しておく必要があります。築年数が経過するにつれ修繕コストは増大し、築10年・20年後には設備更新等が必要になるため、収入の一部は手元に残し計画的に資金を蓄えておきましょう。
また固定資産税や火災保険料、管理組合費(分譲マンションの場合)など、オーナーとして継続的に発生する費用も念頭に置く必要があります。収入と支出のバランスを長期視点で捉え、収益計算時に修繕・維持費の見込みを織り込んでおくことで、思わぬ出費で利回りが下がる事態を防げます。
分散投資でリスクを減らす|不動産以外の投資商品も活用する
不動産だけに偏らず、複数の投資先を持つことが大切
不動産投資は安定収入が魅力ですが、資産運用をより安全に行うには投資対象を不動産だけに集中させないことが重要です。仮に不動産市場の変動や災害などで不動産収入が減った場合でも、他の資産からの収益があれば全体としてリスクを緩和できます。
資金を1つの資産や銘柄に集中させず、複数の種類に分散して投資すれば、リスクが分散されてリターンの安定度が増す効果があります。これは「卵を一つの籠に盛るな」という格言にも通じる考え方です。
不動産に限らず、株式・債券・投資信託・コモディティ(金や原油)など様々な資産クラスを組み合わせることで、ある資産の価格下落を他の資産の上昇でカバーできる可能性が高まります。不動産投資家であっても、ポートフォリオ全体で見れば複数の収入源を確保しておくことが堅実な戦略です。
長期的に見て経済環境や市場トレンドは変化しますから、一つの投資先に固執せず柔軟に資産配分を調整できると安心です。
クラウドファンディングなど少額で始められる投資もある
「分散投資」と聞くと多額の資金が必要なイメージがあるかもしれませんが、少額から参加できる投資商品も増えています。
近年注目の不動産クラウドファンディングは、数万円程度の小口資金で不動産事業に出資できる仕組みです。複数の投資家から少しずつ資金を集めて物件を運用し、賃料収入や売却益を分配するため、個人は少額で不動産収益の一部を享受できます。他にも株式の積立投資や、ロボアドバイザーを使った自動運用サービスなど、初心者でも取り組みやすい選択肢があります。
こうした少額投資を組み合わせれば、たとえ予算規模が小さくても十分な分散効果を持たせることが可能です。例えば、不動産収入に加えて毎月3万円をインデックス投資信託に積み立てたり、5万円を株式型クラウドファンディングに投資したりすれば、複数の資産クラスからリターンを得られる体制を築けます。
要は、自分の余裕資金の範囲で無理なく複数の投資を行うことで、資産全体の安定性を高めていくことが大切です。
分散投資がリスク軽減につながる理由を理解しよう
最後に、なぜ分散投資がリスク軽減に有効なのかを押さえておきましょう。
ポイントは、異なる値動きをする資産を組み合わせることで、全体の変動幅を小さくできるという点です。例えば不動産市場が低迷しても株式市場が好調なら資産全体では損失が抑えられますし、株価が暴落しても債券や金の価格が上がれば資産目減りをカバーできます。
複数資産への分散は、リスク(価格変動)の分散そのものです。また投資タイミングの分散(積立投資)も、高値掴みのリスクを抑えリターンの安定化に有効とされています。このように、投資の世界では「長期・積立・分散」が基本とされ、金融庁も資産形成のポイントとして繰り返し強調しています。
不動産投資自体は悪いことではなく、むしろ長期安定収入を生み出す優良資産ですが、それだけに頼り切ると万一のときに脆さが露呈します。リスクを点ではなく面で捉え、資産全体でバランスを取ることが、長期的な資産防衛につながるのです。
ぜひ不動産以外の投資も学び、実践に取り入れて、より強固で安心なマネープランを築いていきましょう。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】マスターリース契約(ML契約)・サブリース契約でよくある質問

Q: 初心者はML契約とサブリース契約のどちらを選ぶべき?
結論として、初めて賃貸経営を行うなら安定収入が得られるML契約がおすすめです。
副業として手間をかけずに運用したい場合、一括借上げによって空室リスクを業者に任せられます。ただし物件規模やご自身の関与度合いによって適切な方式は異なるため、複数の契約形態を比較して選びましょう。
Q: ML契約は途中で解約できる?違約金や注意点を知りたい
原則、ML契約の途中解約は容易ではありません。
契約期間中にオーナー側から解除するには法律上の正当事由が必要で、違約金が発生するケースもあります。契約前に解約条件や違約金の有無を必ず確認し、無理のない契約期間を設定することが重要です。
Q: ML契約でトラブルを防ぐにはどうすればいい?
契約前の十分な確認と信頼できる事業者の選定がトラブル防止の鍵です。
家賃見直し条件や解約条項など不明点は事前に説明を受け、理解・納得した上で契約しましょう。また実績豊富な会社を選ぶことで、契約後の対応も円滑になり、トラブル発生リスクを減らせます。
まとめ|ML契約を正しく理解して安心の不動産投資を
マスターリース契約(ML契約)は、空室率13.8%という現代の賃貸市場においてオーナーの不安を軽減する有効なスキームです。一定の賃料保証を得る代わりに市場家賃の5~20%を差し出す形にはなりますが、安定収入と管理負担軽減というメリットは大きな魅力と言えます。
重要なのは契約内容を正しく理解し、自身の投資スタイルや物件に合った形でML契約を活用することです。さらに、法改正により重要事項の説明義務化など制度整備も進んでいるため、信頼できる事業者と透明性の高い契約を結ぶことで、安心して長期の不動産投資に臨むことができるでしょう。
最後に、不動産投資に偏りすぎず他の資産にも分散投資することでリスクを抑え、堅実に資産を増やしていく姿勢も忘れずに持ちたいものです。
参考元
- ・総務省統計局:「令和5年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計(速報集計)結果」
- ・国土交通省:「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」
- ・国土交通省:「賃貸住宅管理業法 サブリース事業に係る適正化のための措置」
- ・国土交通省:「日本における不動産取引に関連する法律」
- ・総務省:「令和4年就業構造基本調査」
- ・厚生労働省:「副業・兼業の現状」
- ・国税庁:「No.4602 土地家屋の評価」
- ・国税庁:「No.4614 貸家建付地の評価」
- ・財務省:「投資のリスクを減らす方法【分散投資】」
- ・財務省:「投資のリスクを減らす方法【積立投資】」
- ・財務省:「投資のリスクを減らす方法【長期投資】」
- ・金融庁:「資産形成の基本:NISA特設ウェブサイト」
- ・法務省:「借地借家法の更新拒絶等要件に関する調査研究報告書の公表」
- ・法務省:「民法の一部を改正する法律(債権法改正)」