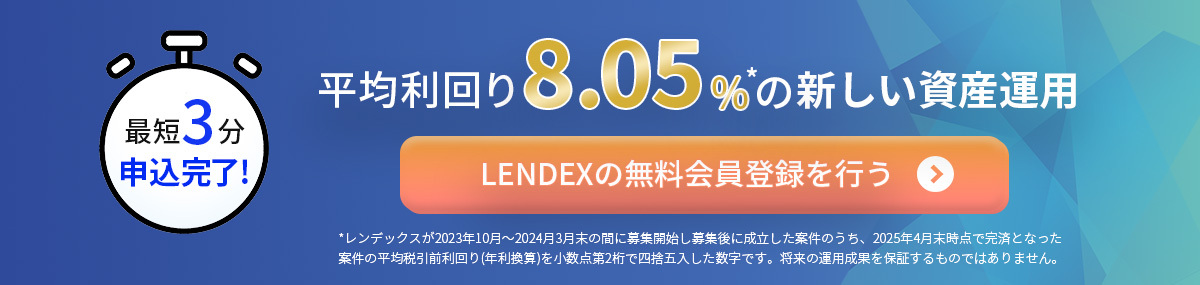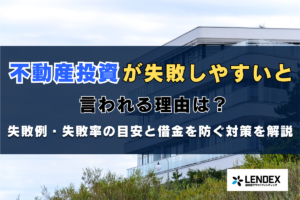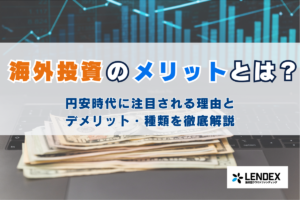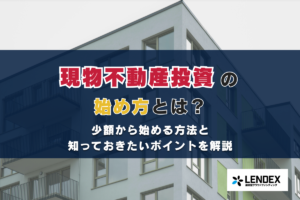「定期預金はおすすめしない」と聞いたことはありませんか?
定期預金は預金先として昔から親しまれており、安全にお金を預けられる方法として多くの日本人が利用しています。しかし近年の超低金利や物価上昇の影響もあり、「定期預金 おすすめしない」という声も少なくありません。本記事では、定期預金の基本的な仕組みや特徴を解説しつつ、定期預金がおすすめできないと言われる主な理由を詳しく見ていきます。
定期預金とは?基本的な仕組み
定期預金とは、銀行や信用金庫など金融機関に一定期間お金を預け入れることで、所定の利息を受け取れる預金商品のことです。預け入れ時に満期となる期間(例えば1ヶ月、1年、5年など)を指定し、その期間が終わるまで基本的に引き出せません。満期時には元本と利息がまとめて受け取れ、多くの場合、自動的に普通預金口座に振り替えられます。
普通預金との違いとは

普通預金との大きな違いは、預け入れ期間と利率です。普通預金は預入期間の定めがなく、いつでも自由に入出金できます。一方で、定期預金は預入期間をあらかじめ決め(例えば1ヶ月〜10年など)、原則その期間は引き出し不可となります。この預け入れ期間中は資金が拘束されますが、その代わりに普通預金より金利(利息の利率)が高めに設定されるのが一般的です。
特に2025年3月以降、日銀によるおよそ17年ぶりの利上げを背景に、定期預金の金利も上昇しています。定期預金の金利相場は2025年4月現在、金融機関によって差があるものの、一般的な銀行で年0.2%〜1.0%程度、一部のネット銀行では年1.0%を超える商品も登場しています。たとえば、1,000万円を1年間、年1.0%の金利で預けた場合、税引前で約10万円の利息を得ることができます。
このように、定期預金は普通預金より高い金利を期待できる点が魅力です。資金を一定期間動かさない代わりに、安定した利息収入を得たいと考える人にとって、有力な選択肢となります。
定期預金の主な利用目的とニーズ
定期預金は「 着実に貯蓄したい 」というニーズにマッチした商品です。例えば、将来使う用途が決まっている資金を安全に貯めておきたい場合に有効な方法だとされています。「○年後に住宅購入をするための頭金を貯めたい」「子どもの進学費用を◯年間で準備したい」といったように使い道と目標額が明確なお金を預けておくには、満期まで引き出さない定期預金が適しています。実際、定期預金では1ヶ月から最長10年程度まで自由に満期を設定できるため、必要になるタイミングに合わせて資金を用意することが可能です。
また、自分で計画的に貯金するのが苦手な人にも定期預金はよく利用されています。毎月決まった額を自動で積み立てる「積立定期預金」などを活用すれば、強制的に貯蓄を続けることができ、ついお金を使いすぎてしまう人でも確実に貯められる仕組みになります。
「定期預金はおすすめしない」と言われる理由とは?
金利が極めて低い現状
第一の理由は金利の低さです。現在の日本の定期預金金利は非常に低水準で推移しています。前述したように、多くの銀行で年0.01%前後、場合によっては年0.002%(0.002%=0.00002の利率)というケースすらあります。実際、1000万円を年0.002%の定期預金に預けても1年後の利息はたった200円にしかなりません。また、「72の法則」で資産が2倍になる期間を試算すると、0.002%の金利では約36,000年(72÷0.002)も必要になる計算です。これでは人間の寿命では到底お金が増えた実感を得られません。
要するに、現行の定期預金は利回りが極めて低く、資産を効率よく増やす手段としては不向きなのです。超低金利の現在では、定期預金に資金を置いていてもお金が増えないどころか、次に述べるインフレの影響で実質的には目減りしてしまう恐れすらあります。
インフレに弱く、お金の価値が目減りする
二つ目の理由はインフレーション(物価上昇)に弱いことです。インフレが進行すると、お金そのものの購買力(価値)は相対的に低下します。定期預金は長期間低金利で資金が拘束されるため、満期時に引き出したときには預けたお金の実質的な価値が下がってしまう恐れがあります。
日本では長らく低インフレ〜デフレ傾向が続いていましたが、近年は物価上昇率が高まる局面も出てきました。日本銀行は物価安定目標として年2%程度の物価上昇率を掲げていますが、仮にインフレ率が2~3%で推移する一方、定期預金の金利が0.01%程度に留まっていれば、毎年2%以上ずつお金の実質価値が減っていく計算になります。
実際、2023年には消費者物価指数が前年比+3%前後の上昇を記録しており、足元でもエネルギー価格高騰などから2025年1月時点で前年同月比+4.0%というインフレ率が報告されています。このような状況下では、定期預金の超低金利では物価上昇に太刀打ちできないのは明らかです。
※補足:仮に年0.02%(一般的な銀行の定期預金金利)の利回りしかないとすると、物価が年3%上がる局面では実質的に毎年約2.98%ずつ資産が目減りしていることになります。
途中解約で利息が得られない可能性
三つ目の理由は資金の流動性が低いことです。定期預金は一度預けると満期まで原則引き出せないため、急にお金が必要になった場合は中途解約(途中解約)しなければなりません。しかし中途解約すると、当初約束された利息は受け取れず、別途定められた低い解約金利が適用されるのが一般的です。多くの場合、その解約金利は普通預金並み(ごくわずかな利率)か、預入期間によっては利息ゼロになるケースもあります。つまり、満期前に解約するとほとんど利息が付かない可能性が高いのです。
資産運用としてのリターンが期待できない
以上の要因を総合すると、定期預金は資産運用手段としてのリターンが期待できないと言えます。極めて低い金利とインフレリスクの前では、預けたお金を増やすことがほぼ望めません。「預金は安全だが増えない」というのが現状であり、効率的にお金を増やす方法として定期預金は不向きなのは間違いないでしょう。
実際、定期預金は管理の手間がかからないという魅力はあるものの、その利回りの低さゆえに資産運用として満足のいく成果を得るのは難しいとの指摘もあります。資産形成のプロからも「現在の低金利下では、銀行にお金を預けても効率的に増やすことは難しい」という声が上がっています。そのため、「お金を殖やしたい」という目的には定期預金は適さず、より高いリターンを期待できる投資商品の検討が必要になってくるわけです。
定期預金のメリットとは?

ここまで定期預金のネガティブな側面を見てきましたが、もちろん定期預金にもメリットは存在します。定期預金の代表的なメリットを改めて確認してみましょう。
元本保証で安心できる
最大のメリットは「元本割れのリスクがない」ことです。定期預金は預けた元本が契約上保証されており、株式投資や投資信託のように元本が目減りしたり、マイナスになる心配が基本的にありません。金融機関が破綻しない限り、預けた金額(元本)はそのまま戻ってくる仕組みです。これは資産運用初心者やリスク許容度の低い人にとって大きな安心材料でしょう。
実際、「定期預金を活用すれば、元本割れの心配もなく、手堅く資産を拡大することができます」と紹介されるように、預金という手段は安全確実にお金を増やす(増やすと言っても微増ですが)方法として広く認識されています。リスクが少ない分リターンも小さいのは事実ですが、「預ければ必ず増えて戻ってくる」(利息分だけでも)という安心感は他の投資商品にはない定期預金ならではの強みです。
預金保険制度で1,000万円まで保護される
「元本保証」と言っても、万が一預け先の銀行が倒産したらどうなるの?と不安に思うかもしれません。その点も大丈夫です。日本には預金保険制度があり、金融機関が破綻した場合でも預金者の資産が保護される仕組みが整っています。具体的には、定期預金や利息の付く普通預金などを合算して元本1,000万円とその利息までが預金保険の対象として保障されます。仮に銀行が破綻しても、1,000万円までは国が主体となって設立された預金保険機構によって払い戻しが保障されるため、大半の預金者にとっては実質的に元本100%保証といってよい安全性が確保されています。
※参考:1,000万円を超える部分については、金融機関の財産状況に応じて支払われる可能性があります。預金額が巨額になる場合は、1金融機関あたり1,000万円以内に分散させることで全額を保護対象に収めることも検討しましょう。
無駄遣いの防止にも効果的
定期預金のもう一つのメリットは、計画的な資金管理をサポートしてくれる点です。満期まで原則引き出せない仕組みゆえに、日常的な衝動買いや無駄遣いを防ぐ効果があります。自分でお金を管理するとつい使い込んでしまう人でも、定期預金に預けてしまえば簡単には引き出せないため強制的に貯蓄を続けたい人に向いていると言えます。貯金の習慣づけや浪費防止に役立つ面があります。
さらに、銀行によっては毎月自動で一定額を定期預金に振り替えるサービス(積立定期など)も提供されています。それを利用すれば意識しなくても自動的に貯蓄できるため、「気づいたらお金が貯まっていた」という状態を作ることも可能です。このように、定期預金はお金を貯める仕組み作りとして有効であり、「貯蓄が苦手」「あると使ってしまう」という人には特に心強いメリットとなります。
定期預金のデメリットとは?資産形成の視点で解説

メリットがある一方で、資産形成(資産運用)の観点から見た定期預金のデメリットも明確になっています。「安全だが増えない」「便利だが融通が利かない」という点で、以下のような欠点が挙げられます。
利率が低く、複利効果を感じにくい
複利効果を享受するにはある程度の利回りが必要ですが、定期預金の現行金利では複利の恩恵はほとんど感じられません。例えば、1000万円を年0.002%の1年定期に預けても1年後の利息は200円程度にしかならず、10年預けても利益はわずか数千円に過ぎません。先述の「72の法則」の例ではありませんが、資産を2倍に増やすまでに気の遠くなるような時間がかかるのが実情です。
また、日本の金利水準は今後も急激な上昇が見込めないとの見方が多く、定期預金の利率が劇的に上がる可能性も低いでしょう。仮に今後金利が上向いたとしても、過去の定期預金(固定金利型)に預けた分については当初の低金利が適用されたままです。そのため、将来のインフレや金利動向に対して柔軟にリターンを得ることが難しい点も、資産形成を目指す上ではデメリットになります。
資金拘束される期間がある
定期預金は一度預けると満期まで資金が拘束されるため、流動性が低いという欠点があります。先ほど途中解約の項目でも触れたように、緊急で現金が必要になった場合は解約手続きをして引き出す手間がかかり、しかも利息面で損をします。つまり、必要なときにすぐ使えない点で不便さがあるのです。
定期預金は当面使う予定のない余裕資金に限って運用するべきであり、生活費や緊急予備資金はいつでも下ろせる普通預金や別の流動性資産で確保しておく必要があります。
また、定期預金にしてしまうと他の投資チャンスを逃す可能性もあります。満期まで資金を動かせないため、たとえば途中で魅力的な金融商品や投資案件が見つかっても乗り換えられません。資産をアクティブに運用したい人にとって、この機会損失のリスクも定期預金のデメリットと言えるでしょう。
将来のインフレリスクを考慮する必要がある
資産形成の長期的視点では、将来のインフレリスクにも注意が必要です。現在は物価が落ち着いているとしても、預け入れ期間中にインフレが進めば前述のようにお金の実質価値が下がります。特に長期間(数年〜十年以上)にわたって預ける場合、その間の物価変動による資産目減りリスクは無視できません。
実際、定期預金の金利が例えば0.2%や0.3%だとしても、物価が年2%上昇すれば実質的には毎年約1.7〜1.8%のマイナスになります。最近の例で言えば、カップ麺やパンなど生活必需品の値上がりが顕著です。一方、定期預金金利(年0.002%〜0.3%程度)では物価上昇率に太刀打ちできていないことがわかります。将来的にインフレが加速すれば、その差はますます開いてしまうでしょう。
定期預金が向いている人・向いていない人の特徴
向いているのは「安全重視派」
定期預金が向いているのは、何より「安全性を最優先する人」です。元本割れのリスクがなく預金保険で保護される定期預金は、とにかく一円たりとも減らしたくないという安全重視派に適しています。例えば、株式や投信の値動きにハラハラするのは嫌だ、とにかく確実に貯めたいという場合、定期預金は心理的な安心感を与えてくれます。
また、計画的にお金を貯めたい人にも定期預金は向いています。具体的には、前述したように「○年後に使う予定のお金を、それまで安定的に置いておきたい」というケースです。車や住宅の購入資金、教育資金など、目標時期と金額が決まっている貯蓄を確実に達成したいなら、その期間だけ定期預金で運用するのは合理的でしょう。
さらに言えば、自分で貯金のコントロールが苦手な人も定期預金に向いています。満期まで引き出せない仕組みを利用して強制的に貯蓄ペースを守れるからです。毎月の積立定期やボーナス定期預金などを使えば、半ば強制的にお金をプールできるので、「気づいたら使い込んでいた」を防ぎたい人にはピッタリです。
向いていないのは「資産を増やしたい人」
反対に、「資産を積極的に増やしたい人」には定期預金は向いていません。定期預金は前述の通り金利がごく低いため、お金を大きく増やすことが期待できないからです。実際、定期預金は金利が決して高くはないので「お金を増やしたい」という目的にはあまり向いていない、と指摘されています。
たとえば、余裕資金を運用して中長期的に資産を倍増させたい、老後資金を効率よく形成したい、といった高いリターンを求めるケースでは、定期預金では力不足です。年利0.01%では物足りず、インフレに負けないどころか実質マイナスになる可能性もあるため、資産成長を目指す人は投資信託や株式、不動産投資などより利回りの見込める資産運用に目を向ける必要があるでしょう。
また、運用に前向きで機動的に資金を動かしたい人にも定期預金は不向きです。他の投資商品に乗り換えたり、相場に応じたアクティブな運用をしたりする際に、定期預金では資金がロックされて自由がききません。常に市場のチャンスを捉えて資産を増やしていきたいという「攻めの姿勢」の投資家にとって、定期預金は退屈で非効率な選択となってしまうでしょう。
さらに言えば、手元資金に余裕がない人も定期預金には向きません。生活費ギリギリの中で無理に定期預金をしてしまうと、急な出費に対応できず困ってしまいます。まずは十分な流動性資金(最低3~6ヶ月分の生活費など)を確保した上で、それでも余るお金を運用に回すのが基本です。
定期預金は「使い方次第」でメリットを活かせる

ここまで定期預金の良し悪しや代替手段について述べてきましたが、最後に定期預金を上手に使うコツにも触れておきます。「定期預金はおすすめしない」という意見には一理ありますが、使い方次第では定期預金のメリットを活かすことも可能です。
短期で目的を持った預け方のすすめ
定期預金を使うなら、短期間で明確な目的を持って預けるのが効果的です。たとえば「半年後に車を買う」「1年後の旅行資金を準備する」といった具体的な使い道がある場合、定期預金は安全に資金を確保できる手段になります。短期間であればインフレの影響も小さく、利率が低くても安心感があります。
また、期間を短めに設定すれば、金利が上昇した際に満期ごとに有利な条件へ乗り換えられます。資金計画が変わっても、柔軟に対応しやすいのもメリットです。1年以内の定期なら、毎年利息を受け取りつつ見直しが可能なので、長期に縛られるイメージを持たずに始めやすいでしょう。
銀行でも目的に応じた定期預金商品が用意されており、教育資金や住宅購入資金など、使う時期が決まっているお金の管理に適しています。このように「目的」と「期間」をセットで考えることで、定期預金をより効果的に活用できます。
緊急用資金と割り切る運用方法
定期預金は「緊急用の予備資金」として活用するのも有効です。普段は使わないが、いざという時に備えて確保しておきたいお金を定期に預けておくことで、簡単に引き出せない環境を作りつつ、少しでも利息を得ることができます。
例えば、半年分の生活費を予備資金として定期に預け、「基本的に使わない」と割り切っておけば、無駄遣いを防ぎつつ、緊急時には解約して対応できます。途中解約で利息が減っても、備えとしての役割を果たせていれば十分意味があります。
さらに、定期預金を6ヶ月・12ヶ月・18ヶ月と期間をずらして分けて預ける「ラダー戦略」を取れば、定期的に満期が訪れるため流動性も確保できます。定期預金は目的を明確にし、必要なタイミングを見越して設計すれば、非常時の備えとしても効果的な資金管理手段になります。
資産運用を考えるなら?定期預金以外の選択肢
「定期預金ではお金が増えないのは分かった。でもリスクは抑えたい…」という方も多いでしょう。ここでは、資産運用を考える際に定期預金以外に検討したい主な選択肢を紹介します。
投資信託や株式との違い
定期預金と対照的なのが、投資信託や株式投資のようなリスク資産です。これらは市場の値動きによって元本が増減するリスクがありますが、長期的には年3〜7%以上のリターンが期待できるなど、より高い利益を狙える可能性があります。
大きな違いは、リターンの仕組みです。投資信託や株式は値上がり益や配当による収益を目指すのに対し、定期預金はあらかじめ決まった利息のみが得られます。また、投資信託や株式は元本保証がなく損失が出ることもありますが、長期で見ればプラスの結果になることも多い資産です。
流動性にも違いがあります。投資信託や株式は基本的にいつでも換金できますが、定期預金は原則満期まで引き出せず、中途解約すると利息が減るなどの不利があります。そのため、柔軟な運用を望む場合は投資信託や株式の方が向いています。
ローリスク運用なら融資型クラウドファンディングも選択肢
株式投資はハードルが高いけれど、定期預金以上の利回りを目指したいという方には、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)もおすすめです。これは、インターネット上で投資家から集めた資金を企業に貸し付け、利息収入を得る仕組みで、比較的安定した利回りが期待できます。
元本保証はないものの、複数案件に分散投資することでリスクを抑えることも可能です。そのため、リスクを抑えながらある程度の収益を目指すローリスク・ミドルリターンの運用先として注目されています。
定期預金に代わる選択肢として、融資型クラウドファンディングのほかにも、債券型の投資信託や個人向け国債などがあります。大切なのは、自分のリスク許容度に合った商品を見極めて選ぶことです。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
まとめ|「定期預金はおすすめしない」は一理あるが、選び方がカギ
「定期預金はおすすめしない」と言われるのは、低金利によるリターンの少なさやインフレによる実質的な価値の目減り、資金が一定期間拘束されるといった理由があるからです。確かに、資産を増やす手段としては物足りなさがありますが、定期預金そのものが無意味というわけではありません。
資金の目的や使う時期が明確で、安全性を重視したい場面では、定期預金も有効な選択肢です。予備資金の管理や短期の貯蓄には適していますし、他の資産運用と組み合わせれば、リスクを抑えつつ全体のバランスを整えることもできます。
大切なのは、資産の一部を「動かさないお金」として定期に預けつつ、増やす目的の資金は投資信託や株式、融資型クラウドファンディングなどに振り分けるといった工夫です。「定期預金は意味がない」と決めつけず、目的に合った使い方をすれば、堅実な資産運用の一助となります。