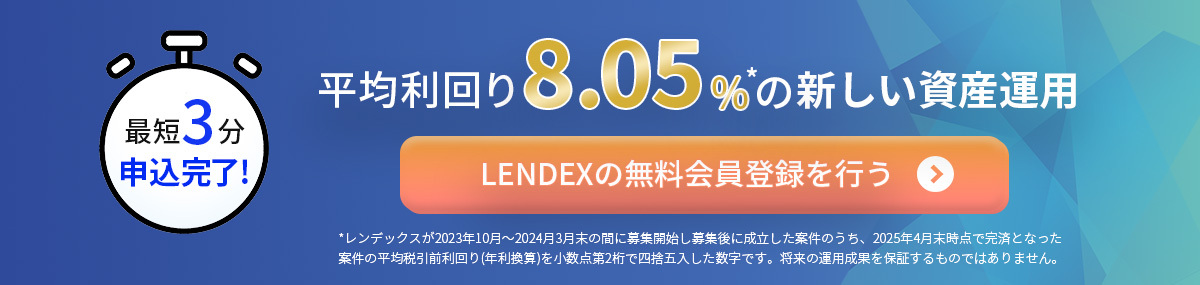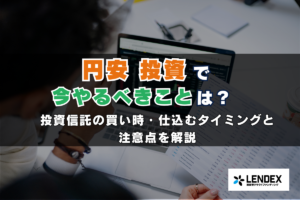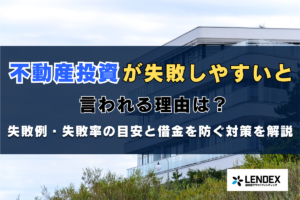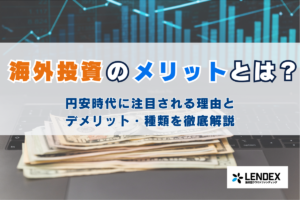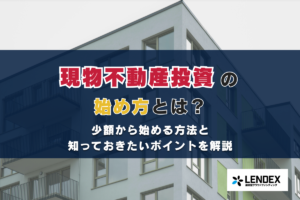最近、「まとまった資産は預金のままで良いのか」という声を耳にすることが増えています。日本では金利が極めて低いため、5,000万円の貯金があっても利息はごくわずかです。むしろインフレや税金の影響で、預金だけに頼ると実質的な資産価値が減ってしまう恐れもあります。しかし、これほどの大きな資産をどのように運用すれば良いのかは、多くの人が迷うポイントです。
本記事では、貯金5,000万円を活かすための資産運用の選択肢や注意点を整理し、運用を成功させるための実践的なコツまで、わかりやすく専門的に解説します。
貯金5,000万円を超えたら考えるべき資産運用の選択肢

預金のままでは資産価値が目減りするリスクがある
5,000万円もの大金をただ銀行預金で持ち続けるだけでは、資産の実質価値が目減りしてしまうリスクがあります。現在の日本は超低金利で、預貯金ではお金はほとんど増えません。例えばメガバンクの普通預金金利は年0.001%程度とごく僅かです。
一方、物価上昇(インフレ)が進めば現金の購買力が下がり、同じ金額で買えるモノやサービスの量が減ってしまいます。預金だけで安心せず、インフレに負けない運用を考える必要があるのです。
資産を運用することで将来の選択肢が広がる
まとまった貯金があるなら、資産運用によってお金に働いてもらうことで、将来の選択肢を大きく広げることができます。資産形成を通じて経済的な余裕が生まれれば、セミリタイアや海外移住、事業への挑戦など、自分が望むライフプランを実現しやすくなります。
現代は人生設計が多様化し、一人一人が自由に生きる時代と言われます。運用によって資産を増やしておけば、そうした多様な生き方に備える余力を持てる点で大きなメリットがあります。5,000万円もの元手があるからこそ、安全に寝かせておくだけでなく上手に増やし、将来の夢や目標の実現に役立てましょう。
なぜ運用が必要なのか?インフレや税金の影響を解説
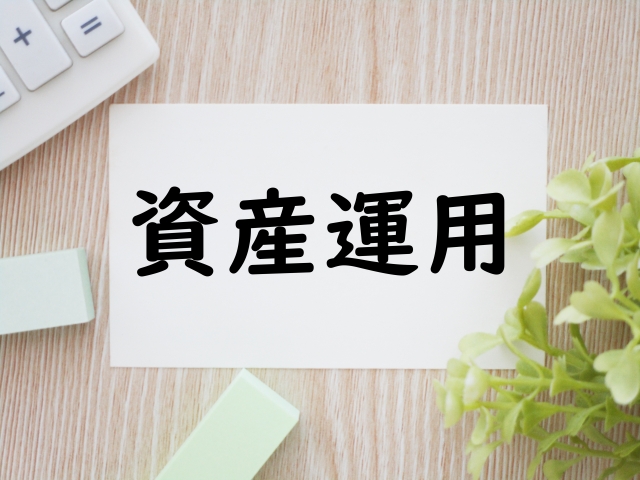
インフレで現金の実質価値が下がる可能性がある
インフレは現金の価値を目減りさせる大きな要因です。日本では長らく低インフレが続いてきましたが、直近では物価が上昇傾向にあります。
実際、2024年の日本の消費者物価指数(生鮮除く)は上昇し、日銀目標の2%を3年連続で上回りました。仮にインフレ率が年2%だと、現金1億円の購買力は10年で約1,800万円分も目減りしてしまう計算です。
超低金利下では預金の利息ではとても埋め合わせできず、現金を持っているだけでは実質的に資産が減少していく恐れがあります。このため、インフレに負けない利回りを狙える資産運用が必要になるのです。
相続税や贈与税への対策として資産運用が役立つ
5,000万円もの資産を持つと、将来的に相続税の課税対象になる可能性が高まります。日本では2015年に相続税の基礎控除額が引き下げられ、5,000万円+1,000万円×法定相続人から3,000万円+600万円×法定相続人に変更されました。この改正により、都市部を中心に課税対象となる世帯が増えています。
そこで資産運用の一環として注目されるのが「資産の組み換え」です。たとえば現金をそのまま相続すると額面どおりに評価されますが、不動産に替えることで相続税評価額を抑えられる場合があります。
特に賃貸用不動産は「貸家建付地評価」などにより評価が下がりやすく、結果的に課税額の軽減につながります。さらに生命保険を活用すれば、法定相続人1人あたり500万円まで非課税枠が認められるため、現金をそのまま残すより効率的に資産を引き継げます。
このように資産の形を工夫することは、単なる節税対策にとどまらず、安定的な運用や家族の将来への備えにも直結します。資産をどう持つかを見直すことは、相続対策の重要な資産運用の一部といえるでしょう。
預金だけに頼ると資産が目減りするリスクがある
大切な資産を預金だけで持ち続けることには、「増えないどころか目減りする」リスクが伴います。現在のような低金利下では、銀行に預けても資産はほとんど増えません。むしろ前述のとおりインフレで実質価値が下がれば、預金しているだけでお金の価値が減っていく可能性があります。
さらに、預金の利息には20.315%(復興特別所得税含む)の税金がかかるため、わずかな利息も手取りではさらに目減りします。仮に5,000万円を年0.001%の普通預金に預けても1年間の利息はわずか500円程度(税引前)です。預金だけに頼る運用では資産を守ることすら難しく、リスク分散の観点からも預金以外の運用先を検討する必要があります。
貯金5,000万円におすすめの資産運用方法
投資信託
投資信託は、投資家から集めた資金をまとめ、運用の専門家が国内外の株式や債券などに投資する仕組みです。
5,000万円規模の資産を保有している場合でも、一括で特定の資産に投じるのではなく、投資信託を通じて幅広い分野に分散できる点が大きなメリットとなります。特に、株式・債券・不動産など複数の資産クラスに投資するバランス型ファンドを利用すれば、資産全体のリスクを抑えながら安定的な運用が可能です。
また、専門家が運用を行うため、自分で個別銘柄を調べて投資先を選ぶ手間が省け、海外市場など個人では難しい分野にもアクセスできます。ただし、投資信託も価格変動リスクを伴い、元本が保証されるわけではありません。
資産規模が大きいほど、どの分野にどれだけ配分するかが成果に直結するため、自身のリスク許容度や運用目的に合わせて商品を選ぶことが重要です。
株式投資
株式投資は、株式市場で企業の株式を直接購入して、その企業の成長に資金を投じる運用方法です。株式を保有すると、その会社の利益に応じて配当金などを受け取ることができます。また、株価が購入時より上昇すればキャピタルゲイン(売却益)も期待できます。
一方で株式市場の価格変動は大きく、預貯金と違い元本割れのおそれがあります。実際、リーマンショック時には主要株価指数が一時半分以下になる暴落も経験しました。株式投資は高いリターンの可能性がある反面、大きなリスクも伴うため、企業研究や分散投資で慎重に運用する必要があります。
不動産投資・REIT
不動産投資には、自分でアパートやマンションといった物件を購入し賃貸収入を得る直接投資と、不動産投資信託(J-REIT)を通じて間接的に投資する方法があります。
J-REITであれば、多くの投資家から資金を集めて大規模な資金として運用するため、個人では難しい複数の不動産への分散投資が可能になります。これによりリスクを軽減できる点が魅力です。また、J-REITは不動産のプロが運用を担当し、物件の維持管理やテナント対応も任せられるため、個人で物件を直接持つ場合の手間が省けます。さらにJ-REITは証券取引所に上場しているため、株式のように日々売買でき流動性が高いメリットもあります。
直接不動産を購入する場合はまとまった資金(頭金やローン審査)が必要で、空室リスクや維持費用などの課題もありますが、他方で不動産価格の上昇益や節税効果が期待できるという利点もあります。
5,000万円の資産を活かすなら、ローンを活用して収益物件を購入するか、手軽さを重視してJ-REITで分散投資するか、自身の投資スタイルに合わせて検討すると良いでしょう。
国内・海外債券
債券への投資は、国や企業にお金を貸し付けて利息を受け取る仕組みで、比較的安定した運用が可能です。国内債券の代表である日本国債は信用度が高く、元本割れのリスクが極めて低いため安全資産とされています。満期まで保有すれば額面金額が戻り、定期的に決まった利息(クーポン)収入を得られるのが特徴です。
一方、海外債券は国や発行体によりますが、日本より金利水準が高い場合が多く、相対的に高い利回りを期待できます。ただし為替変動リスクがあるため、円安・円高の影響で実際の受取額が変動する点には注意が必要です。
債券は株式に比べリターンは穏やかですが、その分価格変動も小さく、5,000万円の運用ポートフォリオに組み入れることで全体の安定性を高める効果が期待できます。
ソーシャルレンディング
ソーシャルレンディングは、資金の貸し手(投資家)と借り手をインターネット上で直接マッチングする融資型の投資サービスです。不特定多数の個人が運営会社のプラットフォームを通じて企業などに資金を貸し出し、借り手から支払われる利息が投資家のリターンになります。銀行を介さない分、少額かつ短期間の投資でも相対的に高い利回りが期待できる利点があります。
たとえば案件にもよりますが、年利5~10%程度の利回りが提示される融資案件も多く、超低金利の銀行預金に比べれば魅力的な収益が見込めます。一方で、貸付先の事業不調による貸し倒れ(デフォルト)リスクや、プラットフォーム運営事業者自体の信用リスクも存在します。元本保証はなく、万一借り手が返済不能になれば損失が発生しうる点に注意が必要です。
高利回りに惹かれがちですが、事業者の情報開示をよく確認し、信頼できる案件に分散投資するなどリスク管理を徹底することが大切です。
ヘッジファンド
ヘッジファンドとは、様々な投資手法を駆使して、相場が上昇局面でも下落局面でも収益を追求することを目的とした絶対収益型のファンドを指します。伝統的な投資信託が市場全体の上昇局面でしか利益を得られない商品が多いのに対し、ヘッジファンドは空売りやレバレッジ、デリバティブ取引など高度な戦略を用いて、どんな相場環境でも利益創出を図ろうとします。そのため、市場平均と関係なく独自の成果を上げる可能性がありますが、ファンドマネージャーの手腕によって運用結果が大きく異なり得る点には注意が必要です。
一般にヘッジファンドは富裕層や機関投資家向けに提供され、最低投資額が数百万円~数千万円と高額だったり、年20%の成功報酬が設定されていたりとハードルが高い商品です。流動性も低く、解約に制限期間(ロックアップ)がある場合もあります。5,000万円の資産を更に積極運用したい場合の選択肢になりますが、投資判断には高度な専門知識が求められるため、慎重に検討すべきでしょう。
融資型クラウドファンディング
融資型クラウドファンディングは、ソーシャルレンディングと同義で、個人がオンライン上で貸付ファンドに出資し、企業や事業への融資を行う資金提供モデルです。投資家にとっては、比較的短期間・少額から始められ、銀行融資が難しい案件にお金を回すことで高めの利息収入を得られるチャンスがあります。
一方、株式型のクラウドファンディング(未上場企業の株式出資)とは異なり、貸付型では利息収入がメインとなり、株価成長による大きな値上がり益は期待できません。その代わり、多くの案件では不動産担保や保証人などの保証措置が設定されており、相場変動の影響を受けにくい安定した運用が可能とされています。例えば不動産担保ローンへの融資案件であれば、不動産という実物資産が裏付けとなるため、万が一借り手が返済不能になっても担保処分による資金回収が図れるケースが多いです。
ただし、融資型クラウドファンディングも元本保証ではない点は銀行預金と決定的に異なります。複数の案件に資金を分散したり、一件あたりの投資額を抑えたりして、リスクをコントロールすることが重要です。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
貯金5,000万円の資産運用の注意点とリスク

高額資産だからこそ分散と安全性を意識する必要がある
5,000万円という大きな資産を運用する際は、「一か所にまとめて預けない・投じない」こと、すなわち分散投資によるリスク低減を強く意識する必要があります。資産をいくつかの異なる商品や分野に分けて投資すれば、一部の投資先で損失が出ても他の収益で補いやすくなり、資産全体が大きく目減りするリスクを抑えられます。例えば、5,000万円を全て株式だけに投じていた場合、株式市場の暴落が起これば資産半減以上の打撃を受けかねません。
しかし、株式・債券・不動産・現金などにバランスよく分散しておけば、一つの資産クラスの不振を他がカバーし、資産全体を守る効果が期待できます。高額な資産だからこそ「全滅」を避ける分散の工夫が肝心です。
流動性を確保して「すぐ使えるお金」も残しておくことが重要
資産運用においては、長期的なリターンを追求する一方で、いざという時にすぐ現金化できる流動性資産を確保しておくことも重要です。5,000万円の資産があるからといって、全額を流動性の低い商品(不動産や満期の長い債券など)に振り向けてしまうと、急な出費や緊急時に必要な資金を用意できない恐れがあります。例えば病気や災害など予期せぬ出費、あるいは絶好の投資チャンスが訪れた際に、手元に使えるお金がないと困ってしまいます。
一般的には、生活費の半年~2年分程度はすぐ引き出せる預金として確保し、残りを中長期の運用に回すなどの方法が推奨されます。特に高額資産を運用する場合、資金繰りの安全網として一定の現金ポジションを維持し、「いつでも使えるお金」と「将来に増やすお金」のバランスを取ることが大切です。
税金や手数料が利益を減らすリスクがある
資産運用で忘れてはならないのが、利益にかかる税金や各種手数料の存在です。せっかく運用が順調でも、税金や高コストのせいで思ったほど手元に残らないケースもあります。
日本では株式の譲渡益や配当金、投資信託の分配金などには原則20.315%(所得税+住民税+復興税)の税金が課されます。例えば年間100万円の運用益が出ても、約20万円は税金で差し引かれてしまう計算です。
また、金融商品の購入・運用には売買手数料や信託報酬(運用管理費用)などのコストもかかります。これら手数料が高い商品ほど、運用益が手数料に食われてリターンが目減りするリスクが高まります。
対策として、NISA(少額投資非課税制度)など運用益が非課税になる制度を活用したり、信託報酬の低いインデックスファンドを選ぶなどして、税金・手数料によるロスを最小限に抑える工夫が重要です。
運用を成功させるためのコツと実践ポイント

投資目的と期間を明確にして計画を立てる
資産運用を始める前に、まず「何のために・いつまでに」増やしたいのかという投資目的と運用期間を明確にすることが大切です。老後資金作りなのか、〇年後の住宅購入資金なのか、といった目的によって取るべきリスクの度合いは変わってきます。運用期間も、短期(数年以内)なのか長期(10年以上先)なのかで適した商品が異なります。
例えば、10年以上先に使う予定の資金であれば株式を含む積極運用も選択肢になりますが、1~2年後に必要な資金であれば元本割れしにくい預金や安全性の高い債券で持っておく方が望ましいでしょう。自分のリスク許容度(どこまでの損失に耐えられるか)を把握しつつ、目的・期間に即した計画を立てることで、ぶれない資産運用が可能になります。
定期的に資産配分を見直す習慣をつける
一度決めたポートフォリオ(資産配分)も、定期的に見直す習慣をつけましょう。市場の値動きやライフイベントの変化により、時間の経過とともに当初の資産配分が自分に適したものではなくなってくる可能性があるためです。例えば株式市場が大きく上昇すると、知らないうちに株式の比率が当初の予定より増えすぎ、ポートフォリオ全体のリスクが高まっていることがあります。
逆に、安全資産に偏りすぎてリターンが伸び悩んでいるケースも考えられます。そこで年に1回程度は資産配分をチェックし、必要に応じてリバランス(資産の組み直し)を行うことが重要です。具体的には、株式比率が上がりすぎていれば一部を売却して債券や現金に振り替える、逆に目標比率より減っていれば買い増す、といった調整をします。
こうした定期的な見直しによって、リスクとリターンのバランスを常に自分の許容範囲内に保つことが、長期的な運用成功のポイントです。
専門家のアドバイスを取り入れてリスクを軽減する
大きな資産を運用する際には、自分だけで抱え込まず専門家の意見を活用するのも有効な手段です。金融機関の資産運用アドバイザーや独立系ファイナンシャルプランナー(FP)など、プロの目線からポートフォリオを診断・助言してもらうことで、思わぬリスクに気付けたり有益な情報を得られたりします。特に5,000万円規模の資産となると、税務や不動産、相続対策など複雑な問題も関わってきます。
信頼できる専門家であれば、最新の税制改正による有利な制度(例:新NISA制度の活用法)や、市場環境に応じた資産移動のタイミングなど、個人では得がたい知見を提供してくれるでしょう。ただし、アドバイザーによっては特定の商品を売りたいあまりに偏った提案をする場合もあるため、複数の意見を聞いたり自分でも基本的な金融知識を身につけておくことが大切です。プロの知恵を上手に取り入れることで、リスクを抑えつつ資産運用をスムーズに進めることができます。
【FAQ】貯金5,000万円の資産運用に関するよくある質問

貯金5,000万円を全額投資に回すのはリスクが高い?
はい、高リスクです。値下がりしうる資産に5,000万円全額を投じれば、市況悪化で資産が半減する恐れもあります。元本保証がない以上、そうした事態も起こり得ます。例えば約1,000万円を預金など流動性資産に残し、残りを複数の投資対象に分散する安全策が必要です。
貯金5,000万円で老後資金は足りるのか?
運用や生活水準によりますが、5,000万円あれば多くの家庭で老後資金として十分と考えられます。2019年に金融庁が公表した報告書では、夫婦が95歳まで生活するケースで、年金だけでは約1,300万~2,000万円不足する可能性があると示されました。5,000万円を保有していれば、この不足分を大きく上回り、年金と併用すれば安心度は高いといえるでしょう。
貯金5,000万円の資産運用で安全性が高い方法はどれ?
安全性が最も高いのは元本保証に近い金融商品です。預金や国債などが該当し、預金は預金保険制度で元本1,000万円まで保護されます。例えば5,000万円全額を複数の銀行に分散預金すれば元本はほぼ確実に守れますが、その分リターンはごくわずかになります。
まとめ|貯金5,000万円を活かす最適な運用の考え方
貯金5,000万円を有効活用するには、預金のまま置いておかず適切に運用することが極めて重要です。金利0.02%では5,000万円あたり年間1万円程度の利息しか得られない一方で、2%のインフレで毎年約100万円の実質目減りとなります。
長期・分散を意識した資産運用によってインフレに負けないリターンを確保し、資産価値を維持・向上させることが最適解と言えるでしょう。
参考元
・金融庁「高齢社会における資産形成・管理報告書」
・総務省統計局「消費者物価指数(CPI)速報値」
・国税庁「令和5年分 相続税の申告及び課税状況(相続税課税割合)」
・東京都区部別「相続税課税割合(令和4年分)情報(都内各区例)」
・IMF「2025年対日4条協議終了に関する報告書」