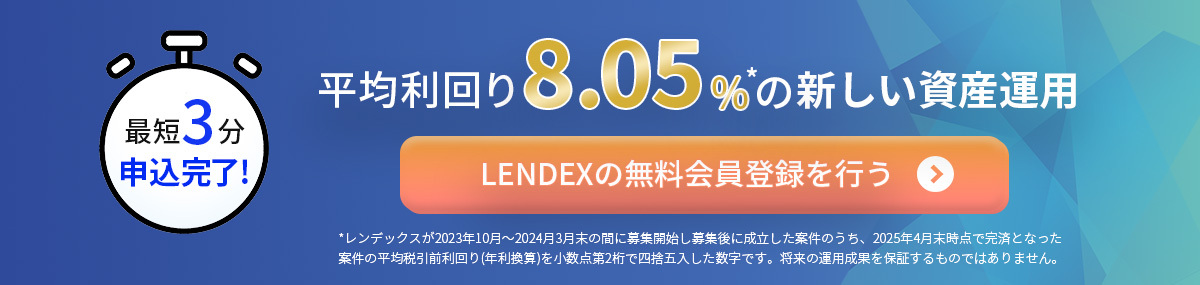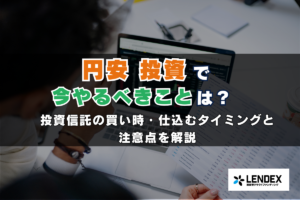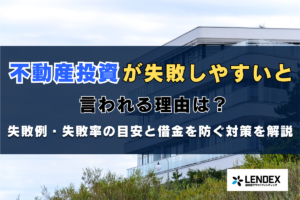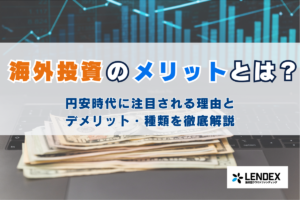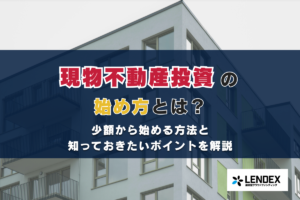『海外不動産投資』に興味はあるけれど、メリットやリスクが分からず迷っている方も多いのではないでしょうか。実際、国内では資産形成の選択肢が広がる中で、海外市場に目を向ける人も増えています。しかし、魅力的に見える一方で「情報が少なくて不安」「どの国を選べばいいのか分からない」といった声も少なくありません。
なぜ海外不動産投資は注目されるのでしょうか。本記事では、国内投資との違いや仕組みを整理し、メリットとデメリットを専門的にわかりやすく解説します。さらに、初心者が失敗を避けるための始め方や注意点についても紹介します。
海外不動産投資とは?基本をわかりやすく解説

国内不動産投資との違いを理解する
海外不動産投資は、日本国内の不動産投資とは異なるリスクと利点があります。まず為替リスクが加わり、通貨の変動によって利益にも損失にも影響します。また情報入手や現地調査が難しく、日本とは商習慣や法規制が異なる点に注意が必要です。
例えば東南アジアの多くの国では外国人は土地を所有できず、コンドミニアム(区分所有マンション)のみ所有可能など制限があります。こうした違いを理解せずに始めるとトラブルに発展しかねないため、事前のリサーチが欠かせません。
海外不動産投資の仕組みをシンプルに説明
海外で不動産を購入する場合、基本的な流れは「物件探し → 現地視察 → 購入交渉・契約 → 登記・決済 → 賃貸運用または売却」です。現地の信頼できる不動産仲介会社や弁護士を通じて契約手続きを進め、言語の壁や法律の違いを専門家のサポートでカバーします。国によって決済方法や制度は様々ですが、例えばアメリカではエスクロー会社が取引に中立介入し、権利調査から代金受け渡しまで安全に進める仕組みが整っています。
また国によっては外国人でも住宅ローンを組めるケースがありますが、難しい場合は自己資金での購入や日本からの融資活用も検討します。購入後は現地の物件管理会社に委託して運用するのが一般的で、家賃送金や維持管理も含めたトータルの仕組みを把握しておくことが重要です。
投資対象になる物件や国の特徴
海外不動産投資の対象は、マンションや戸建住宅から商業物件、リゾート物件まで多岐にわたります。投資先の国ごとに不動産市場の特徴があります。
例えば、新興国では若い人口による住宅需要増加が期待でき、経済成長に伴い不動産価格も上昇しやすい傾向です。一方で先進国の都市部は市場が成熟しており、安定した賃貸需要がある反面、物件価格が高く利回りは低めです。国ごとの外国人規制にも特徴があり、アメリカやヨーロッパの多くの国では外国人でも自由に不動産を購入できますが、アジア新興国では購入できる物件種別や戸数割合に制限がある場合があります。
投資対象国の経済状況、人口動態、法制度を把握し、その国ならではのメリットを活かせる物件を選ぶことが成功のカギとなります。
海外不動産投資で得られる主なメリット
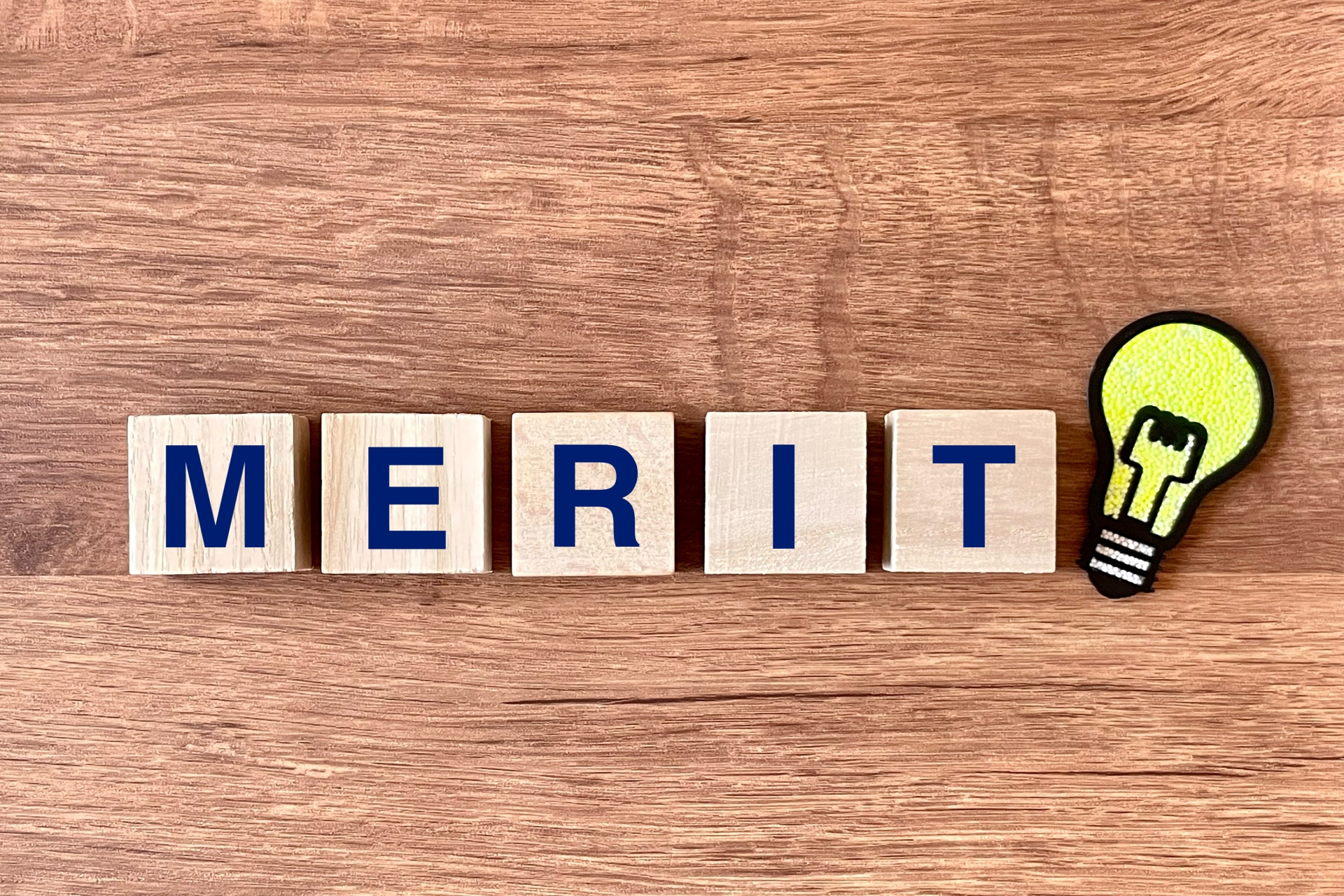
高い利回りが期待できる
海外不動産は日本国内よりも高い賃貸利回りが期待できる点が大きなメリットです。新興国を中心に家賃収入の割合(利回り)が5~9%程度に達する国もあり、国内不動産の平均利回り(おおよそ3~4%前後)を大きく上回ります。例えばエジプトの首都カイロでは、平均的なグロス賃貸利回りが約6~8%前後と報告されており、新興国市場として比較的高い水準にあります。
同じ投資額でも海外ではより多くの家賃収入を得やすく、資金回収期間を短縮できる可能性があります。ただし利回りが高いほどリスクも高まる傾向があるため、物件の収益性だけでなく治安や市場安定性も合わせて判断することが重要です。
為替差益による資産増加のチャンスがある
海外不動産投資では為替レートの変動によって資産価値が増減しますが、円安方向に振れた場合には大きな為替差益を得られるチャンスです。日本円以外の外貨建て資産を持つことで、円の価値が下がった際に相対的に資産評価額が上昇します。
実際、近年も急激な円安が進行し、2022年には為替レートが1ドル=115円程度から9か月で150円を突破する約40%の円安となりました。このように円が下落すれば、ドルや現地通貨建ての不動産の円換算価値が大きく上昇します。ただし為替は常に変動するため、差益を狙う場合も長期的な視点で捉え、一方的な楽観は禁物です。
将来的な資産分散や保有価値の安定につながる
海外不動産はポートフォリオの分散効果を高め、資産全体の安定性向上に寄与します。日本国内だけでなく経済成長が見込まれる国の不動産も組み入れることで、一国の景気や人口動向による資産価値変動リスクを分散できます。
実際、日本は既に人口減少局面にあり不動産需要の先細りが懸念されますが、例えばフィリピンは2060年代以降も人口増加が続き、2093年までプラス成長が見込まれると予測されています。このように若年人口が多く成長力のある国の不動産を保有すれば、中長期的に資産価値が下支えされる可能性が高まります。また、外貨建て資産を持つことで円のインフレや信用不安へのヘッジにもなり、複数通貨で資産を保有することが将来の財産の安定につながるでしょう。
海外不動産投資のリスクやデメリット
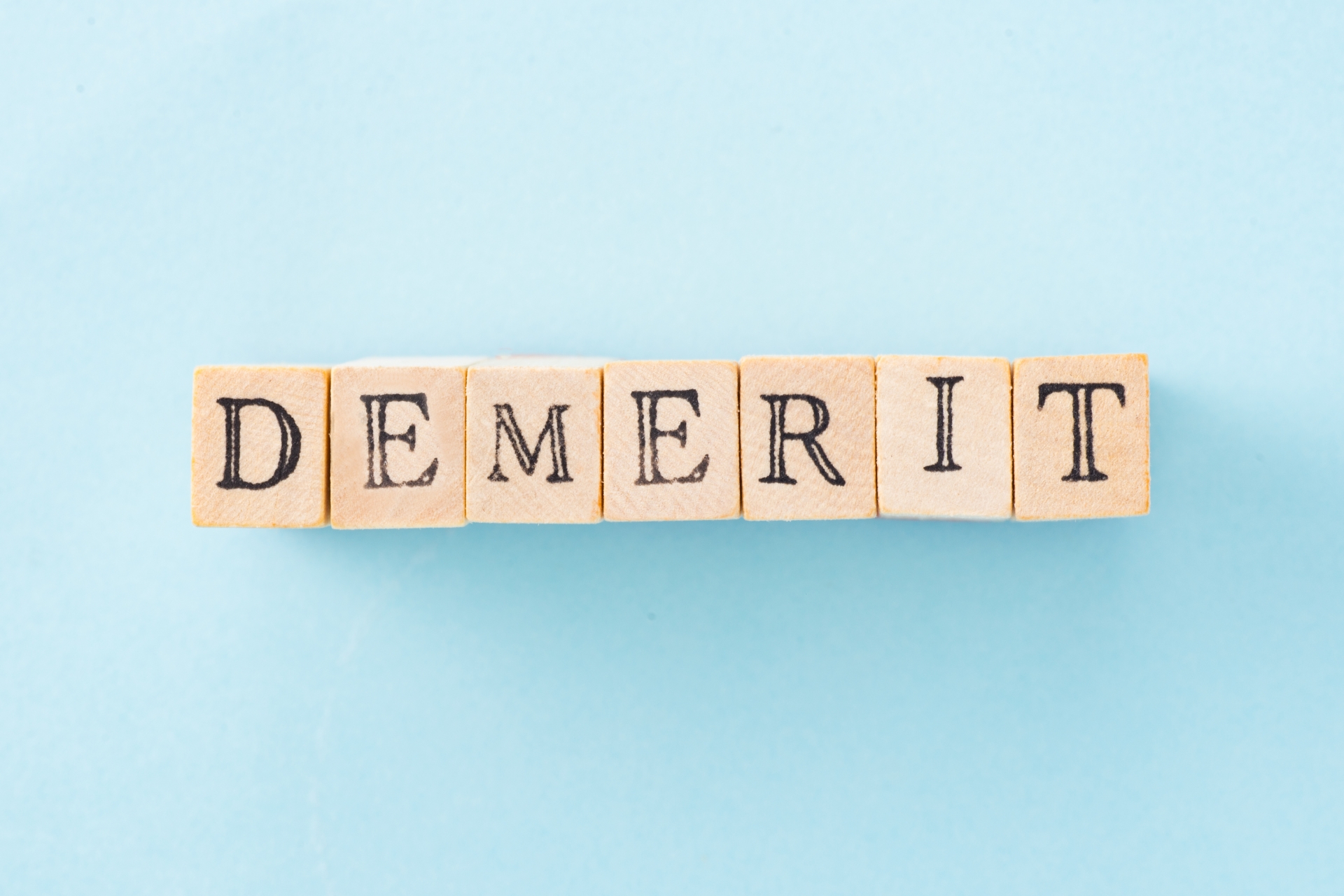
為替変動による損失リスクがある
為替差益はメリットである一方、為替変動は損失リスクも孕んでいます。
円高方向に大きく振れた場合、現地通貨建てで価値が変わらなくても円換算の評価額は目減りします。例えば投資当初に1ドル=150円だったものが将来120円になれば、ドル建て資産の円評価額は20%も減少する計算です。
加えて、為替手数料や送金コストも利益を圧迫する要因になります。為替相場の予測は困難であり、不動産投資は長期に及ぶため、その期間の通貨変動による損益は無視できません。為替リスクを抑えるためには、現地通貨での借入れを活用して資産と負債を同じ通貨にする、あるいは為替ヘッジ手段を講じるなどの対策も検討すると良いでしょう。
法制度や規制の違いでトラブルになる可能性がある
各国の不動産に関する法律や規制の違いは、海外投資で注意すべき重要なポイントです。
国によっては外国人の不動産所有が制限されており、そのルールを誤解すると最悪の場合違法行為になりかねません。例えばベトナムでは外国人によるコンドミニアム所有は全戸数の30%までと決められており、フィリピンやタイなど多くの国で外国人が土地を直接所有することは禁止されています。
また物件購入時の契約制度や権利の考え方も異なり、日本では考えられない商習慣によるトラブルも起こり得ます。こうした法制度の違いによるリスクを避けるためには、現地の法律専門家に確認したり、JETROなど公的機関の提供する最新情報を参照したりして、事前にルールを正しく理解しておく必要があります。
管理や売却が難しくコストがかさむリスクがある
海外物件は距離の壁から管理や売却のハードルが高くなります。
物件購入後は賃貸経営を現地の管理会社に依頼するケースが一般的ですが、その分毎月の管理手数料や維持費などコストが発生します。さらに入居者募集やクレーム対応も直接自分では行えないため、現地業者の対応品質に左右される部分が大きいです。
また、市場環境によっては空室リスクも深刻になります。近年、東南アジアの一部都市ではコンドミニアムの建設が急増し、地域や価格帯によっては一時的に供給が需要を上回るケースも見られます。その結果、物件によっては入居者獲得に時間がかかるなど空室リスクが発生する可能性があります。
いざ売却しようとしても、現地で信頼できる買い手を見つけたり適正価格で売却したりするのは簡単ではありません。売却までに時間がかかる間も固定資産税や維持費は発生し続けます。こうした管理・売却面の難しさとコスト増大リスクも、海外不動産投資のデメリットとして織り込んでおく必要があります。
海外不動産投資におすすめの国5選
アメリカ
アメリカは世界最大の経済規模を誇り、安定した成長を続けているため不動産投資先として根強い人気があります。政治経済の安定性や法制度の整備度が高く、外国人でも内陸部からハワイに至るまで基本的に自由に不動産を購入可能です。
実際、アメリカでは外国人や海外企業も原則としてアメリカ人と同様に不動産取引が認められており、権利保護もしっかりしています。アメリカの賃貸不動産は都市や物件タイプによって利回りに差がありますが、一般的に日本と同水準ながらローリスク・ミドルリターンの堅実な投資先と評価されています。
特に近年は中国をはじめ海外の富裕層投資家も積極的に米国不動産を購入しており、その安定性が裏付けられています。都市部の物価や物件価格は高騰傾向にありますが、逆に地方都市やリゾート地のコンドミニアム投資などでは比較的手頃な価格帯で高い賃貸需要を狙うことも可能です。
経済力と法整備に優れたアメリカは、初心者からプロまで安心して取り組みやすい投資先と言えるでしょう。
フィリピン
フィリピンは東南アジアでも特に高い経済成長率と若い人口構成を背景に、不動産市場の将来性が注目されています。
コロナ禍の落ち込みを除けば安定して年5~7%前後の高成長を維持しており、IMF予測でもASEAN諸国中トップクラスの年約6.5%成長が見込まれています。人口は1億人を超え、平均年齢も25歳程度と非常に若く、働き手となる生産年齢人口が今後も増加する見通しです。
こうした背景から住宅需要の拡大と不動産価格上昇が期待でき、実際、マニラ首都圏の主要エリアでは2024年時点で居住用マンションの平均平米単価が約139,000ペソ(約37万円)と報告されており、上昇傾向が続いています。それでも日本の大都市より割安感があり、賃貸利回りは高水準でインカムゲインも得やすいです。
さらに公用語が英語であるため言語の壁が低く、契約や運用面でも比較的スムーズなのも利点でしょう。フィリピンは高成長・高利回りを狙いたい人にとって、有望な候補国の一つです。
マレーシア
マレーシアは政治・経済の安定度が高く、生活環境の良さから日本人にも長年人気の国です。
実際、2006年から2019年まで14年連続で「日本人が住みたい国」世界第1位に選ばれており、多くの日本人が移住先や長期滞在先にマレーシアを希望してきました。人口約3,400万人と適度な市場規模を持ち、近年も東南アジア平均を上回る人口増加率で推移しています。
経済成長率も安定しており、2025年の予測GDP成長率は4.4~4.5%と先進国並みの堅調な数字です。また、一人当たり所得が高く中間層が厚いため、賃貸需要の質も安定しています。外国人への不動産購入規制が緩やかな点も魅力です。
マレーシアでは外国人による不動産購入に最低価格規制が設けられており、一般的には州政府が定める下限額(約2,200万~3,200万円程度)以上の物件であればコンドミニアムや土地付き戸建ても所有が可能です。そのため東南アジアの中でも比較的外国人投資家に開かれた市場といえます。
クアラルンプールなど都市部の想定利回りは周辺国ほど高くはなく4%前後ですが、不動産価格の上昇によるキャピタルゲインも狙える環境です。多民族国家で英語も通じやすく、日本人コミュニティや日本食レストランなど生活インフラも整っているマレーシアは、安心感と将来性を兼ね備えた投資先として有力です。
タイ
タイは東南アジアにおける拠点国の一つで、日本人駐在員や企業進出も非常に多い国です。
実際、在留邦人は約7万人に達しており、日本人街が形成されるほど生活面での受け入れ基盤があります。首都バンコクを中心に交通インフラが飛躍的に発展し、不動産市場も長期的な成長を続けています。
バンコク市内のコンドミニアム投資は比較的少額から始められる案件も多く、1ユニット300万バーツ(約1,350万円)未満の低価格帯コンドの供給が増加する見通しです。賃貸利回りは首都圏でおおむね4~5%程度と安定した水準で、過去10年にわたり堅調な賃貸需要が見られます。
タイの魅力の一つに、比較的抑えられた不動産関連税制があります。例えば、固定資産税(土地・建物税)は評価額の0.02~0.1%程度と国際的に見ても低い水準に設定されています。また、賃貸収入に対しては累進所得税の対象となりますが、減価償却や必要経費が認められるため、実効税負担は抑えられるケースもあります。その結果、適切に申告・控除を行えば手取り利回りが確保しやすい環境にあるといえます。
さらに温暖な気候と豊富な観光資源によって、バンコクやプーケットなどでは外国人旅行者向けに物件を貸し出すバケーションレンタル需要も期待できます。政治的安定性や法制度面での課題はありますが、日本とも関係が深く情報収集もしやすいタイは、初心者にも比較的取り組みやすい海外投資先と言えるでしょう。
エジプト
エジプトは中東・アフリカ地域で注目される新興市場の一つです。
人口は約1億1,840万人に達してなお年2%超で増加を続けており、15~64歳の生産年齢人口が全体の60%を占める若い人口ピラミッド構造が特徴です。平均年齢(中央値)はわずか24.1歳と非常に若く、将来的な住宅需要の拡大余地が大きいことが期待されます。
不動産投資の観点でもカイロなど主要都市の賃貸利回りは約9%以上と高水準で、世界的に見てもトップクラスの収益性を誇ります。物件価格も平米あたり数百ドル程度からと安価で、限られた予算でも大きな物件を取得できる可能性があります。
高い利回りと若年層主体の人口増による成長期待から、エジプト不動産は高リスク・高リターンを狙う人にとって魅力的な選択肢となります。ただし、為替の不安定さやインフラ整備状況、政治情勢などリスク要因も併存しますので、現地経済の動向を注視しながら慎重に判断することが求められます。
| 国名 | 経済・政治安定性 | 投資リスク・利回り | 投資のポイント |
|---|---|---|---|
|
🇺🇸 アメリカ
|
世界最大の経済規模 政治・法制度が安定 外国人投資に開放的 成熟した不動産市場 |
ローリスク
利回り:日本同水準
ミドルリターン |
• 地方都市が狙い目 • 初心者でも安心 • 情報収集が容易 • 権利保護が確実 • ドル建て資産として人気 |
|
🇵🇭 フィリピン
|
年5〜7%の高成長維持 IMF予測:年6.5%成長 人口1億人超・平均年齢25歳 新興国リスクあり |
ミドルリスク
利回り:高水準
ハイリターン期待 |
• マニラ首都圏が中心 • 日本より割安感 • 公用語が英語 • 若年層主体の人口構成 • 住宅需要拡大期待 |
|
🇲🇾 マレーシア
|
政治・経済が安定 2025年予測:4.5%成長 人口3,400万人・中間層厚い 外国人に開放的 |
ローリスク
利回り:約4%
安定収益+値上がり |
• 最低価格規制あり • 14年連続「住みたい国1位」 • 英語が通じる • 日本人コミュニティ充実 • 多民族国家で安定 |
|
🇹🇭 タイ
|
東南アジア拠点国 インフラが発達 在留邦人7万人 日本企業進出多数 |
ローリスク
利回り:4〜5%
安定水準 |
• 少額投資可能 • 低い不動産税制 • バケーションレンタル需要 • 温暖な気候 • 情報収集しやすい |
|
🇪🇬 エジプト
|
中東・アフリカ新興市場 人口1億1,840万人 平均年齢24.1歳と若い 政情・為替不安定 |
ハイリスク
利回り:約9%以上
ハイリターン |
• 平米数百ドル〜と安価 • 大型物件狙い • 為替リスク要注意 • 上級者向け • 将来の住宅需要大 |
海外不動産投資の始め方|初心者が押さえるステップ
投資先の国やエリアを選ぶ
投資を始める際には、まず投資先の国を選ぶことが大切です。
国ごとに経済成長率や利回り水準、法制度やリスク要因が異なるため、自身の投資目的に合った国・地域を絞り込みます。例えば、高利回りを重視するなら経済成長が著しい東南アジアや中東欧の新興国が候補になりますし、安定性を重視するなら先進国の主要都市やリゾート地が視野に入るでしょう。各国の政治・経済状況、人口動態、そして外国人投資に対する規制の有無を調べ、将来的な見通しも考慮して選定します。
また、日本との時差や地理的距離も無視できません。管理や視察のしやすさという点では、日本から近くアクセスの良いアジア地域は初心者にも取り組みやすいと言えます。最終的には複数候補の国のマーケット情報を比較し、最も魅力とリスクのバランスが取れた投資先を選びましょう。
信頼できる仲介業者や情報源を探す
投資する国が決まったら、その国で実績のある信頼できる不動産仲介業者や情報提供者を見つけることが不可欠です。
海外不動産投資では現地の仲介会社、エージェント、管理会社など複数のビジネスパートナーが関与します。そのため、パートナー選びを誤ると詐欺被害やトラブルに発展するリスクがあります。
まずはJETRO(日本貿易振興機構)の現地事務所や各国の日本人コミュニティの評判などを参考に、信頼性の高い仲介業者リストを把握しましょう。問い合わせのレスポンスや契約内容の透明性、過去の取引実績などを確認し、複数社を比較検討すると安心です。
また、不明点は遠慮なく現地の専門家(弁護士や会計士)に相談し、セカンドオピニオンを得ることも大切です。物件情報についても一社の説明だけを鵜呑みにせず、公式の統計資料や現地ニュース、不動産ポータルサイトなど複数の情報源で裏付けを取るようにしましょう。信頼できるパートナーと正確な情報に基づいて進めることが、海外投資を成功させる秘訣です。
契約から購入、運用までの基本的な流れを把握する
実際の購入プロセスの流れをあらかじめ理解しておくことも重要です。一般的には、現地で物件視察→購入申し込み(オファー)→価格交渉→売買契約→決済・登記という手順を踏みます。
契約段階では日本と異なる契約書式や手付金のルールがありますので、現地の不動産弁護士など専門家にチェックしてもらいましょう。決済時にはエスクロー(第三者預託)や公証人制度が利用できる国もあり、安全に所有権移転と代金支払いを行います。
購入後は賃貸運用を開始しますが、物件管理会社と賃貸管理契約を結び、入居者募集・契約・家賃回収・メンテナンス対応などを委託するのが一般的です。海外送金で家賃を受け取る場合の手数料や、現地で発生する税金の納付方法(現地納税か日本での申告か)についても事前に確認しておきます。
出口戦略として売却の流れも頭に入れておきましょう。売却時には現地の不動産仲介会社に媒介を依頼し、買主との価格交渉・契約・決済という流れになります。国によっては譲渡益課税や印紙税が課されるため、手取り額がいくらになるかも試算しておく必要があります。
これら購入から運用・売却までの基本フローを把握しておけば、実際の投資プロジェクトを進める際にも落ち着いて対処できるはずです。
|
1
3〜7日
|
→ |
2
1〜3日
|
→ |
3
3〜10日
|
→ |
4
1〜2日
|
→ |
5
1〜3日
|
海外不動産投資で失敗しないための注意点
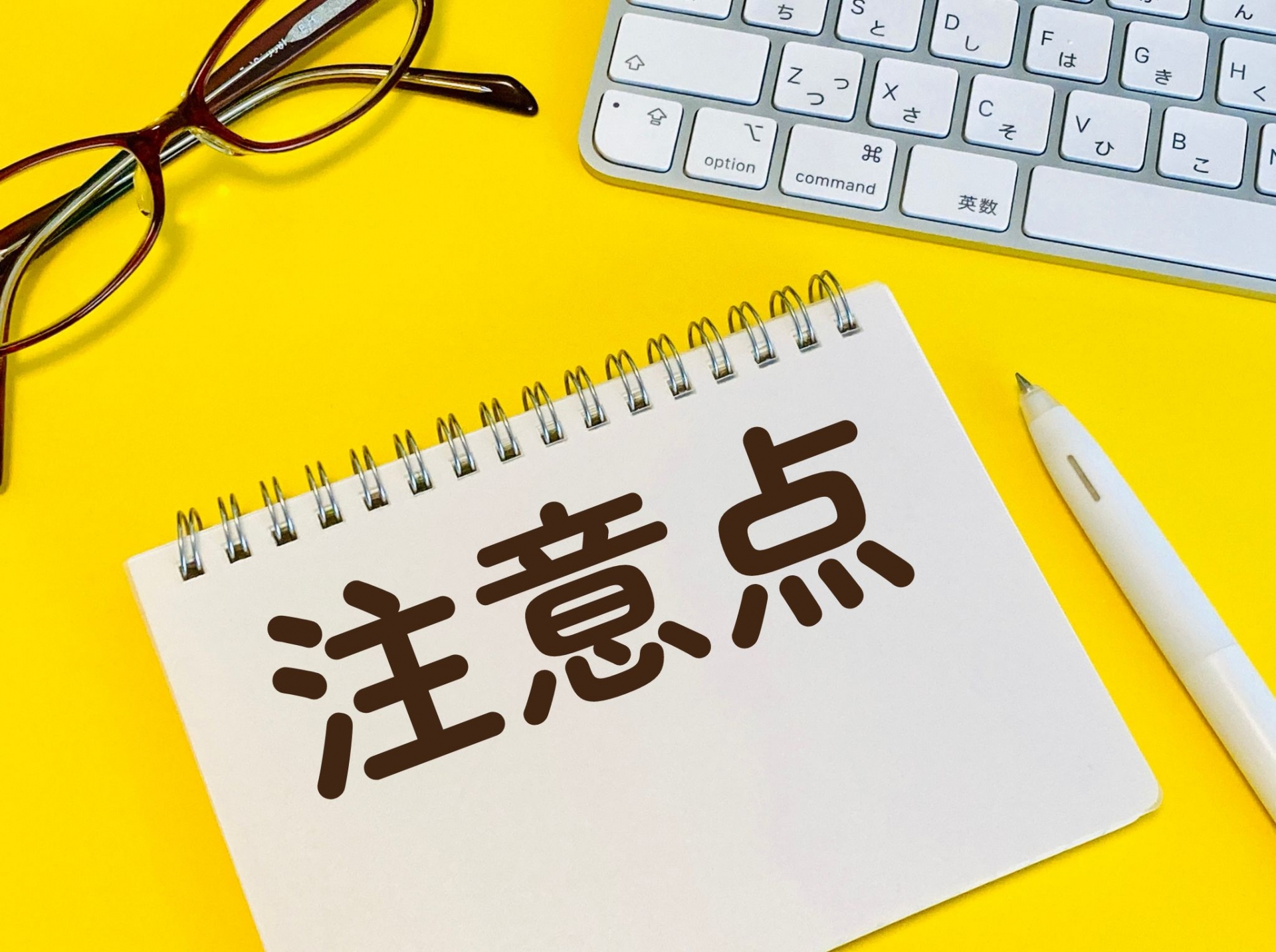
利回りや条件が良すぎる案件に注意する
高利回りや好条件をうたう案件には慎重な姿勢が求められます。「必ず値上がりする」「○年で家賃保証」といった甘い誘い文句には裏がある可能性があります。現地の市況を無視した楽観的な収支計画や、相場とかけ離れた利回りを提示された場合は要注意です。
特に新興国の不動産では、開発業者や販売会社が情報格差を利用して、実際にはテナントが付かない物件を魅力的に見せかけるケースも報告されています。利回りは投資判断の重要な指標ですが、数字だけで飛びつかず、その裏付けとなる現実の賃貸需要や経済状況を確認しましょう。
周辺の類似物件の賃料相場や過去の売買履歴を調べ、極端に高い利回りが継続可能なのか検証することが大切です。投資の世界では「うますぎる話は疑え」が鉄則であり、慎重すぎるくらいで丁度良いと心得ましょう。
税制や法律を事前に確認する
投資対象国の税制や法律を事前に十分確認しておくことも、失敗を防ぐポイントです。
不動産取得時には印紙税や取得税、保有中は固定資産税や都市維持税、賃貸収入への課税、売却時には譲渡所得税など、国ごとに様々な税金が課されます。日本との租税条約により二重課税が調整されるケースもありますが、現地で納税が必要な税金については漏れなく対応しなければなりません。
また、購入手続き上の法律事項も重要です。外国人が不動産を購入する際に政府の許可申請が必要な国や、特定のビザステータスでないと購入できない国もあります。例えばマレーシアでは州政府の許可が必要で最低購入価格が定められており、インドネシアでは外国人個人での土地取得ができないため法人設立が求められるなどの規制があります。
さらに、投資スキームによっては現地通貨での口座開設や送金証明の取得といった手続きも発生します。事前に現地専門家から税務・法務アドバイスを受け、自分の投資計画にどのような法的義務とコストが伴うかを明確にしておきましょう。
複数の情報源から比較検討する
海外不動産投資では情報の非対称性を突かれないよう、常に複数の情報源から物件や市場を分析する姿勢が大切です。現地の不動産会社から提供される情報だけで判断せず、第三者のデータや公的な統計、他の投資家の評判なども参考にしましょう。
例えば、投資対象地域の経済成長率や人口推移、空室率などは現地政府や国際機関の発表データを確認すると客観的に掴めます。また、一つの物件について複数の仲介業者に問い合わせ、提示条件を比較するのも有効です。
言語の壁がある場合は、日本語で読めるJETROの海外ビジネス情報や各国の日本大使館ウェブサイトなどで基礎知識を得ると良いでしょう。セミナーや勉強会で実際に海外投資を行っている人の体験談を聞くことも有益です。
様々な情報を集めて総合的に判断すれば、リスクを見落とす可能性が減り、より確度の高い投資判断につながります。焦らず情報収集と比較検討に時間をかけることで、失敗しない堅実な投資を実現しましょう。
海外不動産投資のリスクを抑える分散投資の考え方
国内と海外の不動産を組み合わせる方法
資産運用全体の中で、国内不動産と海外不動産をバランスよく組み合わせることでリスク分散効果が高まります。
例えば、資産の一部は日本国内の不動産(比較的安定だが低利回り)に投じ、残りを海外の不動産(利回りは高いがリスクも高め)に振り分けるといった手法です。こうすることで、日本経済や円相場に何かあっても海外資産がカバーし、逆に海外市場が不調な場合も国内資産で補完できます。具体的な配分比率は投資家のリスク許容度によりますが、慎重な場合は「国内多め・海外少なめ」、積極運用なら「海外多め」にするなど調整します。
さらに海外不動産の中でも複数の国や地域に分散投資すれば、一国の情勢悪化に左右されにくくなります。例えばアジアと欧米に資産を振り分ければ、地域ごとの経済サイクルの違いを利用してポートフォリオの安定性を高められます。
国内×海外の組み合わせは、資産全体のボラティリティを抑えつつリターン機会を拡大する有効な手段です。自分の資産状況に応じて無理のない範囲で両者を組み合わせ、長所を取り入れるよう心がけましょう。
不動産と金融商品を併用するメリット
海外不動産だけに集中投資するのではなく、他の金融商品と組み合わせることでリスクを抑えつつ安定した運用が可能になります。
不動産は相対的に流動性が低く売却に時間がかかるため、流動性の高い商品(株式や債券、投資信託など)もポートフォリオに含めることで資金繰りの柔軟性を確保できます。例えば、不動産投資による家賃収入に加えて株式の配当金や債券の利息収入があれば、どれか一つの収入源が一時的に途絶えても他で補える安心感があります。
また、不動産市況と株式市場は必ずしも連動しないため、資産クラスを分散することで経済変動に対する耐性が増します。具体的な併用例としては、海外不動産を直接購入する代わりにREIT(不動産投資信託)や不動産クラウドファンディングを利用して少額ずつ複数の不動産プロジェクトに出資する方法があります。これにより、一物件に大金を投じるよりもリスクが細分化され、安定したリターンを得やすくなります。
実際、多くのクラウドファンディングサービスでは複数案件への分散投資が推奨されています。複数の金融商品を組み合わせた分散投資で、安全性と収益性のバランスが取れた資産形成を目指しましょう。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】海外不動産投資に関するよくある質問

海外不動産投資は本当に儲かるの?
はい、適切に運用すれば利益を得ることは可能です。 経済成長が著しく賃貸利回り5~9%程度の国を選べば、日本国内より高い収益を狙える条件です。例えばフィリピン・マニラの賃貸利回りは約5~6%とされ、日本より高水準の家賃収入が期待できます。
海外不動産投資は初心者でも始められる?
はい、初心者でも少額から段階的に始められます。 まずは情報収集を行い、信頼できる仲介会社やクラウドファンディングなどを利用すればハードルが下がります。例えば2万円程度から出資できる不動産ファンドを活用し、リスクを抑えて小口で始める方法もあります。
どの国の不動産に投資するのが安全なの?
一概に「この国なら絶対安全」というものはありませんが、法制度の整った国ほど安心です。 アメリカやイギリスなど先進国は外国人にも所有権が認められ、透明性の高い取引制度があります。例えばアメリカではエスクロー制度により海外からでも安心して不動産取引が行える仕組みが整っています。
海外不動産投資の税金や手続きはどうなっているの?
税金や手続きは国ごとに異なりますが、現地税と日本での申告の両方を考慮する必要があります。 現地では物件取得時の税金や賃貸収入への課税があり、日本では国外所得として申告しなくてはなりません。例えばアメリカでは毎年不動産評価額の約1~2%の固定資産税を納め、日本では外国税額控除を利用して二重課税を調整する仕組みがあります。
まとめ|海外不動産投資のメリットとデメリットを理解して賢く始めよう
海外不動産は日本国内より高い利回り(地域によっては7~9%台)や分散投資効果など魅力が多い一方、為替リスクや法規制の違いといったデメリットも伴います。メリットとデメリットを正しく理解し、信頼できる情報に基づいて計画を立てれば、海外不動産投資で資産を効果的に運用できるでしょう。
小額からの分散投資や現地専門家の活用などリスク低減策を講じつつ、高利回りと安定運用を両立する賢い第一歩を踏み出してください。
参考元
・JETRO(日本貿易振興機構)「海外進出・投資の現地法制度・ビジネス環境解説」
・内閣府「対直接投資の現状」
・国税庁「外国税額控除を受けられる方へ(居住者用)」
・米国国務省「Egypt – Protection of Property Rights/Foreign Real Estate Ownership」
・衆議院憲法調査会事務局「フィリピン共和国憲法-概要及び翻訳-」(衆憲資第19号)
・国土交通省「マレーシアの不動産関連情報」
・国土交通省「タイの不動産関連情報」
・英国政府「Buying Property in Egypt」
・国連「World Population Prospects 2024年版」
・UNFPA「Egypt – World Population Dashboard」
・フィリピン政府統計局「Philippine Population is Projected to be around 138.67 million by 2055」