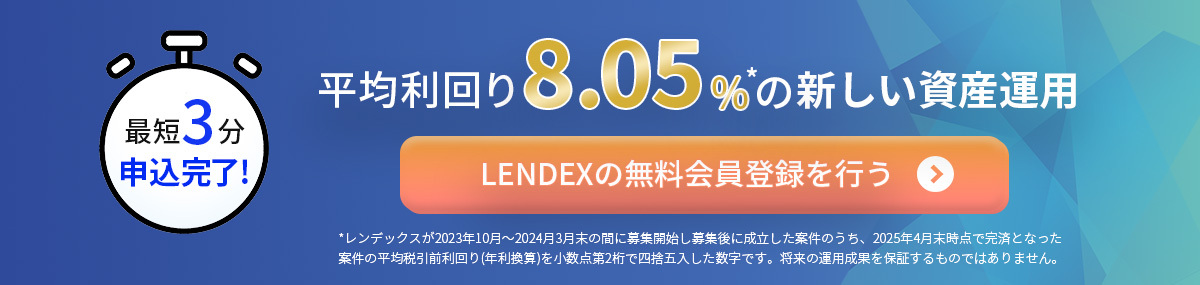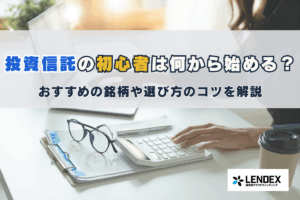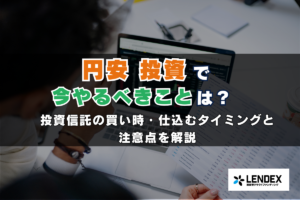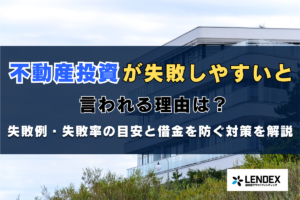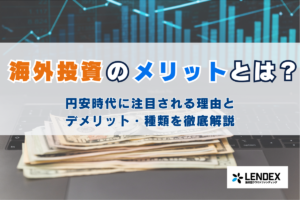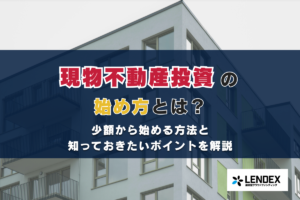近年、投資の選択肢として「太陽光発電投資」が注目を集めています。実際、固定価格買取制度(FIT)をきっかけに多くの投資家が参入し、長期的な安定収入を得ている事例もあります。しかし一方で、「思ったより儲からない」「リスクが大きい」という声も聞かれ、誰にでもおすすめできる投資ではないのも事実です。
では、なぜ太陽光発電投資には賛否が分かれるのでしょうか。本記事ではメリットとデメリットを専門的に解説し、失敗を避けるための対策や利回りの実情まで詳しく紹介します。これから投資を検討している方にとって、判断の一助となる内容をお届けします。
太陽光発電投資はおすすめできる?結論を先に解説
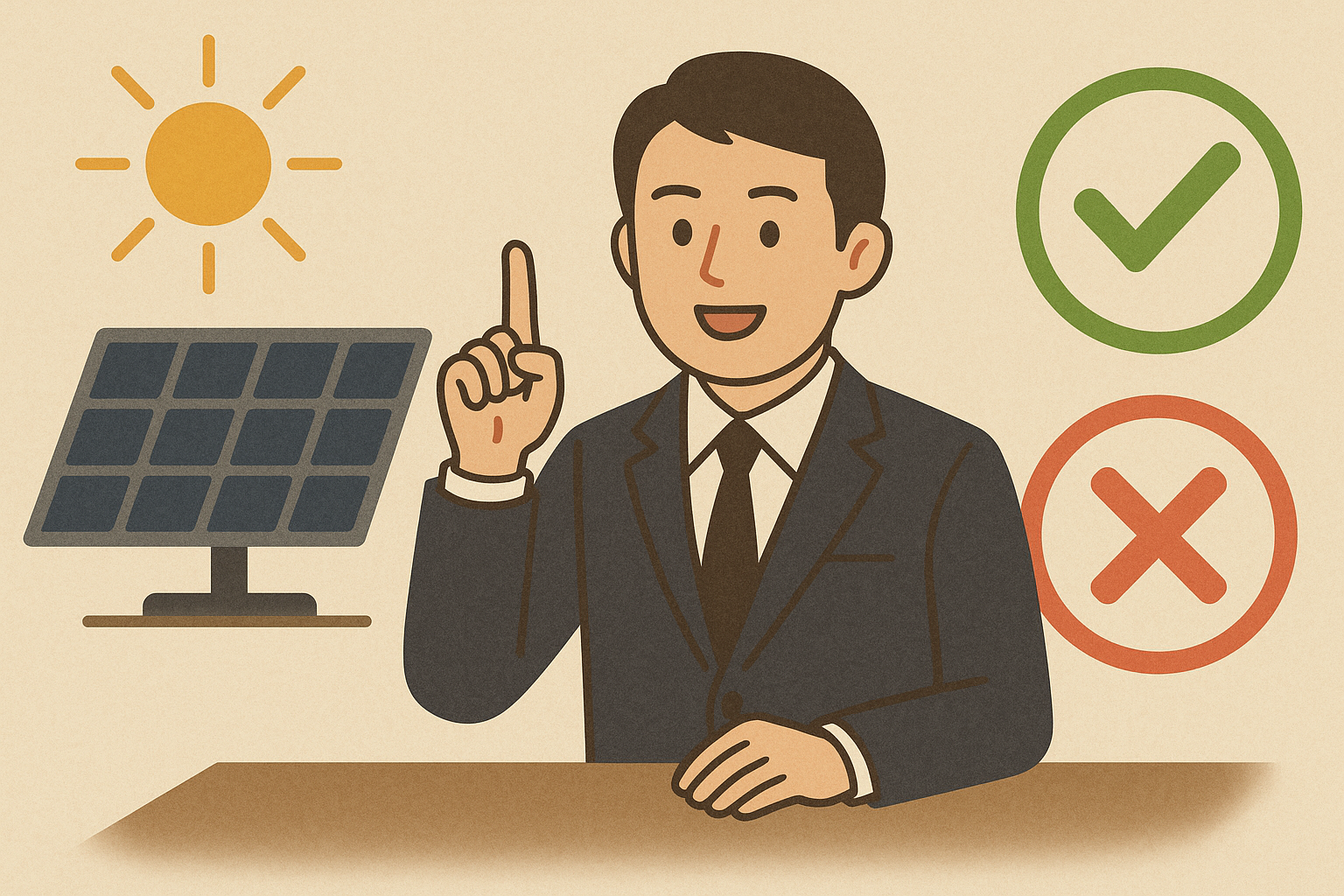
太陽光発電投資は条件を満たせば安定収入が期待できる
太陽光発電投資は、一定の条件を満たすことで長期的な安定収入を期待できる投資方法です。国の固定価格買取制度(FIT)では、事業用太陽光の場合に20年間の売電価格が固定されるため、収益計画を立てやすい点が大きな特徴です。これにより、景気や不動産市況に左右されず、契約期間中は継続的に売電収入を得られる仕組みが整っています。
ただし、安定した収益を実現するにはいくつかの条件が重要です。
第一に、十分な日照が確保できる立地を選ぶこと。次に、信頼性の高い設備や施工会社を利用し、長期的に稼働できる環境を整えることです。さらに、設備の劣化や天候変動による発電量の変化を踏まえたシミュレーションを行うことが求められます。
これらの条件を満たした上で適切に管理すれば、太陽光発電投資は安定したインカムゲインを得られる有効な選択肢となり得ます。
初期費用やリスクを理解していないとおすすめできない
一方で、太陽光発電投資は初期費用の高さや各種リスクを理解していないと安易にはおすすめできません。設備設置には1kWあたり約20万円以上の費用がかかり、例えば出力50kW規模の発電所では数千万円規模の資金が必要になります。
また、融資を利用する場合はローン返済も伴うため、利回り計算時には金利や維持費を含めた実質利回りを把握することが重要です。初期費用回収まで年数を要し、自然災害・設備故障・制度変更などのリスクによって収益が変動し得る点を十分認識しておく必要があります。
太陽光発電投資が注目される理由と主なメリット

売電による長期的な安定収入が見込める
太陽光発電投資最大の魅力は、電力会社への売電による長期安定収入が見込めることです。10kW以上の事業用太陽光発電では20年間の固定価格買取期間が設定されており、契約時に決まった単価で電力を買い取ってもらえます。
そのため、景気や物件需要に左右されにくく、空室リスクのない家賃収入のように毎月安定したインカムゲインを得ることができます。適切な設備管理を行えば計画通りの発電量を維持しやすく、長期にわたり確度の高い収益計画を立てられる点が注目される理由です。
再生可能エネルギーとして社会貢献できる
太陽光発電はクリーンな再生可能エネルギーであり、社会貢献につながる点も大きなメリットです。発電時にCO2を排出しないため、導入すれば自らの投資活動で地球温暖化対策に貢献できます。
例えば家庭用4kWシステムでも年間約2.0トンのCO2削減効果があり、50kW規模なら年間10数トン以上の排出削減が可能です。再生エネ普及によるエネルギー自給率向上や地域の脱炭素化にも寄与でき、環境意識の高まりと相まって社会的評価が得られる投資と言えるでしょう。
節税や補助金制度を活用できる可能性がある
太陽光発電投資には、条件を満たせば税制優遇や補助金制度を活用できる可能性があります。
企業向けには「カーボンニュートラル投資促進税制」により、設備投資額の最大5~14%相当の税額控除や50%の特別償却を受けられる制度が整備されています。また、地方自治体によっては太陽光設備導入への補助金が用意されている場合もあり、初期費用の一部を公的支援で軽減できるケースもあります。
こうした優遇策を上手に利用することで、実質的な負担を下げ投資効率を高められる点も太陽光投資のメリットの一つです。
太陽光発電投資のデメリットと注意すべきリスク

初期費用や借入負担が大きい
太陽光発電投資の代表的なハードルは、初期費用の大きさと借入負担です。発電設備や工事にはまとまった資金が必要で、初期費用が1,000万円以上に及ぶことも珍しくありません。
自己資金だけで賄えない場合、多くは金融機関からの融資を利用しますが、その場合は毎月のローン返済が収益から差し引かれるため、計画通りの発電量と売電収入を確保できないと赤字リスクも生じます。設備認定や土地契約など初期手続きにもコストや時間がかかり、大きな先行投資を回収するまでの期間が長い点は注意が必要です。
自然災害による発電停止リスクがある
屋外に設置する太陽光発電設備は、台風・豪雨・地震など自然災害による被害リスクを避けられません。強風でパネルが飛散・破損したり、大雨による土砂崩れで設備が埋没する事例も報告されています。
環境省も「設置にあたっては災害リスクの高い場所をできる限り避ける」とガイドラインで注意喚起しており、発電所の立地選定時にはハザードマップの確認や十分な土台工事が欠かせません。災害による長期発電停止は収益に直結するため、保険加入や非常時の備えも含めたリスク対策が必要です。
制度変更で収益性が下がるリスクがある
再生可能エネルギーを取り巻く制度は見直しが繰り返されており、変更によって収益性が低下するリスクもあります。
例えば、2022年からは発電事業者にパネル廃棄費用の積立が義務化され、FIT売電収入の一部が10年目以降差し引かれる仕組みが導入されました。この積立金は最終的に返還されるものの、運転期間中の手取り収入は減少します。
また、出力抑制ルールの拡大や系統接続費用の見直しなど、行政の方針次第で収入計算が変わる可能性がある点にも留意しなければなりません。
FIT制度(固定価格買取制度)の見直しが収益に影響する可能性がある
固定価格買取制度(FIT)は導入から時間が経ち、制度見直しによる収益影響も考慮すべきです。FITの新規買取価格は年々引き下げられており、2024年度の事業用太陽光では1kWhあたり9円程度と初年度2012年の約4分の1水準まで低下しました。
さらに、近年は一定規模以上の案件が市場連動型のFIP制度や入札制へ移行しており、直近の入札では平均落札価格が8円台にとどまっています。将来的には太陽光発電を補助なしで自立させる目標も掲げられており、買取制度に過度に依存しない収支計画を立てることが重要です。
太陽光発電投資の失敗事例を具体的に紹介
想定より発電量が少ない
シミュレーション通りに発電量が得られないことは、太陽光発電投資の典型的な失敗例です。事前の発電シミュレーションでは高い収益予測が出ていても、実際の発電量が予想より大幅に少ないケースは珍しくありません。
原因としては、パネルの汚れや雑草による発電効率低下、機器の不具合、予測時に考慮しきれなかった天候不順などが挙げられます。例えば、定期清掃を怠った結果パネルにホコリが積もり発電量が落ちたり、周辺環境の変化で日陰が生じた場合など、計画との差異がそのまま収益の不足・回収遅れにつながるため注意が必要です。
メンテナンス費用が予想以上にかかる
投資当初の想定を上回る維持コストに悩まされるケースも少なくありません。太陽光発電所を安定的に稼働させるには定期的な点検や清掃が欠かせず、その費用を過小評価すると収益を圧迫します。実際の年間維持費は発電所の規模や契約内容によって差があり、数十万円から百万円以上に及ぶ場合もあります。
主な支出としては、除草作業やパネル清掃、パワーコンディショナの交換費用、保険料などが挙げられます。これらは初期の利回り計算で軽視されがちですが、長期的には必ず発生するランニングコストです。特にパワコンは10〜15年で交換時期を迎えることが多く、まとまった出費が必要になる点に注意が必要です。
こうした維持費を事前に見積もらずに投資を始めると、想定していた利回りを大幅に下回り「儲からない」と感じる結果につながりかねません。投資前にメンテナンス契約や将来の修繕費を織り込み、実質利回りをシビアに試算することが失敗回避の鍵となります。
立地選びを誤る
太陽光発電は立地選びの失敗が命取りになります。現地の十分な調査を怠り、日照条件や環境に難のある土地を選んでしまうケースが典型です。
確認すべきポイントとして、パネルに影を落とす恐れのある障害物がないか、海岸や河川から適度に離れて塩害や浸水リスクを避けられるか、地盤がしっかりしているか、近隣住民の反対がない地域か、といった点が挙げられます。例えば、安価な山間部の土地を購入したものの周囲の木々で日射が遮られ発電量が伸びない、排水不良の土地で豪雨時に水たまりができ設備に支障が出た、などの事例があります。
立地の見極めを誤ると収益悪化だけでなく設備トラブルにも直結するため、専門家とともに慎重に選定すべきです。
太陽光発電投資で失敗しないための対策
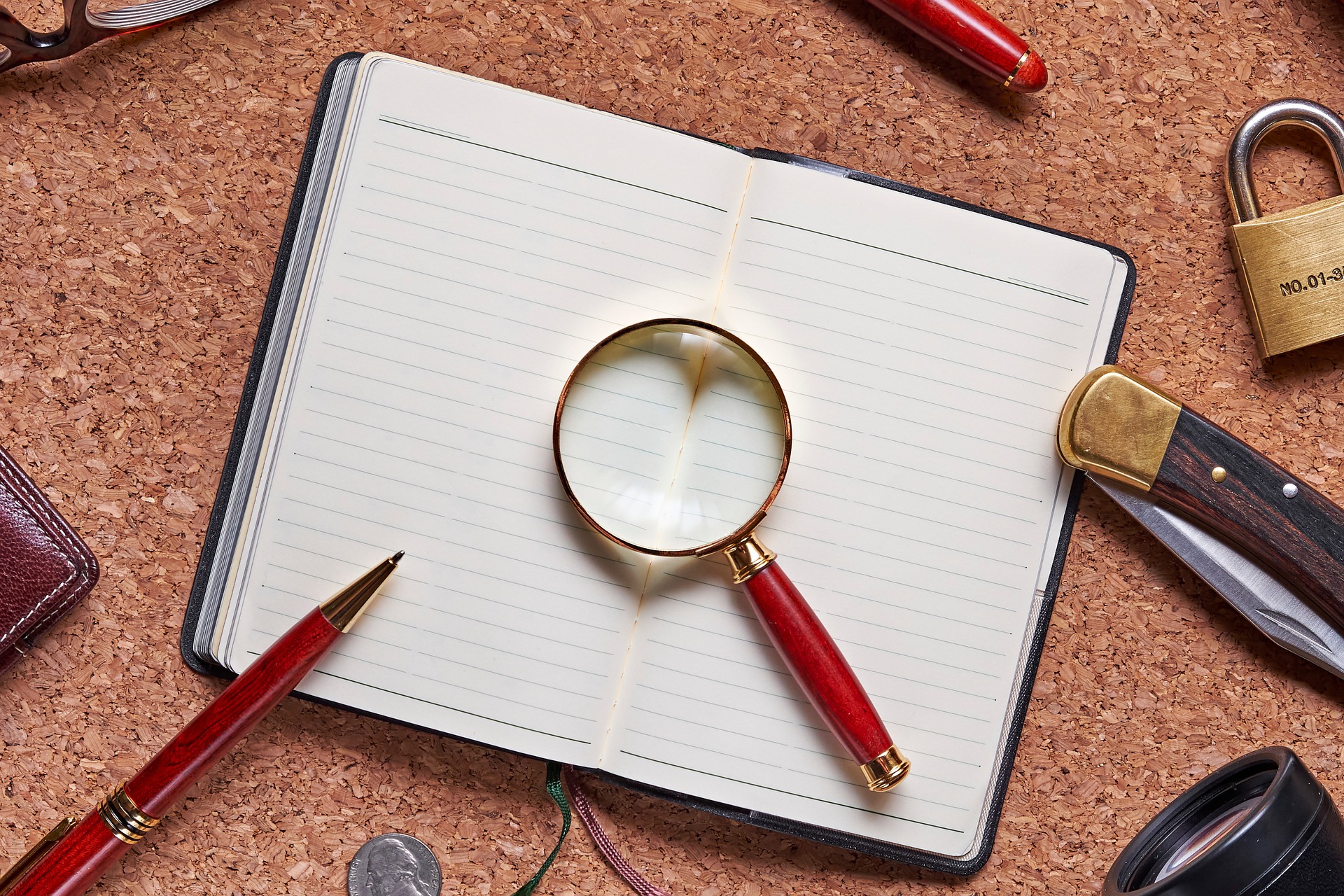
発電シミュレーションを複数条件で確認する
シミュレーションと現実の発電量乖離を防ぐには、事前に様々な条件で発電シミュレーションを行うことが有効です。
楽観シナリオだけでなく悲観シナリオも用意し、日照量が平年より少ない年やパネル劣化を考慮したケースでも採算が合うか検証しておきます。特に、過去の気象データを参考にした精度の高い予測を立てることが重要で、専門業者のシミュレーション結果も鵜呑みにせず複数社で比較検討しましょう。
オムロンの分析でも、日常点検不足やシミュレーション精度の低さが発電量予測外れの主因と指摘されており、シミュレーション段階でリスクを洗い出す工夫が失敗防止につながります。
維持管理や修繕コストを事前に計算する
太陽光発電投資を成功させるには、初期費用だけでなく維持管理や将来的な修繕コストも織り込んだ資金計画が欠かせません。
発電所運営には定期点検・清掃・除草などが伴い、事業者には適切な保守点検の実施と防草対策が求められています。契約前にメンテナンス委託費用やメーカー保証範囲を確認し、パワーコンディショナ交換など将来発生し得る大型出費も見積もっておきます。
一般に、年間の運転維持費は売電収入の一部を充てる計画とし、シミュレーション時に実質利回りへ反映させておくことが重要です。定期メンテ費用の積立や予備費確保によって、予想外の出費にも慌てず対応できる体制を整えましょう。
日照条件や周辺環境を十分に調査する
立地選定で失敗しないためには、現地の日照条件や周辺環境を徹底的に調査することが基本です。発電事業者自ら確認すべき事項として、パネルに影を落とす要因の有無、海や河川からの距離、地盤や土質の適性、近隣住民の反対の有無などが挙げられます。
事前に現地を訪れ、季節や時間帯ごとの日当たり具合、排水状況、工事車両の進入路の有無など細部まで確認しましょう。専門業者による土地造成の必要性(土砂流出防止策等)や電力会社との系統連系費用も含めて調査し、問題点があれば契約前に解決策を講じます。
十分な下調べにより、発電ポテンシャルの高い安全な土地を選ぶことが、長期安定運用への近道となります。
太陽光発電投資の利回りはどのくらい?目安と計算方法
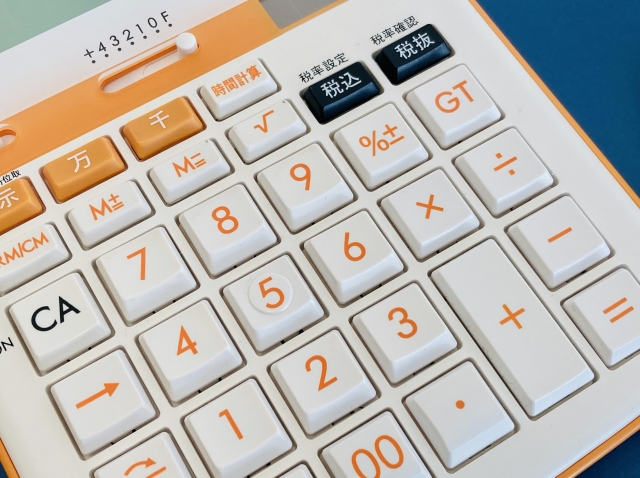
太陽光発電投資の利回りは平均5〜10%程度といわれている
太陽光発電投資の利回りは、物件規模や立地条件、導入コストなどによって変動しますが、一般的には表面利回りで5〜10%前後が目安とされています。維持費や借入金利を考慮した実質利回りでは4〜7%程度に落ち着くケースが多く、同じインカムゲイン型の不動産投資と比べても比較的高水準です。
ただし、利回りは年や案件によって差が出やすく、特に売電単価の低下や出力制御の影響を受けやすいため注意が必要です。かつては12%前後の高利回り案件も存在しましたが、現在は制度変更や市場環境の変化により、そうした案件はまれになっています。投資を検討する際には「平均値」だけに依存せず、設備費や維持管理費を含めた収支シミュレーションを行うことが不可欠です。
適切な条件を満たせば、銀行預金よりも高い収益率を期待できる可能性がある一方、想定を超えるコストや制度リスクを見落とすと利回りは大きく低下します。堅実な試算が成功の第一歩です。
利回りは初期費用や維持費によって大きく変動する
太陽光発電投資の利回りは、初期投資額やランニングコストによって大きく左右されます。一般に、同規模なら初期費用が安いほど利回りは高くなり、逆に設備価格が高いと利回りは低下します。
また、売電単価(FIT認定年度)によっても収益が変わるため、同じ容量でも開始時期によって利回りに差が出る場合があります。近年はFIT単価が下がる一方、設備費用も下がっているため、新旧案件間で利回り自体は大きく変わらないとの分析もあります。
さらに実質利回りを考える際には、毎年のメンテナンス費・保険料・借入金利などを差し引く必要があります。こうしたコスト管理次第で最終的な手取り利回りは大きく変動するため、投資前に様々な条件でシミュレーションすることが重要です。
利回りは「年間収益÷初期投資額」で計算できる
太陽光発電投資の利回りは基本的に年間の収益額を初期投資額で割って算出します。
具体的には、表面利回りは「年間売電収入÷初期投資費用×100(%)」という計算式になり、設備の総工費に対して毎年どれだけの収入があるかを示す指標です。
また、実質利回りは「(年間売電収入-年間経費)÷初期投資費用×100」で計算し、保険料やメンテナンス費など運用経費を差し引いた実際の収益率を表します。
例えば初期投資額1,000万円・年間売電収入120万円・年間経費20万円の場合、表面利回り12%、実質利回り10%となります。利回り計算では初期費用に含まれる項目(土地代・接続負担金など)にも注意が必要で、正確な利回り把握のためには経費込みの実質利回りを確認することが大切です。
太陽光発電投資と不動産投資を比較|どちらが向いている?

初期費用や利回りの違い
太陽光発電投資と不動産投資では、必要となる初期費用や期待利回りにそれぞれ特徴があります。太陽光発電は物件規模によりますが、土地付き50kW程度の発電所を一つ購入するのに数千万円前後の初期費用が必要となるケースが多く、一方、同程度の資金で不動産の場合は地方の区分マンション数戸や都心ワンルーム1戸程度が取得対象となります。
利回り面では、太陽光発電の方が平均利回りが高めです。ある試算によれば、太陽光発電所(50kW)の表面利回りは約8.9%、実質利回り6.8%であるのに対し、東京23区マンション経営では表面5.2%、実質3.9%程度との比較が示されています。また太陽光は空室リスクがなく維持費割合も低めである点から、同程度の初期投資なら太陽光の方がキャッシュフローが安定しやすい傾向があります。
リスク分散のしやすさの違い
投資ポートフォリオ全体で見たとき、太陽光発電と不動産ではリスク分散のしやすさにも違いがあります。
一般に、不動産投資は一物件あたりの金額が大きく個人で複数物件を持つハードルが高いため、どうしても特定物件への集中投資になりがちです。その点、太陽光発電は比較的小規模な区画単位での投資や、各地の案件に分散出資するスキーム(例:ソーシャルレンディングやファンド)もあり、少額から複数案件に資金を振り分けることが可能です。
実際、太陽光と不動産の両方に投資する富裕層も多く、両者は「土地を活用して長期インカムを得る」という収益構造が似通うため組み合わせやすいと言われます。近年は「不動産より太陽光の比率を増やす」動きも見られるほど、太陽光発電投資は安全性が高い一策として注目されています。
このように、双方の特性を理解して適切に組み合わせれば、リスク分散と収益安定化を図りやすいと言えるでしょう。
太陽光発電だけに頼らないための分散投資の考え方
分散投資でリスクを抑えることができる
投資では、一つの資産に集中せず複数に分散させることでリスクを抑えることが基本とされています。
太陽光発電投資も例外ではなく、他の資産と組み合わせることで特有のリスクを補い合う効果が期待できます。たとえば、太陽光発電の収益が天候や制度変更の影響で減少した場合でも、不動産や株式など他の資産が値上がりしていれば、全体の収益を安定させやすくなります。
具体的には、債券・株式・不動産・太陽光発電といった異なる値動きをする資産に資金を振り分けることで、ある分野が不調でも他の分野で補える可能性が高まります。こうしたポートフォリオ構築を行えば、短期的な変動に左右されにくく、資産全体として長期的な成長を目指すことができます。
太陽光発電投資も安定収入を生む選択肢の一つとして組み込み、他の金融商品とバランスを取ることで、より堅実な運用が可能となるでしょう。
不動産やクラウドファンディングとの組み合わせが有効
太陽光発電投資をより安定的に運用するには、他の投資商品と組み合わせて分散効果を高めることが重要です。
不動産投資は家賃収入や物件価値の上昇によるインフレ耐性が期待できる一方、景気変動や需要減少の影響を受けやすい特徴があります。太陽光発電は固定価格買取制度による安定収入が強みですが、天候や制度改正による収益変動リスクが伴います。両者を併用することで、一方の弱点をもう一方が補う効果が得られます。
さらに、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)を取り入れるのも有効です。少額から不動産担保ローンなどに分散投資でき、太陽光投資とは異なる信用リスク商品としてリスク分散の幅を広げられます。
このように、太陽光発電・不動産・クラウドファンディングを組み合わせることで、収益性と安定性のバランスを取りやすくなり、長期的に堅実な運用を目指すことができます。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】太陽光発電投資に関するよくある質問

太陽光発電投資の初期費用はいくらかかる?
太陽光発電投資の初期費用は規模によって大きく変わります。
小規模でも数百万円から数千万円が必要で、土地代や設備仕様で差が出ます。例えば出力50kWの土地付き案件では1,000万円を超えるケースもあります。
太陽光発電投資は本当に儲かるの?
条件次第で十分に利益を得ることは可能ですが、確実に儲かると断言できるものではありません。
平均利回りは表面ベースで7〜10%、実質利回りで5〜8%程度とされ、銀行預金より高い収益水準です。ただし天候不順や設備トラブルで収入が変動するため、リスク対策を講じて計画通りの発電量を維持することが成功のポイントです。
売電制度は今後どうなる?
売電を取り巻く制度は今後段階的に見直され、買取価格の低下や新たな制度移行が進む見通しです。
実際、FITの買取価格は年々引き下げられ、現在は事業用で9円台/kWhと初期より大幅に低く、今後は市場連動型のFIP制度への移行が拡大しています。FIT期間満了後は売電単価が7~9円/kWh程度に下がるケースも出ており、将来的には自家消費の併用や新たな売電契約など柔軟な対応が求められるでしょう。
太陽光発電投資はやめとけと言われるのはなぜ?
「やめとけ」と言われるのは、太陽光発電投資には注意すべきリスクが多いからです。
例えば発電量が天候に左右され収益が不安定になる可能性、年々売電単価が下がって利幅が小さくなっていること、さらにFITによる保証期間が20年と限られている点が挙げられます。地域によっては出力抑制で売電できないリスクもあるため、十分な知識と準備なしに始めると期待した利益を得られず後悔する恐れがあるのです。
まとめ|太陽光発電投資のメリットとリスクを正しく理解して判断しよう
太陽光発電投資は、平均利回りが7%前後と比較的高い安定収入が期待でき、環境貢献もできる魅力的な投資です。
一方で、初期費用の大きさや天候・制度変更に伴うリスクも抱えており、万能な「絶対儲かる」投資ではありません。メリットとデメリットをデータに基づき客観的に比較検討し、リスク許容度に応じた適切な投資判断を行いましょう。
実績数値を踏まえて冷静に評価することが、将来後悔しないためのポイントです。
参考元
・経済産業省 資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT制度) 概要」
・経済産業省「調達価格等算定委員会関連資料」
・環境省「太陽光発電設備の災害リスクと設置ガイドライン」
・国税庁「再生可能エネルギー発電設備に関する税制優遇」
・宮城県「みやぎ二酸化炭素排出削減支援事業補助金」
・日本政策金融公庫「環境・エネルギー対策資金」
・一般社団法人日本電気協会「太陽電池発電設備の維持管理・事故防止」
・経済産業省「再エネ設備の適正な導入・管理に向けた取組状況(災害リスクなど)」
・国土交通省「環境不動産の情報整備に関する調査報告」