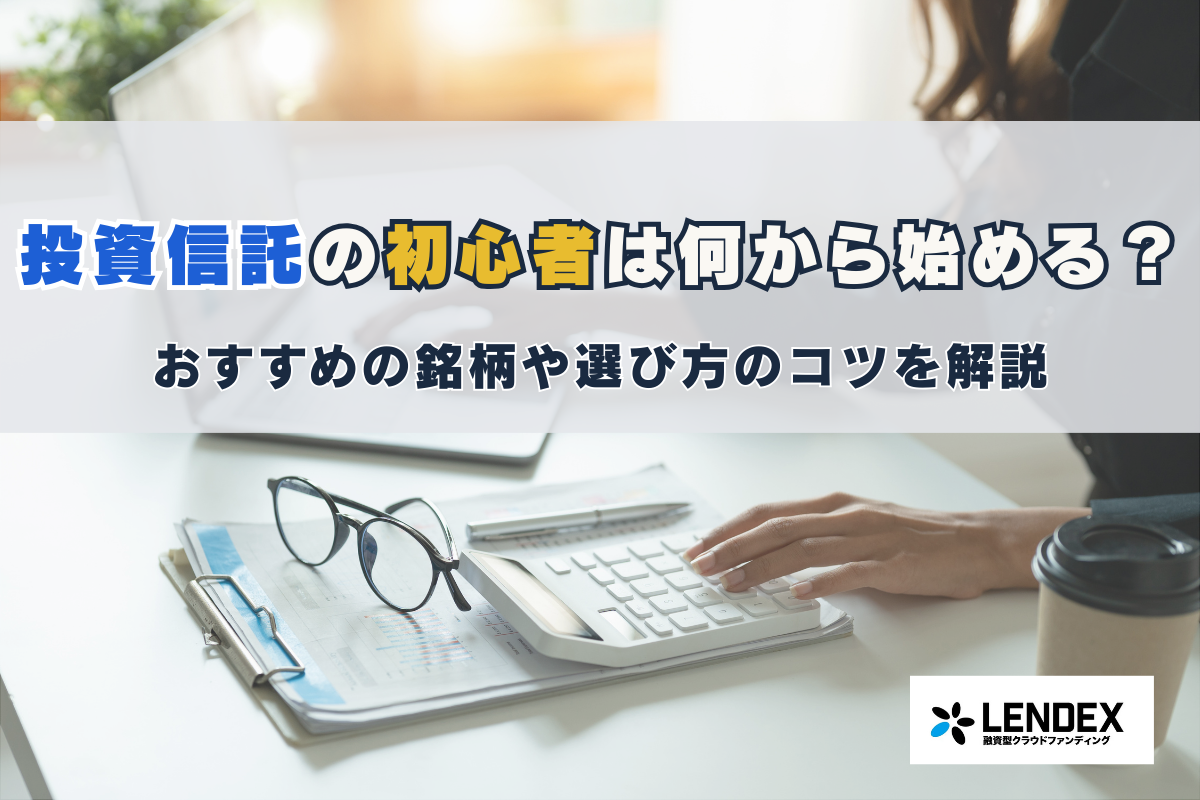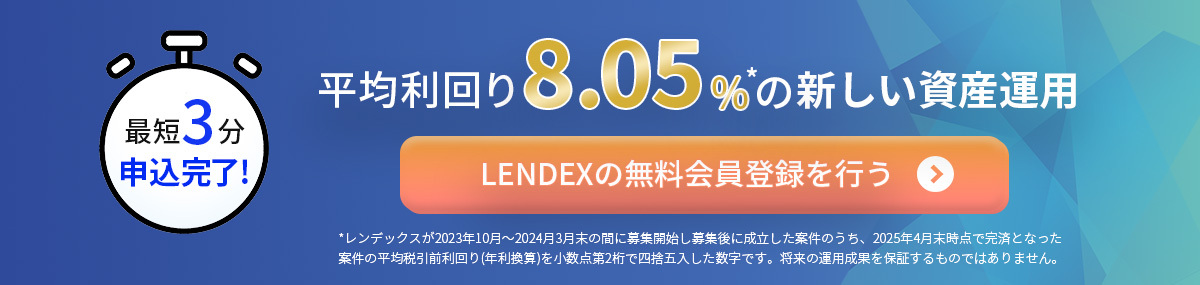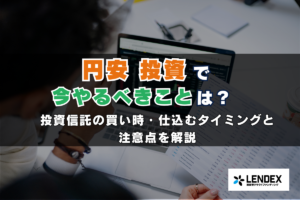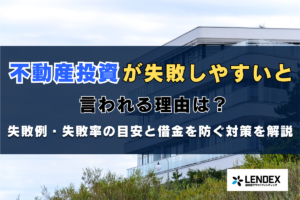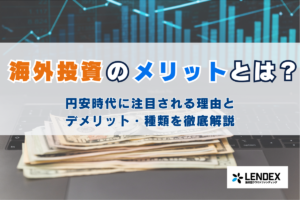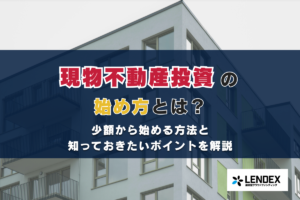最近、「投資を始めたいけれど何から手をつければよいのかわからない」という声を耳にすることが増えています。中でも投資信託は、日本人の多くが資産形成の第一歩として利用しており、少額から始められる点やプロに運用を任せられる点で初心者に選ばれる商品です。
しかし一方で、仕組みが複雑そうに見えたり、種類が多すぎて選び方に迷ったりする方も少なくありません。
本記事では、投資信託が初心者におすすめされる理由や基本的な仕組み、押さえておきたい種類の違い、さらに具体的な銘柄選びのコツまでをわかりやすく解説します。加えて、失敗しやすいケースや分散投資の考え方も紹介するので、読み進めながら自分に合った投資の始め方をイメージできるでしょう。
投資信託はなぜ初心者におすすめなのか

少額から始められてリスクを抑えやすい
投資信託は、少額から始められる点で初心者にとって取り組みやすい金融商品です。まとまった資金を用意する必要がなく、商品によっては1万円程度から購入できるほか、積立方式を選べば100円単位で運用できるケースもあります。
特にネット証券の一部では、100円から積立投資に対応しており、日常生活に無理のない範囲で投資を始められます。少額であれば、万一値下がりしても家計への影響は限定的で、リスクを抑えながら投資経験を積める点が安心材料になります。また、少額から積立を続ければ時間をかけて資産を増やす「ドルコスト平均法」の効果も得やすく、短期的な値動きに左右されにくいという利点もあります。
最初は小さく始めて投資に慣れ、徐々に投資額を増やす方法が、初心者にとって無理なく資産形成を進めるための有効なステップとなるでしょう。
専門家に運用を任せられる安心感がある
投資信託は運用のプロであるファンドマネージャーが資産配分や銘柄選定を行います。言わば「お任せ型」の商品であり、自分で個別銘柄を分析する必要がありません。専門家に運用を任せられるため、初めて資産運用を行う方でも安心して取り組みやすい金融商品と言えます。
ファンドマネージャーは市場動向や企業情報を日々専門的に分析しながら運用判断を下すため、初心者はその知見を活用できる分、有利な運用成果を期待しやすいでしょう。忙しい社会人でも運用の手間をプロに委ねることで無理なく投資を継続しやすいはずです。
このように運用を任せられる安心感は、初心者にとって大きな利点です。
株式や債券など幅広い資産に分散できる
投資信託は一つの商品で複数の資産に投資するため、自然と分散投資が実現できます。株式、債券、不動産投資信託(REIT)など幅広い資産にまたがって投資することで、一つの資産に集中するよりもリスクを低減させる効果が期待できます。
少額から様々な資産に投資できる点で、初心者でも効率よく分散投資が行えるでしょう。例えば国内株式だけでなく海外株式や債券にも投資すれば、一つの市場が不調でも他の資産の値上がりで損失を補いやすくなります。
分散投資によるリスク軽減効果は、初心者にとって大きなメリットの一つです。
投資信託の仕組みと基本をわかりやすく解説

投資家から集めた資金をプロが運用する仕組み
投資信託は、多くの投資家から集めたお金を一つにまとめ、運用の専門家(運用会社)が株式や債券などに投資・運用する金融商品です。投資信託で生じた運用成果(利益や損失)は、各投資家の出資額に応じて配分されます。
例えるなら、投資信託は多数の人のお金をプールして作る大きな投資の器であり、その器をプロが運用し、成果をみんなで分け合うイメージです。
個人では難しい大規模で専門的な運用をプロに任せ、みんなで成果を享受できる仕組みになっています。なお、資産は信託銀行で分別管理されており、仮に販売会社が破綻しても資産が守られる仕組みです。
株式・債券・不動産などさまざまな資産に投資できる
投資信託は投資対象が幅広く、国内外の株式・債券はもちろん、不動産やコモディティに投資するファンドも存在します。例えば、オフィスビルや商業施設などに投資する不動産投資信託(REIT)や、金・原油価格に連動するコモディティファンドもあり、一つの投資信託で複数の資産クラスにアクセスできます。
投資信託ごとに投資対象の範囲は定められており、国内株式だけに投資するものもあれば、外国債券だけに投資するもの、株式と債券を組み合わせたバランス型のものなど多彩です。多様な資産に分散投資できる点は、投資信託の大きな基本特徴です。
選択肢が非常に幅広いため、自分の関心や目標に合わせたファンドを見つけられるのも投資信託の魅力でしょう。
運用益から手数料が差し引かれる点に注意が必要
投資信託には運用管理のコストがかかるため、得られた運用益から手数料が差し引かれることに注意しましょう。
具体的には、投資信託ごとに信託報酬(運用管理費用)が年率で設定されており、ファンドの資産から毎日按分して控除されます。例えば信託報酬が年1.8%のファンドに100万円投資した場合、何もしなくても年間で約1万8千円が費用として差し引かれる計算になり、その分だけリターンが目減りします。
もちろん運用が上振れすれば手数料分を差し引いてもしっかり利益を得られますが、こうしたコストの存在は念頭に置いておく必要があります。
初心者が知っておきたい投資信託の種類
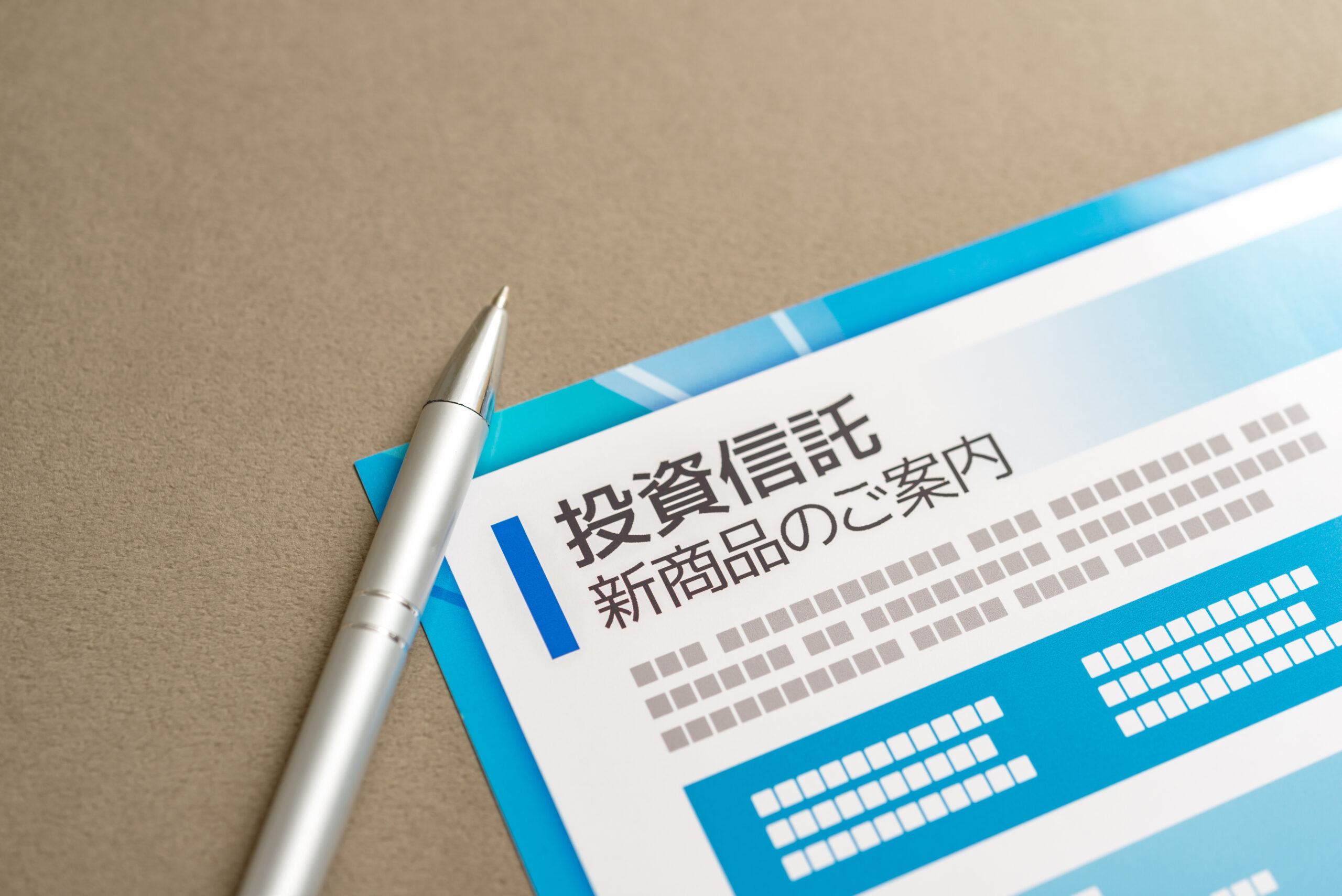
株式型・債券型・バランス型の特徴を理解する
投資信託には運用する資産の種類によりいくつかのカテゴリーがあります。
株式型投資信託は主に株式を組み入れて運用するもので、値動きが大きい分ハイリスク・ハイリターンの性格があります。債券型投資信託は国債や社債など債券を中心に運用し、安定した利息収入が期待できる一方でリターンも比較的穏やかです。
バランス型投資信託は国内外の株式・債券など複数の資産を組み合わせて運用するファンドで、1本で分散投資ができる点が特徴です。バランス型は株式型よりリスクが抑えられ、債券型よりリターンが見込める中庸的な存在と言えるでしょう。例えば、国内株・国内債・外国株・外国債に25%ずつ投資する4資産均等型など、一つのファンドで世界中に分散投資できる商品もあります。
インデックス型とアクティブ型の違いを知る
インデックス型(パッシブ運用)の投資信託は、日経平均株価やTOPIXなどの市場指数に連動する運用成果を目指すファンドです。市場全体の動きと連動するように設計されており、ファンドマネージャーが積極的に売買判断を行わない分、信託報酬が低めに設定される傾向があります。
一方、アクティブ型の投資信託は、市場平均を上回る成果を目指してファンドマネージャーが銘柄選定や売買タイミングを工夫する運用スタイルです。その分コストが高くなる傾向がありますが、市場平均以上のリターンを狙える可能性があります。
インデックス型かアクティブ型かは、目指す運用成果や手数料水準の違いを理解した上で選びましょう。
国内型と海外型の投資信託の違いを押さえる
国内型の投資信託は主に日本国内の資産に投資するファンドであり、海外型は外国の株式や債券など海外資産に投資するファンドです。
最大の違いは為替リスクの有無です。海外の資産に投資する投資信託では、為替レートの変動によって基準価額が影響を受けます。一般に円高になれば海外資産の評価額が目減りし、円安になれば評価額が増えるため、海外型には為替変動リスクが伴います。
一方、国内型には為替リスクはありませんが、投資対象が日本市場に限定されるため、日本経済の動向に運用成績が左右されます。それぞれの特徴を理解し、自分の投資目的に合った地域のファンドを選択することが大切です。
初心者におすすめの投資信託銘柄と選び方のコツ
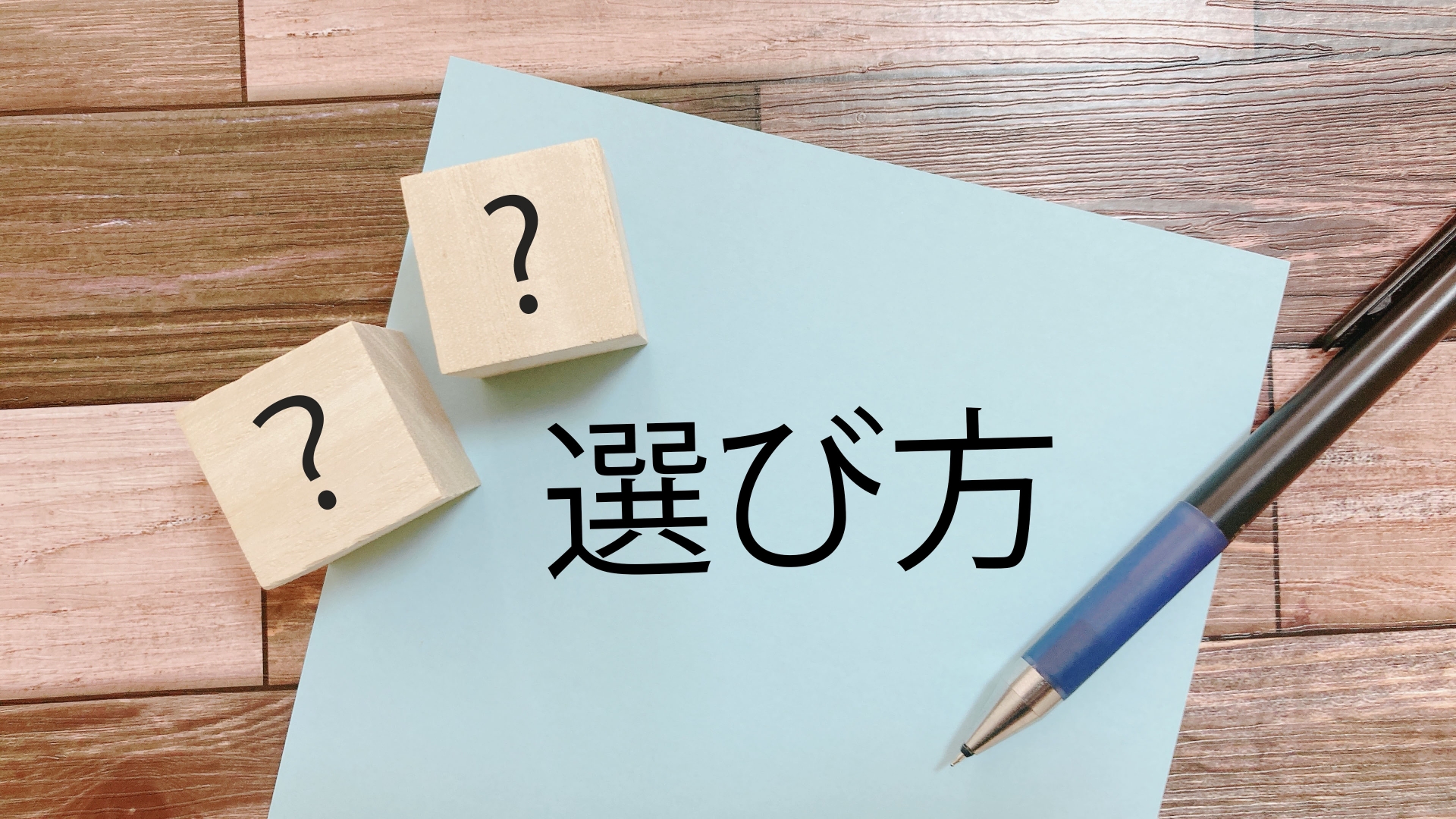
手数料が低いインデックス型を中心に選ぶ
初心者が投資信託を選ぶ際は、信託報酬などコストの低いファンドを中心に検討するのがおすすめです。とりわけ市場指数に連動するインデックス型の投資信託は、総じて運用コストが低く設定されています。
金融庁が定める「つみたてNISA」の対象商品でも販売手数料が0円(ノーロード)で信託報酬が低水準の商品が条件とされており、長期の資産形成には手数料の安いインデックスファンドが適していることが示唆されています。
例えば市場平均に連動する代表的なインデックスファンドでは、信託報酬が年0.1%台という超低コストの商品も存在します。手数料負けしにくいこれらのファンドは長期投資の強い味方となるでしょう。
長期投資に向いた安定性のある銘柄を選ぶ
長期的な資産形成を目指すなら、値動きが安定しているファンドを選ぶこともポイントです。一般的に、投資対象が幅広く分散され規模の大きいファンドほど極端な値動きになりにくく、長期保有と相性が良い傾向があります。
実際、金融庁は長期・積立・分散投資に適した安定的な資産形成を目指す商品として、分配金の頻度が少なく着実に資産が積み上がるタイプの投資信託を推奨しています。例えば投資対象が世界全体に分散されたファンドであれば、一国の景気に左右されにくく、より安定した長期成長が期待できます。
安定性重視のファンドであれば、安心して長期運用を続けられるでしょう。長期投資においては、値動きのブレが小さく信頼性の高いファンドを選ぶことが大切です。
投資目的やリスク許容度に合わせて選ぶ
投資信託選びでもっとも大切なのは、自分の投資目的やリスク許容度に合った商品を選ぶことです。
まず「何のために」「どれくらいの期間」運用する資金かを明確にし、その目的に照らしてふさわしいファンドのタイプを絞り込みます。例えば、数年後に使う予定の資金であれば値動きの小さい債券型や安定重視のバランス型を、10年以上の長期運用なら株式型インデックスファンドで成長を狙うなどの選択肢が考えられます。
自身のリスク許容度(どの程度の損失に耐えられるか)も把握しておきましょう。無理なく継続できる範囲でリスクを取れる商品を選ぶことで、精神的にも安定して投資を続けられます。
投資信託の始め方と購入の流れ
証券口座を開設するところからスタート
投資信託を始めるには、まず証券会社や銀行などの金融機関に証券取引口座を開設する必要があります。口座開設時には、本人確認書類やマイナンバーの確認書類(マイナンバーカード等)の提出が法律で義務付けられているため準備しましょう。
最近ではオンラインで口座開設が可能な証券会社がほとんどで、スマホから必要書類をアップロードするだけで完了します。口座開設の審査には通常数日〜1週間程度かかります。口座が無事開設できたら、そこに運用資金を入金して投資の準備完了です。
一般的にネット証券の方が取扱ファンドが豊富で手数料も低い傾向があるため、初心者にはネット証券での口座開設がおすすめです。迷った場合はネット証券を選ぶと良いでしょう。
投資額と積立方法を決める
次に、どのくらいの金額を投資するかと、購入方法(スポット購入か積立購入か)を決めます。
初心者には、一度に全額を投資するよりも毎月コツコツ積み立てる方法が安心でしょう。同じ金額で定期的に買い付ける積立投資なら、例えば毎月100円や1,000円といった無理のない少額から購入でき、購入時期を分散することで価格変動リスクを抑える効果が期待できます。
実際、積立投資を行えば時間の分散が図れ、購入タイミングに悩まず長期的な資産形成が可能になるとされています。なお、積立額や頻度は途中で変更することもできます。自分の収支状況に合わせ、無理のない積立額を設定しましょう。
投資信託を購入して運用を始める
購入額と方法が決まったら、いよいよ投資信託を購入します。まず購入したいファンドを選び、その交付目論見書(投資信託説明書)を受け取って内容を確認します。内容に同意したら証券会社を通じて購入の申込みを行います。
ネット証券の場合、事前に証券口座に入金した範囲内で注文を出す形となるため、必要資金をあらかじめ口座に用意しておきましょう。購入注文が成立すると、後日「取引報告書」が送付されます。取引報告書には購入した投資信託の名称や取引数量、手数料などが記載されていますので大切に保管してください。
これで購入手続きは完了です。あとはファンドが運用されていくのを長期目線で見守りつつ、必要に応じて追加購入やリバランス(資産配分の調整)を行っていきましょう。
初心者が陥りやすい投資信託の失敗事例

人気やランキングだけで選んでしまうケース
初心者にありがちな失敗の一つが、「人気があるから」「ネットのランキング上位だから」という理由だけで投資信託を選んでしまうことです。
確かに直近で好成績のファンドや話題のファンドは魅力的に映りますが、人気=自分に適した良い商品とは限りません。ランキング上位のファンドは直近で基準価額が大きく上昇しているケースも多く、そのタイミングで飛び乗ると高値掴みになってしまうリスクがあります。
また、販売会社のキャンペーンで一時的に売れているだけの商品もあり得ます。本来は自分の投資目的やリスク許容度に合致した商品かを見極めることが重要ですが、人気だけで選ぶとその検証を怠ってしまいがちです。投資信託選びでは、他人の評価よりも自分の判断基準を大切にしましょう。
短期的な値動きに振り回されるケース
投資信託は長期運用に向いた商品ですが、初心者ほど日々の基準価額の変動が気になってしまい、短期的な値動きに振り回される傾向があります。市場が下落するとすぐに不安になって売却してしまったり、逆に上昇局面で焦って高値で買い増してしまったりすると、結局タイミングを誤って損をすることが少なくありません。
短期売買を繰り返すと、その度に売買手数料や税金もかかり、長期投資のメリットが失われてしまいます。むしろ、短期的に思い通りにいかない場合でも長期的な視点で投資を持続できる余裕を持つことが大切です。
基準価額が一時的に下落しても慌てず、冷静に状況を判断する心の余裕を持つようにしましょう。
手数料の高さに気づかず損をするケース
投資信託には様々な手数料が存在しますが、それを把握せずに購入してしまい、結果として思ったほど利益が出ないという失敗も見られます。
例えば購入時に3%の販売手数料がかかり、さらに年間1.5~2%程度の信託報酬がかかるファンドでは、実質的なコスト負担が非常に大きくなります。購入時手数料3.3%・信託報酬年1.8%のファンドに100万円を投資した場合、初年度は5%以上の利益を上げてようやく元本維持となる計算です。
コストに見合うリターンが出せなければ投資成果はマイナスになりかねません。初心者のうちは手数料が目立ちにくいですが、長期では確実にパフォーマンスに差が出ます。目論見書や運用報告書をきちんと確認し、手数料水準にも注意を払いましょう。
リスクと失敗を避けるための分散投資という考え方
株式や債券、不動産などに投資先を分ける
一つの資産に集中投資すると、その資産が値下がりした際に資産全体が大きく目減りしてしまいます。これを避けるために重要なのが分散投資の考え方です。
株式、債券、不動産、現金といった値動きの異なる資産に投資先を分散させることで、ある資産クラスの損失を他の資産の値上がりで補い、ポートフォリオ全体のリスクを軽減できます。実際、株式100%で運用するよりも、一部を債券や現金で持っていた方が下落局面でのダメージを抑えられることが経験的にも知られています。
初心者の方も、投資信託を活用して複数資産に分散投資することで、安定した資産運用につなげることができるでしょう。
不動産やクラウドファンディングを取り入れて投資対象を広げる
投資対象を株式や債券だけに限定せず、不動産やクラウドファンディングを組み合わせることで、分散効果を高めやすくなります。これらは株式や債券と値動きの要因が異なる場合が多いため、資産全体のリスクを抑える可能性があります。
具体例としては、不動産を対象とする投資信託や不動産ローンへの出資、事業者向けの融資型クラウドファンディングが挙げられます。これらは株式市場と同じ動きをするとは限らず、景気や金利、不動産価格など異なる要因に影響を受けます。そのため、資産全体の安定性を補う効果が期待できる一方で、不動産価格の下落や事業者の信用リスクといったリスクも存在します。
こうした投資を取り入れる場合は、少額から始め、他の資産とのバランスを意識することが大切です。株式や債券に加えて不動産やクラウドファンディングも活用すれば、より幅広い分散が可能になり、安定した資産形成につなげやすくなるでしょう。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】投資信託初心者が抱えるよくある質問

投資信託はいくらから始められる?
投資信託は数百円~数千円程度の比較的少額から始められます。
例えば積立投資なら100円程度から購入できる商品もあり、ほとんどの投資信託は1万円前後の資金があれば始めることが可能です。まずは無理のない金額で小さくスタートしてみましょう。
投資信託は元本割れすることはある?
元本割れの可能性はあります。
投資信託は預貯金と違い、株式や債券など価格変動する資産に投資しているため、市場が下落すれば基準価額が購入時より下回ることもあり得ます。預けた元本が保証される商品ではない点に注意が必要です。
投資信託と株式投資はどちらが初心者に向いている?
一般的には投資信託の方が初心者に向いていると言えます。
投資信託は少額からプロに任せて複数資産に分散投資できるため、初心者でも始めやすいメリットがあります。一方、株式投資は個別銘柄の研究や大きな値動きリスクへの対応が求められるため、経験の浅い人にはハードルが高い傾向です。
まとめ|投資信託初心者が成功するためのポイント
投資信託は、少額からの分散投資と専門家による運用を活用できるため、初心者でも取り組みやすい資産形成の手段です。実際、金融庁も「長期・積立・分散」を基本とした資産形成を推奨しており、銀行預金のような低金利環境では投資信託を活用した方が効率的に資産を増やせる可能性があるとされています。ただし、運用成果は市場環境や投資先の種類によって変動し、必ずしも安定的に成長するわけではありません。
成功のカギは、手数料の低いファンドを選び、焦らずに「長期・積立・分散」を徹底することです。これを実践すれば、市場の一時的な値動きに左右されず、時間を味方につけて堅実に資産形成を進められるでしょう。
参考元
・金融庁「資産形成のための投資信託ガイド」
・金融経済教育推進会議(J-FLEC)「分散投資の意義/投資信託の仕組みと特徴」
・投資信託協会「投資信託ガイド」
・日本証券業協会「今さら聞けない!投資Q&A」
・全国銀行協会「ここにご注意!投資信託」
・金融庁「投資を行っている方へ」