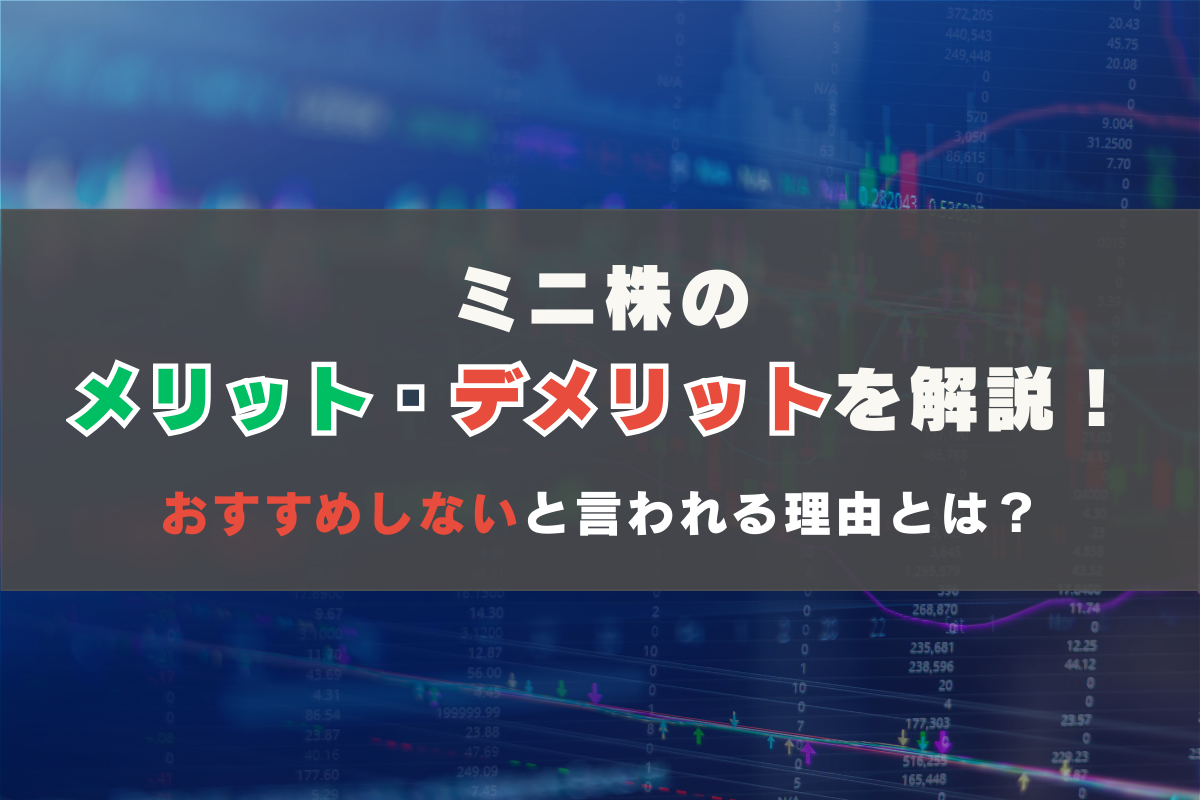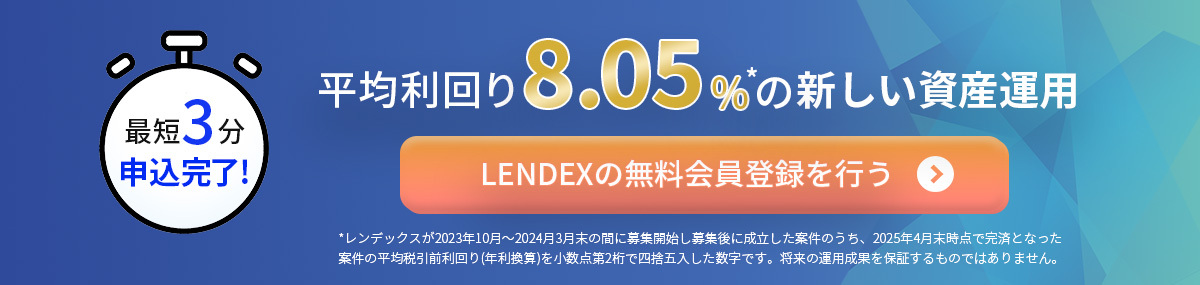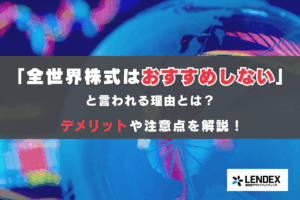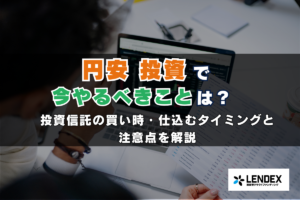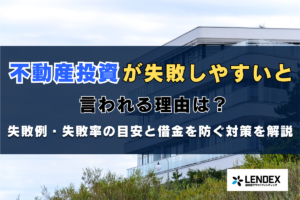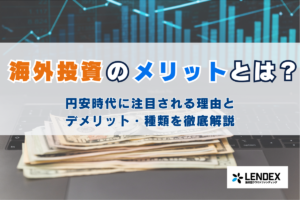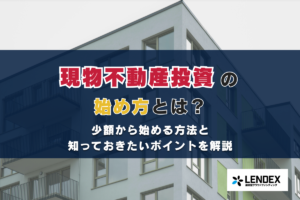ミニ株(単元未満株)は、通常100株単位で購入する株式を1株から買えるサービスです。少額で気軽に始められる反面、デメリットも多く、経験者からは「おすすめしない」という声もあります。
この記事ではミニ株投資のメリット・デメリットを詳しく解説し、なぜおすすめしないと言われるのか、その理由に迫ります。
併せて、ミニ株投資の失敗事例やリスクへの対策、少額から始められる別の投資手段も紹介します。ミニ株が自分に合った投資かどうか、判断する材料にしてください。
ミニ株はなぜおすすめしないと言われるのか?理由を詳しく解説

株数が限られて投資の自由度が下がってしまう
ミニ株は対応する証券会社や取扱銘柄が限られており、自由に投資先を選びにくい側面があります。すべての証券会社でミニ株を扱っているわけではなく、事前に「買いたい銘柄がミニ株で購入可能か」を確認しなければなりません。
また、多くのサービスでは1株単位でしか取引できず、リアルタイムの自由な売買もできません。そのため、まとまった資金で一度に多くの株数を買いたい場合や、素早くポートフォリオを組み替えたい場合に制約となります。
投資できる銘柄・株数が限られることで、通常の株式投資に比べて投資戦略の自由度が下がる点は押さえておきましょう。
手数料が割高になりリターンを削ってしまう
ミニ株最大のデメリットは手数料負担の重さです。
多くのネット証券ではミニ株取引に約定代金の0.5%前後(税込0.55%)という手数料が設定されており、通常の株取引より割高になりがちです。特に少額取引では手数料率が高く、利益を圧迫します。
例えば株価1,000円の銘柄を10株購入すると、約定代金は1万円で手数料は55円となります。これを10回に分けて1株ずつ買った場合も、都度55円の手数料がかかるため合計550円に膨らみ、まとめ買いの10倍のコストになってしまいます。
このように少額を分割して買い続けると、知らないうちに手数料負けして利益が出にくくなる可能性が高まります。
売却のタイミングを逃してしまうことがある
ミニ株はリアルタイム取引ができないケースがほとんどで、注文や約定のタイミングに制限があります。
多くの証券会社では成行注文のみで指値注文ができず、約定は1日数回の決まった時間に行われます。そのため、急な株価変動にリアルタイムで対応できず、狙ったタイミングで売買できないリスクがあるのです。
例えば、急落局面で早めに売り抜けたいと思っても、注文が執行されるのが取引終了後になるため損失が拡大するおそれがあります。また、取引量が証券会社内で調整される仕組み上、流動性が低くすぐ換金できない場合も考えられます。
このように、ミニ株は売買タイミングの融通が利かず、マーケットの動きに合わせた迅速な戦略が取りにくい点に注意が必要です。
ミニ株投資のメリット

少額から株式投資を始められる
ミニ株最大の魅力は、ごく少額から株式投資が始められることです。
通常、日本株は100株単位での取引が必要なため、株価が高い銘柄だと数十万円~数百万円の資金が必要になります。しかしミニ株なら1株単位で購入できるので、数千円~数万円程度から投資が可能です。
例えば1株1万円の株式も、ミニ株なら1万円で1株買えるため、100万円用意しなくても株主になれます。まとまった資金がなくても株式市場に参加できるため、「とりあえず少額で試してみたい」という初心者にとってハードルがぐっと下がります。
また、投入金額が小さい分、万一損失が出てもダメージが限定的で済む点も安心材料です。このようにミニ株は、少ない資金で株式投資を体験できる貴重な方法と言えるでしょう。
高額株でも一部だけ購入できる
ミニ株なら、株価の高い人気銘柄にも少額で手が届くというメリットがあります。
通常は手が出ない値嵩株(株価の高い株)でも、ミニ株なら1株から購入可能です。例えば任天堂やキーエンスのように1株あたり数万円~数十万円する銘柄でも、数千円~数万円あれば1株ずつ保有できます。憧れの有名企業の株を「少しずつ積み立てる」ことができるのは大きな魅力です。
実際、ミニ株を利用すれば「100株単位では資金的に難しい銘柄」にも投資対象を広げられます。
このように、高額な銘柄を一部分だけでも保有できる点で、ミニ株は投資の選択肢を増やしてくれます。少額ずつでも自分の好きな企業に投資できる喜びを味わえるのも、ミニ株のメリットと言えるでしょう。
投資経験を積む練習として活用できる
ミニ株は、投資の勉強・練習台として最適です。初心者がいきなり数十万円を投じるのは心理的ハードルが高いですが、ミニ株なら数千円から市場の値動きや株式投資の仕組みを体験できます。
実際にお金を動かしてみることで、机上の勉強以上に多くの学びを得られるでしょう。例えば、小額でも株を保有すれば日々の株価変動に関心が向き、企業のニュースや決算にも自然と目を通すようになります。
こうした体験は、今後本格的に投資をする上で大いに役立つはずです。「まずはミニ株で市場に慣れてみる」というのは合理的なステップであり、初心者が投資経験を積む手段としてミニ株を活用する価値は十分にあります。ただし、リスクが小さい分、損失への緊張感が薄れがちな点には注意し、実践を通じてリスク管理の意識も身につけましょう。
ミニ株投資のデメリット
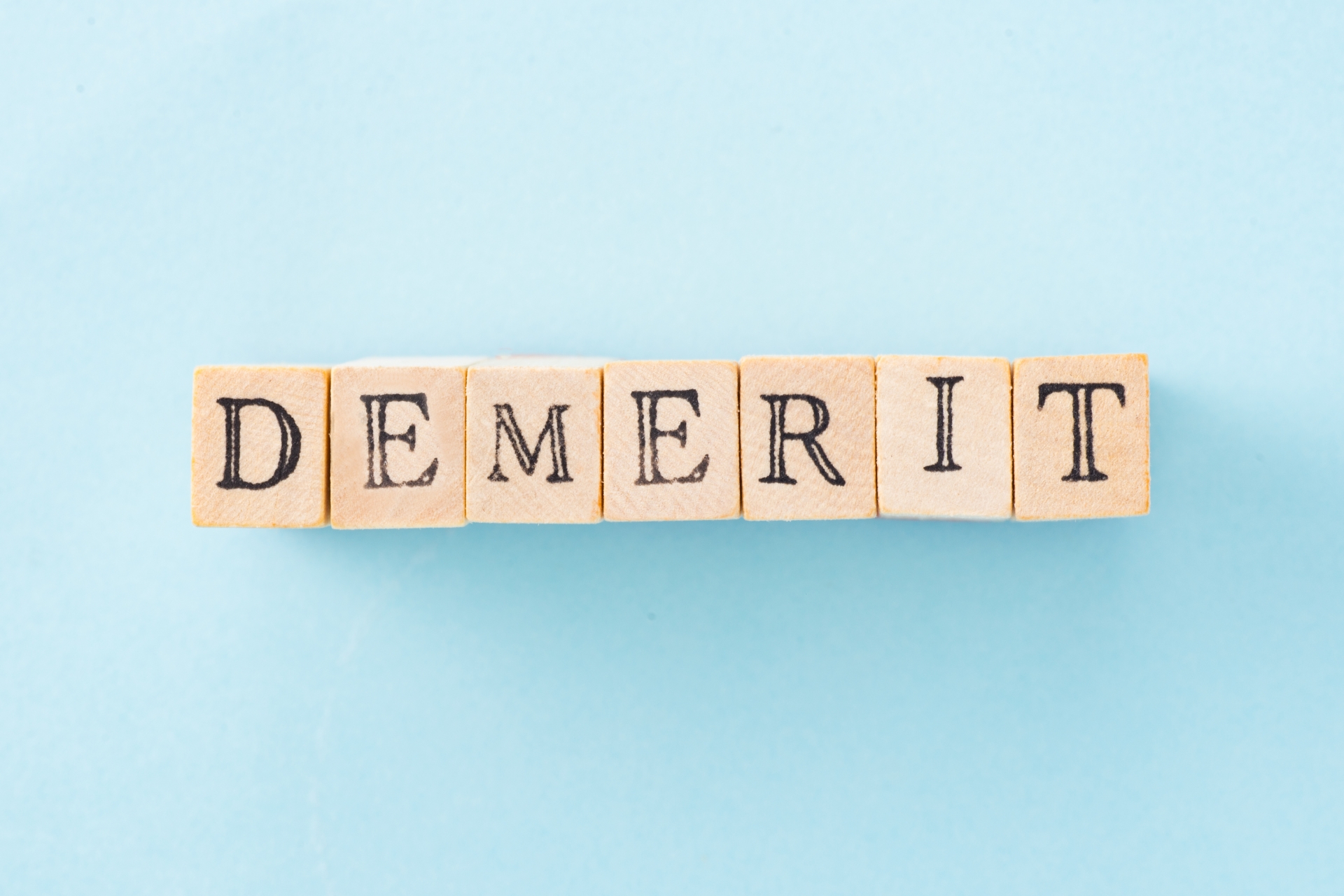
手数料率が高く利益が出にくい
ミニ株は少額で始められる半面、利益を出しにくい構造になりがちです。投資額が小さいため株価上昇による利益もわずかで、その上前述のように手数料率が高いため、せっかくの利益が手数料で相殺されてしまいます。
例えば1株5,000円の株が株価2倍になっても利益は5,000円程度ですが、100株持っていれば50万円の利益になります。つまり小口投資では株価が大きく上がってもリターンはごく小さく、大きな利益を上げるのは難しいのです。
さらに、ミニ株の売買に毎回かかる0.5%前後の手数料が利益を圧縮します。実質「儲からないのにコストだけ割高」という不利な構造になりやすく、短期で大きく儲けることは期待しにくいでしょう。
ミニ株投資ではコツコツ型の小さな利益しか狙えず、効率的に資産を増やすのは難しい点を理解しておく必要があります。
株主優待をもらえない場合がある
多くの日本企業は株主優待や議決権の権利を「1単元(通常100株)以上の保有」が条件としています。ミニ株で1株や数株だけ持っていても、基本的に株主優待は受け取れません。
例えば、100株保有で自社商品の優待がもらえる企業でも、1株や10株では対象外となります。議決権(株主総会での投票権)も同様で、単元未満株主には与えられません。一部例外的に、保有株数に応じて優待を提供している企業もありますがごく稀です。
つまりミニ株投資では基本的に優待の恩恵は享受できないと考えたほうがよいでしょう。優待目当てで銘柄を買ってしまうと「思っていた特典が何も得られなかった」という失敗につながります。
配当金については、保有株数に応じて比例配分されるためミニ株でも受け取れるケースが多いですが、優待はまず期待できない点を理解しておくことが大切です。
投資戦略を柔軟に立てにくい
ミニ株は様々な制約があるため、投資戦略の柔軟性に欠ける側面があります。
まず、前述の通り成行注文のみで指値ができず、リアルタイム売買も不可なので、短期的な値動きに合わせた売買戦略を取りづらいです。デイトレードや素早い損切り・利確が難しく、短期売買には不向きと言えます。また、ミニ株では信用取引(レバレッジをかけた取引)や空売りといった高度な取引手法も利用できません。
さらに、取引できる銘柄数が証券会社ごとに限られているため、投資対象の選択肢も狭まります。加えて、少額で複数銘柄に分散投資しようとするとそれぞれに手数料がかかり、かえって非効率になる場合もあります。
このように、ミニ株は制約の多さゆえに投資計画を思い通りに実行しにくいのです。特に「タイミング重視の売買」や「優待狙い」「高リスク高リターン狙い」の戦略は立てづらく、機動的・柔軟な投資を求める方には不向きでしょう。
ミニ株投資でよくある失敗事例
短期売買を繰り返して手数料ばかりかさんでしまった
ミニ株でデイトレードのような短期売買を頻繁に行った結果、手数料ばかりが嵩んで利益が出なかったという失敗です。
例えば、1日に何度も小さな値幅を狙って売買を繰り返すと、取引の度に数十円〜数百円の手数料が発生します。利益自体が少ないミニ株では、その手数料負担が重くのしかかり、トータルでは手数料負けしてしまうのです。
「何度も取引すればコツコツ儲かるはず」と考えていた初心者が、蓋を開けてみれば利益より手数料支払いの方が多かったというのはよくある話です。短期で利ザヤを稼ごうとすると、ミニ株の割高な売買コストが壁となり、思うように利益が積み上がらないのです。
この失敗から学べるのは、ミニ株では売買回数を減らし長期スタンスに切り替えるか、手数料の安いサービスを選ぶ必要があるということです。
株主優待がもらえると思い込んで投資してしまった
好きな企業の優待欲しさにミニ株でその銘柄を買ったものの、株主優待がもらえず失望したという失敗です。
例えば、ある飲食チェーンの食事券が欲しくてその株を1株だけ買った初心者が、後になって「優待は100株以上保有が条件」と知り戸惑ったケースです。ミニ株では単元未満株主には優待が付与されないのが原則であり、1株や10株ではどんなに長期間持っていても優待は受け取れません。
「少しでも株主になれば特典がもらえるだろう」と安易に考えた結果、期待外れに終わってしまうわけです。特に優待目当てでミニ株投資を始めるのは危険で、最初に制度を理解しておかないとこのような誤解から来る失敗を招きます。
教訓として、投資前に必ず企業の優待条件を確認することが重要です。また、どうしても優待が欲しい場合は100株単位で買うか、優待が手軽にもらえる他の方法(優待ポイントサービスなど)を検討する方が良いでしょう。
人気株に集中投資して値下がりに巻き込まれてしまった
ミニ株で買えるからと人気銘柄に資金を集中させたところ、株価下落により大きな損失を被ったという失敗です。
少額とはいえ、1銘柄に全額を投じてしまうと、その株が下がった時にポートフォリオ全体が直撃を受けます。例えば「将来有望」と話題のハイテク株1銘柄だけを5万円分買った初心者が、その株の業績悪化で株価が半減し、資産が2万5千円にまで減ってしまった…というようなケースです。
分散投資を怠り、人気株1本に集中すると、このようにハイリスク・ハイリターンの状態になります。運良く上昇すれば良いですが、下落すれば資金が大きく目減りする危険は常にあります。
ミニ株は少額ゆえ「全部失っても痛くない」と思いがちですが、だからといって1銘柄集中は望ましくありません。結果的に少ない資金でも丸ごと失うリスクを負うことになります。この失敗は、少額投資でも基本は分散が大事だという投資の鉄則を教えてくれます。
ミニ株を利用するときのリスクと対策

長期保有を前提にコストを抑える工夫をする
ミニ株を始めるなら、長期保有を前提にして売買回数を減らし、手数料コストを抑えることが重要です。短期売買を繰り返すとその度に手数料がかかり利益を圧迫するため、基本は中長期スタンスで構える方が有利です。買ったらすぐ売るのではなく、じっくりホールドして値上がりや配当を待つことで、手数料負担を最小限にできます。
また、証券会社選びも対策の一つです。最近ではミニ株売買手数料を無料にしている証券会社も登場しています。口座開設前に各社の手数料体系を比較し、できるだけコストの低いサービスを選びましょう。
さらに、NISA口座でミニ株を扱える場合はそれを活用するのも手です(※対応状況は証券会社による)。非課税で運用すれば税負担を軽減でき、手数料高をカバーしやすくなります。
総じて、ミニ株は「頻繁に売買しない」「安い手数料環境を選ぶ」ことでコスト面のデメリットを抑え、リターンを確保しやすくできます。
株主優待や配当の条件を事前に確認しておく
ミニ株で投資する前に、配当や株主優待の条件を必ず確認しましょう。優待狙いの場合、その企業の株主優待が何株以上で適用されるかを事前にチェックし、ミニ株ではもらえない場合は無理に買わないことです。
多くの企業は優待に100株以上保有を要求しますから、ミニ株では基本優待は得られません。「ミニ株でも優待がもらえる特例企業なのか?」を確認するのは必須です(該当企業は少数ですが存在します)。
また配当金についても、銘柄によっては単元未満株主には支払われないケースがないとは言い切れません※。一般には1株からでも配当は比例して受け取れますが、念のため証券会社の説明や企業のIR情報で確認すると安心です。
配当を重視するなら、その銘柄の配当利回りや権利確定日、支払い頻度もチェックしておきましょう。このように事前に条件をリサーチしておけば、「思っていた待遇が受けられなかった」*というミニ株特有のミスマッチを避けることができます。
※基本的に日本株の配当は1株から支払い対象ですが、証券会社によっては配当金相当額を後日入金する形になる場合があります。
少額だからこそ分散投資を意識する
ミニ株は投資額が少ないからといって1銘柄に集中せず、分散投資を意識しましょう。少額投資家こそ、一度の失敗で資金を失わないよう複数の銘柄に資金を分けるのが大切です。
幸いミニ株なら同じ資金でも複数銘柄に分散しやすいメリットがあります。例えば10万円の資金でも、通常の株取引では1銘柄しか買えないところ、ミニ株なら10銘柄以上に分散投資が可能です。これにより、特定の銘柄が下落した際のリスクを抑えられます。
たとえ1銘柄あたりの投資額が数千円でも、5銘柄に投資すれば計2~3万円ずつの配分となり、一つが値下がりしても他でカバーしやすくなります。
「少額だから損失も小さいだろう」と油断して1社に賭けるより、少額だからこそ複数に分けて安全網を張るべきです。なお、あまり細かく分散しすぎると手数料がかさむ点には注意し、バランスを考えた分散を行いましょう。
ミニ株でも分散投資の基本を忘れずに実践することで、リスクを軽減し安定した運用に近づけます。
分散投資でリスクを抑える考え方
複数の銘柄に分けて投資する
一つの銘柄に集中すると、その銘柄が下落した際に損失がダイレクトに資産全体へ響きます。そこで、異なる複数の銘柄に資金を配分することでリスク分散を図ります。
例えば、業種の異なる銘柄(例:製造業・IT・医療・食品など)を組み合わせて保有すれば、一社の業績不振や業界不況がポートフォリオ全体に与える影響を和らげることができます。ある銘柄が値下がりしても、他の銘柄の値上がりで損失を補える可能性が高まるためです。
ミニ株であっても、この銘柄分散の効果は有効です。値動きの異なる複数銘柄を組み合わせることで、資産全体のボラティリティ(変動幅)を抑え、安定したリターンを狙いやすくなります。
分散のコツは、なるべく関連性の低い銘柄(値動きが連動しにくい組み合わせ)を選ぶことです。そうすることで一つの要因による資産全体へのダメージを最小限にできます。少額投資でも複数銘柄への分散を心がけ、リスクヘッジに努めましょう。
長期的な視点でリスクを平準化する
時間分散もリスクを抑える重要な考え方です。株価は日々上下しますが、長期で保有するほど価格変動が平準化され安定したリターンに近づく傾向があります。
極端な例では、今日買った株が明日急落することもありえますが、10年保有すれば一時的な暴落も回復しプラスになる可能性が高まるというデータもあります。実際、過去の株式市場では、保有期間が長くなるほどマイナスのリターンになる頻度が減少しています。このため、長期投資を心がけることがリスク平準化につながります。
毎月定額を積み立てて購入する(ドルコスト平均法)手法も有効で、価格が高い時は買う量を抑え、安い時には多く買うことで平均購入単価をならすことができます。長期かつ継続的な投資は、一時的な市場の上下動に一喜一憂せずに済み、結果的にリスクを抑えながら着実に資産形成をする王道と言えます。
ミニ株投資においても、短期の値動きに振り回されず長期目線で構えることで、リスクを減らし利益を積み上げやすくなるでしょう。
株式以外の資産と組み合わせて安定を目指す
分散投資は株式内だけでなく、異なる資産クラス間で行うことでも効果が高まります。株式と値動きの異なる資産(例:債券、不動産、金、現金など)を組み合わせて持つことで、ポートフォリオ全体の安定性を向上させるのです。
例えば、株式相場が下落局面では債券価格が上昇する局面があるため、両方保有していれば株の損失を債券の値上がりが一部カバーしてくれることがあります。同様に、不動産投資や金(ゴールド)は株式と相関が低い資産で、異なる値動きをするものを持つと分散効果が高くなります。
このように、資産クラスを跨いで分散することを資産分散と呼び、リスクヘッジの有力な手段です。
具体的には、株式だけでなく債券やREIT(不動産投信)、預金や投資信託なども組み入れ、一つの市場の影響を受けすぎないポートフォリオを構築します。ミニ株投資をしつつも、資産全体では他の安定的な商品も持つようにすれば、たとえ株式部分が下落しても全財産が大きく目減りするリスクを抑えられるでしょう。
複数の資産を組み合わせることで全体の値動きをマイルドにし、中長期で安定した運用を目指すことが可能です。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】ミニ株に関するよくある質問

ミニ株投資は儲かるんですか?
儲けにくいのが実情です。
少額投資ゆえ株価が10%上がっても利益は数百円程度にとどまり、手数料0.5%前後がその利益をさらに削ります。例えば1万円分の株が10%上昇しても利益1,000円ですが、手数料550円なら実質500円しか残りません。
ミニ株は少額投資に向いていますか?
小額から始めたい人には向いています。
1株から購入できるため、数千円~1万円程度でも様々な銘柄に投資可能です。ただ、あくまで練習や体験としては有用ですが、資産形成の速度は緩やかで、大きく増やすには時間がかかります。
ミニ株はやめた方がいいんですか?
目的次第ですが、効率重視なら避けるべきでしょう。
手数料の高さや取引制限が多く、効率的に資産を増やしたい人には不向きです。一方で、少額で投資体験を積むには有効なので、練習台と割り切るなら活用価値はあります。将来的な資産拡大を目指すなら、投資信託や他の手段も検討しましょう。
ミニ株投資のまとめ|メリット・デメリットを理解して賢い判断を
ミニ株は1株から株式投資を始められる手軽さが魅力ですが、取引コストが約0.5%と割高である上、リアルタイム取引不可や優待が得られないなど制約も多いため、効率的な資産形成には不向きとされています。特に短期売買で利ざやを狙う人や、優待・議決権を重視する人にはおすすめできません。
一方で、少額で投資経験を積む機会を提供してくれる点は評価できます。ミニ株のメリット・デメリットを正しく理解し、自分の投資目的に合った手段かどうかを見極めましょう。必要に応じて他の少額投資手段(投資信託やクラウドファンディングなど)も比較検討し、賢く資産運用を始めてください。
参考元
・金融庁「資本市場の環境整備(議決権や株主優待の制限、投資単位の説明など)」
・日本証券業協会「証券投資に関する全国調査(少額投資・分散投資の実態)」
・日本証券業協会「証券税制(取引手数料・税負担の概要)」
・金融庁「若年層を中心とした個人による投資の現状と NISA の利用」
・日本取引所グループ(JPX)「インサイダー取引規制」
・金融庁「規制改革推進会議 スタートアップ・イノベーション促進施策(少額募集、分散投資の観点から)」