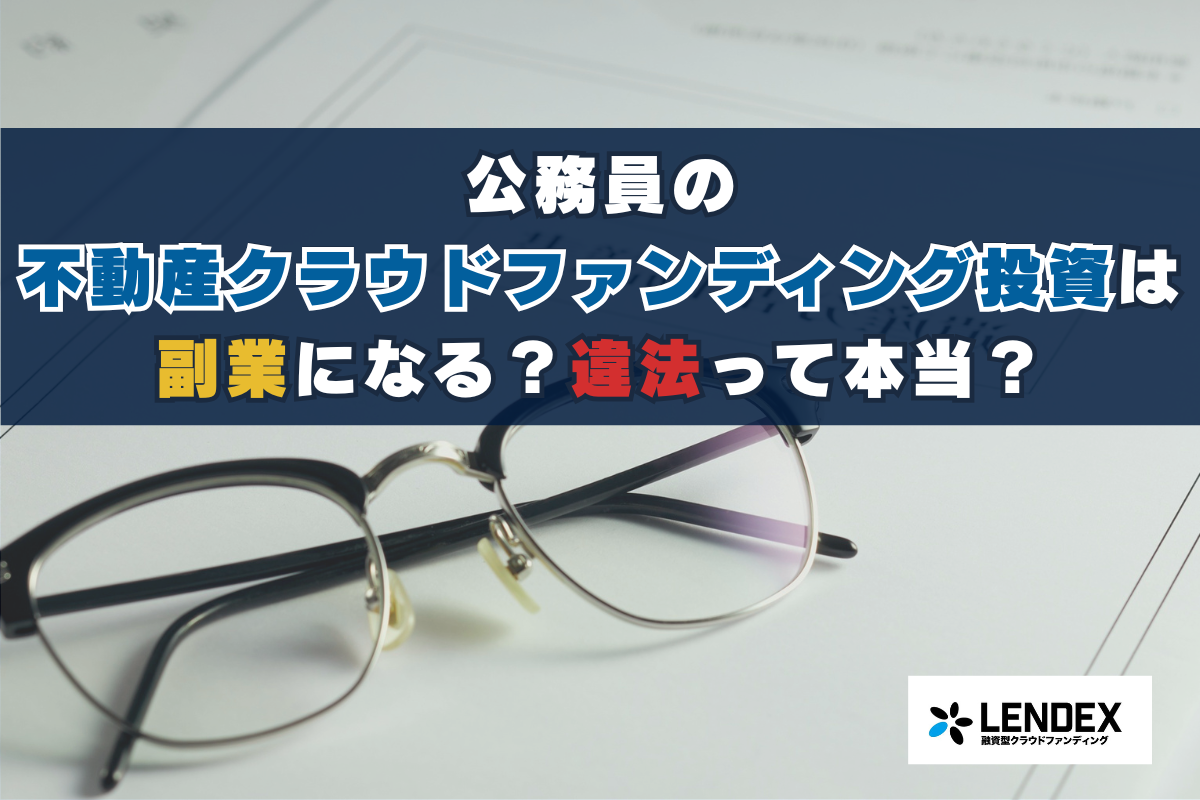公務員として働きながら、将来に向けた資産運用を検討している方は多いのではないでしょうか。
実際、不動産クラウドファンディングは少額から始められる投資として注目を集めています。しかし、「公務員は副業禁止だから投資もできないのでは」「不動産投資は違法になるかもしれない」という不安の声も少なくありません。
実は、公務員の約8割が何らかの資産運用を行っているというデータもあり、適切な知識があれば安心して投資を始められます。一方で、誤った理解のまま投資を始めてしまい、後から問題になるケースも存在します。
では、公務員が不動産クラウドファンディングに投資することは本当に問題ないのでしょうか。
本記事では「公務員の副業禁止規定」と「投資の違い」を法律的な観点から整理し、違法となるケースと合法的に資産運用できるケースの線引きについて、わかりやすく専門的に解説します。
公務員でも不動産クラウドファンディングに投資できる?
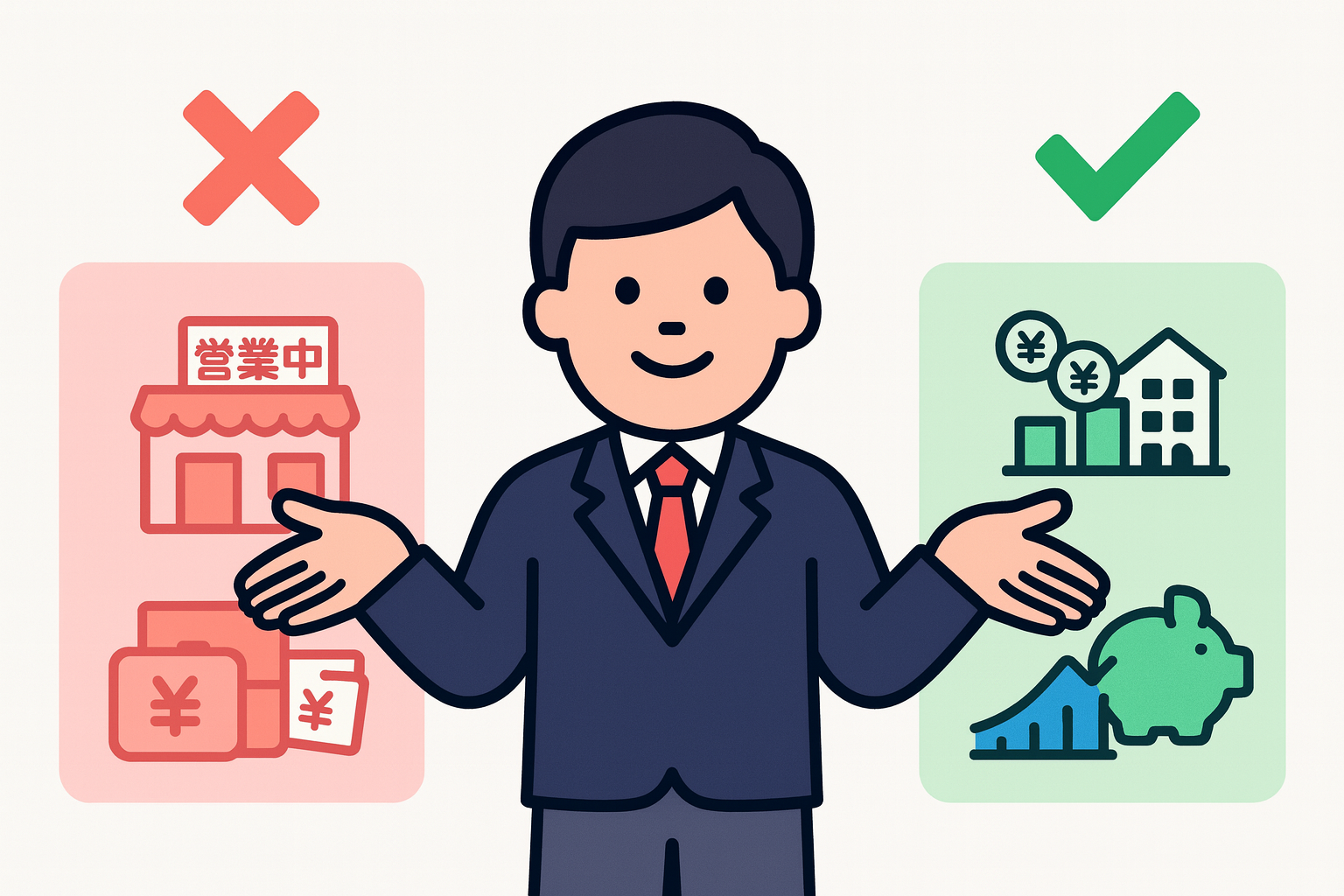
結論:公務員でも不動産クラウドファンディングへの投資は可能
結論から言えば、公務員でも不動産クラウドファンディングへの投資は可能です。国家公務員法や地方公務員法では、公務員が営利企業の役員になったり自ら事業を営むことが禁止されていますが、投資そのものは禁止対象に含まれていません。
人事院規則や内閣人事局等のガイドラインでは、資産運用として出資し配当や利息を得る行為は副業禁止の適用外とされています。単に資金を出資して運用益を得る行為は、報酬を得て事業や事務に従事することには該当しないと解釈されるためです。
実際、人事院のQ&Aや各自治体の通達でも株式の保有・売買など資産運用の一環は兼業規制に抵触しないと示されています。つまり、公務員であっても不動産クラウドファンディングは資産運用として位置づけられ、法律に反することなく投資可能なのです。
投資は資産運用であり副業には該当しない
一般に副業とは、本業とは別に自ら労働を提供して報酬を得る行為を指します。
一方、投資による収益は自分の資金を運用した結果得られるものであり、労働の対価ではありません。そのため、公務員が行う投資は給与を伴う労働とは異なる資産運用とみなされ、副業には該当しないと考えられています。実際に、人事院規則や各自治体のガイドラインでも株式や投資信託、FXなどの資産運用は規制対象外であり許可不要とされています。
重要なのは、その収入が労働によるものか資産運用によるものかという点であり、投資による不労所得は副業禁止規定の範囲外だということです。
不動産クラウドファンディングも一般的な投資と同じ扱い
不動産クラウドファンディングは、少額の資金を不動産事業に出資し、その利回りや利益配分を受け取る仕組みです。これは株式投資や投資信託などと同様に投資商品の一種であり、公務員に対して特別に禁止されているものではありません。
人事院規則や各自治体のガイドラインにおいて、資産運用を禁止する規定は見当たらず、クラウドファンディングによる収益も報酬を伴う兼業には当たらないと解釈されています。要するに、不動産クラウドファンディングは公務員にとって株式投資と同様に認められた資産形成手段なのです。
実際、多くの不動産クラウドファンディング業者が投資家登録の職業欄に公務員を含めていますが、サービスごとに利用条件が異なる場合もあるため、各サービスの規約を確認することが大切です。このことからも、公務員が不動産クラウドファンディングに参加すること自体は一般的に問題なく行えるといえるでしょう。
公務員の副業を制限する法律をわかりやすく解説
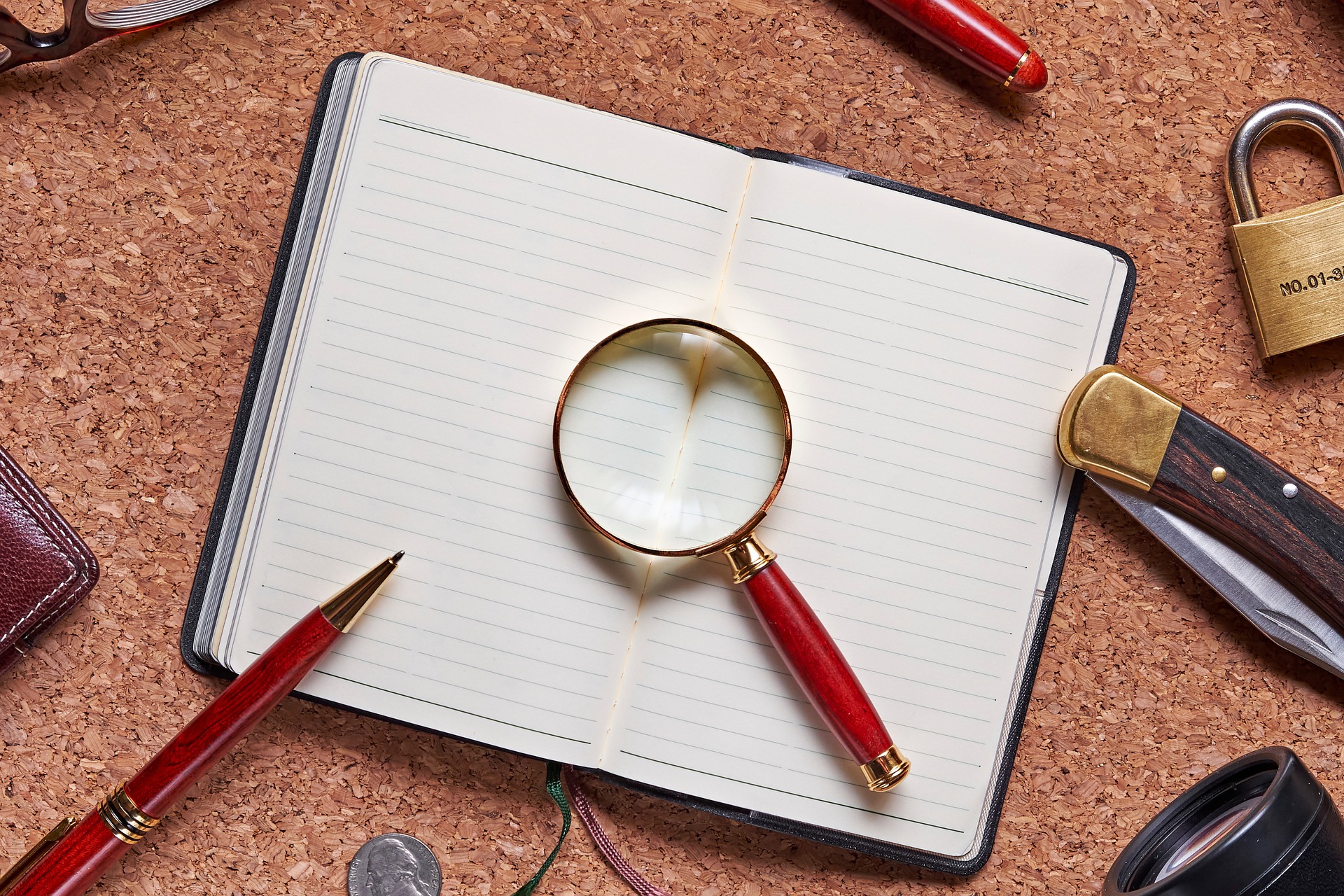
国家公務員法・地方公務員法で定められる副業禁止の目的
公務員の副業を制限する根拠法は、国家公務員なら国家公務員法第103条・104条、地方公務員なら地方公務員法第38条です。これらの規定の目的は、公務員が職務に専念し、公正な行政運営と国民の信頼を守ることにあります。具体的には次のような原則で副業禁止が裏付けられています。
本業専念では、副業により時間や体力が奪われ、本来の公務に支障が出ることを防ぎます。利益相反防止では、公務で得た地位や機密情報を私的な営利活動に利用しないようにします。信用保持では、副業先で不祥事が起きて公務員個人や行政全体の信用が損なわれる事態を防ぎます。
公務員は国民全体の奉仕者として全力を職務に注ぐ義務があり、これらの原則に反する恐れのある営利活動が制限されているのです。
したがって、公務員は私人として営利企業の経営や役職に就くことや、自ら営利事業を営むことが法律で禁止されています。これに違反すると懲戒処分や場合によっては刑事罰の対象にもなり得るため、公務員にとって副業禁止規定は非常に重要なルールとなっています。
なぜ公務員だけ特別に副業が制限されているのか
公務員は民間企業の社員と異なり、法律で直接その副業が規制されています。その背景には、公務員の職務の特殊性があります。
公務員は国民の税金で給与が支払われ、公的な立場で公平・中立に職務を行う責務があります。副業により私的利益を追求すれば、本来の職務との利害衝突や職務専念義務の懈怠が生じ、公務の公正さが損なわれかねません。
また、公務員が副業でトラブルを起こせば行政全体の信用問題にも発展します。これらの理由から、公務員は特別に厳しい兼業禁止規定が設けられているのです。
民間企業でも以前は副業禁止が一般的でしたが、最近は解禁する企業も増えています。しかし公務員の場合、法律で明確に規制されているため、企業の就業規則レベルとは重みが異なります。
要は公務員の副業禁止は職務の公共性と信頼維持のための特別な制度であり、国家公務員法制定当初から続く重要な服務規律なのです。
営利企業への関与・自営業の禁止が基本ルール
公務員の副業禁止を語る上で重要なのが、法律に定められた二本柱のルールです。
一つは営利企業の役員等との兼業禁止、もう一つは自営兼業の禁止です。国家公務員法第103条では、たとえ名目上だけでも営利企業の役員・顧問・評議員になることや、自分で会社を経営することを禁じています。また、地方公務員法第38条でも、許可なく営利企業の役職に就いたり事業を営んだり、有償で他の仕事に従事することを一律に禁止しています。
要するに、公務員は他人の会社に役員などで関わるのも自分で商売をするのも原則NGということです。
例えば公務員が株式会社を設立して代表取締役となることや、飲食店を自分で開業することは、特別な許可を得ない限り法律違反となります。これらは禁止の基本ルールとして、公務員なら誰もが念頭に置くべき事項です。
投資が副業に該当しない理由と公務員が守るべき線引き
投資は資産運用であり労働による収益とは異なる
副業と投資の決定的な違いは、収益が労働の対価か資産の運用益かという点にあります。
多くの副業は自分の労働力や時間を提供して報酬を得るものですが、投資の利益は自分の資金を運用した結果得られるもので、労働そのものではありません。公務員に適用される副業禁止規定も報酬を得て事業や事務に従事することを想定しており、自ら働かずに得る資産運用益はその範疇に入りません。
実際、人事院規則や各自治体のガイドラインでも投資は資産形成の手段として認められており、単なる株式の売買や投資信託の運用は兼業には当たらないとされています。
このように、投資による収益は不労所得と位置づけられるため、公務員が行っても副業には該当しないのです。
収益が自動的に発生する投資は副業ではない
投資の魅力は、自分が直接手を動かさなくてもお金がお金を生むところにあります。
例えば株式の配当金や投資信託の分配金、不動産投資の家賃収入などは、自分の資産を運用していれば自動的に入ってくる収益です。そのため自分が働いて稼ぐものではなく資本が稼ぐ収益であり、一般に副業には当たりません。公務員にとっても、勤務時間外に資産運用から得られる利益は法律上問題にならないケースが大半です。
ただし、投資に熱中するあまり勤務時間中に取引をしたり、本業に支障を来すことがあれば服務規律違反となり得るので注意が必要です。要は、運用益はあくまで資産から生まれるもので、公務の時間とエネルギーを直接消費しない限り副業ではないという点が、公務員が投資可能な根拠になっています。
ただし運営関与や個人事業扱いになると違法の可能性
投資であっても、公務員本人がその運営に深く関与したり、事実上事業主のような立場になる場合は注意が必要です。例えば、自分が所有する不動産を多数貸し出して自ら管理・運営する場合、それが一定規模を超えると事業を営んでいると見なされる可能性があります。
人事院の基準では、独立家屋で5棟以上、アパートなら10室以上を賃貸する規模になると、許可がない限り事業的規模と判断される目安とされています。また、賃貸収入が年間500万円を超えるような場合も同様の目安となります。ただし、これらはあくまで指導基準であり、実際の判断では管理方法や関与度なども総合的に勘案されます。
このように規模が大きくなれば、公務員自らが営利事業を営んでいる状態と見做され、法律違反に問われる恐れがあります。さらに、自分でテナント募集や家賃集金など管理業務まで行っていると運用ではなく経営に関与していると判断されかねません。
公務員が投資を行う際は、単なる出資者の立場を超えて事業の主体者になってしまわない線引きを守ることが肝心です。資産運用に留まらず事業者のように振る舞えば、副業禁止規定に抵触する可能性がある点を忘れてはいけません。
公務員が注意すべき違法になるケースと合法的に投資できるケースの違い

違法になるケース:5棟10室を超える不動産賃貸経営
公務員が不動産投資で賃貸物件を多数所有するケースは規模に注意が必要です。
人事院の定める基準では、戸建てで5棟以上、またはアパートで10室以上を所有して賃貸運用している場合、それは個人による事業的な不動産経営と見なされる目安とされています。
この5棟10室基準を超える規模で許可なく賃貸経営を続けることは、兼業禁止規定に違反するリスクが高まります。(ただし、これはあくまで目安であり、管理方法や関与度によって実際の判断は異なる場合があります。)特に賃貸料収入が年間500万円超にも達すると、営利目的の事業を営んでいると判断される一つの基準となります。
つまり、公務員が自分名義でこれほど大規模な物件運用を行うことは、法律上自営による副業扱いとなる可能性があるのです。実際、これらの条件に該当する場合には人事院や任命権者の許可が必要であり、無許可で行えば懲戒処分の対象にもなります。
以上のように、5棟10室や年500万円というラインは、公務員が不動産投資をする際に注意すべき一つの指標といえます。
違法になるケース:不動産業として事業的規模で運営する場合
物件数や収入規模に関わらず、公務員自身が不動産業者のように積極的に事業を営んでしまうケースも違法のリスクがあります。
例えば、公務員が不動産会社を設立して営業したり、宅地建物取引業者として登録して継続的に売買仲介を行うのは明らかに法律違反です。これは公務員が自ら営利企業を営むことを禁じた国家公務員法103条などに抵触する行為だからです。
また、たとえ個人名義であっても、実質的に不動産事業主と同じ活動を行えば、自営兼業と見なされる可能性が高まります。要するに、公務員が投資の範疇を超えて不動産ビジネスを自分で営むことは、副業禁止の原則に明確に反するため認められません。
なお、これには名義上家族や他人の会社にして実態は自分が経営する場合も含まれます。形式を問わず、公務員本人が営利事業に関与する形になれば違法となることを強く認識しましょう。
合法的に投資できるケース:少額の不動産クラウドファンディング
公務員が違法にならず安心して取り組める不動産投資の一つが、不動産クラウドファンディングへの少額出資です。クラウドファンディングは多数の投資家から小口の資金を集めて大口の融資や事業投資を行う仕組みであり、一人ひとりの出資額は小さく抑えられます。
実際、現在提供されている不動産クラウドファンディング商品には1万円から出資できる案件もあり、まとまった資金を用意しなくても始められます。このような少額からの投資であれば、公務員本人が事業規模で経営しているわけではない明確な資産運用と言え、副業と誤解されにくいメリットもあります。
法律上も、自分が経営者になるわけではなく単なる出資者であれば兼業禁止には抵触しません。したがって、小口の不動産クラウドファンディングは公務員にとって合法かつ始めやすい投資手段となっています。
現に、多くの不動産クラウドファンディングサービスが公務員でも利用可能であることを示しており、職場の許可なく問題なく利用できるケースが一般的です。
合法的に投資できるケース:事業性がなく管理業務を伴わない投資
公務員が副業とならずに資産運用を行うポイントは、自ら事業主のように振る舞わないことです。合法的な投資であるためには、投資対象の運用や管理をプロの業者に任せきりにできる仕組みであることが望ましいでしょう。
不動産クラウドファンディングはまさにその一例で、物件の取得・運営・管理はすべて事業者側が行い、投資家は資金提供のみを担います。これにより、投資家である公務員は日常的な管理業務に関与せずに済み、公務の時間を割く必要もありません。
公務員が所有する不動産を運用する場合でも、小規模であれば管理は専門の不動産管理会社へ委託するよう求められており、自分でテナント対応等をしないことで兼業には当たらないとされています。
このように、運用の手間がかからず事業性を帯びない投資であれば、公務員でも安心して資産形成に取り組めます。具体的には、株式・投資信託・ソーシャルレンディング・不動産クラファンなどが該当し、いずれもお金の運用益を得るだけで副業禁止規定に触れない種類の投資です。
公務員に不動産クラウドファンディングが向いている理由

運用を業者に任せられるため手間がかからない
不動産クラウドファンディングの大きな利点は、運用をプロの事業者に任せられる点です。
投資家は資金を出すだけで、物件の選定・取得から運用・管理・分配までをすべてサービス提供者側が代行してくれます。そのため、公務員のように本業が忙しい方でも自分で賃貸管理等の手間をかけずに投資を継続できます。
直接不動産を購入する場合、金融機関での融資手続きや物件管理など時間と労力が必要ですが、クラウドファンディングならそうした煩雑さがありません。結果として、公務の仕事と投資の両立がしやすく、勤務時間外の負担も最小限で済みます。
ただし、サービスによって運用方法やリスク説明の程度が異なるため、各サービスのガイドラインを確認することが大切です。副業禁止の観点でも、自ら運営に関与しないため安心感が大きいでしょう。
公務員にとって手間を抑えて資産形成できる不動産クラウドファンディングは、続けやすい方法と言えます。
小口から始められるため副業と誤解されにくい
不動産クラウドファンディングは少額の資金から始められる点でも、公務員との相性が良い投資です。
一般に不動産投資となると数百万円以上の自己資金が必要ですが、クラウドファンディングなら1万円や数万円から参加できる案件が多く存在します。小口でコツコツと運用するスタイルであれば、収入も徐々に積み上がる形となり、周囲から副業とみなされにくいという利点があります。
実際、副収入が給与より極端に大きくなったりしなければ勤務先にも怪しまれにくいでしょう。さらに、小額ずつ分散投資することでリスクも抑えられるため、公務員にとって安全に少しずつ増やす資産運用として誤解なく取り組めるのです。
安定した給与との相性が良く、リスク分散もしやすい
公務員は収入が安定している反面、大きな昇給や臨時収入は見込みにくい職業です。そのため、長期的な視点で資産を増やしていく資産運用が求められます。
不動産クラウドファンディングは、毎月分配の利息収入が期待でき、銀行預金に比べて高めの利回りを狙えることから、給与の安定性と組み合わせて堅実に資産形成する手段として適しています。さらに、公務員は職業上リスクを極力避けたい面もありますが、クラウドファンディングでは元本以上の損失が出ない仕組みとなっており、投資額の範囲内でリスクを管理できます。
また、複数のファンドに少額ずつ投資することで分散投資によるリスク低減も図りやすく、公務員のように守りながら増やすスタイルにマッチします。安定収入を土台にして、リスクを抑えつつ着実に資産を増やしたい公務員にとって、不動産クラウドファンディングはまさに堅実な運用とリターン追求を両立できる投資手法なのです。
不動産クラウドファンディングと相性が良い分散投資の考え方

投資先を複数に分けることでリスクを軽減できる
資産運用の基本原則の一つに分散投資があります。これは資金を複数の投資先に振り分けることで、特定の投資対象に問題が起きた場合でも損失を限定し、全体としてリスクを平準化する方法です。
公務員のようにリスクを抑えて着実に資産を増やしたい人にとって、分散投資は非常に有効な手段です。例えば、不動産クラウドファンディングでも複数の案件に少額ずつ投資しておけば、仮に一つの案件で配当減少や遅延が発生しても他の案件からの収益でカバーしやすくなります。
不動産クラウドファンディングは小口投資ゆえに分散しやすく、投資初心者の公務員でもリスクを抑えながら取り組むことができます。卵は一つの籠に盛るなという投資格言の通り、公務員の資産形成でも分散投資を心がけることで、堅実かつ安心な運用が可能になるでしょう。
分散投資は守りながら増やす公務員向きの手法
公務員にとって資産運用は、老後や将来への備えとして長期的にじっくり取り組むものです。
短期で一攫千金を狙うような投機的手法は本業への影響も大きく、リスクも高いため適しません。その点、分散投資による長期運用は、大きく資産を減らすリスクを避けつつ徐々に増やしていける守りながら増やす方法として公務員に向いています。例えば、毎月コツコツと余剰資金を投資に回し、株式・債券・不動産クラファンなど複数の資産クラスに分けて保有することで、一つの景気変動や市場の波に資産全体が左右されにくくなります。
実際、低金利下では預金だけではお金は増えないため、年3から8%程度の利回りが期待できる不動産クラウドファンディングをポートフォリオに組み込むのは有効な選択肢です。
分散投資のメリットは、景気の浮沈やインフレなど不確実な要素に対して資産の防御力を高めつつ、着実に資産を育てられる点にあります。公務員の堅実な性格と計画的な資産形成には、まさにこの分散投資の考え方がフィットすると言えるでしょう。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】公務員のクラウドファンディング投資に関するよくある質問

公務員がクラウドファンディングで利益を得たら確定申告しないと違法になる?
利益額によっては確定申告が必要であり、怠ると税法上の違反になります。
税法では給与以外の所得合計が20万円を超えた場合に確定申告をしなければならないと定められています。例えば、不動産クラウドファンディングで年間30万円の利益が出た場合は、所定の期限までに確定申告を行わないと納税漏れとなるので注意が必要です。
勤務先にバレるリスクは?副業と見なされないためのポイントは?
適切に運用すれば勤務先に知られるリスクは低いです。
業務時間中に取引をしない、インサイダー情報を利用しないなど服務規程を守りつつ、確定申告時に住民税の徴収方法を自分で納付にすれば、副収入分の住民税が給与天引きされず職場に察知されにくくなります。例えば、確定申告書で住民税を自分で納付するよう選択しておけば、クラウドファンディングの利益による住民税増加が給与経由で通知されにくくできます。
ただし、自治体によっては情報連携の方法が異なる場合もあるため、絶対ではない点にご留意ください。
家族名義で投資すればバレない?公務員が注意すべき落とし穴とは?
家族名義で投資しても本質的な解決策にはならず、場合によっては違法になる恐れがあります。
収入の実質的な受け手が公務員本人であるにもかかわらず家族名義で申告することは、所得税法上実質所得者課税の原則に反し脱税と見なされる可能性があります。例えば、公務員本人が資金を出して運用しているのに配当だけ家族の口座で受け取るようなケースでは、実態によっては家族名義でも公務員本人の副業と判断される場合があるので、こうした手段は避けるべきです。
まとめ|公務員でも安心して不動産クラウドファンディングを始めるために
公務員は法律上副業が厳しく制限されていますが、投資は資産運用として認められており、不動産クラウドファンディングも適切な範囲で行えば安心して始められます。
副業とみなされないためのポイントは、事業的規模にしないことや、運用に深く関与せず受動的な投資家に徹することです。法律のルールと税務上の手続きを守りながら少額・分散で取り組めば、公務員でも安定した資産形成を図ることができるでしょう。
公務員という安定収入を活かし、堅実なクラウドファンディング投資で将来に向けた資産運用をスタートしてみてはいかがでしょうか。
参考元
- ・e-Gov法令検索:「国家公務員法第103条・第104条」
- ・e-Gov法令検索:「地方公務員法第38条」
- ・総務省:「地方公務員の兼業について」
- ・人事院:「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」
- ・人事院:「人事院規則14-8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」
- ・総務省:「国家公務員の兼業について(概要)」
- ・国税庁:「No.1373 事業としての不動産貸付けとそれ以外の区分」
- ・国税庁:「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
- ・国税庁:「住民税の徴収方法の選択」
- ・国税庁:「法第12条《実質所得者課税の原則》関係」