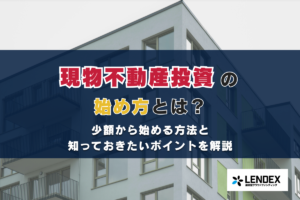固定資産税は不動産を所有している人に毎年かかる大きな支出です。しかし、その支払い方法を工夫することでポイント還元を受けたり、手数料を抑えたりと、賢く節約できる可能性があります。本記事では、投資家目線で固定資産税の基本をおさらいしつつ、「固定資産税 支払い方法 おすすめ」として注目されるお得な支払い方法4選を詳しく解説します。
そもそも固定資産税とは?まずは基礎知識をおさらい
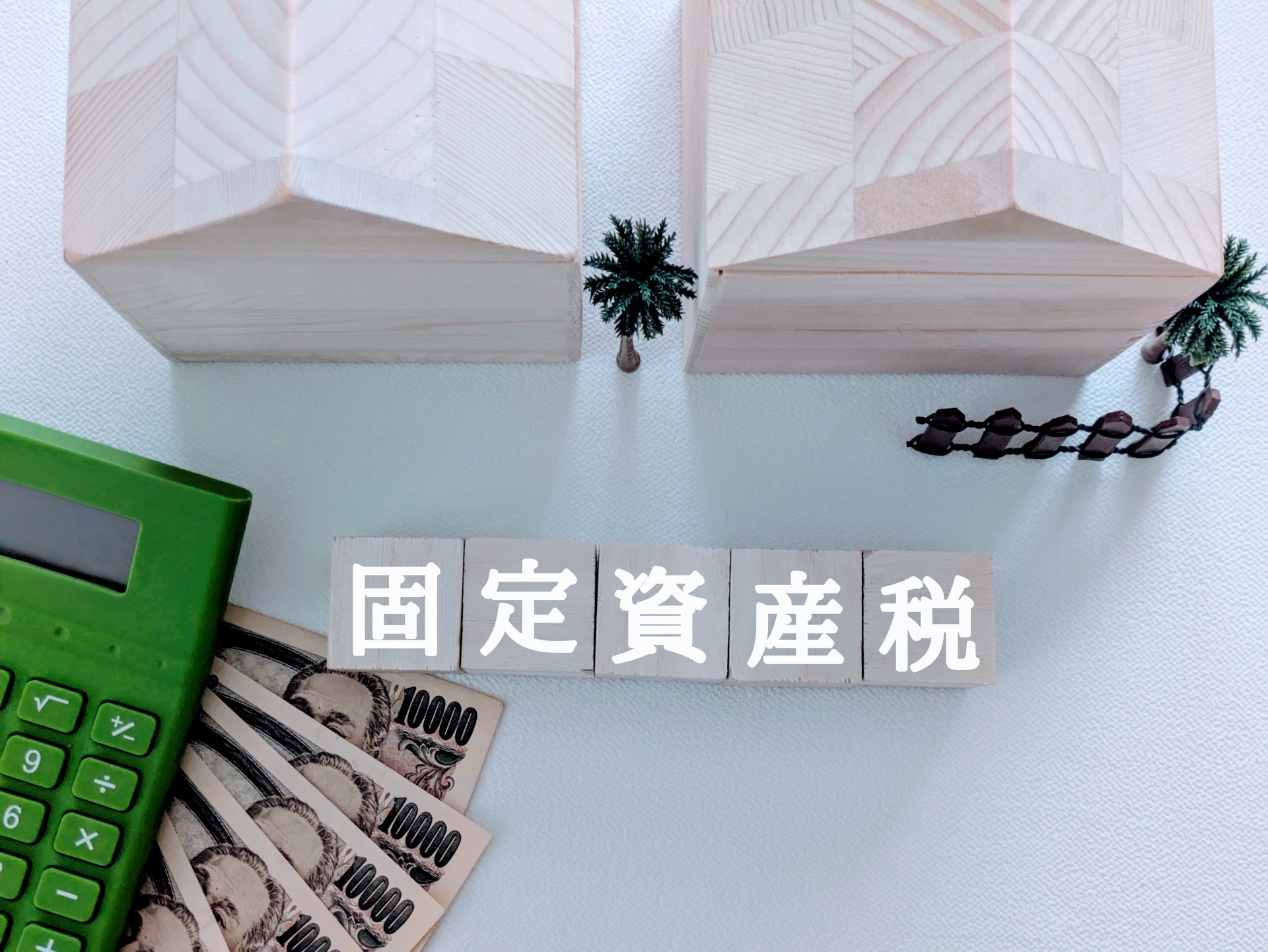
まず初めに、固定資産税とはどのような税金かを押さえておきましょう。固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や建物などの固定資産を所有している人が納める市区町村税(地方税)です。不動産を購入すると翌年度から毎年課税され、地域や資産の評価額に基づいて算出されます。
固定資産税の税率は各自治体で決められますが、国が定めた標準税率は1.4%で、ほとんどの自治体はこの1.4%を採用しています。評価額が高ければ税額も高額となり、例えば評価額3,000万円の住宅なら年間で約42万円もの固定資産税が発生するケースもあります。
納税通知書は毎年春頃に自治体から郵送され、通常は年4回の分割払いか一括払いを選択でき、同封の納付書(振込用紙)を使って期限までに金融機関やコンビニで支払うのが一般的です。
近年では口座振替(自動引き落とし)を利用する人も多く、一度手続きすれば毎回自動で引き落とされるため支払い忘れの防止に役立ちます。
固定資産税の支払い方法はこんなにある!主要な支払い手段を比較
固定資産税の支払い方法には、従来からある現金払いや口座振替のほか、クレジットカードやスマホ決済などキャッシュレスな手段も登場しています。ここでは代表的な支払い方法について、それぞれのメリット・デメリットやお得度を比較してみましょう。
現金・口座振替|手間なく確実だけどお得感は少なめ

現金払いは最もシンプルな固定資産税の支払い方法です。自治体から届く納付書を持参し、銀行やコンビニ、市役所の窓口などで現金で納付します。手数料は無料で、その場で領収証書を受け取れるのがメリットです。
口座振替(自動引き落とし)は、銀行口座から指定期日に税額が自動で引き落とされる方法です。銀行や自治体窓口に出向く必要がなく、支払い忘れの心配も減るため、広く利用されています。
ただし、これら現金や口座振替による納付はポイント還元など金銭的なお得さはありません。あくまで確実に支払うことに重きを置いた方法で、「手間なく確実に支払いたい」方に向いています。
最近は後述するキャッシュレス決済でも領収証書が発行できる自治体も増えていますが、紙の領収証がすぐに欲しい場合は現金払いが確実です。
クレジットカード払い|ポイントが貯まる人気の方法

クレジットカードで固定資産税を支払う方法は、近年利用者が増えている人気の手段です。対応している自治体であれば、自治体指定の納付サイト(例:「地方税お支払いサイト」など)からカード情報を入力して納付が可能で、自宅にいながら24時間手続きできる手軽さがあります。
最大の魅力は、何と言ってもカードのポイントが付与される点でしょう。固定資産税は年額で数万円~数十万円に及ぶため、例えば年間20万円をカード払いすれば1%還元でも2,000円相当のポイントが貯まります。普段からクレジットカードを活用している人にとっては、税金の支払いでもポイントを獲得できるのは大きなメリットです。
ただし、後述するように決済手数料がかかるケースもあるため、ポイント還元率と手数料率のバランスは要確認です。それでも還元率の高いカードやマイルが貯まるカードで支払えば、手数料を差し引いても十分お得になる場合が多いでしょう。
PayPay・楽天ペイなどのスマホ決済|手軽さとキャンペーンが魅力

スマートフォンのQRコード決済アプリを使って固定資産税を納付する方法も、近年急速に普及しています。代表的なものにPayPay、楽天ペイなどがあり、自治体によってはd払いやau Payにも対応しています。納付書に印字された地方税統一QRコード(eL-QR)をスマホで読み取るだけで、その場で支払いが完了します。
このスマホ決済のメリットは、まず手軽さです。アプリを開いて自宅でバーコードをスキャンするだけなので、わざわざ銀行やコンビニに行く必要がありません。24時間いつでも支払えるため、忙しい方や現金を持ち歩かない方にも便利です。また、基本的に決済手数料が無料である点も魅力です(クレジットカード払いでは発生する手数料が不要)。
さらに、各種スマホ決済アプリが実施するキャンペーンを活用できれば、ポイント還元や割引クーポンなどお得な特典を受けられる可能性もあります。例えば、過去にPayPayで公共料金支払い時に○%還元や全額ポイントバックのキャンペーンが開催されたこともあります。最新情報はPayPayアプリ内のお知らせや公式サイトで確認しましょう。
一方で注意したいのは、通常時はポイント還元が付かない場合が多い点です。PayPayの場合、請求書払いはポイント付与の対象外で、固定資産税を支払ってもPayPayポイントは貯まりません。ただし、PayPayステップの達成条件のカウントには利用回数としてカウントされるため、PayPayの還元率を上げるのに役立ちます。
楽天ペイはキャンペーンは少ないものの、普段から楽天ポイントを貯めている人であれば楽天カードからチャージして納付することで間接的にポイントを獲得可能です。さらに、期限間近の期間限定ポイントを納税に充てるなど有効活用もできます。
コンビニ払い|いつでも支払いOKだが注意点も
コンビニエンスストアで固定資産税を支払う方法も、昔から多くの人に利用されています。納付書を持ってコンビニ店頭のレジで支払うだけで、平日昼間に銀行に行けない方でも24時間いつでも納付できる手軽さがあります。多くの自治体で、主要なコンビニ(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなど)なら固定資産税の払込票を取り扱っているため、自宅近くの店舗で深夜でも支払えるのは大きな利点です。
コンビニ払いは基本的に現金での支払いになります。レジで支払うと領収証代わりの受領書が発行され、その場で納付完了となります。手数料も無料で、銀行窓口と違い営業時間を気にしなくて良い便利な方法です。
しかし、コンビニ払いにはいくつか注意点もあります。まず、支払い期限を過ぎた納付書はコンビニで取り扱ってもらえないことです。期限切れの場合はコンビニではなく役所の税務課窓口などで納付する必要があります。また、一度に扱える金額にも上限があります(多くのコンビニでは30万円が上限)。固定資産税額が非常に高額な場合、納付書が複数枚に分かれて発行されたり、高額の場合は金融機関での支払いが案内されることがあります。
もう一点、コンビニでは基本的にクレジットカード払いができないことも覚えておきましょう。公共料金の収納代行という性質上、店頭では現金以外で支払うのは難しく、ポイント獲得は割り切る必要があります。
クレジットカード払いのメリットとデメリット
上記で触れたように、クレジットカード払いはポイント還元が魅力の反面、手数料がかかる場合がある点に注意が必要です。ここでは、固定資産税をカード払いするメリットとデメリットを改めて整理します。
お得なポイント還元が狙える
クレジットカード払い最大のメリットは、なんといってもポイント還元です。先述の通り、税金という大きな支払いでもポイントが貯まるのは家計にとってプラスとなります。特に投資家の方であれば、普段からカードで決済してポイントを資産運用に回したり、マイルを貯めて旅行費用を浮かせたりといったテクニックをお持ちかもしれません。固定資産税の支払いでも同様に、まとまったポイント獲得のチャンスと捉えることができます。
例えば、還元率1%のカードで10万円の固定資産税を支払えば1,000円相当のポイントが付きます。ポイント高還元のカードを使えば、0.5%のカードより2倍、1.5%なら3倍ものポイントがもらえる計算です。最近では特定のQRコード決済と連携したカード(PayPayカード、dカード、楽天カードなど)で高い還元率を実現するケースもあります。手間なく払いながら資産形成につなげられる点で、クレジットカード納付は非常にお得な支払い方法と言えるでしょう。
手数料が発生するケースもあるので注意
一方で、クレジットカード払いには決済手数料がかかる場合がある点に注意が必要です。多くの自治体ではカード納付を外部の決済代行サービスに委託しており、その利用料を納税者が負担する形になっています。
この手数料については、2025年から全国的に引き上げられた経緯もあり、現在では最低でも0.99%〜の割合で設定されているケースが一般的です(以前は0.83%〜)。ただし、手数料率は自治体によって異なり、段階的な固定額制を採用している例もあります。このように、同じクレジットカード払いでも、納付先によって手数料の計算方法が異なるため注意が必要です。
当然、この手数料はポイント還元分を相殺する可能性があり、お得度に大きく影響します。仮に還元率0.5%のカードで10万円を支払った場合、500円相当のポイントが付与されますが、仮に手数料が1%なら1,000円の手数料がかかり、差し引きでマイナスになってしまいます。
一方、1%還元のカードなら+0(トントン)、2%還元のカードであれば差し引きでも+1,000円ほどお得になる計算です。このため、カード払いを選ぶ際は「ポイント還元率」と「手数料率」を比較し、実質的に得になるかをしっかり見極めることが欠かせません。
さらに、カードの利用限度額にも注意が必要です。特に不動産投資をされている方などで、複数物件の固定資産税をまとめて支払うケースでは、決済額が思いのほか高額になる場合もあります。限度額を超えてしまうと決済エラーが発生し、納期限に間に合わないリスクも生じます。
このような事態を避けるためにも、あらかじめカード会社に一時的な利用枠の増額を申請する、納付額を複数枚のカードに分けて支払う、もしくは分割払いや別の決済方法と組み合わせるなどの工夫をしておくと安心です。
PayPayなどスマホ決済での支払いは本当に可能?
「スマホ決済で税金が払えるって本当?」と半信半疑の方もいるかもしれません。ここでは、PayPayなどを使って本当に固定資産税が支払えるのか、その仕組みとお得に使うコツを解説します。

PayPay請求書払い対応自治体のチェック方法
固定資産税はPayPay等のスマホ決済アプリで支払い可能です。2023年以降、固定資産税の納税通知書に共通の地方税統一QRコード(eL-QR)が印刷される自治体が大幅に増え、現在ではほぼ全国の自治体でPayPayによる納付に対応しています。PayPayアプリでこのQRコードを読み取れば、自動的に支払い情報が表示されてそのまま納税できます。
対応自治体かどうか確認する方法としては、納付書に「PayPayで支払えます」等の記載やQRコードがあるかを見るのが手っ取り早いでしょう。また、PayPayの公式サイトやアプリ内の「請求書払い対応自治体一覧」でも確認できます。楽天ペイなど他のアプリも同様で、基本的にはeL-QR対応の納付書であれば複数の主要スマホ決済アプリで支払可能です。
なお、PayPay請求書払いはPayPay残高からのみ決済可能です。事前に納付額相当の残高をチャージしておかないと支払いが完了しないので注意しましょう。
キャンペーン活用でさらにお得に支払うコツ
スマホ決済による固定資産税の支払いをよりお得にするには、各サービスが提供するキャンペーンを上手に活用することがポイントです。以下にいくつか代表的な例を紹介します。
- PayPayのキャンペーン: 過去に請求書払い利用で○%還元や全額ポイントバックのキャンペーンが開催されたこともあります。最新情報はPayPayアプリ内のお知らせや公式サイトで確認しましょう。
- 楽天ペイ: キャンペーンは少ないものの、普段から楽天ポイントを貯めている人であれば楽天カードからチャージして納付することで間接的にポイントを獲得可能です。さらに、期限間近の期間限定ポイントを納税に充てるなど有効活用もできます。
このように、スマホ決済はキャンペーン次第で非常にお得になります。ただし狙いすぎて支払いを忘れては本末転倒ですので、期限内に確実に納付することが最優先です。キャンペーンの有無にかかわらず、基本は手数料ゼロでいつでも納付できる便利な方法として活用し、タイミングが合えばラッキー程度に考えておくと良いでしょう。
ふるさと納税と併用は可能?税金の賢い節約術

固定資産税の話題でよく出る疑問に、「ふるさと納税と併用して節約できないか?」というものがあります。ふるさと納税と固定資産税は別物であり、直接的に固定資産税を安くすることはできません。ただし、賢く組み合わせて活用することで、トータルの税負担に対する満足度を上げることは可能です。
ふるさと納税と固定資産税の違い
ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付をすることで、寄付額のうち2,000円を超える部分について所得税・住民税が控除(減税)される制度です。寄付先からは地域の特産品などのお礼の品がもらえるため、実質的に「税金の前払いによる買い物」のようなメリットが受けられるのが特徴です。
一方、固定資産税はこれまで説明してきた通り、不動産を所有している人に課せられる地方税で、納税先は自分の不動産が所在する自治体です。ふるさと納税と違って任意ではなく必ず支払う義務があり、また減免措置は住宅用地や新築住宅に対する一部軽減など限られたケースのみです。両者の決定的な違いは、税額の使途や控除の仕組みです。ふるさと納税で住民税が軽減されても、固定資産税が減るわけではありません(固定資産税は控除の対象外)。あくまで所得税・住民税の範囲での減税制度であるため、固定資産税そのものを直接安くする手段としてふるさと納税を利用することはできないのです。
組み合わせて賢く節税する方法
とはいえ、トータルで見た税負担という観点では、ふるさと納税の活用は有効です。固定資産税の支払い自体は避けられませんが、その年の他の税(金額的には住民税)の負担をふるさと納税によって翌年軽減できれば、結果として可処分所得(手元に残るお金)を増やすことにつながります。
例えば、毎年固定資産税で20万円支払い、さらに所得に応じて住民税も払っているとします。このとき、上限いっぱいまでふるさと納税を行えば、住民税が翌年減税され、その分を実質的に固定資産税の補填に充てることができます。「固定資産税で出て行くお金の痛みを、別の形で取り戻す」というイメージです。
ただし、ふるさと納税には年収等に応じた控除上限額があり、誰もが自由な額を寄付できるわけではありません。また、寄付には自己負担2,000円がある点も忘れてはいけません。重要なのは、固定資産税を滞りなく納めた上で、余裕資金で無理のない範囲のふるさと納税を行うことです。そうすれば、翌年の住民税負担が軽くなり、実質的な節税メリットと地域からのお礼品を得ることができます。
まとめると、固定資産税そのものを直接節約する裏技は存在しません。しかし、ふるさと納税等の制度を併用して総合的に家計にプラスとなる施策を講じることは、賢い資産運用・税金対策の一環と言えるでしょう。
どの支払い方法が一番お得?ケース別おすすめパターン
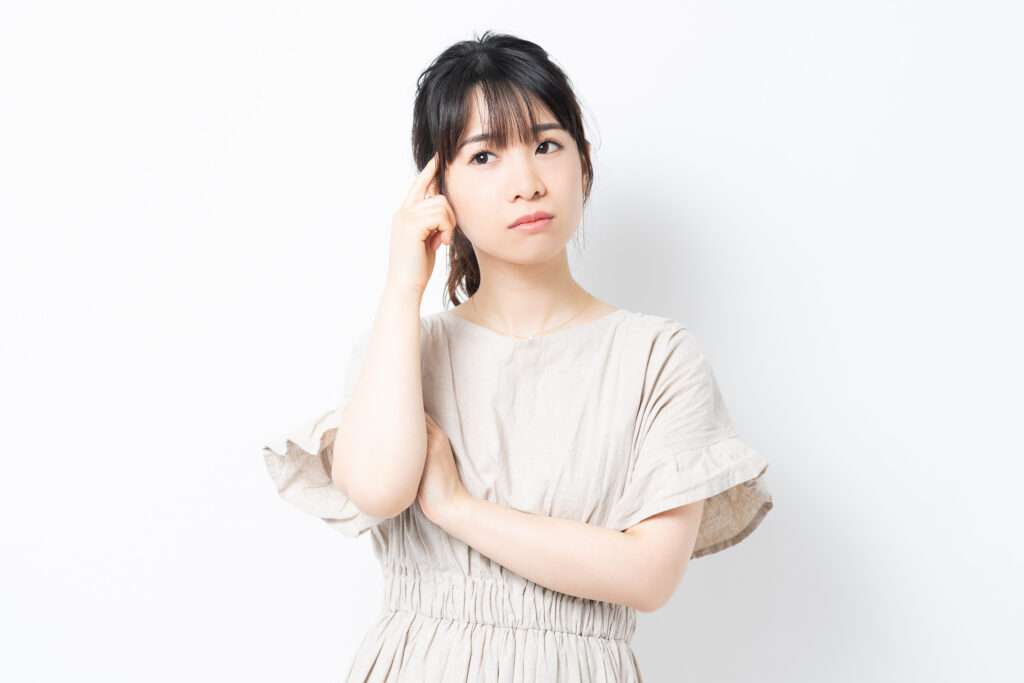
ここまで固定資産税の様々な支払い方法と特徴を見てきましたが、結局「どの支払い方法がおすすめなの?」という疑問が残るかもしれません。答えは、その人の重視するポイントによって異なります。以下に、ケース別に最適な支払い方法を整理します。
とにかくポイント重視ならクレカ
「少しでも多くポイントを貯めたい!」というポイント重視派には、やはりクレジットカード払いが有力です。高還元率のカードやマイル系カードで支払えば、手数料を払っても十分なリターンが期待できます。特に、年間の固定資産税額が大きい人ほどポイント獲得額も大きくなるため、積極的にカード払いを検討したいところです。
例えば30万円の固定資産税をクレカ払いすれば、1%還元のカードでも3,000円分のポイントが付きます。還元率2%のカードなら約6,000円相当となり、手数料を差し引いても十分プラスになるでしょう。(※手数料と限度額については前述の注意点も参照してください。)
手軽さ重視ならPayPayなどのスマホ決済
「とにかく楽に支払いたい。できれば現金や書類は使いたくない」という手軽さ重視派には、スマホ決済アプリでの納付がおすすめです。PayPayやLINE Payなどであれば、届いた納付書のQRコードを読み取るだけで決済が完了し、所要時間はわずか数十秒です。24時間いつでもどこでも手続きでき、紙の納付書と現金を持ち歩く必要もありません。
スマホ決済は基本的に手数料ゼロなのも嬉しいポイントです。思い立ったときにすぐ支払っておけるので、うっかり期限を逃すリスクも下がります。特に忙しいビジネスパーソンや、デジタルツールに慣れた若い世代の不動産オーナーには適した方法です。
ポイント還元については通常期待できませんが、不定期のキャンペーンや先述のカード併用テクニックで恩恵を受けられる可能性があります。あくまで「手軽さ優先」でありつつ、キャンペーンがあればラッキー程度に考えておくとよいでしょう。何より、自宅で数クリックで完了する手軽さは、一度体験すると手放せない便利さです。
手数料なしを優先するなら口座振替や現金
「とにかく余計なお金は一切払いたくない。確実に納税できればそれで良い」という堅実派には、口座振替や現金払いといった手数料ゼロの従来型の方法が向いています。ポイントは付かなくても、支払いに伴うコストが一切かからない安心感は大きなメリットです。
口座振替なら一度手続きしておけば毎回自動引き落としで、手数料無料で確実に納付できます。銀行残高さえ確保しておけば、納期限に勝手に支払われるため、忙しくて納付を忘れがちな人にもおすすめです。
現金払いも手数料ゼロで、領収証が即時にもらえる安心感があります。ただし、銀行や役所の営業時間に行く必要があるのが手間と言えば手間です(コンビニなら時間は自由ですが前述の通り現金のみです)。その分、「お金をかけず確実に払う」という観点では昔ながらの方法が一番と言えるでしょう。ポイントに惑わされず、確実性・安全性を重視する場合は、口座振替の設定を済ませてしまうのが長期的には楽でしょう。
固定資産税の支払いでやってはいけない注意点

最後に、固定資産税の支払いに関して絶対に押さえておきたい注意点をまとめます。お得さを追求するあまり基本を疎かにすると、かえって損をすることもありますので注意しましょう。
支払いを甘く見ると危険!延滞は「信用」と「財産」のリスクに
固定資産税の納付は各期ごとに期限が明確に定められており、1日でも遅れると延滞金が発生します。たとえば20万円の税金を60日間滞納した場合、延滞金は約1,700円。金額だけを見ると大したことがないように感じるかもしれませんが、延滞を軽く見るのは非常に危険です。
まず自治体から督促状が届き、それでも納付しなければ差し押さえ予告書→財産の差し押さえへと進みます。対象は銀行口座・給与・不動産・車など多岐にわたり、強制執行によって生活に直接的な打撃を受けることになります。
さらに、税金の延滞が繰り返されると、自治体や金融機関の内部情報として扱われ、住宅ローンや融資審査に悪影響を及ぼす可能性も。支払えない事情がある場合は、放置せず早めに自治体に相談すれば分割納付にも応じてもらえることがあります。「少額だから」と油断せず、税金の支払いは最優先で対応しましょう。
高額決済時はカード利用限度額にも注意
クレジットカードで高額な固定資産税を払う場合、カードの利用限度額に注意しましょう。特に他の大きな出費と重なると、想定以上にカードを利用していて納付時に限度額オーバー…という事態もありえます。
限度額オーバーで決済エラーになると、納期限ギリギリでは再手続きが間に合わず延滞してしまうリスクもあります。そうならないために、事前にカード利用状況を確認し、必要なら早めに繰上返済して利用枠を空けておく、2枚のカードに分けて納付する等の対策を講じましょう。
また、クレジットカード払いに限らずスマホ決済でも上限額には気を付けてください。例えばPayPay残高の1回あたりや1ヶ月あたりの支払い上限、LINE Payの残高上限など、アプリによって制約があります。自分の支払額がその範囲内か、事前に各サービスのヘルプなどで確認しておくと安心です。
要するに、「支払ったつもりが決済できていなかった」という事態を防ぐことが重要です。特に大口の納税をキャッシュレスで行う際には、利用枠・残高・上限額をしっかり把握し、確実に納税を完了させましょう。
固定資産税の軽減措置の最新情報
新築住宅に対する固定資産税の軽減措置(住宅部分の税額の2分の1を減額)は、令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅が対象です。これは良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上を図るための措置です。
- 一般住宅:3年間(3階建以上の耐火構造住宅は5年間)
- 長期優良住宅:5年間(3階建以上の耐火構造の場合は7年間)
まとめ|自分に合った支払い方法で固定資産税をお得に賢く払おう
固定資産税の支払い方法は多様化しており、現金や口座振替による確実な納付から、クレジットカード払いやスマホ決済といった手軽な方法まで選択肢が広がっています。重要なのは、自分に合った方法を選び、期限内にきちんと納めることです。
ポイントを貯めたいならクレジットカード払い、手軽さを重視するならスマホ決済、確実性を優先するなら口座振替と、それぞれのスタイルに応じた選択が賢明です。
税金の支払いもキャッシュフロー管理の一環と考え、メリットを最大化しながらペナルティを防ぐ意識が大切です。さらに、支出を抑える工夫だけでなく、余裕資金を活かす視点も欠かせません。
たとえば融資型クラウドファンディングを活用すれば、安定した収益源をポートフォリオに加えることが可能です。LENDEXなら、少額から分散投資を始められ、毎月安定した利息収入を得ることができます。
固定資産税の支払いをきっかけに、家計全体を見直し、支出と収入のバランスを整えることを意識していきましょう。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?