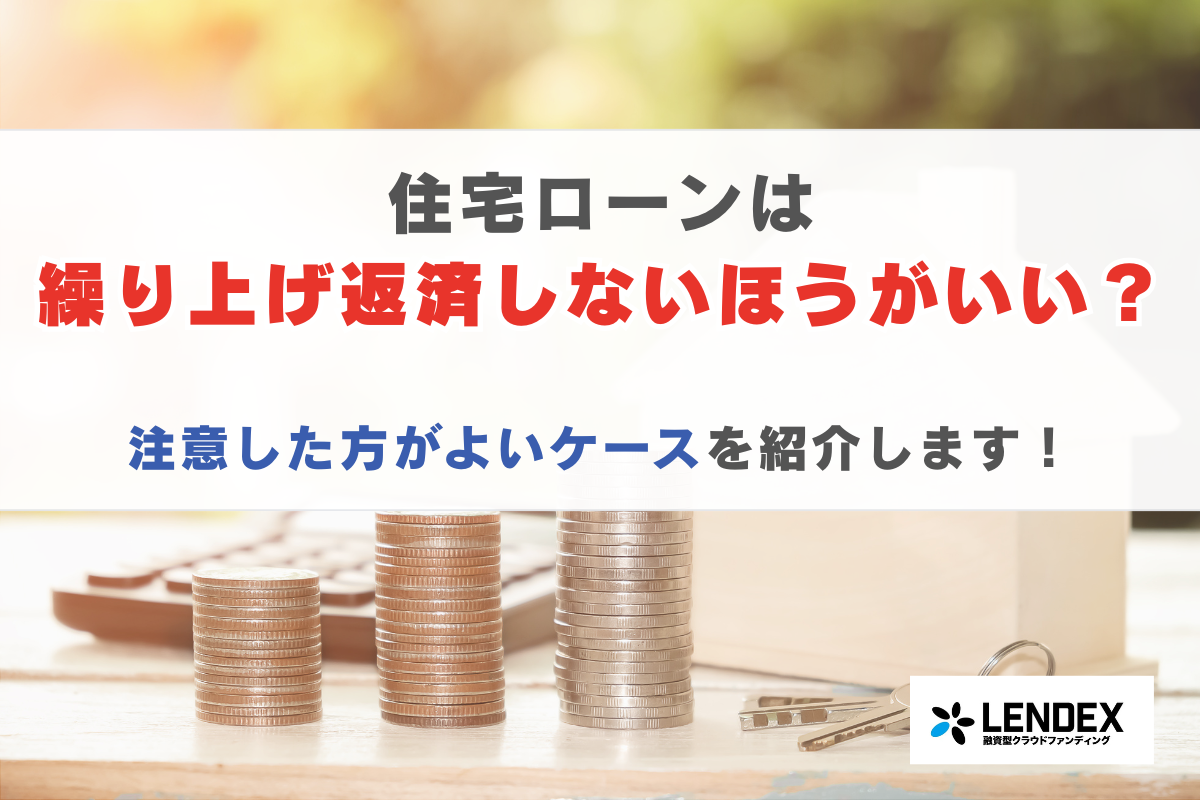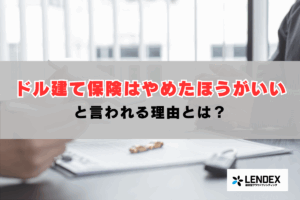住宅ローンを少しでも早く返済したい、そう考えて「繰り上げ返済」を検討する方は多いでしょう。しかし近年では「繰り上げ返済はしないほうがいい」という声も増えてきました。その理由は、低金利や住宅ローン控除といった制度の影響、さらには資産運用の観点からも、必ずしも返済を急ぐ必要がないケースがあるためです。
本記事では、「繰り上げ返済しないほうがいい」と言われる背景や、実際に注意すべき具体的なケース、そして繰り上げ返済と投資を両立させるための考え方をやさしく解説します。今後のマネープランに迷っている方は、ぜひ最後までご覧ください。
住宅ローンの繰り上げ返済はしないほうがいい?まずは基本を確認

繰り上げ返済とは?返済方法の種類と特徴
繰り上げ返済とは、住宅ローンの通常の毎月返済とは別に、手元の余裕資金を使ってローン残高の一部または全額を前倒しで返済することです。大きく分けて2種類の方法があり、「期間短縮型」と「返済額軽減型」です。
期間短縮型は繰り上げ返済後も毎月の返済額を変えずに残りの返済期間を短くする方法で、将来の利息支払いを大幅に減らせるのが特徴です。一方、返済額軽減型は残りの返済期間をそのままに、毎月の返済額を減らす方法で、月々の負担軽減につながります。ただし返済額軽減型では完済時期は当初と変わらず、総支払利息の軽減効果は期間短縮型に比べ小さくなる点に注意が必要です。
繰り上げ返済は一部だけ行うことも可能で、例えばボーナス時に一部繰り上げ返済をすることで元本を減らし、利息負担を減らすことができます。なお、金融機関によっては繰り上げ返済の最低金額や手数料が設定されている場合もあるため、実行前に条件を確認しましょう。
「しないほうがいい」と言われる背景にある考え方
繰り上げ返済には確かに利息軽減などのメリットがあります。しかし一方で、「繰り上げ返済はしないほうがいい」との意見があるのも事実です。その背景にはいくつかの考え方があります。
手元資金の目減りリスク
まとまった資金を繰り上げ返済に充てると、その後に急な出費が発生した際に対応できなくなる恐れがあります。一度返済に回したお金は基本的に手元に戻せないため、教育費や医療費など将来必要となる資金まで投入してしまうと家計を圧迫しかねません。
住宅ローン減税(控除)への影響
借入から一定期間は住宅ローン残高の一定割合を所得税などから控除できる住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の制度があります。繰り上げ返済をするとローン残高が減るため、この控除額も減少してしまいます。
特に控除適用期間中(通常借入後10年間、条件により最大13年間)は、あえて繰り上げず控除の恩恵をフルに受けた方が得になるケースがあります。また、期間短縮型で繰り上げた結果、返済期間が10年未満になると控除の資格自体を失ってしまう点にも注意が必要です。
超低金利環境による機会損失
日本では住宅ローン金利が変動型で年0.5%前後、固定型でも1~2%程度と非常に低水準です。金利負担がもともと小さい場合、繰り上げ返済で削減できる利息もわずかです。そのため、余裕資金を繰り上げ返済に充てるより、他の運用や投資に回した方が有利に働く可能性があります。
例えば適用金利が年1.0%なら、年1%以上の利回りが期待できる運用商品に資金を振り向けた方が得られるメリットが大きいと言えます。ただし投資には元本割れリスクも伴うため、単純比較はできないものの、低金利下では「繰り上げ返済しない」選択肢も十分考えられます。
団体信用生命保険(団信)の有効活用
住宅ローンには通常、契約者が死亡・高度障害状態になった場合に残債がゼロになる団信が付帯しています。繰り上げ返済を進めて残高を減らしすぎると、万一の際に団信で補償される金額も少なくなります。
極端な例では、手元資金700万円のうち300万円を繰り上げ返済に充てた直後に契約者が亡くなった場合、残った手元資金は400万円だけですが、繰り上げしなければ団信によってローン残高は全額カバーされ、手元に700万円残せたはずです。このように、繰り上げ返済を急ぐことで団信の恩恵を減らしてしまう点も「しないほうがいい」と言われる理由の一つです。
以上のような考え方から、繰り上げ返済は「必ずしも最善とは限らない」という見方があります。ただし、これらはあくまで一般論です。実際には各家庭の経済状況やライフプランによって判断が異なります。次章から、繰り上げ返済の具体的なメリット・デメリットを確認しつつ、どんな場合に控えた方がよいかを詳しく見ていきましょう。
繰り上げ返済のメリット|返済総額が減る・完済が早まる

利息軽減の効果
住宅ローンを繰り上げ返済する最大のメリットは、将来支払うはずだった利息を減らせることです。繰り上げによって返済元本が減る分、以降の利息計算の対象額も減少します。特に期間短縮型では、返済期間そのものを短縮するため利息軽減効果が大きく、トータルの返済総額を大幅に圧縮できます。
例えば、残高3,000万円・金利1.5%・残期間30年のローンで100万円を繰り上げ返済した場合、期間短縮型なら約1年4か月(16か月)も完済時期が早まり、約59万円の利息を節約できる試算があります。
一方、返済額軽減型では毎月の支払額が減るものの完済時期は変わらず、同じ条件で利息軽減効果は約24万円にとどまります。このように、繰り上げ返済は方法によって効果に差はありますが、総支払利息を減らし返済総額を減少させる点は大きなメリットです。
また、繰り上げ返済によって完済までの期間が短縮されることも重要です。住宅ローンという長期の借金を予定より早く返し終えることで、将来の金利上昇リスクや支出負担が軽減されます。家計に占める住宅ローン返済の割合(返済比率)が下がれば、浮いた分を他の資金ニーズに回す余裕も生まれるでしょう。つまり繰り上げ返済は、利息の節約だけでなくライフプラン上の選択肢を増やす効果も持つのです。
精神的な安心感も大きい
住宅ローンの繰り上げ返済には、金銭面だけでなく心理的なメリットもあります。借金である住宅ローンの残高が減り、完済までの期間が短くなることで、将来に向けた不安が和らぐ人も多いでしょう。「ローンを早く終わらせた」という事実は大きな安心感につながります。特に定年までに住宅ローンを完済しておきたいと考える方にとって、繰り上げ返済は老後の生活設計を安定させる心の支えとなります。
また、返済額軽減型で繰り上げ返済を行い毎月の支出を減らすことも、家計管理上の安心材料です。月々の住宅ローン返済額が小さくなれば、毎月の可処分所得に余裕が生まれます。教育費や生活費が増える時期でも住宅ローン負担が軽減されていれば、心理的なプレッシャーも少なくて済むでしょう。「ローンが減る」「家計にゆとりができる」という実感は、数字には表しにくいものの繰り上げ返済の大きなメリットと言えます。
もっとも、精神的な安心感を得るために無理をして繰り上げ返済をしてしまうと、かえって不安材料を増やす場合もあります。次章では、繰り上げ返済によるデメリットや注意点について確認していきましょう。
繰り上げ返済のデメリット|資金繰りや機会損失に注意
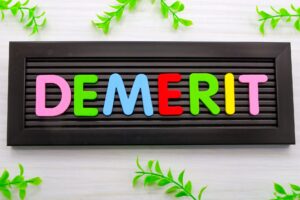
手元資金が減って不測の出費に対応できない
繰り上げ返済を行う際に最も注意すべきは、手元資金が大きく減少してしまうことです。ローン残高を減らすためとはいえ、預貯金から多額の資金を一度に取り崩すと、その後の生活資金に余裕がなくなる恐れがあります。繰り上げ返済後に急な病気やケガ、リストラ、災害などでまとまった出費が必要になっても、一度返済に充当したお金は取り戻せません。結果として、緊急時に借入れや高金利のカードローンに頼らざるを得なくなれば本末転倒です。
特に小さなお子さんがいる家庭や、将来的に転職・独立の予定がある方は、万一に備えて一定の預貯金を手元に残しておくことが大切です。繰り上げ返済をする場合でも、生活防衛資金(緊急予備資金)として病気・失業などに対応できる蓄えはしっかり確保しておきましょう。例えば「少なくとも生活費◯か月分」は残す、といった基準を設けるのも有効です。不測の出費に備える余裕資金を残さずに繰り上げ返済をしてしまうと、家計の安全網がなくなり非常にリスキーだという点を覚えておきましょう。
金利が低い場合、効果が薄い可能性も
繰り上げ返済の主目的は将来の利息支払いを減らすことですが、その効果はローン金利の水準に大きく左右されます。2025年6月現在、住宅ローン金利は変動型で0.6~0.9%程度となっており、2025年1月の日銀利上げの影響で若干上昇していますが、依然として低水準を維持しています。
金利が低いローンでは元々利息の負担が小さいため、繰り上げ返済で削減できる利息額も当然ながらそれほど多くないのです。
もちろん、投資には元本割れのリスクが伴い確実な利回りではない点に留意が必要です。しかし「住宅ローンの金利が十分低い場合、繰り上げ返済の効果は限定的」であることは意識しておくべきでしょう。繰り上げ返済によるメリットが薄いと判断できる場合は、無理に実行せず手元資金を他の資金計画に活かす選択肢も検討すべきです。
繰り上げ返済をしないほうがいいケースとは?

では、どのような場合に繰り上げ返済を控えた方がよいのでしょうか。代表的なケースをいくつか紹介します。以下に当てはまる場合は、繰り上げ返済のメリットよりデメリットや損失の方が大きくなる可能性があるため、慎重に判断しましょう。
住宅ローン控除を受けている期間中
住宅ローンを借りてから一定期間、年末残高の0.7%を所得税から差し引ける住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けている間は、基本的に繰り上げ返済を急ぐ必要はありません。
2025年最新の制度では、控除期間は新築住宅で最大13年、中古住宅は10年、控除率は年末ローン残高の0.7%とされています。また、省エネ基準を満たさない住宅は2025年から控除対象外となるため、注意が必要です。
繰り上げ返済を行うとローン残高が減り、それに伴い毎年の控除額も減少します。特に、借入金利が控除率の0.7%よりも低い、あるいは同程度である場合、控除によって得られる節税効果の方が、繰り上げによる利息軽減よりも上回るケースもあります。
さらに、期間短縮型の繰り上げ返済で返済期間が10年未満になると控除が打ち切られるため、制度の恩恵を十分に受けるには慎重な判断が必要です。控除期間中は無理に返済を急がず、終了後にまとめて繰り上げを行うなど、計画的な対応が求められます。
投資や教育費など、他に優先度の高い資金ニーズがあるとき
余裕資金がある場合でも、それを住宅ローンの繰り上げ返済に充てるより優先度の高い用途があるなら、繰り上げ返済は後回しにした方がよいでしょう。代表的なものが資産運用(投資)と将来の大口支出です。
まず、資産運用については前述の通り、ローン金利より高い利回りが期待できるなら繰り上げ返済より投資に回した方が資金効率が良くなります。例えば、iDeCoやNISAなどの非課税制度を活用した長期投資、または社内預金や社債購入など確実な利回りが得られる手段がある場合、それらを優先することで将来の資産形成に繋がります。
「繰り上げ返済をしない」という選択は、言い換えれば「借金を残したまま手元資金を運用に回す」ことですが、超低金利下では合理的な戦略となり得ます。ただし運用にはリスクもあるため、余裕資金の一部だけ投資に充て、残りで繰り上げ返済をするなどバランスを取ることも検討しましょう。
次に、子どもの教育資金やマイホームのリフォーム資金、ご両親の介護費用など将来の大きな支出が見込まれる場合です。このような状況で無理に繰り上げ返済を行って貯蓄が減ってしまうと、教育費を工面するために新たに教育ローンを借りる羽目になりかねません。それでは低金利の住宅ローンを減らした意味が薄れてしまいます。
したがって、教育費など他の目的に充当すべき資金があるときは繰り上げ返済を優先しない方が賢明です。まずは目的ごとに必要額を見積もり、確保できた余裕資金の範囲内で繰り上げ返済するようにしましょう。
変動金利のまま余剰資金を使い切るリスクがあるとき
現在変動金利型の住宅ローンを利用している場合も、繰り上げ返済のやり方には慎重さが求められます。変動金利は将来的に金利が上昇するリスクがあるためです。
変動金利のリスク管理制度としては、「5年ルール」(金利が上がっても5年間は返済額据え置き)や「125%ルール」(返済額の見直し時、前回返済額の125%が上限)などがありますが、それでも長期的な金利上昇による影響は避けられません。さらに、返済額を超えて利息が増加した場合には未払利息が発生し、最終返済時に一括請求されるリスクもあります。
実際、2025年1月には利上げが実施され、今後も段階的な利上げが予想されています。手元資金をすべて繰り上げ返済に使い切ると、将来的な返済額増加に対応できなくなるおそれがあります。
そのため、変動金利型のローン利用者は「分散繰り上げ返済」(余裕ができたときに少しずつ返済)や、一定の貯蓄を常に残すといった戦略で、金利変動に柔軟に対応できる体制を整えておくことが重要です。
繰り上げ返済と投資のバランスをどう考える?

「金利」と「期待利回り」で判断する考え方
住宅ローンの繰り上げ返済をするべきか、手元資金で投資をするべきか悩んだときは、ローン金利と投資の期待利回りを比較して判断するのが一つの目安になります。基本的な考え方はシンプルで、「期待できる投資利回りがローン金利を上回るなら投資有利、下回るなら繰り上げ返済有利」というものです。以下の表に例を示します。
| 住宅ローン金利 | 資産運用の期待利回り | 判断の目安(有利な選択肢) |
| 1.0% | 0.5% | 繰り上げ返済の方が有利になりやすい(利回り < 金利) |
| 1.0% | 1.0% | 大差ない(安全性重視なら繰り上げ、運用益重視なら投資) |
| 1.0% | 3.0% | 資産運用の方が有利になりやすい(利回り > 金利) |
例えば借入金利が年1%の場合、手元資金で年3%の運用利回りが見込める商品があれば、繰り上げ返済よりも投資に回した方がリターンは大きくなります。逆に安全な定期預金などで年0.5%程度しか増やせないなら、ローン返済に充てて年1%分の利息を節約した方が有利です。
判断が微妙な場合、リスクの有無も考慮しましょう。繰り上げ返済による利息軽減は確実な「節約」であり元本割れの心配はありません。一方、投資の利回りは不確実で、市場変動によってはマイナスになる可能性もあります。したがって「期待利回り≒ローン金利」のケースでは、確実性を重視するなら繰り上げ返済、リスクを取ってでも利益を狙いたいなら投資、といった判断になるでしょう。
また、投資で得た利益には20%前後の税金がかかる点にも留意が必要です(NISA口座等を除く)。住宅ローンの繰り上げ返済で節約できた利息分は非課税の「利益」と同じです。こうした税負担も踏まえると、ローン金利と投資利回りが同程度の場合は、実質的に繰り上げ返済の方が有利になることもあります。
総合的には、ローン金利との差が十分に開いているか(投資利回りが圧倒的に高いか、低いか)が判断のポイントです。
住宅ローン返済と資産形成を両立させるための視点
繰り上げ返済と資産運用は二者択一ではなく、両立させることも可能です。むしろ、多くの家庭にとっては「ローンもできるだけ早く返したいが、将来のための貯蓄・投資もしたい」というのが本音でしょう。そこで重要になるのがバランス感覚です。以下の視点を持つことで、住宅ローン返済と資産形成を両立させやすくなります。
家計全体の配分を決める
毎月やボーナス時の余剰資金について、「○割は繰り上げ返済用、○割は貯蓄・投資用」というようにあらかじめ配分ルールを決めておく方法があります。例えば余裕資金の50%は繰り上げ返済、残り50%は教育資金や運用に回す、といった具合です。こうすることで、偏りなく借金圧縮と資産形成の両方を進められます。
ライフイベントの優先順位を意識
資金ニーズには優先順位があります。直近数年以内に予定されている支出(教育・車購入・住宅リフォームなど)は最優先で備え、次に老後資金など長期の資産形成、その上で余れば繰り上げ返済、と段階づける考え方です。一生の中で必要となるお金のスケジュールを描き、ローン返済とのバランスを検討しましょう。
定期的にシミュレーション
ローン残高や金利、資産運用の利回りは時間と共に変化します。年に一度など定期的に、自分の住宅ローン繰り上げ返済による利息軽減効果と、資産運用の運用益予測を比較シミュレーションしてみることをおすすめします。状況が変われば戦略も柔軟に見直すことで、常に合理的な判断ができます。
要は、住宅ローンも資産形成もバランスよくという発想です。繰り上げ返済だけに注力して手元資金を使い切ってしまうと、その後の資産形成のチャンスを逃したり不測の事態に弱くなったりします。一方で、運用ばかり優先してローンを放置すれば、借金が減らず金利負担が続いてしまいます。
どちらか極端に偏るのではなく、「負債圧縮」と「資産拡大」を両輪で進めていくことが、長期的な家計の安定と成長につながるのです。
分散投資という選択肢|“貯める力”を失わないために

手元資金をすべて繰り上げに使わない戦略
繰り上げ返済を考える際には、手元資金を全てローン返済に充ててしまわないという戦略も重要です。これは前述した資金のバランス管理と通じる考え方ですが、特に強調したいポイントでもあります。
仮に手元の預金をすべて繰り上げ返済に回してしまうと、一時的に負債は減りますが、その後の「貯める力」を損ないかねません。貯める力とは、収入から計画的に貯蓄・投資を行って資産を形成していく力のことです。繰り上げ返済により預金残高がゼロに近くなると、心理的な余裕も失われ、せっかく身につきかけていた貯蓄習慣が途切れてしまう恐れがあります。
そうならないためにも、分散投資という選択肢を取り入れてみましょう。例えば、「ボーナスが出たら半分は繰り上げ返済、半分は投資信託の積立に回す」といった具合に、資金の使い道を分散させるのです。こうすることで、ローン返済による債務圧縮と、資産運用による資産拡大を同時に進められます。手元資金を一度にローンに注ぎ込まない分、残高はゆるやかにしか減りませんが、その代わり手元に残したお金が新たなお金を生む可能性が生まれます。
また、繰り上げ返済を少額ずつ複数回に分けて行うのも一つの戦略です。一度に大金を投入しないことで、手元資金の枯渇を防ぎつつ確実にローン残高を減らせます。近年はネット銀行を中心に繰り上げ返済手数料が無料の金融機関も増えており、少額から気軽に繰り上げ返済できる環境が整っています。「手元資金をゼロにしない」ことを常に意識して、繰り上げ返済と資産形成を賢く両立させましょう。
ローン返済中でも実践できる守りの資産運用
住宅ローン返済中だからといって、「投資は完済してから」と考える必要はありません。むしろローン返済中から少しずつでも資産運用を始めることで、時間を味方につけた資産形成が可能になります。ただし、ローンを抱えている間の運用では、リスクを抑えた「守りの資産運用」を心がけることが大切です。
具体的には、元本割れのリスクが低く比較的安定したリターンが期待できる商品を選ぶと良いでしょう。たとえば、日本国債や個人向け国債、預金保険で保護される範囲内の定期預金、高信用格付けの社債などは堅実な選択肢です。最近では投資信託による積立もポピュラーですが、株式100%のアクティブファンド等は値動きが大きいため、ローン返済中はより分散されたインデックスファンドや債券主体の安定型ファンドを選ぶなど工夫すると良いでしょう。
もう一つ注目したいのが、後述する融資型クラウドファンディングや不動産投資型クラウドファンディングといった、新しい形態の投資商品です。これらは比較的低リスクで年利数%程度のリターンを狙える商品も多く、価格変動を常に気にする必要がないため、本業や家事で忙しい人でも取り組みやすいという特徴があります。まさに「守りながら増やす」運用に向いていると言えるでしょう。
ローン返済中に投資を始めておけば、完済する頃には運用益や配当金が家計を助ける柱に成長している可能性もあります。重要なのは、無理のない範囲で早めに着手することです。例えば毎月1万円を積立投資に回す程度でも、10年続ければ元本だけで120万円、運用益次第ではそれ以上の資産が築けます。これは将来、繰り上げ返済する原資に回すこともできますし、教育費や老後資金に充てることもできます。
ローン返済と並行して資産運用を行うことは決して矛盾する行為ではなく、長期的な家計の安定に資する攻守バランスの取れた戦略なのです。
融資型クラウドファンディングも一案に
低リスクで安定収益を狙いたい人に向いている
資産運用の選択肢の一つとして、最近注目を集めているのが融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)です。融資型クラウドファンディングとは、インターネット上のプラットフォームを通じて多数の投資家から資金を集め、事業者などへの貸付けを行う金融商品です。投資家は貸付先から支払われる利息収入を分配金として受け取ります。株式のように価格変動による損益を狙うのではなく、あらかじめ決まった利率の利息収入を得ることを目的とするため、比較的安定した運用が可能です。
融資型クラウドファンディングの利回りは案件にもよりますが、年利4~8%程度が一般的で、預金や国債より高く、株式投資ほど極端に高リスクでもない中間的な水準と言えます。
融資型クラウドファンディングは、「ローリスクで堅実にお金を増やしたい」「毎月の安定収入が欲しい」といった方に向いている投資手法です。住宅ローンの金利が1%以下であれば、年5%前後の利回りが期待できるこうした商品に投資することで、ローン金利以上のリターンを得つつ手元資金を増やすことができます。繰り上げ返済で元本を減らす代わりに、融資型クラウドファンディングで得た利息収入をローン返済の足しにする、といった組み合わせも可能です。
もちろん投資である以上元本割れリスクはゼロではありませんが、複数の案件に分散投資することでリスクを下げる工夫もできます。
このように、融資型クラウドファンディングは住宅ローン繰り上げ返済と併用しやすい新たな資産運用の選択肢と言えます。「繰り上げ返済する代わりに、そのお金を運用してローン金利以上の収益を狙う」というアプローチを具体的に実践できる手段の一つとして、頭に入れておくと良いでしょう。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
繰り上げ返済前にチェックしたい3つのポイント

繰り上げ返済を実行するか検討するとき、以下のポイントを事前に確認しておくと失敗が少なくなります。家計の安全性を確保し、後悔のない判断をするためのチェックリストとして活用してください。
家計のキャッシュフローに余裕はあるか?
繰り上げ返済するお金は、本来であれば将来の家計支出や貯蓄に回せたはずのお金です。そこでまず、自分の家庭のキャッシュフローを見直し、無理なく捻出できる金額かどうかを確認しましょう。毎月の収支がギリギリの中で貯めたお金を繰り上げ返済に充ててしまうと、急な収入減や出費増に対応できなくなります。
また、ボーナス頼みの家計の場合も注意が必要です。ボーナスで繰り上げ返済するとしても、万一ボーナスカットがあっても生活が成り立つか検証しておきましょう。
具体的には、繰り上げ返済後の残高や毎月返済額が家計収支に与える影響を試算してみてください。家計簿をつけている方は、繰り上げ返済後も数ヶ月分の生活費が残るか、収支が赤字転落しないかなどをチェックします。金融機関のウェブサイト等で提供されている「繰り上げ返済シミュレーション」を使えば、返済額軽減型・期間短縮型それぞれの場合で月々の負担や完済予定時期がどう変わるか簡単に計算できます。
繰り上げ返済はあくまで余裕資金で行うものです。家計の安全運転に支障が出ない範囲の金額か?を冷静に判断しましょう。
将来の大きな支出を見越しているか?
繰り上げ返済をして手元資金を減らしてしまった結果、後で必要な資金が足りなくなる事態は避けねばなりません。お子さんの入学や留学、マイカーやマイホームの買い替え、実家のリフォーム、ご自身の転職や起業資金など、ライフイベントに伴うまとまった支出予定をリストアップしましょう。その上で、それらに充てる資金を確保できているかを確認します。
例えば「子どもが高校から大学を卒業するまでに○百万円必要」「5年後に自宅の屋根修繕で○十万円かかる見込み」といった具合に、できるだけ具体的に見積もります。その費用分を差し引いた上でなお余裕資金があるなら、その範囲内で繰り上げ返済するのは問題ありません。しかし見積もり額ギリギリ、もしくは不足している状態で繰り上げ返済に資金を回すのは危険です。
将来の大きな支出については、目的別に貯蓄口座を分けて管理するのも有効です。「教育資金用」「老後資金用」などと分けて積み立てておけば、それ以外の余剰資金が明確になります。繰り上げ返済はそうした目的別貯蓄を優先した“残りで行う”くらいの位置づけで丁度よいでしょう。繰り上げ返済を実行する前に、5年後・10年後を見据えた資金計画をもう一度点検してみてください。
繰り上げに使う資金の使い道は本当にこれでベストか?
手元にまとまったお金があると、「とりあえず繰り上げ返済しよう」と考えがちですが、その判断がベストか今一度考えてみましょう。例えば、他に高金利の借入れ(カードローンや自動車ローンなど)があるなら、まずはそちらの繰上返済や完済を優先すべきです。住宅ローンより金利が高い負債を残したまま低金利の住宅ローンを繰り上げても、利息負担全体を減らす効果は小さいからです。
また、住宅ローン減税の適用期間中であれば前述のように慌てて繰り上げずに満額控除を受け切る方が得策かもしれません。一方で、投資や預金など他の用途に回した場合との損益比較も重要です。「この100万円で繰り上げ返済すれば利息○万円節約。でも投資に回せば○万円増やせるかも」とシミュレーションしてみて、納得感のある使い道を選びましょう。
さらに、繰り上げ返済に使うお金の原資も確認しておきます。例えば退職金や相続財産など、一度限りの特別な収入を充てる場合、それをそっくりローン返済に回してしまってよいのか考えます。退職金は老後資金にも充てねばならず、全額返済に充てると老後資金不足に陥る恐れがあります。相続財産も、今後の自分の資産運用次第ではより増やして活用できるかもしれません。
いずれにせよ、「このお金を繰り上げ返済に充てるのがベストだ」と心から思えるかが判断基準です。もし少しでも迷いがあるなら、一部だけ返済し残りは手元に残す、もしくはしばらく普通預金でキープしておくという選択肢も検討しましょう。繰り上げ返済は一度実行すると取り消せないため、その資金の使途に悔いがないか事前にしっかり検討することが大切です。
よくある質問(FAQ)|繰り上げ返済で失敗しないために
最後によく寄せられる質問とその回答をまとめました。繰り上げ返済に関する素朴な疑問や不安を解消し、失敗のない判断につなげてください。
Q1. 年収に対していくらまで繰り上げ返済しても大丈夫?
一概には言えませんが、「年間手取り収入の○割まで」などと決めつけるより、生活防衛資金を確保した上で余裕資金の範囲で行うことが大前提です。
年収に対していくらまで…という発想よりも、繰り上げ返済後に半年~1年分程度の生活費が残るかを基準に考えてみましょう。例えば年収600万円(手取り約480万円)の方なら、最低でも240万円以上の貯蓄を残した上で、それを超える分について繰り上げ返済に回す、というイメージです。
また、年間返済額(元利合計)が年収の25%以内に収まるのが望ましいとされています。繰り上げ返済をすることで年間返済額が極端に減り、その分生活費に回せるなら有効ですが、逆に繰り上げ返済のしすぎで貯蓄が減り家計が逼迫しては本末転倒です。
重要なのは、繰り上げ返済に回しても生活が不安定化しない額に留めることです。人によって家計の固定費や将来必要な貯蓄額は異なるため、自分の家計に即した余裕資金を見極めてください。
Q. 繰り上げは一度やると後戻りできない?
基本的にはその通りです。一度繰り上げ返済で返してしまったお金を、再び手元に戻すことはできません。
繰り上げ返済とは銀行との契約上「返済義務のあるお金を前倒しで返した」ことになるため、後から「やっぱり返済した分を返してほしい」とはいきません。もし繰り上げ返済後に資金不足に陥れば、新たに別のローンを組むか、カードローンなどで借り入れするしかなくなります。
ただし例外的に、「借入限度額内で自由に借り入れ・返済を繰り返せるローン」(例えば一部のフリーローンや銀行の預金連動型住宅ローンなど)であれば、余裕があるときに返済しておき、必要になったらまた借りるといった柔軟な運用が可能な商品もあります。しかし一般的な住宅ローンではそうした仕組みはなく、一度繰り上げ返済したら二度と元には戻せないと考えてください。したがって、繰り上げ返済する金額やタイミングは慎重に見極める必要があります。
もし「繰り上げしたいがお金が戻せないのが不安」という場合は、少額から分割して繰り上げ返済する方法もあります。例えば100万円まとめて一度に返すのではなく、20万円ずつ5回に分けて様子を見ながら返す、といったやり方です。そうすれば途中で「これ以上返すと手元資金が心許ない」と感じた時点でストップできます。繰り上げ返済は後戻りできないという性質を踏まえ、無理のない計画を立てましょう。
Q3. 家族の教育費や介護費とどう両立する?
教育費や介護費など、家族のために確保しておくべき資金とは最優先で両立させる必要があります。繰り上げ返済を優先するあまり、これら必要資金の準備がおろそかになっては本末転倒です。両立のコツは、資金を目的別に分けて管理することです。例えば毎月の貯蓄を「教育資金用口座」「介護・医療費用口座」「繰り上げ返済・投資用口座」といった具合に分割します。まず教育費口座に目標額を積み立て、次に介護費用に一定額を積み立て、それでも余裕があれば繰り上げ返済用に回す、という優先順位で考えます。
また、公的制度や保険も活用しましょう。教育費であれば奨学金制度や教育ローンの金利優遇措置、介護費であれば高額介護サービス費の補助など、使えるものは使って自己負担を減らす工夫も大切です。その上でどうしても足りない場合は、繰り上げ返済を見送りその分の資金を教育・介護費用に充当する決断も必要になります。
要は、家族の人生に関わる重要なお金(教育・介護・治療費など)は住宅ローン返済より優先度が高いと認識することです。繰り上げ返済はそれらをクリアした後の余裕資金で行う、と位置づければ自然と両立できます。人生のステージに応じてお金の使い道は変わりますから、無理なく両立できる範囲で繰り上げ返済を活用しましょう。
まとめ|繰り上げ返済は「全額正解」ではなく「選択肢の1つ」
住宅ローンの繰り上げ返済について、その基本からメリット・デメリット、活用しない方がよいケースや資産運用とのバランスまで詳しく見てきました。結論として言えるのは、繰り上げ返済は万能の正解ではないということです。たしかに繰り上げ返済には利息軽減や完済前倒しといった魅力がありますが、それが常に家計にとってベストとは限りません。低金利下では効果が薄くなり、住宅ローン減税期間中はかえって損になるケースもあります。また、繰り上げに充てたお金が将来必要になれば後悔しかねません。
繰り上げ返済は、あくまで家計改善・資産形成の選択肢の一つです。全額を繰り上げるかゼロかの二択ではなく、部分的に実行したり時期をずらしたり、あるいは他の運用に振り向けたりと柔軟に考えることが重要です。住宅ローンという長期の負債と上手に付き合いながら、手元資金の使い方を最適化していくことが賢い家計運営と言えるでしょう。
大切なのは、繰り上げ返済に固執しすぎず総合的な視野で判断することです。家計のキャッシュフロー、ライフイベント、ローン減税や金利動向、資産運用の機会、こうした要素を踏まえつつ、「自分にとって最もメリットの大きいお金の使い方は何か」を考えてください。その答えが繰り上げ返済なら実行すれば良いし、他に優先すべきものがあれば無理に繰り上げる必要はありません。
住宅ローンとの長い付き合いの中で、繰り上げ返済する・しないは何度も判断の機会が訪れるでしょう。その際、本記事で紹介したポイントや事例が判断材料としてお役に立てば幸いです。正解は一家ごとに異なります。ぜひ自分たちのベストな選択を見つけ、将来の安心と豊かさにつなげてください。
参考元
・国税庁「繰上返済等をした場合の償還期間」
・全国銀行協会 「金利が高いほど繰上返済を優先させる方が効果的」
・住宅金融支援機構「住宅ローン利用者調査(2024年)」