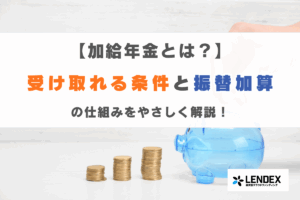老後資金はいくら必要なのか?「2,000万円問題」に象徴されるように、年金だけでは生活が不安という声は少なくありません。実際、総務省の家計調査や金融庁レポートでも、老後は毎月数万円の赤字が発生するケースが一般的とされています。
本記事では、「最低限の生活」と「ゆとりある生活」でどれほど必要額が変わるのかをはじめ、単身世帯と夫婦世帯それぞれの生活費のシミュレーション、医療・介護・葬儀といった特別支出、老後資金を準備する方法まで、最新データをもとに徹底解説します。iDeCoや新NISAを活用した資産形成術、老後破綻を防ぐコツなども紹介していますので、「自分にはいくら必要か?」を具体的に把握したい方はぜひ参考にしてください。
老後資金はいくら必要?結論は「最低でも2,000万円以上」

公的年金だけでは足りない理由
平均的な老後生活では、公的年金収入だけでは月々の支出を賄えず、赤字になるのが現状です。
総務省「2024年家計調査」によると、65歳以上夫婦のみ無職世帯の可処分所得は約22.2万円であるのに対し、消費支出は約25.7万円にのぼり、毎月約3.4万円の不足が生じています。この不足分は、預貯金や退職金などの蓄えから補填する必要があり、多くの家庭で「年金だけでは生活費が足りない」という状況に直面しています。
実際、生命保険文化センターの調査でも、老後の生活資金の手段として「預貯金」を挙げる人は約7割(71.8%)にのぼっており、年金以外の蓄えに頼らざるを得ない現実が浮き彫りになっています。
最低限の生活とゆとりある生活の違いとは?
老後の生活費は、どのような生活水準を望むかで大きく変わります。
生命保険文化センターの調査によると、夫婦2人で必要と考える最低限の老後日常生活費は平均で月約23.2万円です。一方、旅行や趣味など「ゆとり」のために必要な上乗せ額は平均14.8万円で、ゆとりある老後生活費の平均は合計で約37.9万円にもなります。
つまり最低限の質素な生活と、余暇や娯楽も楽しめるゆとりある生活では、月々約15万円もの支出差があるということです。老後にどこまでゆとりを求めるかによって必要資金は大きく異なるため、自分が望む生活水準を具体的に描くことが老後資金計画の第一歩となります。
老後資金の内訳は?生活費・医療・介護費などを分解

住居費・食費・通信費など基本生活費の目安
老後の基本的な生活費の内訳をみると、支出の多くを占めるのは食費です。
総務省の家計調査(2022年)によれば、65歳以上夫婦無職世帯の平均消費支出約23.7万円のうち、食費が約6.8万円と最も高く、次いで交通・通信費が約2.9万円、光熱・水道費が約2.3万円という順になっています。そのほか、住居費は平均約1.6万円(持ち家か賃貸かや地域によって差があります)、家具・日用品が約1万円、医療費が約1.6万円、娯楽費が約2.1万円、雑費・交際費が約4.9万円といった内訳です。
合計すると夫婦で月約26〜27万円程度が老後の基本生活費の目安となります。なお、自宅を所有していない場合は家賃分がさらに必要になる点に注意が必要です。
医療・介護の備えも重要|平均支出のデータから検証
日常の医療費は高齢夫婦世帯で月平均約1.6万円と、さほど大きくありません。しかし高齢になるほど病気や介護が必要になるリスクは高まり、医療・介護費は老後資金計画の要注意ポイントです。
大きな病気で長期入院すれば、高額療養費制度で自己負担に上限はあるものの、差額ベッド代や先進医療など保険適用外の費用はまとまった出費になり得ます。また、要介護状態になれば介護サービスの自己負担や介護用品代が継続的にかかります。
生命保険文化センターの調査では、介護に要した費用(自己負担分)の月平均は約8.3万円で、手すり設置や住宅改造、介護ベッド購入など一時的な費用も平均74万円にのぼると報告されています。こうした平均データに表れない医療・介護の負担も見据え、保険の活用や予備資金の確保といった備えが重要です。
【2025年最新情報】
2025年8月から高額療養費制度の上限額が引き上げられます。年収370万円~770万円の区分では現在より8,100円引き上げられ、8万8,200円程度になる予定です。
【シミュレーション】老後資金の必要額|おひとりさま・夫婦でどう変わる?

単身世帯|年金だけでは足りる?
一人暮らしの高齢者(おひとりさま)の場合、必要な生活費は夫婦世帯の半分よりやや多い程度と言われます。
総務省データでも、65歳以上の単身無職世帯の平均消費支出は月約14.9万円で、夫婦世帯(約25.7万円)のほぼ6割ほどの水準です。収入面では、公的年金の支給額は一人分のみのため平均実収入は約12.1万円/月とさらに少なく、毎月約2.8万円の赤字が発生しています。
このように年金だけでは単身世帯でも足りないのが実態で、貯蓄の取り崩しや継続就労などで不足を補う必要があります。特に一人暮らしは支えてくれる家族がいないため、病気や介護が必要になった時の負担や孤立リスクも踏まえ、夫婦以上に手厚い備えや公的サービスの活用を考えておくことが大切です。
夫婦世帯|二人分の支出と年金の差額とは?
夫婦2人世帯の場合、公的年金は夫婦2人分となるため収入合計は単身より多く、平均で実収入約25.2万円/月(年金など社会保障給付が大部分)です。しかし支出も2人分となるため増加し、平均消費支出は約25.7万円/月に及びます。結果として月平均約3.4万円の赤字が生じており、やはり年金収入だけでは賄い切れていません。
夫婦世帯では生活費をシェアできるメリットがある一方、同時期に医療費や介護費が重なるリスクもあり、必要な蓄えは単身より大きくなりがちです。
また、金融庁の報告書で話題となった「老後30年間で約2,000万円不足する」という試算は、この夫婦無職世帯モデル(夫65歳・妻60歳で30年間生活)のケースを指しています。実際に必要な額は各家庭の年金受給額や支出水準によって異なりますが、夫婦でゆとりある老後を過ごすには少なくとも数千万円規模の蓄えが必要になると考えておきましょう。
生活費以外にかかる「特別支出」にも注意

医療・介護・住宅リフォーム・葬儀費用など
老後には日々の生活費以外にも、突発的または高額な特別支出が発生し得ます。代表的なものとして医療費があります。重い病気で長期入院する場合、高額療養費制度で自己負担の上限はあるものの、食事代や差額ベッド代、先進医療費など保険のきかない費用はまとまった負担となります。
次に介護費も想定以上に高額になり得ます。介護状態が長引けば自己負担額は累積し、加えて住宅のバリアフリー改修費用(手すり設置や段差解消など)も必要になるでしょう。
また、自宅の老朽化に伴う住宅リフォーム費(屋根や配管の修繕など)も高齢期に一度はまとまった出費となるかもしれません。
そして避けられない葬儀費用も、全国平均で約119万円と見積もられています。このような特別支出は発生時期や金額を正確に予測しづらいため、日々の生活費とは別に予備資金や保険で備えておくことが重要になります。
余裕を持った老後資金設計のための備え方
特別支出への備えとしては、まず余裕を持った資金計画を立てることが肝心です。最低限の生活費だけでなく、上記のような臨時費用も見込んで老後必要額を試算しましょう。
例えば、介護や医療のための緊急予備資金として数百万円を別枠で確保しておく、葬儀代については終身保険や共済で用意しておく、といった方法があります。また、公的介護保険サービスで賄えない部分に備える民間の介護保険や、医療保険への加入・継続も検討に値します。
さらに、住宅については年齢とともに住み替えやリフォームが必要になる可能性があります。バリアフリー住宅やサービス付き高齢者向け住宅等への転居も視野に、早めに情報収集しておくと安心です。漠然と「老後資金は○○万円あれば大丈夫」と決めつけず、余裕を持ってシミュレーションし、早めに具体策を講じておくことが、老後資金不足の不安を和らげる最善策と言えるでしょう。
老後資金はどう準備する?貯金だけで大丈夫?
インフレリスクを考えると現金だけでは心もとない
老後資金の準備を「とりあえず貯金だけしておけば安心」と考えるのは危険です。なぜなら、インフレ(物価上昇)によるお金の価値目減りリスクがあるためです。
日本でも近年は物価が上昇傾向にあり、2022年度の消費者物価指数は前年度比3.0%上昇し、41年ぶりの高い伸び率となりました。仮に物価が毎年2〜3%ずつ上がっていけば、10年後には預金の実質価値が2〜3割減ってしまう計算です。
一方で銀行預金金利はごく低水準(普通預金は年0.001%程度)であり、預けているだけではお金は増えません。したがって老後に備えるには、現金だけでなく資産の一部を運用に回して増やす・守る発想が欠かせません。
老後資金を増やす・守るための基本的な考え方
老後資金を運用する際の基本は、無理のない範囲で長期・分散投資を行うことです。現役時代からコツコツ積み立てて資産形成し、定年後も可能であれば資産の一部は運用を続けていくと、インフレや長寿リスクに対抗できます。
ただし、高齢になってから生活資金までリスク資産に投じてしまうのは危険です。老後資金の「守り」と「攻め」のバランスを意識し、日々の生活費や緊急予備資金は元本が目減りしない安全な資産(預貯金や個人向け国債など)で確保しつつ、余裕資金はインフレに負けない資産(投資信託や株式、外貨建て資産、不動産など)に振り向けるといった考え方が有効です。
また、為替や株価の変動リスクを抑えるため、投資対象は国内外の複数の資産クラスに分け、特定の資産に集中しないようにしましょう。リスクを取りすぎず、かといって一切取らないわけでもない、適度なリスク管理で資産を守り育てることが大切です。
「2,000万円問題」は本当?実態と誤解を解説

金融庁レポートの読み解き方
2019年に金融庁の報告書が発端となった「老後資金2,000万円問題」は、「老後30年間で約2,000万円資金が不足する」という試算結果が独り歩きし、大きな話題となりました。この数字はあくまでモデルケース上の試算である点に注意が必要です。
報告書では、夫65歳・妻60歳の無職夫婦世帯が夫95歳・妻90歳まで健在という前提で、毎月の支出が収入(年金)を約5万5千円上回ると仮定しました。この場合、不足額は20年で約1,300万円、30年で約2,000万円に達する計算になります。重要なのは、報告書中にも「不足額は各々の収入・支出の状況やライフスタイル等によって大きく異なる」と明記されていることです。
つまり、2,000万円という数字は平均的な前提に基づく一例であって、すべての人に当てはまるわけではありません。金融庁レポートを正しく読み解くには、自分自身の状況に引き直して考えることが大切です。
自分に必要な金額は「生活水準」で決まる
老後に本当に必要な資金額は、人それぞれの生活水準や家計状況によって異なります。
例えば、持ち家で車もなく質素な暮らしをする場合と、趣味や旅行を積極的に楽しむ暮らしをする場合では、必要となる毎月の生活費は大きく違います。前述のように「ゆとりある老後」を望むなら夫婦で月約37.9万円、最低限なら約23.2万円と、その差は歴然です。この差額(月約15万円)を埋めるには30年で5,400万円にもなる計算であり、2,000万円どころでは足りません。
一方、自宅を含め十分な資産や企業年金・退職金がある方は、公的年金と合わせて2,000万円もの蓄えがなくとも暮らしていけるでしょう。要するに「老後資金〇〇万円」という画一的な数字にとらわれず、自分の生活設計に基づいて必要額を算出することが重要なのです。
老後資金をどう準備する?貯金・年金・投資の役割
iDeCo・NISAなどの制度も活用しよう
効率的に老後資金を準備するためには、税制優遇制度を積極的に活用することが欠かせません。代表的なのがiDeCo(個人型確定拠出年金)とNISA(少額投資非課税制度)です。
iDeCoは掛金が全額所得控除となり、運用益も非課税なので節税しながら老後資金を積み立てられる制度です(加入可能年齢は65歳まで)。一方、NISAは投資の利益が非課税になる制度で、2024年から非課税枠が拡充され生涯にわたり利用可能です。
これらの制度を使えば、本来税金で目減りする分まで老後資金に回せるため、長期的には大きな差が生まれます。国の優遇策はフルに活用し、賢く資産形成・運用を行いましょう。
インフレ対策としての資産分散も視野に
老後資金準備において、資産の分散(ポートフォリオ分散)はリスク管理の面から極めて重要です。現役から定年にかけての数十年の間には、インフレによる物価変動や景気の波が避けられません。預貯金だけに偏った資産構成ではインフレに弱いため、資産の一部は株式・債券・投資信託、不動産、金など、値動きの異なる資産に分散投資しておくことが得策です。
例えば、日本株だけでなく海外株式や外貨資産も組み入れることで、国内経済の停滞リスクに備えることができます。将来の予測が難しいからこそ、資産を一つのかごに盛らないことで資産全体の目減りを防ぎ、安定した運用を目指せます。
分散投資は手間に感じるかもしれませんが、バランス型ファンドやロボアドバイザーなどを活用すれば比較的容易に実践できます。大切なのは、老後資金を長期視点で守り育てるために、複数の資産クラスに目を向けておくことです。
【分散投資】老後資金を守りながら増やすための考え方

「すべて貯金」ではインフレに弱い
老後資金を安全に確保したいからと、全財産を現預金で持っておくのは一見堅実ですが、前述のとおりインフレに非常に弱い欠点があります。預金だけではお金が増えないばかりか、物価上昇によって実質的な購買力が毎年目減りしていくため、長寿化するほどその影響は大きくなります。
現役時代に築いた大切な資産を守りながら増やすには、「すべて貯金」ではなく一部を投資に振り向ける柔軟さが求められます。もちろん貯金も重要で、暴落時にも引き出せる生活防衛資金として確保しつつ、インフレヘッジや資産寿命の延伸策として分散投資を取り入れるのが賢明です。
少額から分散投資を始める方法
分散投資というと難しく感じるかもしれませんが、少額からコツコツ始めることがポイントです。例えば、毎月1万円をインデックスファンドに積み立てるところからスタートすれば、大きな負担なく資産運用に慣れることができます。昨今はネット証券や銀行で積立NISAを利用すれば、100円からでも投資信託を積み立てられ、手軽に国際分散投資が可能です。
投資初心者の方は、全世界株式やバランス型の投資信託など、一つで幅広く分散された商品を選ぶとよいでしょう。重要なのは、時間分散(積立による購入時期の分散)と資産分散を組み合わせ、リスクを平準化しながら運用を続けることです。少額でも長期間続ければ複利効果で大きな資産形成につながります。
まずは無理のない範囲で始め、定期的にポートフォリオを確認・調整しながら、自分なりの資産運用スタイルを築いていきましょう。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
老後資金のためにやっておきたいこと5選

家計の見直しと無理のない積立設定
老後資金準備の第一歩は、現役時代の家計の見直しです。毎月の支出を洗い出し、無駄遣いや過剰な固定費がないか点検しましょう。
例えば使っていないサブスクの解約や保険料の適正化、通信プランの見直しなどで、月々数千〜数万円の節約ができるケースもあります。浮いたお金はそのまま老後資金の積立に回します。大切なのは、無理のない積立金額を設定することです。張り切って高額を設定しすぎると家計が苦しくなり、結局続かなくなる恐れがあります。
少額でも長期間続けることが大きな資産形成につながるため、日々の生活に支障の出ない範囲で自動積立を設定し、給与天引きや口座引落で強制的に貯蓄・運用に回す仕組みを作りましょう。
iDeCo・NISAなどの税制優遇制度の活用
前述のとおり、iDeCoやNISAといった税制優遇制度は老後資金づくりに有効です。
iDeCoは老後資金専用の年金制度で、掛金が全額所得控除になるため大きな節税効果があります。さらに運用益も非課税で再投資され、効率的に資産を増やせます。ただし60歳までは原則引き出せないため、余裕資金でコツコツ積み立てる位置付けとしましょう。
一方NISA(2024年から新制度)は、投資の売却益・配当が非課税になる制度で、非課税投資枠が恒久化・拡大されました。現役時代はもちろんリタイア後に資産運用する場合でも、新NISAなら年齢制限なく利用でき、運用益に税金がかからない分取り崩しペースを緩やかにできます。
これらの制度を積極的に活用し、「税金に取られないお金」を最大化する工夫をしましょう。
退職金や年金の受け取り方の確認
会社員の方なら退職金(退職一時金や企業年金)が老後資金の大きな柱となります。退職金の受け取り方については事前に会社の制度を確認し、一時金でまとめて受け取るか年金形式で分割受取にするか、選択肢があれば比較検討しましょう。一時金で受け取った場合は退職所得控除の範囲内で非課税になりますが、同時に大金を運用する責任も生じます。
一方、企業年金として分割受取すれば、公的年金の上乗せとして毎月定額を得られ、長生きしても安心です。また、公的年金の繰下げ受給も検討に値します。年金の受給開始を遅らせると月額が増え、例えば70歳まで繰下げれば年金が42%増額されます。健康で働けるうちは受給を遅らせ、後年の年金額を増やす戦略も有効でしょう。
自分がもらえる年金額(ねんきん定期便で確認)や退職金制度の詳細を把握した上で、最適な受取方法とタイミングを選ぶことが大切です。
相続・保険の整理
老後を迎える前に、相続や加入中の保険を整理しておきましょう。遺言書の作成や資産の棚卸しなど相続対策を進め、特に不動産を所有している場合は生前贈与や売却等も検討して将来のトラブルを防ぎます。
また、子供の独立後も高額な死亡保障を続けていないか見直し、必要以上の保険料負担を減らしましょう。その分を老後の医療・介護保障に充てたり、保険金の受取人確認やデジタル遺産の整理など身辺の準備も少しずつ進めておくことが大切です。
生活費のダウンサイジングも視野に
最後に、生活費のダウンサイジング(縮小)も老後資金対策として視野に入れておきましょう。定年後は収入が年金中心になり現役時代より減るため、支出面をスリム化する努力が求められます。
例えば、持ち家が大きすぎる場合は売却してコンパクトな住まいに移り住む、地方や郊外の生活コストの低い地域へ転居する、車を手放して公共交通やシェアサービスを利用する等、大きな固定費を削減できる余地があります。また、日々の生活でも外食や娯楽費を抑え、シンプルな暮らしを心がけることで支出は大きく変わります。
無論、我慢ばかりでは充実した老後とは言えませんが、メリハリをつけて優先度の低い出費を減らす工夫は必要です。ダウンサイジングは早めに着手するほど効果が高く、リタイア後の家計を安定させる土台となります。将来の収支シミュレーションをもとに、どの時点でどの支出を見直すか計画しておきましょう。
よくある質問(FAQ)|老後資金にまつわる不安と疑問
Q1. 公的年金だけで老後は暮らせる?
平均的には難しいのが現状です。前述のとおり、夫婦世帯でも単身世帯でも年金収入だけでは毎月数万円の赤字が生じています。
例えば夫婦無職世帯の可処分所得は月約22.2万円ですが、消費支出は約25.7万円あるため3万円以上不足しています。公的年金だけで暮らすには、食費や住居費など基本的な生活費を収入内に抑える大幅な節約が必要です。
持ち家でローンがなく地方で自給的な生活をするなど特別な条件が揃えば年金範囲内で暮らせる場合もありますが、医療費や住宅修繕といった臨時出費も考えると現実には貯蓄の取り崩しや私的年金による補填がほぼ不可欠です。
Q2. 老後破綻しやすい人の特徴は?
老後破産に陥りやすい人にはいくつか共通点があります。主な特徴として以下の3点が挙げられます。
- 支出を管理できていない: 現役時代から家計簿を付けず出費が把握できていない人は、収入減の老後に気付かぬうちにお金が底をつきやすくなります。
- 固定費が高額である: 住宅ローンや家賃、保険料など毎月必ず出る支出が多いと、年金生活に入っても支払いに追われ家計を圧迫しがちです。
- 貯蓄額が少ない: 現役中に十分な貯蓄を準備できていないと、老後に赤字や思いがけない出費が重なると資金が底を突くリスクが高まります。
これらに当てはまる場合は要注意です。家計管理の徹底や固定費の見直し、計画的な貯蓄、老後資金のシミュレーションなどを早めに行い、破綻を防ぐ対策を講じましょう。
Q3. 70歳以降でも運用はすべき?
70歳を過ぎても適度な資産運用は有効です。人生100年時代、70代からでも20年以上生活が続く可能性があり、その間に物価が上がれば資産を遊ばせておくだけでは目減りしてしまいます。
新しいNISA制度は年齢制限がなく70代でも利用できるため、預金だけでなく一部資産は投資で運用し、インフレや長生きに備えることが賢明です。ただし、若い頃のように高リスクの商品に手を出すのは禁物で、特に高齢者を狙う投資詐欺に注意する必要があります。
あくまで元本を大きく減らさない範囲で、安定的な利息や配当を得る運用にとどめるのがポイントです。例えば、日本国債や安定配当株などで運用益を得れば、年金収入を補完する助けになります。
まとめ|老後資金は「早く・具体的に・分散で」備えるのが正解
老後資金に明確な正解はありません。現役のうちから自分の生活設計に沿って必要額を試算し、公的年金で不足する分をどう補うか計画しましょう。その際貯金だけに頼らず資産運用や税制優遇制度を活用して分散備えするのが重要です。
老後資金の不安は誰にでもありますが、「早く・具体的に・分散して」対策を講じておけば、安心して豊かな老後を過ごせるでしょう。今日から一歩ずつ備えを始めましょう。
参考元
-
総務省『家計調査報告(貯蓄・負債編)』
-
厚生労働省『令和5年簡易生命表の概況』
-
厚生労働省『iDeCoとNISA』
-
金融庁『ライフプランシミュレーター』
-
金融庁『「高齢社会における資産形成・管理」報告書』(2019年)