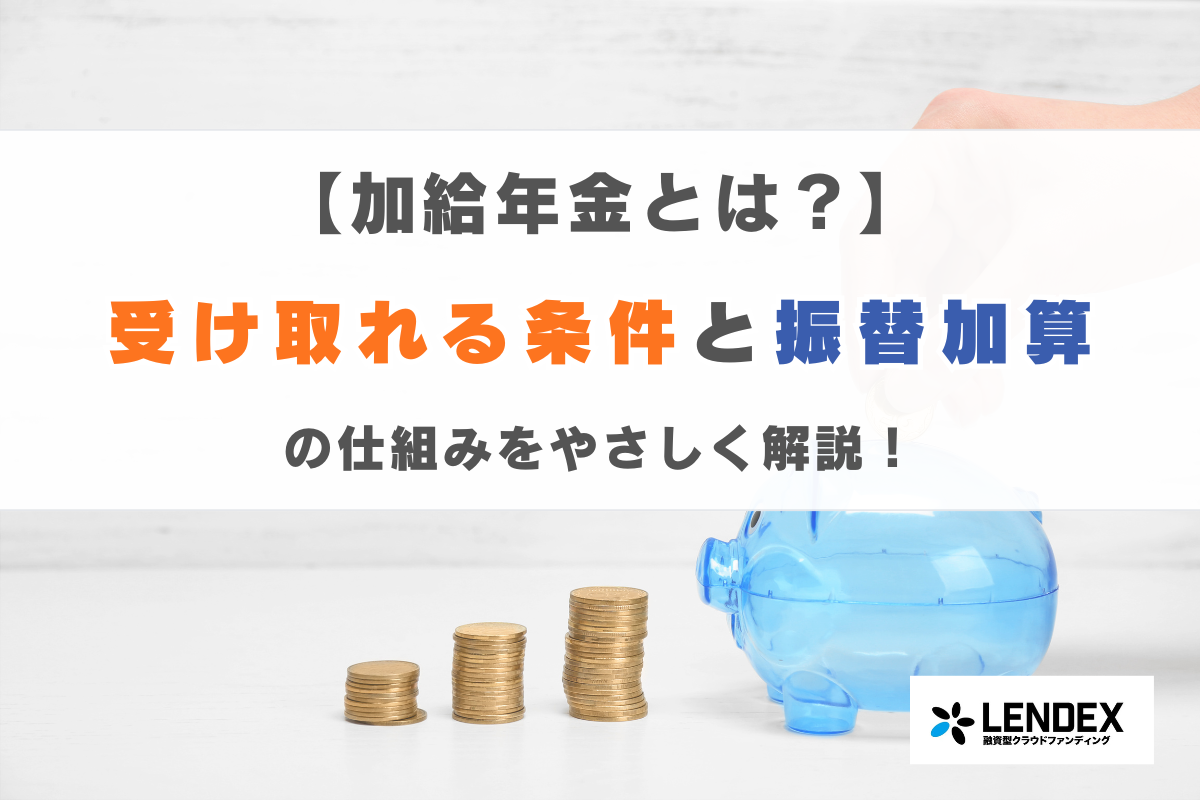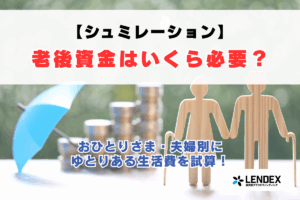老後に受け取る公的年金には、実は「上乗せ」される給付があることをご存じでしょうか?その代表的な制度が加給年金です。これは、一定の条件を満たす厚生年金受給者に対し、配偶者や子どもがいる場合に支給される特別な年金で、「年金版の家族手当」とも言われています。
とはいえ、制度の存在自体を知らなかったり、「自分は対象なのに申請していなかった」といった理由で、本来もらえるはずの加給年金を受け取れないケースも少なくありません。さらに、配偶者が65歳になると加給年金が終了し、その後は振替加算という別の仕組みに切り替わる点も、正しく理解しておく必要があります。
本記事では、「加給年金とは何か」をやさしく解説しながら、もらえる条件と年金額、振替加算との違いや注意点、申請方法まで徹底的に解説します。特に、これから老後資金を考える方々にとって、制度を正しく活用し、将来の備えと向き合うヒントとしてぜひご活用ください。
加給年金とは?制度の基本と対象者をわかりやすく解説
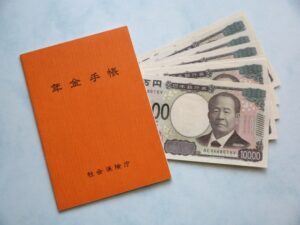
加給年金は「上乗せ支給」の年金制度
加給年金とは、公的年金における家族手当のような上乗せ支給の制度です。厚生年金や共済年金の老齢年金に、一定の条件で扶養家族分の金額が加算されます。
たとえば、会社員や公務員が65歳で老齢厚生年金を受け取る際に、配偶者や子どもを養っている場合、その年金額に上乗せされる仕組みです。簡単に言えば、年金版の扶養手当であり、生計を支える家族がいる年金受給者を経済的に支援する目的で作られました。
支給対象は配偶者や子どもがいる厚生年金受給者
加給年金を受け取れるのは、厚生年金(または共済年金)の老齢年金受給者で、その方に生計を維持されている配偶者または子どもがいる場合です。具体的には、厚生年金保険の加入期間が20年以上(240か月以上)ある人が65歳になったとき、65歳未満の配偶者や18歳未満の子(障害等級1・2級の子は20歳未満)がいれば加給年金が加算されます。
逆に言えば、単身者や国民年金のみの人には対象外の制度です(※老齢基礎年金だけでは加給年金は付きません)。また、配偶者や子がいても収入が一定以上(年収約850万円以上)の場合は扶養とは認められず支給されません。支給対象となるには、家族の年齢・収入条件も満たす必要がある点に注意しましょう。
受給条件と金額はいくら?必要な年金加入期間や注意点

加給年金のもらえる条件と年金額について、具体的な数値や注意点を解説します。
厚生年金20年以上が基本条件
加給年金の受給には、厚生年金の被保険者期間20年以上という基本条件があります。たとえば定年まで会社勤めをした方であれば多くが該当しますが、転職や自営業期間があり厚生年金加入がトータル20年に満たない場合は、たとえ国民年金と合算して年金受給資格があっても加給年金はもらえません。
この要件は共済年金(公務員等)の加入期間にも適用され、2015年以降は共済も厚生年金に統合されたため、公務員の方も同様です。受給者本人の年金加入歴が20年に達しているか、事前にねんきん定期便や「ねんきんネット」で確認しておくと良いでしょう。
また、配偶者とは65歳時点で婚姻関係にあることが必要で、仮に65歳以降に結婚してもその配偶者は加給年金の対象にはなりません。
配偶者・子ども別の支給額と停止リスク
実際にもらえる加給年金額は、扶養している家族の種別によって決まっています。
2025年度(令和7年4月以降)の年額で見ると、配偶者および第1子・第2子については各239,300円、第3子以降は各79,800円と定められています。配偶者に対しては、受給者本人の生年月日に応じ特別加算額が上乗せされる仕組みがあり、合計で415,900円(年額)程度になるケースもあります。これらは年金額改定により毎年度見直されます。
一方、加給年金はずっと支給されるわけではありません。扶養していた配偶者が65歳に達したとき(自身の老齢年金が受給できるとき)や、子が18歳を過ぎたときには加給年金の加算は停止します。また配偶者が自分自身の厚生年金を受給できる状態になった場合や障害年金を受け取っている間も、その配偶者に対する加給年金は支給停止となります。
条件に該当したら年金事務所への届出が必要であり、届け出を怠ると後で返金を求められることもあります。加給年金を受け取っている間は、配偶者や子の状況変化に注意し、必要な手続きを行いましょう。
振替加算との違いは?同時にもらえるの?
振替加算は「代替的支給制度」
振替加算とは、加給年金が終了した後に代わって支給される年金加算制度です。具体的には、夫(または妻)の老齢厚生年金に加給年金が付いていたケースで、配偶者が65歳になり加給年金が打ち切られる際、その配偶者本人の老齢基礎年金に振り替えて加算が行われるものです。いわば加給年金のバトンタッチであり、受給権者(夫)の年金から配偶者の年金へと加算の支給先が移る仕組みです。
振替加算は配偶者の終身年金に上乗せされるため、金額は加給年金より少ないものの一生涯受け取れる利点があります。ただし、誰でももらえるわけではなく、対象となる配偶者の生年月日や年金加入歴に応じて段階的に金額が減少し、昭和41年4月2日以降生まれの配偶者には振替加算がゼロ(支給なし)となるよう設計されています。これは、世代が下るほど配偶者自身の年金加入期間が長くなり、自力年金が充実していると想定されるためです。
加給年金との切り替えタイミングに注意
振替加算と加給年金は同時には受け取れません。
基本的な流れとして、年金受給者(夫など)の加給年金は配偶者が65歳になるまで支給され、配偶者65歳到達とともに加給年金が終了し、その翌月分から配偶者本人の老齢基礎年金に振替加算が加わります。したがって、切り替わるタイミングを把握しておくことが大切です。
例えば夫が65歳になる時点で妻が60歳なら、夫に最長5年間加給年金が支給され、妻が65歳になると夫の加給年金が止まり妻の基礎年金に振替加算が付く流れです。一方、妻が夫より年上で夫65歳時に妻も65歳以上であれば、夫は最初から加給年金を受け取れませんが、その代わり妻の基礎年金に65歳から振替加算が支給されます。
振替加算は配偶者自身の年金請求手続きを行えば自動的に計算・支給されますが、夫が年金を繰下げ受給する場合などイレギュラーなケースでは別途届け出が必要となる場合もあります。配偶者が振替加算を受け取れる時期になったら、年金事務所等に確認し漏れなく受給手続きを行いましょう。
加給年金が支給されない・打ち切られる主なケース

収入・配偶者の年齢・離婚などで対象外に
前述の条件に該当しない場合、加給年金は支給されません。代表的なケースとして、配偶者や子の収入が高い場合(年収850万円以上)は扶養家族とみなされず対象外です。
また、配偶者自身が厚生年金に20年以上加入しており自分の老齢厚生年金を受け取れる権利がある場合も、加給年金の対象にはなりません(※2022年4月の制度改正により、権利があるだけでも加給年金は支給停止となりました)。
さらに、夫婦の年齢差がないケースも該当します。受給者が65歳になる時点で配偶者が65歳以上であれば、そもそも加給年金は付きません(その配偶者は振替加算の対象となります)。
離婚や死亡により扶養家族でなくなった場合も、当然ながら支給は打ち切られます。子どもについても、18歳到達年度末を過ぎた場合や結婚等で扶養状況から外れた場合は対象から除かれます。
また稀なケースですが、老齢厚生年金受給者が年金の繰下げ請求を行っている期間は老齢年金自体を受け取っていないため、加給年金も支給されません。このように、加給年金は条件を満たしている間だけの一時的な加算であり、いずれは終了する可能性がある点を念頭に置きましょう。
「もらえると思っていたのにもらえなかった」事例も
制度に対する理解不足から「自分は加給年金をもらえるはず」と思い込んでいたのに実際は受給できなかったというケースも見受けられます。
例えば、夫が20年以上厚生年金に加入し65歳から年金生活に入ったものの、妻も同い年で既に老齢基礎年金を受給していたため加給年金は付かなかったという例があります。この場合、夫は配偶者加給を得られませんが、妻の年金に振替加算が支給されています。
別の例では、妻が長年フルタイムで働き厚生年金加入期間が20年超あったため、夫は妻を扶養配偶者とはできず加給年金を受け取れなかったというケースもあります。また、加給年金の存在自体を知らず申請しなかったため本来もらえたはずの期間の加給年金を逃してしまった例もあります。
このように、「知らなかった」「勘違いしていた」で損をしないよう、該当しそうな場合は事前に制度を確認しておくことが重要です。特に近年は共働き世帯が増え配偶者が自身の年金権を持つケースが多いため、加給年金を受け取れる夫婦自体が減少傾向にあります。実際、厚労省の統計によると老齢厚生年金の受給者のうち配偶者加給年金を受けている人は約半数以下であり、制度改正も進む中、もらえる条件は徐々に限られてきています。
申請方法と手続きで気をつけたいポイント

申請は自動ではない!年金事務所での手続き方法
加給年金は申請しなければ受け取れません。老齢厚生年金の裁定請求(年金請求手続き)を行う際に、配偶者や子の有無を申告し所定の書類を提出する必要があります。
具体的には、年金請求書に扶養対象となる配偶者・子の情報を記入し、戸籍謄本や住民票、所得証明など生計維持関係を証明する書類を添付します。初回年金請求時に忘れず手続きすれば、その後の年金支給に加給年金分が自動的に上乗せされます。
ただし、後から配偶者を得た(結婚した)場合や子どもが生まれた場合など、年金受給開始後に新たに権利が生じたときは改めて届出が必要です。また、振替加算についても条件によっては別途届出が求められるケースがあります。手続きは居住地の年金事務所や年金相談センターで行えます。
不安な場合は、最寄りの年金ダイヤルや年金事務所の窓口に事前に相談し、必要書類や手順の説明を受けると良いでしょう。
事後申請だと支給が遅れることもある
本来もらえるはずの加給年金も、申請が遅れると受給開始が遅れたり一部受け取れなくなる恐れがあります。公的年金の時効は5年とされており、過去の未請求分を遡って受け取れるのは最大5年分までです。
例えば本来65歳からもらえたのに70歳で申請した場合、65~69歳の分は時効により受け取れない可能性があります。したがって、条件を満たしたらできるだけ早く請求手続きを行うことが大切です。「年金は自動でもらえる」と思い込んでいると、加給年金は支給されませんので注意しましょう。
また、年金受給者本人が老齢厚生年金の受給開始を繰り下げた場合も、繰下げ期間中の加給年金は支給されず後から埋め合わせることもできません。繰下げ受給で年金額が増えるメリットと、加給年金を放棄するデメリットを比較し、慎重に判断する必要があります(一般的には、生存期間が相当長くならない限り加給年金を受け取った方が有利との試算があります)。
このように、加給年金は請求して初めて受け取れるものです。せっかくの権利を無駄にしないよう、必要な時期に忘れず手続きを行いましょう。
「年金制度だけに頼れない現実」に備える
加給年金や振替加算も“いつまでも確実”ではない
公的年金の給付は、将来に向けて制度変更や縮小の可能性が指摘されています。加給年金についても例外ではなく、実際に2022年以降の制度改正で支給停止要件が拡大されるなど、縮小傾向がみられます。
また、振替加算は前述のとおり若い世代の配偶者には支給されない仕組みになっており、今後加給年金・振替加算を受け取れる人自体が減少していく見込みです。厚生労働省の資料でも「加給年金の支給対象者は年々減少している」旨が示されており、制度の役割が相対的に小さくなってきています。
さらに、日本の少子高齢化が進む中、公的年金全体の財政も厳しさを増しています。年金だけに頼る生活設計はリスクがあると言わざるを得ません。将来的に法律変更で加給年金そのものが廃止されたり支給開始年齢が引き上げられる可能性もゼロではないでしょう。こうした現実を踏まえ、加給年金や振替加算は「もらえたらラッキー」くらいの気持ちで、過度に当てにしすぎないことが大切です。
支給額が生活費のすべてをカバーするとは限らない
たとえ加給年金等を受け取れたとしても、その額だけで老後の生活費を賄えるわけではありません。例えば、配偶者加給年金の年額約40万円は月額にすると3万円強で、夫婦2人の生活費(月22万円程度)の一部を補助するに過ぎません。また、公的年金全体でも平均的な高齢夫婦無職世帯の年金収入(月約21万円)に対し、消費支出は月約26万円と毎月5万円程度の不足が生じているとのデータがあります。
いわゆる「老後資金2000万円問題」で指摘されたように、公的年金だけでは平均的な生活水準でも不足が生じ、長い老後を乗り切るには相応の蓄えや収入源が必要なのが現実です。さらに、物価上昇(インフレ)によって年金の実質的価値が目減りするリスクもあります。公的年金制度には物価スライドやマクロ経済スライドがありますが、必ずしも生活実感に見合うとは限りません。
以上のことから、公的年金+αの備えを持っておくことが安心な老後への鍵と言えるでしょう。
「自分で備える」老後資金づくりの新常識
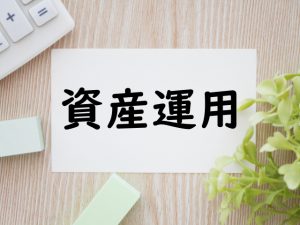
現金貯金だけではインフレ・制度変更に弱い
老後資金を準備する方法として、昔は銀行預金などでコツコツ貯めるのが一般的でした。しかし現在の低金利下では預金だけではお金はほとんど増えません。また、現金のままではインフレに弱いという欠点もあります。物価が毎年2%上がれば、10年で貨幣価値は2割以上目減りします。
超高齢社会の日本では、公的年金や医療・介護制度の見直しもあり得るため、制度に依存しすぎるリスクも大きくなっています。そこで近年は、自助努力で資産形成することが新常識になりつつあります。政府もiDeCo(個人型年金)やNISA(少額投資非課税制度)を拡充し、国民が自ら投資・運用で老後資金を蓄えることを後押ししています。
単に現金を貯め込むだけではなく、資産運用でお金にも働いてもらう発想が大切なのです。ただし、リスクの高い投機ではなく、長期的な視点に立った計画的な運用が求められます。
長期視点で分散・安定型の資産運用も検討を
老後に備える資産運用では、長期的に安定したリターンを目指すことが重要です。株式など成長資産への投資も有効ですが、一極集中は避けましょう。
国内外の株式・債券、不動産、投資信託などに分散投資することでリスクを抑えつつリターンを狙えます。特に定年後は大きな損失を避ける必要がありますから、元本の安全性が高い商品や、値動きの小さい安定型の運用を組み入れると安心です。
具体例としては、債券中心のバランスファンドや、不動産に間接投資できるREIT(不動産投資信託)などが挙げられます。これらは市場を通じて日々価格変動がありますが、配当収入や賃料収入など定期的な収益が期待できる点で年金の補填にもなり得ます。
また、元本保全を重視しつつ利回りを確保したい場合、ソーシャルレンディングや融資型クラウドファンディングなども選択肢に入るでしょう。堅実な運用を心がけ、時間を味方に付けることで、資産形成の効果は大きく高まります。
融資型クラウドファンディングという“守りの投資”
毎月分配・短期運用で老後資金にもフィット
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)は、投資家から集めた資金を企業等への貸付に回し、利息収入を分配する投資形態です。老後資金作りの観点では、定期的な利息収入が得られる点が魅力です。
案件によりますが、多くは運用期間が半年から1年程度と短期で設定されており、資金を長期間拘束されないメリットがあります。さらに融資先からの利息は毎月分配される仕組みが一般的で、年金のように月々の収入を得ることが可能です。これは、定期預金や債券の利払いが半年~年1回であるのに比べ、高頻度でキャッシュフローを受け取れる点でシニア世代にもフィットします。
利回りも比較的高く、案件にもよりますが年率5~10%前後の想定利回りが提示されているものが多いです。一括返済ではなく毎月利息が支払われるため、利益確定のサイクルが短く複利運用もしやすいでしょう。また、融資型クラウドファンディングでは不動産担保付き案件も多く、実物資産で元本を守る工夫がされています。
元本保証ではありませんが、担保評価を専門会社が行うなど透明性・信頼性の高い運用が行われており、過去に貸し倒れや延滞の事例がないサービスも存在します。このように、堅実志向の“守りの投資”として融資型クラウドファンディングは注目されています。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
よくある質問(FAQ)|加給年金・振替加算の不安を解消

Q1. もらえる時期や対象者をどう確認する?
自分が加給年金をもらえるかどうか、いつからもらえるかを確認するには、まず受給資格の条件をチェックしましょう。
具体的には、厚生年金の加入期間が20年以上あるか、そして扶養している配偶者が65歳未満か子どもが18歳未満かがポイントです。これらは年金定期便の加入記録や家族の年齢で概ね判断できます。不安な場合は、最寄りの年金事務所に問い合わせれば、記録を基にシミュレーションして教えてくれます。
また、実際に年金請求を行うときに、日本年金機構から送付される年金決定通知書に加給年金額が記載されますので、そちらで正式に確認できます。受給開始時期は原則として老齢厚生年金の支給開始と同時(65歳到達時)ですが、配偶者や子の状況によってはその後条件を満たした時点で加算が始まる場合もあります。
事前にねんきんネット等で自身の記録を確認し、不明点は専門機関に相談するのが確実です。
Q2. 申請を忘れたらどうなる?自動支給される?
加給年金は申請主義であり、請求手続きをしなければ支給されません。申請を忘れた場合、その間の加給年金は受け取れない可能性があります。
年金は原則として5年を過ぎると時効消滅し、遡って受け取れるのは最大5年分までです。したがって、申請を長期間放置すると、さかのぼっても一部しか受け取れない、あるいは全く受け取れないケースも出てきます。
なお、日本年金機構から自動的に支給されることは基本的にありませんので、必ず自分で請求する必要があります。万一「手続きを失念していた」と気付いたら、一刻も早く年金事務所で相談・手続きを行ってください。
また、配偶者が65歳になる前に請求しないと加給年金そのものが終了してしまう点にも注意が必要です(期間経過後は請求しても受給権が発生しません)。大切な権利を逃さないよう、年金請求時に加給年金の申請も漏れなく行いましょう。
Q3. 振替加算はいつからもらえるの?
振替加算は、加給年金が終了したタイミングから支給が開始されます。具体的には、扶養されていた配偶者が65歳に到達したときが振替加算の支給開始時期です。
例えば、ご主人の年金に加給年金が付いていた奥様の場合、奥様が65歳になるとそれまでご主人に支給されていた加給年金が止まり、代わりに奥様の老齢基礎年金に振替加算が加算されます。支給開始月は、奥様が65歳になった月分(初回受取は原則2か月後の偶数月支給日)となります。
また、ご主人より年上の奥様で、ご主人が65歳時に既に奥様が65歳以上だった場合、ご主人の加給年金は当初からありませんが、奥様の基礎年金に65歳到達時から振替加算が付いています。振替加算の受給にあたって特別な申請は不要で、基礎年金の裁定請求に基づき自動的に計算・支給されます。
ただし、配偶者自身が繰下げ受給を選択した場合は振替加算もその間受け取れませんので注意してください。基本的には配偶者の65歳誕生日以降に年金支給額が増えていれば振替加算が反映されている、と認識すればよいでしょう。
加給年金の確認ポイント|事前にチェックしておくべきこと
配偶者の年齢・年金状況・収入の3要素が重要
加給年金をもらうために事前にチェックしておきたいのは、配偶者に関する3つのポイントです。
配偶者の年齢
受給者が65歳になる時点で配偶者が65歳未満であることが支給条件なので、配偶者が同年齢か年上の場合は当てはまりません。
配偶者の年金加入状況
配偶者自身が長期間厚生年金に加入し老齢厚生年金を受け取れる見込みの場合(特に加入20年以上)は、たとえ年下でも加給年金の対象から外れるか途中で停止となる可能性があります。夫婦共働きでそれぞれ厚生年金に長く加入したケースではこの点に注意が必要です。
配偶者の収入
配偶者に年間850万円以上の収入(給与や事業所得等)がある場合、生計維持関係がないと判断され支給されません。これは子どもについても同様で、アルバイトなどでも一定以上稼いでいる場合は対象から外れる場合があります。
以上の3要素を踏まえ、自分が加給年金の対象になりそうか事前に確認しておきましょう。なお、受給者が会社を定年退職した際に配偶者が60歳未満の場合、その配偶者は第3号被保険者から外れ国民年金第1号被保険者となり、自身で国民年金保険料を納める必要が生じます。この負担も実質的な収入減となるため、年の差夫婦の場合は忘れず織り込んでおきたいポイントです。
対象でも申請しなければもらえないケースも
せっかく条件を満たしていても、申請をしなければ加給年金はもらえません。これは制度の根幹であり、年金事務所が勝手に付けてくれるものではない点に注意が必要です。
実際、「厚生年金に20年以上加入し、妻も65歳未満なのに加給年金が振り込まれない」という相談の多くは、単純に請求手続きをしていなかったことが原因です。また、年金の繰下げ受給を選択したために本来受け取れたはずの加給年金を逃してしまうケースもあります。繰下げによる増額メリットだけに注目しがちですが、加給年金相当額の逸失も考慮しなければなりません。
加給年金の対象である場合、年金請求時に必ず加給年金の申請項目を記入しましょう。万一請求漏れがあっても、5年以内であれば遡及して受け取ることは可能です。ただしその場合も、自ら気づいて手続きを取らない限り支給されません。
配偶者や子を扶養している年金受給者は、「自分は対象か?」「申請は済んでいるか?」という点を念入りにチェックすることが大切です。特に高齢になると手続き漏れが起こりやすいため、家族とも情報を共有し、必要な届出を確実に行うよう心がけましょう。
まとめ|制度の活用と“自分の備え”を並行することが安心につながる

加給年金や振替加算は、公的年金制度の中で家族のいる高齢者を支える有難い仕組みです。該当する方は、忘れず申請して制度を最大限活用するとよいでしょう。
ただし、これらはあくまで補助的な給付であり、老後の生活設計は公的年金だけに委ねるべきではないというのも本稿で述べた通りです。公的制度から支給されるものはきちんと受け取りつつ、自助努力による資金準備も並行して行う、この二本柱が老後の安心につながります。
幸い、昨今はiDeCoやNISAのように個人の資産形成を後押しする制度や、少額から参加できる資産運用のサービス(今回紹介した融資型クラウドファンディング等)も充実してきました。定年までの時間や夫婦の状況に応じて、計画的に貯蓄と運用を組み合わせ、自分自身の“備え”を築いておきましょう。
公的年金制度を正しく理解し上手に利用すること、そして不足分を補えるだけの蓄えを持つこと、この両面に目を向けて準備を進めることが、将来への安心に直結します。老後資金に関する不安を一つずつ解消し、ゆとりあるセカンドライフを実現しましょう。
参考元
- 日本年金機構:「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省:「年金制度における子に係る加算等について」
- 金融庁:「高齢社会における資産形成・管理」