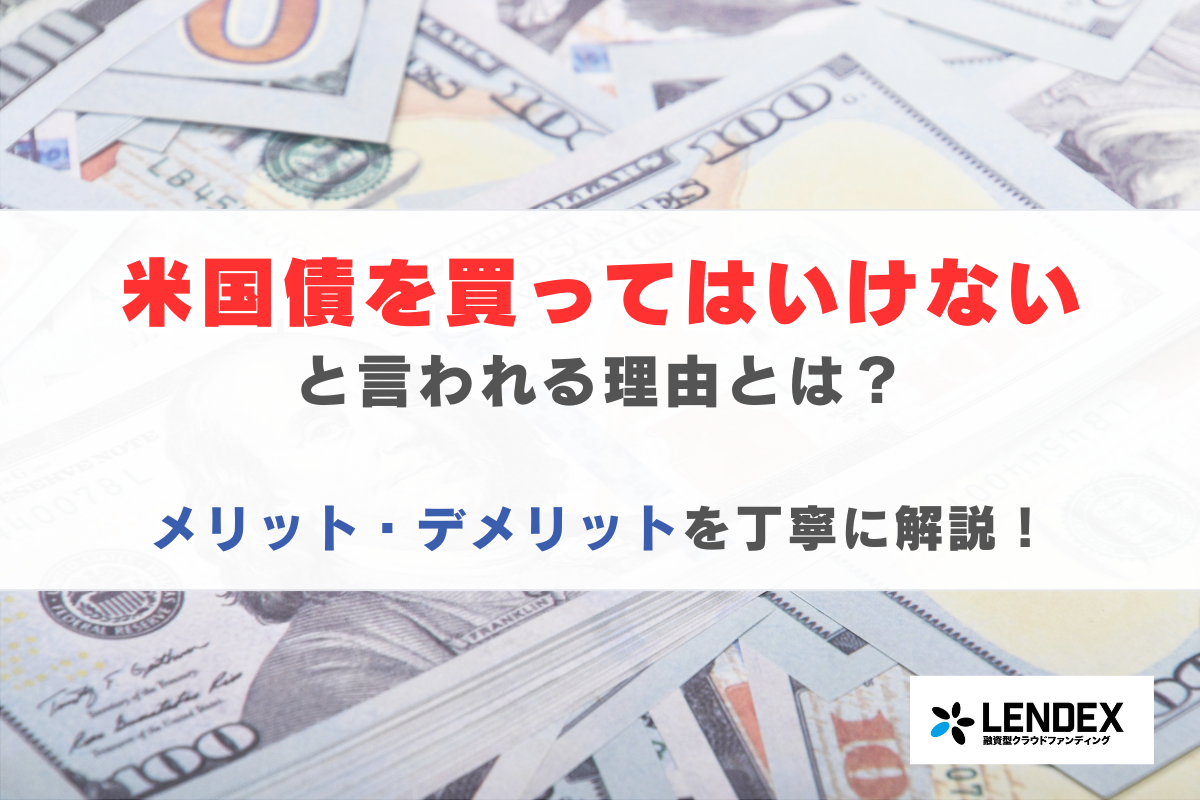はじめに、近年「米国債は買ってはいけない」と耳にすることがあります。米国の国債(米国債)は安全な投資先として知られる一方で、なぜそのように言われるのでしょうか。
本記事では、米国債を買ってはいけないと言われる理由と考えられるポイントを詳しく解説し、あわせて米国債のメリットや活用法についても紹介します。初心者にもわかりやすく仕組みを説明しつつ、メリット・デメリットを踏まえた上手な投資判断の参考になる情報をお届けします。
米国債とは?まずは仕組みと特徴をおさらい
米国債の基本情報|満期・利回り・格付けなど
米国債とは、アメリカの政府が発行する債券のことで、日本の国債にあたるものです。米国財務省が発行し、アメリカ政府が元本と利子の支払いを保証しているため、「ほぼリスクのない安全な資産」として世界中の投資家から人気を集めています。
現在、格付け会社のムーディーズ・S&P・フィッチの3社すべてが、アメリカの格付けを最上位から1段階引き下げています。しかし、それでも依然として高い評価(ムーディーズAa1、S&P AA+、フィッチAA+)を維持しており、信用力の高い資産であることに変わりはありません。
米国債には、短期(4週間~1年未満)・中期(2~10年)・長期(20~30年)など、満期の異なるさまざまな種類があります。また、物価の動きに連動して利息が変わる「物価連動債(TIPS)」などもあります。通常の米国債では、半年ごとに利息を受け取り、満期時に元本が返ってくる仕組みです。つまり、米国債を買うということは、アメリカ政府にお金を貸すことを意味します。そして、決められた期間の間は利息が受け取れ、満期になれば元本が戻るという点が特徴です。
なお、株式も企業が資金調達のために発行するという点では似ていますが、株には満期がなく、利息の支払いも義務ではありません。この点が債券との大きな違いです。
実際の利回りを見てみると、2023年7月の米国債(10年)の利回りは年利3.889%でした。これは、同時期の日本国債(10年)の利回り0.460%と比べて、かなり高い水準です。さらに、米国債の利回りはその後も上昇を続け、2025年6月には約4.5%前後まで上昇しています。一方で、アメリカのインフレ率は落ち着き、2025年4月時点で年率2.3%まで下がっています。これにより、FRB(米連邦準備制度理事会)が近く利下げに動くとの見方が強まっており、市場では2025年9月の利下げ開始を約75%の確率で織り込んでいます。
このように、米国債は利回りの高さに加えて、世界経済や金利動向に大きく関わる重要な投資対象といえます。
どこで買える?購入方法と最低投資額
米国債への投資は、日本国内の証券会社や銀行を通じて行うことができます。多くのネット証券や大手金融機関で米国債の取り扱いがあり、口座を開設して外貨建て債券として購入します。購入時には米ドルで決済するのが一般的ですが、円貨決済に対応している業者もあります。
最低投資額は証券会社によって異なりますが、1口あたり最低100ドル程度(約1.5万円)から購入可能な場合もあり、比較的小額から始められます。もちろん数千ドル単位のまとまった購入も可能です。
購入方法としては、新規発行の米国債を購入する方法(入札に参加するか金融機関経由で買い付け)と、既発行の米国債を市場で購入する方法があります。初心者の場合は証券会社のウェブサイト上で売買できる既発債の購入が手軽でしょう。買付時には為替手数料や売買手数料がかかる場合があるため、事前にコストも確認しておくことが大切です。なお、米国債は通常特定口座や一般口座で保有し、利子や償還時の差益には日本の税制が適用されます。
「米国債を買ってはいけない」と言われる5つの理由

為替リスクが高い|円安・円高で利益が変動
米国債への投資でまず注意すべきは為替リスクです。米国債は米ドル建ての資産であるため、最終的な投資成果はドル円の為替相場に大きく左右されます。たとえば、購入時より円高が進行すると、ドル建てで得た利息や償還金を円に換える際に目減りしてしまう可能性があります。反対に円安が進めば為替差益を得られますが、この為替の変動は予測が難しく、初心者にとって大きな不確実要素となります。
実際、専門家の指摘によれば「外国債券の持つ為替リスクは、債券そのもののリスクより大きく、あまり嬉しいリスクではない」とされています。為替レートの変動によって、米国債の本来の利回り以上の損益変動が生じるためです。特に短期で見れば為替変動の影響が大きく、米国債を買ってはいけないと言われる一因がこの為替リスクの高さにあります。
例えば、同じ5,000米ドルでも、1米ドル=150円と120円の場合では受取額に以下の違いが生じます。
- 1米ドル=150円の場合 5,000米ドル×150円=75万円
- 1米ドル=120円の場合 5,000米ドル×120円=60万円
同じ5,000米ドルでも日本円にすると15万円もの違いになります。購入済みの米国債の償還時期は変更できません。償還時に円高で推移している場合、受取金額が想定よりも少なくなるリスクがある点も理解しておきましょう。
利回りが意外と低い?インフレとの関係
米国債は安全資産とされているため、利回り(金利水準)は相対的に低くなる傾向があります。平時において米国債の利回りは、株式や社債などのリスク資産よりも低めに設定されており、「思ったほど増えない」と感じる投資家もいるでしょう。
特に近年では世界的な低金利環境が長く続いたため、一時期は米国債10年債の利回りが低水準にとどまりましたが、2024年後半以降は4%台後半と比較的高い水準にあります。2025年4月の米CPIは前年比2.3%上昇となり、2021年2月以来、約4年ぶりの低水準まで鈍化しています。
インフレ局面では、名目利回りがプラスでも物価上昇に追いつかなければ、実質利回り(利回り-インフレ率)はマイナスになる可能性があります。これは米国債に限らず、債券投資全般に共通するデメリットですが、特に米国債は安全性ゆえに低利率であるため、インフレには弱い面があります。「米国債は買ってはいけない」と言われる背景には、この利回りの物足りなさも含まれているのです。
売却タイミングに注意|途中売却リスクも
米国債は満期まで保有すれば額面で償還され元本が戻ってきますが、途中で売却する場合には価格変動リスクがあります。債券の価格は市場の金利動向によって日々変動しており、購入後に市場金利が上昇すると、それに伴い保有中の債券価格は下落します。特に購入時のクーポン(金利)が低い債券ほど、金利上昇時の価格下落幅は大きくなります。また満期までの期間が長い債券ほど価格変動リスクは高まります。したがって、米国債を買った後に金利が急上昇すると、売却時に元本割れの損失が出る可能性があります。
一方、市場金利が低下すれば債券価格は上昇するため売却益を得られることもあります。ただしこのような金利変動リスクは投資初心者には読みづらく、長期保有が前提の国債を中途売却すること自体が不利に働くケースも少なくありません。途中換金せざるを得ない状況になったとき、思わぬ損失が発生するリスクがある点は注意が必要です。米国債は原則安全な商品ではありますが、売却タイミングを誤ると損をする可能性があることを覚えておきましょう。
税制メリットが日本債より劣るケース
米国債の利子や為替差益に対する課税面でも、日本の債券より不利になる場合があります。日本国債の利子は国内課税のみで完結しますが、米国債の利子には外国税が源泉徴収されるケースがあり、さらに国内でも課税対象となります。例えば米国外の投資家が米国債の利息を受け取る際、条約等で非課税の場合もありますが、国や条件によっては一部税金が差し引かれることがあります。その上で、日本国内でも20.315%(所得税+住民税)の課税が行われ、確定申告で外国税額控除の手続きをしなければ二重課税となる恐れがあります。
また、国内の税制優遇を活用しづらい点もデメリットです。NISA(少額投資非課税制度)では個別の債券は対象外となっており(※主に株式と投資信託が対象)、米国債の利息を非課税で受け取る仕組みは基本的にありません。日本国債であれば個人向け国債など途中換金時のペナルティ免除や一定のマル優制度(少額貯蓄非課税)対象がある場合もありますが、米国債には適用されません。このように税制面でのメリットが相対的に少ないことも、「米国債は買ってはいけない」と言われる理由の一つです。
景気動向や国際情勢に左右されやすい
米国債の利回りや為替レートは、米国の景気動向や国際情勢によって大きく影響を受けます。たとえば米国の景気が加熱してインフレ懸念が高まれば、FRB(米連邦準備制度理事会)は政策金利を引き上げ、それに伴って米国債利回りも上昇(債券価格は下落)しやすくなります。逆に景気後退局面では金利引き下げ観測から利回りが低下するでしょう。こうした景気サイクルによる金利変動に加え、世界的なイベント(金融危機、地政学リスク、米国の財政問題など)も米国債の価値に影響を及ぼします。
実際、米国債は「世界で最も安全な資産」として高い需要がありますが、その安全性ゆえに利回りが低く抑えられるプレミアムが存在すると指摘されています。しかし、信用不安が高まる事態(例:米国の信用格付け引き下げや政府の債務上限問題)が起きると安全資産としての魅力が低下し、利回りが急上昇する(価格が下落する)可能性があります。このように米国債は国際的な経済・政治の状況に敏感であり、必ずしも常に安定しているとは限らない点に留意が必要です。
米国債のメリット|買ってもいい人・状況とは?

信用度の高い資産を保有したい人に向いている
ここまでデメリットを中心に述べましたが、米国債には高い信用度と安定性という大きなメリットがあります。米国政府が支払いを保証する米国債は、デフォルト(債務不履行)の確率が極めて低く、安全資産の代表格です。株式のように企業破綻リスクを直接負うこともなく、値動きも株式ほど大きくないため、リスク許容度が低い投資家でも保有しやすい商品と言えます。特に日本国債より金利が高めである分、信用力が高いまま少しでも利回りを確保したい人には米国債は魅力的でしょう。
また、米ドル建て資産を持つことで通貨分散になる点もメリットです。円だけでなく基軸通貨であるドル建ての安全資産を持つことは、資産全体のリスク分散につながります。日本国内に資産を偏らせたくない、国際分散投資をしたいという投資家にとって、米国債は有力な選択肢となります。以上より、「絶対に米国債を買ってはいけない」というわけではなく、資産を堅実に守りたい人にはむしろ適した投資対象なのです。
為替を見ながら収益を狙う中上級者向け
米国債は基本的に安定志向の資産ですが、為替変動を味方につけて収益を狙うことも可能です。為替リスクはデメリットにもなりますが、一方で円安が進めば為替差益を享受できるため、為替相場をある程度予測・コントロールできる中上級者にとっては収益機会となります。例えば、日本円が割高(円高)なタイミングで米国債を購入し、その後円安に振れた場合、債券の利息と為替差益の両方を得ることができます。
また、米国債は流動性が高く市場規模も大きいため、市場動向をチェックしながら売買しやすい利点もあります。中上級者であれば、米国債の利回りや米国の金利政策を見ながら、利回りが高い時期に買い、金利低下局面で売却するといった戦略も考えられるでしょう。為替ヘッジ手段(外貨預金や為替予約)を駆使してリスクを抑えつつ運用することも可能です。このように、為替や金利の動きを読み解くスキルがある投資家にとって、米国債は単なる安全資産に留まらず利益機会を提供してくれる存在となります。
米国債に向いていない人の特徴|買わないほうがいいケース

短期で資金を動かしたい人
投資したお金を短期間で使う予定がある場合、米国債への投資は適していません。米国債は基本的に中長期保有を前提とした商品であり、購入後すぐに大きな値上がり益が期待できるものではありません。また前述の通り、中途売却には金利変動リスクが伴うため、短期で売買を繰り返すのは得策ではありません。例えば、半年後や1年後に使う予定のある資金で米国債を買ってしまうと、その時点で金利環境が変わっていれば損失が出る可能性もあります。
短期運用したい資金は、元本割れリスクのない預金や換金性の高い商品で持っておく方が無難です。米国債は安全性が高いとはいえ、市場価格が変動する投資商品である以上、流動性(現金化しやすさ)の面では劣ることを認識しておきましょう。特に個人向け国債のように発行後1年は換金不可といった制限こそありませんが、為替変動や金利変動のリスクを考えれば、数ヶ月〜1年程度の短期資金には不向きと言えます。
為替リスクを避けたい人
「投資で為替リスクは取りたくない」「円で安定運用したい」という方も米国債は避けたほうが無難です。繰り返しになりますが、米国債は米ドル建て資産なので為替の影響を完全には避けられません。購入タイミングで円安方向に大きく振れてしまったり、保有中に急激な円高が起これば、せっかくの利息収入や価格上昇のメリットが相殺されてしまう可能性があります。為替変動による評価損を見るのが精神的に負担になるタイプの方には、米国債より円建ての債券や円預金など為替リスクのない商品が適しています。
なお、為替ヘッジ付きの外債ファンドなどを利用すれば為替リスクを低減する方法もありますが、その場合ヘッジコストがかかるため、結局米国債の利回りの低さが際立つ結果にもなりかねません。為替リスクゼロで運用したいという明確な方針があるなら、最初から米国債は買わず、国内の金融商品で完結するポートフォリオを組むほうが安心でしょう。
分散投資の観点で見た米国債の位置づけ

株式やREITと組み合わせる「守りの資産」
米国債は単体で見るとリターンの物足りなさや為替リスクが指摘されますが、分散投資のポートフォリオに組み込むことで真価を発揮します。具体的には、株式やREIT(不動産投資信託)など値動きの大きい資産と組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスクを抑える「守りの資産」として機能します。一般に景気が悪化して株式市場が下落するとき、安全資産である米国債には資金が流入し価格が上昇(利回りは低下)する傾向があります。そのため、株価暴落時のクッション役としてポートフォリオの下落を緩和してくれる可能性があります。
米国債は信用力が高いため、極端な危機でも元本回収への信頼が保たれやすい傾向があります。他資産との逆相関の関係が期待できる場面もあります。ただし注意点として、昨今のように金利上昇局面では株と債券が同時に下落するケースもあるため、万能ではありません。それでも、米国債を適切な割合で組み入れることは分散効果を高める有力な手段であり、リスク管理上有益だとされています。
リスク分散のひとつとして米国債を考える
資産運用の基本原則である「卵を一つのカゴに盛るな(分散投資)」において、米国債は重要な選択肢の一つです。国内株式・外国株式・債券・不動産・現金など様々な資産クラスに分散する中で、米国債は海外債券枠の代表として組み入れられます。為替リスクはありますが、その分通貨分散になり得ますし、日本国債では実現できない金利収入を得られるメリットもあります。特に日本の低金利状態が続く間は、米国債の利回りは魅力的であり、ポートフォリオ全体の収益率底上げにも貢献します。
重要なのは、米国債の投資比率を自分のリスク許容度に合わせて調整することです。安全資産とはいえ外貨建てである以上リスクがゼロではないので、「無リスク資産」と考えて全額を注ぎ込むのは避けましょう。株式などリスク資産とのバランスを取り、リスク分散の一環として米国債を位置づけるのが賢明です。そのように使いこなせば、米国債はポートフォリオの安定に寄与し、長期的な資産形成においても一役買ってくれるでしょう。
融資型クラウドファンディングも選択肢に
価格変動リスクがない投資とは?
米国債や株式など市場で売買される金融商品は常に価格変動リスクがあります。そこで、「元本価格が変動しない商品」として注目されるのが融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディングとも呼ばれます)です。融資型クラウドファンディングでは、投資家がお金を貸し付けて利息収入を得る仕組みのため、途中で市場価格が上下するといったリスクは基本的にありません。貸付先から返済が滞りなく行われれば、当初約束された利息と元本を受け取れる点で、預金や債券の利息受取に近い感覚で運用できます。
もちろん、融資型クラウドファンディングには借り手の返済不能リスク(信用リスク)が存在しますので、絶対安全とは言えません。しかし、株式や債券のように日々価格が変動して一喜一憂する必要がないのは魅力です。投資期間中は基本的に元本額が固定され、満期まで保有すれば所定の利回りが確定します。したがって、値下がりによる元本割れを極力避けたい人や、市場の値動きを追う時間がない人にとって、融資型クラウドファンディングは価格変動リスクがない安定運用の選択肢となり得ます。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
まとめ|米国債は万能ではないが「使い方次第」
米国債は非常に信用度が高く安全性に優れた投資対象ですが、一方で為替リスクや低利回り、流動性などの課題も抱えています。そのため、「米国債を買ってはいけない」という言葉が出てくる背景には、万人にとって万能な商品ではないという現実があります。しかし、視点を変えれば米国債は資産運用において使い方次第で有効な武器となります。長期的な資産形成の土台として組み入れたり、安全資産としてポートフォリオのバランスを取ったり、目的に応じて上手に活用することが重要です。
大切なのは、米国債のメリット・デメリットを正しく理解した上で、自分の投資方針や資金性格に照らして判断することです。本記事で解説したポイントを参考に、「買ってはいけない」と言われる理由に惑わされず、賢明な資産運用の選択肢の一つとして米国債を検討してみてください。
参考元
・金融庁:「本音が飛び出す! つみたてNISA座談会」
・米国労働省: 「2022年2月の米国消費者物価指数(CPI)」
・大和証券: 「外国債券:債券の税金」
・財務省: 「米国の国債金利と財政の関係について」