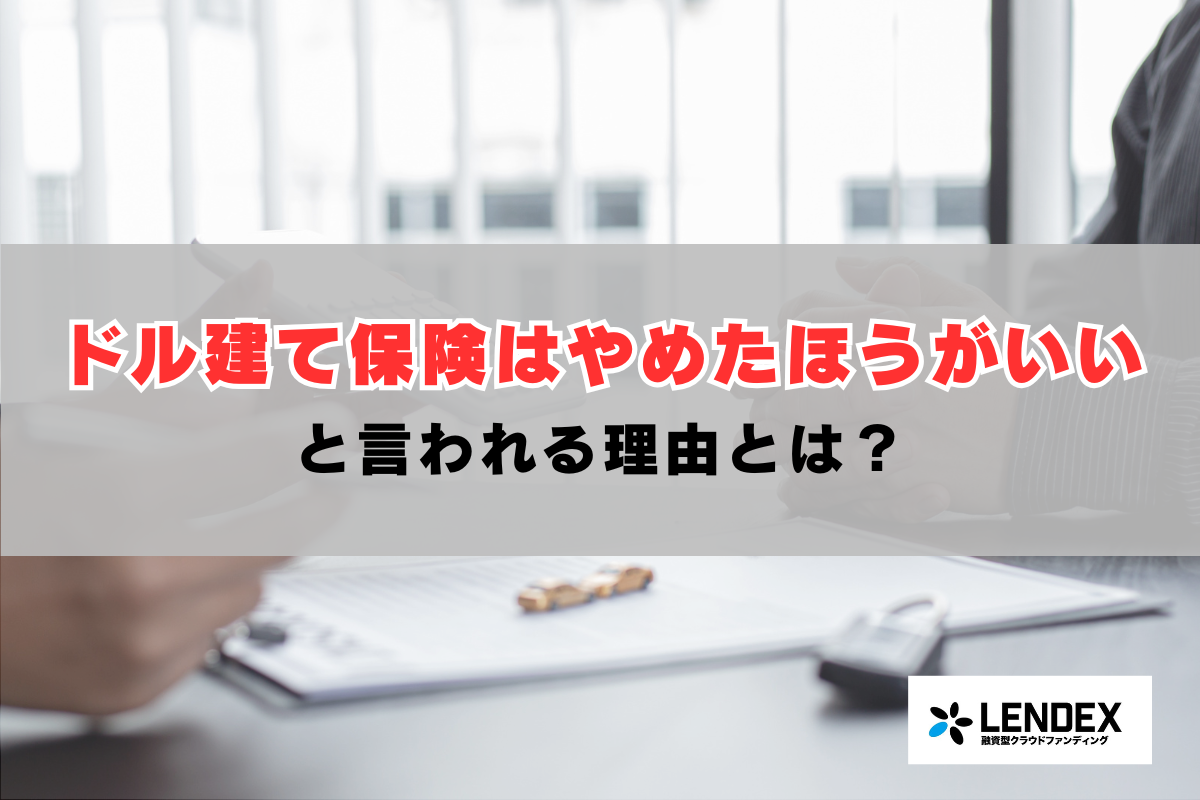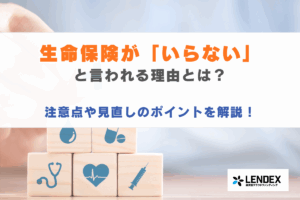近年、資産運用としてドル建て保険が注目されていますが、一方で「ドル建て保険はやめたほうがいい」という声も耳にします。なぜそのように言われるのでしょうか。その理由を初心者にもわかりやすく解説します。
ドル建て保険はやめたほうがいい?その理由をわかりやすく解説

そもそもドル建て保険とは?仕組みをおさらい
ドル建て保険とは、保険料の運用や保険金の支払いを米ドルなど外貨建てで行う生命保険商品のことです。契約者が支払った保険料は保険会社によって外貨で運用され、将来受け取る保険金や解約時に戻ってくるお金(解約返戻金)も基本的に米ドルで計算されます。
貯蓄型の生命保険に分類され、満期や解約時に支払った保険料総額より多い金額を受け取ることも期待できる商品です。ただし受け取り時には円に換えるケースが多く、その際の為替レートにより円ベースの受取額が増減する点が特徴となります。
近年、日本は超低金利が続いており円建ての保険では資産を増やしにくいため、利回りの高い米ドルで運用できるドル建て保険が注目されています。
「やめたほうがいい」と言われる主な理由5つ
ドル建て保険を「やめたほうがいい」と言われる背景には、主に次の5つの理由があります。
為替リスクがあり、円ベースで元本割れする可能性がある。
ドル建て保険の最大の懸念は為替変動による元本割れリスクです。運用通貨である外貨の価値が円に対して下がる(円高になる)と、受け取る円建ての額が払込総額を下回る可能性があります。
例えば、契約時より満期時に円高になれば受取額が大きく目減りし、元本割れの損失が出てしまいます。金融庁も、円高時には払い込んだ保険料総額を下回る可能性があると元本割れリスクに言及しています。したがって為替相場次第でせっかくの運用益が相殺されてしまう点が、ドル建て保険はやめたほうがいいと言われる大きな理由の一つです。
為替手数料や保険の諸費用がかかり、実質的な利回りは低くなりがち。
ドル建て保険は手数料など各種コストが高い点もデメリットです。
まず、円から外貨に換える時と受取時に外貨から円に戻す時、それぞれ為替手数料がかかります。例えば為替手数料が1ドルあたり1円なら、1万ドル(約100万円)を両替するたびに1万円程度のコストが差し引かれる計算です。保険会社に支払う付加保険料(運用管理費用など)も含め、「コスト負け」しないか注意が必要です。
さらに、途中解約時には解約控除(解約手数料)が発生しますが、そのペナルティは契約後の経過年数が短いほど大きく設定されています(一般的に契約後10年ほどで解約控除はなくなります)。そのため早期に解約すると元本割れになる可能性が高く、コスト面からもドル建て保険は長期運用しないとメリットを得にくい商品と言えます。
解約控除(早期解約時のペナルティ)が大きく、短期で解約すると損をしやすい。
ドル建て保険は解約リスクが高く、長期保有が前提となる商品です。実は外貨建て保険は早期解約が非常に多く、金融庁の調査では契約から4年以内に約6割が解約されていたとの結果が出ています。このように途中解約が頻発する背景には、やはり短期間で解約すると損をしやすいことが挙げられます。
前述したように解約控除などで解約返戻金が大きく目減りするため、契約後まもなく資金が必要になったり「思ったより増えない」と感じたりすると、元本割れ覚悟でやむを得ず解約してしまうケースが多いのです。
ドル建て保険は当初から長期で持ち続けることを前提に設計されています。金融庁も「商品性を十分に理解できる顧客に対して、長期保有を前提に提案・販売する必要がある」と指摘しており、長期間継続できない可能性がある場合は契約を見合わせた方がよいでしょう。
資金が長期間拘束され、必要なときに引き出せないなど流動性に欠ける。
ドル建て保険は資金の流動性(現金化のしやすさ)が低く、使い勝手が悪いことも指摘されています。途中で「やっぱりお金が必要」と思っても、株式のようにすぐ換金することはできません。解約するしかありませんが、その場合は前述の通り為替変動や各種費用の影響で解約返戻金が大きく減少し、元本割れとなるリスクが高いです。
このように急な出費や資金ニーズに対応できない点で、ドル建て保険は流動性が低い資産と言えます。必要なときに自由に現金化できないため、手元資金に余裕がない方には不向きです。また、他に有利な投資が見つかっても、資金をすぐ移し替えることが難しいという側面もあります。運用商品としては、こうした現金化のしづらさが大きな欠点になります。
商品内容が複雑でリスクの理解が難しく、「元本保証」と誤解しやすい。
ドル建て保険は商品設計が複雑で、仕組みの理解不足によるトラブルが起きやすい点にも注意が必要です。為替や手数料、解約控除といった考慮すべき事項が多く、内容を十分に理解しないまま契約すると「こんなはずではなかった」という事態になりかねません。
実際、金融庁によれば商品の内容をよく理解しないまま高齢者などが契約しトラブルになるケースが相次いでおり、販売金融機関に対して顧客保護の徹底を求めています。こうした問題を受け、2022年には生命保険協会が「外貨建保険販売資格制度」を創設し、ドル建て保険販売時の丁寧で十分な説明を行うよう取り組みが進められています。契約前に商品内容をしっかり理解することが、何より大切だと言えるでしょう。
以上のような理由から、ドル建て保険は安易に手を出すと損をするリスクが高い商品です。そのため「やめたほうがいい」と言われることが多いのです。
ドル建て保険のデメリット|加入前に必ず知っておくべきこと

ドル建て保険には、契約前に知っておきたいデメリット(注意点)がいくつか存在します。ここでは主なデメリットを3つ解説します。
為替リスクで元本割れの可能性がある
ドル建て保険最大のリスクは、為替変動によって受取額(円換算)が目減りし、元本割れしてしまう可能性があることです。加入時に1ドル=110円だったものが、受取時には円高で1ドル=90円になれば、受け取る円建て金額は払込時より約18%も目減りしてしまいます。
例えば、110円時に100万円(約9,091ドル)払い込んでも、90円時の返戻金は約81万8千円となり元本を下回ります。
為替相場の予測は難しく、為替次第で損益が大きく変わります。実際、この20年で円相場は1ドル=75円台から160円台まで大きく変動しました。2025年6月現在、ドル円相場は144円台で推移しています。想定外の円高に振れれば、利息を含めても円ベースで損失が出るリスクは否めません。
手数料や解約控除など、実質利回りが低くなりがち
ドル建て保険は表面上の利率(予定利率)が魅力的に見えても、各種手数料やコストを差し引くと実質的な利回りはあまり高くありません。
まず、円からドル、ドルから円への為替手数料が必ずかかります。また保険会社の運用管理費や死亡保障部分の保険料など、商品に組み込まれたコストもあります。
さらに契約後一定期間内に解約すると「解約控除」(解約ペナルティ)として高額な手数料が差し引かれます。
これらのコストの影響で、解約返戻金が払込保険料総額を上回るまでに20年以上かかるケースも珍しくありません。短期で解約すればほぼ確実に元本割れとなるため注意が必要です。実際、金融庁の2024年調査では、外貨建て保険商品で購入後4年間に約6割が解約などをしていたことが判明しています。こうした背景には、含み益が出た段階での自動的な利益確定後の乗り換え販売など、販売側の営業方針による問題もあると指摘されています。
保険なのに柔軟性がなく使いにくい場面も
ドル建て保険は、資産運用商品としてみると流動性(現金化のしやすさ)が低く、使い勝手が良いとは言えません。
払い込んだ資金は基本的に長期間ロックされ、途中で引き出したり減額したりすることはできません(契約者貸付などの制度はありますが、別途利息がかかります)。急に資金が必要になっても気軽に取り崩せないため、ライフプランの変化に柔軟に対応しにくい点はデメリットです。
また、一度契約すると為替相場の状況に応じて運用先や通貨を途中で変えることもできません。仮に契約後に「他の投資に回したい」「円高が不安だから円に戻したい」と思っても、解約以外の選択肢はないため自由度が低いと言えます。
それでもドル建て保険にメリットはある?活用できる人とは

デメリットが多いドル建て保険ですが、条件次第ではメリットを享受できるケースもあります。ここではドル建て保険を活用しやすい人の特徴を見てみましょう。
長期的に運用できる人には利回りメリットあり
長期間にわたって資金を運用できる人にとっては、ドル建て保険の利回りメリットが期待できます。米国の金利水準は日本より高いため、時間をかけて複利効果を得ることで、円建て商品より最終的なリターンが大きくなる可能性があります。
実際、前述のように解約返戻金がプラスに転じるには20年超の運用継続が前提となりますが、その期間運用を続けられるならドル建て保険の高金利を享受できるでしょう。
例えば、老後資金づくりとして30代で契約し、60代までコツコツと払い込みを続けられるような人は、満期時に円建て終身保険より多くの解約返戻金を手にできる可能性があります。また途中で解約しない前提なら、「元本保証はないが長く運用すれば増やせる商品」という位置づけで活用できるでしょう。
外貨資産としてリスク分散したい人に向いている
ドル建て保険は、資産の一部を外貨(米ドル)で持ちたい人の分散投資手段としても活用できます。円建て資産だけでは為替変動に弱いため、外貨建ての資産を持つことで円安時に資産価値が目減りするリスクを軽減できるからです。
特に将来の円安に備えておきたい人や、日本円以外の通貨で資産を持っておきたい人にとって、ドル建て保険は選択肢の一つとなるでしょう。
例えば、お子さんの留学資金や自身の海外移住資金など将来的にドルで使う目的がある場合、ドル建て保険で計画的に外貨を積み立てておくことで為替リスクヘッジにもなります。手元の円資産が円高局面で目減りしても、ドル建て保険の部分でカバーできる可能性があり、トータルの資産バランスを安定させる効果も期待できます。
円安・円高の影響は大きい!為替相場とドル建て保険の関係

ドル建て保険の運用結果は、円安・円高など為替相場の動向によって大きく左右されます。ここでは受取時の円相場による損益の違いや、為替損が出た場合の影響について解説します。
受け取るときの円相場で損益が変わる
ドル建て保険では、保険金や解約返戻金を受け取る時点の円相場によって、最終的な運用成果(円換算)が大きく変動します。受取時に円安(1ドルの円換算レートが加入時より高い状態)になっていれば、有利なレートで円に換えられるため、円建ての受取額は増加します。
逆に受取時に円高(レートが低い)になっていると、円換算の受取額が減少し、場合によっては払込総額を下回る可能性もあります。
例えば、加入時に1ドル=110円だったものが、受取時に円安が進み1ドル=130円になっていれば、受け取る円建て金額は払込時より約18%増える計算になります。反対に、受取時に1ドル=90円の円高になっていれば、円建て受取額は払込時より約18%減ってしまい元本割れになります。
このように、為替相場次第でドル建て保険のリターンは良くも悪くも変動します。為替のタイミングは自分でコントロールできないため、受取時の相場次第では想定外の損益が出てしまう点に留意が必要です。
為替差損が出ると保険の意味がなくなる?
ドル建て保険は資産形成の手段として契約する人が多いため、為替差損(円高による目減り)が発生してしまうと「結局損をしただけで意味がなかった」と感じるかもしれません。
実際、為替差損によって受取額が払込総額を下回れば、運用益はおろか元本も守れなかったことになります。そうなると、当初期待した「円建てより有利な運用」というメリットはなく、為替リスクの分だけ損をした形になります。
もっとも、保険としての死亡保障や満期保険金の受取といった本来の機能は残ります。仮に為替で損をした場合でも、保険契約自体が無意味になるわけではありません。しかし、「資産運用」としての意味は薄れてしまうのは事実です。ドル建て保険はあくまでリスク商品であり、「増えればラッキー、損失が出ても保険料だと思える」くらいのスタンスで臨むことが大切です。
こんな人にはドル建て保険は向かないかもしれません

では、具体的にどのような人がドル建て保険に向かないのでしょうか。代表的なケースを3つ挙げてみます。
資金を途中で使う可能性がある人
将来、その資金を別の用途に使う予定や可能性がある人は、ドル建て保険に向いていません。
途中解約すると解約控除で大きく元本を削られるうえ、為替レート次第では大きな損失が出る恐れもあるからです。教育資金や住宅購入資金、緊急予備資金など、一定期間内に必要となるお金はドル建て保険のように流動性の低い商品ではなく、もっと柔軟に引き出せる預金や短期の運用商品で管理する方が安全でしょう。
ドル建て保険は余裕資金で長期間運用する前提の商品です。「もしかしたらこのお金を何年後かに使うかも」という状況なら、無理に契約すべきではありません。必要なときに自由に引き出せないばかりか、タイミングによっては大きく目減りしてしまい、後悔するリスクが高くなります。
為替リスクに不安を感じる人
為替の変動による損失リスクに耐えられない、心配で夜も眠れなくなってしまうような人も、ドル建て保険は避けたほうがいいでしょう。
ドル建て保険は元本保証がなく、為替相場次第で評価額が上下します。為替リスクに不安を強く感じる人は、たとえ高金利に魅力を感じても、あとで円高になった場合のストレスの方が大きくなる可能性があります。
「預けたお金が減るかもしれない」と考えただけで不安になるようであれば、無理にドル建て保険に加入する必要はありません。資産運用には多少のリスクがつきものですが、自分のリスク許容度を超える商品を選ぶべきではないからです。どうしても外貨で運用したい場合は、為替ヘッジ付きの商品や元本保証のある商品など、リスクを抑えた選択肢を検討しましょう。
保険に投資的なリターンを求めすぎる人
「保険でお金を増やしたい」という考えが強すぎる人も注意が必要です。
保険は本来、保障を提供する商品であり、投資商品とは性質が異なります。ドル建て保険は確かに貯蓄性がありますが、それでも投資信託や株式のような高いリターンを追求できる商品ではありません。保険に過度な投資的リターンを期待しすぎると、「思ったほど増えない」「コストばかりかかる」といった不満を抱きやすくなります。
特に低金利の日本においては、保険に資産運用の役割まで求めるのは難しくなっています。資産形成を重視する人は、保険はあくまで保障目的と割り切り、運用は他の金融商品で行う方が合理的でしょう。
ドル建て保険も「保障+外貨建ての運用」というハイブリッド商品ですが、投資リターンを最優先に考える人には物足りず、コストの割に見合わない結果になる可能性があります。
代わりに考えたい選択肢|分散投資という考え方

資産運用では、一つの商品に資金を集中させず、複数の手段に分散してリスクを減らすことが重要です。ドル建て保険も含め、「保障」と「投資」は分けて考えることが現代のスタイルと言えるでしょう。
1つの商品に資産を集中させるのはリスクが高い
資産運用の基本は「卵は一つの籠に盛るな」です。一つの商品に資金をまとめて預けてしまうと、その商品が失敗したときに資産全体が大きな影響を受けてしまいます。ドル建て保険に限らず、どんな金融商品でもメリットとデメリットがありますから、特定の商品だけに依存するのは危険です。
ドル建て保険は魅力的に見える面もありますが、資産のすべてをドル建て保険に託すような運用は避けるべきでしょう。
例えば、円建ての預金・保険、国内外の投資信託、株式、不動産投資など、複数の資産に分散しておけば、一つが不調でも他でカバーできます。1つの商品に集中しないことで、リスクとリターンのバランスを取りながら安定的に資産形成を図ることが可能になります。
「保険+投資」ではなく、分けて考えるのが現代のスタイル
近年の資産形成の考え方としては、保障(保険)と運用(投資)は別々に行う方が効率的とされています。昔は貯蓄型保険で「保障もしながらお金も増やす」というスタイルが好まれましたが、現在は保障は保障、資産運用は資産運用で分けるのが主流です。
必要な保障は掛け捨ての生命保険や医療保険などシンプルな商品で確保し、その分浮いたお金を投資信託や株式などの運用に回す方が、総合的なリターンが高くなるケースが多いです。
保険に半端な運用性を求めるよりも、それぞれ専門の商品の良さを活かした方が合理的と言えるでしょう。ドル建て保険に限らず、「保険で増やそう」と考えるより「保険は保障・投資は投資」と割り切って考えるのが現代的なスタイルなのです。
融資型クラウドファンディングという新しい分散先も
値動きがない投資商品で安定的に運用したい人に
近年注目されている「融資型クラウドファンディング」(貸付型CF)は、価格変動のない商品で安定的に利息収入を得たい人に向いている新しい分散投資先です。投資家がお金を出し、それを事業者などに貸し付けて、利息を受け取る仕組みになっており、株式や投資信託のように日々価格が上下することはありません(貸し倒れリスクはあります)。
値動きがない分、相場に一喜一憂する必要がなく、利息による着実なリターンを狙えるのが魅力です。特に「元本の変動は困るが銀行預金よりは有利に増やしたい」という人にとって、融資型クラウドファンディングは選択肢の一つとなるでしょう。ドル建て保険と違い為替リスクもないため、円建てで安定運用したい層にもマッチします。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
ドル建て保険をすでに契約している人の見直しポイント
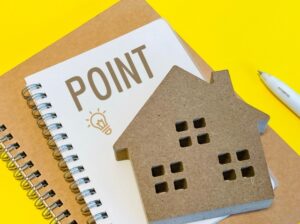
すでにドル建て保険に加入している場合、定期的に内容を見直し、必要に応じて対策を講じることが大切です。以下のポイントを確認しておきましょう。
途中解約は損?タイミングの見極めが重要
ドル建て保険は契約後まもなく解約すると損失が大きくなるため、「途中解約は損」と言われます。ただし、一概に解約すべきでないとも言い切れません。重要なのは解約するタイミングの見極めです。
まず、解約返戻金が払込保険料の累計に近づき、解約控除が小さくなる時期まで待つことが基本です。契約から数年以内の解約はほぼ確実に元本割れなので避けましょう。一方、加入から20年以上経過しており、円換算でもプラスが出ている場合は、解約を検討する価値があります。特に現在が歴史的な円安水準であれば、円高に振れる前に解約して利益を確定する判断も考えられます。
ただし、解約すると保障も失われます。必要な保障まで同時に失ってしまわないよう、解約の際は代わりの保険に入り直すことも検討しましょう。また、解約によって為替差損が出る状況なら、無理に解約せず保有を続けて円高局面が落ち着くのを待つ方が得策な場合もあります。自分だけで判断が難しいときは、ファイナンシャルプランナーなど専門家に相談することをおすすめします。
他の金融商品と組み合わせてカバーする方法も
ドル建て保険だけで将来の資金計画を立てるのではなく、他の金融商品と組み合わせることで弱点を補うことができます。例えば、ドル建て保険で外貨運用をしつつ、国内の円建て債券や預金も併用しておけば、為替変動による影響を緩和できます。
また、ドル建て保険の利回りに物足りなさを感じる場合は、別途投資信託や株式など積極的な運用商品にも資金を配分し、全体として目標利回りを目指すといった工夫も有効です。
途中で解約せず保有を続ける場合も、他の商品でリスクヘッジやリターンの補完をすることで、ドル建て保険のデメリットを緩和できます。要は、ドル建て保険に頼りきりにせず、分散投資の一部として位置付けることが重要です。生命保険としての保障は維持しつつ、資産運用面では他の手段でカバーすることで、全体的な資産形成のバランスを整えることができます。
よくある質問(FAQ)|ドル建て保険に関する不安を解消
最後に、ドル建て保険について多くの人が疑問に感じるポイントをQ&A形式で確認しましょう。
Q1. 円安の今、ドル建て保険は有利?
円安局面だからといって必ずしも有利になるとは限りません。確かに、現在円安であれば過去に比べ円換算の受取額は増えます。しかし、これから先に円高に転じる可能性もあり、受取時の相場がどうなるかは予測困難です。むしろ円安のときに契約を開始すると、将来円高に戻った際に損をするリスクが高まります。
円安だからお得、と安易に考えず、円安・円高の両面でシミュレーションして判断することが重要です。今が円安か円高かは相対的な問題で、将来の方向次第で有利不利が入れ替わります。したがって、為替相場を短期的に予想して契約するよりも、長期的な資産運用方針の中でドル建て保険を位置付けるかどうか検討するべきでしょう。
Q2. 保険を解約して投資に切り替えるのはアリ?
場合によっては選択肢として「アリ」です。ただし慎重な判断が必要です。ドル建て保険を解約して他の投資に切り替える場合、まず解約による損失(解約控除や為替差損)がどの程度か確認しましょう。解約ペナルティが大きいタイミングで無理に解約すると損失が確定してしまいます。
一方で、払い込みを続けるより魅力的な投資先があり、かつ解約損が許容範囲であれば、資金を投資に振り向けることも検討に値します。その際、ドル建て保険で担っていた保障(死亡保障など)が不要でないなら、代わりの保険に加入して保障を確保することも忘れないようにしましょう。
保険を解約して投資に切り替えるのは「アリ」か「ナシ」かは、一概には言えませんが、損益状況と今後の運用方針を総合的に考慮して判断することが大切です。
Q3. 為替ヘッジ付き商品との違いは?
為替ヘッジ付きのドル建て商品は、為替変動によるリスクを抑えるために円とドルの為替レートを実質的に固定またはカバーする仕組みが入っています。その結果、円高になっても受取額が目減りしないメリットがあります。しかしその代わりに、ヘッジコスト(為替予約の費用など)がかかるため、利回りはヘッジなし商品より低く抑えられるのが一般的です。
簡単に言えば、「為替リスクを取る代わりに高めの利回りを狙う」のが通常のドル建て保険、「為替リスクをなくす代わりに利回りは低めになる」のが為替ヘッジ付きの商品です。安全性を優先したい人はヘッジ付き、多少のリスクを取ってもリターンを重視したい人はヘッジなし、と自分の方針に合わせて選択できます。
ただしヘッジ付きでもコスト分だけ利回りが低下する点には留意が必要です。
まとめ|ドル建て保険は「合う人には合う」が、盲信は危険
ドル建て保険は高金利や外貨分散といったメリットもありますが、為替リスクや手数料などのデメリットも大きい商品です。「合う人には合う」一方で、誰にとっても絶対お得なものではありません。ドル建て保険を活用すべきかどうかは、自身の資金の使い道やリスク許容度、運用期間などを総合的に考慮して判断する必要があります。
大切なのは、商品の良い面だけを盲信しないことです。「ドル建て保険はやめたほうがいい」と言われる理由にも目を向け、メリット・デメリットを理解した上で、自分に合った選択をすることが重要です。仮にドル建て保険を契約する場合でも、それに頼りきりにせず、他の資産運用方法とのバランスを取りながら賢く活用していきましょう。
参考元:
・財務省 財務総合政策研究所:「日本企業の成長と内外の資金フローに関する研究会」
・金融庁: 「リスク性金融商品の販売会社等による 顧客本位の業務運営に関するモニタリング結果」