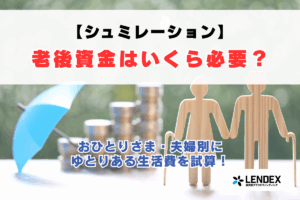「がん保険って、月々いくらくらい払えばいいの?」「掛け捨て型と貯蓄型、結局どっちが得なの?」そんな疑問を持つ方は多いのではないでしょうか。
実際、がん保険の保険料は年齢や性別、保障内容によって大きく異なります。また、保障に特化して保険料を抑えられる「掛け捨て型」と、将来お金が戻る「貯蓄型」では、支払額も目的も大きく違います。
本記事では、がん保険の年代・性別別の相場を明らかにした上で、「掛け捨て型がん保険」の特徴や貯蓄型との違いを丁寧に比較。さらに、公的医療制度との関係や、投資家目線で考える「保険と資産形成のバランス」についても解説します。
保険は“相場”で選ぶものではありません。「自分に必要な保障とは何か」を正しく理解することで、無駄なく安心な備えができるようになります。
がん保険の平均的な保険料はいくら?年代・性別で相場が違う
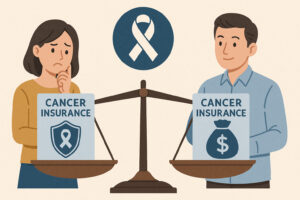
がん保険の保険料相場は、加入年齢や性別によって大きく異なります。一般的に年齢が上がるほど保険料も上昇し、特に50代から60代にかけて急激に高くなる傾向があります。
例えばあるシミュレーションでは、30代男性の月額保険料が約4,600~3,500円(払込期間65歳まで/終身払い)、40代では約7,600~4,900円、50代では約15,100~7,000円と年齢とともに大幅に増加し、60代以降もさらに保険料が上がっていきます
一方、女性の保険料は同条件で30代約4,000~2,900円、40代約6,100~3,700円、50代約10,800~4,600円と男性より割安です。これは男性の方が生涯でがんにかかるリスクが高いためで(男性62.1%、女性48.9%)、保険料にも反映されています。
なお、がん保険料は高齢になるほど加入そのものが難しくなるケースもあるため(健康上の条件や加入年齢制限)、なるべく若いうちからの準備がおすすめです。
月額の平均保険料は?30代・40代・50代で比較
前述のとおり、年代別に見ると月額保険料は30代より40代、40代より50代で大きく上昇します。例えば30代では月額3,000〜5,000円台だったものが、50代では1万円を超える水準になることも珍しくありません。これは年齢とともにがん罹患率が高まるため、保険会社が支払うリスクも高くなるからです。実際、日本人が一生のうちにがんと診断される確率は、30代前後から上昇し始め、40代以降で急激に高まります。そのリスク増加に比例して保険料相場も上がる点に注意しましょう。
- 30代の平均例:月額保険料 約3,000~5,000円前後(男女差あり)
- 40代の平均例:月額保険料 約5,000~7,000円前後(30代より約1.5倍)
- 50代の平均例:月額保険料 1万円超も(40代よりさらに大幅増)
このように年代で負担感が大きく変わるため、「いつ加入するか」は保険料を左右する重要なポイントです。できるだけ負担が小さい若いうちに終身保障に加入し、保険料を固定してしまうと、生涯払い込み額を抑えられるケースもあります。反対に加入が遅れると高額な保険料がネックになるため、将来のリスクに備えるなら早めの検討が望ましいでしょう。
男女別のがん保険料相場の目安も紹介
がん保険料は男女で差があります。一般に女性の方がやや割安なケースが多く、同じ条件で比べると男性より毎月数百円~数千円程度安い傾向です。前述のシミュレーションでも、例えば40代の保険料は男性約7,600円に対し女性約6,100円(払込65歳までの場合)と、女性の方が1,500円程低い結果でした。
これは統計的に男性の方ががんにかかる率が高い(生涯でがんに罹患する確率は男性62.1%、女性48.9%。つまり男性は「約5人に3人」、女性は「約2人に1人」の確率。)ことが背景にあります。
ただし保険料以外にも、男女でかかりやすいがんの種類や必要な保障内容が異なる点にも留意しましょう。例えば女性特有の乳がん・子宮がんなどに備えた特約がある商品もありますし、男性は働き盛りで収入減対策がより重要になるケースもあります。相場金額だけでなく、自身の性別やライフステージに合った保障かどうかを基準に選ぶことが大切です。
がん保険は必要?そもそも保障内容と仕組みをおさらい
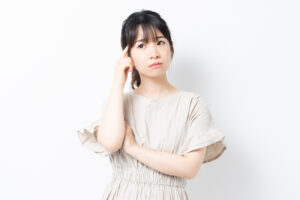
「がん保険は本当に必要なの?」と疑問に思う方もいるでしょう。結論から言えば、公的医療保険でカバーしきれない経済リスクに備えるためにがん保険は存在します。まずはがん保険の基本的な保障内容と、一般的な医療保険との違いを整理してみましょう。
がん保険の基本|診断給付金・入院保障・通院保障など
がん保険はその名の通り「がんの治療」に特化した保険です。一般的な医療保険が病気やケガ全般の入院・手術を対象とするのに対し、がん保険は悪性新生物(がん)および上皮内新生物による入院・手術などに特化して給付金が支払われます。主な保障として以下のようなものがあります。
- 診断給付金(一時金):がんと診断確定された際に受け取れるまとまった一時金。一般的に50万円~200万円程度の設定が多く、使途は自由です。治療開始時の費用や療養中の生活費に充当できます。
- 入院保障:がん治療のため入院した場合に、1日あたり定額の給付金を受け取れます。がん保険では入院日数無制限で保障される商品も多く、長期入院への備えとして有効です。なお、厚生労働省の「2020年患者調査」によれば、がんの平均入院日数は約19.6日とされており、実際の治療期間を想定した保障選びが重要です。
- 通院保障:手術・退院後の通院治療(抗がん剤や放射線治療など)に対して給付金が出ます。近年は入院より通院で治療を続けるケースが増えており、通院治療も回数無制限で保障されるがん保険が主流です。
- 手術給付金:がんの手術を受けた際に一時金が支払われます(手術1回につき◯円など)。
- 先進医療特約:公的保険が効かない先進医療(重粒子線治療等)の費用を保障する特約です。高額になりがちな最先端治療にも備えられます。
これらの保障によって、がんと診断された際の治療費や収入減少に備えるのががん保険の役割です。ただしがん以外の病気やケガは一切対象外なので、範囲の広い医療保険とは用途が異なる点に注意しましょう。公的医療保険では賄えない高額治療費や長期療養の出費にフォーカスしているのが、がん保険の特徴です。
医療保険との違いは?セットで入るべき?
医療保険(民間の入院保険など)とがん保険の違いは、ずばり保障対象の範囲です。医療保険は「がんを含むあらゆる病気やケガ」による入院・手術を幅広くカバーしますが、がん保険はがんに限定して手厚い保障を提供します。
例えば医療保険では入院日額や手術給付金が定められていますが、給付日数や金額に制限がある場合があります。一方、がん保険はがんに絞っている分、給付日数無制限や診断時にまとまった一時金が出るなど、がん治療に特化した保障内容となっています。
では、「医療保険とがん保険、両方入るべきか?」という点については、現在の加入状況や必要保障額によって異なります。すでに医療保険に加入していてがん特約を付けられる場合、セット加入(医療保険+がん特約)は保険料を抑えられるメリットがあります。一方で保障内容は限定的になりがちで、例えば診断一時金が少額だったり、通院保障が付けられなかったりするケースもあります。
これに対し、医療保険とがん保険を別々に加入すれば、がん保険でより充実した保障を得ることが可能です。その代わり保険料の総額は高くなります。例えばがん保険単独契約なら高額な一時金や無制限の通院保障を選べますが、その分コスト増になります。つまり経済的余裕と必要保障量に応じて、セット加入でコストを抑えるか、別々加入で充実保障を取るか判断すると良いでしょう。
保険の専門家も「公的医療保険だけでは不足する分を補うのが民間保険の役割」と指摘しています。まずは公的制度と現状の医療保険でどこまでカバーできるか確認し、不足する部分のみがん保険で補うのが合理的です。必ずしも全員ががん保険に入る必要はありませんが、がん治療に備えたい目的が明確にあるなら、医療保険とのバランスを考えつつ検討してみましょう。
掛け捨て型がん保険の特徴とメリット・デメリット
がん保険には大きく分けて「掛け捨て型」(純粋保証型)と「貯蓄型」(積立型)があります。まずは掛け捨て型の特徴と利点・欠点を見ていきましょう。
掛け捨て型とは、解約時や満期時にお金が戻ってこないタイプの保険です。保険料の中に貯蓄部分がない分、後述する貯蓄型より月々の保険料が割安に設定されています。
保険料が安くてシンプル|若いうちは選びやすい
掛け捨て型がん保険の最大のメリットは保険料の安さです。貯蓄性がないぶん純粋に保障に特化しているため、同じ保障内容でも貯蓄型より毎月の支払いを抑えられます。実際、掛け捨て型の終身がん保険は多くの人気商品で月額2,000~4,000円程度の保険料相場に収まっており、家計への負担を軽減できます。「保険料が高いと感じている方には保障のみが得られる掛け捨て型保険が適している」という指摘もあります。
また、掛け捨て型は保障内容がシンプルで分かりやすい点も若い世代に向いています。例えば学費や住宅購入など他の資金ニーズがある場合でも、掛け捨て型なら必要最低限の保険料で手厚い保障を準備可能です。浮いたお金を貯蓄や投資に回すことで、将来の資産形成と保障を両立しやすいという利点があります。「保険料が安い分、特約を付加して保障を充実させることもできる」とされ、若年層でも無理なく必要な保障を確保できるでしょう。
さらに掛け捨て型は保険の見直しがしやすいこともメリットです。契約に解約返戻金がない分、途中で他の商品に乗り換える際の損失が少なくて済みます。「より自分に合ったがん保険が新たに出たとき、掛け捨て型なら見直しがしやすい」という指摘もあります。ライフステージの変化に合わせて保険を柔軟に変更できるのは、掛け捨て型ならではの利点と言えます。
掛け捨てなので、解約返戻金はゼロ
掛け捨て型がん保険のデメリットは、やはりお金が戻ってこない点です。契約途中で解約しても解約返戻金は基本ゼロ(あってもごくわずか)で、満期保険金もありません。そのため「掛け捨て=保険料がムダになるのでは?」と感じる人もいます。
しかし、これは保障に対する対価と割り切ることが重要です。保険を使わず済んだということは健康でいられた証でもあり、支払った保険料で安心を買ったと考えれば決して損とは言い切れません。むしろ掛け捨て型は割安な保険料で十分な保障を確保できるメリットがあります。同じ保障内容で比較すれば、貯蓄型の保険料は掛け捨て型の2~3倍程度になることも多く、過度な貯蓄性を求める方が支出増につながりかねません。
もう一つの注意点は、掛け捨て型の多くは保障期間が定期型(一定期間)である点です。終身タイプの掛け捨て商品もありますが、多くは10年更新や60歳・65歳満了といった期間が設定されています。保険期間が満了すると以後の保障はなくなり、継続するには更新(高齢になれば保険料アップ)か新規加入が必要です。
以上より、掛け捨て型は「保障を重視し、保険料負担を抑えたい人」に向いています。例えば「保険料が戻らなくても気にしない」「万一の保障を安価に確保したい」という考えの方には最適でしょう。
貯蓄型がん保険の特徴とメリット・デメリット
続いて貯蓄型がん保険です。貯蓄型は保障と貯蓄機能を兼ね備え、解約や満期時にお金が戻ってくるタイプの保険を指します。代表的には解約返戻金や満期保険金が設定されており、万一がんにならなくても将来資金を受け取れる点が掛け捨て型との違いです。
保険+貯蓄機能を兼ねるが保険料は高め
貯蓄型がん保険のメリットは、なんといっても解約返戻金を受け取れることです。途中解約した際に一定の返戻金が戻ってくるため、いざという時は契約を解約して資金に充てることもできます。満期まで持てば満期金を受け取れる商品もあり、「保障を得ながら計画的にお金を貯める」ことが可能です。1つの契約で保障と資産形成の両方を備えたい人には魅力と言えるでしょう。
さらに貯蓄型では契約者貸付が利用できる場合もあります。これは解約せずに積立金の一部を貸し付けてもらえる制度で、急な出費時に保険を維持しながら資金を工面できる利点です。また保険によっては配当金や利差益が付く商品もあり、長期的に預貯金より高い利率で運用できる例もあります。例えば学資保険などでは受取額が払込総額を上回るケースもあり、低金利の中で堅実に増やす手段として検討する人もいるでしょう。
しかし、こうした貯蓄機能と引き換えに保険料は割高になります。解約返戻金がある分、掛け捨て型と比較して毎月の保険料は2~3倍程度に設定されるのが一般的です。たとえば同じ保障内容でも、掛け捨て型なら月々2,000円台で済むところ、貯蓄型では5,000円以上になることも珍しくありません。保険料負担が重くなる分、家計を圧迫する恐れがある点には注意が必要です。
途中解約のリスクや運用利回りの低さにも注意
貯蓄型がん保険のデメリットとしてまず挙げられるのは、保険の見直しや解約がしにくいことです。解約返戻金があるとはいえ、契約からあまり期間が経っていないうちに解約すると返戻金は支払保険料より少なくなる可能性が高いです。結果として払い込んだ保険料の一部が無駄になる形になるため、「他のがん保険に乗り換えたい」「保険料負担が厳しいから解約したい」と思っても簡単に見直せません。長期契約ゆえに身動きが取りづらい点は貯蓄型の欠点です。
また、運用利回りの低さにも目を向ける必要があります。現在のような低金利下では、保険の予定利率(貯蓄部分の運用利率)も低く抑えられています。つまり貯蓄型といっても大きなリターンは期待できず、保険での資産運用は「安定性重視で大きなリターンは求めないもの」と理解すべきでしょう。実際「保険は投資より高い利回りを期待できない。安定性を重視した運用と考えよう」との指摘もあります。
さらに万一、加入している保険会社が破綻した場合には積み立てた資金(解約返戻金)が目減りするリスクもあります。契約者保護機構による補償があるとはいえ全額戻らない可能性も指摘されており、長期契約ゆえに保険会社の経営状況にも注意が必要です。
以上から、貯蓄型は「保障も貯蓄も両方ほしい人」に向いています。貯蓄目的で加入するには向かないとされる掛け捨て型に比べ、将来の備えも兼ねたい人には魅力でしょう。ただし保険料負担に無理がないか、また他の資産運用手段と比べて適切かなど、契約前に慎重に検討することが大切です。
掛け捨て型 vs 貯蓄型|選ぶときの判断基準とは?

掛け捨て型と貯蓄型、それぞれの特徴を踏まえた上で「自分にはどちらが向いているのか」を判断するには、年齢・家族構成・収入(経済状況)といった要素を考慮する必要があります。以下では選択の目安となるポイントを整理します。
年齢・家族構成・収入で選び方が変わる
年齢
若年層~子育て世代で収入が限られている場合は、保険料が安い掛け捨て型が適しています。早い時期に終身型の掛け捨て保険へ加入し、低い保険料を固定しておけば将来まで負担を抑えられます。
一方、50~60代で貯蓄に余裕がある人は、貯蓄型で老後の資金を兼ねた保障を検討してもよいでしょう。ただし高齢で新規加入する場合は保険料が非常に高額になる点に注意が必要です。
家族構成
独身か扶養家族がいるかでもニーズは異なります。例えば扶養家族(配偶者・子ども)がいる場合、自分ががんで働けなくなった際の生活費リスクにも備える必要があります。この場合、安価な掛け捨て型でより高額な一時金を用意するか、もしくは貯蓄型で解約返戻金も使えるようにしておくか検討できます。
逆に独身や子育て後で扶養家族がいない場合、がんで本人が亡くなっても経済的影響が小さいため、高額な保障は不要かもしれません。その場合は掛け捨て型で最低限の治療費保障だけ確保するなど、身の丈に合った選択で十分でしょう。
収入・貯蓄
家計に余裕がない場合は、やはり掛け捨て型で保険料負担を抑えるのが無難です。保障が手厚いほど安心とはいえ、保険料で家計を圧迫しては本末転倒です。収入に応じて「保険にどこまでお金をかけられるか」を考え、無理のない範囲で保障を選びましょう。
逆に十分な貯蓄や収入があり、「保険で備えるより自分で蓄えてリスク対応できる」という人は、あえてがん保険自体を最低限にするか加入しない判断もあります。高額療養費制度などで賄えない部分だけ民間保険で補うという割り切りも一つの考え方です。
このように、一概に「どちらが良い」とは言えず個々の状況で最適解は異なります。FP(ファイナンシャルプランナー)からは「保険料が掛け捨て=損ではないと考えられる人は掛け捨て型向き」「保障と貯蓄両方ほしい人は貯蓄型向き」といったアドバイスもあります。自分や家族の将来計画、リスク許容度を踏まえて選ぶことが大切です。
万が一に備えるだけでなく“家計全体”で考えることが大切
保険選びは「万が一のための保障」ばかりに目が向きがちですが、家計全体のバランスを考える視点も欠かせません。高額な保障を求めすぎて日々の生活が苦しくなっては本末転倒ですし、過剰な保険料負担は将来の貯蓄機会を奪います。専門家も「保険に入ろうと思ったときは、公的保険と預貯金をまずチェック。足りない部分を民間保険で補うのが合理的」と助言しています。つまり公的制度や自己資金で賄える部分と賄えないリスク部分を見極め、その不足分を埋める目的で保険を選ぶのが正解に近いのです。
例えば、がん治療費の自己負担は高額療養費制度で月額上限が設定されています。年収にもよりますが、一般的な所得の方であれば自己負担上限は月約9万円前後です。実際、厚労省のデータではがん入院1件あたりの平均医療費は約77万円ですが、その場合自己負担は約30万円となり、高額療養費の適用で約21万円が後から払い戻されます。結果、自己負担実質8万円ほどに抑えられます。このように、公的制度でどこまでカバーできるかを知れば、「治療費そのものは貯蓄で払えるから収入減に備える保険だけ入ろう」など判断材料になります。
また、リスクはがんだけではありません。 心疾患や脳卒中など他の重大疾病、あるいは介護状態になるリスクも年齢とともに高まります。がん保険に厚く入っていても、他の分野がおろそかでは家計全体の安全網として不十分です。住宅ローンや教育費、老後資金などとの兼ね合いも踏まえ、「トータルで家族の生活を守るプラン」になっているか確認しましょう。場合によっては、がん保険より収入保障保険や就業不能保険などを優先すべきケースもあります。単体の保険商品ではなく、自身のライフプラン全体の中で最適な備えを考えることが重要です。
がん保険の見直しタイミングとチェックポイント

一度加入したがん保険も、ライフステージの変化に応じて定期的な見直しが必要です。では具体的にどんなタイミングで見直しを検討すべきでしょうか。また、見直す際に確認すべきポイントも押さえておきましょう。
就職・結婚・出産・退職などのライフイベント時
ライフイベントに応じて保障ニーズは大きく変化します。例えば以下のタイミングでは、がん保険を含む生命保険全体の見直しを検討すると良いでしょう。
就職・転職
社会人になり収入を得始めたら、自分の医療費や生活費を自力で支える必要が出てきます。会社の医療保険制度(団体保険)に加入できる場合もありますが、ない場合は民間の医療保険・がん保険で備えることを検討しましょう。転職時も福利厚生の変化に注意が必要です。
結婚
配偶者ができ扶養する立場になると、自分が病気になった際の家計への影響が大きくなります。独身時代よりも保障額を手厚くする(または新たに加入する)ことで、配偶者の生活を守る準備をしましょう。
出産・育児
子どもが生まれ家族が増えると、教育費など将来の出費が確定します。同時に親に万一のことがあれば家計が成り立たなくなるため、一時金の額を増やすことも検討されます。特に子どもが小さいうちは貯蓄も十分でないケースが多いため、がん保険で高額給付金を設定するか、他の保障と組み合わせて備えると安心です。
住宅購入
住宅ローンを組んだ場合、団体信用生命保険で死亡時のローン返済はカバーできますが、がんで長期療養になるケースなどはカバーできません。働けず収入が減ってもローン支払いは続くため、就業不能保険やがん保険の所得補償面を強化することも考えましょう。
退職(定年)
会社員の場合、退職すると健康保険の給付(傷病手当金など)が使えなくなります。また退職金や年金生活に移行すると、保険料負担そのものが重荷になる可能性があります。60代以降は保険の新規加入も難しくなるので、退職前に必要かつ無理のない保障内容に見直すことが重要です。
このように各ライフイベント時には保障ニーズと支払い能力を再評価し、「今の保険で十分か?足りないか?過剰か?」をチェックしましょう。特に掛け捨て型の保険は見直しのハードルが低いので、状況変化に合わせて柔軟にプランを調整することが大切です。
「本当に必要な保障額」を見極めよう
見直しの際にもう一つ重要なのが、保障額・保障内容の適正化です。ただ漠然と「手厚い方が安心」と保険金額を設定していないでしょうか?改めて本当に必要な金額をシミュレーションしてみましょう。
治療費の自己負担額
高額療養費制度により、医療費の自己負担額には上限が設けられています。具体的には、標準報酬月額28万~50万円の方(一般的な現役世帯に該当)であれば、1か月あたりの自己負担上限は約8万円程度となります。これは公的医療保険によって医療費負担が一定に抑えられる仕組みです。
たとえば、入院・手術・放射線治療などで総額100万円の医療費がかかった場合、自己負担は約30万円ですが、後日高額療養費制度により約21万円が払い戻され、実質自己負担は約9万円で済みます。
さらに、がんの入院治療費における実際の自己負担額の平均は6万〜8万円程度とされており、制度の活用により多くのケースで費用負担を軽減することが可能です。
また、高額療養費制度に加え、健康保険からの入院給付金や高額医療費支給制度の対象となる場合には、実質負担額がさらに軽くなるケースもあります。このように、実際に必要となる費用は「自己負担限度額 × 治療期間(月数)」が一つの目安になります。
【2025年最新情報】
2025年8月から高額療養費制度の自己負担限度額が引き上げられ、年収約370万~770万円の中間所得層では月額上限が約80,100円から88,200円になります。がんの入院治療費の自己負担額平均は6~8万円程度、通院治療費の自己負担額平均は4,000円~1万1,000円程度です。
収入減・生活費
治療に専念するため働けない期間の生活費はどう賄うか。会社員であれば健康保険から傷病手当金(標準報酬日額の2/3相当)が最長18ヶ月支給されますが、それでも給与満額より減収になります。自営業やフリーランスだと公的な所得補償はありません。貯蓄でどこまでカバーできるか、不足分はいくらかを計算しましょう。
追加費用
保険適用外の先進医療費用、差額ベッド代や交通費・雑費、家事代行サービス利用など、付随的な費用も見込む必要があります。先進医療については、公的な先進医療特約で実費保障できるため、必要に応じて特約加入も検討します。
家族への支援
自身の治療中に家族の生活費や子どもの学費など、長期的な家族の資金計画に穴が空かないかも確認します。がん保険の診断一時金は自由に使えるため、治療費以外にこうした生活サポートに充当することも可能です。
上記を踏まえ、「公的制度+手持ち資金でどこまで賄えるか」を算出し、不足する金額があればそれを埋める保障額に調整します。逆に十分な預貯金があるなら保障額を減らして保険料負担を軽くする決断も必要です。
見直し時はこうした具体的な数字の裏付けを取ることで、無駄や不足のない保障プランに最適化できます。「なんとなく不安だから高額保障」に走らず、「自分に必要な保障額はこのくらい」と明確にすることが、保険料の無駄を省きつつ安心を得るコツです。
がん保険だけで安心?分散して備えるという選択肢

がん保険は心強い備えですが、「がんにさえならなければ大丈夫」という考えで保険プランを完結させてしまうのは危険です。人生にはがん以外にも様々なリスクが存在し、保障を分散させておくことも大切です。
「がんになる」以外のリスクにも備えるべき理由
日本人の死因トップはがんですが、2位は心疾患、3位は脳血管疾患(脳卒中)です。また、ケガによる長期入院や要介護状態になるリスク、さらには自然災害による家屋損壊や事故の可能性もあります。がん保険だけに加入していても、これら他のリスクに対する保障はありません。
例えば脳卒中で半身まひになり長期介護が必要になった場合、公的介護保険はありますが十分な介護サービスを受けるには自己負担もかかります。同様に心筋梗塞で働けなくなった場合、収入減少はがんと変わらぬ打撃となるでしょう。医療保険や所得補償保険で広く病気全般に備えておくことや、障害年金を受給できる公的制度について知っておくことも重要です。
また一度も大病せずとも、認知症や骨折などで要介護になる可能性もあります。老後に備えて介護保険や認知症保険を検討する人も増えています。がん保険は「がん」というリスクには強いですが、それ以外が手薄だと結局安心は得られません。リスクを一点張りせず多面的に備えることで、想定外の事態にも家族の生活を守れるのです。
さらに、がんにかかったとしても治療費以外の経済リスクが存在します。前述の通り収入の減少や、住宅ローンなど固定費の支払い、子どもの教育費などは病気に関わらず発生します。がん保険の給付金は基本的に医療費想定ですが、実際にはそれ以外の用途にも必要となるケースがあります。したがって、がん保険だけで全て安心と考えず、他の保障や資金準備も並行して進めるのが得策です。
医療費以外の備え方、資産形成の必要性
保険だけで全てのリスクに備えるのは現実的ではありません。「保険以外の準備」、つまり自助努力による資産形成や緊急資金の確保も不可欠です。特に医療費以外の費用や長期の収入減に対しては、まとまった貯蓄や流動性のある資産があると安心感が違います。
まず基本となるのは、生活防衛資金として数ヶ月~半年分の生活費を預貯金で確保することです。会社員独身者の場合は1月あたりの生活費の3~6ヶ月分(約535,000円~1,070,000円)、子どもがいる夫婦世帯の場合は6~12ヶ月分(約2,007,000円~4,001,000円)が目安とされています。
資産形成には様々な方法があります。預金の他、投資信託や株式、個人年金保険など選択肢は多彩です。ポイントは長期・分散でコツコツ増やしていくこと。例えばiDeCoや積立NISAを活用すれば、税制優遇を受けながら老後資金を作れます。保険商品ではないですが、低コストのインデックスファンドで運用すればインフレにもある程度対応できます。
また、「もしものときに取り崩せる資産」を持つこともポイントです。不動産や年金など流動性が低い資産ばかりでは、必要なときに現金化できません。現金やすぐ売却できる金融資産で、非常時にパッと使えるお金を備えておきましょう。その意味で、後述する値動きの少ない投資商品などは安定資産として検討の価値があります。
がん保険に入っていれば完璧、ではなく、保険+貯蓄+投資で多層防御を築くことが安心への近道です。
値動きの少ない投資商品で将来の備えをつくる

資産形成の方法として近年注目されているのが、値動きの少ない投資商品です。リスクを抑えつつ預貯金より有利に増やせる手段として、初心者からシニア世代まで利用が広がっています。その代表例の一つが融資型クラウドファンディングです。
融資型クラウドファンディングとは?
融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)は、インターネット上で多くの投資家から資金を集め、それを企業などに貸し付ける仕組みです。投資家はファンドを通じてお金を貸し、その利息を配当として受け取り、満期には元本が償還されます。いわば「小口の融資を束ねた貸付ファンド」です。
魅力は年利3~8%の利回りが期待でき、日々の価格変動がない点。株や投資信託のように値動きに一喜一憂せず、安定して利息を受け取れます。資産を「守りながら増やす」手段として注目されています。
ただし、元本保証はなく、貸し倒れリスクがある点には注意が必要です。担保の有無や事業者の信用力を見極めることが大切です。とはいえ、国内では貸し倒れ率が低く抑えられており、分散投資によってリスク軽減も可能です。
少額から始められ、預金の一部を有効活用したい人や、保険だけでは不安な医療費・老後資金の備えにも活用できます。ネットから簡単に申込できるのも魅力です。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
がん保険と民間・公的制度とのバランスを考えよう
ここまで、保険商品の比較や資産形成について述べてきましたが、最後に公的制度と民間保険のバランスについて整理します。
日本には充実した公的医療保険・社会保障制度がありますから、まずそれを活用し、不足部分を民間保険で補うのが合理的です。公的支援でどこまでカバーできるのか知り、民間のがん保険は「足りない部分を埋める」役割と位置づけましょう。
高額療養費制度などの公的支援でカバーできる範囲
高額療養費制度は、公的医療保険の強力なセーフティネットです。1ヶ月(同一月)に支払った医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が後から払い戻されます。自己負担の上限額(自己負担限度額)は収入に応じて設定されており、例えば一般的な所得の70歳未満の方ですと8万7,430円+(医療費総額-267,000円)×1%という計算式になります。ざっくり言えば、自己負担は月約9万円程度が頭打ちになるイメージです。
他にも、公的医療保険には傷病手当金(会社員が病気で働けないとき給料の一部を補償)や、会社員なら医療費の付加給付(健保組合によっては自己負担限度をさらに引き下げる制度)などがあります。がんに限らず病気全般で使える制度ですが、当然がん治療でもこれらは利用できます。また、所得が少ない世帯向けには自己負担限度額がさらに低く設定されたり、介護保険と医療保険の自己負担を合算して限度を適用する高額介護合算療養費などもあります。
こうした公的支援をフル活用すれば、多くの場合「がん治療費そのもの」はかなりの部分カバー可能です。現実に、がん患者さんの自己負担平均額は入院1回あたり数万円~十数万円程度とのデータもあります。公的制度だけで治療費リスクの大半に対応できる点は心強いです。
「何が足りないか」を見極めて民間保険を選ぶ
公的支援でカバーされる範囲を把握したら、次はその穴を埋める形で民間保険を検討します。例えば高額療養費制度で医療費上限は抑えられても、差額ベッド代や先進医療費、収入減などは公的保障で十分とは言えません。こうした部分こそが民間がん保険の出番です。
具体的には、以下の不足領域を民間保険で補います。
まとまった一時金
入院や手術で医療費負担が生じる際、公的支援後でも自己負担がゼロにはなりません。また治療開始時には医療費の立て替えや雑費もかかります。そこで診断給付金(がんと診断されたら受け取れる一時金)を備え、公的支援の隙間をカバーします。これは治療費だけでなく、収入減や家族の出費にも自由に使えるため安心感があります。
長期の収入サポート
傷病手当金では不足する収入減(特に自営業者やフリーランスは公的補償ゼロ)に対して、がん保険の就業不能保障特約や、別途就業不能保険などで備えることが考えられます。がん治療は通院も含め長期化しやすいため、その間の生活費をどう補填するかがポイントです。
先進医療等の費用
重粒子線や陽子線治療といった先進医療は数百万円単位の費用がかかりますが、公的保険適用外です。ただし先進医療特約を付けておけば、こうした費用も実費補償されます。先進医療は利用するか不確定ですが、万一のために備える意義はあります。
介護・後遺症への備え
がん治療後に障害が残った場合の介護費用など、公的介護保険で不足する部分を考える必要があります。がん保険にはそこまでの保障は基本ないため、必要なら介護保険や障害年金の受給条件を確認しておき、不足分は貯蓄や他の保険で補います。
要するに、公的保障+自己資金で対応困難なリスク領域をピンポイントでカバーするのが民間保険の役割です。無闇に手厚い保障を重ねる必要はなく、自分にとって必要十分な保障額・範囲を見極めましょう。
よくある質問(FAQ)|がん保険に関する不安・疑問に答えます
最後に、読者の方から寄せられそうな「がん保険のよくある疑問」についてQ&A形式でまとめます。
Q1. 掛け捨て型は損じゃない?
いいえ、掛け捨て型保険は決して損とは言い切れません。確かに掛け捨て型は解約返戻金がなく、満期まで使わなければ払い損に見えるかもしれません。しかしその分保険料が割安に設定されており、少ない支出で万一の保障を得られるメリットがあります。
例えば同じ保障内容なら、掛け捨て型の保険料は貯蓄型の2~3分の1程度で済むケースが多いです。大きな保障を安価に持てるという点で、コストパフォーマンスはむしろ高いと言えるでしょう。
また掛け捨て型の場合、「保険を使わない=健康で過ごせた」ということです。それ自体が喜ばしいことであり、支払った保険料は安心を買った対価とも考えられます。手厚い保障を安い保険料で確保でき、その間健康でいられたなら決して無駄遣いではありません。
重要なのは、掛け捨て型を「貯蓄」目的で考えないことです。貯蓄は他の方法で行い、保険は保障本来の目的で利用するものです。掛け捨て型は保障に特化した合理的な選択肢ですので、損か得かより「必要な保障を適正なコストで得られるか」で判断しましょう。
Q. 一度がんになったら保険に入れなくなる?
一般的な傾向として、過去にがんに罹患すると新規でがん保険に加入することは非常に難しくなります。多くの保険会社は申込時の告知で「がんにかかったことがあるか」を確認し、一度でもがんを経験していると加入を断られるケースがほとんどです。特に診断から5年や10年以内など一定期間は標準体扱いされず、通常のがん保険への加入は困難と考えておいた方がいいでしょう。
しかし、引受基準緩和型保険(加入のハードルを下げた保険)であれば、条件付きで加入できる場合があります。一部の保険会社では条件を満たせば加入できる緩和型の医療保険・がん保険を用意しています。もちろん通常の保険に比べ保険料は割増になりますが、完治後間もない方や持病がある方でも加入できる選択肢です。
ただ、緩和型に入れたとしても保障内容は限定的だったり、がん保険の場合だと一度かかった人向けの商品自体が少ないという現状もあります。そのためベストは、健康なうちに必要な保険に加入しておくことです。がん経験者の方は、緩和型保険や共済なども視野に入れて、専門家に相談しながら最適なプランを探すと良いでしょう。
Q. 60歳以上でもがん保険は必要ですか?
60代以降のがん保険は「人による」選択です。60代はがんの発症リスクが高まる時期で、保障があると安心ですが、加入年齢の上限(多くは69~75歳)や健康状態により、新規加入が難しい場合もあります。
FPの見解では、「60~64歳は保険の必要性が高く、65歳以降は貯蓄や年金で対応できる人が多いため必要性が下がる」とされます。特に収入が減る年金前の時期には、がん治療の備えとして保険が有効です。
ただし、保険料は高齢になるほど割高になるため、費用対効果の検討が必要です。十分な貯蓄や他の医療保険でカバーできる場合は、無理に加入する必要はありません。
高齢の親の加入を検討する場合は、年齢・持病の有無・家族の支援体制を含めてよく話し合いましょう。保険以外にも、公的支援や家族のサポートという選択肢もあります。
まとめ|がん保険は「相場」より「目的」で選ぶのが正解

ここまで、がん保険の相場やタイプ別の特徴、公的制度との関係など幅広く解説してきました。最後に重要なポイントをまとめます。
がん保険選びで大切なのは、「みんなこれくらい入っているから」と相場に合わせることではなく、自分の「加入目的」に照らして必要な保障を選ぶことです。 自分や家族の状況、心配なリスク、用意できる資金を総合して、「何のためにどれだけの保障が欲しいのか」を明確にしましょう。
その上で、掛け捨て型・貯蓄型といった商品の特徴を踏まえて最適な手段を選びます。貯蓄性より保険料の安さを優先するのか、多少高くても貯蓄機能が欲しいのか、人それぞれ答えは違います。大事なのは優先順位をはっきりさせることです。目的がはっきりすれば、自ずと選ぶべき保障内容や予算配分が見えてくるはずです。
また、がん保険単体ではなく公的保障や他の備えとのバランスも常に意識しましょう。高額療養費制度など公的支援で賄える部分に過剰な保障は不要ですし、逆に賄えない部分はきちんと補う必要があります。保険料と給付内容のバランス、保険と貯蓄のバランスをとり、家計全体で最適化する視点が重要です。
最後に、定期的な見直しも忘れずに。ライフステージが変われば必要な保障も変わります。加入後も節目節目で「この保障はまだ有効か?」「不足や無駄はないか?」を点検し、必要ならプランを修正しましょう。掛け捨て型なら特に見直しはしやすいので、柔軟に対応することが家計にも安心にもつながります。
がん保険は手段であって目的ではありません。大切なのは、それを通じて自分や家族の暮らしを守ること。その目的意識を持って選べば、きっとあなたにとって「ちょうどいい」保障が見つかるはずです。今回の記事を参考に、ぜひ賢い保険選び・備え方を実践してみてください。
参考元
・国立がん研究センター :「最新がん統計のまとめ」
・金融広報中央委員会:「知るぽると:高額療養費制度とは?」
・ほけんの窓口:「過去にがんと診断されたけれど保険に加入できますか?」