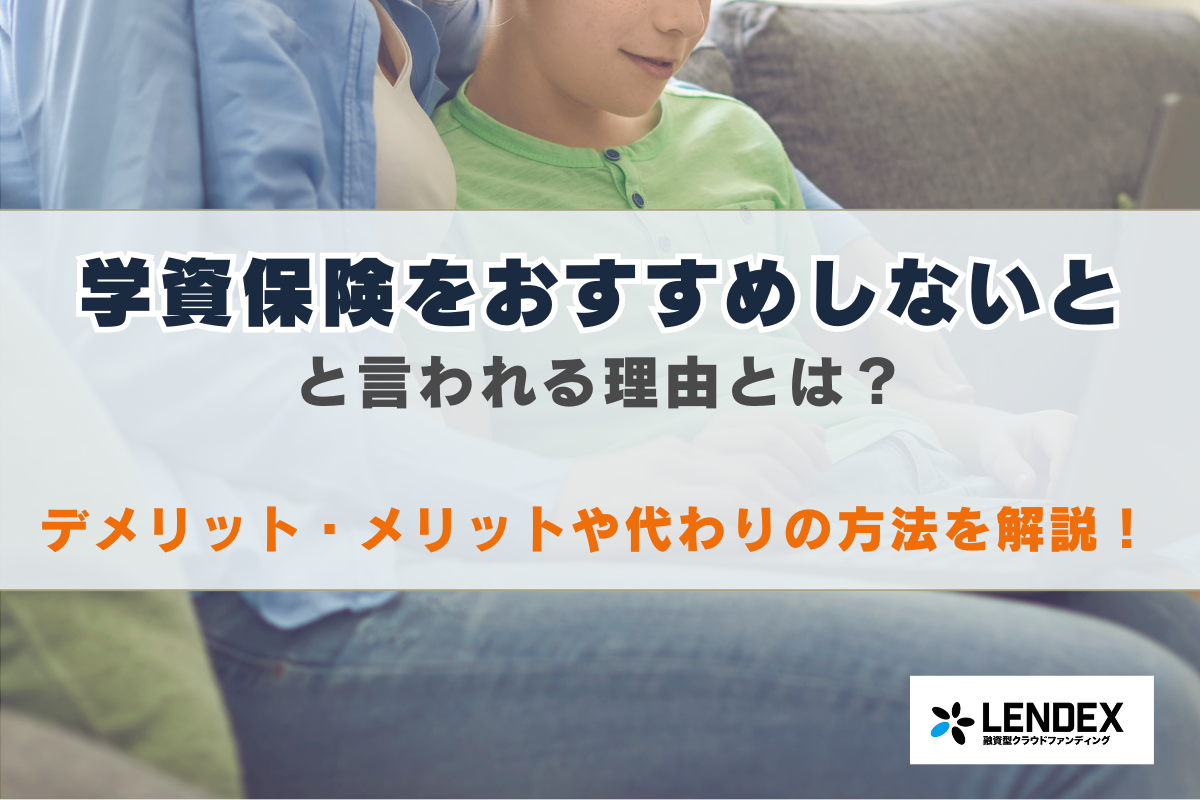「学資保険って、もう時代遅れなの?」
そんな声を耳にすることが増えてきました。実際、教育費の準備方法として長年利用されてきた学資保険ですが、最近では「おすすめしない」とする専門家や利用者も少なくありません。なぜ今、学資保険が見直されているのでしょうか?
この記事では、学資保険が敬遠される理由やその背景、メリット・デメリット、そして代わりに選ばれている資産形成の方法について、わかりやすく丁寧に解説します。
学資保険は本当におすすめしない?そう言われる背景を解説
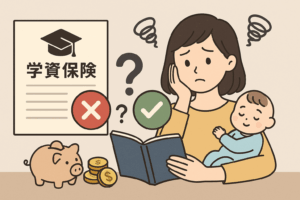
学資保険は子どもの教育資金を計画的に準備できる方法ですが、「おすすめしない」と言われるケースもあります。その背景には、学資保険特有のいくつかの欠点が関係しています。
具体的には、満期前に解約すると元本割れ(払い込んだ保険料総額より解約返戻金が少なくなる)リスク、インフレ(物価上昇)に弱く将来の実質価値が目減りする可能性、運用利回り(リターン)が低く効率的な資産形成に向かないといった点です。これらの理由から、「学資保険はおすすめしない」という意見が生まれています。
元本割れや途中解約のリスクがある
学資保険は基本的に長期間(10年~18年程度)にわたり保険料を払い込み、契約満期で祝い金や満期保険金を受け取ります。そのため契約途中で解約すると、払込保険料より少ない解約返戻金しか戻らず損をするリスクがあります。特に加入後まもない早期解約では戻り率が低く、元本割れになる可能性が高いです。
実際、金融機関の解説でも「契約期間が短いほど元本割れの可能性が高いので、満期まで続ける前提で加入が必要」とされています。このように途中解約時のペナルティが大きいため、学資保険は途中でやめにくい商品であり、資金が必要になっても柔軟に引き出せない点がデメリットです。
インフレに弱く、資産価値が目減りする可能性がある
学資保険は契約時に予定利率(運用利回り)が固定され、その後は契約期間中ずっと同じ利率で運用されます。現在の低金利環境では、その固定利回り自体が低いため、インフレ(物価上昇)が起きると将来受け取る満期金の実質的な価値が下がる恐れがあります。
例えば近年、日本の消費者物価指数は2022年4月時点で前年比+2.5%、同年12月には+4.0%と大きく上昇しました。しかし学資保険の返戻率(払込保険料に対する受取総額の割合)は、以前は130%超えの商品もありましたが現在の主流は105~117%程度のものが多く、年利換算すればごく低い利回りしか期待できません。
この利回りでは物価上昇に追いつけず、預けたお金の購買力(価値)が目減りしてしまいます。したがって、インフレ局面では学資保険だけに頼ると「せっかく貯めたお金で将来の教育費をまかなえない」事態になりかねないのです。
運用利回りが低く、効率的な資産形成には向かない
学資保険のもう一つの背景理由は、運用利回りの低さです。超低金利の影響で各社の学資保険の返戻率は年々下がっており、多くがわずかに100%を上回る程度にとどまっています。例えば、満期時に105%の返戻率だとしても、18年間で見ると年利換算の利回りは1%未満です。預貯金と比べればわずかに有利とはいえ、他の投資商品と比較すると極めて低いリターンしか得られません。
また、近年はネット銀行の登場などで預金金利も一部上昇傾向にあり、最近では一部の主要銀行で普通預金金利が0.182%前後に設定されるなどのデータもあります。それでも学資保険の利回りは物足りない水準であり、長期の資産形成手段としては効率が悪いのが実情です。
さらに、学資保険には保険会社の手数料や付加保険料が含まれているため、契約者が実質得られる利息分はごく僅かになります。このようにリターンが低いことから、「もっと増やせる方法が他にあるのでは?」と考える人が増えており、学資保険離れの一因となっています。
学資保険にはどんなデメリットがある?損をしやすい3つの落とし穴
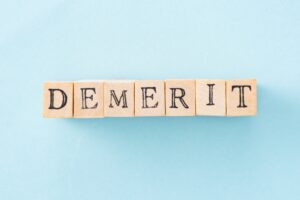
上記で触れた背景を踏まえ、ここでは学資保険の具体的なデメリットを3つの観点から整理します。知らないと損をしやすい「落とし穴」の部分でもあるので、契約前にしっかり確認しておきましょう。
インフレに対応できず、実質的な価値が目減りする可能性がある
学資保険最大の落とし穴はインフレに対応できない点です。契約時に決まった利率で満期まで運用されるため、世の中の物価が上昇しても受取額は契約時点の価値に固定されます。
その結果、インフレによって将来の教育費が膨らんだ場合、受け取った保険金では不足してしまう恐れがあります。例えば、契約時に想定した大学4年間の学費が500万円でも、インフレで物価・学費が上昇すれば18年後には500万円では足りなくなるかもしれません。
実際に日本でも近年は物価上昇が続いており、2022年には年率で+2~4%程度のインフレが記録されています。これに対し、学資保険の固定利回りは上がらないため、受取額の購買力が目減りしてしまうリスクがあるのです。インフレ局面では預貯金の金利は上がる傾向にありますが、学資保険はその恩恵を享受できないため、この点は大きなデメリットと言えます。
支払いが長期にわたり、家計の柔軟性を奪いやすい
学資保険は契約から満期まで10年以上に及ぶ長期の支払いが前提となります。毎月(または毎年)決まった保険料を払い続ける必要があり、その期間中に家計状況やライフプランが変わっても支払いの見直しが難しい商品です。
例えば、子どもの進路が変わって急に教育費が必要になったり、家庭の収入が減少したりしても、学資保険では途中で保険料額や受取時期を大幅に変更することはできません。途中解約すれば前述のように元本割れリスクがあるため、実質的に計画変更がしづらいのです。
一方で、預金やつみたてNISAなどであれば、状況に応じて積立額を調整したり一時停止したり、必要な時に引き出したりと柔軟な対応が可能です。学資保険は一度契約すると家計の一定額を長期にわたり拘束することになるため、将来の不確実性に対して融通が利きにくい点がデメリットになります。ライフイベントや経済状況の変化に合わせて教育資金計画を見直す余地を残したい場合、学資保険は不向きと言えるでしょう。
医療保障や特約が不要でも、セットで支払うことになるケースがある
学資保険には商品によって医療特約や育英年金特約など、教育資金以外の保障が付帯できるものがあります。一見手厚く感じますが、実はこれが返戻率低下の原因になる場合があります。
多くの学資保険では、純粋な貯蓄部分だけなら返戻率100%超(払い込んだ額以上の満期金)を実現できますが、医療保障などを付けると支払い保険料が増えるため、総支払額が受取額を上回り元本割れになることもあるのです。例えば、大学入学時に200万円受け取れる学資保険でも、入院保障特約などを付けると毎月の保険料が上乗せされ、その結果トータルの払込額が210万円になってしまうといったケースがあり得ます。
このように「特約込みの商品だと実は貯蓄性が低い」ことに契約後に気付いて後悔する人もいます。また、契約時点では特約が不要と思っても、商品設計上最初からパッケージになっていて外せない場合もあり、その分リターンが目減りしてしまいます。必要な保障と貯蓄を切り分けて考えたい人にとって、学資保険は融通が利かずコスト高になる可能性がデメリットと言えるでしょう。
学資保険にもメリットはある?使い方次第で役立つケースとは

ここまでデメリットを中心に見てきましたが、学資保険にもメリットは存在します。すべての家庭にとって不要というわけではなく、状況次第では有効な資金準備手段となるケースもあります。以下では、学資保険の代表的なメリットを3つ解説します。
貯金が苦手な人には強制的な積立手段として役立つ
学資保険最大のメリットは、毎月定額を強制的に貯蓄できる仕組みだという点です。銀行預金だとつい使ってしまい貯金が苦手…という方でも、学資保険なら契約者の口座から保険料が自動で引き落とされるため、半強制的にお金を貯められます。この強制力のおかげで、コツコツ貯蓄が苦手な人でも計画的に教育資金を積み立てやすくなるのです。
実際、保険大手の資料でも「“貯金だと下ろしてしまいそう”な人には、強制力のある学資保険が向いている」と紹介されています。毎月の保険料は半ば「支払い義務」のようなものなので、他の出費より優先的に確保されることになり、結果的に確実な積立が可能です。貯金箱代わりに学資保険を活用するという発想で、意志に自信がない方にとっては有効なツールとなるでしょう。
親に万が一のことがあった場合でも教育費を確保できる
学資保険には契約者(親)が死亡・高度障害状態になった場合、それ以降の保険料払込が免除される特約(保険料払込免除)が標準付帯している商品が多くあります。この仕組みにより、万一親に不測の事態が起きても、残りの保険料を払わずに契約通りの満期保険金が受け取れるのです。
つまり、親が亡くなった後でも子どもの教育資金が予定額確保される保障効果があります。これは学資保険ならではのメリットであり、預貯金で自力準備している場合には真似できないポイントです。
実際、貯蓄だけの場合、もし一家の収入源である親が亡くなれば以降の積立が困難になり、計画自体が頓挫してしまう恐れがあります。学資保険なら契約者に万一のことが起きても教育費だけは守られるため、「どんな状況でも子どもの進学資金を確保したい」という家庭には大きな安心材料となります。家庭のリスク管理として生命保険の側面も兼ねられる点は、学資保険の重要な利点です。
教育費を保険として確実に確保したい家庭には合っている
学資保険は満期まで続ければ払い込んだお金以上の学資金を受け取れる設計(返戻率100%超)が一般的であり、「教育資金を確実に確保したい」という家庭には適した商品です。銀行預金だと用途を問わず引き出せてしまうため途中で目的外に使ってしまうリスクがありますが、学資保険は教育費専用のお金として契約上ロックされるため、確実に残せます。子どもの入学時期に合わせて中学・高校・大学入学時に祝い金や満期金を受け取るプランを選べる商品も多く、将来の大きな出費にピンポイントで備えやすい点もメリットです。
さらに、学資保険の保険料は生命保険料控除の対象となり、一定額まで所得控除を受けることでわずかながら税負担が軽減される利点もあります。総合的に見ると、「毎月決まった額を積み立てて、必要なときに確実に教育費を受け取りたい」「万一の時の保障も欲しい」という家庭には、学資保険はフィットする商品と言えます。逆に、多少のリスクを取ってでも資金を増やしたい場合は不向きですが、「増えなくてもいいから減らしたくない」という堅実派には合った選択肢でしょう。
学資保険の代わりに選ばれている資産形成の方法とは
学資保険以外にも、子どもの教育資金を準備する方法は複数あります。近年では「学資保険に入らず、別の資産形成手段を活用する」家庭も増えています。それぞれ特徴が異なるため、自分たちの方針に合った方法を選ぶと良いでしょう。ここでは学資保険の代わりによく検討されている4つの方法を紹介します。
つみたてNISAで投資信託を積み立てて教育費を準備する
つみたてNISA(少額投資非課税制度)は、長期の積立投資に適した公的な優遇制度です。年間上限額まで投資信託等の購入額が非課税枠となり、運用益・分配金が非課税で再投資できます。例えば新しいNISA制度(2024年~)では、つみたて投資枠として年間120万円まで非課税で積み立て可能です。
つみたてNISAを活用すれば、ごく少額からでも株式や債券に分散投資された投資信託を積み立て、インフレに負けない成長が狙える点が魅力です。実際、投資信託による長期運用は預貯金や学資保険と違い物価上昇に対するヘッジ(対抗策)にもなります。
また、投資信託ならいつでも現金化できる流動性もあり、必要に応じて売却して教育費に充てる柔軟性も確保できます。ただし、NISA運用はあくまで投資なので元本保証はなく、市場変動で評価額が下がるリスクはあります。そのため、「絶対に減らしたくない教育資金をすべてNISAで運用する」のではなく、預金や保険と併用してリスクを分散させるのが安心でしょう。
長期・積立・分散投資のメリットを活かせば、過去データでは20年程度の長期運用で元本割れしたケースはなかったとの分析もあり、子どもが小さいうちからコツコツ積み立てることで安定した教育資金形成が期待できます。
iDeCoで節税しながら老後と教育費を同時に備える
iDeCo(個人型確定拠出年金)は老後資金作りの制度ですが、節税効果を活用して教育費準備にも間接的に役立てられます。iDeCoは毎月の拠出金が全額所得控除となり、掛金分だけ所得税・住民税が軽減されます。例えば月23,000円をiDeCoに積み立てる会社員の場合、年約27.6万円の所得控除を受けられ、所得税率20%なら年間5.5万円程度の節税効果が得られます(※税率は仮の例)。
この浮いた税金分を教育資金の貯蓄に回すことで、家計全体で見れば教育費準備を効率化できます。さらにiDeCoの運用益も非課税で再投資され、将来年金として受け取る際にも一定額まで税優遇があります。
つまり、iDeCoで老後資金をしっかり作っておけば、現役時代の収入から教育費に回せる余力が増えるとも考えられます。注意点として、iDeCo資金は原則60歳まで引き出せないため、直接教育費に充当することはできません。また運用結果次第では元本割れの可能性もあります。
しかし、「老後資金を計画的に準備しつつ現役世代の手取りを増やし、その分を教育費に充てる」という発想で、老後と教育の両立を図る家庭が増えています。現に、公的統計でもiDeCo加入者数は年々増加傾向にあり、制度を最大限活用して家計全体の資産形成効率を上げる動きが見られます。教育費と老後資金はいずれも重要なライフイベント資金なので、双方に目配りする上でiDeCoの節税メリットは無視できないでしょう。
普通預金や定期預金で安全性を重視しながら貯める
教育資金の準備方法として昔から定番なのが銀行の預貯金です。普通預金や定期預金は元本保証があり、預金保険制度によって1金融機関あたり元本1,000万円とその利息まで保護されるため、安全性は極めて高いです。また、いつでも引き出せる流動性も持ち合わせているため、急な出費にも対応しやすく、用途に応じた柔軟な資金移動が可能です。
学資保険に比べて途中解約によるペナルティも無く、必要なときに必要な分だけ使える点は大きなメリットでしょう。特に、お子さんが小さいうちは日々の教育関連費用で手一杯で、まとまった投資に回せない場合もあります。そのような場合、毎月わずかな額でも預金に積み立てておくことで「塵も積もれば山となる」効果が期待できます。
例えば月1万円を18年間積み立てれば元本だけで216万円になりますし、児童手当など公的給付を手を付けず預金していけば中学校卒業時までにまとまった額が貯まるとの試算もあります。ただし、預金の弱点は低金利ゆえにお金がほとんど増えないことです。現在の日本の大手銀行の普通預金金利は年0.001%程度、定期預金でも0.002~0.2%程度(銀行・期間による)と超低水準であり、インフレ下では実質目減りするリスクもあります。
それでも「減らさずに確保する」手段としては預金は有力であり、リスクを一切取りたくない方には適しています。預貯金だけで目標額に届かない場合は、次に述べるような他の方法と組み合わせるのも一案です。
融資型クラウドファンディングで堅実に増やす選択肢もある
教育資金の準備方法として、近年注目を集めているのが「融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)」です。これは、インターネット上で個人投資家が企業や事業者への融資に資金を出し、利息収入を得る仕組みの金融商品で、株式投資のような価格変動はなく、比較的安定的にリターンを狙える点が特徴です。
利回りは案件によって異なりますが、年4~10%前後と比較的高めに設定されることが多く、資産形成を加速させたい方にとって魅力的な選択肢となっています。また、1万円~2万円程度の少額から始められるサービスが多く、リスクを抑えた分散投資がしやすい点も利点です。
なかでもLENDEX(レンデックス)は、2万円から投資でき、平均利回り8.05%(税引前)という実績を誇ります。さらに、サービス開始以来「貸し倒れゼロ」の実績が続いており、投資家からの信頼を集めています。多くの案件には不動産担保や保証が設定されており、万が一返済が滞った場合でも、担保の処分などで出資金の回収が図られる仕組みです。
ただし、融資型クラウドファンディングは預金のような元本保証があるわけではなく、リスクはゼロではありません。教育資金の全額を一括投入するのではなく、他の資産と組み合わせて分散投資することが大切です。高利回りと安定運用を両立させたい方にとって、堅実な資産形成手段として検討する価値のある選択肢と言えるでしょう。
教育資金を守るなら、リスクを抑えた分散投資という選択も

「教育資金を増やす」だけでなく「確実に守る」観点からは、リスクを抑えて安定性を高める工夫が大切です。近年は学資保険に代わり、長期・積立・分散投資によって効率よくリスクを管理しながら教育資金を形成する考え方が注目されています。ここでは、教育資金を守りつつ増やすための投資上のポイントを見ていきます。
投資先を分けてリスクを分散すれば安定性が高まる
分散投資はリスク軽減の基本原則であり、複数の資産に資金を分けることで一つひとつの値下がりによる影響を小さくできます。例えば、全額を日本株に投じていた場合、日本株式市場が不調になると資産全体が大きく目減りします。しかし資産を国内株式・外国株式・債券・預金などに分散しておけば、一部の値下がりを他の資産の値上がりや安定で補えるため、全体として損失を抑えられるのです。
事実、過去のデータでも複数資産に均等分散した合成ポートフォリオは、各資産単体より毎年のリターン変動が小さく中位付近に安定して推移したとの分析があります。このように「卵を一つのカゴに盛るな」の格言通り、投資対象を分散させることで資産全体の安定性を高めることが可能です。
教育資金の運用でも、預金・保険・投信・債券など組み合わせておけば、一つの失敗で計画が破綻するリスクを減らせます。特に余裕資金が限られる家庭では、一発勝負の投機よりリスクを分散した堅実運用の方が向いているでしょう。
長期の積立投資なら短期の価格変動に振り回されにくい
長期投資もリスク低減に有効な手段です。一般に、運用期間を長くとるほどリターンのブレ幅(変動リスク)は小さくなり、安定的な収益に収れんしていく傾向があります。短期では相場の上下動により1年ごとの結果が大きく振れることがありますが、長期では景気の波を複数回乗り越えるうちに平均的な成長率に近づいていくためです。
実際、5年程度の運用だと運用開始時期によって大きく勝ったり負けたりするケースがある一方、20年という長期で見るとどの時点から始めても安定してプラス収益に落ち着いた(元本割れケースがなかった)というデータも報告されています。さらに長期積立なら複利効果も働き、利益が利益を生む好循環で元本を雪だるま式に増やしやすくなります。
教育資金作りでは子どもが生まれてから大学進学まで約18年という長期間があります。この時間を味方につけ、毎月決まった金額を投資する「ドルコスト平均法」を実践すれば、価格が高いときには少なく、安いときには多く買えるため、購入価格を平均化してリスクを抑えることができます。
短期的な相場の上下に一喜一憂せず、安定的に資産形成が進められるのが特徴です。長期積立投資は、慌てず計画を継続できる人に最適な戦略であり、教育資金のように使う時期が決まっているお金を準備するのに適しているといえます。
分散投資はリターンとリスクのバランスがとりやすい
分散×長期×積立を組み合わせることで、リスクとリターンのバランスを効率よくとることができます。分散投資はリスクを抑え安定性を高めますが、同時に大きなリターンを狙いすぎないミドルリスク・ミドルリターン志向になります。
長期積立投資も、時間をかけてじっくり増やす代わりに短期で大儲けすることは期待しないスタンスです。これらは裏を返せば「大負けしにくい運用」を目指す考え方であり、教育資金の運用では非常に重要です。なぜなら、教育費は子どもの成長というタイミングに合わせて必要になるため、途中で大きく減らしてしまうと取り返す時間が無いからです。
複数の資産に分散し、過度なリスク資産に偏らず、複利を活かして長期運用することで、「負けにくくじわじわ増やす」運用が可能となります。リスクを分散し、できるだけ大きく負けない運用を心がけることで、結果的に目標額に近づける可能性が高まるでしょう。
少額から始める堅実投資「LENDEX」の融資型クラウドファンディング
LENDEXは、2万円という少額から始められるため、投資初心者にも取り組みやすい融資型クラウドファンディングです。想定利回りは年6~10%と、銀行預金よりも高いリターンが期待できるうえ、不動産担保ローンへの出資となるため、相場変動の影響を受けにくく安定した運用が可能です。
また、毎月の分配金があるため、継続的なインカムゲインを得られる点も魅力です。多くの案件に担保や保証が設定されており、万が一貸し倒れが発生しても、担保処分などで出資金の回収が図れます。
さらに、サービス開始以来、貸し倒れゼロの実績を誇る点も投資家にとって安心材料です。ただし、元本保証はないため、リスク分散が重要です。複数のファンドに少額ずつ分散投資することで、リスク軽減を図ることができます。
高利回りと安定運用を両立するLENDEXで、新しい資産運用を始めてみませんか?
【FAQ】学資保険に迷ったときによくある質問
学資保険はやっぱり入らないほうがいいの?
多くの場合、学資保険に必ずしも入る必要はありません。学資保険はリターンが低くインフレに弱いため、貯蓄やNISAで自分で備えた方が効率的なケースが多いです。 たとえば、毎月1万円をつみたてNISAで18年運用すれば学資保険より高いリターンが期待できます。
学資保険とつみたてNISAはどっちがいい?
資産を増やす力では一般につみたてNISAの方が優れますが、学資保険には保障機能という強みがあります。つみたてNISAは運用益非課税で高リターンを狙えますが元本割れリスクがあり、学資保険はリターンは低いものの親の死亡保障で教育費を守れます。リスク許容度が高く長期運用できるならNISAで増やし、万一に備えたいなら学資保険で確実に教育費を押さえるといった併用も一つの方法です。
学資保険を途中でやめたらどうなる?
学資保険を途中解約すると多くの場合元本割れになってしまいます。解約時に受け取る解約返戻金は払い込んだ保険料総額より少なく設定されており、契約から年数が浅いほどその差額が大きく損失が出ます。例えば10年満期の学資保険を5年で解約すると、払込保険料の70~80%程度しか戻らず、大きく目減りすることがあります。
まとめ|学資保険を選ばない人が後悔しないためにできること
学資保険はインフレの影響を受けやすく、近年の物価上昇(2022年には年+4.0%)を考えると、将来的に実質的な価値が目減りするリスクがあります。そのため、多くの家庭ではつみたてNISAや預金、融資型クラウドファンディングなどを組み合わせて、教育資金を準備する動きが広がっています。
学資保険に頼らず資産を形成する場合は、長期・分散・積立の基本を押さえ、堅実かつ計画的に備えていくことが、後悔のない選択につながるでしょう。
参考元
・文部科学省「令和3年度子供の学習費調査の結果」
・金融庁「NISAガイドブック」
・国民生活センター「生命保険に関する相談事例」
・金融経済教育推進機構「人生とお金の知恵」
・金融庁 「つみたてNISA座談会(第3回)発言録」